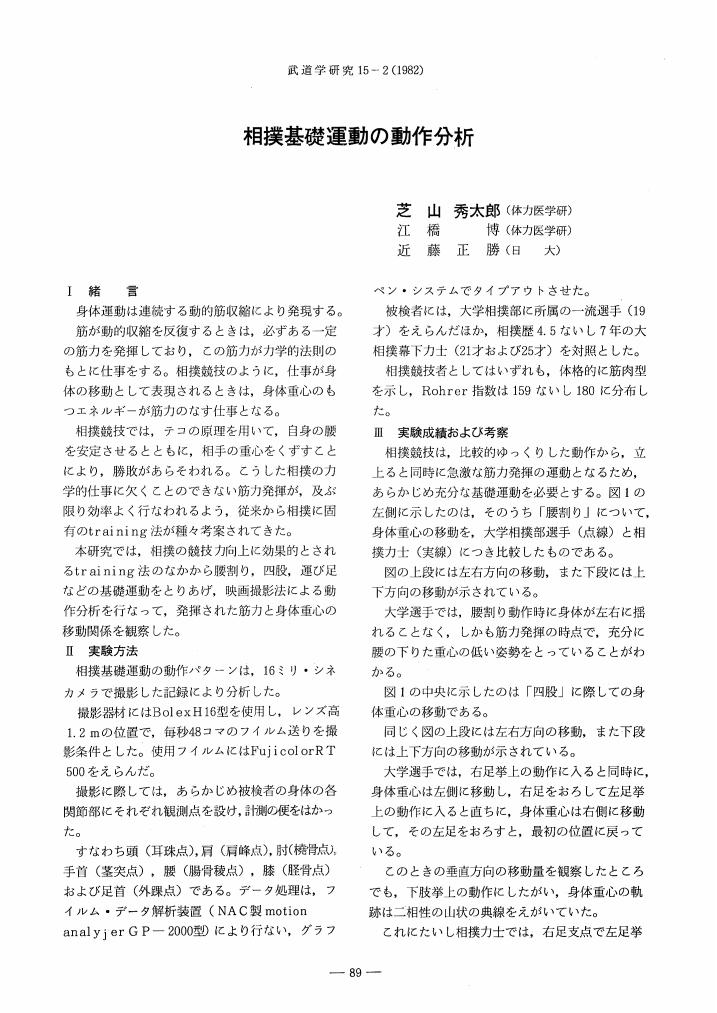1 0 0 0 OA 関東平野における雷雨性降雨の強降雨の地域,移動特性に関する研究
- 著者
- 佐藤 航 土屋 修一 山田 正
- 出版者
- 水文・水資源学会
- 雑誌
- 水文・水資源学会研究発表会要旨集 第19回(2006年度)水文・水資源学会総会・研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.76, 2006 (Released:2006-09-11)
1990年代から関東地方では,夏季に集中豪雨などのごく短時間に30_-_50mm/hrの雷をともなう激しい雨が頻発しており,それにより都市河川の氾濫や交通網の麻痺といった災害が社会問題とされている..著者らは,ドップラーレーダを用いて約10年間の降雨観測を行い,関東平野で発生するメソβスケール降雨の発生から消滅までの一連のメカニズムについて明らかにしてきた.本研究は,夏季の集中豪雨の降雨特性を明らかにするためドップラーレーダによる観測から,関東平野における雷雨性降雨の発生時間・発生地点,降雨強度32mm/hr以上の強雨の降る地域分布,強雨域の移動について解析を行った.結果をしめすと 雷雨性の降雨は東に移動するものが多く,他の方向に移動する降雨域よりも移動速度は早く,降雨強度も大きい傾向がある.
1 0 0 0 OA カシオ計算機における「EXILIM」の開発
- 著者
- 山口 洋平
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.6, pp.253-288, 2004-06-25 (Released:2018-03-18)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2
デジタルスチルカメラ市場は2003年に出荷金額が1兆円を突破し、デジタル家電市場の拡大の中で、日本企業が高い競争力を持つ産業として大きく注目を浴びている。カシオ計算機は「QV-10」を発売することによってデジタルカメラ市場を創出したが、その後銀塩カメラメーカーが仕掛けた多画素・高画質競争の中で低迷した。そのカシオ計算機が2002年に投入した「EXILIM」はデジタルカメラらしさを追求した機種で、それまで多画素・高画質という製品スペックをめぐる競争が行われていたデジタルカメラ市場にとって、製品コンセプトのイノベーションをもたらす斬新な製品であった。本稿では、なぜカシオ計算機が「EXILIM」を開発することになり、どのような過程で開発が進められたかを見ていく。
1 0 0 0 OA 相撲基礎運動の動作分析
1 0 0 0 OA 伊勢参宮御影まいり : 滑稽道中
- 著者
- 暁鐘成, 山川澄成 著
- 出版者
- 忠雅堂
- 巻号頁・発行日
- 1890
1 0 0 0 市バス25周年史
- 出版者
- 京都市交通局企画調査室
- 巻号頁・発行日
- 1953
1 0 0 0 OA アザミウマ捕食性カブリダニ種の採集法の開発
- 著者
- 豊島 真吾
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.173-180, 2021-11-25 (Released:2021-12-23)
- 参考文献数
- 31
Phytoseiid mite species were surveyed on garden and wild plants in an experimental field in Japan. The above-ground part of the plants were collected from the field, and dried in the laboratory to collect phytoseiid mites from the plant-parts. When the plant-parts were dried on the bean leaflets rearing Thrips tabaci larvae, phytoseiid mites on the plant-parts moved to and remained on the leaflets during two-day treatment. Populations of Typhlodromips sessor and Neoseiulus makuwa were established when fed on T. tabaci. Then, the life history parameters of both species were examined in the laboratory. In comparison with the data from previous studies, the daily oviposition of both species was similar to that of Amblyseius eharai, Neoseiulus barkeri, and Neoseiulus cucumeris, and the survival rate during the development of both species was similar to that of N. barkeri. The mode of reproduction of T. sessor was confirmed by the experiment as parthenogenetic thelytokous reproduction.
1 0 0 0 OA 警視庁令建築関係規則類纂 : 附・営業諸取締規則
- 著者
- 警視庁保安部建築課 編
- 出版者
- 警眼社
- 巻号頁・発行日
- 1921
1 0 0 0 OA 「一目瞭然!目で診る症例」問題・解答
1 0 0 0 OA 脳梗塞のリハビリテーション治療
- 著者
- 松元 秀次
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.201-209, 2019-10-15 (Released:2019-12-03)
- 参考文献数
- 18
Stroke is clinically characterized by hemiplegia and exercise intolerance, both of which not only interfere with the ability to perform activities of daily living (ADL), but also significantly reduce quality-of-life (QOL). Neurological and functional recovery occurs mainly within the first 6 weeks after onset of stroke, but the process continues for several months, with maximal functional recovery usually achieved within 6 months. In Japan, convalescent rehabilitation wards play an important role in the rehabilitation of post-stroke patients who have impaired ADL and health status after the acute phase. Various physiotherapies have been developed to improve functional recovery in patients with hemiplegia due to stroke, including the facilitation technique with proprioceptive neuromuscular facilitation, and constraint-induced movement therapy. A novel facilitation technique is repetitive facilitative exercises (RFE), which promote the functional recovery of the hemiplegic limbs to a greater extent than conventional rehabilitation sessions.Functional electrical stimulation (FES) is a technique used to produce contractions in paralyzed muscles by the application of small pulses of electrical stimulation to the nerves that supply the paralyzed muscle. FES is used as an orthosis to assist walking, and also as a means of practicing functional movements for therapeutic benefit. New training technologies involving the use of robots have recently been developed to help in the rehabilitation of post-stroke patients.Robot-assisted rehabilitation therapy provides functional training of the upper and lower limbs in an effective, easy and comfortable manner. Furthermore, the robot-assisted training paradigm offers intensive, repetitive, sufficient, and accurate kinematic feedback along with symmetrical practice while reducing the workload for the therapist, thus reducing the cost of post-stroke rehabilitation. Exoskeleton-type robotic devices have robot axes aligned with the anatomical axes of the wearer. These robots provide direct control over individual joints, which can minimize abnormal posture or movement. Robot-assisted gait training is effective in the long term in improving balance and walking ability, and it has a positive impact on patients' QOL. Several well-designed studies have provided evidence that robot-assisted training promotes motor recovery and functional improvement in post-stroke patients. However, the evidence is insufficient to draw conclusions about the effectiveness because of small samples sizes, methodological flaws, and heterogeneous training procedures. More well-designed randomized controlled trials are needed.
1 0 0 0 OA ホームズ物語言及作曲家に見るドイルの宗教観
- 著者
- 中西 裕 Yutaka NAKANISHI
- 出版者
- 昭和女子大学近代文化研究所
- 雑誌
- 学苑 = Gakuen (ISSN:13480103)
- 巻号頁・発行日
- no.964, pp.1-11, 2021-02-01
Arthur Conan Doyle abandoned Catholicism early on and later devoted himself to spiritualism. Looking at the composers mentioned in the Sherlock Holmes stories, many are Protestants, four of whom, Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach, and Wagner, wrote music using Martin Luther’s Ein’ feste Burg ist unser Gott. He also portrays the Huguenots who, after being chased out of France, resettled in the United States in The Refugees: A Tale of Two Continents. Doyle had a favorable view of Protestantism, especially the Lutheran and Huguenot varieties.
1 0 0 0 OA 特定外来種ツマアカスズメバチの食性と繁殖性を利用した防除の検証試験
対馬、壱岐、北九州、大分に侵入した特定外来種ツマアカスズメバチについてミトコンドリアDNAの全長解析から国内に侵入した個体間には遺伝的変異は存在しないこと、自然分布地の中国、台湾、ベトナム、中国浙江省の個体と一致することがわかった。食性は樹冠に生息する昆虫類であることをDNAバーコーディング法により明らかにした。捕獲トラップは地上部よりも、樹冠10m付近が最も多く捕獲することができた。繁殖は、主に樹冠で交尾をするキイロスズメバチと交雑をしており、在来種に対して繁殖干渉を行っていることがわかった。
- 著者
- 柳沢 英輔
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.2, pp.197-216, 2021-09-30 (Released:2021-12-26)
- 参考文献数
- 88
本論の目的は、フィールドレコーディングを主体とする実践的な研究手法としての音響民族誌(sonic ethnography)について、その意義を論じることにある。音響民族誌とは、人類学的なフィールドワークの成果物としてのフィールド録音作品のことを指す。人々の営みを経験的に記述する民族誌において、聴覚的な経験よりも視覚的な経験が重視されてきたため、音や録音メディアの持つ可能性はこれまで十分に検討されてこなかった。近年、音響民族誌が注目されるようになった技術的、理論的な背景として、機材のデジタル化により録音・編集環境が一般化したこと、そして、1980年代以降の「音の人類学」、「感覚の人類学」、「感覚民族誌」など、ロゴス中心主義、画像中心主義に対抗し、視覚以外の諸感覚や身体経験に着目した研究の潮流がある。 本論では『うみなりとなり』という筆者らが制作した音響民族誌を事例として取り上げる。結論として以下のことが言える。第1に、音響民族誌は、音を通して、ヒト、モノ、自然が響きあう相互的で、流動的な世界の在り様を描くことで、我々のモノや世界の捉え方を転換させうる。第2に、録音という行為を通した人やモノ、場所との感覚的な繋がり、調査手法やプロセスへの省察的な考察と循環に、その意義や可能性がある。
- 著者
- 小川 良磨 秋田 新介 武居 昌宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-00090, (Released:2022-05-25)
- 参考文献数
- 21
Spatiotemporal local changes have been extracted for evaluating physiological phenomena by an image reconstruction algorithm of electrical impedance tomography (EIT) using sparse Bayesian learning (SBL). The proposed method identifies a region of interest (ROI) by a priori information on conductivity distribution σ of each biological tissue and automatically learns block-sparsity and temporal-correlation in the identified ROI in the form of blocked column vector (BCV). Two types of numerical simulations are conducted to model lymphedema (LE) and venous edema (VE) that cause spatiotemporal local changes in σ of subcutaneous tissue fluids in human calf phantom which consists of three parts: great saphenous vein (GSV) as ROI and subcutaneous adipose tissue (SAT) and muscle as background. From the results, spatiotemporal local changes in σ are clearly extracted only near GSV by the proposed method even in a field where the time-varying σ in the background is large. Furthermore, the accuracy of the proposed method is evaluated under the variant conditions of conductivity ratios of SAT and muscle relative to GSV, i.e., ρGSV/SAT and ρGSV/muscle, respectively, and area ratio accuracy ARAGSV is the highest in the case where ρGSV/SAT = ρGSV/muscle, which achieves ARAGSV = 2.241 regardless of the values of ρGSV/SAT and ρGSV/muscle.
1 0 0 0 OA コロナ禍における高等教育へのインパクト
- 著者
- 石井 雅章
- 出版者
- 神田外語大学グローバル・コミュニケーション研究所
- 雑誌
- グローバル・コミュニケーション研究 = Global communication studies (ISSN:21882223)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.5-48, 2022-03
1 0 0 0 OA 一部自治体・教育委員会による「教師塾」の開設と教員養成改革
- 著者
- 村田 俊明 ムラタ トシアキ Toshiaki MURATA
- 雑誌
- 摂南大学教育学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.65-82, 2009-01
最近における教育改革の中で、教員の資質向上に係る動向が注目される。教員免許法改正を機に、教員の人事考課、教職大学院、免許更新制の導入、自治体による教師養成塾、あるいは高等学校における「教育コース」の設置の動きなどがあり、教員養成のあり方を抜本的に問い直すべき状況がある。本稿では、一部自治体あるいはその教育委員会による「教師塾」開設の動きについて考えてみたい。東京都をはじめとして、大阪府・市、堺市、京都市などに「教師塾」が設けられ、特に教員確保が喫緊の課題であるいくつかの大規模都市自治体では、行政が教員養成の一端を担い始めている。規制緩和と分権化が推進される教育改革の下で、「大学養成制」と「開放制」を原則としてきたわが国の戦後教員養成制度が、新自由主義と新保守主義による改革の波に揉まれつつある。そこに教員養成そのものを行政責任の対象と捉え、大学における教員養成を主導し、場合によっては大学の養成段階を飛び越す構造へ向かう契機と問題性が含まれているのではないか。本研究の意図は、大学で教師養成に関わる一教師として、この動向をどう考えたらよいかを考察するものである。そこで、自治体およびその教育委員会による「教師塾」の取り組みを整理し、開設の背景とその問題に関する研究の覚書としたい。「教師塾」とは何なのか。わが国の教員養成・採用・研修政策上、どのように位置づけられるのか。「教師塾」の何が問題なのかといった点について考察した。