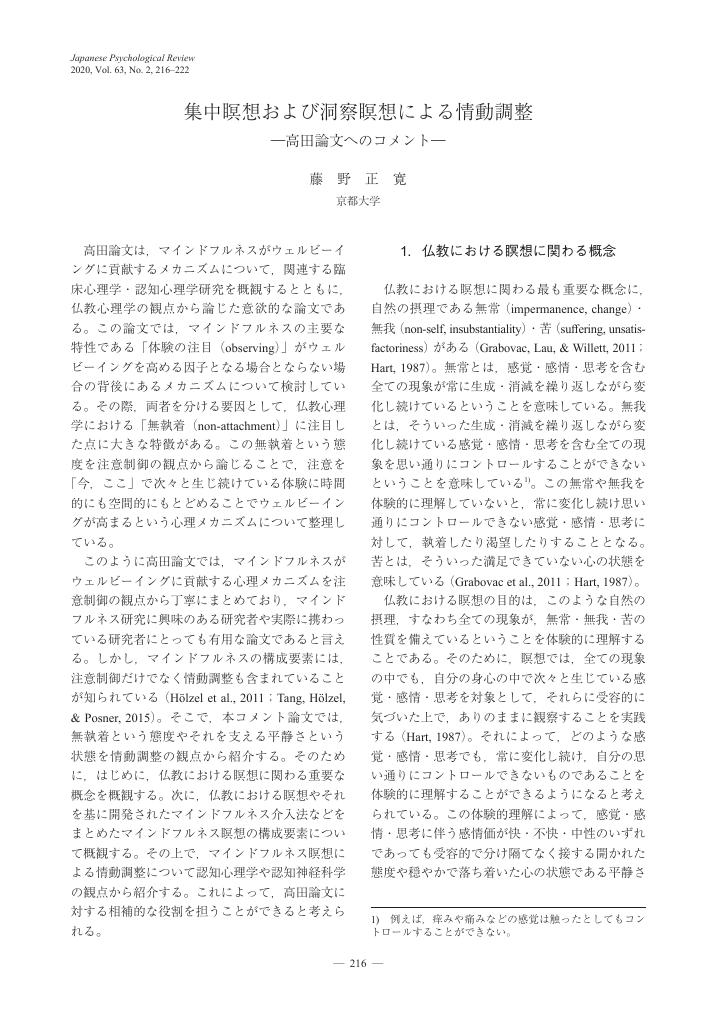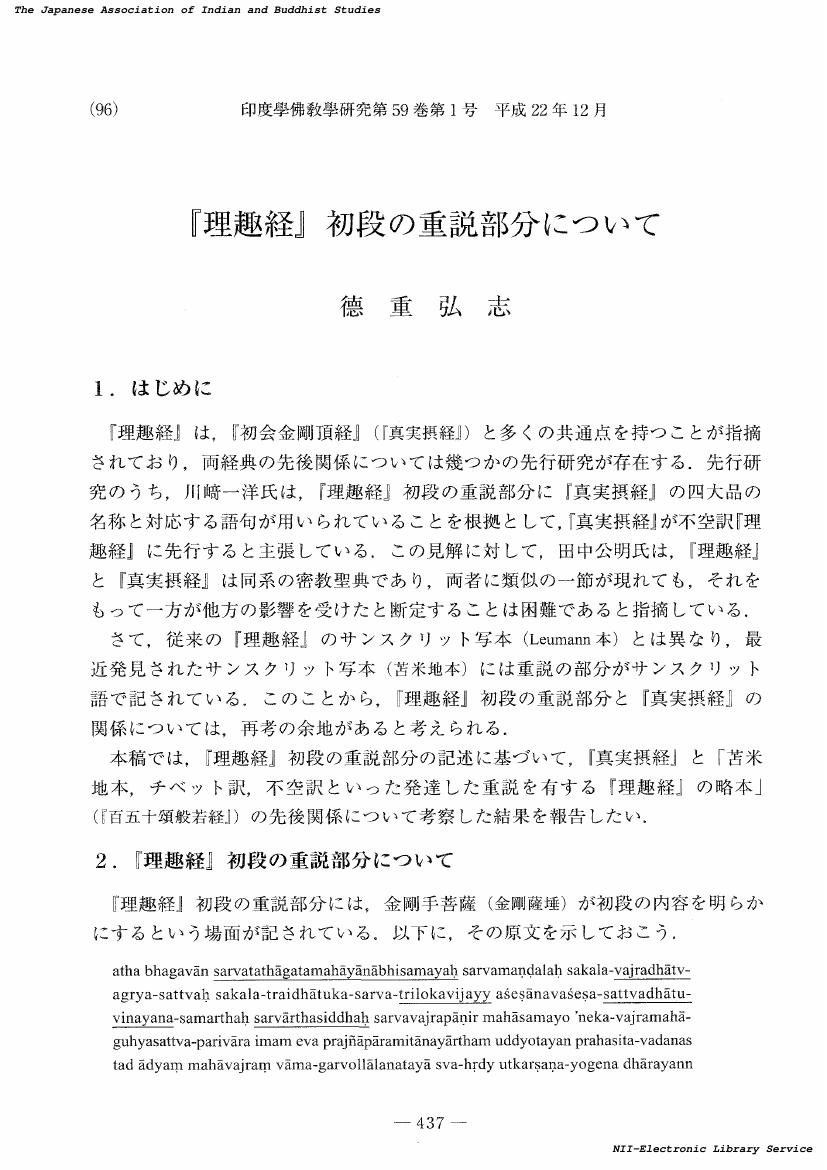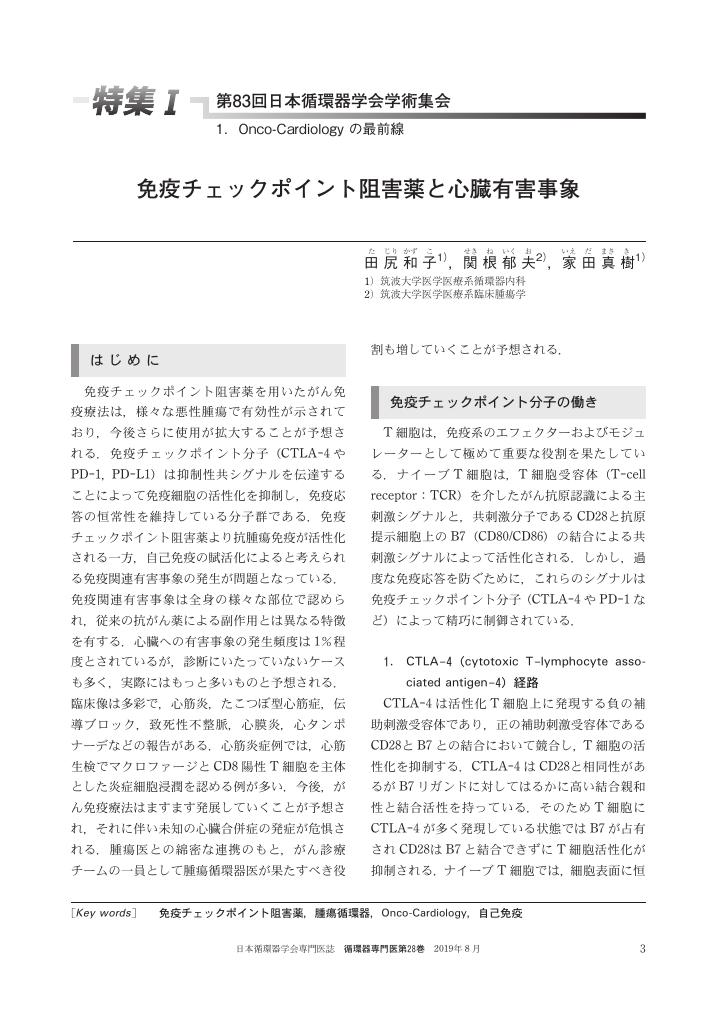1 0 0 0 OA 集中瞑想および洞察瞑想による情動調整 ―高田論文へのコメント―
- 著者
- 藤野 正寛
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.216-222, 2020 (Released:2021-08-05)
- 参考文献数
- 41
1 0 0 0 OA 腰部脊柱管狭窄症における歩行誘発性勃起の発現機序に関する一考察
- 著者
- 安藤 直人 花北 順哉 高橋 敏行 深尾 繁治 北浜 義博 南 学
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.11, pp.852-857, 2007-11-20 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 32
当センターにて約3年半の期間に外科的治療を行った腰部脊柱管狭窄症男性症例206例中4例で勃起症状がみられた.4症例とも歩行に伴う勃起であり,馬尾型の症状を呈し,陰部のシビレを伴うことが特徴的と思われた.腰部脊柱管狭窄症では,歩行時には静脈還流障害に伴い馬尾神経が阻血状態となり,感覚入力系神経に異常な興奮性を生じ,それがシビレなどの過剰な症状を惹起しながら,仙髄勃起中枢に興奮性の入力となりうると推測される.したがって,腰部脊柱管狭窄症での歩行誘発性勃起は,synapticな反射性勃起とする仮説が有力であると考察した.
1 0 0 0 OA DLO(DFOとOWHTOの併用)とDFOTO(DFOとTCVOの併用)の治療成績の検討
- 著者
- 岡本 渉大 米倉 暁彦 岡崎 成弘 中添 悠介 千葉 恒 樋口 尚浩 尾﨑 誠
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.242-246, 2022-03-25 (Released:2022-05-06)
- 参考文献数
- 18
【はじめに】当院で経験したDFOにOWHTOを併用した症例(DLO群)とTCVOを併用した症例(DFOTO群)とで比較検討を行なったので報告する.【対象と方法】2015年から2019年までにDLOまたはDFOTOを施行した17例20膝を対象とし,術前および最終経過観察時のX線計測値,膝関節可動域,JOA score,KOOSを評価した.【結果】膝関節可動域は,DLO群がDFOTO群と比較して術前伸展制限が大きい傾向にあったが有意差はなかった.術後の伸展可動域はDLO群が-5.5°,DFOTO群が-1.6°であり,伸展制限はDLO群が有意に大きかった.両術式間で術前後のX線計測値と臨床スコアに有意差はなかった.DFOTO群において術後%MAとKOOSのPainやSymptomsとの間に相関係数がそれぞれ0.66および0.72の正の相関を,ΔJLCAとKOOSのSymptomsとの間に相関係数-0.75の負の相関を認めた.【結語】DLO群とDFOTO群とで臨床スコアやX線計測値に有意差はなかった.DFOTO群において術後%MAやΔJLCAと臨床スコアの間に相関を認めた.
- 著者
- Masashi Takemura Kentaro Mochizuki Yoshinori Harada Akira Okajima Michiyo Hayakawa Ping Dai Yoshito Itoh Hideo Tanaka
- 出版者
- JAPAN SOCIETY OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY
- 雑誌
- ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA (ISSN:00445991)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.57-66, 2022-04-27 (Released:2022-04-27)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 5
Spontaneous Raman microscopy, which can detect molecular vibrations in cells and tissues, could be a useful tool for the label-free assessment of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, it is unclear whether it can be used to evaluate the nascent state of NAFLD. To address this, we analyzed the Raman spectra of rat liver tissues in the nascent state of NAFLD upon excitation at 532 nm. Raman and histochemical analyses were performed of liver tissues from rats fed a high-fat, high-cholesterol diet (HFHCD). Raman microscopic imaging analysis of formalin-fixed thin tissue slices showed hepatic steatosis, as revealed by the Raman band at 2,854 cm−1, whereas lipid droplets were not detectable by hematoxylin-eosin staining of images until 3 days after feeding a HFHCD. Raman signals of retinol at 1,588 cm−1 emitted from hepatic stellate cells were distributed alongside hepatic cords; the retinol content rapidly decreased after feeding a HFHCD, whereas hepatic lipid content increased inversely. Raman microscopic analysis of the surface of fresh ex vivo livers enabled early detection of lipid accumulation after a 1-day feeding a HFHCD. In conclusion, spontaneous Raman microscopy can be applied to the label-free evaluation of the nascent state of NAFLD liver tissues.
1 0 0 0 OA 病気や障害をもつ子どものきょうだい児への支援に関する研究の動向と課題
- 著者
- 黒岩 めぐみ 金泉 志保美
- 出版者
- 国立大学法人 群馬大学大学院保健学研究科
- 雑誌
- 群馬保健学研究 (ISSN:13434179)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.1-7, 2020 (Released:2020-04-27)
- 参考文献数
- 9
本研究は、病気や障害をもつ子どものきょうだい児に対して行われている支援に関する研究の動向を明らかにし、今後の研究課題を検討することを目的とした。医学中央雑誌Web(Ver.5)を用いて2010年~2019年の文献を検索し、14件を対象に分析した。研究対象は看護師が最も多く、きょうだい児を直接対象として調査・分析している研究は3件と少なかった。NICUを対象とした研究は2件であった。対象文献の研究内容をコード化し、類似性に従って分類した結果、【きょうだい児への具体的な介入の実施とその評価】【看護師をはじめとする医療者が行っているきょうだい児への支援の現状】【家族からきょうだい児に対して行われた情報提供に関する研究】【母親の認識するきょうだい児の面会により得られる効果】の4カテゴリが形成された。今後の課題として、きょうだい児への直接的な支援が積極的に行われること、NICUにおけるきょうだい面会の推進およびきょうだい児の反応を明らかにすることの必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA JAOMPT 整形徒手理学療法国際認定セミナーにおける徒手理学療法教育
- 著者
- 浅田 啓嗣
- 出版者
- 日本徒手理学療法学会
- 雑誌
- 徒手理学療法 (ISSN:13469223)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.33-38, 2019 (Released:2019-04-22)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
日本運動器徒手理学療法学会(JAOMPT) では,IFOMPT(International Federation of OrthopaedicManipulative Physical Therapists)の基準に基づいた国際認定セミナーを開催している。1988 年からKaltenborn -Evjenth International(K-EI)による国際セミナーを継続開催し,現在ではK-EI に限ることなく,IFOMPT の基準に沿った教育へとプログラムの充実を図っている。セミナーは大きく分けて基礎コースと上級コースに分けられている。基礎コースは49 日間,上級コースは34 日間のプログラムが設定されている。コースで習得するテクニックとして,関節モビライゼーション,関節マニピュレーション,軟部組織モビライゼーション,神経モビライゼーション,モーターコントロールトレーニングがある。効果的な治療を行うためには,正確な検査の下,仮説の設定と検証を繰り返し行う臨床推論能力,エビデンスを批判的に分析し臨床応用する能力が求められる。本コースではこの臨床推論過程と最新エビデンスの適用方法をシステマティックに学習することができる。
1 0 0 0 OA 小川卓克氏の業績 ——非線型発展方程式の臨界正則性——
- 著者
- 林 仲夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.189-202, 2020-04-23 (Released:2022-04-24)
- 参考文献数
- 82
1 0 0 0 OA 1995年兵庫県南部地震の複数アスペリティモデルの提案とそれによる強震動シミュレーション
- 著者
- 松島 信一 川瀬 博
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.534, pp.33-40, 2000-08-30 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 9 12
We simulate strong motions in Kobe during the Hyogo-ken Nanbu (Kobe) earthquake of 1995 using a multiple asperity source model and a three-dimensional (3-D) basin structure. We derive a relatively simple rupture process, which consists of four asperities, using theoretical synthetics so that it matches the deconvolved bedrock motion at JMA Kobe. A realistic 3-D basin structure is constructed based on the exploration data. A 3-D finite difference method with fourth ordered staggered-grid scheme developed by Graves (1996) is used. The results show that with the combination of a relatively simple four asperity model and a 3-D basin structure, it is possible to reproduce strong ground motions in a wide area quite accurately. Peak velocity distribution is very similar to the JMA intensity distribution. From these results we confirm that we can reproduce strong ground motion in Kobe quite quantitatively by using a relatively simple source model that efficiently generate 1 second velocity pulses, together with a realistic 3-D basin structure.
1 0 0 0 OA MRI技術の最近のトレンド(第2回)MRI収集系技術の変遷
- 著者
- 木村 徳典
- 出版者
- 日本医用画像工学会
- 雑誌
- Medical Imaging Technology (ISSN:0288450X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.198-203, 2013 (Released:2013-07-27)
- 参考文献数
- 14
MRイメージングの収集系の進歩は単位時間あたりの SNRの増大とパラメータの多様化の歴史である.画像化のためのハード系に対する制御ソフトであるパルスシーケンスは自由度が大きく,生体組織の緩和時間の壁を前提としながらその制約下で進歩してきた.画像化は Fourier変換(spinwarp)法が基本であり,MRI収集高速化の問題は空間周波数空間である k空間をいかに速く,高い SNRのデータで充填するかにある.MRIコントラストも強調画像から定量化・標準化の流れにある.本稿ではMRIの収集系技術の変遷を概観する.
1 0 0 0 OA 『理趣経』初段の重説部分について
- 著者
- 徳重 弘志
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.437-434, 2010-12-20 (Released:2017-09-01)
- 著者
- Akio Morimoto Tadashi Suga Nobuaki Tottori Michio Wachi Jun Misaki Ryo Tsuchikane Tadao Isaka
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.9, pp.1644-1648, 2017 (Released:2017-09-15)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 8 19
[Purpose] Handgrip strength is a surrogate indicator for assessing disease-related and age-related skeletal muscle loss. Clinical utility as such a surrogate can be at least partially explained by the close relationship between handgrip strength and whole-body skeletal muscle mass. The handgrip strength is related to hand muscle size. Thus, the present study examined whether hand muscle thickness is associated with whole-body skeletal muscle mass. [Subjects and Methods] Thirty healthy male adults participated in this study. All subjects were right-hand dominant. Two muscle thicknesses (lumbrical and interosseous muscles) in the right hand were measured using ultrasonography. Whole-body and appendicular skeletal muscle masses were assessed using dual-energy X-ray absorptiometry. [Results] Although lumbrical muscle thickness was not correlated with whole-body skeletal muscle mass, there was a significant correlation with appendicular skeletal muscle mass. Furthermore, interosseous muscle thickness was significantly correlated with both whole-body and appendicular skeletal muscle masses. [Conclusion] The present findings suggest that two muscle thicknesses in the hand are related to whole-body and/or appendicular skeletal muscle mass in healthy adults. Therefore, we propose that despite being smaller than other limb muscles, hand muscle thickness may be useful as surrogate indicator for assessing disease-related and age-related skeletal muscle loss.
1 0 0 0 OA 4. MRI:撮像法と画像所見
- 著者
- 角谷 眞澄 藤永 康成
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.195-202, 2006 (Released:2006-10-26)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 免疫チェックポイント阻害薬と心臓有害事象
- 著者
- 田尻 和子 関根 郁夫 家田 真樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本循環器学会
- 雑誌
- 循環器専門医 (ISSN:09189599)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.3-9, 2019 (Released:2019-09-14)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA <共同研究報告>日本における紀年認識の比較史的考察
- 著者
- 佐藤 正幸
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.177-204, 1998-09-30
人が「年」を認識することは、順序数をただ並べるだけの単純な行為ではなく、極めて政治的・歴史的な知的行為であり、何よりも文化的な行為である。
- 著者
- 野山 広 岩槻 知也 石黒 圭 藤田 美佳 石川 慎一郎 横山 詔一 前田 忠彦 名嶋 義直 大安 喜一 石井 恵理子 佐藤 郡衛
- 出版者
- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
本研究では、現在の社会状況や多様な言語・文化背景を持った日本語使用者が共存・共生する時代に応じた(約70年ぶりの)日本語リテラシー調査(主に読み書きの力に関する調査)の実施に向けて、調査方法の開発を目指す。そのために、以下の1)~3)の実態調査(国内外)、コーパス構築、学際的な観点(基礎教育保障学、日本語教育学、生涯学習論、統計科学、異文化間教育などの多様な分野)からの分析・検討、国際シンポジウム等を実施するとともに、調査の在り方(方向性)や姿勢の追求(追究)、調査方法の開発、試行調査を行う。1)日本語使用の実態調査2)コーパス構築とデータ分析3)調査方法の開発