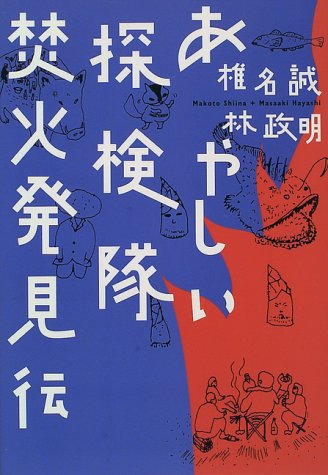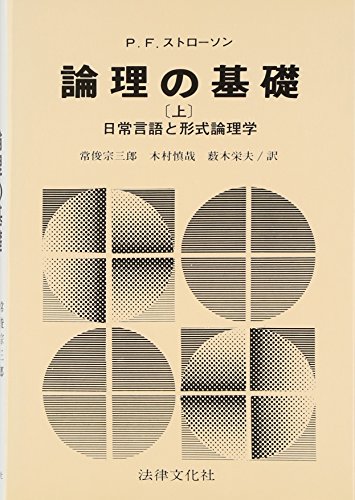1 0 0 0 OA 水中に溶存するガスの分析法
- 著者
- 小穴 進也
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.6, pp.522-528, 1954-12-15 (Released:2010-01-14)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 病態特異的タンパク質複合体の形成原理の解明と筋萎縮性疾患への応用
申請者は、受容体作動性/脂質作動性カチオンチャネルTRPC3の心臓リモデリングにおける役割に着目し、TRPC3と活性酸素生成酵素 (Nox2)との複合体形成を介した過剰な活性酸素の産生がマウス・ラットの心筋細胞萎縮や間質の線維化を形成する引き金となることを見出してきた。興味深いことに、TRPC3-Nox2複合体形成による筋萎縮は心臓だけにとどまらず、同じ赤筋である骨格筋typeI線維の萎縮にも関与する可能性が新たに示されてきた。そこで本研究では、哺乳動物個体の赤筋萎縮(衰弱)に着目し、その根底にあるTRPC3-Nox2複合体の形成機構を解明する。
- 著者
- 萩原 優騎
- 出版者
- 国際基督教大学 International Christian University
- 雑誌
- 社会科学ジャーナル = The Journal of Social Science (ISSN:04542134)
- 巻号頁・発行日
- no.89, pp.165-185, 2022-03-31
“LCS: Less Conflictual Solutions” is a methodology of “functional tolerance” theory proposed by Yoichiro Murakami. Takeaki Komatsu regards the concept of “tolerance” defined by Murakami as the one which shows a necessary condition for information senders to understand the context of their communication with information receivers or to build a new context they will be able to share. This definition appears when Komatsu criticizes the premises of risk communication. This paper aims to reconsider LCS and functional tolerance theory by analyzing Komatsu’s argument based on Niklas Luhmann’s sociology. According to Komatsu, one of the main interests of risk communication is how to convince information receivers. It means that the success of risk communication for information senders is to gain information receivers’ trust in their risk management. However, such an assumption is not self-evident if referred to Luhmann’s comments on risk communication. He distinguishes risks from dangers. Risks belong to the decision-makers, and dangers belong to those affected. In other words, risks are the losses recognized as the results of a decision, and dangers are the ones recognized as what are provided from the outside. There is a gulf between the decision-makers and those affected. What Luhmann pointed out is important to reexamine LCS. Murakami says that it is impossible to achieve the unique solution as the least-conflictual one. Therefore, making a compromise is necessary to reach a less conflictual solution. However, LCS cannot be a methodology to overcome a gulf between the decision-makers and those affected. On the other hand, Murakami emphasizes the importance of seeking a possibility to find a better solution, not the best one. If a person places absolute trust in the option selected already, he/she will lose sight of the possibility of choosing a better solution. He/she should be conscious that their present choice is tentative. Murakami regards that such a person is functionally tolerant. Being functionally tolerant is necessary to improve a situation by recognizing a gulf between the decision-makers and those affected, though it will not be resolved completely. In this meaning, Komatsu’s definition of Murakami’s “tolerance” is incorrect. Komatsu’s criticism against risk communication can be applied to LCS, but not to functional tolerance theory itself. However, this does not mean that functional tolerance theory should be accepted uncritically. It will be possible to revise LCS and functional tolerance theory by referring to Luhmann’s view.
1 0 0 0 OA メルロ=ポンティとラカン
- 著者
- 小野 康男
- 出版者
- 横浜国立大学教育人間科学部
- 雑誌
- 横浜国立大学教育人間科学部紀要Ⅱ(人文科学) (ISSN:1344462X)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.1-20, 2012-02-29
1 0 0 0 OA 榎本武揚等名刺版写真
- 巻号頁・発行日
- vol.写真(河島醇 他),
1 0 0 0 あやしい探検隊焚火発見伝
1 0 0 0 OA 食品組織部会主催平成28年度講演・実習会 テーマ : 米のおいしさと組織構造
- 著者
- 高橋 貴洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.641-644, 2016 (Released:2016-11-26)
1 0 0 0 OA SNS上で当事者は「メンヘラ」をどう語るのか多元的アイデンティティの観点から
- 著者
- 高橋 萌黄
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第85回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.PC-169, 2021 (Released:2022-03-30)
本研究の目的は,第1に,SNS上で当事者が「メンヘラ」を語ることでどのように「メンヘラ」としてアイデンティティを確立しているのかを明らかにすることである。第2に,「メンヘラ」アイデンティティの在り方を明らかにすることである。第3に,多元的アイデンティティの新モデルを提案することである。動画中心のSNS上で「メンヘラカップル」がカップル間のルールを「掟」として示す動画を対象とし,会話分析を行った。「メンヘラカップル」が「掟」を紹介する過程で,「きついことを言ったら緩める」というパターンが繰り返されていることが示された。そのパターンはいくつかの手法に分類される。1つは,強圧的な言葉で「掟」を強調し,その後すぐに「周囲の理解」という視点から自分たちの行為の認められやすさを主張する手法であった。このように,当事者はSNS上で「メンヘラ」を語るとき,「変わっているけど変わりすぎないライン」を模索していた。「メンヘラ」と「普通の人」としての自己を同時に示すことで,社会からの受容を達成し,「メンヘラ」としてアイデンティティを確立していた。そこから多元的アイデンティティの新モデルの提案を目指した。
- 著者
- 南 庄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.123-130, 2022-02-15 (Released:2022-02-15)
- 参考文献数
- 9
殺人未遂事件を起こした統合失調症の対象者に生活行為向上マネジメント(以下,MTDLP)を用いて関わり,「生活行為申し送り表」を通して指定通院医療機関の作業療法士と情報共有し,共に対象者の就労移行を支援した.この結果,対象者は就労継続支援事業所にてやりがいを感じられる仕事に就くことができた.本介入から,MTDLPは対象者の主体的な治療参加を動機づけ,合意目標の達成を目指して対象者と両親,専門的多職種チーム,指定通院医療機関のスタッフの連携を促進するとともに指定入院医療機関と指定通院医療機関における連携を強化し,対象者のシームレスな支援を可能にすると考えられた.
1 0 0 0 OA DSM による地方都市の3次元的時空間分析 -戦後の伊勢市主要部の事例-
- 著者
- 桐村 喬
- 出版者
- 皇學館大学
- 雑誌
- 皇學館大学紀要 = BULLETIN OF KOGAKKAN UNIVERSITY (ISSN:18836984)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.45-20, 2022-03-15
1 0 0 0 OA 大学における教員養成と目的養成 : 教育刷新委員会第五特別委員会の議論を手がかりに
- 著者
- 栗原 崚 Ryo Kurihara
- 出版者
- 学習院大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文 = Jinbun (ISSN:18817920)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.247-261, 2022-03
本稿は、開放制と対置するものとして理解されてきた目的養成の言説の再考を目的とする。目的養成は、教員の需給調整という計画養成として理解されてきたが、それは開放制による大学の養成教育への「消極的思惟」による帰結であった。教育刷新委員会における務台理作による大学と教員養成の整合性と刷新性についての問題提起は、大学が教員養成とその目的をどのように受け取るのか、という重要な課題を呼び起こすものであったが、今日までその根源的な問いが議論されることはなかった。教師教育における大学の自律性と主体性が危ぶまれるなか、大学が回避してきた養成教育への目的意識を自らの教育と研究の責務のなかに定位する道を提示し、目的養成の新たな位相を明らかにする。
1 0 0 0 OA 生体防御機構としてのディフェンシン
- 著者
- 富田 哲治 長瀬 隆英
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.440-443, 2001-07-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 7 9
哺乳類, 昆虫などにおいて感染防御を司る生体内の抗菌物質の存在については以前より知られている. ヒトにおける抗菌ペプチドはディフェンシンと総称され, 細菌, 真菌など広範囲にわたり抗菌活性をもち, このうち粘膜上皮の感染防御に関与しているのがβ-defensin である. 現在, 3種類のβ-defensin が単離・構造決定されているが, human β-defensin-2 (hBD-2) は, 1) 肺, 気管にて発現がみられる, 2) 細菌感染や炎症性サイトカイン刺激にて発現誘導される, という特徴をもっている. そのため, hBD-2は呼吸器感染症により密接な関係をもつことが示唆されている. その抗菌活性機序として従来より細菌細胞膜表面にディフェンシン重合体が孔 (pore) を形成し, 細胞膜透過性を亢進するためと考えられているが, hBD-2ではそれ以外に膜電位への静電気的な関与によるものと考えられている. また発現誘導されるhBD-2の転写活性としてはCD14と Toll like receptors (TLRs) を介してNF-κBを活性化すると報告されている. hBD-2は元来生体で産生されるものであり, 広範囲に抗菌活性を有することより, 今後の臨床的応用が期待される.
1 0 0 0 OA 国内の狂犬病組織培養不活化ワクチン接種犬の抗体保有状況とワクチン接種後の抗体応答
- 著者
- 安田 博美 山中 盛正 江副 伸介 大森 崇司 草薙 公一 西條 加須江 瀧川 義康 天野 健一
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.311-314, 2008-04-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
不活化狂犬病ワクチン接種犬における抗体応答を中和試験によって検討した. 試験には2005年に東京都, 静岡県, 岐阜県, 京都府, 宮崎県および熊本県で飼育されていたワクチン接種犬100頭と未接種犬25頭の合計125頭のペァ血清を用いた. 過去1年間にワクチン接種歴のある犬100頭のうち90頭が有効抗体価25倍以上の中和抗体を保有しており, 8倍以上の抗体価を有する個体の幾何平均抗体価 (geometric mean titers; GMT) は251倍であった. このような犬にワクチンを追加接種すると, 1カ月後には全頭の抗体価が25倍以上に上昇し, GMTは750倍に達した. いっぽう, 今までに接種経験のない25頭にワクチンを接種すると, 23頭が中和抗体を産生したが, 2頭からは抗体が検出されなかった. ワクチン接種1カ月後の抗体価は8倍未満から256倍に分布し, GMTは43倍であった. これらの成績により, ワクチン接種により確実な免疫を付与し, それを維持するためには, 現行の接種プログラムである年1回の追加接種が重要であると考えられる.
1 0 0 0 OA これからの『正規の世界・非正規の世界』と日本の労働市場について
- 著者
- 神林 龍
- 出版者
- 成城大学経済研究所
- 雑誌
- 経済研究所年報 = The annual bulletin of the Institute for Economic Studies (ISSN:09161023)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.5-29, 2020-04-24
1 0 0 0 論理の基礎 : 日常言語と形式論理学
- 著者
- P.F.ストローソン著 常俊宗三郎 木村慎哉 薮木栄夫訳
- 出版者
- 法律文化社
- 巻号頁・発行日
- 1974
1 0 0 0 中国皮影における雷公像の図像的考察
- 著者
- 羅玲
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:24327344)
- 巻号頁・発行日
- no.62, 2017-03-15