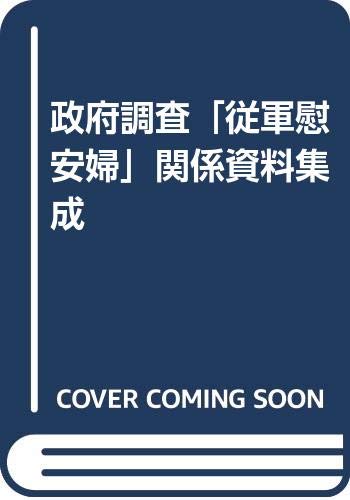- 著者
- Eri Kokubo Hirofumi Sonoki Kenta Aizawa Hiroki Takagi Masayasu Takada Ayako Ito Yuki Nakazato Yasuhiro Takeda Kazuhiro Miyaji
- 出版者
- The Japanese Society of Applied Glycoscience
- 雑誌
- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)
- 巻号頁・発行日
- pp.jag.JAG-2021_0013, (Released:2022-04-19)
Slowly digestible carbohydrates are needed for nutritional support in diabetic patients with malnutrition. They are a good source of energy and have the advantage that their consumption produces a low postprandial peak in blood glucose levels because they are slowly and completely digested in the small intestine. A high-amount isomaltomegalosaccharide containing carbohydrate (H-IMS), made from starch by dextrin dextranase, is a mixture of glucose polymers which has a continuous linear structure of α-1,6-glucosidic bonds and a small number of α-1,4-glucosidic bonds at the reducing ends. It has a broad degree of polymerization (DP) distribution with glucans of DP 10-30 as the major component. In our previous study, H-IMS has been shown to exhibit slow digestibility in vitro and not to raise postprandial blood glucose to such levels as that raised by dextrin in vivo. This marks it out as a potentially useful slowly digestible carbohydrate, and this study aimed to evaluate its in vivo digestibility. The amount of breath hydrogen emitted following oral administration of H-IMS was measured to determine whether any indigestible fraction passed through to and was fermented in the large intestine. Total carbohydrate in the feces was also measured. H-IMS, like glucose and dextrin, did not result in breath hydrogen excretion. Carbohydrate excretion with dietary H-IMS was no different from that of glucose or water. These results show that the H-IMS is completely digested and absorbed in the small intestine, indicating its potential as a slowly digestible carbohydrate in the diet of diabetic patients.
- 著者
- 芝崎 厚士
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.200, pp.200_101-200_118, 2020-03-31 (Released:2020-04-16)
- 参考文献数
- 48
This paper focuses on the main theme of this 200th volume of International Relations: What is the ‘common challenge’, and what is the ‘shared approach’ among all scholars who belong to Japan Association of International Relations? The exploration of this macro-scale issue is taken by the perspective of International Cultural Relations, which seems to effectively deal with the core assumption of this theme.To start with, part 1 configures the systematic understanding of the whole questions, which takes the form of typical dialectic of universal/particular dualism of the discipline: globally universal one International Relations on the one side, and nationally divided many International Relations’ on the other. Also, part 1 pays enough attention to the recent tides of multilingualism and multiculturalism within one scholar or within one national IRs. Then it analyses recent researches on the nature of past and future IR in Japan and future vison of Global IR. Those precedent research has not reached to the further important vision of the global structure of IR, and the paper tries to construct that.Part 2 discusses one of the two main accounts of the basic structure of the discipline of science in general, by examining the researches of Hiroyuki Yoshikawa and Ichikawa Atsunobu. The first is about the theoretical aporia of IR, based on the irrelevances which stems from both the nature of social science / humanity, compared to that of natural science, and the consequence of theory making from the different views toward a given area. Also, this analysis seeks to break through such aporia by making a totally new discipline, which should be called Global Relations.Part 3 explains the second one, which is the theory of interaction between two culturally or lingually different disciplines devised by Kenichiro Hirano and Yanabu Akira. The theory is based on the premise that regards the encounter of two disciplines as mutual ‘encounter’ between the unknown, and that emphasize the unique function of Japanese language which accepts any kinds of foreign concepts through translation.Part 4 introduces the same challenge in the field of global history by Masashi Haneda and tries to acquire some useful implication for advancing the discussion. His contention about the ideal image of making global history through multilingual interaction of different system of knowledges, and rendering asymmetrical power structure between English or western languages and non-Western language including Japanese has ample implication to IR world, which has much asymmetrical relations between English language and others. The concluding section summarizes the whole argument and seeks to suggest the future vision for the future of ‘Japanese’ International Relations.
1 0 0 0 OA 行動指標を用いたCRMスキル計測手法の開発
- 著者
- 津田 宏果 飯島 朋子 野田 文夫 Tsuda Hiroka Iijima Tomoko Noda Fumio
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 = JAXA Research and Development Report (ISSN:13491113)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-RR-09-001, 2009-07-31
ヒューマンエラーに対抗する有効手段として、航空機乗員に対してCRM訓練が実施されている。訓練の妥当性を検証し、訓練内容を改善していくためには訓練による効果を継続・調査することが必要である。一方、航空機乗員においてどのようなCRMスキルが発揮され、また欠如されているかを把握することも、安全な運航を達成するために重要である。JAXAではCRMスキルを実践的なものとして定着化させるため、CRMを実践するための乗員の行動指標(指標として明確に示される具体的な行動)を開発してきたが、本研究ではこの行動指標を用いて、乗員のCRMスキル行動を計測する手法を提案・開発した。開発した計測手法は数回の改良を重ね、最後に模擬LOFTを通して評価を行った。
1 0 0 0 米国国立公文書館所蔵資料 ; 国立国会図書館所蔵資料
- 著者
- 女性のためのアジア平和国民基金編
- 出版者
- 龍溪書舎
- 巻号頁・発行日
- 1998
- 著者
- 高木 滋樹 北村 章 丸本 卓哉
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.41-48, 1992-03-01 (Released:2017-05-31)
- 被引用文献数
- 3
1)キチンと同様に土壌内で特異的に放線菌密度を高める有機物をスクリーニングした結果,光合成細菌処理汚泥発酵物(CPBS)が選抜された。2)第1報で選抜した5株の拮抗菌をCPBSに添加・培養させた資材を調製した。調製した資材は細菌,放線菌密度が高く,添加した拮抗放線菌の存在が確認された。3)CPBSと拮抗放線菌を組み合わせた資材のダイコン萎黄病及びキュウリつる割病に対する発病抑制効果を検討した結果,発病抑制効果が確認された。発病抑制効果は第1報で報告した拮抗菌のみの場合よりも有機物と拮抗菌を組み合わせた場合で大きく,また単菌株よりも複数の拮抗菌を組み合わせた場合に顕著であった。4)ダイコン萎黄病発病抑制試験において添加した各菌株は土壌及び根部より再分離されたが,菌株によって菌密度は異なり,菌株により土壌及び根部での定着とその活動は異なると推察された。5)4種類の異なった土壌において,拮抗菌を含む資材Aは放線菌密度を高め,F. oxysporum密度には影響を与えなかった。6)以上のように放線菌密度を選択的に高める有機物と拮抗菌を組み合わせた資材は各種土壌で放線菌密度を高め,ダイコン及びキュウリにおいて発病を抑制した。しかしその作用については今後の解明が必要である。
1 0 0 0 OA 中性子結晶解析の進展が明らかにする酵素反応機構
- 著者
- 河野 史明 栗原 和男 玉田 太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.216-222, 2021 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 22
Neutron crystallography enables direct observation of hydrogen atoms which play crucial roles in the physiological functions of enzymes, including molecular recognition through hydrogen bonding and catalytic reactions involving proton-coupled electron transfer. Now neutron crystallography is a limited method for protein structure determination, but steadily catholicizes with an operation of diffractometers for bio-macromolecules at neutron facilities and accumulated techniques for sample preparation. In this article, we give a commentary on the current status of neutron crystallography for bio-macromolecules in the world, and illustrate our recent results, neutron structural analyses of copper amine oxidase and copper-containing nitrite reductase, which provide in-depth understandings of the enzymatic reaction mechanism.
1 0 0 0 OA DNAポリメラーゼηによるリン酸ジエステル結合の形成過程の観察
- 著者
- 中村 照也 山縣 ゆり子 YANG Wei
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.254-257, 2013 (Released:2013-09-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
A number of structural and kinetic studies of DNA polymerases have proposed the catalytic mechanism of the nucleotidyl-transfer reaction. However, the actual process has never been visualized. Here we show the nucleotidyl-transfer reaction process catalyzed by human DNA polymerase η using time-resolved protein crystallography. In sequence, the nucleophile 3′-OH is deprotonated, the deoxyribose at the primer end converts from C2′-endo to C3′-endo, and the nucleophile and the α-phosphate of dATP approach each other to form the new bond. A third Mg2+ ion, which arrives with the new bond and stabilizes the intermediate state, may be an unappreciated feature of the two-metal-ion mechanism.
- 著者
- 村田 真樹 神崎 享子 内元 清貴 馬 青 井佐原 均
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.51-66, 2000-01-10 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 15
本稿では単語の羅列を意味でソートするといろいろなときに便利であるということについて記述する. また, この単語を意味でソートするという考え方を示すと同時に, この考え方と辞書, 階層シソーラスとの関係, さらには多観点シソーラスについても論じる. そこでは単語を複数の属性で表現するという考え方も示し, 今後の言語処理のためにその考え方に基づく辞書が必要であることについても述べている. また, 単語を意味でソートすると便利になるであろう主要な三つの例についても述べる.
1 0 0 0 地形プロセスの理解を促すための3Dプリントの活用と効果検証
1 0 0 0 OA マンボウとヤリマンボウにおける体表模様による個体識別の可能性
- 著者
- 久志本 鉄平 柿野 敦志 下村 菜月
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.1-7, 2022-04-01 (Released:2022-04-02)
- 著者
- 徳谷 聡 佐藤 隆弘 中島 菊雄 古島 弘三 塩崎 崇
- 出版者
- 東北膝関節研究会
- 雑誌
- 東北膝関節研究会会誌 (ISSN:09175164)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.19-22, 2005-07-09 (Released:2018-04-16)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 3.白血病の分子病態
- 著者
- 黒川 峰夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.9, pp.2370-2374, 2013-09-10 (Released:2014-09-10)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA パンツパターン作図法の検討―図学的手法による―
1 0 0 0 OA ユネスコの地球市民教育が追究する能力 ―グローバル時代における価値教育の新たな展望―
- 著者
- 小林 亮
- 雑誌
- 玉川大学教育学部紀要 (ISSN:13483331)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.19-32, 2019-03-31
地球市民教育(GCED: Global Citizenship Education)は,国連の専門機関ユネスコがESDとともに主幹教育プログラムとして位置づけている重要課題である。本論文は,認知面,社会情動面,行動面で地球市民性に求められる能力を分析しながら,地球市民教育が多元的アイデンティティの育成を通じて,視点取得と対話のスキルに基づく国際的な葛藤解決能力の開発に向けた効果的なアプローチであることを論証することを目的としている。日本人としての国民アイデンティティと地球市民アイデンティティが矛盾なく共存しうるだけでなく,グローバル人材として必要な複眼的思考の獲得のために自己の多元性が有効であることが議論された。
1 0 0 0 OA 医療観察法病棟における治療意欲の乏しい統合失調症患者に対する作業療法の有用性
- 著者
- 南 庄一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.835-842, 2021-12-15 (Released:2021-12-15)
- 参考文献数
- 10
医療観察法病棟において,殺人未遂事件を起こした統合失調症とADHDの対象者に関わる機会を得た.対象者は統合失調症の病識が乏しく,事件の内省が困難であり,医療観察法病棟の入院治療に対する意欲が持てず,介入は難航した.しかし,筆者と革細工や病棟行事の実行委員を担った体験を通して成功体験を重ね,その後の治療には自発的に参加するようになった.ここから,作業療法は医療観察法病棟での入院治療に意欲の乏しい対象者に対して,MDTによる社会復帰に向けた治療の導入部分を担い,作業を介して対象者と関係性を結び,自己効力感を高めることができ,主体的な治療への参加を可能にすると考えられた.
1 0 0 0 OA 歌唱教材としてのヒット曲に潜む男女観 : 高等学校教科書掲載曲の歌詞傾向
- 著者
- 尾崎 祐司 Yuji Ozaki
- 出版者
- 上越教育大学
- 雑誌
- 上越教育大学研究紀要 (ISSN:09158162)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.237-247, 2014-03
1 0 0 0 OA ポリフェノールの消化管シグナルを介した生体調節機能解明に関する研究
- 著者
- 山下 陽子
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.77-82, 2022 (Released:2022-04-19)
- 参考文献数
- 23
近年, 食品の三次機能である生体調節機能を持つ食品成分に注目が集まっている。筆者は, 多様な機能性を有することが明らかにされているポリフェノールのうち, プロシアニジンやテアフラビンなどの縮合型タンニンの生体調節機能の検証を行ってきた。これらのポリフェノールは, ほとんど体内に吸収されない難吸収性であり, 生体利用性が低いと考えられている。本稿では, 難吸収性のポリフェノールの特性に着目して, 消化管を起点とする新規な生体調節機能として, 消化管ホルモンであるグルカゴン様ペプチド-1 (GLP-1) の分泌促進を介した肥満・高血糖予防作用とその作用機構について解説する。また, 難吸収性ポリフェノールによるGLP-1分泌促進作用は, 血管内皮型一酸化窒素合成酵素の活性化を介した血管機能の向上にも寄与することも紹介する。さらに, プロシアニジンの生体調節能と体内時計の関係についても触れる。これらのことから, 難吸収性のポリフェノールは多臓器間のシグナルネットワークを介してさまざまな生体調節機能を発揮しうることと, 機能を発揮するのに適したタイミングがあることがわかった。