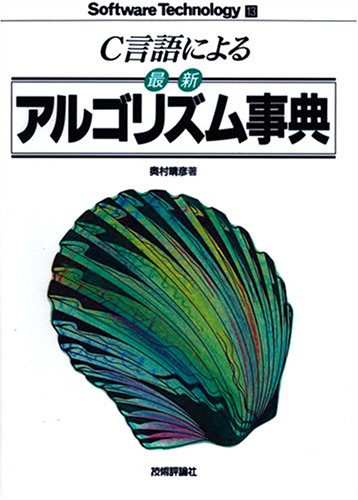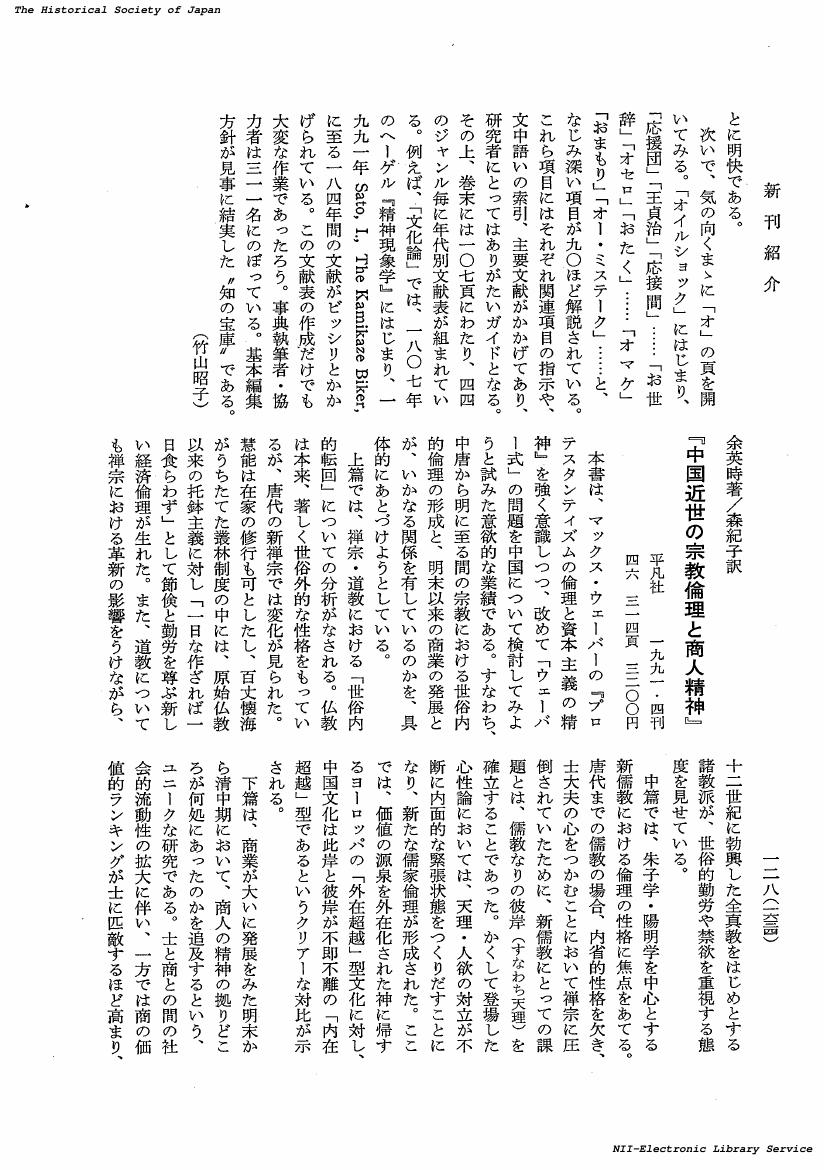1 0 0 0 OA 座位姿勢からみた高齢障害女性の車いす適合範囲の検討
- 著者
- 木之瀬 隆 栗原 トヨ子 寺山 久美子
- 出版者
- 日本保健科学学会
- 雑誌
- 東京保健科学学会誌 (ISSN:13443844)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.223-225, 1999-12-25 (Released:2017-10-27)
- 被引用文献数
- 1
車いすの適合の基本は使用者の身体寸法と合わせることである。しかし, 高齢障害者では既製の普通型車いすを用いることが多く, 座位姿勢や車いす操作について不具合が生じる。座位姿勢では仙骨座りや褥瘡が発生し, 社会的には車いす座位の身体拘束の問題まである。一般に普通型車いすはJIS規格大型が使用され, 高齢障害者の身体寸法と比較すると不適合が予測された。今回, 高齢者の身体寸法と普通型車いすの適合範囲について検討した結果, 70歳台の高齢障害女性では, 肘掛け, 座幅, 座奥行きについて不適合が明らかになった。
1 0 0 0 C言語による最新アルゴリズム事典
1 0 0 0 OA 狂犬病を疑われたフェレットに咬まれて狂犬病曝露後発病予防を行った1例
- 著者
- 高山 直秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.3, pp.274-276, 2004-03-20 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 2
A woman bought two ferrets from a pet shop. These ferrets became brutal soon, excreted a large amount of saliva and then died. One of these ferrets had bitten the owner's hand before it died. As for the ferret, rabies and distemper were suspected. To receive rabies post-exposure prophylaxis the woman visited our vaccine clinic. To clarify the ferret's cause of death virological examinations were requested to Tokyo Metropolitan Institute of Public Health. The rabies examination of the ferret that had bitten the owner was performed according the law. However the tests of the other ferret that had not bitten the owner was not done though it was suspected to die from rabies, because the law does not mention such a case like the latter ferret. The virological tests concerning distemper were not accepted by the Institute, so the examination was done at a private laboratory. These two ferrets were diagnosed to have had distemper from the results. It is clearly shown from this biteaccident that the legal system where the cause of the animal's death required is extremely incomplete in Japan.
1 0 0 0 OA 低温焼きもどしによる焼入れ中炭素鋼の引張強さと弾性限の変化
- 著者
- 新部 純三 熊谷 正芳 田邉 晃弘 水野 湧太
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-00082, (Released:2021-08-05)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
Although elastic limit and tensile strength are essential for mechanical strength design, the measurement of high hardness materials is a challenge due to their sensitivity on notches. As an alternative, the tensile strength can be easily assumed from hardness using the conversion table (e.g. SAE J 417); however, the table does not include the data for high hardness region, namely tempered materials at low temperature. We performed tensile tests and obtained elastic limits and tensile strengths of quenched martensitic medium-carbon steel with tempering at several temperatures. The hardness was monotonically decreased with the increase of tempering temperature. However, the tensile strength and elastic limit improved as the increase of temperature at low tempering temperature. In contrast, at high tempering temperature, the tensile strength and elastic limit were decreased with increase of tempering temperature. Consequently, the ratios of hardness to tensile strength or elastic limit were changed below or above the transition point. The ratios were constant below a tempering temperature (290 ℃ for elastic limit and 200 ℃-300 ℃ for tensile strength in the present experiments) and increased with the increase of the tempering temperature above the temperature. The variation of the ratio, hardness to tensile strength, is due to the brittle fracture on high hardness specimens before reaching the threshold to start plastic instability. In addition to, it is considered that the variation of the ratio, hardness to elastic limit, is caused by another mechanism, a decrease in elastic limit due to mobile dislocations.
1 0 0 0 空手の型構造に関する基礎理論(そのV)
- 著者
- 土谷 秀男
- 出版者
- Japanese Academy of Budo
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.183-184, 1987
1 0 0 0 OA 「運動」概念に関する史的考察--雑誌『運動界』記事にみる「運動」の概念
- 著者
- 野口 邦子
- 出版者
- 東洋大学社会学部
- 雑誌
- 東洋大学社会学部紀要 = The Bulletin of Faculty of Sociology,Toyo University (ISSN:04959892)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.19-33, 2004-02
- 著者
- 吉澤 誠一郎
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.9, pp.1634-1635, 1991-09-20 (Released:2017-11-29)
1 0 0 0 空手の型構造に関する基礎理論(VI)
- 著者
- 土谷 秀男
- 出版者
- Japanese Academy of Budo
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.57-58, 1988
1 0 0 0 OA 食品中における微生物増殖の数学モデル
- 著者
- 藤川 浩 伊藤 武
- 出版者
- Japanese Society of Food Microbiology
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.203-208, 1996-03-20 (Released:2010-07-12)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 拡大するアメリカ合衆国の都市農業とその課題
- 著者
- 二村 太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本不動産学会
- 雑誌
- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.32-37, 2020-06-29 (Released:2021-06-29)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
This paper examines the recent growth of urban agriculture in the United States. Since the late 20th century, spaces and practices of urban agriculture have increased substantially in US cities. This is especially significant in areas where land prices are relatively low and/or in plots that were vacant. Due to increasing interest in production and supply of local foods, urban agriculture is set to continue growth in the long term. This, however, conflicts with the potential development of land for urban land use, such as residential or commercial purposes. This paper suggests that revitalization of property where urban agriculture and local community’s interests coexist is critical to the future of urban agriculture.
1 0 0 0 世界コンピュータ将棋選手権における対戦結果分析
- 著者
- 瀧澤 武信
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2008論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.11, pp.128-131, 2008-10-31
1 0 0 0 OA U二〇二号 : 独逸潜航艇戦実録
- 著者
- スヒーゲル・フオン・チユー・ペツケルスハイム 著
- 出版者
- 文雅堂
- 巻号頁・発行日
- 1917
1 0 0 0 世界コンピュータ将棋選手権における 対戦結果分析(3)
- 著者
- 瀧澤 武信
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2010論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.12, pp.55-58, 2010-11-12
世界コンピュータ将棋選手権は,第8回は,上位予選,下位予選と決勝,第9回以降は1次予選,2次予選,決勝という形で行われている.第11回は,決勝に10チームが参加して行われたが,通常は決勝に8チームが参加して行われている.ここでは,決勝8チーム制が定着した2002年から2010年までの決勝における先手の勝率,初手から6手目までの流れ,戦形別成績について分析する.
1 0 0 0 OA 向山-マイケル反応は実は電子移動反応だった!
- 著者
- 兼田 直武
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.66, 1992-01-01 (Released:2018-08-26)
- 著者
- 徐 希姃
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.41-50, 2005
20世紀美術は、科学技術の進歩を背景として技術を造形表現に積極的に導入しなから繰り広げられた。モホイ=ナジもモーター、金属部品、写真、光学機器などを自ら造形表現に導入して先駆的な活動を展開し、テクノロジー・アートの先駆者として認められている。本研究では、モホイ=ナジの造形理念の中心を占める「光の造形」概念を彼の作品と理論書から探り、モホイ=ナジによってなされた「光の造形」の視覚的意味を探ることを目的とする。そこで、彼の「光の造形」概念の形成過程を踏まえて、「光の造形」概念の中心を占める"Optical"という意味をVisualという言葉との比較によって検討し、"Optical"概念から検討した「光の造形」の視覚的意味を探った。モホイ=ナジの「光の造形」は、1922年にベルリンに亡命し、ドイツの工業化された環境の影響を受けて形成されたもので、物に光が当たることによって物の表面が明るく見える現象を造形に取り入れることから始まった。彼は眼が光を媒介として物を見るという視覚に関る生理的な仕組みを意味する"Optical"という概念に基づき、光そのものやそれによる視覚の生理的な反応を用いた表現を「光の造形」概念としている。彼の「光の造形」概念は、工業的な環境を背景にして用いられ始めた光という新しい材料とその表現について考える上で良い手がかりになると思われる。
1 0 0 0 空手の型構造に関する基礎理論(その3)
- 著者
- 土谷 秀男
- 出版者
- Japanese Academy of Budo
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.41-42, 1985
1 0 0 0 IR よく鳴る風鈴の力学的考察
- 著者
- 下村 裕
- 出版者
- 慶應義塾大学法学研究会
- 雑誌
- 法學研究 : 法律・政治・社会 (ISSN:03890538)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.1074(13)-1086(1), 2009-01
1 序論2 風鈴のモデル化2.1 二重振り子2.2 初期条件2.3 解とその極大値3 極大値の最大条件3.1 一般の場合3.2 重量比, あるいは長さ比が固定されている場合4 結論