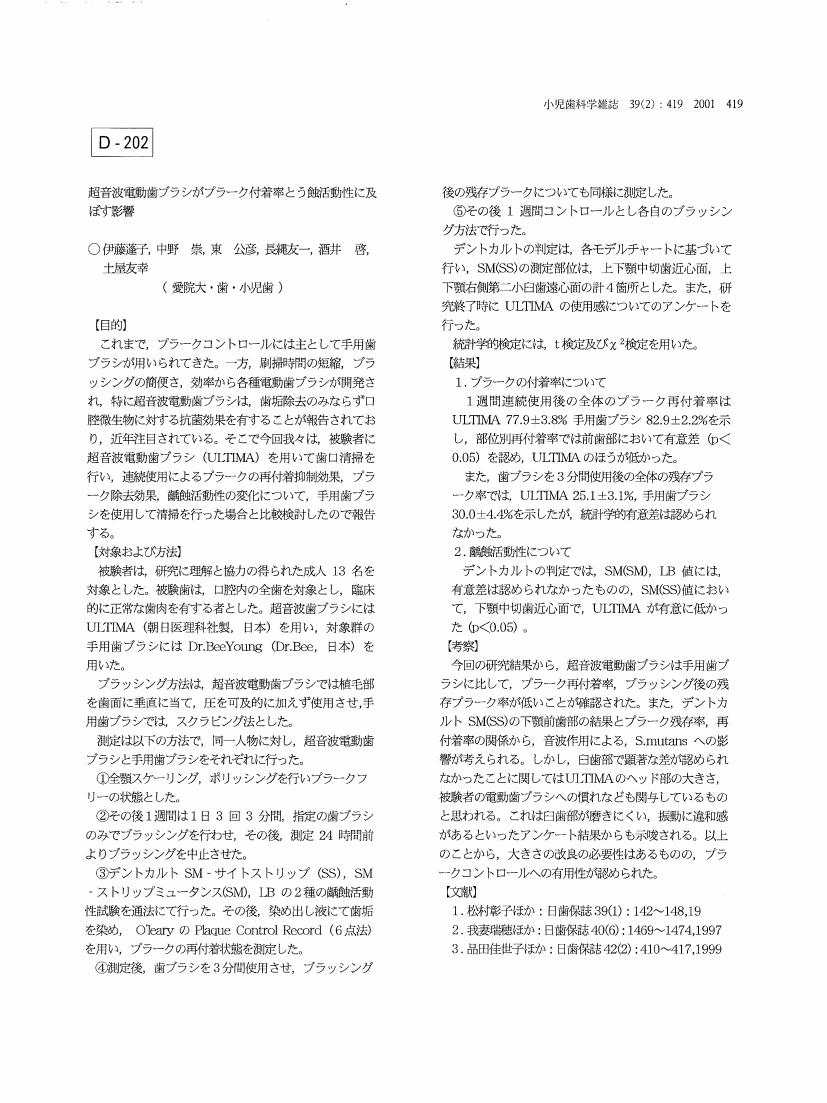2 0 0 0 OA ブレイクダンスにおける踊りの習得とその発展
- 著者
- 清水 大地 岡田 猛
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, 2013
本研究ではブレイクダンスにおける特定の踊り(技)の習得過程に注目し,エキスパートダンサーを対象とした長期のフィールドワーク,インタビューによる縦断的検討を行った.インタビュー回答や映像の分析より,複数のスランプを経て踊りの質を向上させたこと,スランプでは身体の使い方を試行錯誤し新しい使い方を発見したこと,その踊りにおける身体動作を利用して新しい踊りを随時創作したことが示された.
2 0 0 0 OA 超音波電動歯ブラシがプラーク付着率とう蝕活動性に及ぼす影響
- 著者
- 伊藤 蓬子 中野 崇 東 公彦 長縄 友一 酒井 啓 土屋 友幸
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.419-419, 2001-04-01 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 第一次世界大戦と日本の植民地経営 : 帝国日本総力戦体制への道のり
- 著者
- 釜谷 周子 小林 基 中井 勇人 濱田 恭幸 柳 侑子
- 出版者
- 大阪大学歴史教育研究会
- 雑誌
- 大阪大学歴史教育研究会 成果報告書シリーズ (ISSN:21869308)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.21-44, 2015-03-15
2014年度大阪大学歴史教育研究会院生グループ報告(2)
2 0 0 0 OA セルビア法―ローマ・ビザンツとオーストリアの法伝統の間で
- 著者
- シーマ・ アヴラモーヴィチ 松本 英実 訳
- 出版者
- 東洋大学国際哲学研究センター
- 雑誌
- 国際哲学研究 = Journal of International Philosophy (ISSN:21868581)
- 巻号頁・発行日
- no.別冊4, pp.95-107, 2014-08-01
- 著者
- 丸川 雄三
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. PRMU, パターン認識・メディア理解
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.493, 2014-03-06
発表者がこれまで手掛けてきた「文化遺産オンライン」,「想-IMAGINE国立美術館」,「実業史錦絵絵引」などのウェブサイトの紹介を通して,文化財情報発信において画像資料が必要とされている場面を示すとともに,画像資料の有効活用を促すための技術的課題について論じる.
2 0 0 0 IR 赤十字リポジトリ導入の目的と運営状況
- 著者
- 天野 いづみ
- 出版者
- 日本医学図書館協会
- 雑誌
- 医学図書館 (ISSN:04452429)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.44-50, 2015-03
- 著者
- 江成 元伸 藤井 文絵
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.30-34, 2015
- 著者
- 石原 眞理
- 出版者
- 社団法人情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.74-79, 2009-02-01
ここ数年,図書館関係の機関・団体が,図書館員の研修や養成に関する調査研究を行っている。本稿では,主に全国公共図書館協議会が行った研究を基に,図書館員の研修とキャリアパスについて考察した。図書館においては,急激に人員の削減や非正規職員化が進んでいる。一方,図書館に対する利用者の期待は,年々高まっている。図書館の現場では,従来から続いている図書・逐次刊行物などの現物提供に加え,ITC関連の技術の進展など図書館サービスをめぐる変化がある。このような状況の中で,研修の主催側は,これまで以上に研修の強化が必要になっている。図書館員側は自らのキャリアパスについての認識を持ち,受講する研修を主体的に選択することが必要であるだろう。
- 著者
- 前田 朗 加藤 寛士 高橋 菜奈子
- 出版者
- 学術文献普及会
- 雑誌
- 大学図書館研究 = Journal of college and university libraries (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- no.103, pp.9-15, 2016-03
2 0 0 0 OA ミヤンマーのナッ信仰とナッカドー - タウンビョンとヤタナグの祭りを通して -
- 著者
- 中村 羊一郎
- 出版者
- 静岡産業大学
- 雑誌
- 静岡産業大学情報学部研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-32, 2015-03-01
2 0 0 0 OA 教師志望の規定要因に関する研究 : 大学生の家庭的背景に着目して
- 著者
- 太田 拓紀
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.318-330, 2008-03-31
This paper examined factors that lead university students to pursue a teaching career by focusing on their family backgrounds, A questionnaire survey was conducted among students in 18 universities to evaluate their father's profession, level of education in family, experience of lesson (e.g. sports, cramming school) in childhood and their outlook of the future. The results show that among the students pursuing teaching, the majority of their fathers are white-•collared businessmen, and less blue-collared businessmen and farmers. Further, these students have a stronger cultural and educational experience in their family. In addition, male students tend toward sports, while female students take music lessons in their childhood. On investigating the valuable factor in their future, it is found that students pursuing teaching are less status-oriented and more family-oriented. Finally, the author examined which factors affect the aspiration toward a teaching career from the above mentioned variables. Using multinomial logistic regression, variables such as level of education in the family, experience in sports and music, and family-orientation, raises the possibility of a student aspiring to be a teacher. In addition, it is inferred that family-oriented disposition of would-be teachers is related to "familism”, which is regarded as a tradition in teachers' culture.
2 0 0 0 OA 1894年庄内地震と1896年陸羽地震の写真資料
- 著者
- 大迫 正弘
- 出版者
- 国立科学博物館
- 雑誌
- Bulletin of the National Science Museum. Series E, Physical sciences & engineering (ISSN:03878511)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.1-11, 2005-12
Late in the 19th century two earthquakes struck northeastern Honshu at an interval of two years. The Imperial Earthquake Investigation Committee reported on the 1894 Shonai Earthquake, including many handwritten copies from photographs in the form of blueprints or dry plates, which are now kept in the collection of the National Science Museum. In contrast, fewer photographs of the 1896 Riku-u Earthquake are left in the collections. This was the case for the investigations of the earthquake at that time, although the event showed interesting phenomena in seismology, such as apparent faults. Afterwards, Dr Akitsune Imamura made a report of the Riku-u earthquake, introducing photographs in an album donated from an individual. This rare material is also preserved in the NSM.
2 0 0 0 OA 日本語の現在 : 「ラ抜き言葉」の創発
- 著者
- 金杉 高雄
- 出版者
- 太成学院大学
- 雑誌
- 太成学院大学紀要 (ISSN:13490966)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.53-62, 2012-03
"現代日本語については研究分野が多種多様に行き渡っている。音韻、形態、意味、文法の各分野ではかなりの膨大な調査と研究が試みられてきている。そのような多岐にわたる研究の中でも、現代日本語が今、いかに変化を遂げつつあるのか、そしてかなり以前から変化が起こり、現在も進行中である現象について調査・考察を行う。10代の人々が使用する語彙、発音の仕方、アクセントの置き方を目の当たりにすると、驚きと同時に非常に興味深く感じることがよくある。言語の移り変わりに関心をいだき、その変化の原因を探ろうとする側にとっては生きた貴重な教材であり、研究対象となる。電車に乗り合わせた中学生、高校生の「言語」にはいささか、面食らう。当のご本人たちにとっては自然な語彙、文法、発音、アクセントのはずである。助詞、助動詞らしき語を何とか聞き取っても、話が盛り上がるにつれて、言っていることが理解できなくなることがある。それだけ、言葉の変化が目まぐるしく進んでいる証拠であろう。言葉はこころと密接に関係しているので、変化が激しい分、それだけ認知主体(話し手・聞き手)の思考態度も劇的に変化していると捉えることができる。新たに創造された表現の動機づけを探ることは根気の要る多くの時間を費やす調査・研究になる。しかし、我々が普段、見聞きする新造語は言葉とこころとの深い絆がいかにして成立しているかを捉えることができる最良の素材の一つである。その理由に日本という土地と文化的背景を共有していることが挙げられる。本稿は新造語として若年層に特有と見なされているはずの「ラ抜き言葉」を中心に考察を進め、言葉とこころとの密接な関係に一歩でも接近することを目指す論考である。"
- 著者
- 井上 彰
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 三田商学研究学生論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, pp.1-18, 1997-03-10
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1469, pp.40-43, 2008-12-08
九州・大隅半島の北に位置する鹿児島県志布志市。森と農地を切り開いた先に、突如として巨大な施設が現れる。 建物の中には半透明のビニールに覆われた169もの「池」が整然と並び、水面からはもうもうと湯気が上がる。摂氏30度前後に保たれた水の中では、無数のウナギが身をよじらせるように泳いでいる。
2 0 0 0 ロシア語イントネーションの離散性
- 著者
- 河井 亨
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.641-653, 2011-04-25
This paper attempts to clarify the lives of people that socially were becoming individualized by reviewing theories of G. H. Mead and E. H. Erikson of the relationship between individual and society. They were organizing their own lives rather than adapting them to their life course provided by society. The theories of Mead and Erikson, though they had been proposed in the early 20th century, were still eff ective to consider their own lives to be organized. Because of this, it was valuable to review and consider these theories. As a result, I found that the relationship between self and community could be located in the relationship between individual and society by reviewing Mead’s interactional social psychology, Erikson’s identity theory, and Mead’s social theory of practice. In this mediation, individuals’ selves were constructed in the communities and those communities consisting of society were also reconstructed by people’s involvement.
2 0 0 0 芸術における必然と偶然 (シンポジウム「偶然性と必然性」提題)
- 著者
- 桑原 俊介
- 出版者
- 国士館大学哲学会
- 雑誌
- 国士館哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.56-86, 2014-03