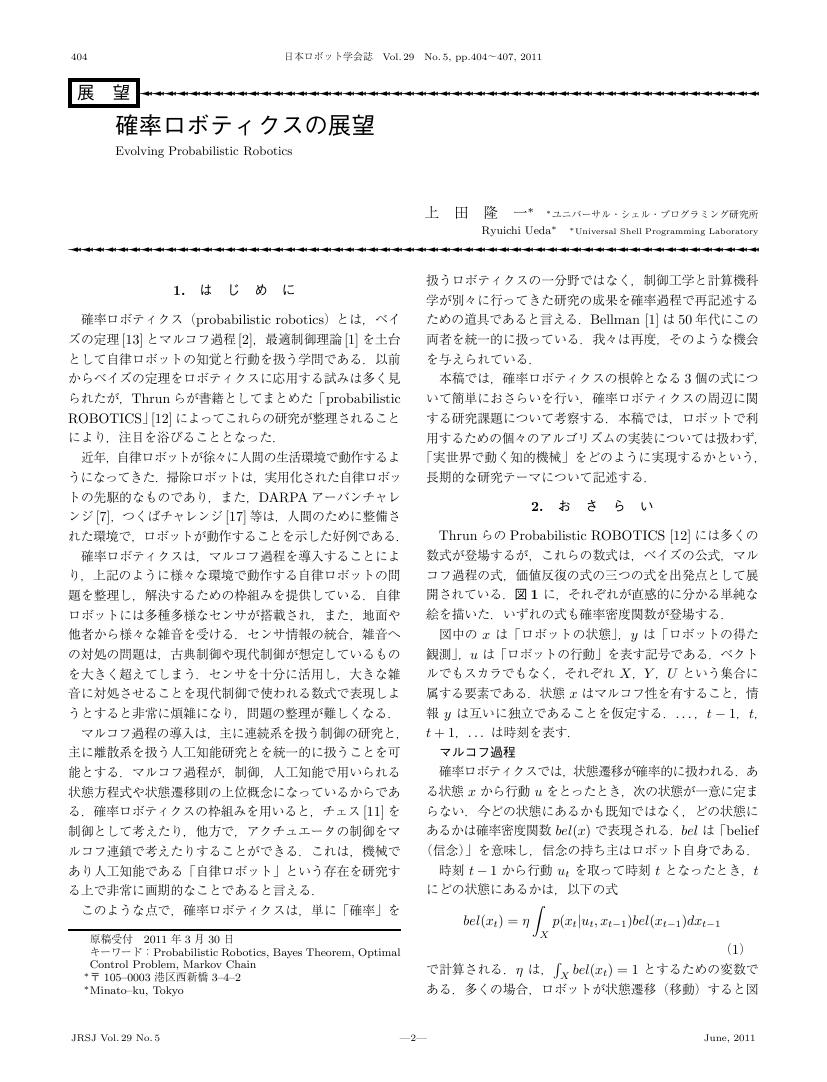48 0 0 0 OA アリジゴクの殺虫性タンパク質および関連物質の分子構造と作用機構に関する研究
- 著者
- 松田 一彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.20-25, 2004-01-01 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 21
48 0 0 0 OA レボフロキサシンの副作用による両側アキレス腱断裂の一例
- 著者
- 久保 壱仁 田行 活視 渡邊 匡能 佐藤 元紀
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.244-246, 2017-03-25 (Released:2017-05-01)
- 参考文献数
- 8
レボフロキサシンの稀な副作用としてアキレス腱障害がある.今回レボフロキサシン投与が誘因と考えられる両側アキレス腱断裂の1例を経験したので報告する.症例は70歳男性.尿路感染症に対しレボフロキサシン500 mg/日で4日間投与され,3日目より両側足関節痛を認めていた.レボフロキサシン投与中止後NSAIDS内服にて経過観察されていたが4週後起床時に両側足関節腫脹を認め,徐々に階段昇降やつま先立ちができなくなったためMRI撮影したところ両側アキレス腱断裂を認めた.両側アキレス腱縫合術を施行し,術後3週間免荷期間を設け,その後荷重訓練を開始した.現在は自立歩行可能で再断裂は認めていない.ニューキノロン系薬剤の副作用による腱障害の機序については明らかにされていないが,高齢,ステロイド内服,慢性腎不全などがリスク因子である.
48 0 0 0 OA 多粒子系の量子論
- 著者
- 大井 万紀人
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.10, pp.733-734, 2018-10-05 (Released:2019-05-17)
新著紹介多粒子系の量子論
48 0 0 0 OA ポスト・アンダークラスの貧困論に向けて ――概念の受容と使用のプラグマティック社会学――
- 著者
- 川野 英二
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.59-67, 2018-06-01 (Released:2021-07-10)
- 参考文献数
- 21
48 0 0 0 OA 自尊心の高低と不安定性が被援助志向性・援助要請に及ぼす影響
- 著者
- 脇本 竜太郎
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.160-168, 2008 (Released:2008-03-19)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4 3
自尊心の高低と援助要請に関しては,正の関係を想定する脆弱性仮説と負の関係を想定する認知的一貫性仮説・自尊心脅威モデルという対立する仮説が提案され,双方を支持する知見が蓄積されている。本研究では,そのような知見を整理する1つの視点として自尊心の不安定性を取り上げ,自尊心の高低と不安定性が青年の被援助志向性および援助要請に及ぼす影響について,対人ストレスイベントの頻度・日間変動を統制した上で検討した。援助要請についてはさらに,家族・非家族という対象ごとの検討も行った。 48名の大学生・大学院生が1週間の日誌法による調査に回答した。階層的重回帰分析の結果,自尊心の高低と被援助志向性・援助要請の関係は,自尊心の不安定性により調節されていた。具体的には,自尊心が不安定である場合は高さと被援助志向性,援助要請の回数は負の関係を,特に自尊心が安定している場合は正の関係を持つことが示された。また,対象別の援助要請の分析では,上記のような関係が非家族への援助要請数でのみ認められた。自尊心の高低と同時に不安定性を検討することの意義・有用性および今後の研究に対する示唆について議論した。
48 0 0 0 OA 確率ロボティクスの展望
- 著者
- 上田 隆一
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.5, pp.404-407, 2011 (Released:2011-07-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3 3
- 著者
- 麦倉 佳奈 Eldrin DLR. Arguelles 鎌倉 史帆 大塚 泰介 佐藤 晋也
- 出版者
- 日本珪藻学会
- 雑誌
- Diatom (ISSN:09119310)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.49-53, 2022 (Released:2022-10-26)
- 参考文献数
- 18
We report the occurrence of Cymbella janischii in Ado River flowing into the Lake Biwa in 2022; this is the first report of this diatom from Kinki Area, Japan. Cymbella janischii has been known as an endemic species in the Pacific Northwest of North America. In Japan, however, it has become known as an invasive species. It is likely that it was introduced from the native locality into Kyushu in 2006 or shortly before, and has rapidly spread throughout Japanese rivers. In Ado River, it formed massive colonies on rocks by means of mucilage stalks secreted from one end of the cells, but the colony scattered only on the river bed. The cell had a dorsiventral outline, with an intricately shaped plastid. Fluorescence microscopy on living cells stained with SYBR Green and fluorescence-labeled lectin revealed that the position of the nucleus was appressed to the ventral side, and polysaccharide covered the entire frustule as well as the mucilage stalks. We also confirmed the identity of the species with the sequence of the 18S ribosomal RNA gene.
48 0 0 0 OA 脚式移動機構の設計(<特集>「バイオメカニズムと設計」)
- 著者
- 金子 真 阿部 稔
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.10-17, 1985-02-01 (Released:2016-10-31)
48 0 0 0 OA 因子分析モデルにおける因子回転問題
- 著者
- 山本 倫生
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 計算機統計学 (ISSN:09148930)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.21-44, 2019 (Released:2020-07-17)
- 参考文献数
- 56
探索的因子分析において, 因子負荷量行列を用いて結果の解釈を行う際には, いわゆる因子回転を行うことが有用であり, これまでに数多くの回転方法が開発されてきている. 因子回転問題自体は古典的な問題であり, 例えば Browne (2001) では2000年までの研究内容がよくまとめられている. 一方で, 因子回転基準の最適化における一般的なアルゴリズムである勾配射影法の開発や, component loss functionを用いた回転方法の提案など, 2000年以降も因子回転問題に関連する研究が継続して行われている. 本稿では因子回転法やその最適化アルゴリズムの古典的内容から比較的近年の内容についても解説を行うとともに, 構造方程式モデリングでの因子回転の利用や正則化法との関連などについても言及する.
48 0 0 0 OA TRPチャネルと痛み
- 著者
- 富永 真琴
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.3, pp.128-132, 2006 (Released:2006-05-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 3 3
TRPチャネルは6回の膜貫通領域を有する陽イオンチャネルであり,4量体として機能すると考えられている.また,大きなスーパーファミリーを形成し,哺乳類では6つのサブファミリーに分かれている.カプサイシン受容体TRPV1は1997年にクローニングされ,感覚神経特異的に発現し,カプサイシンのみならず私達の身体に痛みをもたらすプロトン,熱によっても活性化される多刺激痛み受容体として機能することが,TRPV1発現細胞やTRPV1遺伝子欠損マウスを用いた解析から明らかにされた.さらに,TRPV1は炎症関連メディエイター存在下でPKCによるリン酸化によってその活性化温度閾値が体温以下に低下し,体温で活性化されて痛みを惹起しうることが分かった.このTRPV1の機能制御機構は急性炎症性疼痛発生の分子機構の1つと考えられている.カプサイシンは逆説的に鎮痛薬としても使われているが,その作用メカニズムの一つとしてTRPV1の脱感作機構が考えられている.痛みを惹起する刺激(温度刺激,機械刺激,化学刺激)のうち,温度刺激による痛みはおよそ43度以上あるいは15度以下で起こるとされている.TRPV1は初めて分子実体の明らかになった温度受容体であり,現在までに8つの温度感受性TRPチャネルが報告されている.侵害刺激となる温度によって活性化するTRPV1,TRPV2,TRPA1は侵害温度刺激受容に関与するものと思われる.感覚神経に発現する他の温度感受性あるいは機械刺激感受性TRPチャネルも侵害刺激受容に関わる可能性が考えられている.これらの侵害刺激受容TRPチャネルは,新たな鎮痛薬開発のターゲットとして注目される.
48 0 0 0 OA 石油・ガス、炭鉱、畜産部門からの排出による過去30年間のメタン濃度の増加
- 著者
- Naveen CHANDRA Prabir K. PATRA Jagat S. H. BISHT 伊藤 昭彦 梅澤 拓 三枝 信子 森本 真司 青木 周司 Greet JANSSENS-MAENHOUT 藤田 遼 滝川 雅之 渡辺 真吾 齋藤 尚子 Josep G. CANADELL
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.2, pp.309-337, 2021 (Released:2021-04-15)
- 参考文献数
- 92
- 被引用文献数
- 6 38
メタン(CH4)は主要な温室効果気体の一つであり、対流圏および成層圏における化学過程にも重要な役割を果たしている。気候変動および大気汚染に関するCH4の影響は非常に大きいが、過去30年間のCH4濃度増加率や経年変動の要因については、未だ科学的な確証が得られていない。本研究は、十分に検証された化学輸送モデルを用いて、1988年から2016年の期間を対象に大気中CH4濃度をシミュレートし、逆解析によって地域別CH4排出量を推定した。まず、標準実験としてOHラジカルの季節変動のみを考慮し、大気中CH4濃度の観測データを用いた逆解法モデル、排出インベントリ、湿地モデル、およびδ13C-CH4のボックスモデルを用いた解析を行ったところ、1988年以降におけるヨーロッパとロシアでのCH4排出量の減少が示された。特に、石油・天然ガス採掘と畜産由来の排出量の減少が1990年代のCH4増加率の減少に寄与していることが明らかとなった。その後、2000年代初頭には大気中CH4濃度が準定常状態になった。 2007年からはCH4濃度は再び増加に転じたが、これは主に中国の炭鉱からの排出量の増加と熱帯域での畜産の拡大によるものと推定された。OHラジカルの年々変動を考慮した感度実験を行ったところ、逆解析による中高緯度域からのCH4排出推定量はOHラジカルの年々変動には影響されないことが示された。さらに,我々は全球的なCH4排出量が低緯度側へシフトしたことと熱帯域でのOHラジカルによるCH4消失の増加が相殺したことによって、南半球熱帯域と北半球高緯度域の間のCH4濃度の勾配は1988-2016年の間にわたってほとんど変化していなかったことを明らかにした。このような排出地域の南北方向のシフトは、衛星によるCH4カラム観測の全球分布からも確認された。今回の解析期間には、北極域を含めて地球温暖化によるCH4排出量の増加は確認できなかった。これらの解析結果は、気候変動の緩和へ向けた効果的な排出削減策を行う上で重要な排出部門を特定することに貢献できると思われる。
48 0 0 0 OA 脇差しによる頸部気管刺創の 1 経験例
- 著者
- 片倉 浩理 畠中 陸郎 山下 直己 佐藤 寿彦 岩切 章太郎 尾崎 良智 長井 信二郎 岡崎 強 塙 健 松井 輝夫 美崎 幸平 桑原 正喜 松原 義人 船津 武志 池田 貞雄
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学 (ISSN:02872137)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.281-284, 1999-05-25 (Released:2016-10-15)
- 参考文献数
- 14
症例は41歳, 男性。脇差しにより頸部正中刺創を受け, 近医で皮膚縫合を施行されたが, 頸部腫脹, 発声障害が進行するため, 受傷後約18時間後に当院を受診した。著明な皮下気腫を認め, 気管の損傷を疑い気管支鏡を施行した。第1気管軟骨輪に約2cm, 同レベルの膜様部に約1cmの損傷を認めた。同検査中再出血により緊急手術を施行した。出血は甲状腺左葉内の動脈性出血であり縫合止血した。食道の損傷はなかった。気管軟骨輪および膜様部の縫合を行った。術後経過は良好で退院したが, 肉芽形成の可能性もあり, 経過観察が必要である。
48 0 0 0 OA 情報幾何学
- 著者
- 甘利 俊一
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.37-56, 1992-03-16 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 26
Information geometry is a new theoretical method to elucidate intrinsic geometrical structures underlying information systems. It is applicable to wide areas of information sciences including statistics, information theory, systems theory, etc. More concretely, information geometry studies the intrinsic geometrical structure of the manifold of probability distributions. It is found that the manifold of probability distributions leads us to a new and rich differential geometrical theory. Since most of information sciences are closely related to probability distributions, it gives a powerful method to study their intrinsic structures. A manifold consisting of a smooth family of probability distributions has a unique invariant Riemannian metric given by the Fisher information. It admits a one-parameter family of invariant affine connections, called the α-connection, where α and-α-connections are dually coupled with the Riemannian metric. The duality in affine connections is a new concept in differential geometry. When a manifold is dually flat, it admits an invariant divergence measure for which a generalized Pythagorian theorem and a projection theorem hold. The dual structure of such manifolds can be applied to statistical inference, multiterminal information theory, control systems theory, neural networks manifolds, etc. It has potential ability to be applied to general disciplines including physical and engineering sciences.
- 著者
- 北村 淳一 金 銀眞 中島 淳 髙久 宏佑 諸澤 崇裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-012, (Released:2020-12-18)
- 参考文献数
- 25
Habitat use of Misgurnus anguillicaudatus was surveyed at Tanushimaru, Kurume City, Fukuoka Prefecture, Kyushu Island, Japan, at winter season. The study site was composed as traditional agricultural ditches in parts of the paddy field with some parts of concrete artificial type of the canals. The spatial distribution of M. anguillicaudatus in the study area was examined in 36 square frames (1 m × 1 m) located spaced along agricultural pathway for approximately 20 m. Relationships between presence of M. anguillicaudatus and several environmental factors was analyzed using the generalized linear model (GLM). Result of the GLM analysis showed that probability of the presence of M. anguillicaudatus mainly explained by water depth and the probability increased with increasing water depth.
48 0 0 0 OA ブタの尾かじり被害を軽減する飼養管理法の検討
- 著者
- 渡邊 哲夫 野口 宗彦 沼野井 憲一 長谷山 聡也 青山 真人
- 出版者
- 日本養豚学会
- 雑誌
- 日本養豚学会誌 (ISSN:0913882X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.123-134, 2015-09-26 (Released:2015-12-28)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
ブタが他のブタの尾を齧る「尾かじり」は,被害ブタに強いストレスを与え,このブタの生産性を悪化させるので,軽減されなければならない問題行動である。本研究では,安価で簡便な尾かじり被害を軽減する飼養管理技術を検討した。栃木県畜産酪農研究センター芳賀分場において,生後約35〜40日齢から60日齢までのランドレース種とデュロック種の交雑種を使用した。実験1では,特に処理をしない対照区,鉄製・プラスチック製鎖あるいは綿製ロープを提供した環境エンリッチメント(EE)区,1.8%塩化ナトリウム(NaCl)水溶液を給与したNaCl区を設定した。実験2では,飼料の形状が尾かじり被害に及ぼす影響を検討するため,ペレット状の飼料を給与したペレット区,これを顆粒状に砕いて給与したクランブル区を設定した。いずれの実験においても,ブタの尾の被害状況をスコア化し,その経時的変化を観察した。また,唾液を採取し,ストレスの生理的指標であるコルチゾルの濃度を測定した。実験1において,対照区では尾の被害スコアが増加する傾向であったのに対し,EE区では処置開始後には,時間経過に伴うスコア増減はほとんど無く,ほぼ処置前の値を維持していた。一方,NaCl区では尾の被害スコアは塩水給与後に減少した。処置前から処置約2週間後の尾の被害スコアの増加分を区ごとに比較すると,NaCl区では対照区に比べ有意に低かった。また,処置前と処置約2週間後の唾液中コルチゾル濃度を区ごとに比較すると,対照区では増減はなかったが,EE区とNaCl区では処置後に減少する傾向があり,ストレスが軽減されている可能性が示唆された。実験2において,ペレット区では尾の被害が悪化し,この区の尾の被害スコアの増加分はクランブル区に比べ有意に高かった。これらのことから,特に塩水の給与が,尾かじり被害の軽減に有効であるという結果が得られた。
48 0 0 0 OA 日本初のエレベーター式魚道の土木史的考察
- 著者
- 竹林 征三 貴堂 巌
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.425-435, 1995-06-09 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1
A 64m high, elevator-type fishway was constructed at the Komaki Dam on the Sho River in Toyama Prefecture which was completed in 1929. Although highly effective in the early years after construction, the influence of the Soyama Dam which was built upstream and the development of the fish breeding industry led to the decline of dependence on the fishway and in 1943 it was converted into harbor equipment. This paper studies the evaluation of the Komaki Dam fishway and the social and technical background against which it was judged to be inflective and was removed.
48 0 0 0 OA 狩野川台風による東京西郊の水害の性格
- 著者
- 菊地 光秋
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.184-189, 1960-03-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
狩野川台風による東京地方の水害地域は,水害型と地形の上から, (A) 東部および東南部のデルタ地帯, (B) 西部の武蔵野台地上の地域に2大別される. (B) 地域はさらに3分され, (1) 武蔵野台地上に水源を持つて,台地上を貫流している白子川・石神井川・妙正寺川・桃園川・善福寺川・旧神田上水など,荒川水系の谷とその沿岸地域, (2) 排水溝幹線として利用されている灌漑用水路および元灌漑用水路の沿岸地域, (3) 武蔵野台地上に点在する窪地の湛水による浸水地域で,水路に沿つていない地域とすることができる.東京地方西部の台地上の水害では,山岳部に雨量が少なく,平野部に豪雨が集中したために,中小河川の氾濫が目立つて多く,また窪地の浸水が多かつた.東京西部の市街地における家屋密度の増大と,西部の近郊農村の住宅地域化は,近年目立つて大きくなつている.この住宅地域の拡張と,下水溝および排水路としての中小河川対策が,平行して行われていないため,豪雨の影響をうけて被害が大きかつた.東京西部の台地上における多数の浸水家屋のうち,新築住宅の被つた水害の多いのもいちじるしい特色である.
48 0 0 0 OA CGMにおける炎上の分析とその応用
- 著者
- 岩崎 祐貴 折原 良平 清 雄一 中川 博之 田原 康之 大須賀 昭彦
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.152-160, 2015-01-06 (Released:2015-01-06)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
Nowadays, anybody can easily express their opinion publicly through Consumer Generated Media. Because of this, a phenomenon of flooding criticism on the Internet, called flaming, frequently occurs. Although there are strong demands for flaming management, a service to reduce damage caused by a flaming after one occurs, it is very difficult to properly do so in practice. We are trying to keep the flaming from happening. It is necessary to identify the situation and the remark which are likely to cause flaming for our goal. Concretely, we propose methods to identify a potential tweet which will be a likely candidate of a flaming on Twitter, considering public opinion among Twitter users. Among three categories of flamings, our main focus is Struggles between Conflicting Values (SBCV), which is defined as a remark that forces one's own opinion about a topic on others. Forecasting of this type of flamings is potentially desired since most of its victims are celebrities, who need to care one's own social images. We proceed with a working hypothesis: a SBCV is caused by a gap between the polarity of the remark and that of public opinion. First, we have visualized the process how a remark gets flamed when its content is far from public opinion, by means of our original parameter daily polarity (dp). Second, we have built a highly accurate flaming prediction model with decision tree learning, using cumulative dp as an attribute along with parameters available from Twitter APIs. The experimental result suggests that the hypothesis is correct.
- 著者
- Yoshikazu Iha Futoshi Higa Satoko Sunagawa Masamitsu Naka Haley L. Cash Kazuya Miyagi Shusaku Haranaga Masao Tateyama Tsukasa Uno Jiro Fujita
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.295-300, 2012 (Released:2012-09-21)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 8 11
Climatic conditions may have affected the incidence of influenza during the pandemic of 2009 as well as at other times. This study evaluated the effects of climatic conditions on influenza incidence in Okinawa, a subtropical region in Japan, during the 2009 pandemic using surveillance data from rapid antigen test (RAT) results. Weekly RAT results performed in four acute care hospitals in the Naha region of the Okinawa Islands from January 2007 to July 2011 were anonymously collected for surveillance of regional influenza prevalence. Intense epidemic peaks were noted in August 2009 and December 2009–January 2010 during the influenza pandemic of 2009. RAT positivity rates were lower during the pandemic period than during the pre- and post-pandemic periods. Lower ambient temperature was associated with higher influenza incidence during pre- and post-pandemic periods but not during the pandemic of 2009. Lower relative humidity was associated with higher influenza incidence during the pandemic as well as during the other two periods. The association of climatic conditions and influenza incidence was less prominent during the pandemic of 2009 than during pre- and post-pandemic periods.
- 著者
- Mie Kazama Keiko Maruyama Kazutoshi Nakamura
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.236, no.2, pp.107-113, 2015 (Released:2015-05-29)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 23 55
Dysmenorrhea is a common menstrual disorder experienced by adolescents, and its major symptoms, including pain, adversely affect daily life and school performance. However, little epidemiologic evidence on dysmenorrhea in Japanese adolescents exists. This cross-sectional study aimed to determine the prevalence of and identify factors associated with dysmenorrhea in Japanese female junior high school students. Among 1,167 girls aged between 12 and 15 years, 1,018 participants completed a questionnaire that solicited information on age at menarche, menstruation, and lifestyle, as well as demographic characteristics. Dysmenorrhea was defined based on menstrual pain using a Visual Analog Scale (VAS), with moderate or severe (moderate-severe) dysmenorrhea, which adversely affects daily life, defined as VAS ≥ 4, and severe dysmenorrhea defined as VAS ≥ 7. The prevalence of moderate-severe dysmenorrhea was 476/1,018 (46.8%), and that of severe dysmenorrhea was 180/1,018 (17.7%). Higher chronological and gynecological ages (years after menarche) were significantly associated with a higher prevalence of dysmenorrhea regardless of severity (P for trend < 0.001). In addition, short sleeping hours (< 6/day) were associated with moderate-severe dysmenorrhea (OR = 3.05, 95%CI: 1.06-8.77), and sports activity levels were associated with severe dysmenorrhea (P for trend = 0.045). Our findings suggest that dysmenorrhea that adversely affects daily activities is highly prevalent, and may be associated with certain lifestyle factors in junior high school students. Health education teachers should be made aware of these facts, and appropriately care for those suffering from dysmenorrhea symptoms, absentees, and those experiencing difficulties in school life due to dysmenorrhea symptoms.