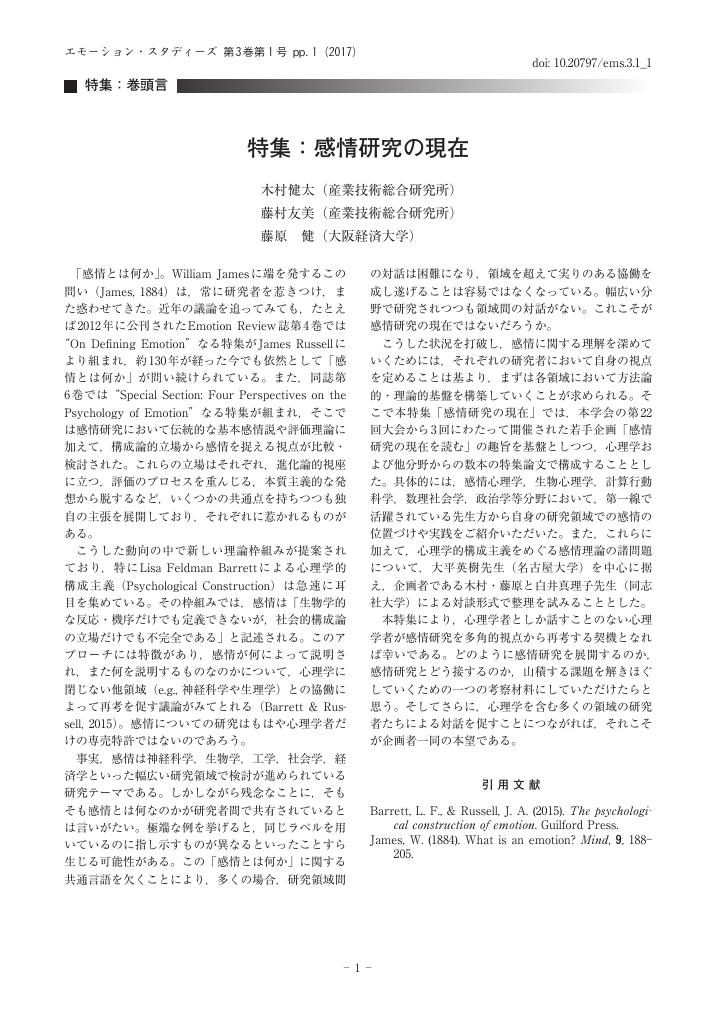1 0 0 0 OA 住宅型有料老人ホーム入居高齢者における下肢筋力と歩行速度との間の関連性
- 著者
- 谷 佳成恵 津田 彰 村田 伸
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.87-94, 2023 (Released:2023-11-10)
- 参考文献数
- 32
本研究では第1 の目的として,住宅型有料老人ホームに入居する高齢者33名を対象として,下肢筋力と歩行速度との間の関連性を検討した。第2 の目的として,対象集団の下肢筋力の強度の違い(弱・平均・強)が,下肢筋力と歩行速度との間の関連性へ及ぼす影響を検討した。下肢筋力は30秒椅子立ち上がりテスト(30-sec Chair-Stand test; CS-30)によって測定した。歩行パラメータは歩行速度,歩行率,ストライド長,歩幅,歩隔,つま先角,歩行角,立脚時間,両脚支持時間,遊脚時間を測定した。3群間の比較の結果,下肢筋力,歩行速度,歩行率,ストライド長,歩幅,歩隔,歩行角,立脚時間,両脚支持時間に有意差を認めた。各群におけるSpearman の順位相関分析の結果,弱群のみ下肢筋力と歩行速度との間に有意な正の相関を認めた。下肢筋力の低下に伴い歩行速度が遅くなること,下肢筋力の強度の違いによって,下肢筋力と歩行速度との間の関連性は異なることが示唆された。
1 0 0 0 OA 関節リウマチや骨粗鬆症などの多発する痛みを呈する疾患の鑑別に─腫瘍性骨軟化症の診断と治療
- 著者
- 小林 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.53-57, 2023 (Released:2023-11-11)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA P2E1-24 臨床場面における足部および足関節周囲の周径測定用メジャーテープの開発
- 著者
- 中村 菜々子 山口 智志 下村 義弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.Supplement, pp.P2E1-24, 2023-09-07 (Released:2023-11-17)
1 0 0 0 OA P1E5-19 靴の重心位置の違いが歩容に与える影響
- 著者
- 河村 隼太 赤木 暢浩 角 紀行 和田 健希 武本 悠希 小東 千里 齋藤 誠二
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.Supplement, pp.P1E5-19, 2023-09-07 (Released:2023-11-17)
1 0 0 0 OA P2E5-10 成人女性における靴選びと足部トラブルの実態
- 著者
- 入口 舜太 石川 静香 佐々木 新介 齋藤 誠二
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.Supplement, pp.P2E5-10, 2023-09-07 (Released:2023-11-17)
1 0 0 0 OA 液体の物性および量による嚥下時舌圧の変化とAIによる解析
- 著者
- 李 宙垣 渡辺 崇文 松岸 諒 喜田 悠太 板 離子 津賀 一弘 兒玉 匠平 大川 純平 堀 一浩
- 出版者
- 日本顎口腔機能学会
- 雑誌
- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.130-131, 2023 (Released:2023-11-22)
- 参考文献数
- 2
I.目的舌は,咀嚼や嚥下,構音などの機能を担っており,嚥下時には,口蓋と接触することで食塊を咽頭へ送り込む役割を果たす1).また,嚥下障害を呈する者には,誤嚥のリスク低減のために液体へのとろみ付けや一口量の調整が行われている.しかしながら,液体の物性や一口量の違いによって嚥下時の舌圧がどのように変化するかは明らかになっていない.本研究では,健常者における液体嚥下時の舌圧を測定し,液体の物性や嚥下量による舌圧の変化を検討した.さらに,AIによる解析として機械学習を用い舌圧の特徴を探索した.
1 0 0 0 OA 唾液分泌量の増加が,摂食嚥下動態に及ぼす影響
- 著者
- 新開 瑞希 中川 悠 馬場 政典 松田 有加子 佐藤 理加子 高野 日南子 鈴木 拓 真柄 仁 井上 誠
- 出版者
- 日本顎口腔機能学会
- 雑誌
- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.128-129, 2023 (Released:2023-11-22)
I.目的加齢に伴う口腔内の生理学的変化の一つとして,唾液分泌量の減少が挙げられる.我々は,本学会第66回,67回学術大会において,唾液分泌量の減少が摂食嚥下動態に及ぼす影響について報告した.今回,健常成人を対象に,塩酸ピロカルピン誘発性の唾液分泌量の増加が咀嚼嚥下に及ぼす影響を検証した.
1 0 0 0 OA カリウムイオンの嚥下誘発促進効果
- 著者
- 川田 里美 TiTi Chotirungsan 筒井 雄平 真柄 仁 辻村 恭憲 井上 誠
- 出版者
- 日本顎口腔機能学会
- 雑誌
- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.106-107, 2023 (Released:2023-11-22)
- 参考文献数
- 2
I.目的摂食嚥下障害において,嚥下惹起遅延は主たる病態のひとつである.過去の報告では,麻酔下ラットにおける塩化カリウム(KCl)の喉頭滴下による嚥下反射誘発効果は塩化ナトリウム(NaCl)に比して効果的である1),ヒトではKClを適用した時の随意嚥下間隔時間はNaClよりも短かった2)と報告している.しかし,カリウムイオンがどのように嚥下開始に関与しているかは明らかではない.本研究では,生理学的手法を用いてカリウムイオンが嚥下開始に及ぼす影響について,ラットを対象として評価した.
1 0 0 0 OA 最高のヨーガ
- 著者
- 遠藤 康
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.963-956, 1995-03-25 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 消防隊と救急隊の連携活動についての検証 ~特定行為時間短縮効果との関係性について~
1 0 0 0 OA 電気防食用整流器としてのセレンとシリコンの優劣 (抄訳)
- 著者
- D. P. Wilson 花田 政明
- 出版者
- Japan Society of Corrosion Engineering
- 雑誌
- 防蝕技術 (ISSN:00109355)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.8, pp.365, 1960-08-25 (Released:2009-11-25)
1 0 0 0 OA 会計主導の原価企画と行動的原価企画 ―トヨタの事例から―
- 著者
- 加藤 典生 小林 英幸
- 出版者
- 日本原価計算研究学会
- 雑誌
- 原価計算研究 (ISSN:13496530)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.14-24, 2021 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 23
従来の原価企画は主として会計的立場(コントロールする側)からの検討であり,エンジニアの立場(コントロールされる側)からの検討は十分であるとはいえない。本稿では,トヨタ自動車における原価企画を題材にし,会計的立場から見た適切な環境の整備が,エンジニアの立場から見た場合,必ずしもそうであるとはいえないことを明らかにする。
1 0 0 0 OA バイオフィルムを知る―レジオネラバイオフィルムの評価―
- 著者
- 古畑 勝則
- 出版者
- NPO法人 環境バイオテクノロジー学会
- 雑誌
- 環境バイオテクノロジー学会誌 (ISSN:13471856)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.23-32, 2022 (Released:2022-06-18)
- 参考文献数
- 35
1 0 0 0 OA 18世紀の日本における冬の気候復元
- 著者
- 深石 一夫 田上 善夫
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.2, pp.176-182, 1993-04-25 (Released:2010-11-18)
- 参考文献数
- 19
In order to reconstruct the winter climate in Japan in the 18th century, the authors tried to gather weather records of old diaries written in that period. The winter climate in Japan is influenced by the east high-west low pressure pattern and its severity is highly correlated with the frequency of the pressure pattern on a seasonally or monthly time scale. The weather distribution pattern under the west high-east low pressure type is characterized by the bad weather in Japan Sea Coast and fine one in Pacific Coast.By the use of the character of the weather distribution pattern under the winter pressure, the frequencies of the typical winter days are interpreted from the weather distribution diagram made for the research period on a daily base from 1st November of the former year to the 31 st March of the year. The stations of the diaries gathered for the study are Hirosaki, Takada, Kanazawa, Sabae, Tottori and Hagi as Japan Sea Coast, Hachinohe, Morioka, Nikko, Kofu, Ise, Kyoto, Ikeda, Tsuyama and Usuki as inland or Pacific Coast.The results obtained from the study are shown in Figure 1 as an annual number of the frequency of winter pressure days. On the same time scale, the freezing dates and the records of unusual weather in winter (cold or mild) are composed in the figure. The relationsbetween the frequency and other historical documents are investigated.The secular changes of severity in winter were well coincided with the other weather proxies. The cold winter years can be found in the decades in the 1700s-1710s, the former 1730s, the 1750s and the former 1780s. The warmer winter years were in the decades in the 1720s, the 1740s, the 1770s, and the 1790s. Unusual severe winters recorded in the periods are not always identical to the frequency of the winter pressure days, because of its temporal or local effects.
1 0 0 0 OA 糖尿病と認知機能障害
- 著者
- 大澤 匡弘 山田 彬博
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.4, pp.201-202, 2013 (Released:2013-10-10)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 自発ならびに誘発性めまいの病態生理補遺
- 著者
- 坂田 英治 梅田 悦生 大都 京子 金沢 致吉 村岡 潔
- 出版者
- Japanese Society of Otorhinolaryngology-Head and neck surgery
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.7, pp.676-682, 1978-07-20 (Released:2008-03-19)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
Unter den Krankheitsfällen, die über Schwindel klagen, findet man nicht selten Prodromalsymptome schwerer Krankheiten oder Initialsymptome von Hirntumor usw.Neben der Schwindelbeschwerde, dem subjektven Symptom der Patienten, lassen sich auch die objektiven Symptome Spontan-und Provokations-Nystagmus feststellen. Hierhin liegt auch der Grund für die in den letzten Jahren die Forschung in Bezug auf Spontan-Nystagmus, über deren Bedeutung man sich mehr und meter hewusst geworden ist. Tatsache ist jedoch, dass vom pathophysiologischen Aspekt aus betrachtet uber Schwindel noch viel Dunkel herrscht.Wir haben deshalb aufgrund von Untersuchungen Genaueres über die Mechanismen, die beim Zuatandekommen von Spontan-und Provokations-Schwindel wirken, zu ergründen versucht, wobei wir erstere an einem Krankengut mit Morbus Ménière, akuten Labyrinthf unktionsausfall sowie Innenohrentzündungen, letztere bei Lageschwindel vom gut-bzw. bösartigen paroxysmalen Typ sowie bei Zervikalschwindel anstellten.Die Verfasser haben insbesondere Schuknechts mechanische Erklärung über den Lageschwindel vom gutartigen paroxysmalen Typ zum Anlass seiner Forschung, da er glaubte theseArt von Schwindel durch einen funktionelleren Mechanismus erklärbar machen zu können. Desweiteren hat der Autor die Zusaznmenhänge von "Bruns-Syndrom" und "akutem Unterwurmsyndrom" beim Lageschwindel vom bösartigen paroxysmalen Typ ereörtert und dabei betont, dass Storung im Vestibulariscerebellum die Hauptursache bei der Entstehung dieser Erkrankungen sind.
- 著者
- 谷村 洋輔 坪井 重樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.665-668, 2023-10-31 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 10
症例は50歳代女性,家族歴なし。5,6年前から自然に軽快する腹痛を何度か自覚し,原因不明の腹膜炎と発熱で近医から発熱外来へ紹介された。腹部全体に腹膜刺激症状を認め血液検査で炎症反応の上昇を示すものの,その他の項目や画像検査で異常は指摘できなかった。 繰り返す症状のエピソードから,家族性地中海熱(familial Mediterranean fever,以下FMFと略す)を疑った。その後も同様の症状を繰り返すことから,FMFと臨床診断し専門機関に紹介した。関連遺伝子のMEFV遺伝子異常が同定され,FMFと確定診断した。コルヒチンの内服を開始し,発作の頻度,程度ともに著明に改善した。繰り返す発熱や腹膜炎・胸膜炎を呈する症例では,FMFを鑑別にあげる必要がある。
1 0 0 0 OA 特集:感情研究の現在
- 著者
- 木村 健太 藤村 友美 藤原 健
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- エモーション・スタディーズ (ISSN:21897425)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.1, 2017-10-01 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 手指消毒薬誤飲による高齢者の急性エタノール中毒の1例
- 著者
- 入江 仁 青柳 有沙 杉山 佳奈 石澤 義也 花田 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.661-664, 2023-10-31 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 10
意識障害の原因が消毒用エタノールの誤飲であった高齢者の症例を経験した。患者は92歳,女性。既往歴に認知症があり施設に入所中であった。嘔吐,意識障害,ショック状態を呈し救急搬送された。施設職員より本人の部屋にある手指消毒用エタノールの容器の蓋が外され,内容量が減った状態で枕元に置かれていたと申告があった。血中エタノール濃度は300mg/dL以上(当院測定上限)であり,誤飲による急性エタノール中毒と診断し,即日入院とした。第2病日に血中エタノール濃度は189mg/dLまで低下し,意識レベルも改善したため,第5病日に他院へ転院とした。新型コロナウイルス感染症を契機に手指消毒薬はきわめて身近な存在となったが,一般的に用いられている消毒用エタノール溶液は濃度が80%程度であり,誤飲により意識障害などの中毒症状で受診に至る可能性があることを認識しておく必要がある。また,認知症を有する高齢者が誤飲しないための対策が必要である。
- 著者
- 田久 浩志
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 日本行動計量学会大会抄録集 51 (ISSN:21897484)
- 巻号頁・発行日
- pp.110-111, 2023-08-28 (Released:2023-11-10)