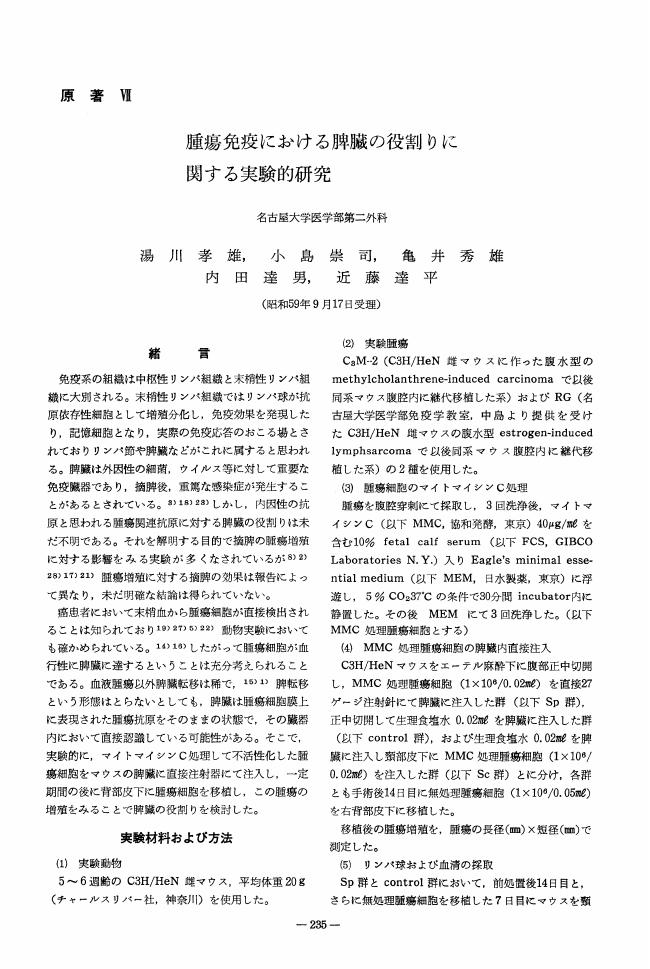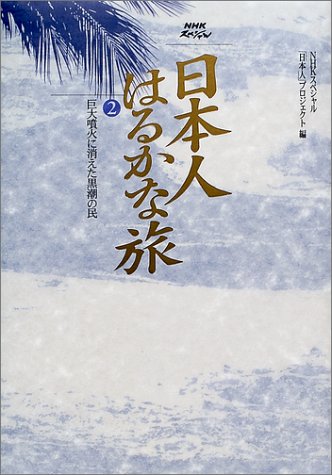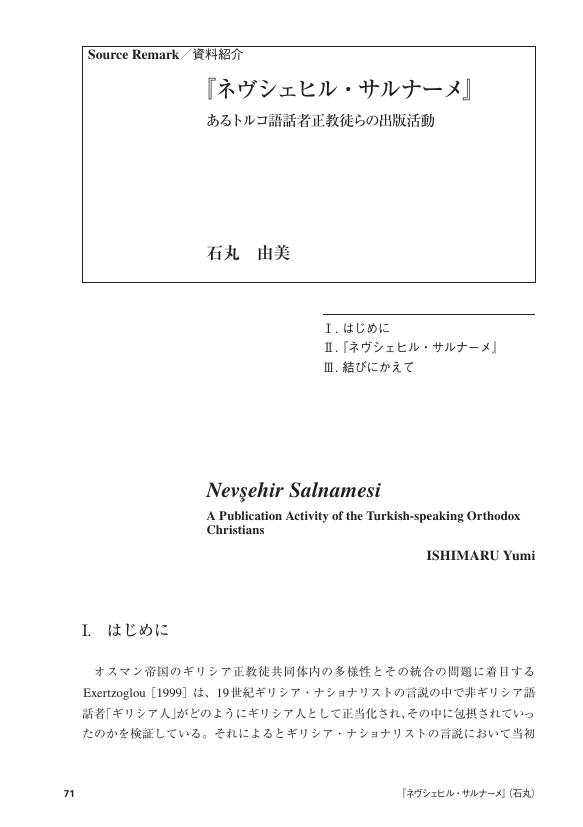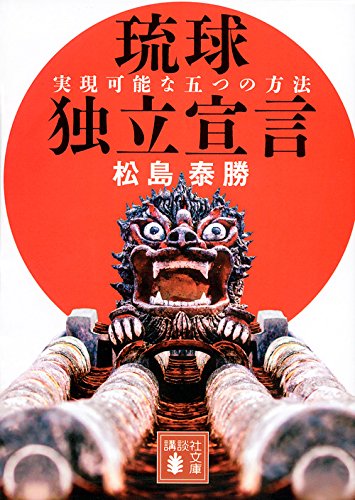1 0 0 0 OA 加速度を基にしたスリップ率制御によるモータアシスト4WD車両のトラクション性能向上
- 著者
- 森木 秀一 井村 進也 伊藤 勝 松崎 則和 藤原 慎 伊藤 恒平
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.1417-1421, 2009 (Released:2010-06-18)
- 参考文献数
- 10
スリップ率の変化率に基づく全輪駆動車のためのスリップ率制御手法を提案する。本制御手法によれば,目標スリップ率が最適値よりも大きく設定されており,スリップ率が最適値を超えた場合であっても,スリップ率の増加が自動的に抑制される。本制御手法をモータアシスト4WD車両に適用した結果を示す。
1 0 0 0 OA 腫瘍免疫における脾臓の役割りに関する実験的研究
- 著者
- 湯川 孝雄 小島 崇司 亀井 秀雄 内田 達男 近藤 達平
- 出版者
- 日本リンパ網内系学会
- 雑誌
- 日本網内系学会会誌 (ISSN:03869725)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.235-241, 1984 (Released:2009-06-04)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 機能性直腸肛門痛に対して両側脛骨神経刺激療法が奏効した1例
- 著者
- 高野 正太 辻 順行 山田 一隆
- 出版者
- 日本大腸肛門病学会
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.8, pp.530-533, 2015 (Released:2015-08-04)
- 参考文献数
- 23
症例は64歳女性.肛門痛,会陰痛を主訴に受診し肛門診,肛門指診,肛門鏡診および経肛門超音波検査にて異常所見を認めず機能性直腸肛門痛と診断された.ロキソプロフェンナトリウム錠,ジクロフェナクナトリウム坐剤,トリベノシド・リドカイン軟膏による保存療法を施行し疼痛は落ち着いていたが,1年後に疼痛増悪した.両側脛骨神経刺激療法を開始し週2回,計12回施行した.Visual analog scale for painは治療前8.3から治療後0へ減少,1ヵ月間で疼痛を感じた日数は治療前30日から0日へ減少し,また会陰痛も消失した.脛骨神経刺激療法は簡便に施行でき侵襲も少なく,機能性直腸肛門痛の治療の選択肢のひとつと考える.
1 0 0 0 OA VR手術シミュレータの20年と今日的意義
- 著者
- 藤原 道隆 岩田 直樹 三澤 一成 丹羽 由紀子 高見 秀樹 田中 千恵 小寺 泰弘
- 出版者
- 日本VR医学会
- 雑誌
- VR医学 (ISSN:13479342)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.1-14, 2020-01-10 (Released:2021-02-05)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1 1
It has been about 20 years since the commercial use virtual reality (VR) surgical simulator was launched. We have used VR surgical simulator for surgical education from early stage. At present, the weight of the VR simulator in current surgical education is lower than initially expected. This has been mainly due to the discord between the expectation for the functions of the VR simulator of the coaching surgeon and the actual use of the VR simulators without essential comprehension of simulation training. In addition, the focus of developers of the VR simulators has been besides the points. In this article, we summarize the situation of VR simulator so far, and describe the future measures of surgical training using VR simulators more effectively from the view point of clinician.
1 0 0 0 巨大噴火に消えた黒潮の民
- 出版者
- 日本放送出版協会
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 OA BSデータ放送サービスの方式
- 著者
- 石川 亮 楠見 雄規
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.47-53, 2000-01-20 (Released:2011-08-17)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
2000年末に本放送開始が予定されているBSデジタル放送では, 通常の映像・音声の放送に加えデータ放送サービスが行われる.本稿ではマルチメディアデータ放送サービスを実現するためのサービス方式について解説する.
1 0 0 0 OA 水理模型実験による尼崎港の海水交換促進技術について
- 著者
- 山崎 宗広 上嶋 英機 村上 和男
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 海洋開発論文集 (ISSN:09127348)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.977-982, 2004 (Released:2011-06-27)
- 参考文献数
- 2
Amagasaki Harbor is enclosed coastal sea. Therefore water in a harbor basin is stagnant, and the water quality is deteriorated. In this study, we carried out hydraulic model experiments in order to enhance the water exchange of Amagasaki Harbor. The channel making technique is very effective to strengthen the flow in Amagasaki Harbor. This is because a Yodo River flows into harbour basin. And it is also highly effective to enhance water exchange of the harbor water.
1 0 0 0 OA 魚の嗜好性と機能性を高める調理法の開発
魚の嗜好性と機能性を高める調理法の開発を目的として、魚臭成分の原因となる脂質酸化生成物の生成を抑える抗酸化成分を含む香味野菜を加えて調理を行い、海産魚に含まれるにおい成分及び機能性成分の調理過程における変化を解析した。その結果、香味野菜を加えて調理することにより、脂質劣化に由来する揮発性成分が減少した。また、薬味なしの試料では調理後、抗酸化活性は減少していたが、薬味を加えることにより抗酸化活性が増加していた。以上の結果から、魚に香味野菜を加えて調理することにより嗜好性及び機能性において優れた効果を発揮することが示唆された。
- 著者
- 岩田 晋典
- 出版者
- 愛知大学国際コミュニケーション学会
- 雑誌
- 文明21 = Civilization 21 (ISSN:13444220)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.1-20, 2022-12-20
1 0 0 0 OA 地域生活定着支援センターにおけるフォローアップ業務の適正化に関する調査研究
- 著者
- 佐々木 茜 岡田 裕樹 水藤 昌彦 大村 美保 遅塚 昭彦
- 出版者
- 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
- 雑誌
- 国立のぞみの園紀要 (ISSN:24350494)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.49-68, 2023 (Released:2023-11-21)
- 参考文献数
- 4
地域生活定着支援センターのフォローアップ業務について,福祉施設等に入所した者のフォローアップ期間の長期化が課題となっている.本研究では,高齢・障害各領域の入所施設等および相談支援機関を対象として,地域生活定着支援センターのフォローアップ業務に関する実態と課題についてヒアリング調査を実施した.その結果,①地域定着支援センターが,福祉施設に対して支援の依頼を行う際に,自らのフォローアップ業務の期限について明示しないことから,福祉施設は地域生活定着支援センターに対して「何かあった時にいつでも相談できる」と理解していること,②地域の社会資源や支援対象者の個別的な特性により,地域生活定着支援センターが直接的な支援を担わざるを得ない面があることが長期化の要因であることが分かった.本研究では,長期化しているフォローアップ業務の課題を解消することを「適正化」と位置づけ,適正化については①フォローアップ業務の整理,②地域生活定着支援センターと福祉サービス事業所間フォローアップ概念の一致,③支援経験のある福祉サービス事業所同士による支援ネットワーク構築が重要と考えられた.
1 0 0 0 OA 歩容からうける美的印象に観察者の性別が及ぼす影響
- 著者
- 齋藤 早紀子 小林 吉之 河内 まき子
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.228, 2023 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 23
若年女性の歩容から受ける美的印象に対する観察者の性別の影響を調べた.はじめに,歩行動作の印象を具体的なイメージとして喚起するような評価用語を検討した.重回帰分析の結果,色っぽい,スムーズである,バランスが悪い,が選定された.20 の歩行動作に女性のデジタルマネキンをあてはめた動画を作成し,各用語がどの程度当てはまるかを5 件法で回答させた.その結果,同じ歩容から受ける色っぽいという印象は,男性観察者群の方が女性観察者群よりも有意に高い評価得点を示し,スムーズである,バランスが悪いには有意差がなかった.さらに,色っぽいという用語のみ,男性観察者と女性観察者の評価得点間に有意な相関が見られなかったことから,男性観察者と女性観察者では色っぽいと感じる女性の歩容が異なるものといえる.そこで,提示画像に用いた1 歩分の関節角度を主成分分析によって分析し,動作特徴を抽出し,「色っぽい」という語の評価得点との関連を調べた.「色っぽい」という語の評価得点は,男性観察者では第5 主成分得点との間に有意な負の,女性観察者では第3 および第5 主成分得点との間に有意な負の相関がみられ,男性観察者と女性観察者では,色っぽいという印象をうける女性の歩行特徴が異なっていた.また色っぽいという印象をうける女性の歩容は,先行研究とは異なり,必ずしも歩行者の腰部の動きが大きいこととは関係していなかった.
1 0 0 0 OA ICF及びICTを活用した強度行動障害PDCA支援パッケージ作成のための 社会実装研究
- 著者
- 岡田 裕樹 日詰 正文 内山 聡至 髙橋 理恵
- 出版者
- 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
- 雑誌
- 国立のぞみの園紀要 (ISSN:24350494)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.1-21, 2022 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 5
本研究は,国立のぞみの園が令和2(2020)年度の研究において開発した強度行動障害PDCA支援パッケージを実際の支援現場で試行し,効果や課題を収集することを目的として,強度行動障害者支援に取り組んでいる事業所を対象とした調査等を行った.調査対象は,一次調査として14カ所,二次調査として国立のぞみの園が実施した「実践検討・意見交換会」に参加した29カ所とした.結果として,「強度行動障害の状態にある者の全体的な理解と情報の整理」,「効率的な記録と分析」,「支援計画の作成と見直し」等に効果があることがわかった.強度行動障害PDCA支援パッケージを活用することで,行動の背景要因を見つけることや支援の記録と分析を迅速に行うこと等の強度行動障害者支援の課題を改善することが期待できると考えられた.
1 0 0 0 OA 強度行動障害のある方の「異食」の対応に関する研究 -A園で発生した異食事故の検証-
- 著者
- 黒岩 利生 佐々木 茜
- 出版者
- 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
- 雑誌
- 国立のぞみの園紀要 (ISSN:24350494)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.1-7, 2023 (Released:2023-11-21)
- 参考文献数
- 5
強度行動障害のある方の中には,通常食べられないものを口にする「異食」が見られる人がいる.本研究は,異食の発生要因を把握し以後の発生予防方法を検討するため,A園で発生した強度行動障害のある方の異食事故の検証を行った.異食事故に携わった経験のある職員を対象としたヒアリング調査の結果,異食の発生要因は①不満・ストレス,②注意喚起・要求,③周期的な変化,④予測困難に分類された.対象者の所属寮では事前の情報収集や日常生活の観察を通し情報を集約した上で応用行動分析を用いて異食の要因を分析し,要因に応じた支援を行っていた.異食は身体的合併症のほか,生活の場の選択への影響もみられる緊急性の高い行動だが,異食の可能性のある物をすべて排除するのではなく,QOL向上の視点を持って発生要因に応じた支援を行うことが重要と考えられた.
- 著者
- Julia Oliveira Lima ZAHRA Camila Zanetti SEGATTO Gustavo Ricci ZANELLI Tatiane dos Santos BRUNO Gabriel Montoro NICÁCIO Rogerio GIUFFRIDA Renata Navarro CASSU
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.11, pp.1172-1179, 2023 (Released:2023-11-02)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 1
The aim of this study was to compare the intra and postoperative analgesic effects of sacrococcygeal epidural levobupivacaine with those of lumbosacral levobupivacaine in feline ovariohysterectomy. Thirty-six cats were premedicated with intramuscular acepromazine (0.05 mg/kg) and meperidine (6 mg/kg). Anesthesia was induced with intravenous propofol and maintained with isoflurane in oxygen. The cats were randomly assigned one of the three treatments receiving 0.33% levobupivacaine (0.3 mL/kg) into the sacrococcygeal (S-C group, n=12) or lumbosacral (L-S group, n=12) epidural space, or the same volume of 0.9% saline solution into one of the epidural approaches (Control group, n=12). Intraoperatively, cardiorespiratory variables, end-tidal isoflurane concentration (FE´ISO), and fentanyl requirements were recorded. Postoperative pain was assessed by the UNESP (Universidade Estadual Paulista)-Botucatu multidimensional composite pain scale and the Glasgow feline composite measure pain scale up to 8 hr post-extubation. Morphine was administered as rescue analgesia. Overall FE´ISO and fentanyl requirements were lower in the L-S and S-C compared to the Control (P=0.002–0.048, respectively). There was no significant difference in the cardiorespiratory variables during anesthesia, postoperative pain and rescue analgesia among groups. The time to standing after anesthesia was prolonged in the L-S and S-C groups than in the Control (P<0.001). Lumbosacral and sacrococcygeal epidural levobupivacaine resulted in similar decreases in isoflurane requirements and intraoperative fentanyl supplementation in the cats, with no postoperative benefits.
1 0 0 0 OA 機能性リポソームによる遺伝子の細胞内送達
- 著者
- 河野 健司
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.330-333, 2006-05-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 21
標的細胞に遺伝子を導入し,効率よく発現させる技術の確立は,遺伝子治療や再生医療などの先進医療の発展にかかわる重要な鍵である.効率のよい遺伝子発現を実現するためには,遺伝子の最終目的地点である細胞核内まで遺伝子をスムーズに送り届けることができ,しかも生体にとって安全性の高い運搬体の開発が必要である.本稿では,標的細胞において効率的な遺伝子発現を誘導するための遺伝子送達システムの設計について,筆者らが進めている機能性リボソームを用いた遺伝子送達システムを中心に解説する.
1 0 0 0 OA 構音障害を主訴に脳卒中選定された劇症1型糖尿病の1例
- 著者
- 緒方 友紀 持田 勇希 海田 賢彦 山口 芳裕
- 出版者
- 日本救急医学会関東地方会
- 雑誌
- 日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.261-264, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 11
糖尿病の既往のない60歳代男性。入院1週間前より消化器症状が出現し, さらに構音障害と異常行動が出現したため家族が救急要請した。救急隊により脳梗塞を疑われ, 当院脳卒中科へ搬送された。来院直後にショックバイタルとなり, 精査結果から糖尿病性ケトアシドーシスを伴う劇症1型糖尿病と診断し, 集中治療室に入室した。血糖コントロールを含めた全身管理により状態が改善し, 第14病日には一般病棟へ転床となり良好な転帰を得た。劇症1型糖尿病の症状は多彩で急速な経過をたどることが特徴であり, 救急要請の段階で中枢神経症状を呈している可能性が高い。プレホスピタルで脳卒中が疑われた際には初期診療から専門診療科に振り分けられるため, 脳卒中選定患者に当該疾患が潜んでいる認識をもち, 遅滞なく糖尿病ケトアシドーシスに対する治療介入することが肝要である。
- 著者
- 江田 康太郎 菊池 英明
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- pp.TJSKE-D-21-00032, (Released:2021-11-16)
- 参考文献数
- 17
Sound symbolism is the non-arbitrary associations between pseudowords and meanings. It has been reported that these associations extend to the lexical stimulus (e.g., names and faces); however, it is not clear whether non-native English speakers feel the same way. Experimental results using the stimuli that have existing associations might be affected by language family. In this study, we created high-quality images of Caucasians with generative modeling and then conducted a questionnaire survey on Japanese native speakers. The results showed that names containing round-sounding phonemes could be associated with face images possessing feature amounts related to roundness. The same is true of sharpness. This tendency implies Japanese native speakers also feel the non-arbitrary associations between names and faces.
1 0 0 0 OA 『ネヴシェヒル・サルナーメ』 あるトルコ語話者正教徒らの出版活動
- 著者
- 石丸 由美
- 出版者
- 日本中東学会
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.71-90, 2018-01-15 (Released:2019-03-15)