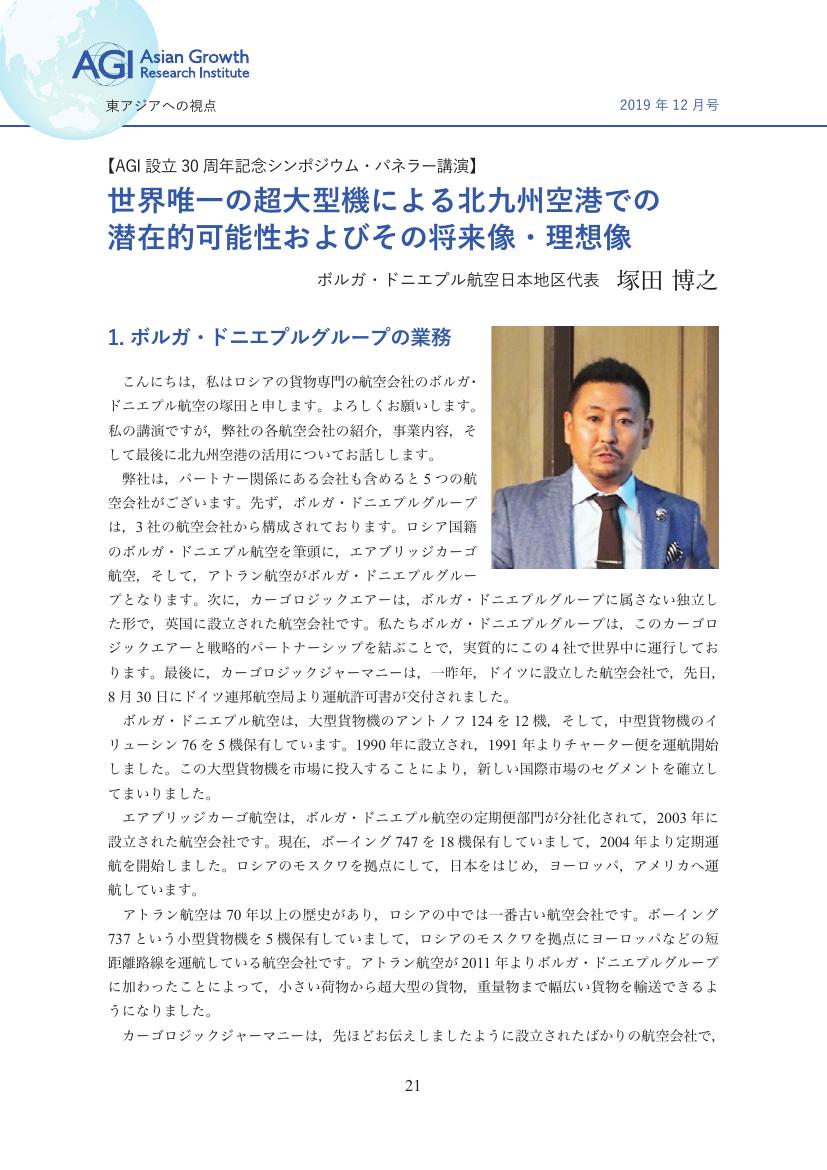1 0 0 0 OA ストレス関連疾患における予防薬及び治療薬としてのポリフェノールの有効性の基礎解析
交感神経系モデルとしての培養ウシ副腎髄質細胞を用いて、ストレス軽減効果の有る予防薬や気分障害の治療薬として適用できる可能性があるポリフェノールを選定した。アピゲニン、オーラプテン、イカリソサイドAはニコチン性アセチルコリン(ACh)受容体刺激よるカテコールアミン(CA)分泌と細胞内へのCa、Naイオン流入を濃度依存性に抑制した。アピゲニンとルテオリンはチロシン水酸化酵素(TH)活性を濃度依存的に抑制した。イカリソサイドAはACh刺激によるCA生合成やTH活性を濃度依存的に抑制した。アピゲニンとイカリソサイドAはイオンチャネルの機能を阻害してCA神経系の機能を抑制することが示唆された。
1 0 0 0 OA 3. 日本の医学教育の現状と医師国家試験
- 著者
- 中谷 晴昭
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.14-17, 2015-02-25 (Released:2017-03-03)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
日本の医学教育では, 欧米に比して, 学生の医学知識の面では決して劣ることはないものの, 臨床実習の時間と内容という面で不十分であることが指摘されている. 全国医学部長病院長会議では, CBTとOSCEからなる共用試験の資格化に取り組み, 全国統一基準でスチューデント・ドクターの認定を行おうとしている. これにより臨床実習に進む学生の質保証が行われ, 国民の理解を得たうえで, より充実した診療参加型臨床実習に実施することが可能となる. 日本の医師国家試験は問題数が多く, 受験生の負担も大きい. 今後, 医師国家試験が臨床実習の成果を判断するものになると共に, 将来的には各大学での客観性, 公平性の担保された卒業時OSCEの実施を条件として医師国家試験の軽減化も考慮されるべきであろう.
比叡山西麓に位置する京都府左京区八瀬は八瀬童子会という組織をもつ。八瀬童子は天皇から特権を与えられ,明治・大正・昭和の三天皇の大喪にかかわった。皇室と比叡山との関係の中で八瀬童子の人々は独特な空間認識と歴史意識を育んだ。本研究は絵図,古文書,聞き取りから八瀬童子の空間認識と歴史意識を明らかにした。八瀬童子の空間認識は18世紀初頭に起こった比叡山延暦寺との境界争いで顕在化する。裁許の結果,比叡山と八瀬の境界が「老中連署山門結界絵図」に描かれた。地形図,空中写真などにより絵図に描かれた境界線や事物の位置を推定,現地で確認調査を行った。また絵図のデジタル画像を作成,5点の絵図の違いを明確にした。この結果,八瀬と比叡山の境界は現在の琵琶湖国定公園の西端,すなわち元禄国絵図における山城国と近江国の国境と一致した。この争論が発生した原因は八瀬や大原の集落で行われていた柴の採取にある。八瀬の人々は比叡山の聖域を越えて柴の採取を行い,京の市中で柴を売り歩いた。この日常的な経済行為が比叡山との境界争いを生んだ。しかしこの争論は天皇から特権を与えられた八瀬童子に有利な裁決が下された。これに感謝して始まったとされる「赦免地踊り」は実は11世紀中期まで遡ることができる。すなわち中世的な祭礼組織にみられる歴史意識は18世紀初頭に変質したと考えられる。
1 0 0 0 OA 和歌山県ドクターヘリの急性期脳梗塞診療体制への貢献
- 著者
- 藤田 浩二 岩崎 安博 宮本 恭兵 米満 尚史 八子 理恵 上田 健太郎 中尾 直之 加藤 正哉
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本脳神経外科救急学会 Neurosurgical Emergency
- 雑誌
- NEUROSURGICAL EMERGENCY (ISSN:13426214)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.165-173, 2020 (Released:2020-12-23)
- 参考文献数
- 13
和歌山県では和歌山県立医科大学附属病院(以下,当院)に2003年1月からドクターヘリが導入され,積極的な救急医療活動を展開している.当院を起点としたドクターヘリが脳梗塞治療に寄与しているかを検証すべく,2011年7月より2017年12月の6.5年間で当院救急外来に搬送,入院に至った脳梗塞症例1479例を搬送手段別にドクターヘリ113例,救急車1039例,直接来院327例の3群に分け患者背景,治療成績を検討した.来院時年齢はドクターヘリ群(平均79.3歳)が他の2群に比し有意に高齢,病型はドクターヘリ群が脳塞栓(60.2%),直接来院群はラクナ梗塞(51.7%)が有意に高頻度であった.来院時NIHSSもドクターヘリ群(平均15.8)が他群に比し有意に高く,来院時重症であった.発症から来院までの時間はドクターヘリ群が有意に短く(平均210.3分),その結果アルテプラーゼ静注療法や急性期血行再建術の施行頻度も他群に比し有意に高かった.また和歌山県内を2次保健医療圏別に分け解析すると,ある医療圏では過半数の症例で当該医療圏内への患者病院搬送後に,当地の医師の判断で高次の治療目的に当院へのドクターヘリ搬送を要請,すなわち施設間搬送がなされていた.その一方で別の医療圏では施設間搬送依頼は極めて少なく,ほとんどが現着した初動救急救命士の判断で現場よりドクターヘリが要請されていた.このように医療圏によりドクターヘリ要請目的が大きく異なることが明らかとなった.本検討で和歌山県ドクターヘリは,遠隔地域の脳梗塞患者に対するアルテプラーゼ静注療法や血行再建術等の早期治療介入に寄与していたことがわかった.和歌山県ドクターヘリが拠点病院を核とする脳卒中診療体制を補完するには,地域毎に異なるドクターヘリ要請目的に応需する“柔軟性”の継続が重要である.
1 0 0 0 OA 家電小売流通の日英比較研究-ディクソンズ社(英国)の展開を比較の基軸として-
- 著者
- 薄井 和夫 DAWSON John
- 出版者
- 埼玉大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2007
本研究は、英国最大手の家電小売企業ディクソンズ社(現在DSGI社)が、(1) わが国カメラの英国への輸入とわが国チノン社との提携によって成長の端緒をつかみ、(2) 競合企業カリーズの買収を機に総合家電小売として成長を遂げる一方で、アメリカ市場参入の失敗による深刻な危機を経験し、(3) これを克服して現在の地位を確立するまでの発展の軌跡を解明し、「漸次的イノベーション」[=画期的な革新とは異なる部分改良型の革新]を同時並行的に継続することの重要性を明らかにした。同時に、わが国独自の系列家電チェーンの端緒を築いた戦前の展開を解明し、独立系企業の近年の展開によって欧米の家電小売業と直接比較研究を行ないうる条件が成熟してきたことを示した。
1 0 0 0 OA 根菜類の機械利用収穫試験
- 著者
- 上原 洋一 三善 重信
- 出版者
- 農業食料工学会
- 雑誌
- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.298, 1976 (Released:2010-04-30)
1 0 0 0 OA 1.慢性腎臓病と高血圧パターン
- 著者
- 脇野 修
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.5, pp.793-801, 2016-05-10 (Released:2017-05-10)
- 参考文献数
- 15
慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)における高血圧のパターンは夜間高血圧,dippingの消失,仮面高血圧といった血圧日内変動の異常,血圧変動性の亢進が特徴であり,自由行動下血圧測定(ambulatory blood pressure monitoring:ABPM)による24時間血圧測定や家庭血圧測定が重要である.さらに,治療抵抗性であり,その原因として塩分貯留,レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の亢進のみならず,交感神経活性の亢進,血管内皮機能障害,血管構造異常といった機序も関与する.
1 0 0 0 OA 病院外心停止に対する二次救命処置の実施場 所判断因子に関する疫学調査
1 0 0 0 OA 東京の市区改正条例 (明治時代) を中心とした幹線道路形成の史的研究
- 著者
- 堀江 興
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文報告集 (ISSN:03855392)
- 巻号頁・発行日
- vol.1982, no.327, pp.115-127, 1982-11-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 自己開示の対人魅力に及ぼす効果
- 著者
- 中村 雅彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.131-137, 1984-08-30 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
The purpose of this study is to examine the effects of personalistic self-disclosure on interpersonal attraction. Thirty-two male subjects participated in the experiment. After showing intimate or superficial disclosure, the confederate attributed the cause of his disclosure either to the subjects (personalistic condition) or to the confederate himself (non-personalistic condition). Subjects were then informed of these attributions. Results obtained clearly supported the hypotheses. Subjects who received intimate and personalistic disclosures liked the confederate significantly more than those who received intimate and non-personalistic disclosures. On the other hand, subjects who received superficial and personalistic disclosures disliked the confederate significantly more than those who received superficial and non-personalistic disclosures.
- 著者
- 木田 真美 吉越 仁美 小西 秀知 内海 さやか 佐藤 修一 小泉 勝
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.540-547, 2017-08-30 (Released:2017-08-30)
- 参考文献数
- 19
2型糖尿病患者は年々増加傾向で,加齢に伴い種々の臓器障害を合併する.腎機能障害が高率にみられる高齢者では,薬剤の選択・用量調整が重症低血糖回避のために必要となる.汎用されているDPP-4阻害薬の中で,胆汁排泄型リナグリプチンを75歳以上の39例に,新規・上乗せあるいはシタグリプチン,ビルダグリプチン常用量からの切り替え投与を行い,血糖及び肝腎機能,脂質の変動を観察した.75歳未満75例と比較すると,6か月後の血糖,HbA1cが新規および切り替え両群で有意に改善し,全体の改善度も高かった.Crea>1.0 mg/dLの腎機能障害例でもHbA1cは有意に改善し,肝腎機能悪化や脂質代謝異常,低血糖,体重増加その他の副作用もなかった.高齢2型糖尿病患者において,腎機能障害に関わらず,リナグリプチンは単一用量で安全に使用でき,有用な薬剤と考えられた.
1 0 0 0 OA メダカOryzias latipesの骨学的研究
- 著者
- 籔本 美孝 上野 輝彌
- 出版者
- 北九州市立自然史・歴史博物館
- 雑誌
- 北九州市立自然史博物館研究報告 (ISSN:0387964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.143-161, 1984-09-20 (Released:2023-11-24)
Recent studies which drastically changed the systematic position of Oryzias latipes stimulated us to investigate and provide complete osteological illustrations and description of the rice fish which has been one of the most popular fishes in Japan.The important osteological features of Oryzias latipes Temminck et Schlegel include loss of some elements, and specialization in structures related to feeding and sexual dimorphism. Bony elements lost in Oryzias latipes are parietals, prevomer, infraorbital bones, supraorbitals, intercalars, orbitosphenoid, basisphenoid, 1st and 2nd pleural ribs, ectopterygoids, metapterygoids, 1st pharyngobranchials, upper hypohyals, interhyals, supracleithra, mesocoracoids. Morphological specializations include sexual dimorphism in tooth forms: teeth are larger and fewer in male with robust teeth at the posterior end of the premaxillary. Branchial skeletons have special enlargement of 3rd pharyngobranchials and pharyngeal bones. Number of vertebrae is 27–30 with 11–12 abdominal and 16–18 caudal vertebrae.
1 0 0 0 OA 世界唯一の超大型機による北九州空港での潜在的可能性およびその将来像・理想像
- 著者
- 塚田 博之
- 出版者
- 公益財団法人 アジア成長研究所
- 雑誌
- 東アジアへの視点 (ISSN:1348091X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.21-24, 2019 (Released:2020-01-08)
1 0 0 0 OA 消防覚知段階における墜落外傷のトリアージ
- 著者
- 大西 新介 小野寺 良太 杉浦 岳 高橋 宏之 近藤 統 岡本 博之 大城 あき子 清水 隆文 森下 由香 奈良 理
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.469-474, 2019-06-30 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 8
目的:消防覚知段階の情報から墜落外傷のトリアージが可能か検討する。方法:2003年4月からの4年間に当院へ救急搬送された墜落外傷症例を導出コホート,検証コホートに分けて後方視的に調査した。まず墜落高の重症外傷(ISS≧25)予測能についてROC解析を行った。次に重症予測にかかわる因子の多変量解析を行い,スコアリングを作成し検証した。結果:導出コホート111例において墜落高の重症予測能はAUCが0.65であり,墜落高の閾値は4mとなった。多重ロジスティック解析では高所,高齢,受傷時の意識障害が独立した重症予測因子であった。それぞれの因子を1点としたスコアリングを用いるとAUCが0.76となった。検証コホート128例においてもAUCは0.77であった。結論:墜落外傷においては,墜落高だけではなく高齢,受傷時の意識障害の情報を付加することでより正確なトリアージが可能となる。
1 0 0 0 ライフヒストリーレポート選
- 著者
- 菊地暁編
- 出版者
- 京都大学民俗学研究会 (京民研)
- 巻号頁・発行日
- 2014
- 著者
- Takeo KAWAMICHI Samdannyamin DAWANYAM
- 出版者
- THE MAMMAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Mammal Study (ISSN:13434152)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1+2, pp.89-93, 1997 (Released:2005-10-07)
- 参考文献数
- 10
We excavated a breeding nest of the Daurian pika, Ochotona daurica, in central Mongolia. Four young were captured within the burrows. Three food storage chambers contained plant fragments and a large amount of fecal matter, indicating that hoarded food had been consumed during the last winter. The nest chamber was spherical and measured 22×18×21 cm. Most of the nest chamber was filled with piles of grasses, and these piles were presumably their resting site. The burrow system had three entrances, and the nest chamber was connected to three burrows. Multiple nest entrances were provided ready access to refuge for pikas active on the ground surface from aerial and terrestrial predators, while multiple burrows also provide refuge against the intrusion of predators such as stoats into nest chambers.
1 0 0 0 OA コガネムシの昆虫ポックスウイルス研究,最近の進展
- 著者
- 三橋 渡
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.1_51-1_63, 2015 (Released:2015-07-08)
- 参考文献数
- 65
1 0 0 0 OA Politicizing the Fear of Crime in Decentralized Indonesia: An Insight from Central Lombok
- 著者
- Yogi Setya Permana
- 出版者
- Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
- 雑誌
- Southeast Asian Studies (ISSN:21867275)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.99-116, 2019 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1
In the study of contemporary local politics and the dynamics of decentralization in Indonesia, there is insufficient research on how political actors integrate both psychologically and emotionally as a strategy to gain power at the local level. This paper explores the way in which the emotion labelled “fear of crime” embodies local power, specifically in the Central Lombok District of West Nusa Tenggara Province. Efforts have been made to investigate how the fear of crime emerged and was disseminated, as well as how the politics of fear appeared and functioned in a social setting. This paper argues that fear can be socially constructed through talk of crime and politicized in the context of local elections by elites through informal security groups or individual datu maling, two entities that I refer to as “fear entrepreneurs.”