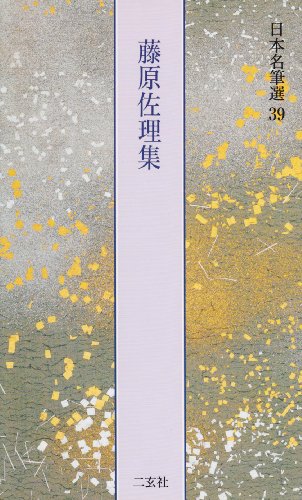1 0 0 0 地方神に対する天皇祭祀の研究
- 著者
- 新林 力哉 (2023) 新林 力哉 (2022)
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2023-03-08
古代社会では祈雨など政治的・社会的に意味のある祭祀を為政者が行うことが重要である。本研究は、日本古代における天皇がどのような構造で地方の神々を祭っていたかを検討し、古代天皇が持つ祭祀執行者としての性格を明らかにするものである。特に地方神祭祀の究明を重視するのは、各地域の共同体を支配下に置く天皇がその神をどのように祭るかが国家としての特性を表すという考えからである。また地方神祭祀を研究するため国司や地方豪族の祭祀のあり方をも対象とし、天皇祭祀との関係を検討することで、古代国家の地方神祭祀の構造を明らかにする。そして奈良時代から平安時代後期にわたる変化を追い、古代国家の中世への変化を明らかにする。
1 0 0 0 OA 従業員エンゲージメントを高めるリモートワークとは?
- 著者
- 安藤 真一郎 矢本 成恒
- 出版者
- 日本開発工学会
- 雑誌
- 開発工学 (ISSN:13437623)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.39-43, 2021-10-20 (Released:2022-05-20)
- 参考文献数
- 6
The purpose of this study is to clarify how the environmental changes caused by the Covid-19 affected employee engagement, and to examine how remote work affects employee engagement and how it should be managed. In this study, social trends in working attitudes are confirmed from newspaper articles to understand the current situation, and a questionnaire survey of actual employees and interviews with employees are conducted to extract specific issues.The results of the survey indicate that telework not only has the effect of increasing employee engagement, but also has the effect of decreasing employee engagement by greatly affecting communication among workers. Therefore, it was concluded that although remote work is an effective tool for increasing employee engagement, it is necessary to introduce performance-based workplace culture and communication policies at the same time in order to take advantage of its effectiveness.
1 0 0 0 OA 1960年以降の全国高速交通体系のサービス水準の変化とその評価
- 著者
- 近藤 光男 青山 吉隆 廣瀬 義伸 山ロ 行一
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.777-784, 1996-08-31 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 17
本研究では、道路、鉄道、航空からなる高速交通体系における1960年以降の整備変化について、旅行時間と費用に着目して分析を行い、どのようなサービス水準の向上があったのかを交通機関の利用者の時間価値に基づいて明らかにするとともに費用差時間差比指標を用いて評価を行った。その結果、道路と鉄道の比較では、この指標は激しく変動し互いに影響を及ぼしやすいことがわかった。鉄道と航空を比較した場合には、費用差時間差比が全体的に低下しており、航空が有利になる傾向がみられた。一方、都市部と地方部を比較してみると、同じ交通機関でも地域によって利用者の選好比率に大きな差があり、高速交通サービスにおける地域間格差の存在が浮き彫りにされた。
1 0 0 0 OA 研究 転移性心腫瘍64例の臨床病理学的検討
- 著者
- 星野 智 大川 真一郎 今井 保 久保木 謙二 千田 宏司 前田 茂 渡辺 千鶴子 嶋田 裕之 大坪 浩一郎 杉浦 昌也
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.130-135, 1992-02-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 17
悪性腫瘍の心転移はまれでないが生前診断は困難なことが多い.今回剖検例にて発見された転移性心腫瘍につき臨床病理学的検討を行った.1980年から1987年の連続剖検2,061例のうち肉眼的に転移性心腫瘍の認められた64例を対象とした.年齢は55歳から93歳(平均76.6歳),男39例,女25例であった.全悪性腫瘍は845例であり,心転移率は7.6%であった.原発巣は肺癌34例が最も多かった.心転移率は肺癌,胃癌などが高かったが,消化器癌では低かった.転移部位は心膜81.3%が最も多く,心内膜へ単独に転移した例はなかった.心膜へはリンパ行性転移が多く,心筋へは血行性転移が多かった.特に肺癌は心膜の転移,心房への転移が多い傾向にあった.心単独の転移はまれで55例は他の臓器へ転移が認められ,肺,肝,胸膜,骨に多かった.心電図異常所見は95%にみられたが,転移部位による特異性は認められなかった.しかし心膜転移例で心膜液量増加に伴い低電位差と洞頻脈が高率に出現してきた.悪性腫瘍を有する患者では常に心転移を念頭におき,注意深い臨床観察が必要である.
- 著者
- 長田 貴之 柴山 良彦 熊井 正貴 山田 武宏 笠師 久美子 倉本 倫之介 洲崎 真吾 赤澤 茂 真栄田 浩行 坂下 智博 折舘 伸彦 本間 明宏 福田 諭 菅原 満 井関 健
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.51-55, 2012-01-10 (Released:2013-01-10)
- 参考文献数
- 14
Intractable nausea and vertigo induced by opioid treatment are occasionally difficult to treat. It has been reported that antiemetic drugs and opioid rotation may be effective in treating nausea in such cases; however, this approach has been occasionally ineffective. Symptomatic treatment has not been developed for vertigo induced by opioid treatment. Here, we report a case study where combined treatment with perospirone and a histamine H1 receptor antagonist was used in 2 patients who developed intractable nausea and vertigo induced by opioid treatment. Treatment with a histamine H1 receptor antagonist drug (tablet form, containing 40 mg diphenhydramine salicylate and 26 mg diprophylline) suppressed the nausea and vertigo. However, increasing the opioid dosage exacerbated the symptoms, and treatment involving the histamine H1 receptor antagonist and opioid rotation was ineffective. Subsequently, combination treatment with the histamine H1 receptor antagonist (3 tablets per day) and perospirone (maximum daily dose, 16 mg) improved the symptoms. The results of the present study suggest that combination treatment with a histamine H1 receptor antagonist and perospirone might improve intractable nausea and vertigo induced by opioid treatment.
1 0 0 0 OA 歯学部外来における意識障害の救急対応
- 著者
- 千葉 俊美
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.133-139, 2019-03-29 (Released:2020-02-06)
- 参考文献数
- 18
症例は80 歳代女性.主訴は意識障害である.既往歴は 61 歳からラクナ梗塞の診断でバイアスピリンを内服しており,70 歳から慢性気管支炎で加療中である.本学歯科外来で義歯調整中に突然意識消失が出現し,直後にいびきと食物残渣の嘔吐を頻回認めた.歯科治療における薬剤の投与はなく,観血的治療も行っていなかった.意識障害のレベルは Japan Coma Scale で3桁であり,意識消失直後は最高血圧が 90mmHg 台まで低下し,経皮的動脈血酸素飽和度も 90% 前半まで低下したため,院内救急コールで救急外来に搬送となった.血液検査では血清 CRP 値の軽度上昇を認め,頭部CT 検査所見で両側大脳半球に低吸収域を認めたが,神経学的所見に明らかな異常を認めず,神経調節性失神の疑いの診断となった.本邦の歯科病院における救急症例数の発生頻度は 0.003-0.009% で,原因としては異常血圧上昇,異物誤嚥誤飲,血管迷走神経反射,過換気症候群の順である.救急症例発生時の迅速な対応は患者の予後を左右するため,常に患者の容体急変時の対処法の知識および技術の維持が求められる.
- 著者
- Makoto Mizuguchi Akitoshi Takayasu Takayuki Kubo Shin'ichi Oishi
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE (ISSN:21854106)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.386-394, 2016 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 20
This paper is concerned with the embedding constant of the Sobolev type inequality for fractional derivatives on $\Omega\subset\mathbb{R}^{N}~(N\in\mathbb{N})$. The constant is explicitly described using the analytic semigroup over L2(Ω) generated by the Laplace operator. Some numerical examples of estimating the embedding constant are also provided.
1 0 0 0 OA 現行JIS衣料品サイズ表示における問題点
- 著者
- 松山 容子
- 出版者
- Japan Human Factors and Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.Supplement, pp.26-27, 1994-06-01 (Released:2010-03-11)
1 0 0 0 OA 新たな地球公共秩序構築へ向けて -国連の役割に関する考察-
- 著者
- 内田 孟男
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.137, pp.12-29,L6, 2004-06-19 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 56
The prototype of the post-World War II order was formulated at the Dumbarton Oaks and Bretton Woods conferences in the summer of 1944. The United Nations system has since occupied a central place in the international collaborative framework in peace and security as well as in development and environment. The accelerated process of globalization, however, in the wake of the end of the cold war, has increasingly eroded the existing “international” order and transformed the role of the states. Non-state actors such as civil society, NGOs, the private sector, and other social forces have appeared on the global arena, to supplement if not supplant, the states in the making of a new order.Against this historical backdrop, this essay purports to examine the possible role that can and should be played by the United Nations in constructing a humane and more equitable global order. After reviewing briefly the impacts of globalization and the concepts and theories of global governance, the essay focuses on the UN's role in various phases of global public policy making, starting from the identification of global issues, consensus-building on goals and principles, deliberations and decision-making, implementation, and review and evaluation. The UN's unique status that enjoys legitimacy as the sole general and universal organization has contributed to each of these phases. A difficult phase is that of deliberation and decision-making. The decision-making in the Security Council reflects quite directly the power configuration of the permanent members and by constitution is restricted to the issues of international peace and security. The General Assembly decision-making, on the other hand, mirrors the concerns of the majority of the developing countries. The consensus arrived at by the General Assembly serves as guidelines, though not legally binding, for world society to act as well as for the UN system.The implementation of the decision is possibly the most problematic phase in the global policy making since the bulk of its actual execution has to be done by the states. This is a crucial phase of providing the global public goods. In further elaborating this phase, the essay attempts to demonstrate the relevance of the concept of global public goods in the making of global public policy within the all-inclusive perspective of global governance. Through this exercise, we may build a manageable theoretical frame on the UN's role in the new global era. It finally addresses the role of the UN Secretariat in particular the leadership and initiative in mobilizing the resources through forming and developing partnerships with NGOs, business and regional organizations. Such efforts led by the Secretary-General augur the nature of a nascent new global order.
1 0 0 0 OA 日本株ファクターモデルに足りないもの—データマイニング法を用いた探訪—
- 著者
- 山田 徹 後藤 晋吾
- 出版者
- 日本ファイナンス学会 MPTフォーラム
- 雑誌
- 現代ファイナンス (ISSN:24334464)
- 巻号頁・発行日
- pp.420002, (Released:2020-04-28)
- 参考文献数
- 60
財務データベースにある全ての項目を用いて財務シグナルを生成するデータマイニング法を用いて,現行の日本株ファクターモデルの説明力を検証し,今後のモデル改良への示唆を得た.検証対象は主にFama–Frenchファクターモデル群とした.収益性ファクターと低投資ファクターを含む新しいファクターモデルは,これらを含まない3ファクターモデルに比べて財務シグナルのポートフォリオ・リターンをより良く説明する.しかし,ブートストラップ法による検定により,偶然(偽発見)の可能性を勘案した後でも現行のファクターモデルでは十分に説明できないアノマリーがあることがわかった.これら頑健なアノマリーの中には,企業の無形資産投資や経営者の内生的な意思決定を強く反映すると解釈できる財務シグナルが複数見つかった.これらは今後のファクターモデルが織り込んで発展していくべき方向を示唆していると考えられる.
1 0 0 0 OA COVID-19後遺症としての認知機能障害―病態機序と治療の展望―
- 著者
- 下畑 享良
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.11, pp.725-731, 2023 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 51
COVID-19後遺症として認知機能障害が生じることが明らかになっている.危険因子としては,高齢者,重症感染,嗅覚障害の長期間の持続が報告されている.またCOVID-19はアルツハイマー病の危険因子となることや,軽症感染でも視空間認知障害を呈しうることも報告されている.複数の病態機序が指摘されているが,治療に直結する可能性があるSARS-CoV-2ウイルスの持続感染が注目されている.持続感染は,スパイク蛋白による神経毒性,サイトカインによる神経炎症の惹起,細胞融合などを介して認知機能障害を引き起こす可能性がある.予防・治療としてはワクチン接種,メトホルミン,抗ウイルス薬などが期待されている.
1 0 0 0 OA 2C5-11 TIMSS1999 数学授業ビデオ研究のねらいと主な結果
- 著者
- 瀬沼 花子
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 27 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.229-232, 2003-07-20 (Released:2018-05-16)
- 参考文献数
- 2
TIMSS1999の付帯調査として, 7か国の中学校2年生について合計638の数学授業のビデオ撮影と分析が行われた。分析の結果, 各国の指導法には類似点とともに多くの相違点があり, 高い得点を導く指導法はただ一つに決まるのではないことが明らかになった。例えば香港と日本は同じくらい数学得点の高い国であるが, 指導法はかなり異なっていた。なお, 国際比較結果に対する各国の視点は, その国の文化と相まって様々である。日本にとっては, 撮影された授業が典型か否かの検討と生徒の数学に対する態度を高める指導法の追求が今後の課題である。
- 著者
- 清水 美憲
- 出版者
- 公益社団法人 日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.3, pp.2, 2002 (Released:2021-04-01)
- 被引用文献数
- 5
1 0 0 0 OA 頂窩に関する研究(第1報)-人間永久臼歯頂窩のSEMによる観察-
- 著者
- 後藤 讓治 細矢 由美子
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.447-454, 1985-06-25 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 13
頂窩は,1937年,所によって報告された歯牙咬頭部附近のエナメル質に認められる小窩であり,これまで頂窩に関する報告は少ない。本研究においては,10例の咬耗,磨耗の少ない人間永久歯の頂窩49例が観察された。観察は先ず実体顕微鏡によってなされ,次いで超音波洗浄器による洗浄,乾燥後,金蒸着が施され,走査型電子顕微鏡によって観察並びに計測が行われた。また,標本の一部は,頂窩中央部で矢状断され,その側壁部が走査型電子顕微鏡によって観察された。観察の結果,1歯あたり最大9個,最小2個,平均4.9個の頂窩が見られた。頂窩の開口部の形態は,円形(46.9%),楕円形(36.7%)三角形(10.2%),その他(6.1%)に分類された。頂窩の直径は最大0.68mm,最小0.014mmで,平均0.17mmであった。頂窩は,歯牙の咬頭部付近のエナメル質に喇叭状に開口し,エナメル象牙境付近で試験管状に終了する盲管である。また,頂窩の側壁には,側枝状の小孔が開口しているのが観察された。
1 0 0 0 OA 長期寛解が得られた犬の腸リンパ管拡張症の1例
1 0 0 0 OA 頭部外傷による心肺停止で搬送され心拍再開後に救急外来で心停止後臓器提供に至った1例
- 著者
- 山田 哲久 名取 良弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本神経救急学会
- 雑誌
- Journal of Japan Society of Neurological Emergencies & Critical Care (ISSN:24330485)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.32-36, 2023-06-22 (Released:2023-06-23)
- 参考文献数
- 14
Introduction: We report the case of a patient transported to emergency outpatient department by ambulance due to cardiopulmonary arrest following a head injury. He underwent systemic management, leading to organ donation.Case: A 56-year-old man.Current illness history/course: The patient sustained a head injury after falling from the bed of a truck and then suffered cardiopulmonary arrest. He was transported to the emergency department by ambulance. After his heart resumed beating, his intention to donate his organs was confirmed on the back of his health insurance card. Discussions with the organ donation hospital coordinator reveal that, donating organs after brain death was difficult due to the general condition; still the possibility of organ donation after cardiac arrest was considered. Systemic management was continued in the emergency department, and upon obtaining consent from his family, post-cardiac arrest organ donation was carried out.Conclusion: Establishing a system to confirm the intention to donate organs is important. Donor management can be done by performing normal life-saving measures, but certain donor-specific matters require attention.
- 著者
- 大竹 孝司
- 出版者
- The Phonetic Society of Japan
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.76-85, 2010-04-30 (Released:2017-08-31)
本研究は,心理言語学の領域における音声言語の語彙認識の研究で提案されている語彙候補活性化モデルの観点から,話し言葉としての日本語の駄洒落のメカニズムについて考察を試みたものである。このモデルでは,聞き手は話し言葉の個々の単語を直接認識するのではなく,類似した音構造を持つ複数の活性化された単語の中から競合を経て目標の単語を選択するとしている。その際,候補となるのは話者が意図した単語のみならず,単語内や単語間に潜む「埋め込み語」が含まれる。本研究では,即時性を伴う言葉遊びと「埋め込み語」の関係を明らかにするために日本語の駄洒落のデータベースの分析を行った。その結果,駄洒落には同音異義語と類音異議語に加えて単語に内包された単語や外延的な関係にある単語も利用されていることが明らかになった。この結果は,駄洒落では活性化された候補群から最適のものが選択されていると解釈される。このことは駄洒落では候補が英語のpunなどよりも広範囲から選択されるためより自由度の高い言葉遊びであることを示唆している。
1 0 0 0 OA Putrākhyā Daśa Pañca Ca
- 著者
- 谷口 力光
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.943-947, 2023-03-25 (Released:2023-09-08)
- 参考文献数
- 8
家産分割,相続の主体となる様々な「息子」は12世紀頃以降においていかにカテゴライズされ,相対的に位置づけられたか.本報告は,Vijñāneśvara著Mitākṣarā(ca. 1056-1126),Haradattamiśra著Ujjvalā(ca. 1100-1300)という2作品のdharmanibandhaが伝える息子論(eg., putraprakaraṇa)から,このような議論が精緻化してゆく様相の一端を跡付ける. putraprakaraṇaは,主要な息子とされる嫡出子(aurasa)と,養子(dattaka)や再婚女性の息子(paunarbhava)などとの相続上の関係性について情報を伝える.中世サンスクリット法律学における法益論や近現代南アジアにおける寡婦再婚問題などにも関連する重要主題の一つである. 主たる初期文献群(dharmasūtra, dharmaśāstra)は,微妙な相違はあるものの,一般に息子として12-13種類を数える.しかし,その数はMitākṣarāでは14種類,さらにUjjvalāでは15種類に至る.既往研究では,このような息子に関する議論について,諸資料に見られる相違点は「なにか」という点での貢献が行われてきた.本稿は,それらの相違点が「どのように」生じるのかに焦点を当てる. 具体的には,Mitākṣarā,Ujjvalāに見られる発達した議論の間にある唯一の相違点である “yatra kvacanotpādita”と呼ばれる息子種について,これがなぜ前者では言及されず,後者では第15位の息子として掲げられるようになったのかについて,その学的背景を探る.そして,これら両資料が想定していたであろう「結婚の正当性」との関係から,この差異を説明可能であることなどを指摘する. 南アジア広域で指導的地歩を築いたMitākṣarāと,最多の息子種を数えるらしいUjjvalāとの差異化の一端が示されることで,それ以降に著されたdharmanibandhaなどとの比較を行う上での基盤が得られたと期待する.