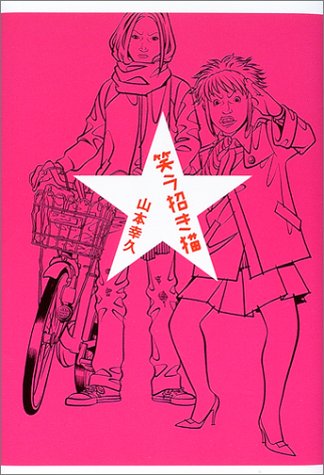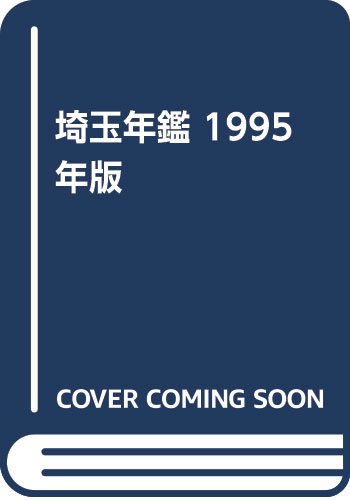1 0 0 0 OA 符号化の違いが顔の記憶に及ぼす影響について
- 著者
- 木原 香代子
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.155-164, 2002-04-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 17
本研究では, 2種類の相貌印象判断と2種類の提示方法を用いて顔の再認記憶に及ぼす影響を検討した。実験1では, 2種類の特性語を用いて相貌印象判断を行い, 顔の再認記憶にどのような影響を及ぼすかを検討した。再認課題には記銘時と再認時で提示される表情が異なる異画像再認課題を用いて行った。その結果, 表情独立特性語で相貌印象判断を行った方が表情依存特性語で行うよりも後の再認成績が良くなることが示された。実験2では, 同一人物の異なる3種類の表情が連続提示され, 一括して相貌印象判断を行う一括符号化条件と, 同一人物の異なる3種類の表情がリスト中に分散して提示され, 個々に相貌印象判断を行う分離符号化条件を設定し, それぞれの提示方法が顔の再認記憶に及ぼす影響について検討した。相貌印象判断は実験1同様2種類の特性語を用い, 再認課題は異画像再認課題で行われた。その結果, 一括符号化条件の方が分離符号化条件よりも後の再認成績が良くなることが示された。したがって, 3つの表情の統合を促す符号化が顔の再認記憶を促進することが示唆された。
1 0 0 0 OA REFRANERO ESPANOL(31) : スペインの諺辞典
- 著者
- Villasanz Bernardo 新井 藍子 Arai Aiko
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.1321-1334, 2007-03
1 0 0 0 OA 低温プラズマによるリグノセルロースのガス化とその応用
- 著者
- Hiroshi SHIIGI Takahiro FUJITA Xueling SHAN Masahiro TERABE Atsushi MIHASHI Yojiro YAMAMOTO Tsutomu NAGAOKA
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.281-285, 2016-03-10 (Released:2016-03-10)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 5 6
Generally, the characterization of a metal layer formed on a planar substrate has been achieved using scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. These techniques provide details of the surface and/or the cross-section of a planar structure with high resolution. However, the evaluation of sphere-like structures is troublesome owing to the necessity to observe a sample from various angles and/or to calculate the yield from many values obtained for many samples, since the conventional methods can observe a sample only from one direction. We have developed a simple evaluation method for a thin metal layer on plastic microbeads based on its light-scattering properties using dark-field microscopy coupled with a spectrometer. The light-scattering intensity of gold-nanoparticle-coated microbeads depends significantly on the gold coverage. We believe that our study is significant because it describes the development and evaluation of the surface coverage of a thin metal layer on a sphere-like microstructure.
1 0 0 0 OA 車道上の走行環境と自動車交通が自転車利用者の注視挙動に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 西原 大樹 辰巳 浩 吉城 秀治 堤 香代子
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.A_125-A_133, 2016-02-05 (Released:2016-02-05)
- 参考文献数
- 10
本研究では、自転車専用通行帯及び車道路肩部のそれぞれ幅員の違う路線において、視点を解析することができるアイマークレコーダを用いた自転車走行実験を行い、自転車を追い越していく自動車から受ける影響に関して分析を行った。その結果、調査対象路線の中で走行空間幅員が 1m と最も狭かった路線においては、自動車の追い越し台数が増加するにつれて自らの走行場所である車道路肩を注視する時間や回数が増加していた。また、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」で望ましいとされている幅員 1.5 m以上の、幅員が 1.85 mの路線においては自転車を追い越す自動車台数が増加するほどサッカードが発生していること、それよりもさらに幅員の広い路線では注視挙動に自動車交通の影響がみられなくなることが明らかになった。
1 0 0 0 OA 自転車の短時間駐輪に関する一考察 -JR国立駅南口における社会実験をもとに対策を考える-
- 著者
- 橋本 悟
- 出版者
- 一般財団法人 運輸総合研究所
- 雑誌
- 運輸政策研究 (ISSN:13443348)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.022-029, 2013-07-23 (Released:2019-03-29)
- 参考文献数
- 12
本稿は,東京都国立市のJR国立駅南口周辺におけるアンケート結果と社会実験に基づいて,違法駐輪を減少させるための対策を具体的に考えるものである.買い物などの短時間駐輪については,目的地の近傍に駐輪場がなければ,それを利用しない傾向がある.そこで,歩道の一部に短時間駐輪スペースを設けて違法駐輪を減少させる社会実験を行った.結果として,約20mごとに約10台程度の駐輪スペースを設けた場合,30分以内の駐輪であれば十分に対応できることがわかった.ただし,経常的に違法駐輪をしている人は利用しない可能性があること,駐輪場の管理,駐輪時間の問題,及び近隣住民の協力体制などさまざまな問題があることもわかった.
1 0 0 0 OA 睡眠時無呼吸症候群の胃食道逆流症合併とCPAPによる治療効果の検討
- 著者
- 佐藤 英夫 岩島 明 河辺 昌哲 中山 秀章 吉澤 弘久 下条 文武 鈴木 榮一
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.491-495, 2005-05-31 (Released:2017-11-10)
- 参考文献数
- 16
睡眠時無呼吸症候群(以下SAS)の胃食道逆流症(以下GERD)合併頻度を,QUEST問診票を用いて検討した.QUESTは4点以上をGERD合併ありと判断した.PSG(Polysomnography)検査を実施した84例中の73例にAHI(Apnea Hypopnea Index)≧5 (/hr) のSASを認めた.QUEST 4点以上が25例(34.2%)あり,GERD合併の有無で2群に分けたときAHI,脳波上の短時間覚醒指数(以下Arousal Index),BMIなどに有意差はなかった.AHI≧20かつQUEST≧4点の17例中,11例がCPAP治療を開始した.CPAP治療を開始した4週間後のQUEST得点は7例で無症状(0点)となった.残る4例はプロトンポンプ阻害薬(PPI)の内服を追加して,症状の消失が得られた.SASによる胸腔腹腔内圧較差開大をCPAP治療が改善して,胃酸逆流を抑制する機序が関与すると考える.SASには高頻度にGERDが合併することから積極的な問診と治療追加が望まれる.
- 著者
- Yuanji Cui Kiyotaka Hao Jun Takahashi Satoshi Miyata Tomohiko Shindo Kensuke Nishimiya Yoku Kikuchi Ryuji Tsuburaya Yasuharu Matsumoto Kenta Ito Yasuhiko Sakata Hiroaki Shimokawa
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.520-528, 2017-03-24 (Released:2017-03-24)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 61 68
Background:We are now facing rapid population aging in Japan, which will affect the actual situation of cardiovascular diseases. However, age-specific trends in the incidence and mortality of acute myocardial infarction (AMI) in Japan remain to be elucidated.Methods and Results:We enrolled a total of 27,220 AMI patients (male/female 19,818/7,402) in our Miyagi AMI Registry during the past 30 years. We divided them into 4 age groups (≤59, 60–69, 70–79 and ≥80 years) and examined the temporal trends in the incidence and in-hospital mortality of AMI during 3 decades (1985–1994, 1995–2004 and 2005–2014). Throughout the entire period, the incidence of AMI steadily increased in the younger group (≤59 years in both sexes), while in the elderly groups (≥70 years in both sexes), the incidence significantly decreased during the last decade (all P<0.01). In-hospital cardiac mortality significantly decreased during the first 2 decades in elderly groups of both sexes (all P<0.01), whereas no further improvement was noted in the last decade irrespective of age or sex, despite improved critical care of AMI.Conclusions:These results provide the novel findings that the incidence of AMI has been increasing in younger populations and decreasing in the elderly, and that improvement in the in-hospital mortality of AMI may have reached a plateau in all age groups in Japan.
1 0 0 0 ロシアン・ゴッドファーザー
- 著者
- ヴァディム・ベリフドミトリー・リハノフ共著 中出政保訳
- 出版者
- エーブイエス(発売)
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 OA 新規遺伝子改変技術を利用したコオロギの再生芽形成メカニズムの解明
- 著者
- 渡辺 崇人
- 出版者
- 徳島県立農林水産総合技術支援センター(試験研究部)
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-01
ゲノム編集技術を用いて、コオロギのHox遺伝子に最小化プロモーターの下流にeGFP遺伝子を配置したベクターをノックインした結果、予想される発現パターンで蛍光が観察され、エンハンサートラップ系統を作製することに成功した。ノックインの方向及び結合部位を正確に組み込む方法として、MMEJの経路を用いたノックイン技術の導入を試み、標的遺伝子の終止コドン上にeGFP遺伝子を正確に組み込み、その発現を観察することができた。また、PacBioRSIIを用いたRNA-seq解析を行った。抽出したmRNAを分画し、4cellずつシークエンス解析を行った結果、合計で76万リード、2.25Gbの配列が得られた。
1 0 0 0 OA コンディショナルノックアウト技術を用いた不完全変態昆虫の翅形成メカニズムの解明
1 0 0 0 OA 大般若会についての一考察
- 著者
- 小峰 彌彦
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.39-50, 2020 (Released:2021-04-06)
The Daihanyae is a ceremony, which is held in Japan, in which monks perform group recitations (albeit abbreviated) of the “Large Perfection of Wisdom Sūtra” for the purpose of commemorating Genzo’s translation of 600 scrolls of the sūtra from Sanskrit into Chinese. These recitations were originally performed as Shingon rituals in Nara at the Todaiji, Kofukuji, and Yakushiji temples. The Daihanyae, which goes beyond sectarian bounds, is an important traditional ceremony in Tendai, Zen, and several other schools of Buddhism. This study is written from the perspective of ceremonies that include religious belief and, thus, goes no further than pointing out the issues and simply reflects the thoughts of the author. The subject matter of the study is the group recitations of the “Large Perfection of Wisdom Sūtra”; it examines this religious ceremony from several perspectives, delves into the development of Buddhism in Japan as a whole, and raises further issues for discussion.
- 著者
- Satoru Okuda Yasuhiro Inoue Taiji Adachi
- 出版者
- The Biophysical Society of Japan
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.13-20, 2015 (Released:2015-08-18)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 32 47
During morphogenesis, various cellular activities are spatiotemporally coordinated on the protein regulatory background to construct the complicated, three-dimensional (3D) structures of organs. Computational simulations using 3D vertex models have been the focus of efforts to approach the mechanisms underlying 3D multicellular constructions, such as dynamics of the 3D monolayer or multilayer cell sheet like epithelia as well as the 3D compacted cell aggregate, including dynamic changes in layer structures. 3D vertex models enable the quantitative simulation of multicellular morphogenesis on the basis of single-cell mechanics, with complete control of various cellular activities such as cell contraction, growth, rearrangement, division, and death. This review describes the general use of the 3D vertex model, along with its applications to several simplified problems of developmental phenomena.
- 著者
- 梶 茂樹
- 出版者
- Japan Association for African Studies
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.1982, no.21, pp.106-110, 1982-03-30 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 【資料:解題】明星学苑海外日本人小学校の足跡 : カジフ明星小学校を中心に
- 著者
- 高島 秀樹
- 出版者
- 明星大学明星教育センター
- 雑誌
- 明星大学明星教育センター研究紀要 = Research bulletin of Meisei University Meisei kyoiku center (ISSN:21862974)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.85-99, 2017-03-31
1 0 0 0 OA ニホンアカガエルとヤマアカガエルの染色体分染法による核型
- 著者
- 飯塚 光司
- 出版者
- 日本爬虫両棲類学会
- 雑誌
- 爬虫両棲類学雑誌 (ISSN:02853191)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.15-20, 1989-06-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 6
The chromosomes of Japanese brown frogs Rana japonica and R. ornativentris were analyzed with conventional Giemsa staining, C-banding for heterochromatin distribution, and silver staining for nucleolus organizer regions (NORs). R. japonica had 2n=26 chromosomes, centromeric heterochromatin on all chromosome pairs, and NORs on the secondary constrictions on a long arm of No. 9 chromosome. R. ornativentris had 2n=24 chromosomes, pericentric heterochromatin on 5 large chromosomes, and NORs situated in the secondary constrictions of a long arm in No. 10 chromosome. According to the banding karyotype analyses of both species, the process and possible consequences of chromosome number reduction from an ancestral 26-chromosome karyotype is discussed.
- 出版者
- ニューサイエンス社
1 0 0 0 西宮市立図書館三十年史
- 著者
- 西宮市立図書館三十年史編集委員会編
- 出版者
- 西宮市立図書館
- 巻号頁・発行日
- 1958