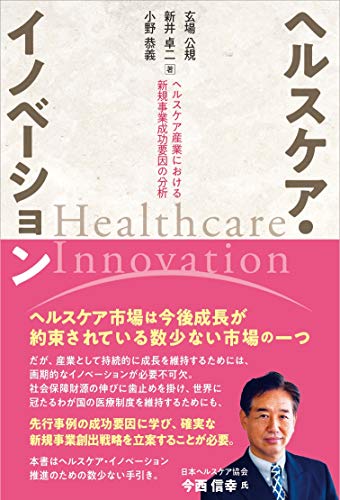1 0 0 0 OA 泣菫詩集
- 著者
- 薄田泣菫 著
- 出版者
- 大阪毎日新聞社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1925
1 0 0 0 OA 倉沢愛子著『ジャカルタ路地裏フィールドノート』
- 著者
- 内藤 耕
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.85-91, 2002 (Released:2014-09-15)
1 0 0 0 OA スポーツにおける 「コミュニタス性」
- 著者
- 舛本 直文
- 出版者
- Japanese Society of Sport Education
- 雑誌
- スポーツ教育学研究 (ISSN:09118845)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.113-123, 1985-06-20 (Released:2010-08-10)
- 参考文献数
- 21
The purpose of this study is to clarify the specific behaviors of sport groups by means of the concept, “communitas” which is offered by V, Turner. This analysis takes the semioticstructual method which differs from the structual-functional one. And the ritual process in sport is interpreted in the light of the cultural-anthropology. The procedure of this study, firstly, makes an overview of the concept, “communitas”, which appears in three dimensions of culture; “liminality”, “outsiderhood”, and “structual inferiority”, then proceeds to the relation with the rite of passage. Secondly, in view of the interaction of members, “communitas” can be demonstrated with “rhizome type” model which takes the form of the multidimensional network system. On the contrary, “community” is characterized by “tree typ” model. According to these procedure, this analysis proceeds to the examination of “communitas” and the ritual traits in sport groups.The results are as follows;1) It is necessary for the analysis of sport groups characterized by “communitas” to take supplementary approach with the team-work theory which has been developed for the social structual system.2) The specific behaviors in sports, e.g. the encouraging shout and cry “GANBA!”, or mass running exercises in formation, could be clarified as “rites of passage” or “transition rites” in broad sense.3) This shout “GANBA!” is a password for performing audiences to take part in the sport situation sympathetically. At the same time, the shout is also a prayer for athletes to enter into the movement landscape or background of ordinary sports.
1 0 0 0 OA 通常ダイカスト法によるアルミクローズドデッキシリンダブロックの実用化
- 著者
- 高橋 忠生 多胡 博司 萬谷 信廣
- 出版者
- 公益社団法人 日本鋳造工学会
- 雑誌
- 鋳物 (ISSN:00214396)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.5, pp.371-375, 1994-05-25 (Released:2015-01-21)
- 著者
- 熊田 ふみ子 倉橋 節也
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.1331-1344, 2022-07-15
SDGs(持続可能な開発目標)に代表されるように,相互に関連しあい複雑な問題に直面している現在,個人では正解を導き出すことは難しい.そのために,1人1人の知識だけでは創造できない高次元の集合知が求められている.そして,集合知を生み出すためには,ファシリテーションが重要といわれている.そこで本研究は,ダイバーシティ・マネジメントの研究分野のフォールトライン(以下,FL)理論を応用して,議論のプロセスを可視化する.そのうえで,議論の進行と集合知の生成関係と,そのプロセスへのファシリテータの関与を明らかにすることを目的とする.FLとは,グループを1つ以上の属性によりサブグループ(以下,SG)に分ける仮想の分割線である.実際に議論された内容をテキストデータに起こし,議論の特徴語を分散表現でベクトル化する.そのベクトルを特徴語の属性と見なし,10発言を1つのグループにして特徴語の関係性をFLとSGで測る.そして,移動平均法を用いて,議論の発散・収束プロセスをFLの強さ,多様性をSG数の変化で可視化する.その結果,特徴語を引継ぎながら発言が続いた後に,ある特徴語を中心に収束し,新たに拡大に転じることによりFLが収束・発散を描き,その過程で補完による集合知に発展する可能性がある話題展開が発生することが分かった.また,そのプロセスにおいて,ファシリテータがテーマを絞り込むことが重要であることも分かった.
1 0 0 0 昔の労働争議の思い出
1 0 0 0 OA カイコゲノム研究の現状と今後の展開
- 著者
- 山本 公子
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.2_3, pp.2_3_99-2_3_102, 2009 (Released:2016-04-20)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA COVID-19と海洋 ──パンデミックをいかに克服するか
- 著者
- 坂元 茂樹
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.3_48-3_50, 2022-03-01 (Released:2022-07-25)
世界保健機関(WHO)は、2020年1月30日に新型コロナウイルス(COVID-19)を「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」と宣言した。同年2月3日、厚生労働省が、横浜検疫所でクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員全員に対するCOVID-19に関するPCR検査を行ったところ、712名の陽性者が判明した。 ダイヤモンド・プリンセス号の旗国は英国、運航国は米国、寄港国は日本であるが、クルーズ船内で発生した感染症について、旗国、運航国および寄港国のいずれの国が感染拡大防止の第一次的責任を負うのか、国連海洋法条約には直接的な規定はなく、国際法上明確な規則はない。さらに、COVID-19のパンデミックにより、交代のための船員の乗船または下船を阻止し、入港拒否を行う国が続出した。 WHOの特別総会は、2021年12月、パンデミックの防止、準備、および対応に関する歴史的合意(パンデミックに関する国際条約)に向けたプロセスを進めることにコンセンサスで合意した。
1 0 0 0 OA インフォメーションハイディング:2.画像を用いたステガノグラフィ
1 0 0 0 OA 視点移動映像視聴時の注視と予告の酔いと速度感および注視行動への影響
- 著者
- 磯部 祐輔 藤田 欣也
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.385-391, 2008-09-30 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
The influences of visual target and predictive visual cue on gaze behavior and cybersickness were experimentally evaluated, in order to maintain the presence and reduce the cybersickness. The severity of sickness and the sense of velocity were evaluated using simulator sickness questionnaire and method of reproduction. The eye movement was also monitored using an eye tracking camera. The results suggested that the visual target at the optical flow center has more cybersickness reduction effect than the fixed visual target, and the predictive visual cue increases the reduction effect of the target further, while the sense of velocity does not significantly differs among the visual conditions. The feasibility was suggested that presenting predictive visual cue via visual target can reduce cybersickness without impairing sense of velocity.
1 0 0 0 OA 第三者の視点取得が社会的比較過程に与える影響
- 著者
- 大久保 暢俊
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.333-338, 2010 (Released:2011-04-20)
- 参考文献数
- 25
This study examined the effects of attention by a third party to a comparison target on self-evaluation in social comparison. University students (N=114; 42 males and 72 females) were randomly assigned to comparison-target (superior, inferior) and perspective-taking (perspective taking of a third party, non-perspective taking) conditions. First, participants completed a linguistic performance test and were given feedback on their results. Next, participants were asked to look at another's score (either high or low) from the viewpoint of a friend, or from their own viewpoint. Finally, participants rated their own test performance. In social comparison research, a contrast effect is said to occur when self-evaluation is displaced away from the evaluation of the comparison target. The results indicated that undergraduate females who saw the other's score from the viewpoint of a friend had a contrast effect in their self-ratings. Conversely, undergraduate males who saw the other's score from their own viewpoint showed a contrast effect in their self-ratings. The results suggest that social comparison depends on the attention of a third party and that there are gender differences in the direction of this influence.
- 著者
- 玄場公規 新井卓二 小野恭義著
- 出版者
- 同友館
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 OA 鎌倉御家人 -とくに「文士」について-(2)
- 著者
- 北爪 真佐夫 Masao KITAZUME
- 雑誌
- 札幌学院大学人文学会紀要 = Journal of the Society of Humanities (ISSN:09163166)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.41-72, 2000-03-25
本稿は「鎌倉御家人-とくに文士について-(1)」の続編である。鎌倉御家人を大別すれば「武士」と「文士」に分けられる。文士は員数が少ないため一括して扱われる場合が多いが, 彼等は王朝国家体制下で下級官人として職務を担当するかそうした職掌を担当する家柄に出自をもつものなのである。彼等は鎌倉幕府の成立にあたり, その傘下に加わって政所, 問注所, 侍所などの職員に就任し, 中期以降ではその子孫は評定衆, 引付衆, あるいは法曹官僚として裁判などにたずさわっているのである。このような仕事は「武士」ではよく果たし得ないものであって, 彼等によって王朝国家体制下の遺産が「武士の世界」に持ちこまれ, ひいては幕府の性格をも規定するような役割を果たしたのである。本稿では「文士」につづけて「雑色」にも注目して, そうした視座から幕府の性格を検討しようとしたものである。
1 0 0 0 Poiret
1 0 0 0 OA <土着性>と<都市性> : アドルノによるハイデガー批判の考察
- 著者
- 田路 青浩
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.524, pp.319-325, 1999-10-30 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 7
Adomo criticizes Heidegger's thought of "rootedness" in The Jargon of Authenticity. The purpose of this paper is to define the concepts of "rootedness" and "urbanity" that are important to consider the design of 20th century architecture, by considering Adomo's criticism. According to Heidegger, "rootedness" is to ground variable "history" on constant "nature". But Adomo insists that both "nature" and "history" always change and Heidegger's "rootedness" isn't truth. He calls such changeability "urbanity". We may, therefore, conclude that "rootedness" and "hometown" are ideal to look for incessantly.
1 0 0 0 OA 古墳時代像再構築のための考察 : 前方後円墳時代は律令国家の前史か
- 著者
- 広瀬 和雄
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.150, pp.33-147, 2009-03-31
西日本各地の首長同盟が急速に東日本各地へも拡大し,やがて大王を中心とした畿内有力首長層は,各地の「反乱」を制圧しながら強大化し,中央集権化への歩みをはじめる。地方首長層はかつての同盟から服属へと隷属の途をたどって,律令国家へと社会は発展していく,というのが古墳時代にたいする一般的な理解である。そこには,古墳時代は律令国家の前史で古代国家の形成過程にすぎない,古墳時代が順調に発展して律令国家が成立した,というような通説が根底に横たわっている。さらには律令国家の時代が文明で,古墳時代は未熟な政治システムの社会である,といった<未開―文明史観>的な歴史観が強力に作用している。北海道・北東北と沖縄諸島を除いた日本列島では,3世紀中ごろから7世紀初めごろに約5200基の前方後円(方)墳が造営された。墳長超200mの前方後円墳32/35基,超100mの前方後円(方)墳140/302基が,畿内地域に集中していた。そこには中央―地方の関係があったが,その政治秩序は首長と首長の人的な結合で維持されていた。いっぽう,『記紀』が表す国造・ミヤケ・部民の地方統治システムも,中央と地方の人的関係にもとづく政治制度だった。つまり,複数の畿内有力首長が,各々中小首長層を統率して中央政権を共同統治した<人的統治システム>の古墳時代と,国家的土地所有にもとづく<領域的統治システム>を理念とした律令国家の統治原理は異質であった。律令国家の正統性を著した『日本書紀』の体系的な叙述と,考古学・古代史研究者を規制してきた発展史観から,みずからの観念を解き放たねばならない。そして,膨大な考古資料をもとに,墳墓に政治が表象された古墳時代の350年間を,一個のまとまった時代として,先見主義に陥らずにその特質を解明していかねばならない。
1 0 0 0 OA Agingの社会心理学的考察
- 著者
- 渋谷 昌三
- 出版者
- 山梨医科大学
- 雑誌
- 山梨医科大学紀要 = 山梨医科大学紀要 (ISSN:09105069)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.87-96, 1998
本論文ではaging に関する展望を試みた。aging についての社会心理学的な問題点を次の観点から考察した。(1) 老人イメージの歴史的な変遷とaging への適応,(2) 高齢者の孤独感と幸福感,(3) 結婚生活の変化の問題,(4) aging と性格特性との関係。本論文でとりあげたaging に関する論文からaging についての問題提起をすることができた。
1 0 0 0 OA ジャンケン遊びにおける三すくみとシンボル
- 著者
- 杉谷 修一
- 出版者
- 西南女学院大学
- 雑誌
- 西南女学院大学紀要 = Bulletin of Seinan Jo Gakuin University (ISSN:13426354)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.51-60, 2012-03-01
1 0 0 0 OA 保健学から見た顎骨の縮小変化
- 著者
- 井上 直彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.2, pp.105-119, 1999 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 93