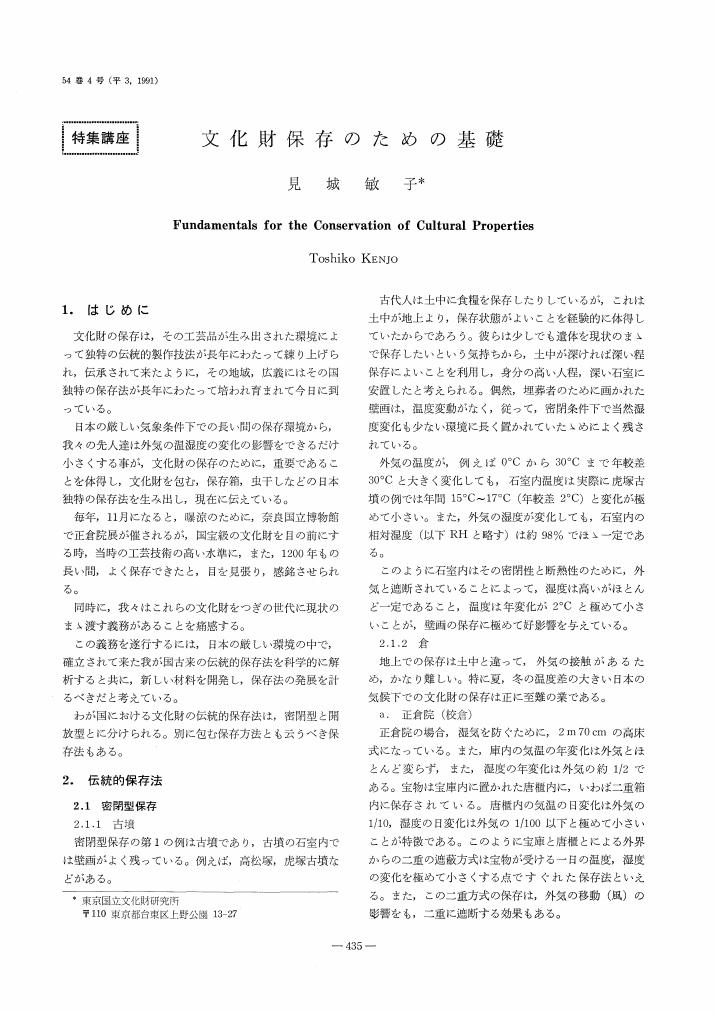1 0 0 0 OA 学習者の素朴理論の転換をはかる社会科授業の構成について 「山小屋の缶ジュースはなぜ高い」
- 著者
- 栗原 久
- 出版者
- 日本社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.102, pp.62-74, 2007 (Released:2016-12-01)
1 0 0 0 OA 韓国キリスト教の日本宣教―在日大韓基督教会と韓国系キリスト教会群の連続性―
- 著者
- 中西 尋子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.33-41, 2016-06-11 (Released:2018-07-20)
- 参考文献数
- 24
1 0 0 0 OA 宮古島狩俣の「ニーラアーグ」をめぐって
- 著者
- 上原 孝三
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 沖縄文化研究 (ISSN:13494015)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.187-208, 2015-03-31
1 0 0 0 帝国美術院美術展覧会図録
1 0 0 0 OA 運動誘発性喘息
- 著者
- 藤本 繁夫 田中 繁宏
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.453-459, 1998-08-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2 1
1 0 0 0 ブレーン = Brain
- 出版者
- 宣伝会議
- 巻号頁・発行日
- vol.30(1), no.354, 1990-01
1 0 0 0 OA 河川空間の活用をめぐる経緯と現状
- 著者
- 塚田洋
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.859, 2022-07
1 0 0 0 OA 文化財保存のための基礎
- 著者
- 見城 敏子
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.435-439, 1991-08-28 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 児童虐待は犯罪現象か福祉課題か? —大学生ならびに専門職の心的表象—
- 著者
- 緒方 康介 籔内 秀樹 反中 亜弓 吉田 花恵
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.31-42, 2022-01-31 (Released:2022-02-21)
- 参考文献数
- 17
The purpose of this study was to examine mental representations with respect to child abuse and neglect. In particular, we focused on whether child maltreatment is more strongly associated with being a crime or a welfare issue. Study I included 220 university students and 44 correctional experts. They were made to rate the extent to which five practical psychologies were related to five child clinical issues. Multi-dimensional scaling (MDS) showed that (1) child maltreatment posited between Psychology for Human Services (PHS) and Forensic and Criminal Psychology (FCP) in university students, and (2) child abuse and neglect was close to PHS in correctional experts. Study II consisted of 46 university students who were measured twice, before and after a lecture regarding child abuse and neglect. Individual analysis of the MDS results revealed that knowledge about child maltreatment could make PHS closer to but remain the closest between FCP and child abuse and neglect. Study III included 197 university students who were required to select the better procedure (social welfare or forensic) for maltreated children. We found that they reported significantly more of the former than the latter and concluded that university students have a mental representation of child abuse and neglect being a crime, not a welfare issue.
- 著者
- 田宮 寛己
- 出版者
- 不明
- 雑誌
- 日本教育社会学会大会発表要旨集録
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.37-38, 1967
- 著者
- 田宮,寛己
- 出版者
- 不明
- 雑誌
- 日本教育社会学会大会発表要旨集録
- 巻号頁・発行日
- no.20, 1967-10-05
1 0 0 0 OA メニエール氏病患者の自律神経機能状態に関する研究
- 著者
- 日前 健介
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.Supplement3, pp.254-282, 1960-03-01 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 99
The author studied statically and dynamically, the general functional status of the autonomic nerve in patients of Ménière's disease in the intermittent period of the attacks of vertigo and further the etiopathogensis of the disease.(A) The functional status of the automonic nerve in the statical condition of patients of Ménière's disease when they are not stressed.1) The psychosomatic studies on Ménière's disease.The functional status of the autonomic nerve has a close relation to the individual character and mental condition, and further the existence of the autonomic center in the lymbic system of the cerebral cortex has been made clear in recent years. The author investigated the psychosomatic aspects of Ménière's disease in 214 items, and compared them with the controls using the Cornell Medical Index Health Questionnare (CMI) which was made by K. Brodman and the clinical reliability of which was ensured by K. Fukamachi (Table 2, 3. Fig. 2, 3).i) Significant differences between the Ménière and the control groups were revealed by the following questions. In Ménière's disease, the following complaints due to the autonomic imbalance were observed: pressure or pain in the head, stiffness in the shoulders or the neck, thumping of the heart, cold hands or feet even in hot weather, stubborn coughs following colds, liability to severe colds. From this it is conseivable that these might become one of the etiologic factors of Ménière's disease in the middle ear. Besides, the patients of Ménière's disease have suffered from liver or gall bladder trouble oftener than the controls. This confirmed the report of K. Kubo that the functional disorder of the liver would become one of the predispositions of the nerve deafness.ii) The discriminative chart by Fukamachi (Fig. 1) made by the statistical method was used to classify patients of Ménière's disease into four groups; normal, provisionally normal, provisionally neurotic and neurotic. The percentage of each type showed the similar ratio to the other psychosomatic diseases such as bronchial asthma and essential hypertension. Ménière's disease lay between neurosis and the normal.(Table 3. Fig. 3)iii) From above facts, it was made clear that Ménière's disease was a psychosomatic disease, and the author concluded that the therapy of Ménière's disease required not only the somatic but psychic consideration with reference to the judgment of the discriminative chart.2) The measurement of the activity of serum cholinesterase.In five cases out of twelve, the fall of the activity of serum cholinesterase was observed, and it showed that it would mean parasympathetic predominance.3) The measurement of electrolytes in the serum (Na, K, Ca).The results with 18 patients of Ménière's disease in the intermittent period of the attacks of vertigo were in the normal range.4) The measurement of 17-Ketosteroid (17-KS) in the urine was made considering the part played by the adrenocortical hormones in the defense mechanism of the living body.The fall of 17-Ketosteroid in the urine was observed in five cases out of ten, and one feature of Ménière's disease as an adaptation disease was confirmed and an intimate interrelation of the neuro-hormones was suggested. The fact that the fall of 17-KS was rare in males as compared with females seems to be due to the possibility of 17-KS secreted from the testicles in males having masked the deficiency of the 17-KS from the adrenal glands.5) The measurement of the functional status of the autonomic nerve by Wenger's method.The measurement was undertaken about the following seven articles.
1 0 0 0 OA 幕末維新外交史料集成
- 著者
- 原秀穂 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 OA 行動問題を示す自閉症児へのトークン・エコノミー法を用いた課題従事に対する支援
- 著者
- 小笠原 恵 広野 みゆき 加藤 慎吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.41-49, 2013 (Released:2015-02-18)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 5 2
本研究では、行動問題を示すことによって授業における課題従事が困難になっている自閉症児1名に対して、トークン・エコノミー法を用いて課題従事を支援し、その効果を課題従事の促進および行動問題の低減から検討することを目的とした。支援開始前、授業中の本児の要求が拒否された場合に行動問題が生起し、課題従事をせずにその場から離されるという随伴性が成立していた。本研究では、この行動問題が生起する環境に、トークン・エコノミー法を用いて課題従事すれば本児の要求が満たされるという新たな随伴性を組み込んだ。その結果、課題の従事率は80%を超えた。しかし、行動問題は半減するにとどまった。これらの結果より、本研究で用いたトークン・エコノミー法は課題従事を促進することと、一部の行動問題の低減に有効であることが示唆された。また、残存する行動問題について、経時的にその機能を分析する必要性が課題として残された。
1 0 0 0 OA 母趾外反角軽減シューズが外反母趾女性の歩行に及ぼす効果
- 著者
- 村田 伸 安彦 鉄平 中野 英樹 阪本 昌志 鈴木 景太 川口 道生 松尾 大
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.151-156, 2022-02-28 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 16
本研究の目的は,母趾外反角(hallux valgus;HV 角)軽減シューズが外反母趾女性の歩行に及ぼす効果を検証することである。外反母趾のある女性12名(平均年齢24.8±11.5歳)を対象に,HV 角軽減シューズと外見が同じコントロールシューズを履いた際の歩行パラメータを比較した。その結果,HV 角軽減シューズを履いて歩くと,歩幅が有意(p<0.05)に広がり,両脚支持時間は有意(p<0.05)に短縮して,歩行速度が有意(p <0.05)に速まった。一方,歩隔,足角,歩行角,立脚時間,遊脚時間の5項目には有意差は認められなかった。有意差が認められた歩幅,両脚支持時間,歩行速度の効果量はΔ=|0.46|~|0.60|の範囲にあり,HV 角軽減シューズが外反母趾女性の歩行に及ぼす一定の効果が示唆された。
1 0 0 0 OA 仙台市の盛土造成地において発生した地すべり的変形の再現解析及び要因検討
- 著者
- 門田 浩一 本橋 あずさ 佐藤 真吾 三嶋 昭二
- 出版者
- 公益社団法人 地盤工学会
- 雑誌
- 地盤工学ジャーナル (ISSN:18806341)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.253-271, 2019-08-31 (Released:2019-10-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
東北地方太平洋沖地震では,仙台市の盛土造成地において,多数の地すべり的変形被害が発生した。この被害は細粒分を多く混入する液状化が生じにくい盛土で発生しており,液状化に起因する盛土の変形被害とは異なる現象であった。本研究では,地すべり的変形が発生した盛土を対象として,変動部における物理・力学特性及び地下水特性を分析すると伴に,動的有効応力解析法等による再現解析を行い,その発生要因と機構について検討した。その結果,液状化が生じにくい盛土であっても,盛土内の締固め度89%以下の飽和部及び不飽和部(飽和度80%以上)では,大規模地震による繰返し載荷を受けると間隙水圧が上昇し,塑性変形が発生することを示した。また,繰返し載荷により上昇する過剰間隙水圧比は,盛土の静的な三軸圧縮試験結果より得られるせん断破壊時の過剰間隙水圧比と,同程度であることを示した。
1 0 0 0 OA 東日本大震災による宮城県内の宅地造成地被災事例
- 著者
- 清田 隆 京川 裕之
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.709-715, 2011 (Released:2011-12-27)
- 参考文献数
- 2
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(Mw 9.0)による東日本大震災では,宅地造成地において地震動による地盤の変状が多数発生し,人命・家屋に損害を与えた.いずれの造成地でも谷埋め盛土が行われた箇所に被害が集中する傾向にあった.ここでは,比較的被害の大きかった宮城県内の造成地の被害事例を報告する.また,1978年宮城県沖地震後に施工された対策工の効果についても言及する.[本要旨はPDFには含まれない]
1 0 0 0 OA 2011年東北地方太平洋沖地震で発生した造成地盤地すべりにおける変動量観測
- 著者
- 釜井 俊孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.282-291, 2013-02-10 (Released:2014-02-28)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 4
2011年東北地方太平洋沖地震によって,仙台市緑ヶ丘4丁目では造成地盤地すべりが発生した.ここでは,約1年間にわたる地すべり変動(地表傾斜,地中傾斜),地表地震動,間隙水圧の精密動的観測結果を報告する.この斜面では,本震から10~11か月後まで,地山を巻き込む重力性の斜面変動が継続した.しかし,地中傾斜は盛土下底のすべり層で最大であり,盛土全体の地すべりが,今回の斜面変動の主体である.地中傾斜の地震応答は,すべり層や亜炭層など地盤内の弱層で最大となり,それよりも上部の盛土では増幅率が小さくなる傾向が認められた.この弱層による免震効果は,弱層の層厚や地震の震央距離によって異なり,地すべりの構造が,地震応答に強く影響を及ぼしている.過剰間隙水圧は最大水平地動速度にほぼ比例して増加した.この関係から,80 cm/sを越える強震動によって,過剰間隙水圧の増加によるすべり層強度の喪失が発生し,地すべりに至ったと推定される.また,すべり層における局所破壊が成長し,より規模の大きい地すべり変動に発展する過程が観測された.今回のような精密動的観測は,強震時における地すべりの挙動を知るうえで,基礎的な知見を提供するものとして重要である.