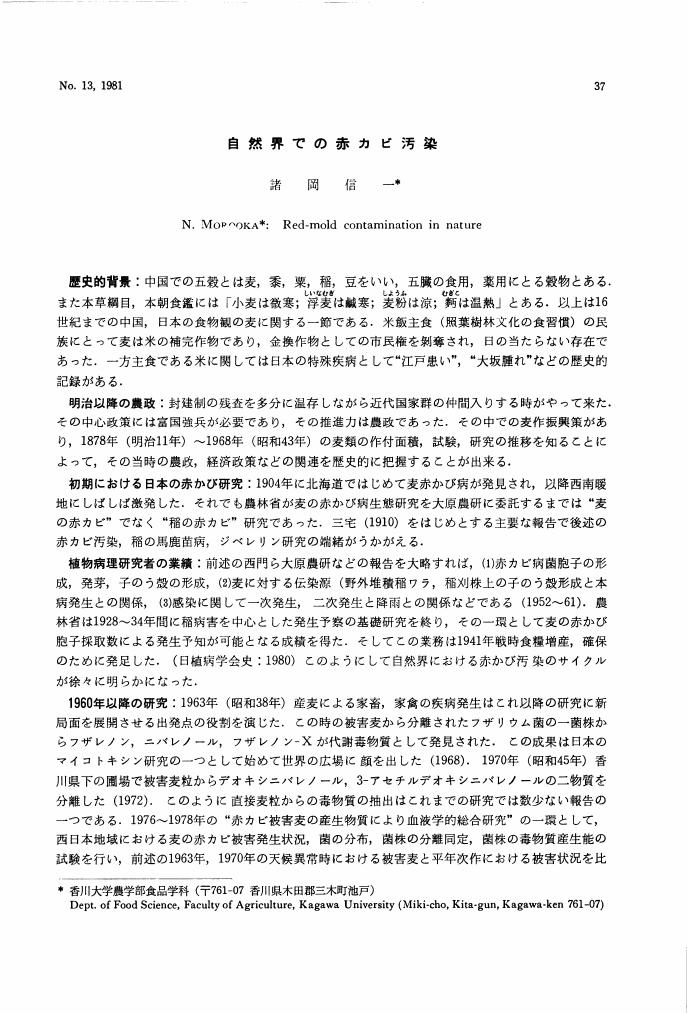1 0 0 0 OA 探究学習としての維管束の観察 ―トルイジンブルー染色を利用した教材開発―
- 著者
- 渡邉 重義
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物教育学会
- 雑誌
- 生物教育 (ISSN:0287119X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1-2, pp.1-12, 2011 (Released:2019-09-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
Under the curriculum of new course of study (2008) the learning on vascular system in junior high school becomes more significant. The students are expected to learn the vascular system through inquiry. For guiding students’ inquiry I investigated the vascular bundle of angiosperm stems using the polychromatic staining method by toluidine blue O and developed some teaching materials and method. The basic investigation on vascular bundle of plants in surroundings showed that the metachromasia of toluidine blue O was observed in the 80 % of 63 angiosperms species. In such species the xylem and the phloem could be differentiated easily by color. The xylem was stained blue or greenish blue while the phloem was stained reddish or bluish purple. Some species such as Lamium amplexicaule, Cyperus cyperoides, Mirabilis jalapa showed the suitable morphological feature of vascular system to study the patterns and diversity of plants. The developed teaching materials and method for inquiry are as follows: (1) Work sheets guiding observation of vascular system stained by toluidine blue O; (2) Photographic plates and information photo cards for comparative observation or the activity of classification of vascular system; (3) Work sheets and photographic plate on vascular system of climbing plants for relating the structure of stem to the adaptation in the environment.
1 0 0 0 OA 高効率熱電発電材料の新展開
- 著者
- 梶川 武信
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) (ISSN:03854205)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.4, pp.303-306, 2004 (Released:2004-07-01)
- 参考文献数
- 12
Recent innovative research and development of high performance thermoelectric materials for power generation in the temperature range from room temperature up to 1300K has been investigated. The concept of guiding principle for the enhancement of thermoelectric performance was briefly summarized including PGEC materials and independent control of the structure and function. In this paper as some of the promising materials, modified Bi-Te system, (filled) Skutterudites, clathrates and layered oxides were discussed.
1 0 0 0 OA 語用論的機能からみた二つの「のだ」
- 著者
- 神田 靖子 Yasuko Kanda
- 出版者
- 同志社大学留学生別科
- 雑誌
- 同志社大学留学生別科紀要 = Bulletin of Center for Japanese Language Doshisha University (ISSN:13469789)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.77-91, 2001-12-25
これまでの研究において「のだ」は「認識モダリティ」を表すという説が一般的であった。しかし,泉子・K・メイナード(2000)は「のだ」には「情意」を表す機能があることを指摘しており,彼女の言う「情意」とはモダリティの側面からいえば「発話・伝達モダリティ」に属するものである。なぜ「のだ」に二つのモダリティが認められるのであろうか。本稿はこのようなモダリティの食い違いは「のだ」に二種の機能があることに原因すると見て,「主観的論理の「のだ」」と「情意の「のだ」」があることを示す。そして,とりわけ後者が話し手の発話伝達における心的態度を直接的に表現するものとして,その語用論的機能を観察する。
1 0 0 0 OA <Research Note>関西弁コーパスの紹介
- 著者
- ヘファナン ケビン Kevin Heffernan
- 雑誌
- 総合政策研究 (ISSN:1341996X)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.157-163, 2012-10-30
1 0 0 0 OA 自然界での赤カビ汚染
- 著者
- 諸岡 信一
- 出版者
- Japanese Society of Mycotoxicology
- 雑誌
- マイコトキシン (ISSN:02851466)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.13, pp.37-38, 1981-12-31 (Released:2009-08-04)
1 0 0 0 OA 大統領制化と政党政治のガバナンス
- 著者
- 岩崎 正洋
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.2_91-2_109, 2014 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 37
In this article, we focus on a relationship between presidentialization and party politics. Especially, we pay attention to the governance of party politics. According to Thomas Poguntke and Paul Webb, phenomenon of presidentialization “denominates a process by which regimes are becoming more presidential in their actual practice without, in most cases, changing their formal structure, that is, their regime type.” They refer to as three faces of presidentialization, that is, (1) the executive face, (2) the party face, and (3) the electoral face. These faces are complementary in the democratic governance. In this paper, the phenomenon of presidentialization means the governance of party politics. There are two types of governance by political parties. One is “governance in the party” and another one is “governance among the parties.” It is useful for us to understand the changes of party politics by using the concepts of “governance in the party” and “governance among the parties.”
1 0 0 0 OA 前庭障害が頸部前屈に対する動脈圧応答に及ぼす影響
- 著者
- 松尾 聡 中村 陽祐 松尾 紀子 竹内 裕美
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.57-62, 2021-03-20 (Released:2022-03-20)
- 参考文献数
- 12
頭部低位に体位変換(Head-down tilt:HDT)すると、交感神経活動が抑制され一過性に血圧が低下する。この血圧応答は、HDT による体液の頭方移動で圧受容器が賦活された結果生じたと考えられるが、前庭器が関与する可能性がある。そこで頸部前屈により頭位変換し、同様の応答が起こるか麻酔ウサギを用いて調べた。腹臥位、水平位を保ち、45° 頸部を前屈し、頭部を下方に 5 秒かけて頭位変換した。そして 1 分間その姿勢を維持し、動脈圧と腎交感神経の活動を記録した。この頸部前屈刺激によって、交感神経活動が抑制され一過性に動脈圧が低下した。動脈圧低下応答は自律神経節遮断薬であるヘキサメソニウムの投与で消失し、両側前庭障害群で著明に減弱した。これらの結果は、HDT や頸部前屈によって左右を軸に頭部を下方に頭位変換する前庭刺激が、交感神経抑制を介し動脈圧を低下させることを示唆している。
1 0 0 0 OA パキスタン・パンジャブ地方のフッ素・ヒ素複合汚染地下水拡大の規制要因
- 著者
- 益田 晴恵 三田村 宗樹 ファルーキ アビダ
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集 2007年度日本地球化学会第54回年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.71, 2007 (Released:2008-01-18)
パキスタン・パンジャブ地方には,高濃度のフッ素とヒ素の汚染地下水に伴う健康被害が知られている。これらの汚染物質の移動には,硫酸イオン・リン酸イオンを伴うことがある。また,土壌からはトリフルオロ酢酸が抽出された。これらの観察事実から,フッ素の原因物質は肥料>工場排水>大気汚染物質であり,ヒ素の汚染物質は大気汚染物質>工場排水>肥料(農薬)であると推定された。地下水浸透に伴って,汚染物質は被圧帯水層へ移動する。このとき,帯水層下部の形状が汚染の拡大にとって本質的な役割を担っている。すなわち,帯水層下部の傾斜に沿って埋没河川に流入し,この埋没河川に沿って汚染物質は水平移動する。
- 著者
- 上橋 俊介 西本 浩 富塚 浩志 佐野 裕康 半谷 政毅
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-B, no.5, pp.446-453, 2022-05-01
フェージングによる信号強度低下を簡易な処理で軽減できる技術として,差動時空間ブロック符号化(DSTBC)伝送が検討されている.また,高い周波数利用効率を得るため,セル間で同一の周波数を用いる単一周波数繰り返しは,主にセル境界での同一チャネル干渉(CCI)が課題となる.一般に移動局では設置スペースなどの制約で多くのアンテナを搭載することは困難であり,送信側で複数アンテナを用いるDSTBC伝送ではより多くのCCIが観測される.このような環境では,従来のアレー信号処理による干渉抑圧では劣決定問題となるために十分な受信性能が得られない可能性がある.本論文では,少ない受信アンテナ数の条件においても動作可能なDSTBC伝送向けのCCI抑圧方式を示し,更に多数の干渉波が到来する複局同時送信システムへの拡張法も示す.計算機シミュレーションにより複局同時送信システムにおけるセル境界付近での干渉抑圧性能を評価し,受信アンテナ数の2倍を超える干渉波が到来する環境においてもチャネル行列の拡張,合成処理を行うことで決定問題に帰着させ,適切に干渉を抑圧可能であることを示す.
1 0 0 0 OA 醸造業の後継者育成に取り組む「新潟県立吉川高等学校醸造科」の概要
- 著者
- 新潟県立吉川高等学校醸造科
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.5, pp.306-309, 1997-05-15 (Released:2011-09-20)
新潟県の吉川高校には全国唯一の醸造科があり, その卒業生が関係分野で活躍している。この伝統あるユニークな醸造科の教育の現状及び最近の社会変化に応じた新しい取組等について, 紹介いただいた。
1 0 0 0 OA 卒業会員氏名録
- 出版者
- 東京外国語学校校友会
- 巻号頁・発行日
- 1910
1 0 0 0 OA 汎用・専用技術の相互浸透 ――インターフェイス知識の蓄積――
- 著者
- 原田 勉
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.93-111, 1998 (Released:2022-07-22)
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は,日本工作機械産業における技術革新のプロセスについて汎用・専用技術の相互転換プロセスという独自の概念によって分析し,その背後にある学習メカニズムについて明らかにすることにある.われわれは,汎用・専用技術の相互転換プロセスは両技術の相互浸透したインターフェイス知識の増大を伴うということを議論する.インターフェイス知識は,汎用・専用技術の相互転換プロセスを助長する機能をもっており,技術革新を推進していく上で極めて重要な役割を担っている.このようなインターフェイス知識をいかに効率的に蓄積していくかが今後の工作機械産業のみならず技術融合が進むハイテク産業においても重要な課題となることを議論する.
1 0 0 0 OA 意思決定原理と日本企業
- 著者
- 高橋 伸夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.14-27, 1998 (Released:2022-07-22)
- 被引用文献数
- 5
日本企業で見られる意思決定の多くは,ゲーム理論や決定理論から見ると一見不合理なものに感じられるが,実は「未来の重さ」によって導かれた合理的なものである.非ゼロ和の世界では均衡も安定ももはや説得的ではなく,これらに代わって経営の現場で実際の行動に意味を与え続けてきたのが「未来の重さ」である.単に概念としてではなく,実際に手応え,やりがい,生きがいとなって,われわれの日常感覚の基礎をなしてきている.
1 0 0 0 OA プラットフォーム型経営戦略と協働の未来形
- 著者
- 國領 二郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.4-13, 1998 (Released:2022-07-22)
情報・通信産業などにおいて,商品供給連鎖を構成する諸階層のうちで,自社の提供する階層を絞る一方で,自分がコミットする階層についてはより多くの地域で高いシェアをとろうとするプラットフォーム型の経営戦略が一般的になりつつある.プラットフォーム型経営戦略がただちに全ての産業に広がることは考えられないが,このトレンドは知識経済化の現われであると認識され,今後広がることが予想される.プラットフォーム型経営戦略は短期的には従来の日本の組織の強みを否定するが,情報技術を組織構成員間の文脈共有の道具として活用していくことに成功すれば,日本の組織の強みを強化するものともなりうる.
1 0 0 0 OA 個人決定と合議決定の乖離に関する動態的分析
- 著者
- 長瀬 勝彦
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.60-78, 1997 (Released:2022-07-22)
この報告の目的は,競争的状況下におけるリスクを含む連続意思決定について,合議決定と個人決定を動態的に比較分析することにある.被験者212名を対象にした実験の結果,いくつかの事実発見があった.強気の意思決定が高いパフォーマンスをもたらすポジティブ・フィードバックが続くと,個人群よりも2人合議群,4人合議群と人数が多い方がよりリスク・シーキングな意思決定を下すようになった.また,弱気の意思決定が高いパフォーマンスにつながるネガティプ・フィードバックが与えられると,逆に人数が多いほどリスク・アバースに振れた.全体的に,環境からのフィードバックに対しては個人よりも小集団合議のほうが敏感に反応し,またその反応は単純であると考えられる.この結果は,選択シフト,プロスペクト理論,エスカレーティング・コミットメント,組織の慣性等の諸理論に新しい論点を提供する可能性がある.
1 0 0 0 OA 日米半導体産業における制度と企業戦略 ――資源投入の2極分化の可能性について――
- 著者
- 輕部 大
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.85-98, 1997 (Released:2022-07-22)
- 被引用文献数
- 1
半導体プロセス技術における日米の支配的な企業戦略の違いに注目して,両国の資源投入パターンの違いを明らかにする.その上で,資源投入パターンの相違が生み出される原因を,外部事業化の可能性の違いという経済制度的要因に求め,その要因が企業戦略に与える影響を考察する.最後に,外部事業化の可能性が高い米国型システム下では,資源投入の2極分化が起きやすくなる,という論理的な可能性を仮説として提示する.
1 0 0 0 OA 組織のエージェンシー・モデル ――集団ネットワークの視点――
- 著者
- 伊藤 秀史
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.51-59, 1997 (Released:2022-07-22)
- 被引用文献数
- 1
本論文で紹介される組織の分析視座は,次の3つの要素からなる.(1)ゲーム理論の人間観.(2)階層組織のエージェンシー・モデル.(3)集団ネットワークとしての組織とりわけ,組織のメンバーが集団を形成し集団として行動する可能性を,元来個人主義的な人間観に立脚したエージェンシー・モデルに導入し,組織を個人間の相互作用と集団のネットワークを規定する全体的ルール設計の問題として捉える見方を強調する.
1 0 0 0 OA 組織において「自由なコミュニケーション」がもつ意味 ――情報と認知のマネジメント――
- 著者
- 福留 恵子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.37-50, 1997 (Released:2022-07-22)
組織成員間の自由なコミュニケーションは,組織の活力や創発,成員の満足などとの関係からその重要性が注目されているが,現場におけるその実現や維持は決して容易ではない.本論文ではグループウェア等情報通信技術の利用現場の経験から,自由なコミュニケーションの実現・維持の試みが自由と制約の循環に陥りがちであること,さらにルーマンらの議論を参考に,それが実は(近代組織にとって)原理的・必然的な事態であることを示す.その上で,この困難を解消して自由なコミュニケーションを導入するためのマネジメントのデザインを考察する.
1 0 0 0 OA プロジェクト知識のマネジメント
- 著者
- 青島 矢一 延岡 健太郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.20-36, 1997 (Released:2022-07-22)
- 被引用文献数
- 17
競争環境が厳しくなる中,短いリードタイムで連続的に製品を導入していくことがますます重要になってきている.しかし,個々の新製品開発プロジェクトで創造される「プロジェク卜知識」を,他のプロジェクトヘと効果的に移転・伝承する体系的なメカニズムをもつ企業は必ずしも多くない.それは,プロジェクト知識が開発の過程やシステムに関係する暗黙知的要素を多く含むがゆえのマネジメントの難しさを反映している.本論文は,プロジェクト知識を効果的に移転・蓄積する方法として人的移転型プロジェクト連鎖と時間的オーバーラップ型プロジェクト連鎖の2つの方法を議論する.プロジェクト間の直接連鎖に関するこうした議論は従来の新製品開発組織論に新しい視点を提供する.