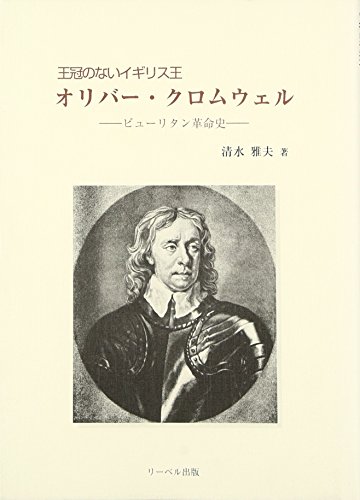1 0 0 0 OA ベトナムの伝統的私塾に関する研究のための予備的報告
- 著者
- 嶋尾 稔
- 出版者
- 関西大学文化交渉学教育研究拠点(ICIS)
- 雑誌
- 東アジア文化交渉研究 別冊 = Journal of East Asian cultural interaction studies (ISSN:18827756)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.53-66, 2008-06-30
1 0 0 0 IR 韓国の書院建築 : 儒教・風水思想と自然に基づく空間理念
- 著者
- 松下 慧南
- 出版者
- 法政大学大学院デザイン工学研究科
- 雑誌
- 法政大学大学院紀要. デザイン工学研究科編 = 法政大学大学院紀要. デザイン工学研究科編 (ISSN:21867240)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.1-8, 2015-03-31
Charm of Shoin architecture in Korea is not only educational institutions of mere provinces. It was felt strongly when I visited for the first time Shoin architecture. Mountains towering behind the Shoin architecture, gently wrap us. River slowly flow, seems time has stopped. Its strange feeling, can not forget even now. By Feng Shui philosophy, humans and nature have to realize the harmony while keeping a good distance. In this paper it is in the background of the Shoin architecture, Feng Shui philosophy, and Confucianism, while considering the overwhelming nature and human relationships that exist in the underlying, I want to unravel the space philosophy of Shoin architecture.
1 0 0 0 OA 全国汽車汽船発着時間及賃金表
1 0 0 0 OA 低融点はんだ適用のためのBi-In-Sn合金の特性評価
- 著者
- 近藤 未希 赤田 裕亮 廣瀬 明夫 小林 紘二郎
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会全国大会講演概要 平成18年度秋季全国大会
- 巻号頁・発行日
- pp.207, 2006 (Released:2006-11-09)
非耐熱部品の一括実装を実現するためには、実装温度100℃以下の低融点はんだの開発が必要である。本研究では、Bi-In-Sn合金に着目し、溶融特性、濡れ性、機械的特性、継手強度の観点から、低融点はんだとして適用可能な合金組成の検討を行った。
- 著者
- Ayako Nakamura-Ishizu Fumio Nakamura
- 出版者
- Society of Tokyo Women's Medical University
- 雑誌
- Tokyo Women's Medical University Journal (ISSN:24326186)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021003, (Released:2021-07-12)
- 参考文献数
- 58
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has a wide range of clinical manifestations, including acute respiratory distress syndrome, severe inflammation, abnormal blood coagulation, and cytokine storm syndrome. SARS-CoV-2 uniquely facilitates its entry and expansion in host cells through the spike protein consisting of S1 (receptor binding domain) and S2 (fusion peptide domain). The S1 binds to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), the host cell receptor. The cleavage at the boundary of S1 and S2 by Furin protease and subsequent digestion within the S2 by TMPRSS2 activate the S2 fusion peptides, which are necessary for the entry of SARS-CoV-2 into host cells. After infection, SARS-CoV-2 RNA genome encodes viral proteins including structural proteins, RNA polymerases/helicases, and modulators of host- defense system, which inhibit type I interferon-related immune signaling and signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) signaling. In contrast, SARS-CoV-2 infection activates the proinflammatory cytokines, such as interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor α (TNFα). In severe cases of COVID-19, these alterations in immune signaling may induce a state of systemic immune dysfunction. Recent studies also revealed the involvement of hematopoietic cells and alteration of cellular metabolic state in COVID-19. We here review the pathogenesis of COVID-19, primarily focusing on the molecular mechanism underlying SARS-CoV-2 infection and the resulting immunological and hematological alterations.
1 0 0 0 IR テーマ化される観光とまちづくり
- 著者
- 高山 啓子
- 出版者
- 川村学園女子大学図書委員会
- 雑誌
- 川村学園女子大学研究紀要 (ISSN:09186050)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.55-65, 2014
1 0 0 0 社会のディズニー化と大学教育とホスピタリティ
- 著者
- 土井 文博
- 出版者
- 熊本学園大学付属産業経営研究所
- 雑誌
- 産業経営研究 (ISSN:02887371)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.27-45, 2012-03
1 0 0 0 OA テーマ化される観光とまちづくり
- 著者
- 高山 啓子
- 出版者
- 川村学園女子大学図書委員会
- 雑誌
- 川村学園女子大学研究紀要 (ISSN:09186050)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.55-65, 2014
1 0 0 0 IR 有効需要の貨幣的理論--J.A.クリ-ゲルの所説によせて
- 著者
- 原 正彦
- 出版者
- 明治大學商學研究所
- 雑誌
- 明大商学論叢 (ISSN:03895955)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.p1-27, 1987-12
1 0 0 0 IR ケインズ「有効需要の原理」再考
- 著者
- 美濃口 武雄
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 一橋論叢 (ISSN:00182818)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.6, pp.747-762, 1999-06
論文タイプ||論説(経済学部号 = Economics)
1 0 0 0 IR アンドレ・パケ「販路法則と有効需要原理の歴史的論争」
- 著者
- 地主 重美
- 出版者
- 小樽商科大学
- 雑誌
- 商學討究 (ISSN:04748638)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, 1955-06
紹介
1 0 0 0 OA 雷雲下の風力発電施設からの前兆電波を利用した被雷回数の大幅低減手法の開発
1 0 0 0 OA 近世日本における<現世主義>の成立
- 著者
- 阿満 利麿
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.55-67, 1993-09-30
死後の世界や生まれる以前の世界など<他界>に関心を払わず、もっぱら現世の人事に関心を集中する<現世主義>は、日本の場合、一六世紀後半から顕著となってくる。その背景には、新田開発による生産力の増強といった経済的要因があげられることがおおいが、この論文では、いくつかの思想史的要因が重要な役割を果たしていることを強調する。
1 0 0 0 OA 幼児の音楽表現における付点8分音符+16分音符のリズム
- 著者
- 西澤 志穂
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.319-342, 2017
- 著者
- 溝渕 佳史 永廣 信治 荻野 雅宏 McCrory Paul スポーツ頭部外傷検討委員会(日本脳神経外傷学会)
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳神経外傷学会
- 雑誌
- 神経外傷 (ISSN:03895610)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-26, 2016
<p>【 解 説 】 「スポーツにおける脳振盪に関する国際会議」 はおよそ4年に一度開催される。2001年にウィーンで第1回会議が開かれ,第2回 (プラハ,2004年),第3回 (チューリッヒ,2008年) を経て,2012年には再びチューリッヒにて 「第4回国際スポーツ脳振盪会議」 が開催された。この4回にわたる国際会議の目的は,選手の安全確保と健康改善であり,プロフェッショナル,アマチュアを問わず,スポーツで脳振盪を負った選手の状態を正しく評価し,安全にスポーツに復帰させることを目指すものである。さまざまな分野のエキスパートが討論を重ねて 「共同声明 (consensus statement)」 を発表する一方,脳振盪を負った選手の臨床所見を競技場内外で明らかにする評価ツール 「Sport Concussion Assessment Tool (SCAT)」 が作成された。</p><p>SCAT2からSCAT3への改訂にあたって変更されたのは,重症な状態を早期に評価できるようにしたことである。はじめに救急対応を取るべき状態 (Glasgow Coma Scaleが15点未満,精神状態の悪化,脊髄損傷の可能性,症状の進行 ・ 悪化あるいは新たな神経症状の出現) が記載された。そのため,SCAT2では3番目の評価項目であったGlasgow Coma Scaleが1番目に変更され,意識状態の評価を早期に行うことを重視している。さらに5項目目に頚部の評価が加えられ,脊髄損傷などの重症外傷を評価できるよう改訂された。バランステストの項目では,SCAT2ではModified Balance Error Scoring System (BESS) を用いて評価していたが,SCAT3ではBESSとつぎ足歩行の両方か,もしくはどちらか一方を選択できるようになっている。またSCAT2は10歳以上を対象にしていたため,SCAT3では13歳未満の選手用にChild SCAT3が追加された。</p><p>以下は,</p><p>McCrory P. Consensus Statement on Concussion in Sport: The 4th international Conference on Concussion in Sport, Zurich, November 2012. BJSM 47(5): 250-258, 2013.の翻訳である。</p>
1 0 0 0 樹上動物のためのアニマルパスウェイに関する研究と実績
- 著者
- 饗場 葉留果 小林 修 湊 秋作 岩渕 真奈美 大竹 公一 岩本 和明 小田 信治 岡田 美穂 小林 春美 佐藤 良晴 高橋 正敏
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.29, 2013
日本,世界各地には道路や線路で分断されている森が非常に多く,野生動物の移動,繁殖,餌の確保等が困難になっている.そのため我々の研究グループは 1998年から森を分断する道路上に樹上動物が利用できるための橋を研究し,建築してきた.これまでに山梨県に 3ヶ所,栃木県に 1ヶ所,愛知県に 1ヶ所建設された.<br> 1998年,山梨県の有料道路上に道路標識を兼ねたヤマネブリッジの建設を提案し,実現させた.建設後,ヤマネを初め,リス,ヒメネズミ,シジュウカラの利用が確認された.建設費用は約 2000万円であった.<br> しかし,2000万円という高額なものでは,この技術を「一般化」し,普及していくことが難しい.そこでより安く,簡易な設計にし,建設できる樹上動物が利用しやすい「アニマルパスウェイ」(以下,パスウェイ)の開発研究を 2004年から行った.2004年の材料研究,2005年には構造研究を実施し,森林を分断している私道上に実験基を建設し,モニタリングを実施したところ,2006年,リスとヤマネの利用を確認した.<br> 2007年に北杜市の市道にパスウェイの建設をし,そのモニタリングの結果は 2008年のポスターにて発表した.その後,2010年には,北杜市に.号機が,2011年には栃木県,2013年 4月には愛知県でパスウェイの建設がされた.栃木県では,モモンガの利用が確認され,これで樹上性の小型哺乳類はほぼ利用するということが証左された.山梨県の.号機と.号機では継続的にモニタリングを実施しており,ヤマネの利用は,.号機と.号機では 2割程であり,ヒメネズミは,両機とも 8割程であり,ヒメネズミの利用頻度が高かった.また,パスウェイの利用部位に関しては,ヤマネでは床面とパイプ面を,ヒメネズミとテンでは床面を,多く利用することが確認された.今後,これらのデータを元に,より効果的なパスウェイの普及を行っていく.
1 0 0 0 OA ロボット技術を活用した資源化施設における手選別作業支援システムの開発
- 著者
- 中野 裕 川本 直哉 梅本 司 桂木 格
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第31回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.95, 2020 (Released:2020-11-30)
我が国では少子高齢化や生産年齢人口の減少が進展する中、ロボット技術は、製造業の生産現場、医療・介護現場、農業・建設・インフラの作業現場などの幅広い分野で、人手不足の解消、過重な労働からの解放、生産性の向上などの社会課題を解決する可能性を有している。 資源化施設における選別工程では、機械による選別に加えて、精度向上のため、人による手選別が広く採用されている。手選別作業はベルトコンベヤ上で行われることが多く、作業員はベルトコンベヤ上を流れる混合廃棄物の中から対象物または異物を見つけ、選別・除去を行っている。これらは繁忙な作業であることに加えて、選別対象物に重量物が含まれる場合もあり、作業員への負担は小さくない。当社は手選別作業に係る負荷軽減を目的として、人共存型ロボットによる支援システムの開発を行っており、本稿ではその取り組みについて紹介する。
- 著者
- 三隅 二不二 篠原 弘章 杉万 俊夫
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.77-98, 1977
- 被引用文献数
- 4
本研究は, 地方官公庁における管理・監督者のリーダーシップに関して, 客観的測定方式を作成し, その妥当性を検討しようとするものである。<BR>まず, 基礎資料として, 地方官公庁の管理・監督者から, 自由記述によって, 彼らの職場における上司としての役割行動についての行動記述を収集した。この基礎資料をもとに質問項目を作成し, 数回にわたる専門家会議を経て, 調査票を作成した。質問項目はすべて, 部下である一般職員が上司のリーダーシップ行動について回答するという, 部下評価の形式をとった。また, 係長と課長のリーダーシップ行動を各々区別して評定するように調査票を作成した。係長のリーダーシップ行動に関する質問項目は49項目であり, 課長のリーダーシップ行動に関する項目は, 係長用49項目に5項目を追加した計54項目である。調査票には, リーダーシップ得点の妥当性を吟味するための資料として, モチベーター・モラール, ハイジーン・モラール, チーム・ワーク, 会合評価, コミュニケーション, メンタル・ハイジーン, 業績規範に関する質問項目40項目 (モラール等項目) を含めた。なお, 調査票の質問項目はすべて, 5段階の評定尺度項目である。<BR>この調査票を用いて, 集合調査方式により調査を実施した。調査対象は, 栃木県, 東京都, 静岡県, 兵庫県, 北九州市, 福岡市, 久留米市, 都城市の自治体に勤務している一般職員967名である。<BR>分析は, 単純集計に引続いて, 因子分析を行なった。因子分析は次の3つに分けて行なった。すなわち, (1) 係長のリーダーシップに関する49項目, (2) 課長のリーダーシップに関する54項目, (3) モラール等項目40項目, に対する因子分析である。因子分析にあたっては, 相関行列の主対角要素に1.00を用いて, 主軸法によって因子を抽出した後, ノーマル・バリマックス法によって因子軸の回転を行なった。<BR>係長のリーダーシップ行動に関する因子分析の結果, 次の4因子が見出された。すなわち, 「集団維持の因子」・「実行計画の因子」・「規律指導の因子」・「自己規律の因子」の4因子である。「集団維持の因子」は, 集団維持のリーダーシップ行動 (M行動) に関する因子であり, 「実行計画の因子」・「規律指導の因子」・「自己規律の因子」の3因子は, 集団目標達成のリーダーシップ行動 (P行動) に関する因子であると考えられた。<BR>課長のリーダーシップ行動に関する因子分析の結果, 次の4因子が見出された。すなわち, 「集団維持の因子」・「企画・調整の因子」・「規律指導および実行計画の因子」・「自己規律の因子」の4因子である。「集団維持の因子」はM行動に関する因子であり, 他の3因子はP行動に関する因子であると考えられた。<BR>係長と課長のリーダーシップ行動に関する因子分析の結果, 産業企業体でみられた「目標達成への圧力の因子」に相当する因子が見出されず, それに代わって, 規律指導あるいは自己規律の因子のような規律に関する因子が見出されたことは, 地方官公庁におけるリーダーシップ行動の特質と考察された。<BR>また, モラール等項目に関する因子分析では, 予め設定した7カテゴリーの妥当性を検証するために8因子解を求めたが, 全般的に, 予め設定した各カテゴリーは, 各因子と1対1の対応をもつことが明らかになった。ただ, メンタル・ハイジーンと業績規範の2カテゴリーは, それぞれ2因子, 3因子構造を有していた。<BR>係長および課長を部下評定によって分類したリーダーシップP-M4類型の効果について分析した。まず, 係長および課長のリーダーシップ・タイプを測定する項目を因子分析の結果に基づいて選定した。係長の場合も, 課長の場合も, P行動測定項目, M行動測定項目をそれぞれ8項目ずつ選定した。<BR>係長のP-M指導類型とモラール等項目得点の関係をみると, 業績規範のカテゴリーを除く各カテゴリーにおいて, PM型が最高点を示し, M型が第2位, P型が第3位, pm型が最下位の平均値を示した。業績規範のカテゴリーにおいては, M型とP型の順位が逆転した。この傾向は, 三隅他 (1970) が産業企業体の第一線監督者において見出したリーダーシップP-M類型効果差の順位と同じである。また, 相関比の2乗の大きさから, コミュニケーション・会合評価の2カテゴリーにおいて, 特にリーダーシップ類型効果差が著しいことが明らかとなり, これは, 行政体における特徴であると考察された。
1 0 0 0 OA サッケード適応における小脳脳幹神経機構
- 著者
- 小島 奉子
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.126-134, 2012-09-05 (Released:2012-10-29)
- 参考文献数
- 56