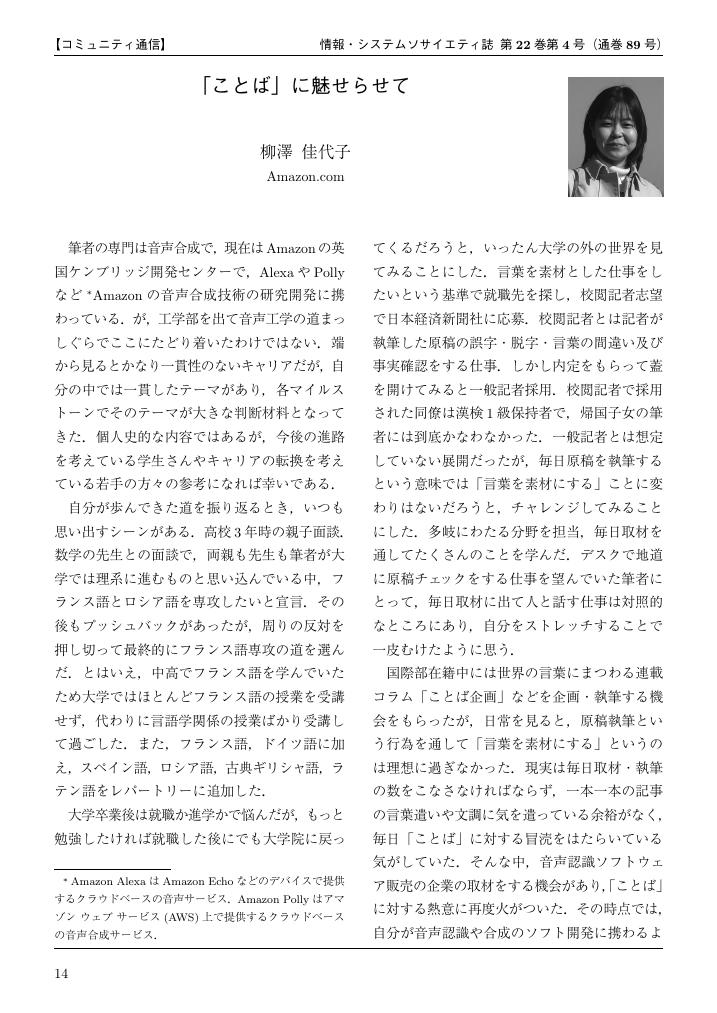1 0 0 0 OA 日本の小型捕鯨業の歴史と現状
- 著者
- Hajime Ishikawa 石川 創
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館調査報告 = Senri Ethnological Reports (ISSN:13406787)
- 巻号頁・発行日
- vol.149, pp.129-152, 2019-06-24
- 著者
- 星野 政博 泉澤 正和 糸井 孝雄
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 (ISSN:13414534)
- 巻号頁・発行日
- no.2000, pp.683-684, 2000-07-31
1 0 0 0 OA 「ことば」に魅せらせて
- 著者
- 柳澤 佳代子
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 情報・システムソサイエティ誌 (ISSN:21899797)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.14-15, 2018 (Released:2018-02-01)
1 0 0 0 OA 最適制御とその条件
- 著者
- 市川 邦彦
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.5, pp.340-352, 1971-05-10 (Released:2009-11-26)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 関節形ロボットアームの最適冗長性制御
- 著者
- 中村 仁彦 花房 秀郎
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.501-507, 1985-05-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3 4
In this paper, the optimal redundancy utilization of articulated robot arms is discussed. Concerning redundancy utilization of robot arms, the momentary optimal control scheme has been proposed so far, where the null spaces of Jacobian matrices are made optimal use of instantaneously. However, it is not enough when the exact optimality covering the full working time is required. For examples, the energy saving motion is required for robot manipulators of space use. The successful motion may not be always obtained for obstacle avoidance problem in the working space with complicated obstacles, if we apply the momentary optimal control scheme.The globally optimal control scheme of redundancy is formulated based on Maximum Principle. By applying this scheme, the optimal solution is necessarily obtained, if it exists. And the amount of computation is reduced to one dimensional search for the minimum value when the degree of redundancy is equal to one.
- 著者
- 朝田 隆
- 出版者
- 科学評論社
- 雑誌
- 精神科 = Psychiatry (ISSN:13474790)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.677-681, 2021-06
- 著者
- 川勝 平太
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.238, pp.36-40, 1999-08-27
「21世紀の国土のグランドデザイン」で,「庭園の島(ガーデン・アイランズ)」構想を提唱した川勝氏。6月末にはこの国土計画を推進するための戦略も出されたが,「庭園の島構想,生活空間倍増計画,新首都建設を三位一体として,地球時代にふさわしい戦略を立てるべき時が来ている」と語る。
1 0 0 0 IR 地方政治における保守王国形成の政治過程
- 著者
- 前田 繁一 Shigekazu Maeda
- 出版者
- 松山大学
- 雑誌
- 松山大学論集 (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.45-84, 2005-04
1 0 0 0 蛔虫の免疫に関する研究補遺
- 著者
- 森下 哲夫 小林 瑞穂
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.79-88, 1954
我々はさきの報告に於て蛔虫を海〓に多数感染させて, 1週以後に蛔虫の幼虫及び成虫から得た抗元を以て, 罹患海〓に皮内反応を実施し特異な成績を得た.しかもこの反応は蛔虫の種類(人, 豚及び犬に)関係なく陽性であるが, 鉤虫抗元に対しては蛔虫罹患海〓は皮膚反応を示さないことを知つた.その逆に犬鈎虫罹患海〓は鈎虫抗元にのみ陽性の反応を示し蛔虫抗元には反応しない.更に蛔虫及び鈎虫抗元共抗元分析の結果polysaccharide fractionは注射後30分で烈しい発赤を惹起し, 6時間位継続して消褪し, 一方protein fractionは2〜3時間後から水腫を伴つて発赤を起し72時間継続することを知つた.豚蛔虫飼養液を抗元として蛔虫罹患海〓の皮膚反応を行うと蛔虫体成分のpolysaccharide fractionに相当する反応丈を示し, protein fractionに相当する反応は全然認められなかつた.Schultz-Dale反応を罹患海〓の腸に対し施行すると蛔, 鈎虫抗元ともpolysaccharide fractionのみが腸の著しいれんしゆくを示すが, protein fractionでは反応が陰性であつた.蛔, 鈎虫共成虫と幼虫との間には共通の皮膚反応が認められ犬鈎虫の場合はfilaria型幼虫のみならずrhabditis型幼虫が成虫と同様な皮膚反応陽性成分を有するが, 卵には認められなかつた.蛔虫卵に依る抗元の場合は更に判然とした変化を認められ蛔虫卵の数を一定にして抗元を製造すると, 単細胞のものには反応が認められず桑実期迄はこの状態が続くが, 蝌蚪期に至つて多少弱いが皮膚反応が陽性になつて来る.幼虫形成の蛔虫卵では勿論成虫と同様の反応を示した.以上の様な結果に対して更に精しい抗元の性質の究明を試みたのが本報文である.
- 著者
- 佐藤 恵 姜 来娜 嶋田 洋徳
- 出版者
- 科学評論社
- 雑誌
- 精神科 = Psychiatry (ISSN:13474790)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.715-722, 2021-06
1 0 0 0 IR 崑崙と獅子 : 祇洹寺図経覚書
- 著者
- 黒田 彰
- 出版者
- 佛教大学国語国文学会
- 雑誌
- 京都語文 (ISSN:13424254)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.129-153,5,7-36, 2014-11-29
本誌前号の拙稿「祇園精舎覚書|鐘はいつ誰が鳴らすのか|」において、祇園精舎の無常堂の鐘の鼻には、金の獅子に乗り、手に白払を持った、金の崑崙が造型されていることを明らかにした。さて、その崑崙とは如何なるものなのか、戦前の研究史を参照しつつ、伎楽面の崑崙等を上げ、前稿の末尾部分で、聊か述べる所があったものの、その後、崑崙については二つ、大きな問題があることに気付いた。一つは、第二次世界大戦後、新中国において唐代を中心とする、崑崙の出土が相次ぐなど考古、美術、仏教、音楽(芸能)、文学、歴史等の諸分野にあって、崑崙研究が大きな進展を見たことである。もう一つは、崑崙が祇園精舎無常院(堂)の鐘と深く関わることである。小稿は、その第一の問題に取り組んだものである。近時の上記諸分野における崑崙研究は、目を見張るものがあるが、遺憾なことに、それら各分野の成果を統合し、纏めたものがない。そこで、小稿にあっては現時点における崑崙研究を、図像資料を中心として総合的に纏めてみることとした。小稿の図版(図一|三十五<図三十四を除く> 、参考図一|三)に関しては、巻頭カラー図版を参照されたい。なお第二の問題については、近稿「祇園精舎の鐘|祇洹寺図経覚書|」を予定する
1 0 0 0 OA 『倶舎論』における本無今有論の背景 -- 『勝義空性経』の解釈をめぐって --
- 著者
- 宮下 晴輝
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー = BUDDHIST SEMINAR (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.7-37, 1986-10-30
- 著者
- 川勝 平太 平島 寛
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ア-キテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.683, pp.32-35, 2001-01-01
「土地を土台として,そこにつくられた物が,人間の立ち居振る舞いを決める。変な形の物産複合は,人間の立ち居振る舞い,つまり文化までおかしくする」と語る川勝氏。
1 0 0 0 スパンボンド不織布を用いた補強盛土の人工降雨実験
- 著者
- 久楽 勝行 三木 博史 林 義之 永野 豊 山田 知正 中野 正己 高砂 武彦 高橋 修三 志藤 日出夫 岩崎 高明 末石 辰広
- 出版者
- Japan Chapter of International Geosynthetics Society
- 雑誌
- ジオテキスタイルシンポジウム発表論文集 (ISSN:09137882)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.15-22, 1990
スパンボンド不織布による浸食抑制効果を調べるため、大型補強盛土の人工降雨実験を行った。試験盛土は、シルト質砂で築造したもので、高さが2.75m,のり面勾配が1:1.0である。試験盛土3ケースのうち、1つは無補強で、他の2つはスパンボンド不織布をそれぞれ60cmと30cm間隔で敷設したものである。累積降雨量は453mmである。<br>実験結果によると、スパンボンド不織布は盛土ののり先から進行してくる浸食を抑制する効果を十分に有しており、しかも浸透水を排水して飽和度の上昇に伴う盛土の強度低下を遅らせる効果もあわせもつことが明らかになった。そして、スパンボンド不織布の敷設間隔を密にするほど、これらの効果が大きいことがわかった。
1 0 0 0 OA 脳梗塞による突発難聴の3症例
- 著者
- 小林 泰輔 暁 清文 柳原 尚明 松本 康 町田 敏之 堀内 譲治
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.3, pp.321-327, 1993-03-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
Case 1: a 59-year-old male with a one-year history of diabetes mellitus complained of right sudden deafness with vertigo. Otoneurological examinations showed sensorineural hearing loss of the right ear and bidirectional horizontal gaze nystagmus. MRI revealed infarction of the right cerebellar hemisphere indicating occlusion of the anterior inferior cerebellar artery (AICA). With conservative treatment his hearing returned to the contralateral ear level. Case 2: a 49-year-old female who complained of right sudden deafness with vertigo and ipsilateral facial palsy. Audiometric studies showed total deafness on the right. Bidirectional horizontal gaze nystagmus, together with V, VII, IX and X cranial nerve palsies were recognized. CT and MRI proved infarction of the right cerebellum and pons. Her hearing improved only partially. Other neurological signs disappeared within eight months. Case 3: a 54-year-old male with a history of hypertension and angina pectoris complained of right sudden deafness with dizziness. Right sensorineural hearing loss and spontaneous nystagmus toward the left were noted. His hearing improved on the next day. Two days later, however, he lost consciousness. CT showed no abnormality, but angiography revealed occlusion of the basilar artery.These three cases showed the importance of differential diagnosis between acute hearing loss due to cerebral infarction and idiopathic sudden deafness. We emphasize the diagnostic importance of risk factors such as hypertension and diabetes mellitus and the sign of vertigo with nystagmus of central origin in cases of cerebral infarction.
1 0 0 0 アトミズムによる生命理論の歴史的展開と原理的課題
アトミズにおける生命論の最も深刻な問題点は、魂を構成するアトムにアトム本来の規定を逸脱した、他のアトムを統合する働きが要請されていたことであった。このことはより一般化すれば、アトム同士が結合する「力」の問題である。その根底には、アトムが結合する場合に、なぜアトムが結合して新たな大きなアトムを形成せず独立性を保ちうるのかというアトムの独立性の問題が伏在している。それはアトムの不可分割の本質規定の問題と表裏一体である。アトムの不可分割の理由として、従来、アトムが空虚をうちに含まないことが最大の理由とされていた。しかし、そこから論理的に導出されるのは、アトム同士の結合や衝突は、アトムが独立性を保つ限り、空虚の薄膜が介在する遠隔的な間接的接触になるという帰結である。しかし、その帰結はピロポノスが6世紀にアリストテレスのテキストから可能性として古注で示唆する以外は、古代アトミストたちの文献には見られず、また、古代アトミズムが復活された16世紀以降の西洋の思想家たちにも総じて無視されている。しかも、重要なことに遠隔的な斥力や引力を働かせる働きは、空虚そのものにもアトムの性質にも何ら想定されていないのである。空虚を内部に含まないことに基礎を置くアトムの不可分割性は、アトムに、結合や衝突や反発のあり方をまったく説明できないという重大な欠陥をはらんでいる。それゆえ、ハイゼンベルグが指摘しているように、19世紀までのアトム同士の結合の説明として、アトムにホックや釣り金具がついたような、奇妙な形態のアトムが想像されたのである。古代原子論とそれを歴史的に継承した原子論において、不可分割性というアトムの本質規定が、アトム同士の結合を説明できない原理的な欠陥を内包している。それが生命論として、魂を構成するアトムが他の他のアトムを統合する力を説明できないことのより原理的な問題であることが明らかになった。
1 0 0 0 IR 家兎における肝蛭の単数感染試験
- 著者
- 河野 潤一 清水 晃 梅田 史郎 木村 重
- 出版者
- 神戸大学農学部
- 雑誌
- 神戸大学農学部研究報告 (ISSN:04522370)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.p85-92, 1990
日本産およびアメリカ産肝蛭を家兎に単数感染させ,各種変化について検索した。臨床症状は認められなかった。肝蛭卵および沈降抗体の検出時期は多数感染例と同様であった。肝病変は,肉眼的にも組織学的にも軽微であった。血液性状は,白血球数および好酸球数の若干の増加を認めた。血清の生化学的性状は,日本産肝蛭感染家兎において感染後9-10週に,GPT活性および総コレステロールの上昇を認めたが,そのほかでは著しい変化はなかった。肝蛭単数感染家兎の胆嚢から採集した虫卵の孵化率は,多数感染例におけるそれより低率であった。感染虫体の発育状況は,単数および多数感染例とも同様であった。 / Rabbits were experimentally infected either perorally with a single metacercaria or intraperitoneally with a newly excysted juvenile fluke of Japanese Fasciola sp. and American Fasciola hepatica. No clinical signs were noted. Fluke eggs were first detected in feces at the 63rd and 53rd post infection days for F. sp. and F. hepatica, respectively. Precipitating antibodies were first detected in sera at the 4th post infection week for both of the Fasciola species. Gross lesions showing adhesions, haemorrhages, nodules, scars, hyperplasia of connective tissue and thickening of the bile duct were all moderate. Histopathologically, tract lesions and haemorrhages were noted. In hematological examinations, no remarkable changes were observed in erythrocyte counts, leukocyte counts and hemoglobin content. Eosinophil percent increased in 6-8 weeks after infection. In biochemical examinations of sera, no remarkable changes were noted in concentrations of total protein, albumin and globulin, and the GOT activity. The GPT activity and total cholesterol concentration increased at the 10th and 9th post infection weeks, respectively, in the rabbits infected with F. sp. Hatching rates of fluke eggs that were collected from the gallbladder of the infected rabbits were 5-46% for F. sp. and 7-51% for F. hepatica. While, hatching rates of eggs that were collected from those infected with a multiple dose of Fasciola were 18-57% for F. sp. and 67-81% for F. hepatica. Body size and development of the inner organs of the flukes recovered from the rabbits that were infected with a single dose were the same as those recovered in the infections of multiple dose of the Fasciola species.
- 著者
- 清水 義和
- 出版者
- 愛知学院大学教養教育研究会
- 雑誌
- 愛知学院大学教養部紀要 (ISSN:09162631)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.23-51, 2011