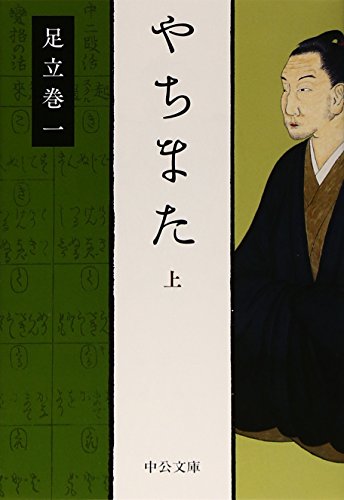1 0 0 0 OA 再帰性とメタ認知 : ドイツ語の再帰動詞を手掛かりにして
- 著者
- 荻野 蔵平
- 出版者
- 熊本大学大学院人文社会科学研究部(文学系)
- 雑誌
- 人文科学論叢 = Kumamoto Journal of Humanities (ISSN:24350052)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-12, 2021-03-31
Im vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Überarbeitung meiner Austrittsvorlesung, die am 7. März 2020 an der Universität Kumamoto vorgesehen war, jedoch wegen der Corona-Krise leider nicht stattfinden konnte. Die Meta-Kognition, die auf kognitiver Ebene als Denken über das eigene Denken bzw. Wissen über das eigene Wissen definiert wird, drückt sich auf sprachlicher Ebene in der Reflexivität aus: z.B. sich betrachten/自分を見つめる. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von deutschen und japanischen reflexiven Verben festzustellen, wie unterschiedlich stark die Meta-Kognition in beiden Sprachen ausgeprägt ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unterschiedliche Konkretion der „Ich-Spaltung“ bei den Deutschsprachigen und den Japanischsprachigen eng mit einigen Eigentümlichkeiten der deutschen und der japanischen Sprache zusammenhängt: erstens mit den reflexiven Ausdrücken, zweitens mit der Diskursstrukur und drittens mit der Subjekt-Prädikat-Relation und schließlich mit der Sprecherperspektive.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ニューメディア (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1453, 2015-02-16
MVNOによる格安スマホサービス「U-mobile」を展開するU-NEXTは、スマホのアプリケーションストアを用意して提供する構想を持っていることを明らかにした(詳細は本号のp.11-12参照)。 同社では、設備を持たない通信キャリアになることを目標においている。単にバ…
1 0 0 0 OA Maintenance of mouse trophoblast stem cells in KSR-based medium allows conventional 3D culture
- 著者
- Shuai SUN Shota YANO Momo O NAKANISHI Michiko HIROSE Kazuhiko NAKABAYASHI Kenichiro HATA Atsuo OGURA Satoshi TANAKA
- 出版者
- The Society for Reproduction and Development
- 雑誌
- Journal of Reproduction and Development (ISSN:09168818)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-119, (Released:2021-03-20)
- 被引用文献数
- 4
Mouse trophoblast stem cells (TSCs) can differentiate into trophoblast cells, which constitute the placenta. Under conventional culture conditions, in a medium supplemented with 20% fetal bovine serum (FBS), fibroblast growth factor 4 (FGF4), and heparin and in the presence of mouse embryonic fibroblast cells (MEFs) as feeder cells, TSCs maintain their undifferentiated, proliferative status. MEFs can be replaced by a 70% MEF-conditioned medium (MEF-CM) or by TGF-ß/activin A. To find out if KnockOutTM Serum Replacement (KSR) can replace FBS for TSC maintenance, we cultured mouse TSCs in KSR-based, FBS-free medium and investigated their proliferation capacity, stemness, and differentiation potential. The results indicated that fibronectin, vitronectin, or laminin coating was necessary for adhesion of TSCs under KSR-based conditions but not for their survival or proliferation. While the presence of FGF4, heparin, and activin A was not sufficient to support the proliferation of TSCs, the addition of a pan-retinoic acid receptor inverse agonist and a ROCK-inhibitor yielded a proliferation rate comparable to that obtained under the conventional FBS-based conditions. TSCs cultured under the KSR-based conditions had a gene expression and DNA methylation profile characteristic of TSCs and exhibited a differentiation potential. Moreover, under KSR-based conditions, we could obtain a suspension culture of TSCs using extracellular matrix (ECM) coating-free dishes. Thus, we have established here, KSR-based culture conditions for the maintenance of TSCs, which should be useful for future studies.
1 0 0 0 OA 毛色の遺伝子
- 著者
- 辻 荘一 万年 英之
- 出版者
- Japanese Society of Animal Breeding and Genetics
- 雑誌
- 動物遺伝研究会誌 (ISSN:09194371)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.13-18, 1998-03-20 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 18
- 著者
- 武石 正宣
- 出版者
- 一般社団法人照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.1, pp.44-46, 2012-01-01
NIIGATA MONOLITH is a comprehensive bridal facility newly built in Niigata prefecture. The ceiling of the banquet room has an inclination of CH:5,700mm to CH:7,300mm, and approximately one thousand transparent acrylic tubes are laid on the ceiling. The challenge was to reduce the running costs including maintenance fees while keeping the ceiling high. HIMEJI MONOLITH is a comprehensive bridal facility built based on an about 80 year-old house by renovating the interior as a guest house. The minimum LED spotlights are used to illuminate the exterior of the building, which received a designation of the Important Building for Landscape of Himeji-shi, Hyogo prefecture.
- 著者
- 遠藤 智子 ヴァタネン アンナ 横森 大輔
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.160-174, 2018-09-30 (Released:2018-12-26)
- 参考文献数
- 29
本研究は,フィンランド語・日本語・中国語における先行発話に重なって開始される応答,特に同意的応答について,対面会話の録画をデータとして検討する.会話分析の手法を用いた分析により,まず,完結可能点より早い位置で同意を開始することは,話題に関する認識的独立性を主張し,同意的応答が持つ行為連鎖上の従属的な性質を調整するということに動機づけられていることを示す.重なって開始される同意的応答の構造的特徴として,(1)同意のパーティクル+理解の提示および(2)認識性に関する修正を含む繰り返しという2つのパターンが3言語に共通して見られた.また,重ねられる側の発話には,条件節や因果節による複文構造やトピック–コメント構造が3言語に共通して見られた一方で,フィンランド語と中国語ではSVX語順が,日本語では引用構文が観察された.これらの構造は,その前半または初めの部分が次にどのような内容が産出されるかを強く投射するため,聞き手が完結可能点よりも早く応答を開始することを可能にする.本研究は,発話の開始位置と発話の言語構造を調整することによって会話参与者間の知識状態に関する相対的な位置取りを交渉するということが,人類の文化に(あるいは少なくともここで取り上げた3言語に)共通してみられる普遍的なプラクティスであることを示唆するものである.
1 0 0 0 OA 窃盗犯人でない者の事後強盗への共同加功
- 著者
- 今上 益雄
- 出版者
- 東洋大学法学会
- 雑誌
- 東洋法学 = Toyohogaku (ISSN:05640245)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.83-110, 1993-01
1 0 0 0 原四郎追悼録
- 出版者
- 原四郎追悼録編纂刊行委員会
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 OA モンゴル人の歳月名に就いて
- 著者
- 小林 高四郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1-2, pp.55-65, 1957-05-30 (Released:2018-03-27)
1 0 0 0 IR 医学論文における言語的特徴のコーパス研究 : 教育応用についての試みの延長検討
- 著者
- 浅野 元子 Asano Motoko アサノ モトコ
- 出版者
- 大阪大学大学院言語文化研究科
- 雑誌
- 言語文化共同研究プロジェクト
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, pp.55-91, 2017-05-31
テクストマイニングとデジタルヒューマニティーズThis paper describes an extension study for the preliminary assessments of pedagogical implications of a corpus-based ESP approach to medical research article reading in classrooms of Japanese medicalcollege students. Over the course of lectures spanning four to five hours on two different days with one to three weeks in between, a total of 222 second-and third-year students were involved in activities in which mini-corpora were compiled, and the rhetorical structure of the abstract and introduction sections of research articles from the New England Journal of Medicine were determined by finding non-thematic linguistic clues or hint expressions.Before and after the course, a questionnaire was administered preliminarily to examine whether or not the course had helped the students to alleviate the burdens of reading textbooks in English. The students' written comments were also invited on a voluntary basis. The statistical analysis using Welch's paired t-test revealed that the degree of'difficulty'in reading textbooks in English decreased significantly (p≤0.00234); however, the effect size was as small as 0.260. The move analysis of the students'written comments showed that th e' burdens or anxiety/dissatisfaction'comments tended to be provided together with 'achievements or findings', indicating that the students tended to soften their negative comments by combining them with positive ones. The observation revealed that quantitative, multivariate analyses may not be suitable for a small amount of written comments and might need to be used in combination with qualitative examinations. The results of this study suggested that the number of learning items should be reduced and the amount of explicit explanations about corpus tools as well as moves should be increased in the classroom in the future.本研究は,医学論文における言語的特徴の検討についての教育応用を模索するために,ミニコーパスの構築ならびにムーブの明示的指導と練習を取り入れた授業を行い,授業後に,学生にとって英語で書かれた専門文書を読むことの負荷が軽減するであろうかという聞いに対する答えを得る方法について予備的に検討した研究の延長研究である。本研究の背景としては,グローパル化に対応した英語教育において,医学生のリーデイング能力としては医学・医療の研究の基礎に必要な医学英語が理解できること,ライティング能力としては医学論文の英文abstractを書けることなどが, 医学英語教育学会によるガイドラインでの最低要件とされることがある。医学系単科大学の第2学年と第3学年の男女学生合計222名を対象にl回当たり60分の授業を4~5回行った。授業は,学術文書を英語で書くためには,学術文書をその分野の専門家のように英語で読むのが最良の方法であるというESPの概念や実践報告の積み重ねを重視する授業学の考えに基づいて行った。l回目の授業開始前と最後の授業終了後に英語で書かれた専門文書のなかでもより身近な教科書を読むことへの負担について質問紙調査を実施し,最後の授業後には自由回答による授業についての意見を求めた。質問紙調査では,欠損値のなかった197名を対象として統計学的に検討した。自由回答による意見は,回答が得られた34名の叙述を対象に,ムーブをコードして質的に検討し,多変量解析を用いて量的に検討した。質問紙調査では,英語で喜かれた教科書を読むことの難しさについて,授業終了後に授業開始前と比較して統計学的に有意な低下(p≤0.00234, Welchの対応のあるt検定)が認められたが,効果量は0.260と低かった。自由回答による意見では,量的検討に質的検討を組み合わせることの必要性が示唆され,授業での「負担または不安・不満」 は「達成または発見・気づき」や「提案」などとともに述べられ,和らげた語調を用いて述べられる傾向が示されたと考えられた。授業時間当たりの学習項目が多く,難易度が高かったことが示唆され,今後改善の必要があると考えられた。
1 0 0 0 OA アイヌ民族が伝承するオオウバユリとその保存食品の栄養成分
- 著者
- 塩崎 美保 石井 智美
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.303-306, 2004-10-01 (Released:2010-02-09)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 2
The Ainu are indigenous people of Japan who have mainly resided in the Hokkaido and Tohoku regions. They have traditionally obtained starch and onturep from roots of the lily (Cardiocrinum cordatum var. glehnii) which is thought to have been their main edible plant for use as a food and medicine.We prepared starch and onturep in this study and analyzed their compositions. Starch was extracted from roots of the lily, and the remaining root materials were fermented, dried, and made into onturep. They had a high carbohydrate content. Onturep was made into gruel, the energy of the gruel for one meal being calculated to be about 240kcal.The Ainu have traditionally made dried foods high in energy level and fiber content by using starch extracted from the roots and the remaining root materials. The consumption of these dried foods has enabled the Ainu to maintain a stable and nutritious diet.
1 0 0 0 OA 子供の体力と脳の発達 -行動学的研究と脳イメージング研究のナラティブ・レビュー-
- 著者
- 紙上 敬太 樽味 孝
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.239-247, 2020-06-01 (Released:2020-05-12)
- 参考文献数
- 52
The global pandemic of childhood physical inactivity and the associated reduction in physical fitness have become the major health problem. Based on such background, there is growing interest in child development research to investigate the associations among physical fitness, cognitive function, and the underlying neurobiological mechanisms. In the present narrative review, we first summarize the findings from behavioral studies that examined the relations of childhood fitness to academic performance and executive function. Because these behavioral findings remain controversial due to methodological inconsistencies, we further discuss differences in independent variables (e.g., physical activity vs. fitness), confounders (e.g., socioeconomic status), study designs (e.g., cross-sectional vs. randomized controlled trial), and assessments used to measure academic performance and executive function (e.g., task difficulty). Subsequently, we introduce neuroimaging studies on brain volume, task-evoked brain activation, and white matter fiber integrity which may provide mechanistic insights into the behavioral observations. To date, several randomized controlled trials using advanced imaging techniques showed that regular physical activity may change brain activations during executive function tasks and improve white matter fiber integrity in children. Collectively, our literature review suggests that regular physical activity leading to increase in physical fitness is likely to contribute to healthy brain development. Nevertheless, the current evidence is still limited and inconclusive, thus further rigorously designed randomized controlled trails are needed to clarify the association between childhood fitness and brain development.
- 著者
- Changmann Yoon Shin-Ho Kang Jeong-Oh Yang Doo-Jin Noh Pandiyan Indiragandhi Gil-Hah Kim
- 出版者
- Pesticide Science Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.77-88, 2009-05-25 (Released:2009-06-01)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 22 34
The repellent efficacy of 17 essential oils against the German cockroach, Blattella germanica was examined using a T-tube olfactometer. Five oils repelled B. germanica with good efficacy, ranging from 70.0 to 96.7%. Four of these oils, grapefruit, lemon, lime, and orange, were from the citrus family Rutaceae. These citrus essential oils showed similar repellent activity against two more cockroach species, such as Periplaneta americana and P. fuliginosa. Gas chromatography (GC) and GC-mass spectrometry analyses revealed that the major components responsible for the repellent activity of the citrus oils were limonene, β-pinene and γ-terpinene. Limonene appears to be the main component responsible for the repellent activity rather than β-pinene and γ-terpinene. The repellent efficacy of these components varied with different doses and the cockroach species tested. It is likely that minor components of the oils also contributed to the overall repellent activity of citrus essential oils, except orange oil. The activity of orange oil is almost solely attributed to the activity of limonene. Also, the repellent activity of citrus oil and that of each of the terpenoids makes little difference to the efficacy of a repellant against the three species of cockroaches.
1 0 0 0 OA H. pyloriによる人類移動の推定と病原因子の進化解析
本研究は、(1)Helicobacter pylori(ピロリ菌)を利用した先史時代アジアにおける人類移動経路の推定、および、(2)ピロリ菌が持つ新規疾患関連因子の探索の2つをテーマとして進めた。テーマ(1)に関しては、沖縄に特異的に見られるピロリ菌の分岐年代(2~3万年前)から、縄文時代以前に琉球列島に人口流入があった可能性が示唆された。テーマ(2)に関しては、胃がん、および胃MALTリンパ腫患者由来のピロリ菌の比較から、主要な病原性遺伝子であるcagAとvacAで、アミノ酸頻度に有意差のある座位を見出した。
- 著者
- 藤原 豊 堀川 敬 本多 敏朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.249-257, 2012 (Released:2012-05-28)
- 参考文献数
- 22
日本人2型糖尿病患者を対象に膵β細胞機能の12ヶ月間の変化と影響因子を検討した.著しい高血糖からの離脱例,高度肥満例,進行した肝障害,腎障害,インクレチン使用例,インスリンと経口血糖降下薬併用例を除外し,血糖コントロールが3ヶ月以上良好で安定している症例205名を対象とした.膵β細胞機能はグルカゴン負荷試験のCペプチドの6分間の反応量(ΔCPR)で評価した.検討する臨床指標は,年齢,性別,糖尿病罹病期間,糖尿病網膜症,高血圧,尿アルブミン,HbA1c,血清脂質を用いた.観察開始時(ベースライン)での横断的検討では,糖尿病罹病期間はΔCPRと有意(r=0.357, p<0.001)な負の相関を示した.ステップワイズ法による重回帰分析の結果,臨床指標の中で糖尿病罹病期間はΔCPRを予測する主な独立変数(F=16.951)であった.全対象例の12ヶ月間の縦断的検討で,ΔCPRは有意(p<0.001)に低下した.これらを治療法別に検討すると,非薬物療法群(39名)と経口血糖降下薬群(134名)のΔCPRはそれぞれ有意(p<0.05, p<0.001)に低下したが,インスリン治療群(32名)のΔCPRは有意な変化は認めなかった.経口血糖降下薬群での投薬内容に関するサブ解析で,ΔCPRの低下にインスリン分泌促進系経口血糖降下薬,特にスルホニル尿素薬の関与が強く示唆された.日本人2型糖尿病における膵β細胞のインスリン分泌能の経年変化には,高血糖曝露による自然史的影響ばかりでなく,種々の治療方法の影響が関与していることが示唆された.
1 0 0 0 OA 格助詞で終わる文について : 「~を / が~に」 構文と 「~に~を」 構文
- 著者
- 杉村 泰 SUGIMURA YASUSHI
- 出版者
- 名古屋大学言語文化研究会
- 雑誌
- ことばの科学 (ISSN:13456156)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.235-250, 2002-12-15
1 0 0 0 OA 遺伝毒性発がん物質のリスク評価:新しいアプローチ
- 著者
- 梅村 隆志
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第40回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.2032, 2013 (Released:2013-08-14)
「遺伝毒性発がん物質にはその作用に閾値が存在しない」という概念は,DNA塩基修飾の定量解析やin vivo変異原性試験の進歩に伴い,科学的観点からは否定的な傾向にあるものの,リスク評価の実際では,この概念に基づいた考え方から無毒性量(NOAEL)は設定できないとされている。従って,食品添加物などの意図的な食品中化学物質では,その際に使用を禁ずる処置などで対応できるが,食品製造過程で生じてくる化学物質や汚染物質などの非意図的食品中化学物質の場合,その含量をゼロにすることは困難であり,また,食品添加物においてもその製造過程等で生じる副生成物などがそれに該当する場合など,NOAELが設定できない遺伝毒性発がん物質へのリスクマネージメントが求められている。そのような背景の中で,1995年に国際保健機関(WHO)・国連食糧農業機関(FAO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)はアクリルアミドに対して,ベンチマークドーズ(BMD)を用いた暴露マージン(MOE)アプローチを実施した。現在この方法は,他の国際機関においても追随され,我が国唯一の食品安全のリスク評価機関である食品安全委員会においてもその使用が検討されている。具体的には,実験動物を用いた発がん性試験の用量反応曲線から求められるBMD(通常は95%信頼限界からのBMDL)と当該物質の推定ばく露量との差を求めていくと言うものである。本シンポジウムでは,これまで6年間にわたり参加しているJECFA会議での実例を紹介しながら,MOEアプローチの問題点を議論したい。また,JECFAのみならず,食品安全委員会でもすでに実施しているMOEをその評価手順に組み込んだ香料の安全性評価(この場合はBMDLではなくNOAEL)について概略し,香料評価の際の遺伝毒性発がん物質への対応,また,その算出の際に最も重要な推定ばく露量の考え方等についても,併せて紹介していきたい。
1 0 0 0 OA 英国における終末期ケア : 近年の政策・制度の動向
- 著者
- 小寺正一
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.843, 2021-03
1 0 0 0 OA 補陀落渡海船の宗教的意味
- 著者
- 根井 浄
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.309-312, 1992-12-20 (Released:2010-03-09)