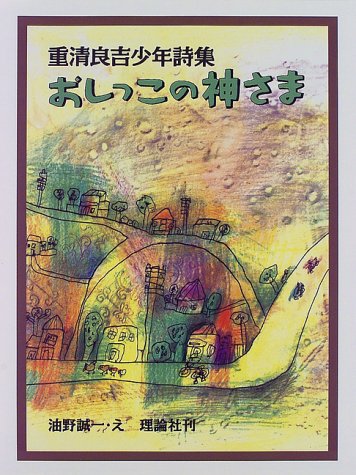1 0 0 0 おしっこの神さま : 重清良吉少年詩集
1 0 0 0 OA 極低温におけるオーステナイト系ステンレス鋼の変形挙動と試料温度の変化
- 著者
- 緒形 俊夫 石川 圭介
- 出版者
- CRYOGENICS AND SUPERCONDUCTIVITY SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 低温工学 (ISSN:03892441)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.99-103, 1986-04-25 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
Measurements were made on the temperature rise of tensile test specimens of austenitic stainless steels undergoing plastic deformation and discontinuous flow in normal liquid helium and superfluid helium. As the strain rate increased, the ultimate tensile strength and elongation decreased and the temperature rise increased. Compared with the results in normal liquid helium, the frequency of stress drop increased and the temperature rise was suppressed in superfluid helium.
1 0 0 0 日本人における加齢黄斑変性の遺伝的特徴
- 著者
- 吉田 統彦 坂本 泰二
- 出版者
- メディカル葵出版
- 雑誌
- あたらしい眼科 = Journal of the eye (ISSN:09101810)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.12, pp.1637-1639, 2007-12-30
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 急激な眼球突出で発症した小児眼窩膿瘍の一例
- 著者
- 大川 絢子 吉田 統彦 岡崎 嘉樹 平岩 貴志 羅 錦營
- 出版者
- 眼科臨床紀要会
- 雑誌
- 眼科臨床紀要 = Folia Japonica de ophthalmologica clinica (ISSN:18825176)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.5-8, 2008-01-15
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 山城 健二 吉原 理恵 石井 博尚 赤司 俊彦 横山 淳一 田嶼 尚子
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.7, pp.493-497, 2007 (Released:2009-05-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3
症例は62歳,男性.46歳時に糖尿病を指摘され,57歳より経口血糖降下薬を内服していたがコントロール不良のため,ヒトインスリン混合型製剤による治療が開始された.初回注射時より注射部位に発赤・腫脹を認め,また,消化器症状も出現し,症状が持続したため当院を紹介受診.皮内テスト・皮膚生検により,ヒトインスリンに対する即時型アレルギーを確認した.製剤をインスリンアナログ製剤に変更したところアレルギー症状は軽快し,インスリン治療継続可能となり血糖コントロールは改善.また,インスリン抗体,抗ヒトインスリン特異的IgE抗体の低下をみた.インスリンのアミノ酸配列のわずかな差異がインスリンアレルギーの発症,生体の免疫反応に関与する可能性があると考えられた.
- 著者
- 鈴木 理加
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.79-82, 2006
Webで利用できる無料の検索データベース、Google Scholar, Windows Live Search Academic, NII CiNiiと商用データベースCA, JSTPlusなどについて、各データベースの内容・検索機能・表示機能などを比較した。Google Scholarは無料で全文を見られることがあり、Windows Live AcademicはRSS対応や概要表示・ダウンロード機能があり、CiNiiは日本の文献の収録範囲が広いという特徴がある。
- 著者
- Pinar ISGUVEN Ilknur ARSLANOGLU Melih EROL Metin YILDIZ Erdal ADAL Muferret ERGUVEN
- 出版者
- The Japan Endocrine Society
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.985-990, 2007 (Released:2008-02-20)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 26 33
The aim of the present study is to investigate possible alterations in ghrelin and other hormone levels related to appetite and somatic growth in children with iron deficiency anemia. Twenty-five patients and 25 healthy controls that were prepubertal and within normal limits regarding height and BMI standard deviation scores were recruited. Ghrelin, leptin, IGF-I, IGFBP-3, insulin, thyroid hormones and cortisol levels were studied. Ghrelin, insulin and IGF-I levels were significantly low in the study group (ghrelin 13.58 ± 16.32 vs. 35.39 ± 23.69 ng/ml, p<.001; insulin 3.41 ± 2.42 vs. 5.67 ± 1.09 mU/ml, p = .008 and IGF-I 126.94 ± 92.82 vs. 203 ± 105.1 ng/ml, p = .015). We concluded that low ghrelin and insulin levels might be causes of the appetite loss in iron deficiency and as a result of appetite loss and undernutrition as well as by direct effects they might be related with growth retardation, which could be also influenced by low IGF-I levels.
1 0 0 0 売主に有利なCISG
- 著者
- 柏木 昇
- 出版者
- 貿易奨励会
- 雑誌
- 財団法人貿易奨励会貿易研究会研究報告書
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.217-233, 2009
1 0 0 0 IR 黥と渡来人
- 著者
- 張 従軍 岡部 孝道
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.31-67, 2000-02
渡来人の問題は、日本歴史の文化を研究する上で重要な課題である。一般には、渡来人は稲作とともに日本列島に入ってきたとされている。しかし、考古学の資料を見ると、古くは稲作が渡来した以前の縄文時代前・中期には、日本列島において、大陸文化に極めて類例した新しい文化要素が、すでに出現していたことが判明する。特に、顔に刻まれた入れ墨を特徴とする土偶などは、大陸の黄河流域における新石器文化に見られる入れ墨の形象と、ほぼ完全に一致している。入れ墨は、古代中国においては刑罰の一種であり、その起源も大変古い。入れ墨の刑を受けた者は、ただちに辺境の寒冷な北方地区に追放されるのが常で、二度と故郷に戻ることはなかった。このため、受刑者が追放された地方もまた、「鬼」の国と呼ばれていた。アジア東北地域に広く存在していた「鬼」の信仰など、この地域一帯で古くから密接な交流があったことを物語っている。初期に日本に上陸してきた「渡来人」とは、入れ墨の刑を受けた大陸からの流刑囚であった可能性を提起したい。彼らの影響によって日本列島では「紋身黥面」という風習が起こったのではなかろうか。
- 著者
- 國本 千裕 宮田 洋輔 小泉 公乃 金城 裕奈 上田 修一
- 出版者
- 日本図書館情報学会
- 雑誌
- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.199-212, 2009
本研究は読書の行為に焦点を当て「読書とはいかなる行為であるのか」を明らかにすることを目的としている。既存の読書研究は,読書の対象や,児童や生徒に対する読書指導といった側面に焦点を当てるものが多かった。これに対して本研究は,個人の行う読書は様々な次元からなる行為であると考え,成人を対象として読書の次元を明らかにしようと試みた。20代から40代の計29名を対象にフォーカス・グループ・インタビューを5回実施し,発言を分析した結果,読書とは,対象(何を読むのか)に加えて,志向(なぜ・何のために読むのか),行動(どのように読むのか),作用(読んだ結果何を得るのか),場所(どこで読むのか)の五つの次元から成る行為であることが明らかになった。特に対象は,物理的媒体,ジャンル,内容評価といった観点からみられる可能性が示唆された。
- 著者
- 西本 章宏 勝又 壮太郎 石丸 小也香 高橋 一樹
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1_85-1_110, 2010 (Released:2018-08-31)
- 参考文献数
- 44
本研究は、カテゴリー不確実性における消費者の製品カテゴライゼーションに焦点を当てている。本研究の目的は、このような認知状況下においてファジー理論を適用させることで、新たな製品カテゴライゼーションのあり方を明らかにすることである。そこで、本分析では、カテゴリー・メンバーシップ関数を用い、カテゴリー不確実性における消費者の製品カテゴライゼーションのモデリングを試みている。その結果、カテゴリー不確実性における製品カテゴライゼーションは(1)消費者ごとに異質であり、(2)その認知的異質性が当該マルチプル・カテゴリー製品に対する評価に大きな影響を及ぼしていることを明らかにしている。
- 著者
- 三輪 佳見
- 出版者
- 日本スポーツ運動学会
- 雑誌
- スポーツ運動学研究 (ISSN:24345636)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.13-28, 2006 (Released:2020-05-11)
- 参考文献数
- 15
Für Kinder ist es schwierig, das obere Zuspiel im Volleyball zu erlernen. Beim oberen Zuspiel wird der Ball mit den körbchenähnlich geformten Händen, vorwiegend mit den zwei ersten Gliedern von Zeige- und Mittelfingern sowie den Daumen, kurz und federnd kontaktiert („Pritschen”) (Stiuehler u.a. 1988). Wir haben die Bewegungsformen von 24 Kindern (Mädchen und Jungen im 10. /II. Lebensjahr), die das obere Zuspiel ausgeführt haben, beobachtet und Videoaufnahmen davon gemacht. Keines des Kindes hat einen steil zugeworfenen Ball gepritscht, sondern mit beiden Handtellern geschlagen. In der Vorbereitungsphase wurden die Arme dabei parallel gehalten, im Ellbogen gebeugt und vor und nach oben geführt. Die Armbewegungen beim Schlagen des Balls waren nur Extensionen im Ellbogengelenk, fast ohne Umsatz des oberen Armes. Diese Bewegungsformen entsprechen den Bewegungen des Werfens, Fangens und Schlagens im Vorschulalter. Ein Kleinkind wirft und fängt einen größeren Ball, z.B. Gymnastikball, mit beiden Händen, dabei werden die Arme parallel gehalten. Es schlägt einen leichten Ball, z.B. Luftballon, mit seinem Handteller. Kinder überlegen nicht, wie Einzelheiten einer Bewegung auszuführen sind. Ausfühliche Bewegungsanweisungen und weitschweifige technische Erklärungen sind im Allgemeinen nicht erforderlich und mitunter sogar unzweckmäßig (Meinel 1960). Wir haben jedem Kind die Aufgabe gestellt, einen steil zugeworfenen Ball mit den körbchenähnlich geformten Händen zu fangen. Trotzdem die Kinder die Körbchenhaltung als Vorbereitung des Fangens geübt hatten, wurden die Arme dem fliegenden Ball entgegengestreckt, die Handteller dem Balldurchmesser entsprechend zueinander gestellt und der Ball mit einer Zangenhaltung gegriffen. Damit die Kinder die für Kleinkinder typischen Bewegungen korrigieren und eine neue Bewegungsweise des oberen Zuspiels generieren, haben wir sie bei den Bewegungsausführungen nicht verbal angewiesen, sondern einige Geräte und Gegenstände bei den Vorübungen benutzt. Dafür sollen zwei Beispiele der Vorübungen angeführt werden. 1 . Das Fangen eines steil zugeworfenen Balls. Dabei benutzen die Kinder zunächst ein echtes Körbchen, um den Ball über der Stirn zu fangen und bilden dann ein Körbchen mit den Händen, wobei die Daumen und Zeigefinger ein offenes Dreieck bilden. 2. Das Dribbling mit beiden Händen. Die Kinder stehen auf einem erhöhten Gerät, z.B. dem größeren Kasten, damit sie den Ball nach unten in Richtung Boden kraftvoll und aktiv drücken können. Durch die erste Übung hat jedes Kina ohne verbale Bewegungsanweisung erlernen können, unter den von oben fallenden Ball zu gehen und ihn über der Stirn mit dem „Körbchen" zu fangen, wobei die beiden Arme nicht parallel gehalten wurden. Bei der anschließenden Übung ist die geeignete Bewegungsweise der Arme von den Kindern ausgeführt worden: Die körbchenähnlich geformten Hände sind dem vom Boden zurückprallenden Ball entgegengegangen, haben die aufwärtsgerichtete Ballbewegung elastisch abgebremst und den Ball wieder auf den Boden gedrückt. Durch diese Vorübungen konnte jedes Kind auch beim oberen Zuspiel den Ball mit den körbchenähnlich geformten Händen pritschen, ohne dass es seine Arme parallel gehalten und den Ball mit seinen Handtellern geschlagen hat.
1 0 0 0 OA 筑波大学筑波キャンパスの陸産・淡水産貝類相
- 著者
- 南波 紀昭 向峯 遼 芳賀 拓真 佐伯 いく代 Ikuyo SAEKI
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- ちりぼたん = The Chiribotan (ISSN:05779316)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.221-240, 2020-07-15
本研究は筑波大学自然保護寄附講座より研究助成を受けて行われた。
1 0 0 0 IR 中国内モンゴルにおける磚茶文化 : 茶馬交易が結んだ乳と茶
- 著者
- 才藤 千津子 SAITO Chizuko
- 出版者
- 京田辺
- 雑誌
- 同志社女子大學學術研究年報 = Doshisha Women's College of Liberal Arts annual reports of studies (ISSN:04180038)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.85-87, 2016-12-26
書評
1 0 0 0 OA 乳化系での防腐剤低減化のための原料選択の考え方
- 著者
- 森田 和良
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.124-137, 1997-06-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
最近, 肌に優しい化粧品の開発が求められ, 微生物面からも考慮された化粧品の開発が望まれる。そのため, 化粧品の品質を保証する上で防腐剤の利用は避けがたいものではあるが, 防腐剤の可能な限りの低減化が望まれる。そこで化粧品処方全体の構成を再考してみる。その結果, 次の (1), (2), (3) の要素を総合的に構築することにより防腐剤を極力低減化した乳化系化粧品を開発する道が開かれると考えられた。即ち, (1) 非資化性原料の選択 (2) 抗微生物活性が温和な脂肪族化合物および精油の利用, それに加えて新規機能性原料の開発 (3) 防腐剤の油水分配に係わる理論の利用である。
1 0 0 0 IR ニーチェをめぐる女性たち--ニーチェの女性観の背景(2)
- 著者
- 恒吉 良隆 Yoshitaka TSUNEYOSHI 福岡女子大学文学部独文学 Faculty of Literature Fukuoka Women's University
- 出版者
- 福岡女子大学文学部
- 雑誌
- 文芸と思想 (ISSN:05217873)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.143-174, 2003
1 0 0 0 IR ニーチェをめぐる女性たち--ニーチェの女性観の背景(1)
- 著者
- 恒吉 良隆 Yoshitaka TSUNEYOSHI
- 出版者
- 福岡女子大学文学部
- 雑誌
- 文芸と思想 (ISSN:05217873)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.53-85, 2002