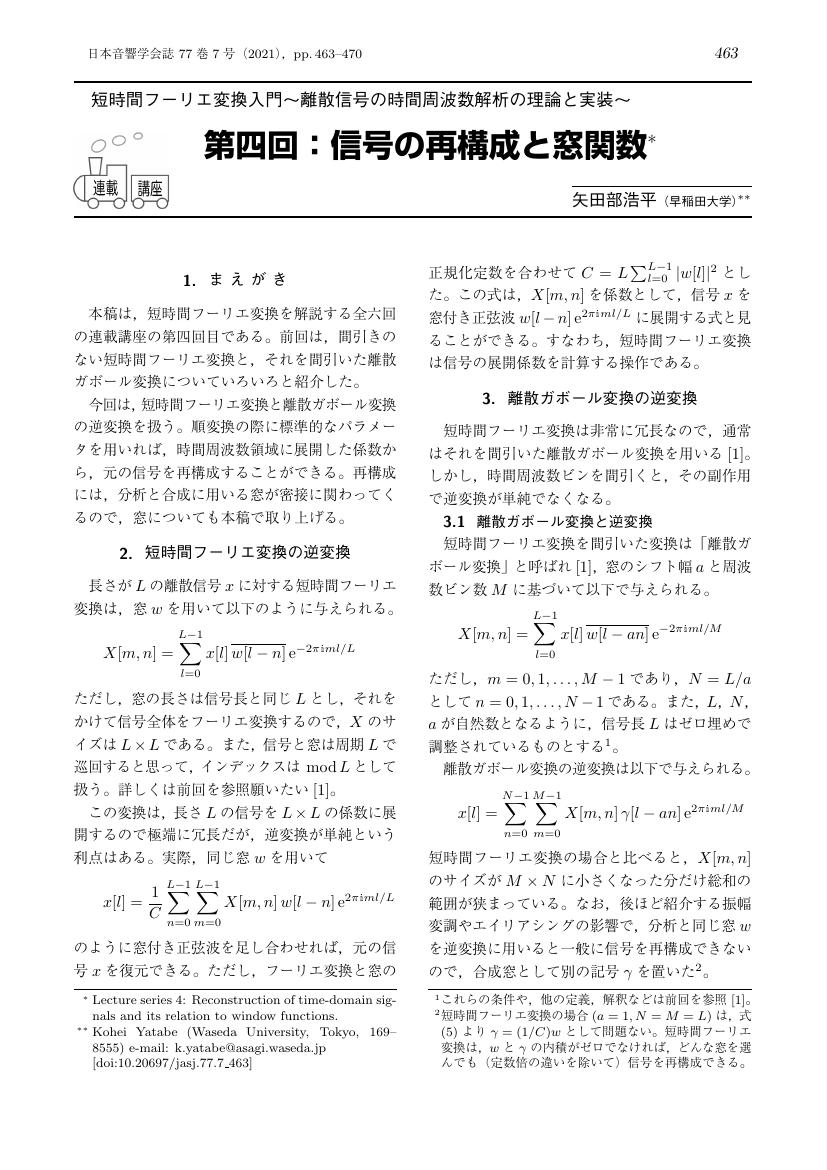29 0 0 0 OA 「特定地方交通線転換鉄道」の利用状況と路線再生の要因に関する研究
- 著者
- 井本 雅史 岩崎 義一 山口 行一
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 (ISSN:1348592X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.41-44, 2017 (Released:2017-07-30)
- 参考文献数
- 3
本稿では、地方鉄道の利用者数減少とそれに伴う地域衰退を背景に、鉄道会社が実施している路線活性化策に着目し、利用者の増加に効果的な要因を明らかにすることを研究目的とする。調査対象路線は特定地方交通線転換鉄道20社とし、利用者数等の統計データの収集と三角グラフ・回帰分析・数量化分析一類を用いて分析した。これらの分析から、利用者の増加には、定期外利用者に視点を置いた、地元食材や地酒を提供するイベント列車の運行が効果的であることが明らかになった。今後の課題として、地元食材の旬・調理方法・組み合わせ等の工夫や多様な情報発信を沿線地域と連携して行っていくことが、継続的な利用や地域の活性化にもつながると考える。
29 0 0 0 OA 希少種トウキョウサンショウウオ地域野生個体群を守り続ける道路ビオトープ
- 著者
- 大磯 毅晃 石坂 健彦 森崎 耕一 小谷地 進太 浅川 尚熙 国武 陽子
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.131-133, 2020-08-31 (Released:2020-12-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 2
1989年の千葉東金道路建設の際にトウキョウサンショウウオの生息地が確認され,1993年から1995年にかけて同道路近傍に代替産卵池の整備がなされた。2016年から2020年にかけて,その整備効果を把握することを目的として,地元大学との共同で同池及び周辺地域において産卵状況調査を行った。その結果,同池周辺地域において既存産卵水域は乾燥化などによる消失が多くみられた。一方,同池では年間平均100個以上もの卵塊が確認された。以上より,当池は整備後20年以上経過した現在も,なお効果を十分に発揮しており,道路建設により整備したビオトープが地域個体群の維持に欠かせないものとなっていることが示唆された。
29 0 0 0 OA スペクトル幾何学とグラフ理論
- 著者
- 浦川 肇
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.29-45, 2002-03-15 (Released:2017-04-08)
- 参考文献数
- 48
A brief survey on the spectral geometry of a finite or infinite graph is given. After the adjacency matrix, discrete Laplacian and discrete Green's formula are introduced, the spectral geometry of finite graphs, particularly, estimation of the first positive eigenvalue in terms of the Cheeger constant, examples of isospectral or cospectral graphs and the Faber=Krahn type inequality are discussed. For infinite graphs, spectrum of the discrete Laplacian, the heat kernel and Green kernel are estimated. Finally, a relation between the finite element method for the Dirichlet boundary eigenvalue problem and the eigenvalue problem of the adjacency matrix for a graph is given.
- 著者
- 川中 豪
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.34-49, 2021-03-15 (Released:2021-03-25)
- 参考文献数
- 29
29 0 0 0 OA 6AM1-A-1 ラピッドプロトタイピングの創作と特許(招待講演)
- 著者
- 小玉 秀男
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- マイクロ・ナノ工学シンポジウム 2013.5 (ISSN:24329495)
- 巻号頁・発行日
- pp.v-viii, 2013-11-04 (Released:2017-06-19)
The concept of rapid prototyping was created based on a technique of making a block copy for printing newspapers. It took a long time till the usefulness of the concept was accepted. A wide variety of practicing the concept was created. The patent application for the concept was abandoned due to law evaluation of the concept. Several modifications adopting the same concept were patented by others due to failure to disclose the modifications.
29 0 0 0 OA 新型コロナウイルス禍のアマビエにみる妖怪の社会的機能
- 著者
- 高橋 綾子 藤井 修平
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.93.20340, (Released:2022-02-10)
- 参考文献数
- 17
The purposes of this study are to clarify the relationship between attitudes toward Amabie (folkloric mermaid -like creature) during the COVID-19 calamity and traditional values, including everyday religious activities in Japan, and to explore the social functions of Yokai (Japanese supernatural creature and phenomena). Although Yokai have historically had both religious and entertainment roles, recent studies have shown that contemporary Yokai are only seen as entertainment. In Japan, however, Amabie has been attracting public attention for its historic ability to repulse plagues and therefore seems to have social functions other than entertainment. Study 1 used newspaper articles and other supporting materials to investigate the social prevalence of Amabie and the way people relate to it. Study 2 investigated attitudes towards Amabie and traditional values. The results suggested that with the expectations that Amabie could drive the plague off, Amabie evoked not only positive but also negative impressions, and for that reason, it might be accepted as a Yokai. This showed that the function of Yokai may change depending on the situation.
- 著者
- 阿曽 三樹 島雄 周平 岩崎 和美 井上 忠典 森村 司 岡田 しのぶ 三原 基之
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.352-358, 1989-04-01 (Released:2012-03-03)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
自家感作性皮膚炎1例, 尋常性乾癬4例, 計5例の患者に0.05% difluprednate軟膏30∼60g/dayを単純塗布し, 血清11-OHCS値, 末梢循環好酸球数, 血糖値の変動並びに臨床効果を観察した。外用中, 血清11-OHCS値は40g/day塗布3例中2例で明らかな低下が認められたが, 30g/day, 60g/day塗布各1例では低下は認められなかつた。末梢循環好酸球数は30g/day, 40g/day各1例で明らかに減少した。血糖値は40g/day 1例で一過性に上昇した。臨床効果は非常に優れていた。Difluprednate軟膏はその臨床効果と比較すると, 副腎皮質機能抑制作用は軽度であり, 臨床効果と全身作用の分離を示すコルチコステロイド外用剤と考えられた。
29 0 0 0 OA インターネット時代の灰色文献 灰色文献の定義の変容とピサ宣言を中心に
- 著者
- 池田 貴儀
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.193-203, 2015-06-01 (Released:2015-06-01)
- 参考文献数
- 21
インターネット時代における灰色文献の動向について,灰色文献の定義の変容,灰色文献資源の政策策定に関するピサ宣言の2つの視点を中心に,さまざまな角度から考察する。まず,灰色文献の定義について整理する。次に,定義に関連して,インターネット時代における灰色文献の現状や課題について触れる。最後に,2014年に公表された,灰色文献資源の政策策定に関するピサ宣言を取り上げ,灰色文献をめぐる最新の動向について紹介する。
- 著者
- Nobutaka Nagano Toshiyuki Nagai Yasuo Sugano Yoshiaki Morita Yasuhide Asaumi Takeshi Aiba Hideaki Kanzaki Kengo Kusano Teruo Noguchi Satoshi Yasuda Hisao Ogawa Toshihisa Anzai
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.7, pp.1601-1608, 2015-06-25 (Released:2015-06-25)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 20 29
Background:Basal thinning of the interventricular septum (IVS) is an important diagnostic feature of cardiac sarcoidosis (CS), but its long-term prognostic significance remains unclear.Methods and Results:We examined 74 consecutive patients who were diagnosed with CS. Basal IVS thickness at a point located 10 mm from the aortic annulus was measured. IVS thickness at the left ventricular minor axis level (IVS) was also measured according to the recommended procedure of the American Society of Echocardiography. Patients were divided into 2 groups based on the presence or absence of basal IVS thinning, which was defined as basal IVS ≤4 mm and/or basal IVS/IVS ratio ≤0.6. Basal IVS thinning was observed in 21 patients and was associated with greater long-term adverse events during follow-up (5.1±2.5 years), although the baseline characteristics were comparable between groups (overall, P<0.01; all-cause death, P=0.53; symptomatic arrhythmias, P<0.01; heart failure admission, P=0.027). Multivariate analysis showed basal IVS thinning was an independent determinant of long-term adverse events (hazard ratio 2.86, 95% confidence interval 1.31–6.14) even after adjustment for existing prognostic variables.Conclusions:The presence of basal IVS thinning at the time of CS diagnosis was associated with poor long-term clinical outcomes, suggesting its prognostic significance in patients with CS. (Circ J 2015; 79: 1601–1608)
29 0 0 0 OA 哲学史研究の哲学的意義
- 著者
- 松田 克進
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.68, pp.9-27, 2017-04-01 (Released:2017-06-14)
- 参考文献数
- 23
In this paper, the author offers an overview of some methods that have thus far been used in research on the history of philosophy. From the perspective of philosophical importance, the paper further discusses which kinds of methods are relevant or irrelevant. The examples which are specifically examined in this paper are those of Harry Wolfson, an expert in Medieval Philosophy who treated the history of philosophy exclusively from the view point of diachronic influences; Martial Gueroult, the renowned historian of twentieth century France who studied the internal structure or ‘order of reasons’ of several great philosophical systems of the past; and Jonathan Bennett who examined the history of modern philosophy in the manner of analytic philosophy. After indicating the problem with Wolfson’s method, as well as the difficulty with the idea of Dianoématique which Gueroult developed while producing his monumental works on great philosophers, the author concludes that another possible philosophically significant approach is a method which consists of analyzing the internal structure of some of the past’s philosophical doctrines (like Gueroult and others) and daring (unlike Gueroult) to criticize weaknesses, e. g. an inconsistency, in them. The author calls this method “non-idolizing or de-idolizing structuralism.”
- 著者
- 林 武
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.151-153, 1975-09-30 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 大山 貴稔
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.113-131, 2018-12-31 (Released:2022-03-14)
29 0 0 0 OA 第四回:信号の再構成と窓関数
- 著者
- 矢田部 浩平
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.7, pp.463-470, 2021-07-01 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 6
29 0 0 0 OA 原子力発電所の立地規制と地帯整備基本計画
- 著者
- 乾 康代
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.507-512, 2014-10-25 (Released:2014-10-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
本研究は,1954年に始まる原子力政策の黎明期につくられた原子炉立地審査指針や東海村を対象とした整備計画について分析した。主な結果は以下のとおりである。1)東海原子力発電所は,統一基準のない時期に,個別審査により,米軍射爆場隣接地という立地上の問題を残して1959年に設置許可された。2)1964年に作成された原子炉立地審査指針は、原子炉周辺の人口抑制条件を求めたものの,設置審査目的を超えてその実現手段は示せなかった。3)1959年,原子力委員長となった中曽根康弘は原子力都市計画法を構想したが,法成立には至らず,その後,代わって,原子力委員会部会が,原子炉をグリーンベルトと人口抑制の2地区で取り囲む3重構成を示す答申を出した(1964年)。4)しかし,翌1965年,答申を受けて茨城県が作成した地帯整備基本計画では,グリンベルトは一部のみの採用,人口抑制の2地区は採用されず,東海村の都市計画は不完全な形で出発することとなった。
29 0 0 0 OA 私のブックマーク:金融情報学
- 著者
- 和泉 潔
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.88-94, 2022-01-01 (Released:2022-01-01)
29 0 0 0 OA 日本におけるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの実際
- 著者
- 長谷川 世一
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.343-352, 2015-08-01 (Released:2015-08-01)
- 参考文献数
- 23
2015年現在,クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは今やインターネット上における著作権に関するパブリックライセンスのグローバル・スタンダードとなった。また,クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの活用方法も日々さまざまな形で変化し続けており,日本においても独特な活用事例がいくつか見られるようになっている。世界におけるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの普及状況を報告した後,日本におけるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの活用事例を紹介する。
- 著者
- 村田 浩一
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.41-47, 2019-07-11 (Released:2019-09-15)
- 参考文献数
- 16
日本に初めて誕生した動物園は,フランス革命直後の1794年に開園したパリ国立自然史博物館内の植物園附属動物園(Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes)をモデルにしている。幕末にそこを訪れた田中芳男や福澤諭吉は,西欧文化や博物学の奥深さに驚いたことだろう。当時の動物園(メナジェリー)には,ラマルク,サンチレール,そしてキュヴィエなど,現在もなお名を馳せている学者たちが関与していた。動物園の歴史が,博物学や動物学や比較解剖学などの学術研究を基盤としている証左である。しかし,本邦の動物園は,その基盤の重要性を認識していた形跡が明治時代の文書である「博物館ノ儀」に認められるにも関わらず,上野公園に動物園が創設されて以降とくに戦後の発展過程において継承されることなく現在に至っている。国内動物園で学術研究が滞っているのは,研究環境が十分に整っていないことが原因であるのは確かだ。だが,それだけだろうか? 現今の停滞を打開するために日本の動物園関係者が必要とするのは,200年以上に及ぶ動物園における学術研究の歴史を背負い,時代に応じた新たな研究を興し,その成果を世界に向けて発信する覚悟ではないかと思う。動物園が歴史的に大切にしてきた“研究する心”を持って新たな未来を切り開くために闘い続けるべきであろう。
29 0 0 0 OA 変数選択理論の現況
- 著者
- 柴田 里程
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.344-352, 1984-11-09 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 73
29 0 0 0 OA 「上農は草を見ずして草をとる」ということわざの解釈の変遷
- 著者
- 三浦 励一
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.54-57, 2015 (Released:2015-07-17)
- 参考文献数
- 31
29 0 0 0 OA 『分析手帖』と『マルクス=レーニン主義手帖』 1960 年代フランスにおける学知、革命、文学
- 著者
- 坂本 尚志
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, pp.255-269, 2019 (Released:2019-10-25)