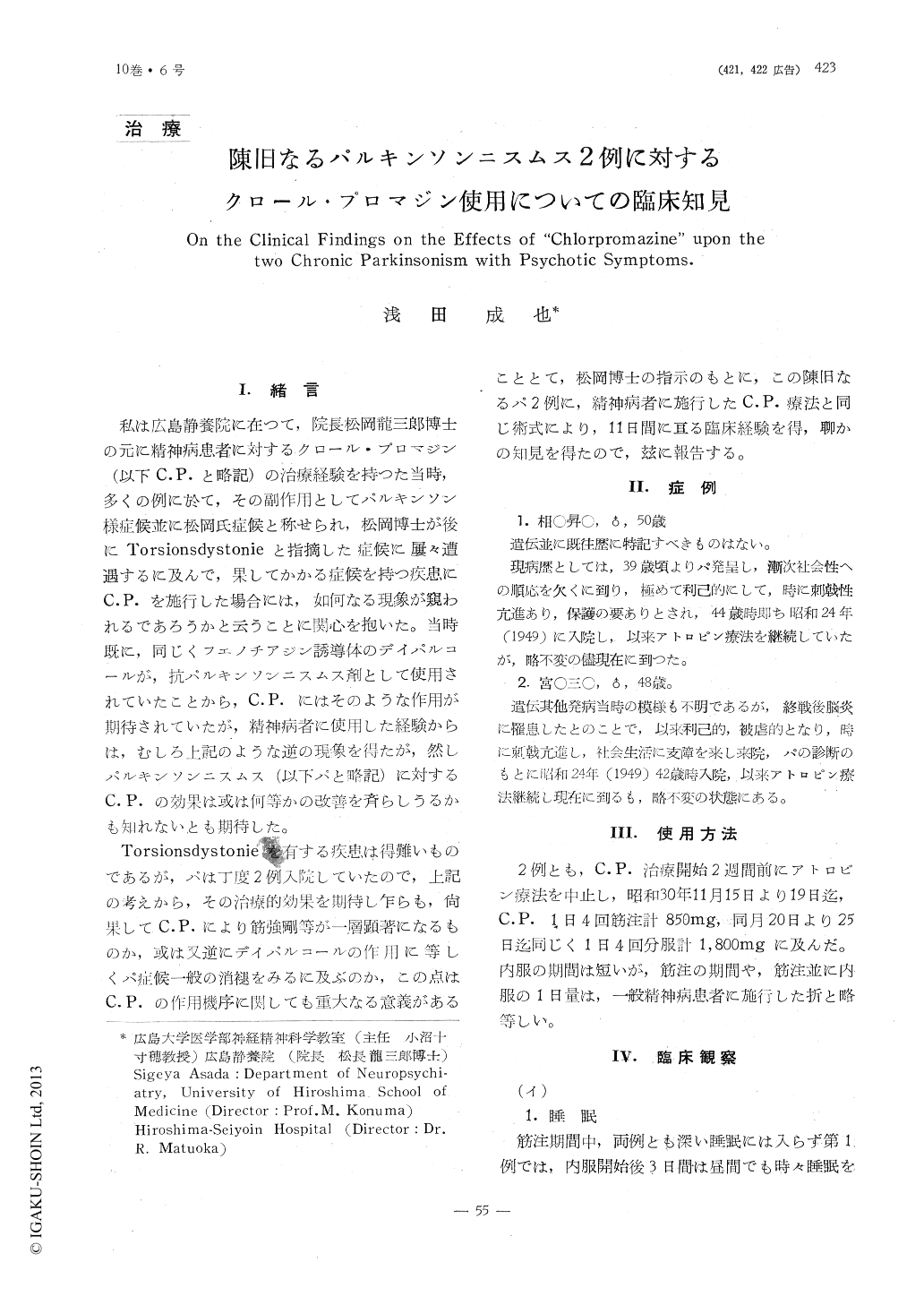1 0 0 0 IR 生涯学習施設としての公共図書館 : 「体験」は図書館サービスなのか
- 著者
- 日向 良和 HINATA Yoshikazu
- 出版者
- 都留文科大学
- 雑誌
- 都留文科大學研究紀要 (ISSN:02863774)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, pp.161-173, 2017
近年新設された公共図書館において、調理室や工作室、音楽スタジオ等を同一建物内に備えて、調理、3 D プリンタ等出力、バンド練習など、さまざまな体験活動をおこなうことができる図書館が出現している。これらの活動がおこなわれている図書館を訪問し、その共通する特徴として、「読む・調べる→考える→やってみる」という活動の特徴があることを認識した。この認識を基に、これまでの公共図書館でおこなわれてきた資料・情報提供サービス(読書含む)の他に、これらの体験活動をサービスとして提供することの是非を検討した。本稿では体験活動を公共図書館の役割を越えるものであるとし、生涯学習施設における図書館機能の提供と位置づけ、否定的なものでないと結論づけた。
- 著者
- パーリ学仏教文化学会 = Society for the Study of Pali and Buddhist Culture
- 出版者
- パーリ学仏教文化学会
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 漢訳仏典における「倶生神」の解釈
- 著者
- 長尾 佳代子
- 出版者
- パーリ学仏教文化学会
- 雑誌
- パーリ学仏教文化学 (ISSN:09148604)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.55-66, 1999
1 0 0 0 OA 失語症患者の自動車運転再開支援
- 著者
- 奥野 隆司 井上 拓也 吉田 希 仲野 剛由 西岡 拓未 石黒 望 一杉 正仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.24-31, 2018 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 18
失語症患者において自動車運転再開に必要な言語能力を明らかにすること、失語症患者に対する効果的な運転支援策を明らかにすることを目的に、脳卒中後の失語症患者で運転再開に至った6症例を検討した。失語症の検査として、Standard Language Test of Aphasia(SLTA)を実施した。神経心理学的検査として、Mini Mental State Examination(MMSE)、Trail Making Test(TMT)-AおよびB、Kohs立方体組み合わせテストを実施した。運転の評価・訓練には、簡易ドライビングシミュレーター(DS)を用いた。SLTAにおいて文字認識・理解は全6人で良好であった。一方、6人全員が減点されたのは「口頭命令に従う」・「語の列挙」であった。神経心理学的検査では、MMSEで基準値を下回った者が3人、TMT-Bを完遂できなかった者が1人であった。DSでは、訓練当初から運転能力にほぼ問題のなかった者が3人、訓練当初は運転能力に問題はあったものの徐々に改善がみられた者が3人であった。失語症の検査で文字認識・理解の程度を把握することは重要である。そして、失語症患者では、神経心理学的検査だけで運転再開の可否を判断することは困難であり、DSを用いた運転評価及び訓練が有用であった。失語症患者では、神経心理学的検査や文字認識・理解の程度を評価したうえで、DSを用いた運転能力の評価と訓練を継続的に実施することが重要である。
1 0 0 0 OA 学校教育における神話教材整備のための予備調査
小学校低学年の国語授業における伝統的言語文化の教え方について、現場教員から現状の問題点について意見を聞いた。それを受けて、教材の提示や教え方に工夫をした模擬授業を行った。教員からの反応は総じて好意的であった。本研究ではより広い展望を得る準備段階として、まず小学校低学年の国語教育に範囲を限定した調査を行ったが、小学生児童も成長し、その後は高校段階になると、古文では『古事記』神話に出会い、また日本史の授業では古代の資料として『古事記』や『日本書紀』に出会い、伝統的言語文化での記述をどのように理解するかという別の形での教育が必要となる。本研究ではそうしたより高学年での対応についても提言を試みた。
- 著者
- 杉田 征吾
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国大国語教育研究 (ISSN:13411950)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.5-13, 1999-05
I.緒言 私は広島静養院に在つて,院長松岡龍三郎博士の元に精神病患者に対するクロール・プロマジン(以下C.P.と略記)の治療経験を持つた当時,多くの例に於て,その副作用としてパルキンソン様症候並に松岡氏症候と称せられ,松岡博士が後にTorsionsdystonieと指摘した症候に屡々遭遇するに及んで,果してかかる症候を持つ疾患にC.P.を施行した場合には,如何なる現象が窺われるであろうかと云うことに関心を抱いた。当時既に,同じくフエノチアジン誘導体のデイパルコールが,抗パルキンソンニスムス剤として使用されていたことから,C.P.にはそのような作用が期待されていたが,精神病者に使用した経験からは,むしろ上記のような逆の現象を得たが,然しパルキンソンニスムス(以下パと略記)に対するC.P.の効果は或は何等かの改善を斉らしうるかも知れないとも期待した。
1 0 0 0 OA 照度レベルに依存するコントラスト感度の加齢変化
- 著者
- 岩田 三千子 岡嶋 克典 氏家 弘裕
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.5, pp.352-359, 2001-05-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 4 7
We measured contrast sensitivity function in the vision of young and aged observers under combinations of four different illuminance levels (1, 10, 100, and 1000 lx) and three different color temperatures (3000, 5000, and 6700K). We found that (i) no systematic difference appeared across color temperatures, (ii) the sensitivity was relatively worse in aged observers at higher spatial frequencies when the illuminance was high and at all spatial frequencies examined when the illuminance was low, and (iii) the deterioration cannot be explained only by the equality of retinal effective illuminance. These results suggest that the contrast sensitivity function can be used as the basis of lighting design for different visual tasks.
1 0 0 0 OA クロアカ接種法による免疫応答
- 著者
- 杉森 義一 正木 俊一郎 小西 喬郎 林 幸之
- 出版者
- Japan Poultry Science Association
- 雑誌
- 日本家禽学会誌 (ISSN:00290254)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.309-317, 1990-07-25 (Released:2008-11-12)
- 参考文献数
- 21
鶏の敗血症大腸菌症より分離した大腸菌(O2型)を用いて4種類の不活化抗原液(BF:約109CFU/ml含む培養菌液,BFS:BF液を超音波処理した菌液,CF:BF液を遠心によって,約1010CFU/mlに濃縮した菌液,CFS:CF液を超音波処理した菌液)を調整した。これら抗原液を1日齢ヒナにクロアカ接種法(pa法)で免疫,その後20日目にホモ株の致死量を静脈内攻撃し,攻撃後7日後の生存率で評価した。抗原液の内,超音波処理を施したBFSとCFS液で攻撃による生存率が統計的に有意であったが,含有菌量が約10倍量多いCFS液の方が強かった(P<0.01)。一方,超音波処理を施していないBF液とCF液では,生存率の改善傾向は見られたが,その効果は有意ではなかった。超音波処理は,15分間(5分間を3回)で最も強い免疫効果が得られた。その効果はKetodeox-yoctonate (KDO)値や抗体結合性などに相関性が認められ,in vitroでの重要な指標となった。CFS液をpa,筋肉内あるいは皮下接種法で接種した時の免疫性と安全性を調査したところ,免疫効果はpa法(P<0.01)と筋肉内接種法(P<0.05)で認められた。安全性は筋肉内や皮下接種法では接種後の体重増加が有意(P<0.01)に低下したが,pa法ではこのような現象は観察されなかった。CFS液のpa法による免疫効果は接種7日目以降27日間にわたると推察されたが,O抗原型が異なるO78型の攻撃に対して,効果を認めなかった。
- 著者
- 小栗 貴弘 長澤 順 岸本 智典 青木 章彦
- 出版者
- 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部教職実践センター
- 雑誌
- 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部教職実践センター研究紀要 (ISSN:2188580X)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.57-67, 2018-02-28
1 0 0 0 「実証主義」の興亡:―科学哲学の視点から―
- 著者
- 野家 啓一
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.3-17, 2001
「実証主義」および「実証的方法」の起源、歴史的展開、現状を科学史・科学哲学の観点から概観する。科学における実証的方法は、17世紀の科学革命を推進した「実験哲学」の精神に由来し、19世紀半ばに「観察-実験」および「検証-反証」の手続きを組み合わせた「仮説演繹法」として定式化された。社会科学の領域に実証的方法が導入され、古典的実証主義が成立するのも、この19世紀半ばのことである。20世紀に入ると、「論理実証主義」を標榜するウィーン学団が「統一科学」を目標に掲げ、自然科学と社会科学の方法的統合を試みた。しかし、物理学の統一言語によって社会科学をも自然科学に同化吸収しようとするラディカルな還元主義は、種々の困難から中途で挫折せざるをえなかった。論理実証主義に代わって登場した「ポスト実証主義」の潮流は、「観察の理論負荷性」や「決定実験の不可能性」などのテーゼを提起することによって、「実証性」の理解に重大な変更を迫った。それを踏まえるならば、自然科学と社会科学の関係もまた、「階層関係」ではなく「多元的共存」の形で捉え直されねばならない。
【目的】コラーゲン分子の大部分は3重らせん構造をとっており,さらに分子間は架橋構造により結合・安定化されている。代表的な成熟架橋成分としてはピリジノリンの存在が報告されており,生体の加齢によりその量が増加するなど,分子あるいは組織の安定化にピリジノリンが大きく関与していると考えられている。しかしながら従来の研究は哺乳類が中心となっており,魚類コラーゲンのピリジノリンに関する研究例は少ない。そこで本研究では,魚類コラーゲン中のピリジノリン量を魚種間で定量・比較し,コラーゲンの安定性との相関性について考察した。【方法】佐藤らの方法に基づき,0.1N NaOHを用いてハマチ・マダイの活魚の筋肉および表皮より粗コラーゲン画分を抽出した。凍結乾燥後,約100mgのコラーゲンを6N塩酸で加水分解し,塩酸を蒸発乾固した。次にn-ブタノール:酢酸:水=4:1:1の混合液で平衡化したCF-11カラムに試料を添加・吸着させた後,蒸留水で溶出した。蒸発乾固した試料に0.02N塩酸を加えて溶解し,日立アミノ酸分析計(L-8500)を用いて蛍光検出器(ex. 295nm, em. 395nm)によりピリジノリンを検出・定量した。【結果】試料をCF-11カラムに吸着させることで効果的に他のアミノ酸を除去することができた。またニンヒドリン発色の場合と比較することにより,蛍光によって検出されたピークは生体構成アミノ酸ではないことが確認された。ピリジノリン含量はマダイにおいてハマチの2〜2.5倍となったが,表皮と筋肉とで比較した場合には、両魚種の間で顕著な違いは認められなかった。筋肉の死後変化において,マダイのコラーゲンはハマチよりも構造的に安定であるが,このことにピリジノリン量の違いが影響している可能性が考えられた。
1 0 0 0 OA 二重労働市場と失業補償
- 著者
- 阿部 太郎
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学 ディスカッションペーパー = Discussion Paper
- 巻号頁・発行日
- no.134, pp.1-12, 2020-03
1 0 0 0 OA セナガアナバチの二三の生活記録
(1) I found Ampulex amoena Stal in Kyoto first in the summer of 1951. Since then the wasp was observed every year in my garden. It appears in June and disappears in late autumn. In 1954 the first ♀ was found on June 21 while in 1956 on June 29 and the last ♀ was seen on Nov.13 in 1955. (2) The adult wasps (♀♂) seems to suck in sap oozing out from the points injured by the rostrum of cicadas (Graptopsaltria nigrofuscata Motschulsky and Platypleura kaempheri Fabricius on Abies and other trees. (3) The female wasp hunts the medium-sized nymph of Periplaneta picea Shiraki and hides it in some crevices of wooden buildings to oviposit on it. At 2 p.m. on Aug. 13, 1956, I observed only once her hunting habit in a small glass box (7×5×0.5 cm.) made as a cage for artificial ant nest. "She grasped one of the cockroach legs with her mandibles to prevent it from escape and soon changed her grasping point to the edge of its 2nd abdominal tergite. She stretched her abdomen towards the ventral surface of its thorax to sting it at the base of one of its coxae. The stinging point was not ascertained. Then she seized it by the proximal portion of its antennae and stung it 3 times behind its gular region. She began to transport it seizing by its antennae." (4) The paralyzed cockroach (18 mm. long) had short-cut antennae (6 mm. long) and was able to move its legs violently when stimulated but not walk voluntarily. It could suck up fruit juice the next day. The wasp egg (2.5×0.95 mm.) was attached longitudinally along the basal portion of one of its mesocoxae, directing its cephalic pole proximad. (5) The above egg hatched at 6 : 35 a.m. on Aug. 15. After sucking up the body fluid, the larva began to devour the prey at 15 p.m. on Aug. 17 and the prey lost its response ability. On Aug. 20 the larva spun its cocoon and on Sep. 19 a female wasp came out from this cocoon.
1 0 0 0 セナガアナバチの二三の生活記録
(1) I found Ampulex amoena Stal in Kyoto first in the summer of 1951. Since then the wasp was observed every year in my garden. It appears in June and disappears in late autumn. In 1954 the first ♀ was found on June 21 while in 1956 on June 29 and the last ♀ was seen on Nov.13 in 1955. (2) The adult wasps (♀♂) seems to suck in sap oozing out from the points injured by the rostrum of cicadas (Graptopsaltria nigrofuscata Motschulsky and Platypleura kaempheri Fabricius on Abies and other trees. (3) The female wasp hunts the medium-sized nymph of Periplaneta picea Shiraki and hides it in some crevices of wooden buildings to oviposit on it. At 2 p.m. on Aug. 13, 1956, I observed only once her hunting habit in a small glass box (7×5×0.5 cm.) made as a cage for artificial ant nest. "She grasped one of the cockroach legs with her mandibles to prevent it from escape and soon changed her grasping point to the edge of its 2nd abdominal tergite. She stretched her abdomen towards the ventral surface of its thorax to sting it at the base of one of its coxae. The stinging point was not ascertained. Then she seized it by the proximal portion of its antennae and stung it 3 times behind its gular region. She began to transport it seizing by its antennae." (4) The paralyzed cockroach (18 mm. long) had short-cut antennae (6 mm. long) and was able to move its legs violently when stimulated but not walk voluntarily. It could suck up fruit juice the next day. The wasp egg (2.5×0.95 mm.) was attached longitudinally along the basal portion of one of its mesocoxae, directing its cephalic pole proximad. (5) The above egg hatched at 6 : 35 a.m. on Aug. 15. After sucking up the body fluid, the larva began to devour the prey at 15 p.m. on Aug. 17 and the prey lost its response ability. On Aug. 20 the larva spun its cocoon and on Sep. 19 a female wasp came out from this cocoon.
1 0 0 0 IR 大学における性教育についての一考察 : 短期大学生における性意識と性行動の調査から
- 著者
- 小川 真由子 引田 郁美 Mayuko Ogawa Ikumi Hikita 鈴鹿大学短期大学部 鈴鹿大学短期大学部 Suzuka Junior College Suzuka Junior College
- 出版者
- [鈴鹿大学短期大学部紀要編集委員会]
- 雑誌
- 鈴鹿大学短期大学部紀要 = Journal of Suzuka Junior College (ISSN:21896992)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.75-85, 2016
本研究の目的は、短期大学生における性行動および性意識に関する調査を行い、現状と課題を明らかにすることであり、今後の大学における性教育の課題を検討する一助とするものである。短期大学部1年生を対象に性意識と性行動に関する質問紙調査を行った。性交経験率は43.4%であり、妊娠経験については、11 名が「妊娠の経験あり」と答え、そのうち「妊娠中絶をした」と回答したものが4件あり、望まない妊娠を防ぐための性教育の必要性が伺える結果となった。また、「結婚に関係なく、性行為をしてもいい」と答えたのは48%で、性交経験者への質問のうち、「避妊をしなかった」という回答が12%であった。性についての知識を学ぶものとして望ましいと考えているのは、「学校・教師」が最も多く挙げられ、情報源として多く挙げられた「雑誌・漫画」や「テレビ・ビデオ」、「インターネット」は望ましいものとしては考えていないという結果であった。これまで受けた性教育への印象は否定的なものが多く、大学生の教育や指導のニードに応えられるような対策に加えて、性教育の授業構成や教授方法の工夫が必要であると考えられる。結婚願望については、65%が「ある」と回答していたが、それ以上に「将来、子どもが欲しいと考えている」回答が76%と上回り、その多くが複数の子どもを希望していた。今後は将来構想についての人生設計を含めた性教育の実施が望まれる。
1 0 0 0 OA 黒田三郎詩集『ひとりの女に』(読む)
- 著者
- 宮崎 真素美
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.64-68, 1992-08-10 (Released:2017-08-01)
- 著者
- 俵木 悟
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.205, pp.435-458, 2017-03-31
柳田國男は一九三〇年代から、特定の時代・地域の人びとにおける「良い/悪い」や「好き/嫌い」といった感性的な価値判断を「趣味」という言葉でとらえ、心意現象の一部として民俗資料に含めることを提唱していた。これを展開した千葉徳爾は、芸術・娯楽に関わる民俗資料に「審美の基準」を位置づけた。本稿は、従来の民俗学が十分に論じてこなかったこの「趣味」や「審美の基準」を、民俗芸能の具体的事例にもとづいて論じる試みである。鹿児島県いちき串木野市大里の七夕踊りは、ナラシと呼ばれる一週間の稽古の過程において、各集落から選ばれた青年による太鼓踊りの評価が行われる。その評価が地域の人びとの関心を集め、多様な「良い踊り」に関する多様な言語表現や、流派に関する知識、技法の細部へのこだわり、踊りの特徴を継承する筋の意識などを生み出し伝えている。それらを手がかりとして、この踊りに関わる人びとにとって「良い踊り」という評価がどのように構成されているのかについて考察した。大里七夕踊りの場合、その評価の際だった特徴は、「成長を評価する」ということである。単に知覚的(視覚的・聴覚的)に受けとられる特徴だけでなく、踊り手がどれだけ十分に各人の個性を踊りで表現し得たかが評価の観点として重視されていた。これは近代美学における審美性の理解からは外れるかもしれないが、民俗芸能として生活に即した環境で演じられる踊りの評価に、文化に内在する様々な価値が混然として含まれるのは自然なことであろう。大里七夕踊りの場合、そのような価値を形成してきた背景には、近代以降に人格の陶冶の機関として地域の生活に根付いてきた青年団(二才)によって踊りが担われてきたという歴史が強く作用していると考えられる。
1 0 0 0 OA <資料>ルーマニア社会主義共和国憲法
- 著者
- 奥原 忠弘 Okuhara Tadahiro
- 出版者
- 神奈川大学
- 雑誌
- 神奈川法学
- 巻号頁・発行日
- vol.3(1), pp.145-161, 1968-01-31
1 0 0 0 IR 学習院と音楽 : 明治・大正期の音楽教育をめぐる資料解釈の試み
- 著者
- 玉川 裕子
- 出版者
- 桐朋学園大学
- 雑誌
- 桐朋学園大学研究紀要 (ISSN:03855627)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.81-107, 2016