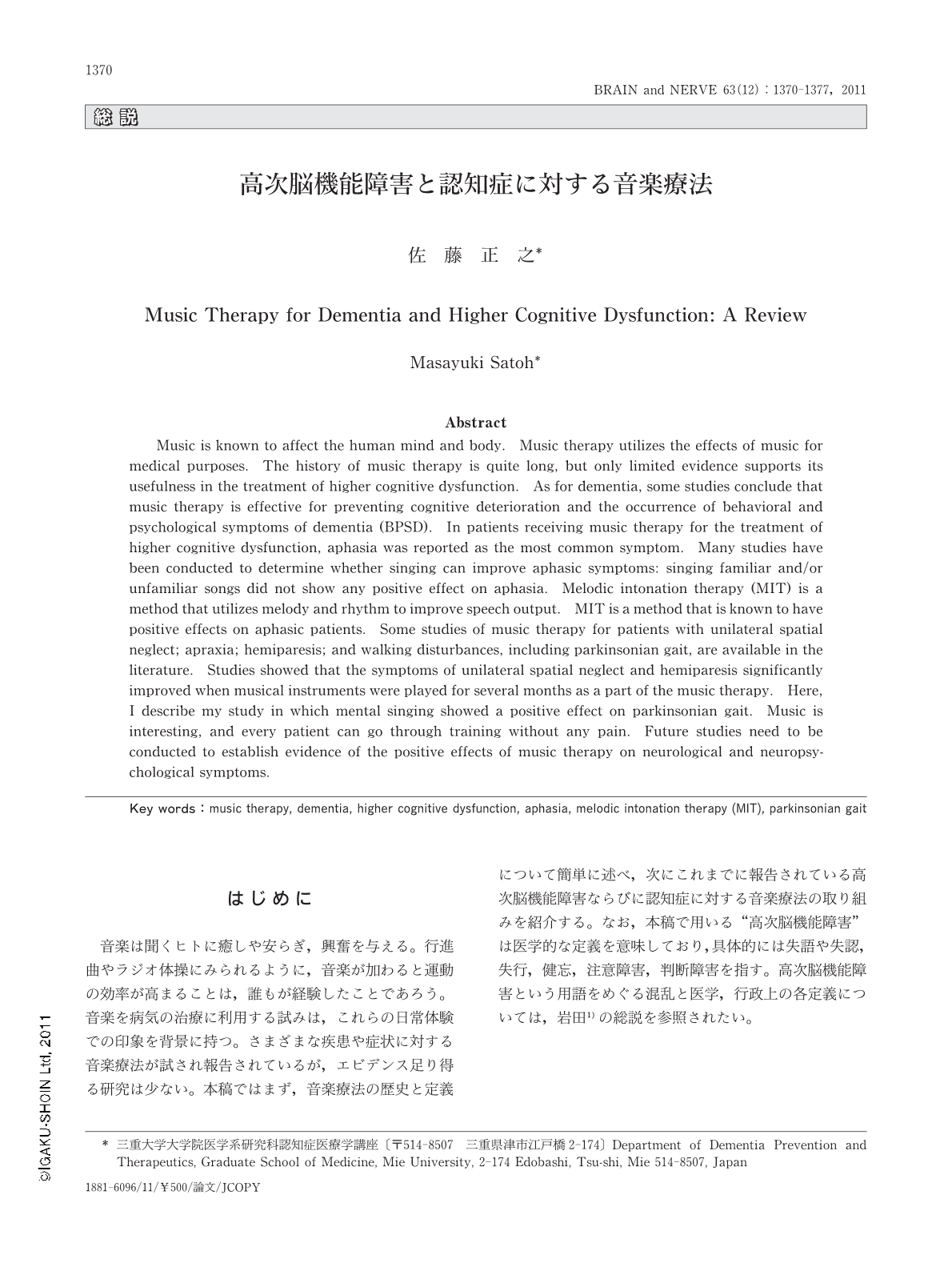1 0 0 0 神楽歌「杖」をめぐって (大谷雅夫教授退職記念特輯(第1))
- 著者
- 田林 千尋
- 出版者
- 臨川書店
- 雑誌
- 国語国文 (ISSN:09107509)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.4, pp.45-59, 2017-04
- 著者
- 篠原 啓子 圓藤 勝義 澤田 英司 永峰 賢一 水口 博之 福井 裕行
- 出版者
- 徳島県立農林水産総合技術支援センター
- 雑誌
- 徳島県立農林水産総合技術支援センター研究報告 = Bulletin of Tokushima Agriculture, Forestry and Fisheries Technology Support Center (ISSN:21891176)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.7-13, 2016-11
国内で流通する同年度同時期に収穫したレンコンを集め,品種・系統の由来により大別するとともに,大別したグループ毎で違いがあるのか,同一品種・系統といわれているものでも産地間で違いがあり形状が違うのか調査した。供試したレンコンは,国内の主要産地(茨城県,徳島県,佐賀県,愛知県,山口県,石川県,新潟県)の15種類で,「中国種」が6種類,「備中種」が2種類,「金澄系」が6種類,「その他」が1種類であった。肥大根茎の長さは,「備中種」が長く,「金澄系」と「その他」が短く,中国種がその中間であった。「中国種」のロータスは,徳島県産が愛知県産より長く,産地間で違いがあった。レンコンの肥大指数は,「備中種」が小さく,「金澄系」と「その他」が大きく,「中国種」はその中間であった。一方,肥大根茎の直径と肉厚比は,グループ間や産地間で違いはなかった。
1 0 0 0 高次脳機能障害と認知症に対する音楽療法
はじめに 音楽は聞くヒトに癒しや安らぎ,興奮を与える。行進曲やラジオ体操にみられるように,音楽が加わると運動の効率が高まることは,誰もが経験したことであろう。音楽を病気の治療に利用する試みは,これらの日常体験での印象を背景に持つ。さまざまな疾患や症状に対する音楽療法が試され報告されているが,エビデンス足り得る研究は少ない。本稿ではまず,音楽療法の歴史と定義について簡単に述べ,次にこれまでに報告されている高次脳機能障害ならびに認知症に対する音楽療法の取り組みを紹介する。なお,本稿で用いる“高次脳機能障害”は医学的な定義を意味しており,具体的には失語や失認,失行,健忘,注意障害,判断障害を指す。高次脳機能障害という用語をめぐる混乱と医学,行政上の各定義については,岩田1)の総説を参照されたい。
- 著者
- 金子 信博 井上 浩輔 南谷 幸雄 三浦 季子 角田 智詞 池田 紘士 杉山 修一
- 出版者
- 日本土壌動物学会
- 雑誌
- Edaphologia (ISSN:03891445)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.31-39, 2018
人間によるさまざまな土地管理は,そこに生息する土壌生物にも大きな影響を与え,土壌生物群集の組成やその機能が,さらにそこに生育する植物の生長にも影響している.農業においても保全管理を行うことで土壌生物の多様性や現存量を高めることが必要である.日本におけるリンゴ栽培は,品種改良と栽培技術の向上により,世界的に高い品質を誇るが,有機栽培は困難であると考えられている.青森県弘前市の木村秋則氏は, 独自の工夫により無施肥, 化学合成農薬不使用による有機栽培を成功させている.その成功の理由については地上部の天敵が増加することや,リンゴ葉内の内生菌による植物の保護力が高まることが考えられているが,土壌生態系の変化については十分調べられていない.そこで,2014 年 9 月に, 木村園(有機) と隣接する慣行リンゴ園, 森林の 3 箇所で土壌理化学性,微生物バイオマス,小型節足動物,および大型土壌動物の調査を行い,比較した.有機の理化学性は,慣行と森林の中間を示したが,カリウム濃度はもっとも低かった.AM 菌根菌のバイオマス, 小型節足動物, 大型土壌動物の個体数は有機で最も多く, 慣行で最も少なかった.特にササラダニの密度は有機が慣行の 10 倍であった.落葉と草本が多く,土壌孔隙が多いことが,有機での土壌生物の多様性および現存量を高めており,植物に必要な栄養塩類の循環と,土壌から地上に供給される生物量を増やすことで,天敵生物の密度を高めることが予測できた.
1 0 0 0 OA カメルーン首都ヤウンデをめぐる都市-農村間の農作物流通と女性商人の商業活動
1 0 0 0 OA Latest advances in antiaging medicine
- 著者
- Terry Grossman
- 出版者
- The Keio Journal of Medicine
- 雑誌
- The Keio Journal of Medicine (ISSN:00229717)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.85-94, 2005 (Released:2006-06-20)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 9 10
Rapid progress is being made in our ability to modify the aging process. Rather than serving as a period of debility and decreasing health, for many people, the later years of life are becoming a period of continued productivity, independence and good health. Progress is also being made in increasing average lifespan. The leading causes of death (cardiovascular disease, cancer, lung disease, diabetes) are the end result of decades-long processes. With current knowledge, it is possible to delay the onset of these diseases. This can be assisted by lifestyle choices incorporating healthful diet, exercise, stress management, and nutritional supplementation. Emerging genomics technology will allow individuals to establish personalized programs, while early detection of heart disease and cancer will contribute to longevity. Biotechnological therapies involving stem cells, recombinant DNA, proteomics, therapeutic cloning and gene-based therapies are expected to play major roles in promoting successful aging. We are at the threshold of artificial intelligence (AI) and nanotechnology (NT). AI will allow for a merging of our biological thinking with advanced forms of non-biological intelligence to vastly expand our ability to think, create and experience. NT will ultimately allow us to build devices able to build molecules much like our current cellular machinery does, one atom at a time. It is the goal of today’s antiaging medicine to forestall disease and aging long enough for people to utilize the powerful biotechnology and nanotechnology therapies that will be developed over the decades ahead. These future therapies have the potential to greatly extend longevity.
1 0 0 0 IR 根室地域における屯田兵村と神社の研究--士族屯田としての和田兵村と太田兵村を中心に
- 著者
- 遠藤 由紀子 Yukiko ENDO
- 出版者
- 昭和女子大学文化史学会
- 雑誌
- 昭和女子大学文化史研究 (ISSN:13463993)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.35-57, 2006
1 0 0 0 OA カレーの効能・効果と新規レシピの考案
- 著者
- 栗 彩子 森 美紗希 宮内 莉華 谷口(山田) 亜樹子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成29年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.132, 2017 (Released:2017-08-31)
【目的】カレーはインドで生まれ、明治時代に日本に入ってきたと言われている。今日では日本の国民食とまで言われるようになり、各地域の名産品やその土地で取れる食材を使ったいろいろなカレーが食べられている。さらに近年、健康志向の高まりにより、カレーの栄養価値が見直され、その第3次機能に強い関心が寄せられている。しかしながら、カレーの利用方法といえば「カレーライス」というように、そのバリエーションには限りがあり、カレーに含まれるスパイスの種類や栄養価値もあまり知られていないのが現状である。そこで演者らは、カレーの基礎特性を明らかにし、健康効果・効能につて考え、さらに地場産の食材を用いた、簡単においしくできる新たなカレーレシピの考案を試みることとした。【方法】文献調査から、カレーの基礎特性を明らかにし、どのような健康効果・効能をもたらすのかを検討した。 新規料理については、市販カレー粉、神奈川県産のキャベツ、しらす、大豆、雑穀を用いて新たなカレー料理を考案し、調理した。また、栄養計算を行った。【結果】(1)カレーの基礎特性文献調査より、カレーには30種類以上の様々なパイスが存在することがわかった。中でも代表的なものとして、コリアンダー、クミン、フェヌグリーク、ターメリック、オレガノ、ペッパー、フェネル、ジンジャー、オニオン、カルダモンなど10種類のスパイスがカレーに用いられている。また、これらのスパイスについてさらに調査した結果、漢方薬として使われていたものが多く、肝臓・胃腸の働きを良くする、せき止め、疲労回復、殺菌作用、下痢止め、風邪・肥満・二日酔い・冷え性・肩凝り予防など様々な健康効果があることがわかった。(2)新規カレーレシピの紹介神奈川県産の食材を用いてカレー春雨、 カレー鍋、カレー雑穀リゾット、大豆カレーの4つのレシピを考案し調理した。
1 0 0 0 IR 一演奏家の表現形式より省みる現場教育の実践--日本語教授法・日本語教育を中心的事例として
- 著者
- 岩佐 靖夫
- 出版者
- 尚美学園大学芸術情報学部
- 雑誌
- 尚美学園大学芸術情報学部紀要 (ISSN:13471023)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.69-80, 2005-12
ウラディーミル・ホロヴィッツは、20世紀を代表するピアニストとして、晩年に数本のビデオ録画を通し、自己の演奏以外に、一般の聴衆に自己の演奏表現形式、価値観、人生などについて語る機会があった。小稿では、そうしたホロヴィッツの直接の言より、演奏表現形式について述べられているものを中心に、現場教育でそれを実践した場合にどのような方法が考えられるかを、日本語教授法と日本語教育の科目を事例にとり具体的に考察する。
1 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 日本細菌学会
- 雑誌
- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.53-105, 1989-01-25 (Released:2009-02-19)
1 0 0 0 OA 自家経験の臨床皮膚科外用薬に関する, その処方及び内容集
- 著者
- 黒田 守
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.372-384, 1969-11-03 (Released:2010-08-25)
1 0 0 0 OA 活性汚泥の沈降性 (SV30およびSVI) に関する一考察
- 著者
- 松崎 晴美 高橋 燦吉 朱 宏麗 小栗 敬堯
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.91-95, 1983-01-10 (Released:2010-03-15)
- 参考文献数
- 5
活性汚泥のSV30, SVIに及ぼす活性汚泥濃度, メスシリンダの諸元の影響を, 合成廃水を供試した活性汚泥処理実験をとおして検討した.その結果, 界面沈降速度dx/dtはdx/dt=k/ (MLSS) 2.4で表されることを示した. ここで, kは界面沈降速度係数, (MLSS) は界面下部の活性汚泥濃度である. また, SV30, SVIに及ぼす活性汚泥濃度, メスシリンダ内の試料液深の影響は大きく, SVI値による汚泥沈降性の比較は活性汚泥濃度の狭い範囲に限って有効であることを示した. さらに, kは活性汚泥濃度, 試料液深などの影響を受けず, SVI値に比べ, 汚泥の沈降性を正確に反映し, kにより, 沈降性の精細な検討が可能であることを示した.
1 0 0 0 内侍所臨時御神楽の意義について
- 著者
- 伊東 裕介
- 出版者
- 國學院大學
- 雑誌
- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.4, pp.21-36, 2020-04
- 著者
- 中野 登志美
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.27-34, 2012-03-31 (Released:2017-07-10)
Eimi Yamada's "Eyes of Baby Chick" is included in many high school textbooks. According to an instructor who teaches the story many high school students read it as a love story. However, the work seems by no means a mere a love story when we note the function of the first-person narration. That they read it as a love story shows that high school students do not read deeply. This fact goes to the very heart of the problem when we direct our attention to the new "criticism" in high school courses of study. This paper studies the reading of "Eyes of Baby Chick" from the "criticism" point of view and obtains the following results: "Eyes of Baby Chick" clearly contains a duality of critical function both in the substance of its first-person narration and in ways of describing its first-person narration. If we attach importance to reading the duality in the critical function of the first-person narration, this work reads deeply, not superficially. This paper demonstrates that this work can instruct in the ability to read critically.
1 0 0 0 OA 細胞壁形成および修飾における植物ペルオキシダーゼの役割
- 著者
- 重藤 潤 堤 祐司
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.91-100, 2016-07-25 (Released:2016-08-05)
- 参考文献数
- 54
植物ペルオキシダーゼは,大きな遺伝子ファミリーを形成しており,大部分が細胞壁に局在することが知られている。しかし,細胞壁におけるそれらの機能については不明な点が多い。植物ペルオキシダーゼの中にはフェノール類に対する酸化酵素としてだけでなく,活性酸素種の発生源としても機能するものが存在する。さらに近年の生化学的な研究によって,木化に関与する植物ペルオキシダーゼのもつ特徴的な基質酸化能力が明らかとなった。したがって,植物ペルオキシダーゼは反応特性の面でもそれぞれ差別化されており,相応の役割を細胞壁で果たしていると考えられる。
1 0 0 0 雁(民謠) 蒙古古歌
1 0 0 0 OA 内側半月板損傷者における荷重下の内側半月板逸脱が疼痛に及ぼす影響
- 著者
- 石井 陽介 出家 正隆 藤田 直人 車谷 洋 中前 敦雄 石川 正和 林 聖樹 安達 伸生 砂川 融
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0343, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】内側半月板損傷は膝関節の疼痛を呈する。しかし,内側半月板自体に神経線維は少なく,内側半月板損傷の疼痛は他の要因が影響していると考えられる。内側半月板逸脱(medial meniscus extrusion:以下MME)は内側半月板付着部の損傷や伸長によって内側半月板がより内側に逸脱する現象で,膝関節内側部の衝撃吸収を破綻させ,内側大腿脛骨部の荷重負荷を増大させる。しかし,MMEと疼痛との関係は明らかにされておらず,荷重下でのMMEの逸脱量と疼痛に着目した報告は見られない。本研究は,内側半月板損傷者における荷重下MMEの逸脱量が疼痛を増加させるのかを明らかにすることを目的とした。【方法】対象は内側半月板損傷と診断された患者16名16膝(平均年齢57.6±9.5歳)を対象とした。内側半月板の逸脱量は超音波装置(Hivision Avius,HITACHI社)を用いて,内側半月板中節部で測定し,脛骨骨皮質の延長線から垂直に内側半月板の最大内側縁距離を逸脱量として計測した。測定は臥位と立位の2条件で行い,臥位と立位の逸脱量の差から,内側半月板移動量を算出した。先行研究を参考に,対象者を内側半月板の逸脱量が3mm以上の6名をLarge群,3mm未満の10名をSmall群に分類した。疼痛はVASとKOOSを用いて評価した。内側半月板の逸脱量の比較には,群間(Large群,Small群)と条件(臥位,立位)を2要因とした混合2元配置分散分析を行い,交互作用を認めた場合には単純主効果検定を行った。2群間における内側半月板移動量,VAS,およびKOOSの比較には,Mann-WhitneyのU検定を用いた。統計解析には,SPSS Ver19.0(日本IBM社,東京)を用い,統計学的有意水準は5%未満とした。【結果】Large群,Small群ともに,内側半月板逸脱量は臥位よりも立位で有意に大きかった(Large群臥位:3.7±1.2mm,立位:4.5±1.0mm;Small群臥位:1.7±0.5mm,立位:2.1±0.7mm)。内側半月板移動量はLarge群がSmall群より有意に大きかった(Large群:0.9±0.3mm,non Small群:0.4±0.3mm)。VAS値はLarge群がSmall群より有意に高く,KOOSのpain scoreはLarge群がSmall群より有意に低かった。【結論】本研究の結果から,荷重下MMEの逸脱量が疼痛に影響を及ぼす一要因である可能性が示唆された。これは荷重に伴う内側半月板の逸脱が膝関内側部の負荷をより増大させたためと予想される。内側半月板損傷者の疼痛には,荷重下MMEの逸脱量が影響している可能性が示された点に関して,理学療法研究としての意義があると思われる。
1 0 0 0 OA 第38回独立行政法人酒類総合研究所講演会
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.1, pp.35-54, 2003-01-15 (Released:2011-09-20)
1 0 0 0 OA 地域で暮らす精神障害者に対して用いられる熟練看護師の技
- 著者
- 濱田 淳子
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.40-48, 2007-05-31 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 10