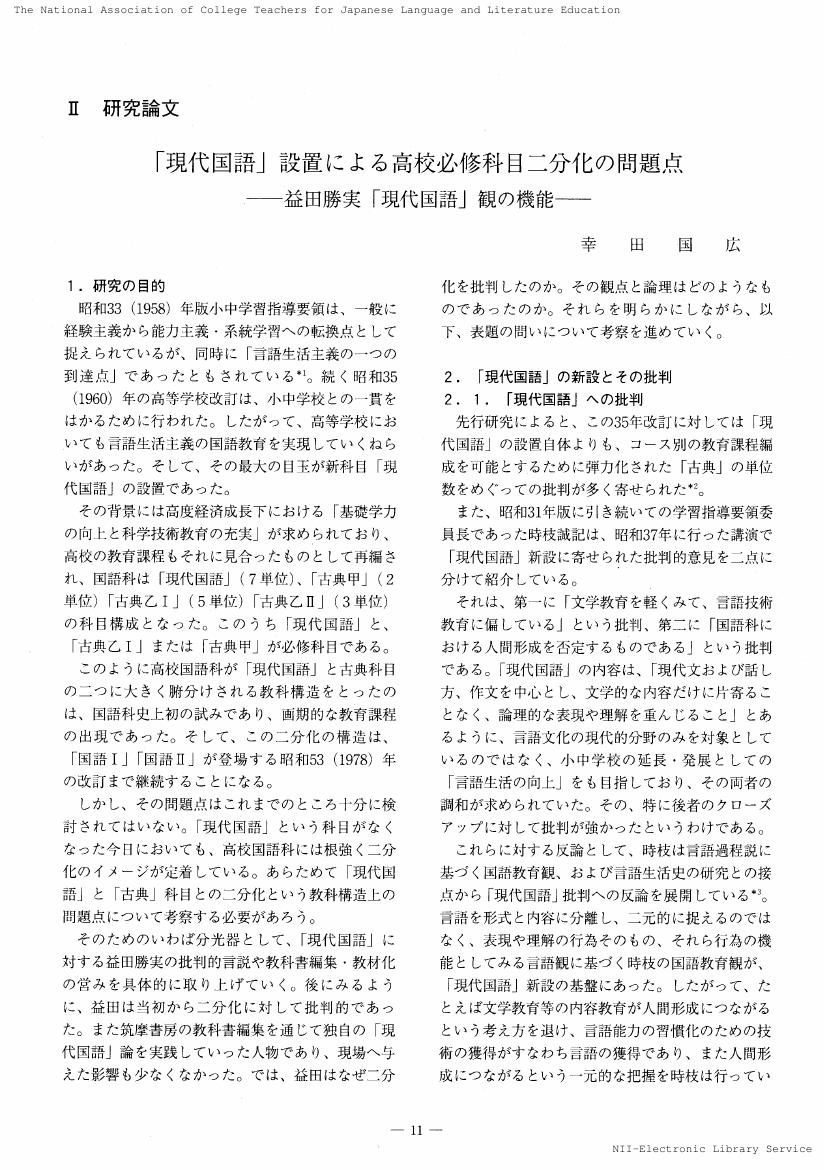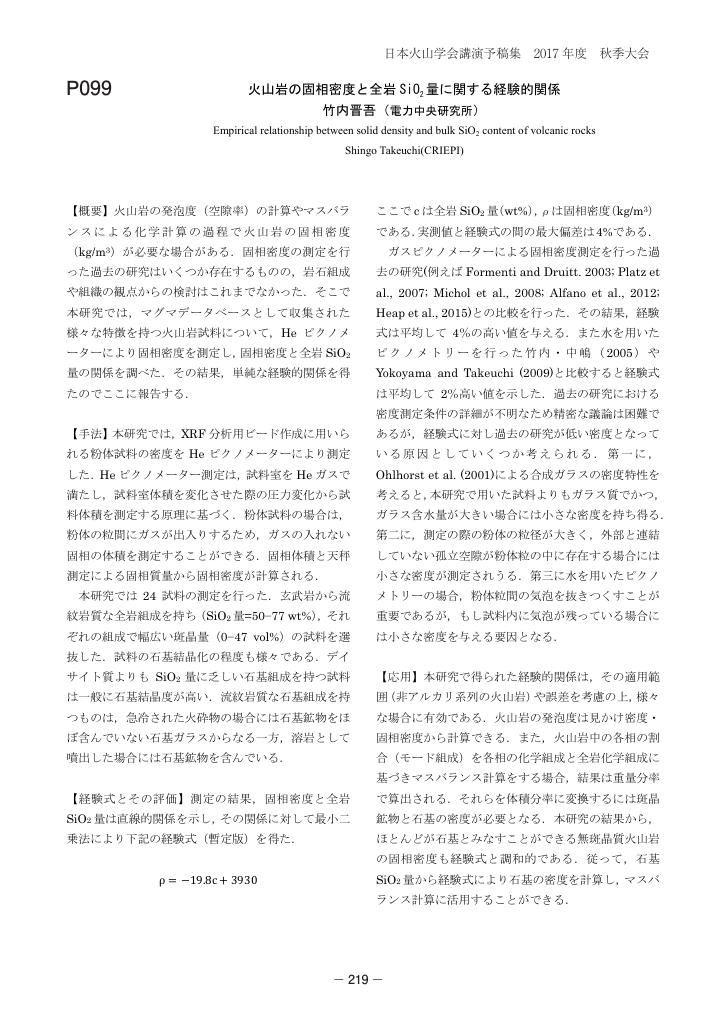1 0 0 0 OA 「現代国語」設置による高校必修科目二分化の問題点 : 益田勝実「現代国語」観の機能
- 著者
- 幸田 国広
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.11-18, 2006-03-31 (Released:2017-07-10)
1 0 0 0 OA イェイツとケルト文化復興
- 著者
- 日下 隆平 Ryuhei Kusaka 桃山学院大学文学部
- 雑誌
- 桃山学院大学総合研究所紀要 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY BULLETIN OF THE RESEARCH INSTITUTE (ISSN:1346048X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.1-14, 2003-07-15
In recent years, there has been a growing inclination to re-examine the nineteenth-century Celtic Revival in colonial England. The goal of this study is to discuss the meaning of Celtic Revival through the work of William Butler Yeats. He was a distinguished figure of this movement and a descendant of Anglo-Irish family. He felt the necessity to reconcile the Protestant Ascendancy and the Irish Catholic tradition in his mind. Yeats wrote a famous essay in which he expressed his response to On the Studies of Celtic Literature by Matthew Arnold. Arnold’s writing was important to Yeats because he mystified the Celtic character and introduced the Celtic idea as a differentiating fact between Ireland and England. Arnold attempted to bring about ‘healing measure’ by blending the delicacy and spirituality of the Celtic peoples with ‘Philistinism’of British middle-class. The mystification of the Celt becomes, in effect, the romanticizing of the Irish Catholic in Revivalists. Yeats tried to discover an aristocratic element within the Protestant Ascendancy and to associate this with the spiritual aristocracy of the Catholic and Celtic peasantry in his mind. In the first chapter, the Irish identity under colonialism will be examined. In the second chapter, Arnold’s Celtic essay will be discussed. He admitted the femininity and the spirituality of Irish Celt into the British character. In the last chapter, I will examine Yeats’s prose based on the Celtic material. He knew from O’Grady’s writing that there was the bardic tradition in Ireland. The bard (in Irish file or ollamh) was ‘highly trained in the use of a polished literary medium.’ The monks and even the abbot in the monastery are afraid of a wandering poet’s rhyme in ‘The Crucifixion of the Outcast.’ This is derived from the legend that people in the old Gaelic society were afraid of the satire of the file poet. Finally, his attempt to ennoble the Irish peasantry, as represented in the Irish folklore and legend, can be accounted for by the same logic that Arnold admitted the Celtic sensibility into the national character. This is, at the same time, true of his Ireland he invented in Celtic Revival.
1 0 0 0 OA 結帯動作と体幹回旋可動域について
- 著者
- 小林 未菜実 川角 謙一 齋藤 佳久 寺尾 靖也 佐野 勝弥 石井 裕也 辰巳 麻由美 大瀬 眞人(MD)
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第28回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.89, 2012 (Released:2013-01-10)
【目的】 肩関節疾患に対する理学療法において、肩甲上腕関節の可動域制限は良化しても結帯動作の改善に難渋するケースを多くみる。結帯動作において同側肋骨は前方回旋、胸椎は対側回旋の運動連鎖を生ずる。今回、体幹回旋可動域の左右差、体幹対側回旋可動域の変化に伴う患側肩関節の結帯動作可動域の変化に着目し、体幹の対側回旋へのアプローチを行い、結帯動作可動域に改善のみられた症例を経験したので報告する。【方法】 対象は当院に通院する女性患者3名(右肩関節周囲炎2名、右石灰性腱炎1名)である。また本発表にあたり、対象者には倫理的配慮としてヘルシンキ宣言に基づき十分に説明を行い同意を得た。 3症例の共通した条件は、患側肩関節屈曲・外転可動域160°以上、結帯動作に関してL5レベル以上の可動域を有することである。実施介入としては、自動での体幹対側回旋を患側肋骨の前方回旋を徒手にて補助しながら5回繰り返し、5回目は最終域で徒手抵抗下にて10秒間の保持を行った。介入前後に下記の方法で患側の結帯動作と体幹の両側回旋を行い、メジャー、角度計にて測定した。いずれも測定肢位は端座位である。1. 結帯動作:肘関節屈曲90°にて座面-橈骨茎状突起距離を測定。2. 体幹回旋:胸骨前方で両側の手掌を合わせ、骨盤を中間位にて固定、両膝関節内側を接触させた状態で体幹の回旋角度を測定。【結果】 体幹回旋運動に関しては、症例1:同側45°/対側30°、症例2:同側50°/対側35°、症例3:同側45°/対側40°と、3症例すべてにおいて体幹対側回旋可動域は同側回旋に比べ制限がみられた。介入後、体幹対側回旋可動域は3症例すべてにおいて拡大した。それに伴い結帯動作に関して、座面-橈骨茎状突起距離は、症例1:介入前26.0㎝→介入後30.0㎝、症例2:24.0㎝→27.5㎝、症例3:27.0㎝→35.0㎝と、3症例すべてにおいて結帯動作可動域の拡大が確認できた。【考察】 今回対象とした結帯動作制限の3症例では、全例において体幹の対側回旋制限がみられた。この原因の1つとしては患側の前鋸筋の機能不全が考えられる。前鋸筋と外腹斜筋には筋連結があり、前鋸筋の機能不全は外腹斜筋の機能不全を招くといわれている。このようなことから患側前鋸筋、外腹斜筋の機能不全が体幹対側回旋可動域の減少を生じさせたと考えた。従って、介入により外腹斜筋の活動性を向上させ、体幹対側回旋可動域を拡大させた結果、同側肋骨の前方回旋運動が促進され、肩甲骨の前傾角度が増加することで結帯動作可動域の拡大につながったのだと考える。以上より、結帯動作可動域拡大のアプローチとして、体幹対側回旋可動域の拡大による同側肋骨の前方回旋運動の促進は有効であることが示唆された。【まとめ】 結帯動作と体幹回旋可動域との相関性について考えた。今後は体幹回旋可動域の変化が結髪動作に与える影響についても考えていきたい。
- 著者
- 滝沢馬琴 [著] . 小泉保敬 [著] . 三浦梅園 [著] . 神谷養勇軒 [著]
- 出版者
- 吉川弘文館
- 巻号頁・発行日
- 1974
1 0 0 0 OA 溶解度推算における最近の進歩
1 0 0 0 OA 火山岩の固相密度と全岩SiO2量に関する経験的関係
- 著者
- 竹内 晋吾
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 日本火山学会講演予稿集 2017 (ISSN:24335320)
- 巻号頁・発行日
- pp.219, 2017 (Released:2018-02-01)
- 著者
- 佐藤 健太郎
- 出版者
- 古代学研究会
- 雑誌
- 古代学研究 (ISSN:03869121)
- 巻号頁・発行日
- no.208, pp.3-11, 2016-02
1 0 0 0 OA 2018年のベトナム 党書記長への権力集中が進むなか,10年ぶりの高成長を記録
- 著者
- 石塚 二葉 藤田 麻衣
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア動向年報 (ISSN:09151109)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, pp.213-240, 2019 (Released:2019-10-24)
1 0 0 0 OA 「構文の処理」における側頭葉の関与と障害機序について
- 著者
- 川崎 聡大
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.253-262, 2010-06-30 (Released:2011-07-02)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
近年の機能画像や認知神経心理学の進歩により Brodmann44,45 野が構文の処理に密接に関与していることは明らかである。今回,「構文処理」の障害について特異的言語障害と FOXP2 遺伝子変異の関連から,「構文処理」における側頭葉の関与については機能画像および損傷脳での知見とGarrett (1981) のプロセスモデルとの対応関係の二つの視点から検討を行った。その結果,「構文処理」の障害における形態素以前と,意味論以降で障害機序が異なる可能性を示唆した。後者では,構文処理のプロセスにおいて, 統語構造の生成や語彙の選択,文法的形態素の付与には Brodmann44,45 野が関与し,述語項構造については側頭葉が関与し「動詞の意味」を手がかりとして格の付与を行うことが示唆された。このことは,前方病変での文法障害症例への新たな訓練の視点を付与するものであると考えられた。
1 0 0 0 OA Pediatric Optic Pathway/Hypothalamic Glioma
- 著者
- Yasuo AIHARA Kentaro CHIBA Seiichiro EGUCHI Kosaku AMANO Takakazu KAWAMATA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.1-9, 2018 (Released:2018-01-15)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 44
Optic pathway/hypothalamic gliomas (OP/HGs) are rare astrocytic tumors that appear more commonly among young children and often are unresectable. They comprise approximately 2% of all central nervous system tumors and account for 3–5% of pediatric intracranial tumors. Initial manifestations are often visual disturbances, endocrinopathies and hypothalamic dysfunction such as the diencephalic syndrome, and sometimes hydrocephalus due to cerebrospinal fluid (CSF) outflow obstruction. In many cases, the tumors are diagnosed late in the clinical course because they silently enlarge. These tumors consist mostly of histologically benign, World Health Organization (WHO) grade I tumors represented by pilocytic astrocytomas (PA), the rest being pilomyxoid astrocytomas (PXA) – WHO grade II tumors. In young pediatric patients, however, can be seen PXA that show aggressive clinical course such as CSF dissemination. Our small series of 14 non-Neurofibromatosis type 1 (NF-1) OP/HGs PA patients underwent extended resection without any adjuvant treatments. The median age at initial treatment was 11.5 ± 6.90 years (range, 1–25 years) and median follow up 85.5 ± 25.0 months. Surgical resection for OP/HGs results in acceptable middle-term survival, tumor control and functional outcome equivalent to chemotherapy. There is, however, no longer doubt that chemotherapy with or without biopsy and as-needed debulking surgery remains the golden standard in management of OP/H. Clinical conditions and treatment plans for OP/HGs vary depending on their structure of origin.
1 0 0 0 IR 市民のための地球社会とは?--グローバル化の過程と影響への市民的視座
- 著者
- Shoji Kokichi
- 出版者
- 清泉女子大学
- 雑誌
- 清泉女子大学紀要 (ISSN:05824435)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.29-48, 2007-12
現代世界に国民国家間の諸関係を中心とする国際社会が存在することは疑いない。しかし、核戦争の危険からテロリズムの脅威へ、国家間および国家内における貧富の格差の複雑化、環境破壊の地球的規模への拡大、人口爆発と少子高齢化の錯綜など、今日の人類が直面している重要問題の多くが国際社会の枠組内での解決の可能性を超えてしまっており、それを超える新しい社会の出現を把握するための新しい概念が必要とされている。それを世界社会と呼石ことも可能であるが、米ソ冷戦が終結して「二つの世界」および「第三世界」の意義が縮小し、地球環境問題が最大の問題となってきている今、地球社会の概念こそが必要である。地球社会の概念は、社会を共同性、階層性、システム性、および生態系内在性の相克と重層化としてとらえる視点から、共同性と階層性の相克の、宗教、国家、市場、都市による一次システム化、すなわち帝国を超えて普及してきた二次システム化、すなわち政教分離と民主主義と科学技術にもとづく市民社会(市場的都市的社会)の地球的規模への拡大の過程と結果としてとらえることができる。現状では、その共同性はあまりにも弱く、その階層性はあまりにも険しく複雑に見えるが、それは地球社会としてのシステム化かあまりに不十分であるからであり、そういう状態のまま地球環境の危機という生態系内在性の厳しさを露呈しているのが、地球社会の現実である。その危機的状況を打開するために、市民の立場からする、言語問題に配慮した地球的情報化の積極的活用、国際組織の限界と「帝国」的世界システムの批判、イデオロギーから宗教への「改心」を克服する新たな主体的意識の高揚、およびNGOsやNPOsなどによる積極的な対抗地球社会形成が必要である。世界経済会議に対抗してくり返されてきた世界社会フォーラムのような活動が、今後ますます能動的に展開されていかなければならない。
1 0 0 0 OA Gauss-Bonnetの定理について
- 著者
- 佐々木 重夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.350-368, 1950-11-20 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 24
1 0 0 0 OA ハーレム・ルネサンス小説(10) : George Schuyler
- 著者
- 岸本 寿雄 Hisao KISHIMOTO
- 出版者
- 創価大学英文学会
- 雑誌
- 英語英文学研究 (ISSN:03882519)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.25-37, 2001-10-01
- 著者
- Jimin YOO Jaeeun KO Hakyoung YOON Kidong EOM Jaehwan KIM
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-0518, (Released:2020-05-15)
- 被引用文献数
- 1
A seven-month-old cat was referred for evaluation of exercise intolerance and open-mouth breathing. Based on ultrasonographic examination, caudal vena cava (CVC) aneurysm associated with right congestive heart failure resulting from congenital heart disease was diagnosed. Conservative treatment for alleviating pulmonary hypertension mildly improved the clinical signs and decreased the heart size and CVC aneurysm diameter. However, the improvements were transient and four months after initiating therapy, the cat developed dyspnea and uncontrollable seizures and was euthanized.
1 0 0 0 OA 大都市圏郊外部における都市農家の生産緑地の維持・貸与意向
- 著者
- 栗本 開 飯田 晶子 倉田 貴文 横張 真
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.529-536, 2018-10-25 (Released:2018-10-25)
- 参考文献数
- 17
本研究は,人口減少基調にある東京都八王子市を対象に,生産緑地所有者への悉皆的なアンケート調査を通じ,所有者の生産緑地の維持・貸与意向と意向に影響を及ぼすと推察される因子,およびこれら意向の空間的傾向の把握を行い,今後の都市縮小時代における都市農地の維持方策の方向性を考察した.その結果,既往研究で指摘されていた個人属性とは別に,立地属性である地価と周辺農地率が独立して生産緑地の維持意向と正の関係にあることが示された.日本では集約型都市構造が志向されているという点に着目すると,特に都市農地が失われる危険性が高い,地価と周辺農地率がともに低いエリアにおいて,生産緑地の貸借の推進による農地維持が求められることが示された.反対に,都市農家の生産緑地の維持意向が高い傾向にある,地価と周辺農地率がともに高いエリアでは,画一的な居住誘導を進めるだけでなく,都市の構成要素として都市農地を認め,農地と住宅地の共存による良好な住環境の形成を図ることが今後の可能性の一つとして示された.
- 著者
- 岩間 厚志
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
強い転写活性を有する白血病融合蛋白MLL-AF9によって発現が直接活性化されるhuman lincRNAを、ヒト血液細胞株を用いたChIP sequenceとRNA sequence解析によってプロファイリングした。しかし、この細胞系においては主要標的遺伝子座におけるMLL-AF9の十分な結合が得られなかったため、臍帯血CD34+造血幹・前駆細胞をMLL-AF9で形質転換した細胞を用意し、同様の検討を行った。その結果、MLL-AF9の十分な結合が得られ、特異性の高いMLL-AF9の標的遺伝子リストが得られた。すなわち、coding遺伝子174個に加えて、非遺伝子領域に8,000を超えるMLL-AF9の特異的な結合が確認され、この中に多くのlincRNAが含まれるものと考えられた。同時におこなった転写活性化のヒストンマークであるH3K4me3のChIP-sequenceデータと照合することにより、MLL-AF9によって直接転写が活性化されるlincRNAを同定することが可能である。MLL-AF9をはじめとするMLL融合白血病遺伝子によって転写されるlincRNAを絞り込むため、MLL-AF9を持つ急性骨髄性白血病5例と正常核型急性骨髄性白血病5例を用いて、MLL-AF9白血病に特異的なlincRNAをマイクロアレイ (SurePrint G3 Human GE: Agelent社) 解析によってリストアップした。また、ヒトCD34+CD38-造血幹細胞とCD34+CD38+造血前駆細胞のRNA sequenceも終了した。現在、これらのアレイ解析データとRNA sequenceデータを、上記のMLL-AF9結合遺伝子データと照合することにより、MLL-AF9によって直接転写が活性化されるlincRNAを絞り込みつつある。
1 0 0 0 OA MLL遺伝子再構成を有する小児白血病発症の分子機構
- 著者
- 小埜 良一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児血液・がん学会
- 雑誌
- 日本小児血液学会雑誌 (ISSN:09138706)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.111-120, 2007-06-30 (Released:2011-03-09)
- 参考文献数
- 56
MLL (Mixed-Lineage Leukemia) 遺伝子は, 乳児や二次性の白血病で頻度の高い11q23転座から同定された.MLL再構成の結果, MLLは転座相手遺伝子の1つと融合し, MLL融合蛋白を発現する.MLLは, クロマチン構造を修飾する転写調節複合体を構成して, ヒストンメチル化を調節するなどして, 成体型造血においてHOX遺伝子群の発現の維持を通じて重要な役割を果たしている.MLL融合蛋白は, MLL断片内のmenin結合モチーフやDNAメチルトランスフェラーゼ様領域が癌化能に必須であり, 転座相手断片内の転写活性化または多量体形成ドメインを介して白血病発症に至る.また, ヒストンメチル化能を欠くが, プロモーターへの結合を介してHOXを異常に活性化する.最近, われわれは, MLL融合蛋白は, 単独で長期の潜伏期を経て骨髄増殖性疾患を発症するのに対し, FLT3変異体のような二次的遺伝子変異と協調して早期に急性白血病を発症する多段階白血病発症モデルを確立した.この分野における進歩はMLL関連白血病発症の分子機構に新たな知見を開拓し, MLL融合を標的とした治療法の開発にも有用である.
1 0 0 0 OA 胆石イレウスの3例
- 著者
- 箕輪 啓太 高階 謙一郎 下村 克己 亀井 武志
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.723-726, 2016-05-31 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 15
腹痛・嘔吐を主訴に当院を受診し,胆石イレウスと診断された3例を経験したので報告する。症例1は78歳,男性。腹痛を主訴に他院を受診し,CTにて回腸に最大径4.0cmの結石を指摘された。手術目的に当院転院搬送され,胆石除去術を施行した。症例2は69歳,男性。消化器内科にて胆囊十二指腸瘻で通院中。嘔吐・腹痛を主訴に救急外来を受診し,CTにて最大径4.0cmの結石を指摘され,胆石除去術を施行。症例3は57歳,女性。嘔吐と間欠的な腹痛を主訴に救急外来を受診した。CTにて胆囊内に胆石1個,回腸内に落石胆石1個認めた。胆石イレウスに対して胆石除去術を施行した。第6病日に再び胆囊内の胆石が落石し,再び胆石イレウスが出現したために同日緊急手術を施行した。3症例ともに,胆石除去術のみで胆囊十二指腸瘻の根治術はせず外来通院にて経過観察となった。
- 著者
- 伊藤 史朗
- 出版者
- 専修大学人間科学学会
- 雑誌
- 専修人間科学論集. 社会学篇 (ISSN:21863156)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.27-43, 2019-03
本研究は、在日フィリピン人のホスト社会に対する社会的距離と逆社会的距離の度合いを分析したものである。エモリー・S・ボガーダス(Bogardus 1933)が考案した社会的距離尺度(Social Distance Scale)とリー、サップとレイ(Lee, Sapp and Ray 1996)による逆社会的距離尺度(Reverse Social Distance Scale)を用い、主に首都圏在住の在日フィリピン人71人の当事者意識を分析した。本調査の結果から以下が明らかとなった。1)在日フィリピン人の日本人に対する社会的距離の度合いは総じて低い。在日フィリピン人の日本人に対する親密度が高いことを意味する。2)9割以上の回答者が、日本社会から概ね受け入れられていると感じている。3)同国人(フィリピン人)間とのソーシャル・ネットワークが日本人に対するそれよりも強い。同国人との強靭なソーシャル・ネットワークを形成・維持しつつ、それが反作用することなく、低い社会的距離の度合いを示した。母国、同国人とのネットワークを堅牢に維持する一方、閉ざされたエンクレーブを形成していない。「適応すれども同化せず」(広田 2003)の「非同化的適応」の姿勢を維持し、ホスト社会に対して高い親密性を持っていることを示す調査結果となった。今後、課題になるであろう「構造的統合」に対しどのような姿勢を持つのかが、ホスト社会の側に問われることになる。
1 0 0 0 IR 育児語の全国分布 : 「神仏」と「座る」を対象に
- 著者
- 椎名 渉子 Shoko Shiina
- 出版者
- フェリス女学院大学文学部紀要委員会
- 雑誌
- フェリス女学院大学文学部紀要 = Ferris studies (ISSN:09165959)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.73-89, 2016-03