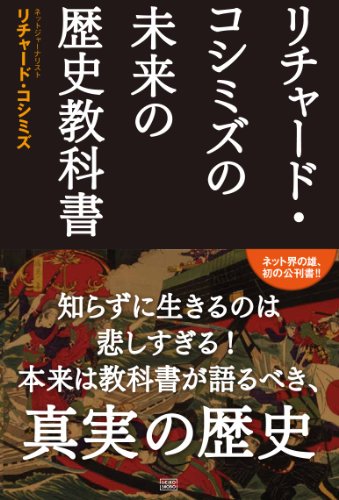1 0 0 0 OA 肩関節周囲炎患者の肩関節可動域と同側母指可動域の関係性
- 著者
- 金城 慎也 田中 創 副島 義久 西川 英夫 森澤 佳三
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第31回九州理学療法士・作業療法士合同学会 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- pp.102, 2009 (Released:2009-12-01)
【はじめに】 肩関節周囲炎患者において,肩関節の内外旋や前腕の回内外の可動域制限が肩関節挙上角度に影響を及ぼすことは先行研究により示唆されている.また,臨床場面においても,前腕の回内外可動域制限を来している症例が多い.しかし,それと同時に手指機能が不良な例も多く,特に母指の伸展,外転の可動域制限を来している症例をよく経験する.母指の伸展,外転の可動域制限は末梢からの運動連鎖として前腕の回内,肩関節の内旋を余儀なくされ,肩関節挙上制限の一因子となると考えられる.そこで今回,肩関節周囲炎患者に対して,母指可動域と肩,前腕可動域の関係性について検討したので報告する.【対象及び方法】 対象は保存的加療中の一側肩関節周囲炎患者12名(平均年齢54.25±6歳)とし,自動運動での肩関節の前方挙上(以下、前挙),外旋,前腕回内外,母指橈側外転,伸展の可動域を計測した.得られた計測値をもとに健側を基準として各計測値の左右差を求めた.統計学的処理にはウィルコクソン符号付順位和検定を用い,得られた値から肩,前腕,母指の可動域制限の関係性を調べた.【結果】 統計処理の結果,肩関節前挙と母指橈側外転(p<0.05),肩関節前挙と母指伸展(p<0.01),肩関節外旋と母指橈側外転(p<0.05),肩関節外旋と母指伸展(p<0.01),前腕回外と母指伸展(p<0.05),母指橈側外転と母指伸展(p<0.05)に有意な正の相関が認められた.【考察】 研究結果より,肩関節周囲炎患者において,肩関節前挙制限には母指橈側外転制限と伸展制限,肩外旋制限には母指橈側外転制限と伸展制限,前腕回外制限には母指伸展制限との関係性が認められた.肩関節前挙に関して肩外旋可動域制限が多大な影響を及ぼすことは知られており,上肢の運動連鎖において,前腕の回外運動には肩外旋として運動が波及することが言われてる.今回の研究結果から,遠位関節からの運動連鎖として,母指橈側外転と伸展が前腕の回外運動に影響していることが示された.その背景として,遠位橈尺関節から回外運動を波及させる為には,筋の起始停止の走行から長母指外転筋と短母指伸筋が関与していると考えられ,それらの機能が破綻することで前腕回外制限が生じると考えられる.これらのことから,肩関節周囲炎患者の挙上制限に対しては前腕,母指の影響まで考慮してアプローチしていく必要性が示唆された.
- 著者
- 山本 優
- 出版者
- 日本陸水學會
- 雑誌
- 陸水学雑誌 = Japanese journal of limnology (ISSN:00215104)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.51-58, 2017-01
この30年間で日本のユスリカの分類学的な知見は飛躍的に増大し,現時点で1206種の分布が確認されている。しかし,日本列島の多様な環境から,おそらく2000を超える種が分布するものと推測される。形態分類学の立場からユスリカの系統関係を推定するとき,正確な形態理解は必須条件である。しかし,特に雄生殖器の付属器や幼虫頭部の頭楯・上唇域は亜科や属間で形質状態に大きな相違が見られ,同一の名称が付けられていても,それらが相同器官であると判断するのは必ずしも容易ではない。Saether(1980)は雄生殖器基節上の三つの付属肢をvolsellaと判断し,それぞれsuperior volsella,median volsellaおよびinferior volsellaという形態述語(ターム)を与えている。この述語自体の使用はSnodgrass(1957)の解釈に基づけば形態学的には問題はないと判断されるが,各々の器官がユスリカ科全体を通して相同であると捉えることについては疑問が残る。現時点では雄生殖器に関してChironominaeについてはTokunaga(1938)あるいはEdwards(1929)に,OrthocladiinaeではSoponis(1977)の解釈に従っておく。幼虫頭部の形態についてはTokunaga(1935)の解釈を採用する。
- 著者
- 田辺 晋 石原 与四郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.5, pp.350-367, 2013
- 被引用文献数
- 10
日本の沿岸河口低地の沖積層に一般的にみられる最上部陸成層は,これまでその分布深度や堆積年代にもとづいて"弥生の小海退"の根拠とされてきた.しかし"弥生の小海退"の存在は汎世界的なコンセンサスを得ているわけではない.東京低地と中川低地の最上部陸成層の堆積相と放射性炭素年代値を整理したところ,最上部陸成層を構成する氾濫原堆積物が標高-1 m以浅に分布し,最上部陸成層の下部(標高-7~-3 m,約3~2 ka)と上部(標高-3 m以浅,約2~0 ka)で河川システムの形態がシート状からアナストモーズする河川チャネル堆積物へと変化することが明らかになった.シート状とアナストモーズする河川チャネル堆積物はそれぞれ低海水準期と海水準上昇期に一般的である.したがって,これらの事象は,約3~2 kaに相対的な海水準が現在よりも低く,その後現在にかけて上昇したことによって整合的に説明することができる.
1 0 0 0 OA 武器なき戦ひ : スパイは君を狙つてゐる
- 著者
- 大政翼賛会宣伝部 編
- 出版者
- 翼賛図書刊行会
- 巻号頁・発行日
- 1942
1 0 0 0 OA 足位および後足部アライメントと内外側ハムストリングスの筋活動比の関係
- 著者
- 水元 紗矢 島田 周輔 神原 雅典 石原 剛 加藤 彩奈 大野 範夫 鈴木 貞興 小笹 佳史 浅海 祐介 吉川 美佳
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.CbPI1300, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】変形性膝関節症において、異常な膝回旋運動を呈しているという報告を散見する。膝回旋はわずかな運動であり、回旋を評価することは難しい。内外側ハムストリングスは膝屈曲においては共同筋だが、回旋では拮抗筋となるため筋活動をみることで膝回旋運動を推察することができる。我々は第45回の本学会で下肢アライメントと歩行時筋活動との関係について、Q-angle高値側は内外側ハムストリングス筋活動比(M/L比)が低いと報告した。臨床において足位や後足部アライメントが脛骨回旋異常を引き起こしている症例を経験することから、今回足位および後足部回内外アライメントがM/L比に与える影響について検討したので報告する。【方法】対象は膝に障害のない健常男性10名(平均年齢27.5歳±1.9歳)の左膝10肢である。足位と後足部アライメントを変化させた条件下で、片脚スクワットを行なわせた際のM/L比を比較検討した。課題運動は片脚立位から膝屈曲60°の片脚スクワットである。上肢は胸の前で固定し、反対側の下肢は膝屈曲位、膝内外反および股関節内外転中間位で後挙させた。スクワットは屈曲2秒、屈曲保持2秒、伸展2秒の計6秒間とし、計3回行った。被験者には十分練習を行った上で計測した。筋活動の算出にはスクワット伸展2秒間の大腿二頭筋(BF)、半腱様筋(ST)、半膜様筋(SM)の筋活動を計測した。筋活動の記録には表面筋電計(Megawin Version2.0、Mega Electronics社)を用いた。得られた筋活動のRoot Mean Square(RMS)振幅平均値を算出し、計3回の平均値を各筋のRMSとした。さらに膝屈曲45°での最大等尺性収縮を100%として正規化し、%RMSを算出し各筋の%RMS を求めた。ST、SMに対するBFの割合をそれぞれST/BF比、SM/BF比とした。足位は、床に対して足長軸を進行方向に向けた位置をtoe 0°、それより5°外側に向けた位置をtoe-outとした。後足部アライメントは、入谷の方法をもとに2mmのパットを用いて回内位(PR)、中間位(NP)、回外位(SP)を誘導した。検討項目は、ST/BF比とSM/BF比を以下に示す3通りの方法で比較検討した。1.(1) NP・toe0°とNP・toe-out、(2) NP・toe0°とPR・toe0°とSP・toe0°、(3) NP・toe-out とPR・toe-out とSP・toe-outとした。2.NP・toe-outでのST/BF比とSM/BF比を検討した。各筋の%RMSを比較した。統計学的解析には、二元配置分散分析法と多重比較検定、対応のあるt-検定を用いた。有意水準は5%未満とした。【説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、被験者には研究の主旨を十分に説明し同意を得た上で計測した。【結果】1-(1) toe0°とtoe-outではST/BF比、SM/BF比とも有意差を認め(P<0.05)、toe-outでBFの活動が高くなった。1-(2) toe0°では、ST/BF比でPRとSP間に有意差を認めた(P<0.05)。1-(3) toe-outでは、SM/BF比でNPとPR間に有意差を認め(P<0.05)、PRでBFの活動が高まり、SMの活動低下がみられた。2. toe-outでのST/BF比とSM/BF比は有意差を認めなかった。【考察】 本研究により、荷重位での足位および後足部アライメントによりM/L比が変化することが示された。Scott.K(2009)はtoe-outでのエクササイズにてM/L比の減少が起こると報告しており、本研究の結果もそれを支持する結果となった。toe-outにてBF筋活動が高まることは、内旋方向へ誘導される下腿の運動を制御した結果ではないかと考えた。toe-out・PRにおいてSM/BF比は減少を認めたが、ST/BF比は有意差を認めなかった。この理由としては、STとSMの筋機能の違いによるものと考えた。SMは筋形状とレバーアームの関係により浅屈曲で筋活動が優位になり、STは深屈曲で筋活動が優位となる。回旋作用としてはSMに比べSTで作用が高い。本研究ではスクワット60°屈曲位で行ったことから、SM筋活動の抑制が起きたためSM/BF比に有意差を認めたと考えた。【理学療法学研究としての意義】本報告で、足位および後足部アライメントの変化によるST/BF比、SM/BF比の基礎的データが得られた。足位および後足部アライメントが内外側ハムストリングスの筋バランスに影響を与えることが示された。スクワット運動や荷重位でのエクササイズにおいて、足位や後足部アライメントを考慮する必要があると考えた。
1 0 0 0 リチャード・コシミズの未来の歴史教科書
- 著者
- リチャード・コシミズ著
- 出版者
- 成甲書房
- 巻号頁・発行日
- 2013
- 著者
- 本塚 亘
- 出版者
- 説話文学会
- 雑誌
- 説話文学研究 (ISSN:02886707)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.184-194, 2016-08
1 0 0 0 『看聞日記』の舞楽記事を読む
- 著者
- 村井 章介
- 出版者
- 立正大学文学部
- 雑誌
- 立正大学文学部論叢 (ISSN:0485215X)
- 巻号頁・発行日
- no.138, pp.37-55, 2015-03
1 0 0 0 OA 水田秋植物(Autumn paddy ephemeral)に関する一考察
- 著者
- 梅本 信也 藤井 伸二
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 分類 (ISSN:13466852)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.47-51, 2003-02-28 (Released:2017-03-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
We proposed a life strategy concept as "autumn paddy ephemeral" which is unique in paddy fields after rice reaping. For the adaptation to this strategy, short life cycle for completing reproduction until the beginning of winter or plasticity of growing period for both long summer and short autumn, may be important Paddy weeds are supposed to be now adapting to the open marshy habitat in autumn paddies which has been widely spread for only several decades.
1 0 0 0 OA 関東地方南部の水田における非栽培期の植物相に及ぼす水稲収穫時期の影響
- 著者
- 山田 晋
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.417-420, 2010 (Released:2011-07-22)
- 参考文献数
- 17
Uncultivated periods are important in rice paddy fields for the survival of species favoring unaerated soils. Clarifying the mechanisms affecting the floristic diversity of in-field habitats is a key part of sustainable agriculture. We hypothesized that the timing of crop harvest influences the flora in the subsequent uncultivated period in rice paddy fields. To confirm this hypothesis, surface soils were sampled in cultivated paddy fields at the beginning of August.The sampled soils stored in ≤ 5% relative light intensity were exposed to direct light at different periods varied from late August to the beginning of October. Germinated seedlings were counted until spring the next year. Observation in autumn showed that the numbers of species, germinated individuals, and flowering individuals differed as a function of the duration of light exposure, although these differences were less clear in the subsequent spring. These differences can be explained by differences in ecological traits such as maturation rate and optimum germination temperature. Timing of the rice harvest is closely linked to the timing of rice planting, which in turn can affect the germination of species maturing before the rice is planted.
- 著者
- 小笠原 正薫
- 出版者
- 桜の聖母短期大学
- 雑誌
- Bulletin of Sakura no Seibo Junior College (ISSN:03868168)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.77-103, 2002-03
1 0 0 0 OA 日本におけるスピノザ
- 著者
- 宮永 孝
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.304-156, 2014-12
1 0 0 0 IR ルネサンスを旅する日本の若者たち : 『天正遣欧使節記』に見るグランドツアー
- 著者
- 根占 献一
- 出版者
- 学習院女子大学
- 雑誌
- 学習院女子大学紀要 (ISSN:13447378)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.49-61, 2020
1 0 0 0 笑い学―海外での研究動向
1 0 0 0 OA P-1-G16 重症心身障害児(者)に対する視覚機能評価の試み
- 著者
- 山際 英男 甲斐 結城 松木 友美 矢崎 有希 小町 祐子 軍司 敦子 山本 晃子 加我 牧子 益山 龍雄 荒井 康裕 本澤 志方 太田 秀臣 立岡 祐司 野口 ひとみ 高木 真理子 真野 ちひろ
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.262, 2017 (Released:2019-06-01)
はじめに 重症心身障害児(者)(以下、重症児者)は視覚刺激に対する応答がきわめて乏しい者があり、環境情報取得の制限から周囲の人や物との相互作用が乏しくなりがちである。何をどのように知覚しているのかの視覚認知機能評価は、療育上きわめて重要であり、自覚応答に頼らない視覚機能検査により、視覚情報提供の際の注意点を明らかにするため検討を行った。 対象 重症児者施設長期入所利用者50名(平均年齢37歳、男性26名、女性24名)、大島分類1:39名、2:4名、3:2名、4:3名、5:1名、9:1名。 方法 小町ら(日本重症心身障害学会誌、2013)の方法に準じて検討し、評価した。定性的視覚機能評価は対光反射、光覚反応、回避反応、視覚性反射性瞬目、睫毛反射、視運動性眼振(OKN)、注視、追視、瞥見視野)を調べ、反応状態により、反応あり、条件付き反応、反応無しの3段階の順序尺度で評価し、追視、瞥見視野は角度も測定した。注視・追視可能な者は縞視力測定を行った。機能の有無は評価に参加したセラピスト2/3以上の同意をもって判定した。 結果 各項目の反応出現率は睫毛反射94%、対光反射94%、光覚反応84%、視覚性反射性瞬目68%、注視66%、追視54%、瞥見視野52%、OKN58%、縞視力34%、回避反応40%であった。追視、瞥見視野の結果は個人差が大きく、かつ方向・範囲の制約がみられた。 考察 以上より対象者のうち、94%は情報取得手段として視覚を何らかの形で利用できる可能性があり、追視と瞥見視野の結果は刺激提示場所としてどの位置に提示すれば視覚応答が得られやすいかが示され、個別に考慮、対応すべきことが確認された。重症児者の多くは適切な視野を確保するための自動的な頭部コントロールが困難なことが多いため、「見える位置・距離」に対象を提示することが、残存視力を活かし豊かな相互作用につながると考えられる。
- 著者
- 遠藤 浩
- 出版者
- 誌友会民事研修編集室
- 雑誌
- みんけん (ISSN:13422766)
- 巻号頁・発行日
- no.519, pp.12-15, 2000-07
1 0 0 0 OA VRを使用した蒸気機関車シミュレータ -スコップ型デバイスの開発と検証-
この研究ではSLブームに対して蒸気機関車の乗務経験者の高齢化、減少が深刻化しており今後、新たに復活しうる乗務員の経験、知識不足が予測される。そこで各種装置や状況を自由に変化させることができるVRを用いた蒸気機関車のシミュレータを想定し、今回は蒸気機関車への給炭作業を再現するためのスコップ型デバイスの開発を行う。デバイス開発にあたり、給炭作業の再現はスコップで石炭をすくった際と投げ入れる際の重量変化の再現が必要となるため本実験では棒形状のデバイスにステッピングモータによってレール上のおもりを前後にスライド移動させることで体感重量が変化し、体験者が実在感を与えられたかを実験の結果から論ずる。
1 0 0 0 OA 脳動脈瘤クリッピングシミュレータの開発
- 著者
- 庄野 直之 金 太一 斉藤 雄介 斎藤 季 斉藤 延人 小山 博史
- 出版者
- 日本VR医学会
- 雑誌
- VR医学 (ISSN:13479342)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.20-26, 2015-11-10 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 17
BACKGROUND: Subarachnoid hemorrhages may occur spontaneously from a ruptured cerebral aneurysm. The placement of clips around the neck of the aneurysm (clipping) is one of the very common surgical treatments. However, clipping is a challenging surgery for most neurosurgeons. To help support the surgeon’s decision-making process and preoperative surgical planning, we developed a VR clipping simulator (ClipSim).METHODS: High definition 3DCG models such as aneurysms, arteries, and brain were segmented by Amira® software (FEI, Hillsboro, OR) and surgical clips were modeled by Maya® software (Autodesk, San Rafael, CA). These models were integrated and simulated into Unity® (Unity Technologies, San Francisco, CA) software.RESULTS: We successfully developed a real-time, interactive, clipping simulator with an aneurysm deformable model used by PhysX real-time physics engine (Ageia, Santa Clara, CA). In conclusion, the simulator may be useful prior to surgery during the surgeon’s decision making process for selecting the most appropriate clips.
- 著者
- 岩切 朋彦
- 出版者
- 鹿児島女子短期大学
- 雑誌
- 鹿児島女子短期大学紀要 = Bulletin of Kagoshima Women's College (ISSN:02868970)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.37-49, 2018
「働く留学生」をめぐる諸問題について,前稿で提起した問題に答えるために,本稿では福岡市の日本語学校に通うネパール人留学生に対して行ったインタビュー調査をもとに,留学生の日常生活をエスノグラフィとして描いていく.留学生たちはアルバイト先において,学校教育では経験できない言語的かつ文化的な学びを得ており,他者との相互作用を通じて複雑な文化的アイデンティフィケーションの過程を経ていることが明らかになった.このことから,留学生の就労制限の緩和は,学習効果への影響という側面から考えてもそれほど問題はないと結論付けた.むしろ,就労を通した「状況的学習」という観点から見れば,地域コミュニティとの社会的相互作用を経ることで,来るべき移民社会へ向けた過渡段階として,多文化共生の社会的素地を作り上げているとも言えるのである.