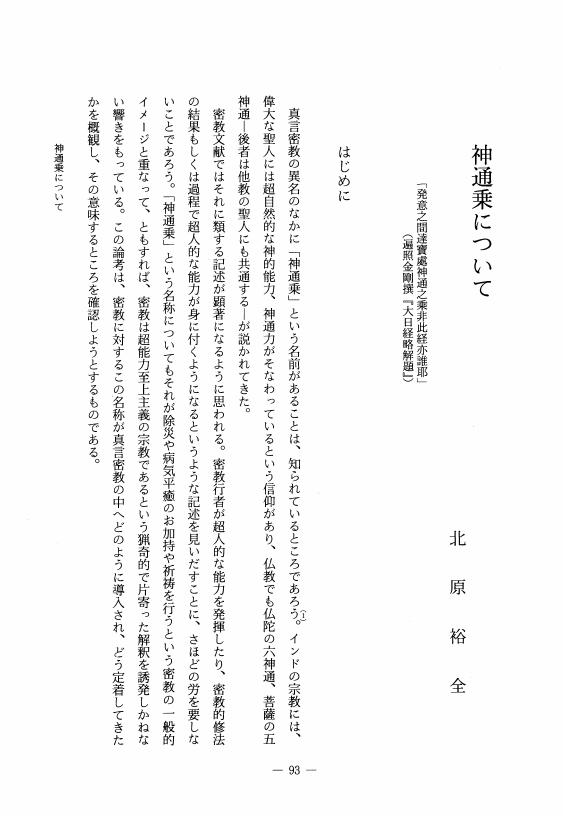1 0 0 0 OA 北海道における法医昆虫学の研究:ブタの死骸上での昆虫遷移
- 著者
- 亀井 雄二 岩佐 光啓
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第58回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.52, 2006 (Released:2006-06-07)
欧米では早くから死骸の腐敗分解過程と照らし合わした昆虫遷移の実験データを法医学に応用し、死亡場所や死亡経過時間の推定などに役立てる法医昆虫学(forensic entomology)という分野が確立されているが、日本ではその存在すらほとんど知られていない。そこで日本における法医昆虫学について研究するために、2005年の6月下旬と8月上旬に帯広畜産大学近辺の林に3頭のブタの死骸を置いて、そこに集まる昆虫相およびハエ類の羽化について調べた。その結果、死骸からは主にクロバエ科、イエバエ科、ニクバエ科、ツヤホソバエ科、チーズバエ科、ハヤトビバエ科、ノミバエ科、ミギワバエ科、ミズアブ科、シデムシ科、エンマムシ科、ハネカクシ科、オサムシ科らが採取された。また上記の実験期間中において昆虫遷移の違いはほとんど見られなかったが、集まる昆虫相の種構成には明らかな違いが見られた。今回はそれらの実験結果の詳細に加えて、日本における法医昆虫学の有用性や新たに法医学的に重要であると思われる昆虫についても報告する。
1 0 0 0 OA 直接操作による流体挙動の制御
- 著者
- 早川 雄登 藤代 一成
- 雑誌
- 第78回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.1, pp.185-186, 2016-03-10
流体シミュレーションでは,流体の写実性とともに可制御性も重要である.アニメーション制作では,流体の非写実的な表現が必要となる場合も多く,流体らしさを維持しながら,期待通りに流体形状を制御しなければならない.また,流体シミュレーションの知識がなければ,パラメータの感度を理解することも容易ではない.そこで本研究は,流体シミュレーションに用いるパラメータを特定のモーションデータに対応させた直接操作により,流体形状を直感的に制御することを試みる.
1 0 0 0 OA コントラアングルドライバーを併用した口内法にて整復固定した下顎骨関節突起骨折の1例
- 著者
- 村上 拓也 越沼 伸也 肥後 智樹 山本 学
- 出版者
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 雑誌
- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.87-91, 2013 (Released:2013-10-15)
- 参考文献数
- 9
下顎骨関節突起骨折において,コントラアングルドライバーを用いた口内法による観血的整復固定術を施行した1例を報告した。顎顔面領域における骨折のなかでは下顎骨骨折が最も多くみられる。観血的整復固定術を行うには,口外法と口内法があるが,口外法は,顔面神経麻痺や皮膚瘢痕などのリスクがある。一方,口内法は皮膚切開,皮弁挙上の必要がなく,顔面神経麻痺や皮膚瘢痕が生じない。術野の明示は口外法に比較するとやや困難となるが,侵襲を最小限に抑えることが可能であり,今回の症例においては術後の機能障害もなく良好な結果となった。以上のことから,骨折部位が関節突起基底部より低位である症例では,コントラアングルドライバーを用いた口内法による観血的整復固定術は有用な方法であると考えられた。
- 著者
- サクニミット モラコット 稲月 一高 杉山 芳宏 八神 健一
- 出版者
- 公益社団法人 日本実験動物学会
- 雑誌
- Experimental Animals (ISSN:00075124)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.341-345, 1988
- 被引用文献数
- 71
マウス肝炎ウイルス (MHV) , イヌコロナウイルス (CCV) , Kilhamラットウイルス (KRV) およびイヌパルボウイルス (CPV) に対する消毒薬, 加熱, 紫外線の殺ウイルス効果を検討した。コロナウィルス (MHVおよびCCV) に対しては, ほとんどの消毒薬, 60℃, 15分の加熱で不活化ができたが, パルポウイルス (KRVおよびCPV) に対しては, ホルムアルデヒド, ヨードホール, 次亜塩素酸ナトリウム, 亜塩素酸ナトリウム以外に有効な消毒薬はなく, 80℃, 30分の加熱でも不活化できなかった。紫外線は, いずれのウイルスに対しても, 15分の照射で不活化できた。また, 同一ウイルス群に属するウイルスは各処置に対して同程度の反応を示し, ウイルス種, 株による差は認められなかった。
1 0 0 0 OA スギ花粉症に対するアイピーディ®の効果
- 著者
- 水田 啓介 伊藤 八次 西田 基 秋田 茂樹 加藤 雅也 小塩 勝博 海田 健宏 古田 充哉 宮田 英雄 柳田 正巳 柴田 康成 横山 壽一 松原 茂規 小泉 光 森 芳郎 大野 通敏 近藤 由香 藤宮 大 山田 匡彦 渡辺 英彦 加藤 洋治
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.12, pp.1399-1407, 1997-12-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 14
IPD® (supratast tosilate) was investigated for its prophylactic efficacy and therapeutic efficacy in the treatment of cedar pollinosis during the 1996 cedar pollen season. The subjects investigated were patients at the Gifu University School of Medicine and its affiliated hospitals, who had a history of cedar pollinosis. The patients were classified into two treatment groups: the prophylaxis group (70 patients), in whom IPD® administration began before the start of cedar pollen dispersion, and the treatment group (49 patients), who underwent IPD® treatment only after cedar pollen dispersion had begun and symptoms of pollinosis had manifested.Results were as follows: (1) The nasal symptoms (sneezing, runny nose, nasal congestion) were milder in the prophylaxis group than in the treatment group throughout the cedar pollen season, with the difference being significant during the season's first 2 weeks. (2) In the prophylaxis group, IPD®'s inhibitory effect was rated as excellent in 18.6% of the patients, good in 45.7% and fair in 20.0%. In the treatment group, the improvement in the symptoms was rated as disappearance in 4.2%, excellent in 20.8% and good in 43.8%. (3) When symptom inhibition in the prophylaxis group was investigated as a function of the duration of IPD® administration prior to the start of pollen dispersion, the good + excellent inhibition rate was 57.7% in the subpopulation pretreated for <2 weeks (26 cases), 64.9% with 2 to <4 weeks' pretreatment (37 cases) and 85.7% with 4 to <6 weeks' pretreatment (7 cases). Thus, IPD®'s prophylactic inhibitory rate increased with the length of the pretreatment period. (4) In the prophylaxis groups, the CAP-RAST value was significantly reduced at the time of peak pollen level and at the end of the pollen season compared with the value before IPD® administration.
1 0 0 0 三条西実隆と三条流
- 著者
- 島谷 弘幸
- 出版者
- 東京国立博物館
- 雑誌
- 東京国立博物館紀要 (ISSN:05638259)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.p5-151,図p153〜191, 1990
1 0 0 0 OA 反省的判断力はいかに道徳的な実践的判断に寄与し得るか
- 著者
- 蓮尾 浩之
- 出版者
- 関西倫理学会
- 雑誌
- 倫理学研究 (ISSN:03877485)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.157, 2016 (Released:2018-03-15)
1 0 0 0 OA 表現法の変遷 ― ラテン修辞学からグループμへ
- 著者
- 小田 淳一
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.253-268, 2007 (Released:2009-04-24)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
Born as a technique of persuasio, rhetoric has been organized according to five canons in Latin rhetoric. These canons were subsequently reduced down to onlyelocutio, due to various factors such as the invention of typography where the written text replaced the verbal text as the object of elocutio. Elocutio itself was later gradually reduced to kinds of tropes, then to tropes pairings of metaphor and metonymy, and finally to the metaphor. In spite of its declared demise at the end of the 19th century, rhetoric was revived after the latter half of the 20th century by structural linguistics, and modern rhetoric continues to transform in close contact with poetics and semiotics. Among neo-rhetorical researches on the figures, Groupe μ's approach seems to provide one of the most elaborate models. The model regards figures as a system of metaboly, where four simple operations are executed on a text at various elemental levels. The aim of this article is to reinvestigate the whole system of rhetoric from a cognitive viewpoint by presenting not only rhetorical resources -- specifically the figure system of Latin rhetoric (Cicero and Quintilianus) and French classical rhetoric (Dumarsais and Fontanier) which is the legitimate heir to the former -- but also Groupe μ's several productions which have yet to be introduced to academic research apart from Rhétorique générale.
1 0 0 0 全国水道企業団協議会の会長に就任して
- 著者
- 尾高 暉重
- 雑誌
- 水道協會雜誌 (ISSN:03710785)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.9, 2009-09-01
1 0 0 0 OA 急性寒冷暴露および寒冷馴化は免疫機能に変調を引き起こす単球/マクロファージを誘導する
- 著者
- 木崎 節子 山下 均 瀬川 雅彦 大石 修司 長沢 純一 大野 秀樹
- 出版者
- 公益財団法人 明治安田厚生事業団 体力医学研究所
- 雑誌
- 体力研究 (ISSN:03899071)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.44-53, 1995 (Released:2019-01-21)
1 0 0 0 4H-SiC極性面の表面再結合速度の注入フォトン数依存性
- 著者
- 韓 磊 加藤 智久 加藤 正史
- 出版者
- 応用物理学会
- 雑誌
- 2020年第67回応用物理学会春季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2020-01-28
1 0 0 0 OA 食品の機能性成分と植物の二次代謝
- 著者
- 日比野 久美子
- 出版者
- 学校法人滝川学園 名古屋文理大学
- 雑誌
- 名古屋文理短期大学紀要 (ISSN:09146474)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.1-15, 2004-04-01 (Released:2019-07-01)
機能性食品という名称と概念は世界に先駆け日本から発信されたものである.機能性食品の研究と開発の進展に伴い,食品中のフラボノイド・テルペノイド・揮発性物質などの非栄養性成分が疾病予防の上に有する機能を科学的に解明する研究が増加している.文部科学技術省は世界に先駆け非栄養性機能物質の体系化を目指し,食品成分表に記載されている植物について,フラボノイド・ポリフェノール類,テルペノイド・カロテノイド類,含硫化合物・揮発性成分・香辛物質等の含量と機能を分析・体系化して,現在試験的に"機能性食品因子データベース"としてホームページで公開している.これらの機能性成分は植物の二次代謝物質であり,様々な環境ストレスに対する植物の防御物質として機能していることが明らかにされつつあり,これらの物質については今後学際的な研究の広がりが期待される.
1 0 0 0 ギターの評価と弦の鳴りの関係について
- 著者
- 徳弘 一路 浅野 誠 渡辺 久晃 津村 尚志
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. EA, 応用音響
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.179, pp.47-54, 1997-07-18
- 参考文献数
- 27
「3弦の鳴るギターは良いギターである.」 というギターの評価法はどのような原理に基づいているかを調べた. 1弦と3弦の位置を交換し, スペクトルの変化を調べ, ギター全弦に第3弦を張り, その弾弦音の時間波形, 減衰特性, スペクトルを比較した結果, 3弦の位置におけるスペクトルのエンベロープが滑らかでなく, 5kHz以上の周波数帯域において倍音成分が小さく, 1弦の場所と比較して良い音がでないことがわかった. また, 同じ製作者による鳴るギターと鳴らないギターを比較した結果, 鳴らないギターは音量が非常に小さく, さらに, エンベロープが滑らかでなく, 5kHz以上の周波数帯域において倍音成分が小さいことなどがわかった.
- 著者
- 北原 裕全
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.199, pp.93-105, 1998
1 0 0 0 OA 神通乗について
- 著者
- 北原 裕全
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.199-200, pp.93-105, 1998-03-31 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 中平 比沙子 小尾 信子 宮原 龍郎
- 出版者
- 日本アロマ環境協会
- 雑誌
- アロマテラピー学雑誌 (ISSN:13463748)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.38-46, 2009-03
1 0 0 0 OA グローバル化社会の現代中国仏教
- 著者
- 吉原 浩人
- 出版者
- 早稲田大学多元文化学会
- 雑誌
- 多元文化 (ISSN:21867674)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.二三七-二二三, 2015-02-28
1 0 0 0 IR 神戸の美術商濱田篤三郎 : 明治前期における海外直輸出への試み
- 著者
- 川村 範子 Noriko KAWAMURA
- 出版者
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科
- 雑誌
- 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集 = Bulletin of the Graduate School of International Cultural Studies Aichi Prefectural University (ISSN:13454579)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.289-309, 2015
- 著者
- by George Galavaris
- 出版者
- Princeton University Press
- 巻号頁・発行日
- 1969
- 著者
- 平光 睦子
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.69-76, 2013-05-31
- 参考文献数
- 27
本稿は、明治期の京都の美術工芸学校の図案教育について、岡倉天心(1863 . 1913年)が美術教育施設二付意見」において示した美術教育制度との比較において考察するものであり、その目的は美術工芸学校の特性や傾向を明らかにすることにある。<br>1894(明治27)年に発表された「美術教育施設ニ付意見」には、近代日本に相応しい美術教育制度の構想が示されている。このなかで、京都の美術工芸学校は、高等美術学校としても技芸学校としても否定されている。<br>岡倉の構想した高等美術学校は、日本美術の保護継承を目的とする専門家養成機関であった。また、技芸学校の目的は直接的に殖産興業に資することであり、ここでの産業は主に大量生産の機械工業をさしていた。<br>一方京都の美術工芸学校は、創立以来の地元の工芸諸産業との関係性を明治中期には一層強めており、1891(明治24)年の工芸図案科設置もその表れといえる。高等美術学校として否定された要因はこの産業との直接的な関係性にあり、技芸学校として否定された要因は、その産業が主に工芸であって機械工業ではないことにあった。