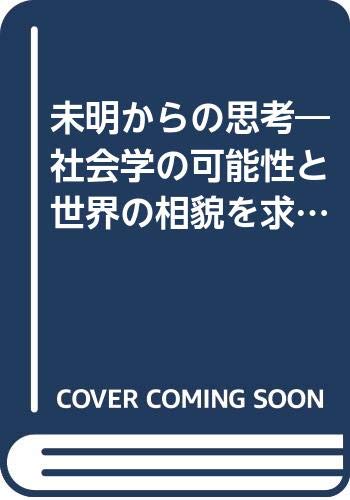1 0 0 0 筋収縮の違いからみた下肢三関節のトルク発揮特性
- 著者
- 図子 浩二 西薗 秀嗣 平田 文夫
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.593-600, 1998-10-01
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 4 2
A study was conducted to investigate the relationship between the characteristics of torque production with special reference to eccentric and concentric muscle contraction and the structural and functional properties at the lower limb joints in the human kinetic chain. Ten male college athletes were tested with a isokinetic dynamometer (biodex) for eccentric and concentric torques during extension and flexion at the hip and knee, and plantar flexion and dorsiflexion at the ankle (angular velocity ; 30, 60, 120 deg/s) . The peak eccentric and concentric torques were higher in the order hip, knee and ankle joints, as the size of each muscle acting on its joint increased. However, the rate of peak concentric to eccentric torque (CON/ECC, %) was higher at the ankle joint than at the hip and knee joints. They tended to increase in the order of angular velocity ; 30, 60, 120 deg/s. These results suggest that the ankle joint is charactered by higher eccentric torque production. This characteristic is probably due to the fact that (1) the ankle joint is located at the end of the human kinetic chain and plays a role in transmitting the power to the ground effectively, (2) the muscle tendon complex acting at the ankle joint must have increased stiffness and tolerate great stretch loads to store and reuse the amount of elastic energy, (3) the hip and knee joints located at the center are the main sources of power supply. On the other hand, no significant correlations were observed among the torques at the hip, knee and ankle. These results suggest that torque production is independent at each of the lower limb joints, and is based on the structural and functional properties of each joint. These findings seem to be useful to clarifying the methods of strength and power training that can be adapted to the characteristics of torque production and the structural and functional properties of the hip, knee and ankle joints.
- 著者
- 図子 浩二 高松 薫
- 出版者
- Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.29-39, 1995-05-10 (Released:2017-09-27)
- 被引用文献数
- 5 6
Rebound drop jump index [RDJ_<index>=(1/8・g・RDJt_a^2)/RDJt_c] was developed to evaluate the ability to perform the ballistic stretch. shortening cycle (SSC) movement. The RDJ_<index> consists of ability to jump higher (RDJt_a) and that to shorten the contact time (RDJt_c) in rebound drop jump (RDJ), a typical SSC movement. The former is affected by leg strength and counter movement jump ability but the factors affecting the latter case have not yet been well established. This study examined the factors to shorten the contact time with special reference to two important views, i.e. work done by the lower limb joints and anticipation of the landing. 1. Relationships between work done by the lower limb joints and RDJ_<index>, RDJt_c, and RDJt_a in RDJ from height of 0.3m were examined in ten college male athletes. There was a significant correlation between the ratio of negative work at the ankle to total work done by the lower limb joints and RDJ_<index> (r=0.726, p<0.05), and RDJt_c (r=-0.823, p<0.01) but not RDJt_a (r=0.226,ns). Furthermore, there was no significant correlation between the ratio of negative work at the ankle and maximum plantar flexion strength (r=-0.329,ns). These results suggested that the rate of energy absorption at the ankle joint in former contact phase was one important factor to shorten the contact time in RDJ but not affected by plantar flexion strength. 2. RDJ_<index>, RDJt_c and RDJt_a in two RDJs with or without visual information to inhibit temporal and spatial anticipation of landing were compared in six college male athletes. As compared without and with visual information, RDJt_c was longer, RDJt_a was shorter and RDJ_<index> was lower, significantly. These changes were greater in subjects showing the higher RDJ_<index> than those showing the lower RDJ_<index>. Furthermore, changes of RDJ_<index>, RDJt_c and RDJt_a in series of nine RDJs without visual information at thirty seconds of rest intervals were compared between subject A showing high RDJ_<index> and subject B showing low RDJ_<index>. RDJt_c decreased and RDJt_a increased slightly, and RDJ_<index> increased by repeated trials even without visual information in subject A but not in subject B. These results suggested that temporal and spatial anticipation of the landing were another important factors to shorten the contact time in RDJ. These finding seemed to be beneficial for establishing strength and power training methods for jumper and ballgame players who are required ballistic stretch-shortening cycle movement.
- 著者
- 阿江 通良
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.57-62, 1996-05-01 (Released:2016-10-31)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 5 3
- 著者
- 中村 善行 高田 明子 藏之内 利和 増田 亮一 片山 健二
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.62-69, 2014-02-15 (Released:2014-03-18)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4 6
糊化温度が通常のサツマイモ品種・系統より著しく低いデンプンを含有する品種「クイックスイート」における加熱に伴うマルトース生成の機序を通常のサツマイモ品種「ベニアズマ」と比較検討した.50°Cから100°Cまで10°C毎に変えた温度で加熱した塊根から組織液を採取し,その糖度ならびにマルトースおよびスクロース含量を測定するとともに,同じ塊根から調製した粗酵素液の β-アミラーゼ活性を可溶性デンプンを基質として定量した.また,塊根組織細胞内のデンプン粒の形態を走査型電子顕微鏡で観察し,糊化度を β-アミラーゼ-プルラナーゼ法で調べた.「クイックスイート」では β-アミラーゼが高い活性を示す60°Cから塊根細胞内のデンプンが糊化した.また,デンプンが完全に糊化する80°Cにおいても β-アミラーゼの活性は維持されていた.他方,「ベニアズマ」では加熱温度が80°C以上からデンプン糊化が確認されたが,この温度域では β-アミラーゼ活性は大きく低下していた.両品種の β-アミラーゼに対する温度の直接的影響はほぼ同じであったことから,80°Cで加熱された「クイックスイート」塊根で β-アミラーゼ活性が未加熱塊根なみに維持されたことは当品種のデンプンが温度の低い加熱早期から糊化することと密接に関連すると推察される.すなわち,「クイックスイート」では「ベニアズマ」に比べ,より低い温度約60°Cから80°Cを超える高温に至るまでの広い温度域でマルトース生成が持続するため,「ベニアズマ」より糖度が高くなると考えられた.
1 0 0 0 OA 平安期里内裏の空間秩序について : 陣口および門の用法からみた
- 著者
- 飯淵 康一
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.340, pp.159-168, 1984-06-30 (Released:2017-08-22)
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1938年04月18日, 1938-04-18
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1935年10月28日, 1935-10-28
- 著者
- 須貝 千里
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.95, 1998-10-17
1 0 0 0 IR 広島戦後直後に実施された建築設計コンペティションにおける設計案に関連しての原型・類似型に関する研究 : その6.広島平和記念公園丹下健三案とル・コルビュジェ提案ソヴィエト・パレス案
- 著者
- 石丸 紀興
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.903-904, 2010-07-20
1 0 0 0 OA マックス・ヴェーバーの政治思想 : 政治を通した生の意味獲得
1 0 0 0 OA 零度のプロレタリアート : 〈絶対貧困〉に躙り寄るノート
- 著者
- 松本 潤一郎
- 出版者
- 信州大学人文学部人文学科松本和也研究室
- 雑誌
- ゲストハウス
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.2-19, 2013-04-25
1 0 0 0 未明からの思考 : 社会学の可能性と世界の相貌を求めて
1 0 0 0 IR ビルマ語の種まき(I.特集:桜美林大学の外国語教育)
- 著者
- 大澤 幸子 桜美林大学基盤教育院
- 雑誌
- Obirin today : 教育の現場から = In search of a learner-centered education (ISSN:13498754)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.71-77, 2012-01-01
1 0 0 0 OA ヨーロッパとアジアの異なる個体群におけるオオヨシキリの繁殖生態
- 著者
- Andrzej DYRCZ
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.123-142,211, 1995-08-25 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 2 4
本論文では文献および未発表データに基づいて、オオヨシキリの個体群を比較することを目的とし、とくに基亜種 A.a.arundinaceus と東アジア産亜種 A.a.orientalis との違いに注意を払う。異なる地域(Figs.1 & 2)の19個体群(基亜種13、東アジア産亜種6)での研究を比較の対象とする。大部分(17)の個体群において、本種はさまざまな種類のヨシ原に生息し、ほとんどの場合、ヨシの茎に営巣する。2個体群は例外的で、チェコのNamestske養魚池では抽水植物帯に優占するガマに営巣し、極東アジアのChanka湖では湖岸沿いに広大なヨシ原があるにもかかわらず、大部分の巣は林縁のやぶや低木に造られた(Table 1)。Chanka 湖では比較的多くの巣が乾燥した土地に造られたが、このようなことはヨーロッパではきわめてまれであり、日本でもまれである。一般的に亜種 orientalis の個体群では基亜種に比べて繁殖密度がはるかに高い(Table 2)。理由の一部は亜種 orientalis の生息場所の方が人間による改変をより強く受けているためと考えられる。日本のヨシ原ではオオヨシキリが繁殖鳥の優占種だが、ヨーロッパではふつう、ヨーロッパヨシキリ、オオジュリン、オオバンなどの方が数が多い。ヨーロッパではオオヨシキリと競合する可能性があるヨーロッパヨシキリが日本に生息しないことは、日本でオオヨシキリが非常に高密度な理由の1つかもしれない。平均一腹産卵数は南から北に向けて少し多くなる傾向がある(Table 3)が、東西の亜種間に基本的な違いは見いだせなかった。営巣失敗の個体群間での違いに、地理的な傾向は見られなかった(Table 4)。失敗の主な理由は捕食によるものだった。ヨーロッパに比べて、日本ではヘビ類がより重要な捕食者と考えられる。人手の加わった生息場所に棲むネズミ、オナガ、ハシボソガラスのような動物についても同様と考えられる。スウェーデンの Kvismaren 湖では卵や小さな雛への加害者として、同種の個体が重要と考えられている(BENSCH & HASSELQUIST 1993)。これはとくに、一夫多妻第一雌の卵を破壊することで、自身の社会的地位と適応度を上げることのできる第二雌にあてはまるだろう。雛全員の餓死はヨーロッパ個体群に限られるようで、日本では巣内の1雛しか餓死しない(EZAKI 1990)。理由の1つは一夫多妻の同じなわばり内の雌の間での巣内雛期の重なり具合にあるのかもしれない。同じなわばり内の雌の初卵産卵日のずれは、ヨーロッパ(ポーランド、スウェーデン)ではたいてい5日以内だが、日本では14日程度ある。このため、第二雌の雛に対する雄親の給餌が、日本ではヨーロッパよりもふつうにみられる。日本で雛の餓死がまれな別な理由は温和な気候にあるかもしれない(URANQ 1990a)。カッコウによる托卵は亜種 orientalis でより一般的なようだ(Table 5)。卵の孵化率には2亜種間で大きな違いはない(Table 6)。巣当たりの平均巣立ち雛数には場所や年度によって1.84羽から3.57羽までの変異がみられ、最大値と最小値はスイスの同じ個体群で2年間に得られたものである。雛が与えられる餌内容の個体群間での類似性は、地理的分布によるものではなく、生息場所のタイプによる(Tables 7 & 8)。一夫多妻の頻度がもっとも高かったのは、本種の地理的分布範囲の北端と南にある2つの富栄養湖においてだった(Table 9)。他の9個体群では一夫多妻雄の割合は14.3%から27.8%だった。本州~中国東北部の方がヨーロッパ中央部よりも南に位置し、気候もいくらか温和にもかかわらず、平均初卵日は遅かった(Table 10)。2亜種間の顕著な違いは換羽と渡りにみられる。基亜種の大多数の個体は晩秋にアフリカ北部で完全換羽を行ってから赤道以南の越冬地へと移動する。亜種 orientalis の大多数は繁殖期直後に繁殖地かその近くで完全換羽し、成鳥•幼鳥とも秋の渡り前に換羽を完了する。基亜種に比べて亜種 orientalis は渡りの期間が短く、越冬地で過ごす期間が長い(NISBET & MEDWAY 1972,EZAKI 1984,1988)。オオヨシキリの繁殖生態の諸側面に関する個体群間の違いは亜種の区分と一致するものと結論できるだろう。すなわち、亜種 orientalis の個体群の方が、生息場所に対する耐性が強く(やぶや低木、また水のない場所での繁殖)、繁殖密度が高く、巣内雛の餓死が少なく、カッコウの托卵を多く受ける。ただし、これらの特徴のいくつかは、研究された orientalis 個体群のいくつかが人為的に著しく改変された場所に棲んでいるという理由によるのかもしれない。一方、一腹卵数、巣の全滅、孵化率、巣立ち雛数、巣内雛の餌内容は、亜種の区分とは関係のない個体群間の変異を示した。
1 0 0 0 OA 海洋島に雌雄異株は侵入しやすいか? 形成31年後の小笠原諸島西之島の生物相
- 著者
- 安部 哲人
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第52回日本生態学会大会 大阪大会
- 巻号頁・発行日
- pp.200, 2005 (Released:2005-03-17)
海洋島への生物の侵入過程には不明な点が多い.火山島での数少ない研究事例としてクラカタウ島,スルツェイ島,ロング島などがあるだけである.一般に海洋島生態系にはさまざまなシンドロームがあるが,その中の一つに植物の性表現に関してフロラが雌雄異株性に偏っていることがあげられる.この理由については大きく分けて,1.雌雄異株が侵入しやすい,2.侵入してから雌雄異株になった,という2つの対立する仮説がある.しかしながら,実際に誕生して間もない海洋島での生物の侵入過程を観察できる機会は世界的にもほとんどないため,検証することは非常に困難である.その意味でも噴火31年後の小笠原諸島西之島の生物相の現状は興味深い. 2004年7月に調査した結果,西之島のフロラはわずか6種で構成され,前回報告された1978年以降で2種増加したのみであった.種子散布型の内訳は海流散布4種,付着型鳥散布2種であった.このことから,他の火山島での侵入過程と比較しても,西之島の生物相は侵入のごく初期の段階を脱しておらず,海洋島では侵入速度がはるかに遅いことが示された.植生は1978年以降,大きく拡大していたが,溶岩部分には全く植物が侵入できておらず,新たに拡大したのは砂礫が堆積した平地部分のみにとどまっていた.島内ではカツオドリをはじめとする海鳥が高密度で営巣しており,種の侵入や植生に対しても少なからず影響がありそうな反面,植物の果実を食べる山鳥は全くみられず,被食型鳥散布種子が侵入できる確率は非常に低いと考えられた.また,フロラの構成種は全て両性花植物であり,被食型鳥散布種子を持つ種も見られなかったことから,侵入に関して雌雄異株の優位性は認められなかった.一方で,非常に貧弱なフロラであるにもかかわらずハマゴウやスベリヒユなどの花には540分間で複数種の訪花昆虫が観察された.このことは自家和合性のある種でなくても定着が十分可能であることを示唆する.
1 0 0 0 OA イギリスにおけるイスラム教徒の学校教育に関する一考察 -多文化教育の実現に向けて-
1 0 0 0 OA 乳児の泣き声に対する若者の反応
- 著者
- 中山 博子
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.127-136, 2016 (Released:2017-01-06)
本研究は、乳児の泣き声を若者が聞いた場合どのように感じるか調査することを目的とし、女子大学生および大学院生を対象に泣き声を刺激とした聴取実験を行った。音声刺激は生後0か月から12か月の乳児を縦断的に観察して得られた泣き声を用いた。実験の結果、泣き声に対する嫌悪感は音圧など音の強さにかかわる指標が影響していることが判明した。また、泣き声に対する嫌悪感は乳児の機嫌の悪さとは必ずしも一致しなかった。乳児初期の泣き声と比べて乳児後期に観察される泣き声のほうが実験参加者に与える嫌悪感の度合いは高くなる傾向がみられた。実験参加者は乳児が表出するすべての泣き声に嫌悪感を抱くわけではなく、一部の甘え泣きに対しては好感をもつことが判明した。本研究の結果は、乳児の泣き声が不快であるというこれまでの前提に立っているのとは異なり、泣き声によっては聞き手にポジティブな感情をもたらし、ベビーシェマとして機能している可能性を示したといえる。