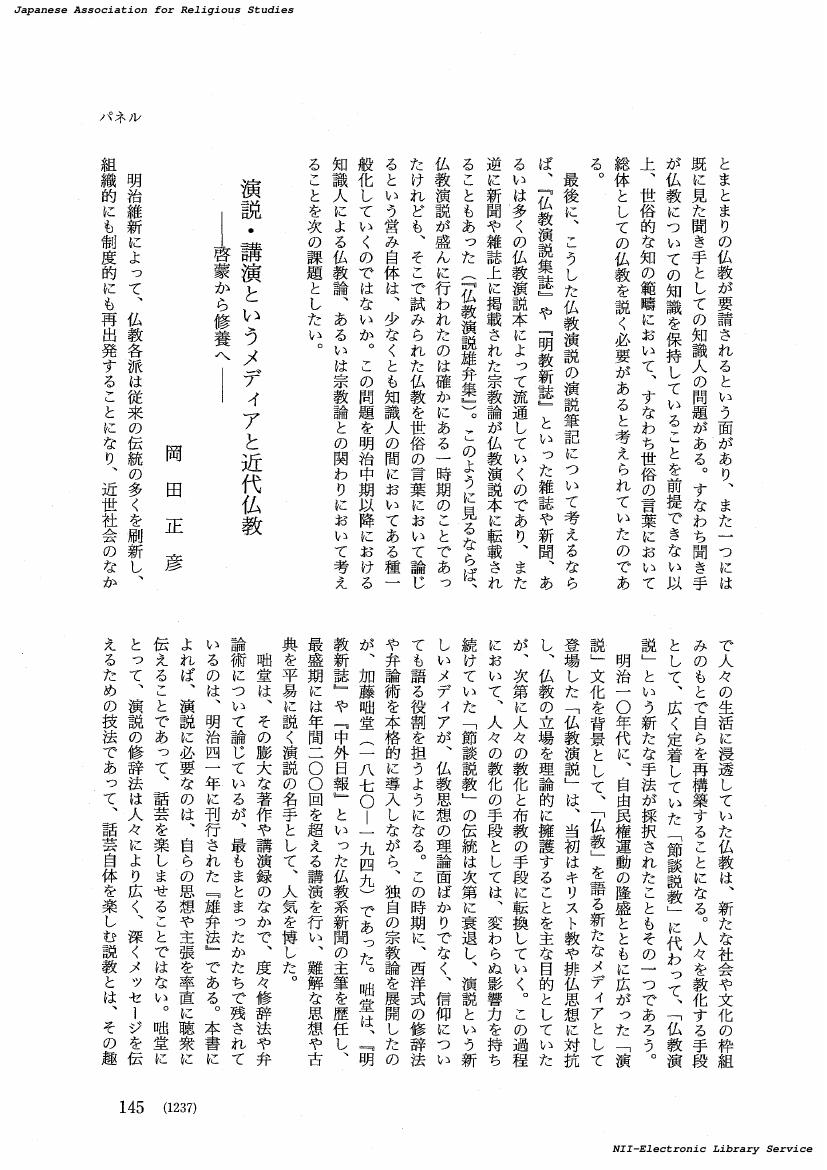- 著者
- 青村 和夫 新田 昌弘 松本 繁美
- 出版者
- 北海道大学 = Hokkaido University
- 雑誌
- 北海道大學工學部研究報告 (ISSN:0385602X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.171-178, 1973-06-30
1 0 0 0 OA Zn/ゼオライト触媒でのエタノール転換反応におけるゼオライトの影響
- 著者
- 今井 裕之 寺坂 一沙 黎 暁紅
- 出版者
- 公益社団法人 石油学会
- 雑誌
- 石油学会 年会・秋季大会講演要旨集 第45回石油・石油化学討論会(名古屋大会)
- 巻号頁・発行日
- pp.166, 2015 (Released:2016-01-05)
Znをゼオライトに担持した固体触媒を用いて、エタノールからの一段での1,3-ブタジエン合成反応を行った。反応にはゼオライトの酸性質が大きく影響し、ゼオライトの酸量・酸強度が大きい場合ではエタノールからエチレンまたはジエチルエーテルの生成が優勢になった。酸量の少ないチタノシリケートを担体に用いることで、エチレンよりも1,3-ブタジエンの生成が優勢になることを見出した。
- 著者
- 岡田 正彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.1237-1238, 2010-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 OA 八戸港における東北地方太平洋沖地震津波の再現計算
- 著者
- 富田 孝史 丹羽 竜也
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.I_236-I_240, 2013 (Released:2013-11-12)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 6
The tsunami generated by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake inundated coastal flat areas, moved auto vehicles, boats and ships and destroyed part of a breakwater in Hachinohe Port. In this paper, propagation and inundation calculations of the tsunami are implemented from an estimated tsunami source. Consideration of the breakwater damage in the calculations provides a good result of the tsunami in the port in comparison with the waveform observed at a tide station in the port, the measured inundation border and heights of tsunami watermarks. Based on the time of breakwater destructions in the calculation, failure mechanisms of the breakwater damage are estimated. Further, movement of a ship in the port is calculated and compared with a result of video footage analysis.
- 著者
- CHEN Yaodeng WANG Jia GAO Yufang CHEN Xiaomeng WANG Hongli HUANG Xiang-Yu
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2018-048, (Released:2018-06-22)
- 被引用文献数
- 3
Background error covariance (BEC) is one of the key components in the data assimilation systems for numerical weather prediction. Recently, a scheme of using an inhomogeneous and anisotropic BEC estimated from historical forecast error samples has been tested by employing the extended alpha control variable approach (BEC-CVA) in the framework of the Variational Data Assimilation system for the Weather Research and Forecasting model (WRFDA). In this paper, the BEC-CVA approach is further examined by conducting single observation assimilation experiments and continuously cycling data assimilation and forecasting experiments covering a 3-weeks period. Moreover, additional benefits of using a blending approach (BEC-BLD), which combines a static, homogeneous BEC with an inhomogeneous and anisotropic BEC, are also assessed. Single observation experiments indicate that the noises in the increments in BEC-CVA can be somehow reduced by using BEC-BLD, while the inhomogeneous and multivariable correlations from the BEC-CVA are still taken into account. The impact of BEC-CVA and BEC-BLD on short-term weather forecasts is compared with three-dimensional variational data assimilation scheme (3DVar), and compared with the hybrid ensemble transform Kalman filter and 3DVar (ETKF-3DVar) in WRFDA also. Results show that the BEC-CVA and BEC-BLD outperform the use of 3DVar. It is shown that BEC-CVA and BEC-BLD underperform ETKF-3DVar as expected, however the computational cost of BEC-CVA and BEC-BLD is considerably less expensive since no ensemble forecasts are required.
1 0 0 0 OA 老年病の一元病因説
- 著者
- 佐々木 英忠
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.301-310, 2018-07-25 (Released:2018-08-18)
- 参考文献数
- 72
1 0 0 0 OA ユーザ好みのスキャットを強化学習する初音ミクとのジャムセッションシステムの開発
- 著者
- 鶴田 穣士 岡 夏樹 田中 一晶
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-12
音楽を用いたコミュニケーション手段として,ジャムセッションというものがある.それを人間と機械の間でも可能としたものがジャムセッションシステムであり,今まで多く研究がなされてきた.ジャムセッションではボーカルがスキャットと呼ばれる歌唱法を用いることがある.本稿では,ユーザの演奏に対してシステムが初音ミクを用いてスキャットを返すという形態のジャムセッションシステムを提案する.また,この提案システムでは,ジャムセッションを通してユーザが好むスキャットの言葉を強化学習することを目指した.提案システムの実装を行い,ユーザが好むスキャットの言葉の学習を確かめた.
- 著者
- 仁科 エミ
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.40-45, 2008-12-25 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 女性IT技術者のキャリア課題とアジャイル型キャリア開発の提案
- 著者
- 森本 千佳子 渡辺 知恵美 櫻井 浩子 木塚 あゆみ 永瀬 美穂
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, pp.261-264, 2015
近年、企業では性別・年齢・価値観など人材の多様性を活かし、働き方を改革するダイバーシティの取り組みが進められている。女性の積極的な活用もその中の一つである。しかし、IT 業界ではこの5 年間のうち女性社員の割合はほぼ12%前後の横ばい、企業の半数以上で管理職全体における女性管理職の割合は10%以下という現状にある。このような要因として、仕事と家庭の両立が困難、「技術者」としての将来のキャリアが描けないなどが考えられる。本研究では、女性IT技術者へのインタビュー調査を通して得たキャリアパスの課題について整理し、環境に応じた臨機応変(アジャイル型)のキャリア開発について提案する。
1 0 0 0 OA ぺた語義:新学習指導要領で求められる情報科教員の育成・採用・研修
高等学校の新しい学習指導要領と解説が公表された.高等学校の情報科では,共通教科「情報I」「情報II」では高度化したうえに内容が多岐にわたる.また専門教科では「情報セキュリティ」の科目が新設されるなど,新たな分野を指導する能力も要求されている.しかし,現在高等学校で情報科を担当している教員には,短期間の研修で情報の免許状を取得した者も多く,このままでは新学習指導要領での教育を十分に行うことが難しいと考える.新学習指導要領の実施までに,さらなる情報科教員の育成と採用,また現職教員への研修も必要とされることをふまえて,現職教員として情報処理学会に協力してほしい点について述べる.
1 0 0 0 OA ぺた語義:学習管理システムを活用した実践的なアカデミック英語教育の取り組み
筆者は英語圏への留学等を想定した実践的な英語の運用能力の養成を目標とした授業のオンラインコースのデザイン・開発・実施・評価に関する研究を行なっています.リスニングやリーディングの学習が中心だったこれまでの「実践英語e-learning」というオンラインコースを,4技能をバランス良く学習し実践的な英語を修得できるようオンラインコースを改善しました.本授業は2017年度の春学期より開講され,コースが受講生のニーズを満たし,実践的な英語スキルが向上したことを確認しました.また,クオリティ・マターズ(Quality Matters)コースデザイン評価を受け,現在はコースがHigher Education Course Design Rubric(第5版)のすべての基準を満たしています.
1 0 0 0 OA ぺた語義:教材の公衆送信と著作権法改正
1 0 0 0 OA 第151号全文
- 著者
- 金沢大学附属図書館
- 出版者
- 金沢大学附属図書館
- 雑誌
- こだま (ISSN:09158782)
- 巻号頁・発行日
- vol.151, pp.1-10, 2003-10-01
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1957, pp.30-33, 2018-09-10
中国・瀋陽にある七宝山飯店は、北朝鮮資本のホテルである。PART1に登場した元英国諜報員のケネス・マレン氏は、「上層階の6フロアは外から見えないように、窓が全て黒く塗りつぶされている。北朝鮮サイバー部隊の活動拠点だ」という。
1 0 0 0 信頼性工学の現状
- 著者
- Coppola Anthony 石森 富太郎
- 出版者
- 日本信頼性学会
- 雑誌
- 日本信頼性学会誌 信頼性
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.4-13, 1995
米国宇宙航空産業界は、国防省(DOD)の調達へのMIL規格の適用に距離を置く旨の国防長官通達の成り行きを、引き続きかたづをのんで見守っている。他方、品質保証プログラム規格集のISO9000番台は、相対的にかつ着実に世界で通用する規格になりつつある。現在取り上げられている問題には、信頼性予測の正確さ;プラスチック累積回路への適用;信頼性向上を目的としたコンピュータ支援技術;ソフトウェアの信頼性に関するものが多い。共同研究およびネットワーク作りが増えており、信頼性に関心を持つグループの結成がインッタネットに基づいて行われる例も多い。数多くの有用なツールが多数入手できるようになったものの、依然として問題を楽に解決するための"特効薬"はない。
1 0 0 0 OA 明治期から昭和戦前期の日本に建設された霧笛舎の建築的特徴
- 著者
- 山崎 鯛介
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.664, pp.1171-1178, 2011-06-30 (Released:2011-11-16)
Delving the history of foghorn buildings in Japan, this paper shows that most of them were built on the cape of Hokkaido and Tohoku area between 1879 and 1932, and their construction materials were changed from steel in Meiji period to concrete in Taisho period. In the Meiji period, they were designed as a rectangular room with a vaulted roof and all made of steel panels. The Inubosaki's foghorn building is the latest, largest, and well-designed one of them. It is also the last one in existence, therefore it is now having a new value as a cultural asset.
- 著者
- 森田 椋也 後藤 春彦 山崎 義人 野田 満
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.730, pp.2731-2740, 2016
- 被引用文献数
- 1
The aim of this paper is to clarify the reality of the reviving of shrine ritual in order not only to rethink ongoing projects implemented under the word “Earthquake Disaster Reconstruction” but to think post-earthquake rebuilding of town in future tsunami-prone areas.<br> The results are the following:<br> (1) Damage and Post-Earthquake Movement of the Shrines Hit by Tsunami:<br> Most of the shrines hit by tsunami have been rebuilt or rehabilitated by the time of the survey. In some cases, the shrines got support from outside.<br> (2) Relationship between Shrine Rituals and Folk Cultural Assets in Yamada-Town:<br> In Yamada-town, the shrines play an important role in sustaining the folk cultural assets.<br> (3) Movement of Ohsugi Shrine Annual Festival Before and After the Earthquake:<br> Ohsugi shrine has been rebuilt until two years after the earthquake. After further a year, the annual festival was held with the traditional content.<br> (4) Processes and Problems of Reviving of the Groups of Folk Performing Artists:<br> Most of the groups of folk performing artists participated in Yamada Festival a half year after the earthquake, and have finished getting an almost full set of equipment until four years after the earthquake, the time of the survey.<br> (5) Processes and Problems of Reviving of the Group of Mikoshi Bearers:<br> The group of mikoshi bearers was reorganized for its reviving a year and a half after the earthquake. After further two years, it participated in Yamada Festival in the traditional format once again. When the group of mikoshi bearers was reorganized, the chief priest of Ohsugi shrine became the top adviser of it. Carrying mikoshi in the annual festival is not the same as before in several points because rebuilding of dwelling environment is not going along smoothly.<br> (6) Relationship between the Rebuilding of Town and the Reviving of Shrine Ritual in Yamada-Town:<br> The rebuilding of dwelling environment and the industrial recovery reached major milestones at almost the same time as the reviving of shrine ritual. The buildings for the sake of industrial recovery have been used as bases of the group of folk performing artists and the group of mikoshi bearers.<br> We consider that disaster victims could feel that Reconstruction is going along if annual events were held with the traditional content without suspension. In that sense, it can be said important to hold annual festivals with the possibly same content as before the earthquake since the early stage of rebuilding of town. Although restoring and carrying Mikoshi require a high amount of funds, we infer that support for reviving should be provided as soon after earthquake as possible. Besides, we found that it is especially necessary to make a point for each group to get bases commensurate with its size in likely place.<br> We also argue the importance of the role played by the chief priest of shrine in rebuilding and sustaining of town to contribute to sustaining the groups of folk performing artists, the group of mikoshi bearers and therefore the community based on above-referenced groups.<br> Interestingly, the reviving of shrine ritual reached major milestones to coincide with the shifts of dwelling environment from shelter to temporary housing, or from temporary housing to disaster public housing.<br> Not only in Yamada-town but in general reconstruction, it is hoped that as well as being a memorial for victims of the disaster, shrine ritual would be revived while linking it organically to rebuilding of dwelling environment and industrial recovery to which it is indivisibly related.
1 0 0 0 IR 南河内郊外における神社祭祀に関する一試論 : 美具久留御魂神社秋季例大祭の事例から
- 著者
- 濱田 時実
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇 (ISSN:18833985)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.55-71, 2015-03-01
大阪府富田林市にある美具久留御魂神社の秋季例大祭はだんじりが出る特徴がある。同地域は、「都市」や「農村」ではなく「郊外」と呼べる地域である。南河内においてだんじりが出る祭りは太子町にある科長神社の夏祭りで始まり、美具久留御魂神社の秋季例大祭で終わると言われている。したがって、だんじりが地域の祭礼における象徴ともなっている。本稿ではだんじりに関係する行事を主として取り扱う。これまでの地域研究において、民俗学が扱ってきたフィールドは大きく分けると「都市」「農村」「山村」「海村」に分類することが可能だが、現代におけるフィールドの概況は必ずしもそれらだけでは十分と言えない。祭礼研究においてもフィールドがそれらの分類に属していることを前提として論が進められているのが現状であり、祭礼研究の大きな課題である。本稿では、「都市」「農村」などに属さず、これまで民俗学が取り扱うことのなかった「郊外」という立場に注目し神社祭祀の現状を取り上げる。そして都市祭礼とも村落祭祀とも呼べない、郊外における神社祭祀の事例から、祭礼研究における課題を主張したい。
1 0 0 0 12人−09−口−05 祭りの身体性と真正性
- 著者
- 大森 重宜 櫻井 貴志 佐々木 達也
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.289_2-289_2, 2017
<p> 「青柏祭の曳山行事(通称でか山)」は、石川県七尾市の大地主神社の例大祭「青柏祭」に奉納される山車の曳行行事で1983年(昭和58年)に国重要無形文化財に指定され、2016年ユネスコ無形遺産に登録された33の「山・鉾・屋台」の一つである。</p><p> 日本の祭りは、華やかな神輿の渡御や山車曳行などがその中心にある。本研究では日本一巨大な山車「青柏祭の曳行行事」を身体運動文化と捉え、神輿、山車などを担ぎ、舁き、曳くという遊びとしての山車曳行の身体技法と神事での祝詞などから儀式性を考察し、青柏祭曳山行事の身体性と真正性を考察する。</p>
1 0 0 0 OA 過疎地域での生活排水と可燃ごみの連携処理による温室効果ガス削減について
- 著者
- 靏巻 峰夫 久保 朱里 山本 祐吾 吉田 登
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.II_23-II_34, 2016 (Released:2017-04-10)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2
少子高齢化,過疎化の問題に同時に直面する地方圏域では生活排水処理,廃棄物処理等の静脈系インフラの維持運営は難しさを増している.加えて,低炭素社会や経済性の要請によってインフラ運営が非効率にならないよう改善も必要とされている.本研究では,従来,別系統のシステムで運営されている生活排水処理と可燃ごみ処理を連携させてエネルギーリサイクルの促進と効率化を図ることによって,このような圏域でも適用できるシステムにより削減できる温室効果ガス量を検討したものである.可燃ごみのメタン発酵,発酵分離水の処理,発酵残渣及び排水処理汚泥の焼却等の対策に技術進展を加味した連携によって現在のシステムに対して約40%の削減の可能性があることがわかり,連携の有効性を明らかにした.