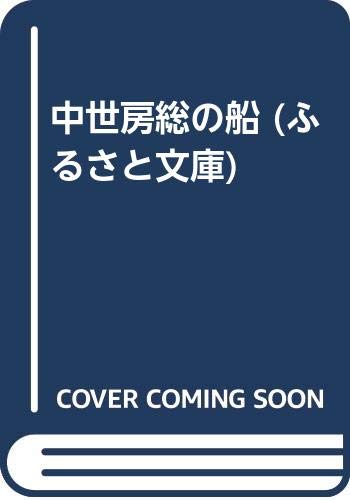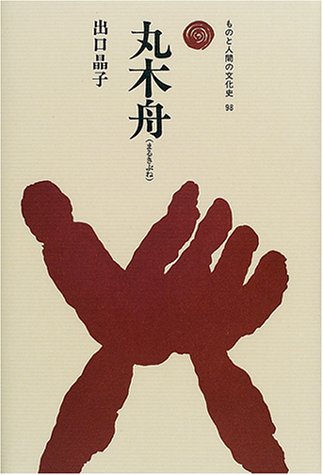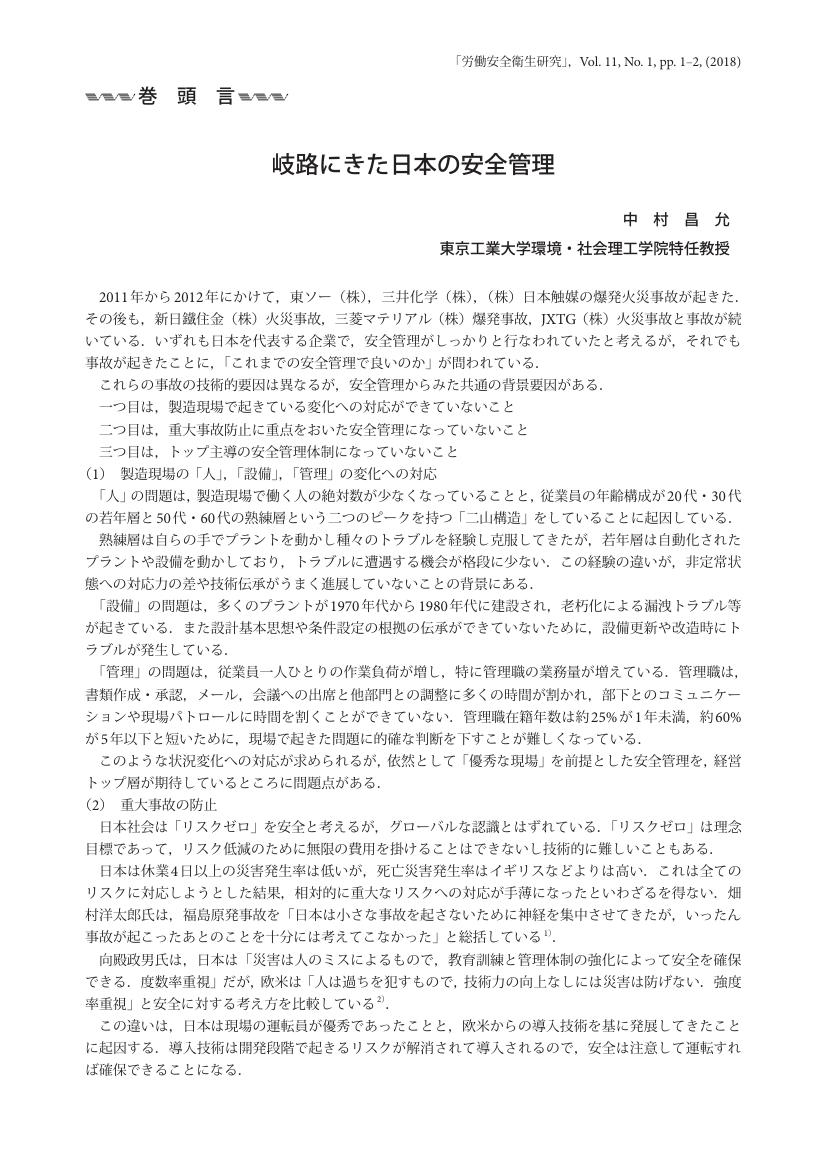1 0 0 0 OA 湧水地帯における陸封型イトヨの潜在的な生息可能区域
- 著者
- 端 憲二 多田 敦 冨永 隆志
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.169-174,a2, 2001-02-01 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 6
地域固有の生態系に配慮した農業水路の計画を考える一例として, 近年その減少が危惧されている陸封型イトヨの生息地である湧水地帯で環境調査を行った。生息地の調査で, DO, pH, COD, 窒素, リン等の水質条件とともに, イトヨは日中の最高水温が20℃を上回らない水路では生息可能なことなどを明らかにした。これらの条件と植生, 流速等の諸条件を小流域としてまとまっている6本の水路 (総延長23.1km) について調査した結果, イトヨが生息している, または生息できる可能性が高い潜在的な生息可能区域は, 総延長にして5.4kmに相当した。また, この区域は年間を通じ枯渇しない湧水の影響下の1~2kmであった。
1 0 0 0 OA 岩手県沿岸に生息するイトヨの生活史
- 著者
- 佐々木 剛 猿渡 敏郎 渡邊 精一
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.117-118, 2002-03-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
The Strontium: Calcium (Sr: Ca) ratio from an otolith section of three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus (L.) was examined in samples taken from the Hei River mouth, and the Gensui district of Otsuchi in the coast of Iwate, Japan. The samples were analyzed using an electron probe X-ray micro analyzer (JEOLJXA 8600) . While the otolith from the Hei River showed a high Sr : Ca ratio, those from the Gensui district showed a low value and little fluctuation. We can conclude from these findings that G. aculeatus (L.) collected from the Hei River is an anadromous type, whilst G. aculeatus (L.) collected from the Gensui district is a fresh water type.
- 著者
- 後藤 光将
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.60, 2009
1 0 0 0 IR ジョージア州における黒人リテラシー教授禁止法制の展開
- 著者
- 住岡 敏弘 Toshihiro SUMIOKA
- 出版者
- 宮崎公立大学
- 雑誌
- 宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities (ISSN:13403613)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.73-84, 2014
本稿は、アメリカ南部で、プランテーション労働を支える労働力として奴隷制が発展していくなかで、どのように黒人に対して「読み書き」の教授の禁止の法制化が展開したかについて、ジョージア州を事例に取り上げ、明らかにしてきた。その法制化過程は大きく2つの段階に分けることができる。第一段階は、奴隷法による奴隷に対する読み書きの禁止の法制化の段階である。第二段階は、1829年の、いわゆる「反識字法」の一環として「黒人商船隔離法」が制定された段階である。こうした段階を経て、リテラシー教授禁止は自由黒人にまで広げられ強化されていった。
1 0 0 0 OA 超音速分子ジェット分光分析
- 著者
- 今坂 藤太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.3-30, 2001-01-05 (Released:2008-12-12)
- 参考文献数
- 98
- 被引用文献数
- 3 4
超音速分子ジェット分光法は, 試料分子を気体状態で絶対零度付近に冷却して測定する方法である. 試料分子を冷却することにより, 鋭い構造の励起スペクトル, あるいは多光子イオン化スペクトルが得られる. 更に, 蛍光スペクトルあるいは光イオン化質量スペクトルを測定して, 試料分子を同定することもできる. したがって, スペクトル選択性が極めて高い. 必要な場合には, シンクロナススキャンルミネッセンス分光法や, クロマトグラフなどの分離手段と結合することにより, 更に選択性を向上させることも可能である. 一方, この手法は原理的には単一分子を検出できる分析感度を有している. したがって, 本法は極限の選択性と感度を同時に持っている. 最近, ダイオキシンを超微量分析するための手法が強く要望されているが, 超音速分子ジェット法は, そのための有力な分析法として注目されている. しかし, ダイオキシンは毒性の異なる多数の分子種の集まりであり, それらを区別して測定することが必要である. また, これらの化合物は極めて毒性が高く, 極微量分析も同時に要求される. 現在, ダイオキシン分析に適用できる超音速分子ジェット分光法の技術開発が進められており, ここではその現状についても言及する.
1 0 0 0 OA ダム建設と技術基準
- 著者
- 勝俣 昇
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.201-207,a1, 1987-03-01 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 17
ダム建設技術の発展と基準化の過程およびわが国と世界各国の基準の整備状況を解説した。また問題点としてダムの安全率の合理的な分析と, わが国と諸外国の基準の相異点の調和の必要性を指摘した。とくに, 動的解析等の新しい技術体系が大型のRC表面遮水壁型ロックフィルダムを可能とした点, また地震力と洪水流量の適用性の広い決め方等で基準が異なること, さらにこれらの点が, わが国の海外技術活動の制約となりうることを指摘した。
1 0 0 0 IR 拡大EUの境界--なぜオランダはトルコのEU加盟を拒否するのか
- 著者
- 尾崎 正延 久保 幸恵
- 出版者
- 神奈川工科大学
- 雑誌
- 神奈川工科大学研究報告 A 人文社会科学編 (ISSN:09161899)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.15-20, 2010-03
1 0 0 0 IR 「出雲方言と石見方言の境界域調査」のための予備調査結果の分析とその方法の検討(1)
- 著者
- 高橋 純 山下 由紀恵
- 出版者
- 島根県立大学短期大学部
- 雑誌
- 島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要 (ISSN:18826768)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.63-71, 2013-03-31
- 著者
- 吉田 実 森本 宏
- 出版者
- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.337-341, 1963
- 被引用文献数
- 1
予備飼育飼料を与えて調整した成熟雄ラットに,各種澱粉を含む試験飼料を給与して排糞量を測定することによって,それぞれの供試澱粉と同じ消化性をもつトウモロコシ,ジャガイモ澱粉混合物を推定し,混合物中のジャガイモ澱粉含量をもってPSスコアとし,これによって各種澱粉の消化性を示すことを試みた.<br> 15種類の天然澱粉について検討した結果,穀類澱粉のPSスコアはほぽ0であって消化性が非常によかった.マメ類の澱粉がこれについでPSスコアは約10であった.球根,塊根類はかなり変化があって, PSスコアはタピオカ,タロー,クズ,ヒガンバナ,サツマイモ,ヤマユリ,ジャガイモの順であった.このようなPSスコアによる配列の順序は澱粉結晶部分の結晶構造による配列とかなりよく似ている.<br> さらに,排糞量から消化率を推定する方法を考案して各種澱粉の消化率を推定した.この方法は非常に簡便で化学分析の必要がなく,供試澱粉の所要量も非常に少なくてよい長所をもっている.
1 0 0 0 OA 岐路にきた日本の安全管理
- 著者
- 中村 昌允
- 出版者
- 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.1-2, 2018-02-28 (Released:2018-02-28)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA Prognostic Impact of Statin Use in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction
- 著者
- Kotaro Nochioka Yasuhiko Sakata Satoshi Miyata Masanobu Miura Tsuyoshi Takada Soichiro Tadaki Ryoichi Ushigome Takeshi Yamauchi Jun Takahashi Hiroaki Shimokawa on behalf of the CHART-2 Investigators’
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.574-582, 2015-02-25 (Released:2015-02-25)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 15 53
Background:The effectiveness of statins remains to be examined in patients with heart failure (HF) with preserved ejection fraction (EF).Methods and Results:Among 4,544 consecutive HF patients registered in the Chronic Heart Failure Registry and Analysis in the Tohoku district-2 (CHART-2) between 2006 and 2010, 3,124 had EF ≥50% (HFpEF; mean age 69 years; male 65%) and 1,420 had EF <50% (HF with reduced EF (HFrEF); mean age 67 years; male 75%). The median follow-up was 3.4 years. The 3-year mortality in HFpEF patients was lower in patients receiving statins [8.7% vs. 14.5%, adjusted hazard ratio (HR) 0.74; 95% confidence interval (CI), 0.58–0.94; P<0.001], which was confirmed in the propensity score-matched cohort (HR, 0.72; 95% CI, 0.49–0.99; P=0.044). The inverse probability of treatment weighted further confirmed that statin use was associated with reduced incidence of all-cause death (HR, 0.71; 95% CI, 0.62–0.82, P<0.001) and noncardiovascular death (HR, 0.53; 95% CI, 0.43–0.66, P<0.001), specifically reduction of sudden death (HR, 0.59; 95% CI, 0.36–0.98, P=0.041) and infection death (HR, 0.53; 95% CI, 0.35–0.77, P=0.001) in HFpEF. In the HFrEF cohort, statin use was not associated with mortality (HR, 0.87; 95% CI, 0.73–1.04, P=0.12), suggesting a lack of statin benefit in HFrEF patients.Conclusions:These results suggest that statin use is associated with improved mortality rates in HFpEF patients, mainly attributable to reductions in sudden death and noncardiovascular death. (Circ J 2015; 79: 574–582)
1 0 0 0 OA ワクチン変遷半世紀を共にして
- 著者
- 大谷 明
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.85-87, 2000-06-01 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 鳥居 昭久 小形 滋彦
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.C4P1126-C4P1126, 2010
【目的】ボートジュニア世界選手権大会(2009年8月5日~8日、フランス)への日本代表チームトレーナーとして帯同する経験を得た。ボート競技については、シニアチームには専属トレーナーが帯同しているが、ジュニアチームには初めての帯同となった。これは競技力向上の一つとして、これまでコーチと選手のみだったジュニアチームに、トレーナーサポートを加え、コンディショニングなどに対する意識向上を図る意味があった。今回、このサポート経験からボート競技における今後の課題を明らかにし、多くのジュニアスポーツに共通すると思われる課題について考察することを目的に報告する。<BR><BR>【方法】2009年ボートジュニア世界選手権大会に参加した日本代表選手10名(男性5名、年齢17.8±0.4歳、身長182.8±5.1cm、体重78.0±6.8kg、女性5名、年齢17.2±0.4歳、身長165.2±2.9cm、体重61.8±2.4kg)を対象として、国内外での事前合宿および本大会期間中の約3週間のトレーナーサポートを実施、ここでみられた問題点について検討した。選手把握の為に国内合宿前に文書にて状況調査を行い、それに基づいて合宿時に初回面接を行った。また、合宿および遠征中の毎朝、簡易調査票を配布回収し、必要に応じて問診を行った。トレーナーサポートとしては、身体的問題点に対する治療的なアプローチ(物理療法や運動療法による)、ストレッチングやテーピングなどの指導や実施、休養や栄養摂取などのアドバイス、必要に応じて面接などによる心理的サポート、日本ボート協会医科学委員会所属医師との連携による医療サポートなどを行った。<BR><BR>【説明と同意】今回のトレーナーサポートは日本ボート協会医科学委員会からの派遣によるものであり、得られた情報は全て日本ボート協会医科学委員会に帰属する。また、各選手および所属の高校ボート部顧問へ事前に説明の文書を送付し、トレーナーサポートとそこで得られた情報は、個人情報保護法に則り厳正に管理される旨の説明を文書にて行い、同意を得た。<BR><BR>【結果】最終的には、全選手に何らかのトレーナーサポートが必要であった。身体的問題点としては、慢性障害がほとんどであり、筋の張りや関節可動域制限が中心であった。原因は疲労の影響によるもの、フォームの崩れ、アライメント不正からと考えられるものが多かった。国内合宿2日間におけるトレーナーサポートは合計20回、移動日を除く直前合宿および本大会期間中の17日間は合計141回となった。また、全選手にストレッチ方法や事後のトレーニング、休養方法や栄養摂取などについてのアドバイスが必要であった。特に補食摂取については、管理が必要な場面があった。他、本大会競技中には大きなトラブルは発生せず、各レースに向けてのコンディショニングは順調であった。<BR><BR>【考察】ボート競技は陸上競技や水泳競技などと同様に、本大会までのトレーニングやコンディショニングピークの合わせ方が、競技成績に大きな影響を与える。今回のトレーナーサポートによって、身体的問題点に対して事前に対応できたことが、本大会でのトラブルを未然に防ぐことにつながったと推察される。一方、ジュニアスポーツ選手ということもあり、自分の身体的特徴や問題点を十分に把握できていない面がみられ、将来的な障害発生の危険性が推察された。これは、身体的機能やトレーニング方法のみならず、栄養管理や休養の取り方などの知識にもみられ、個人差も大きかった。今回の帯同時に、これらについて個々に具体的な指導ができたことの意義は大きいと感じた。身体的変化の大きな発達期のジュニアスポーツ選手という特性から考えても、日常的、長期的なサポートが必要であり、加えて、中高校部活動が中心のジュニアスポーツにおける指導者の多くが、必ずしも身体的問題の専門家ではないことを含めて考えても、日常的で継続的なトレーナーサポートの必要性は大きいと思われた。<BR><BR>【理学療法学研究としての意義】ジュニアスポーツに対する日常的で継続的なトレーナーサポートは、スポーツ障害予防の観点からも重要であり、理学療法士がチームのトレーナーとして果たせる役割は大きい。このため、様々なジュニアスポーツにおける理学療法士の関わり方を検討する必要がある。