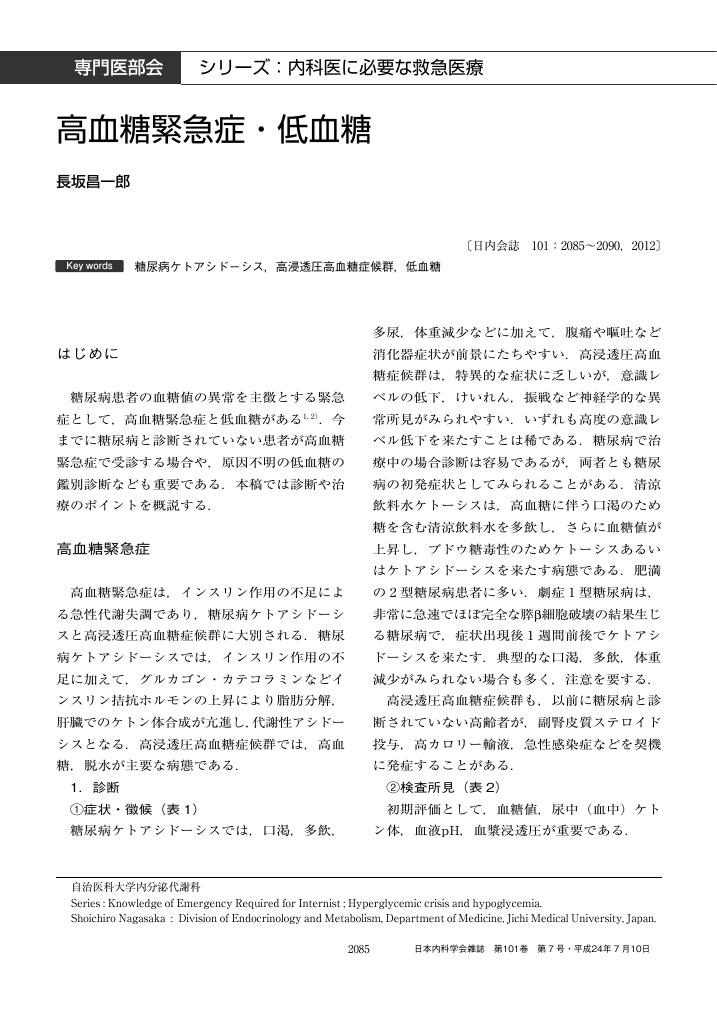5 0 0 0 IR H.D.マクラウドの信用理論と近代的信用観の形成
- 著者
- 二階堂 達郎
- 出版者
- 大手前女子大学
- 雑誌
- 大手前女子大学論集 (ISSN:02859785)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.p159-171, 1993-12
5 0 0 0 IR マラッカの琉球人 : ポルトガル史料にみる
- 著者
- 中島 楽章
- 出版者
- 九州大学大学院人文科学研究院
- 雑誌
- 史淵 (ISSN:03869326)
- 巻号頁・発行日
- vol.154, pp.1-42, 2017-03
5 0 0 0 OA CYP2C19,CYP2D6,およびCYP2C9の遺伝子多型と人種差
- 著者
- 久保田 隆廣 千葉 寛 伊賀 立二
- 出版者
- The Japanese Society for the Study of Xenobiotics
- 雑誌
- 薬物動態 (ISSN:09161139)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.69-74, 2001 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2 4
Approximately 1% of Orientals and 7 to 10% of Caucasians lack the activity of cytochrome P450 (CYP) 2D6, and these individuals are known as poor metabolizers (PM). On the other hand, approximately 4% of Caucasians are PM of CYP2C19, while its frequencies are 18 to 23% in Orientals. These differences in the frequencies of PM seen in the different ethnic populations are mainly due to the differences in the distribution frequency of variously defective alleles of CYP2D6 and 2C19. Recent progress in molecular biology of CYPs has enabled the mechanism of CYP polymorphism to be elucidated and the polymerase chain reaction was developed for its genotyping. Our previous studies showed that the frequencies of CYP2C19*2, *3, CYP2D6*2, *5, *10, *14, and CYP2C9*3 among the Japanese subjects were 28.7, 13.2, 12.9, 6.2, 38.6, 2.2 and 2.1%, respectively. In this review, we compared the frequencies of these mutant alleles of CYPs seen in the Japanese population with those reported previously for other ethnic populations.
5 0 0 0 OA マッド・マックスは遺伝子転写を抑制する!
- 著者
- 米田 幸雄
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.62-63, 1994-01-01
5 0 0 0 OA ドイツ連邦共和国における男女平等立法 : 第2次指導的地位法に至るまで
- 著者
- 泉眞樹子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- no.290, 2021-12
5 0 0 0 OA 日常の対人関係と実験場面における内集団の成立について
- 著者
- 田島 司
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.145-155, 2001-07-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 41
本研究の目的は, 日常生活における対人関係が実験場面における内集団バイアスと協力行動とに与える影響を検討することである。87名の女性の調査対象者は, 日常での対人関係に関するいくつかの質問に回答するよう求められた。その回答によって, 他者との同一化の程度と, 自己の役割を顧みている程度が測定された。実験参加者は無作為に2つの集団のどちらか一方に所属するよう割り振られ, その後集団成員の属性について評価するよう求められた。また, 被験者は社会的ジレンマ状況におかれ, 100ポイントを自己と内集団とに対して分配するよう求められた。実験の結果は以下の通りである, (a) 能力評価における内集団バイアスは家族との同一化と負の相関関係にあった, (b) 協力的分配は家族での自己の役割を顧みる程度と正の相関関係にあった。
- 著者
- 望月吉彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.30-39, 2021-02-26 (Released:2021-03-01)
- 参考文献数
- 17
5 0 0 0 OA 犯罪報道研究の現状と課題
- 著者
- 牧野 智和
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 : 別冊 (ISSN:13402218)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.13-24, 2012-09-30
- 著者
- 槌野 正裕 荒川 広宣 石井 郁江 西尾 幸博 高野 正太 山田 一隆 高野 正博
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.AcOF1012-AcOF1012, 2011
【背景】アブラハム・マズローは、人間の基本的欲求を低次元から、1.生理的欲求、2.安全欲求、3.愛情欲求、4.承認欲求、5.自己実現欲求と5段階に分類している。生きていくうえで欠かすことの出来ない生理的欲求には、食欲、性欲、睡眠欲、排泄欲などが含まれている。リハビリテーション医療分野では、排泄欲に対する機能訓練は皆無である。排泄に関する問題は、個人だけではなく、その家族や介護者にとっても社会参加の阻害因子となり、Quality of Life(QOL)の重要な要素となる。我々は、大腸肛門病の専門病院として第43回当学会から継続して、排便に関する研究を行ってきた。今回、排便時の動態を調査することを目的として、排便姿勢の違いにより、直腸肛門角(anorectal angle:ARA)がどのように変化し、また、排出量に及ぼす影響について、排便造影検査(Defecography)を用いて検討したので以下に報告する。【方法】対象は、2010年1月~6月にDefecographyを行った160例とし、以下の3項目について検討した。1.排出時(strain)での伸展姿勢と前屈姿勢を撮影できた59例(男性21例、女性38例、62.2±18.7歳)を対象としてARAを比較した。2.大腿骨頭を頂点とし、仙骨上端(岬角)と尾骨先端との為す角(α)を計測できた23例(男性13例、女性10例、60.1±25.1歳)を対象として、排便姿勢の違いによる仙骨の傾きを比較した。3.排便困難を主訴とした症例の中で、排便姿勢を変えて排出量の測定が可能であった20例(男性7例、女性13例、64.6±13.7歳)では、伸展姿勢と前屈姿勢での排出量の差を比較した。Defecographyは、小麦粉と粉末バリウムを混ぜ合わせた疑似便(1回量225g)を直腸内に注入し、安静時(rest)、肛門収縮時(squeeze)、排出時(strain)の3動態と一連の動きを動画で撮影する。撮影された画像は、放射線技師が電子ファイル上で計測を行った。検定は、関連あるT検定と相関係数を用いて、有意水準5%未満を有意と判断した。【説明と同意】当院倫理委員会の許可を得て、臨床当研究に取り組んだ。【結果】59例の主訴の内訳は、便秘(排便困難含む)22例、便失禁(尿失禁含む)9例、脱出12例、肛門痛17例、その他21例(重複あり)であった。1.StrainでのARAは、伸展姿勢で114.1°±21.0°、前屈姿勢で134.6°±16.8°となり、前屈姿勢で有意に鈍角であった。また、相関係数は、0.716と高い正の相関を示した。2.α角は、伸展姿勢で84.9°±10.8°、前屈姿勢で92.4°±10.7°となり、前屈姿勢で有意に鈍角であり、仙骨はうなずいていた。相関係数は、0.826と高い正の相関を示した。3.排出量は、伸展姿勢で90.1g±18.3g、前屈姿勢で140.7g±20.9gであり、前屈姿勢で有意に排出量が増大した。【考察】今回、Defecographyを用いて、排便姿勢の違いはARAにどのような変化をもたらすのかを検討した。ARAに関する報告は多数存在するが、排便姿勢の違いによる報告は見当たらない。臨床場面での経験から、排便困難症例では、息めば息むほど背筋を伸ばした伸展姿勢となる症例が多く存在する。そのような症例に対して、排便姿勢の指導を行うことで排便困難が改善する症例もみられていた。今回の研究結果から、排便時は前屈姿勢の方がARAは鈍化し、排出量が増大する結果となり、姿勢指導の方法が妥当であったと考えられる。排便に関しては、まず、便意の出現が重要であることは言うまでもないが、その他の要素として、前屈姿勢になることで骨盤帯は後傾方向への動きとなる。骨盤が後傾することで仙骨は前方へ倒れ、うなずき運動を伴う。直腸は、仙骨前面の彎曲と一致することから、仙骨が前方へうなずくと、骨盤底の後方ゾーンで重要とされる肛門挙筋が緊張し、直腸を後上方へ引き上げるためARAは鈍化したと考えられる。【理学療法学研究としての意義】生きていく上で、また、在宅生活を遂行する上で、排泄は大きな課題となる。日常生活動作に直結する排泄動作に関して、理学療法士が排便の仕組みを知ることで、適切なアドバイスが提供できるようになると考えられる。それは、例えば、介護分野で数年前から言われている、「寝たままのオムツでの排泄ではなく、トイレでの排泄を介助する。」ことの根拠となり、また、運動学的知識が豊富な理学療法士が、骨盤周囲の運動機能の評価・治療を行うことで、排便を行いやすくできる可能性があると考えられる。
5 0 0 0 IR アイドル文化における「チェキ」 : 撮影による関係性の強化と可視化
- 著者
- 上岡 磨奈
- 出版者
- 三田哲學會
- 雑誌
- 哲學 (ISSN:05632099)
- 巻号頁・発行日
- no.147, pp.135-159, 2021-03
This study examines the tools of communication between fans and young pop singers, also known as idols, focusing on the "Cheki" — a type of photography taken by small polaroid camera. It has been proposed that the figure of idol culture is in the relationship between idols and fans, and it is not vertical but horizontal. "Cheki" notably symbolize this relationship. In this paper, I will clarify the meaning of this phenomenon in the context of the Japanese idol culture. I demonstrate that the concept and process of taking "Cheki" photography has not been described in previous studies. Although "Cheki" can be considered a similar to Handshake events, there are many differences between these activities. To observe the rules and behavior during the "Cheki" shootings, I have conducted web survey and interview with participants, including both fans and idols. As a result, it became clear that "Cheki" photography has strong connection with and within the idol culture. I argue that intimacy between fans and idols tha t appears during the photo shooting is a symbol of idol culture. Moreover, the materialness of "Cheki" also visualizes accumulation and such connection.投稿論文
5 0 0 0 OA マルチエージェントシミュレーション:1.マルチエージェントシミュレーションの基本設計
5 0 0 0 OA 『権記』所載の一条院出離歌について
- 著者
- 山本 淳子
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.35-43, 2006-09-10 (Released:2017-08-01)
『権記』は一条院が出家後死の床で詠んだ歌を記し、後に「其の御志は皇后に寄するに在り」とする。近年この「皇后」を時の中宮彰子ではなく故定子だとする新釈が提出された。検証のため『権記』中の定子と彰子の呼称を全て調査すると、「皇后」は彰子立后当初は彰子専用だったが、定子崩御後は定子専用の語となったと判明、当該「皇后」は定子との結論に達した。これを受け、行成がそう考えた要因を考察、彼の見方に従う本歌通釈を試みた。
5 0 0 0 OA 小田流の一考察
- 著者
- 岡田 一男
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.1-9, 1974-03-25 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 7
5 0 0 0 OA 「原子力の平和利用」と近代家族
- 著者
- 加納 実紀代
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.5-19, 2015 (Released:2016-11-10)
- 参考文献数
- 21
日本の原発導入は、1953 年12 月のアイゼンハワー米大統領の国連演説「原子力の平和利用」に始まるが、その年は日本の「電化元年」でもあった。テレビ放映が始まり、家庭電化製品が相次いで売り出された。54 年3 月には「原子力の平和利用」は国策として動き出すが、それにともなって電化ブームがおこり、55 年にはテレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫が「三種の神器」としてもてはやされる。その背景には、占領下において流布した原爆の威力への肯定的評価やアメリカ文化の紹介によってかき立てられた電化生活への憧れがあった。1952 年4 月の独立後、原爆の人体への被害が報道されるようになるが、物理学者武谷三男は被爆国だからこそ「平和利用」すべきだという原発推進の論理を展開、『読売新聞』を中心とするマスメディアも、アメリカと協力して「平和利用博覧会」を主催するなどキャンペーンにつとめた。その一方、54 年3 月のアメリカの水爆実験によるビキニ事件をきっかけに、女性を中心に原水爆禁止署名運動が盛り上がり、55 年8 月には国民の3 分の1 以上という多数の署名が集まっている。原発導入と原水爆禁止運動は両立・同時進行したことになる。それを可能にした一因として、「原子力の平和利用」という経済発展は男性、原水爆禁止という平和運動は女性というジェンダー分業があげられる。電化生活による近代化、産業構造の高度化により、社員・主婦というジェンダー分業を柱とする近代家族が普遍化したが、それは家庭内にとどまらず、進歩・発展は男性、ケアや後始末は女性という社会的分業をも定着強化した。
5 0 0 0 OA 人間の歩行, ロボットの歩行
- 著者
- 江原 義弘
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.12, pp.1018-1023, 2006-12-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 小林 豊 飯干 茜 渡邉 博文 井出 和希 堀内 祐希 手島 麻美子 中川 喜文 山口 安乃 小林 伸一郎 谷口 幹太 関 泰 榊間 昌哲 鈴木 豊秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会
- 雑誌
- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.347-355, 2021 (Released:2021-12-29)
- 参考文献数
- 12
CKDシールは、腎機能情報共有により患者に有効かつ安全な薬物療法を提供することを目的に各地で検討されている。CKDシールに対する病院・薬局薬剤師のニーズに関する調査は存在するものの、患者が腎機能情報共有の必要性をどのように理解しているかは不明である。静岡県富士宮市でCKDシール貼付システムを構築するとともに、富士宮市立病院でシールを貼付した患者のニーズと、同地域における腎機能情報共有の現状と課題を調査した。2019年7月10日からの3か月間にお薬手帳にCKDシールの貼付を提案した228名の患者全員より同意を得た。医師と作成したプロトコルに基づく貼付を行った患者は62名(27%)であった。アンケートは入院患者、腎臓病教室受講患者、維持透析患者74名中67名(G3b/G4/G5/G5D=7/12/11/37、回答率91%)及び、腎臓病薬物療法の研修会に参加した薬局薬剤師20名中19名(回答率95%)から回答を得た。保険薬局で薬を貰った経験は患者51名(76%)が有したが、51名のうち腎機能を伝えた患者は10名(20%)のみであり、薬局薬剤師から腎機能を聞かれた患者は15名(29%)のみであった。一方、薬局薬剤師16名(84%)は検査値を入手できた時にのみ腎機能を確認していた。腎機能により薬を調節することへの患者の認知度は29名(43%)と低く、CKDシール貼付開始を全ての患者と薬局薬剤師が期待すると回答した。薬局薬剤師のCKDシール活用方法は用法用量等の確認だけでなく、患者とのコミュニケーションや生活指導が挙げられた。患者は薬局薬剤師に腎機能情報が必要との認識が低く、腎機能の共有はされていなかった。CKDシールが薬物療法適正化につながるだけでなく、腎機能情報共有の意義を患者に説明し理解を得ることで、CKDシールが貼られたお薬手帳の活用と薬剤師による腎臓病療養指導につながる可能性が示唆された。
5 0 0 0 IR こわい隣人――香港における東南アジアの呪いのイメージ
- 著者
- 小栗 宏太 オグリ コウタ OGURI Kouta
- 出版者
- 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
- 雑誌
- Field+ : フィールドプラス : 世界を感応する雑誌 / 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 [編] (ISSN:18834957)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.14-15, 2021-07-10
5 0 0 0 OA 高血糖緊急症・低血糖
- 著者
- 長坂 昌一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.7, pp.2085-2090, 2012 (Released:2013-07-10)
- 参考文献数
- 3
本研究では、以下のようなことを明らかにすることができた。1.地方自治体に対して国が交付する在日米軍基地・自衛隊関連交付金等(基地交付金)は、補助率が高く、これを受ける地方自治体は基地交付金に依存する傾向が見られる。また、その算定にあたり国の裁量が働く余地があり、この仕組みは依存を昂じさせる。2.基地交付金は、これまで自治体の公共事業の実施に大きな影響を与えてきた。過疎地域の地方自治体がこの傾向から脱却することは容易でない。しかし、産業の発展している都市周辺部の自治体の基地交付金依存度はさほど大きくない。3.一部地域では、新しい基地公害(野生種絶滅の危険)などに基地交付金を対応させる必要が見られる。4.軍事施設・基地は、当該地域の産業や住民の生活に密着する限りにおいて地域経済の活性化効果をもつが、その施設の後始末、発生する公害等の処理を考慮すると、短期的な効果だけでみるのは問題である。5.基地と地域経済とは微妙なバランスをたもたせながらも、将来的には暮らし密着型の産業構造へシフトすることが求められる地域は少なくない。6.沖縄県では、復帰により経済の基地依存度は大きく落ちたが、近年、やや高めている。そのような中で、軍用地料が「相当に高い」という問題がある。このことが沖縄経済だけでなく自治体行財政にもゆがみをもたらしている。