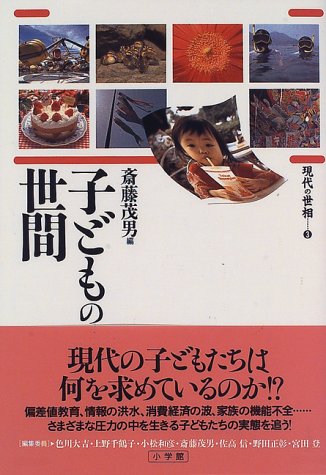1 0 0 0 IR 書評リプライ : ドキュメントとストーリー : 水野節夫氏の拙著書評に寄せて
- 著者
- 有末 賢
- 出版者
- 三田社会学会
- 雑誌
- 三田社会学 (ISSN:13491458)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.146-150, 2013-07
書評目次のタイトル : 「著者リプライ :」
1 0 0 0 OA 50回特別記念講演「日本赤十字社医学会の50 年を紐解く」
- 著者
- 富田 博樹
- 雑誌
- 日赤医学 = The Japanese Red Cross Medical Journal
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.27-29, 2014-10-16 (Released:2014-09-24)
第50 回日本赤十字社医学会総会市民会館崇城大学ホール平成26 年10 月16 日(木)・17 日(金)熊本赤十字病院座長 若杉健三(大分赤十字病院 院長)
1 0 0 0 劉漢関係緯書の五徳終始説について
- 著者
- 安居 香山
- 出版者
- 東京支那学会
- 雑誌
- 東京支那学報 (ISSN:05638348)
- 巻号頁・発行日
- no.10, 1964-06
1 0 0 0 IR 認定こども園における子育て支援の現状と課題
- 著者
- 吉田 幸恵
- 出版者
- 名古屋経営短期大学子ども学科子育て環境支援研究センター
- 雑誌
- 子ども学研究論集 (ISSN:18837387)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.51-68, 2009-03
- 著者
- 山下 明
- 出版者
- 文学教育研究者集団
- 雑誌
- 文学と教育 (ISSN:02876205)
- 巻号頁・発行日
- no.142, pp.34-40, 1987-11-01
1 0 0 0 OA 藤原道信とその和歌についての一考察
- 著者
- 大隅 順子
- 出版者
- 福岡女子大学
- 雑誌
- 香椎潟 (ISSN:02874113)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.6-23, 1965-02-25
これまでマングローブ林を農地開発した場所や開拓地で第四系海成堆積物を起源とした酸性硫酸塩土壌が問題となってきた。しかし農地開発や土木工事の規模が大きくなるにつれ、第三系堆積岩を起源とする酸性硫酸塩土壌の生成も顕在化してきた。本研究により、酸性硫酸塩土壌の母材となるパイライトを含む第三系堆積岩が、これまで問題となっていなかった場所も含め、広く日本に分布することがわかった。インドネシア東カリマンタン州やタイ南部でパイライトを含む第三系堆積岩を発見し、これまで第四系堆積物のみが問題となっていた熱帯地域においても、今後開発にともない第三系堆積岩を起源とする酸性硫酸塩土壌が問題となる可能性があること明らかにした。常磐自動車道の建設地で露出した古第三系堆積岩からは酸性化により特徴的にマンガンの溶出が起こり、植栽された樹木にもマンガンの過剰障害が顕著に現れた。このような強酸性土壌には低pHに対する耐性だけでなく、マンガン過剰に対する耐性が植栽樹木に要求される。このため比較的マンガン過剰に耐性があると考えられるシラカンバを用いて、マンガンによる障害の発生機構を調べ、光合成系に障害が発生することがわかった。熱帯産マメ科樹木のAcacia mangiumとA.auriculiformisは、低pHやマンガン、アルミニウムの過剰に対して耐性が大きく、熱帯での酸性硫酸塩土壌による荒廃地の森林再生に有効な樹種であることがわかった。さらなる耐性をもつ新樹木の作成にむけて、A.mangiumとA.auriculiformisの組織培養系を確立し、さらにA.mangiumの細胞培養系を用いて低pHとマンガン過剰に対する細胞レベルの反応を明らかにした。また高マンガン耐性細胞系の選抜をおこなった。これらの研究を基盤にして、酸性土壌に起因するストレスに対する耐性機構を解明し、また新たな耐性の付与を行い、荒廃地への造林樹種の開発と森林再生を目指して研究を進めて行く。
- 著者
- 川合 道雄
- 出版者
- 早稲田大学国文学会
- 雑誌
- 国文学研究 (ISSN:03898636)
- 巻号頁・発行日
- no.78, pp.p59-70, 1982-10
本研究は次の3つの計画から構成されている.計画1:過去のサンゴ礁生態系の復元(最終氷期以降のサンゴ礁試料を用いて,過去のサンゴ礁生態系を復元する.とくに,サンゴ礁生態系の成立維持に関わった重要な生物(以下,鍵種)を発見する.).計画2:現在のサンゴ礁生態系の評価(過去100年間を対象に,地球温暖化と人為影響を受けたサンゴ礁生態系の現状評価を行う.).計画3:将来のサンゴ礁生態系の予測(将来の地球温暖化と人為影響下におけるサンゴ礁生態系の予測を行う.).・計画1の実施状況:南西太平洋におけるサンゴ礁生態系の鍵種発見についての成果を国際誌に公表した.また,西インド洋におけるサンゴ礁生態系の鍵種発見についての成果をまとめた.さらに,これまで進めてきた3つの海域(北西太平洋と南西太平洋,インド洋)の鍵種の生物地理が明らかとなったため,国際誌に投稿した.・計画2の実施状況:沖縄県石垣島のサンゴ礁生態系を対象に現状評価を行なった.過去15年間のサンゴの被度の低下が,高水温と頻繁に来襲した台風による影響であることが明らかとなった.また,人間活動に伴う陸域からの赤土流出も影響していることも明らかとなった.この成果は国際誌に公表した.・計画3の実施状況:琉球列島(沖縄本島と石垣島,久米島,奄美大島,徳之島)のサンゴ礁生態系を対象に将来予測をおこなった.石垣島を対象とした例では,将来の海面上昇と台風の強度の増大に注目したところ,鍵種が減少している西海岸では今後,サンゴ礁生態系の成立が困難になる可能性が高いことが明らかとなった.この成果は国際誌投稿に向けて準備中である.
1 0 0 0 OA アイルランド修道会の女子教育への貢献―日本に派遣されたシスターを中心に
カトリック国アイルランドでは、学校教育にも教会が様々に関与し、強い影響を及ぼしてきた。20世紀初頭のイギリスに対する抵抗を経て、勝ち得た共和国においても、女性の生き方に制約や抑圧を加える面が大きかった。しかし、一方でイギリスに比べても早い時期に男性と対等な高等教育を受け、混乱期に立ち上がり、強く戦った女性たちも少なくない。その中の著名な1人の一族で、日本では閉鎖的な印象を与えてきた女子修道会運営の中等教育の場に入って、社会正義と公正さを大切に、闊達な生き方で周囲を魅了したシスターシーヒーの女子教育への貢献などを理解し、本来修道会が目指す外部社会に対しても開かれた考え方を認識させられた。
1 0 0 0 OA 講座 : 微分解析機(1)
- 著者
- 渡邊 勝 三井田 純一
- 出版者
- 誠文堂新光社
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.6, pp.274-279, 1950-06-01
微分解析機(Differential Analyzer)は原則として常微分方程式を自動的に解く裝置です.このような機械の出現はおそらく技術の革命をもたらし,今後われわれは式を作ることと,これを機械の上に導く變形をするだけで問在題は解決され近似式とか,數値計算は不要になるでしようまた計算の困難のために捨てておかれた重要な問題も解決して行くでしよう.こゝではこの裝置の詳細と原理及びわれわれが今まで取扱つた問題を例としてその應用についての解説を行います
1 0 0 0 OA 基質強化した文化遺産建造物基材に対する地衣類の定着特性
- 著者
- 河崎 衣美
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2014-08-29
屋外環境に曝される石造文化遺産に初期に付着する微生物のうち、初期対応の必要性が高いと考えられる地衣類について修復材料を適応した際の文化遺産建造物基材に対する定着挙動を調査した。基質強化が施された試験体への地衣類の付着は撥水処置のみ施された試験体と比較して著しく少ないことがわかり、基質強化処置の重要性が明らかとなった。基材の化学的劣化の要因となる地衣類の二次代謝産物の有無を分析する方法を構築した。
1 0 0 0 OA 覚醒度向上のための体内時計光受容センサー・光制御用 LED システムの開発
1 0 0 0 OA 支那事変と半島人の銃後の護り
- 出版者
- 栄尚協会本部
- 巻号頁・発行日
- 1937
1 0 0 0 量子ドット構造によるボルツマンマシン形ニューロンデバイス
- 著者
- 李 学秀 呉 南健 雨宮 好仁
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SDM, シリコン材料・デバイス
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.273, pp.45-50, 1997-09-26
電子スピンの交換相互作用を利用した量子ボルツマンマシンニユーロンデバイスを提案する. このデバイスは結合量子ドットの2次元アレイからなる多入力しきい素子である. 各量子ドットを占める電子のスピン状態("up"と"down")でバイナリ信号("1"と"0")を表す. 入力総和の大きさに応じて確率的に"1"と"0"を出力する. 計算機シミュレーションで本デバイスの動作特性を解析し, ボルツマンマシン用ニューロンデバイスとして動作し得ることを示す.
1 0 0 0 OA 転送ボトルネックフリー不揮発ロジックインメモリ多値VLSIの開発
細粒度ダイナミックリコンフィギャラブルVLSIの小型化,高性能化,低電力化のため,多値Xネット,マイクロパケット転送方式,多値電流モード回路技術,不揮発ロジックなどを駆使したアーキテクチャを検討した.これにより,メモリ・演算部の転送に伴う遅延や消費電力の減少やコンフィグレーション/コントロールメモリサイズの減少を達成することができた.さらに,より少ないハードウェアリソースにより任意の論理関数を実現でき,マルチプレクサを用いたラッチ機能を活用することにより記憶要素としても動作できるという特長を有する,2入力マルチプレクサを構成要素とする新しいセル構成も提案することができた.
1 0 0 0 久住真也著『長州戦争と徳川将軍-幕末期畿内の政治空間-』
- 著者
- 友田 昌宏
- 出版者
- 中央大学
- 雑誌
- 中央史学 (ISSN:03889440)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.123-134, 2008-03
1 0 0 0 OA 咀嚼時, 主機能部位の観察
- 著者
- 加藤 均 古木 譲 長谷川 成男
- 出版者
- 日本顎口腔機能学会
- 雑誌
- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.119-127, 1996-01-31
- 被引用文献数
- 30
硬い食品の咀嚼時に破砕を行う部位を確定するために, 試験食品としてストッピングを用い, これを舌上に乗せて任意の位置での噛みしめを行わせた.5回の噛みしめで, 噛みしめ部位は多くの被験者で一定していたので, これを主機能部位と名付けた.24側の被験例について主機能部位の観察を行い, 以下の結論を得た.1.主機能部位は多くの被験例で対合する上顎第1大臼歯口蓋側咬頭と下顎第1大臼歯頬側咬頭内斜面の間に存在していた。2.主機能部位は咬頭嵌合位において最も緊密な咬合関係を示す部位に一致していた.3.主機能部位は, 咬頭嵌合位での咬合関係の変化に伴って, 隣在歯あるいは頬舌的に同一歯牙の他の部位に移動した.