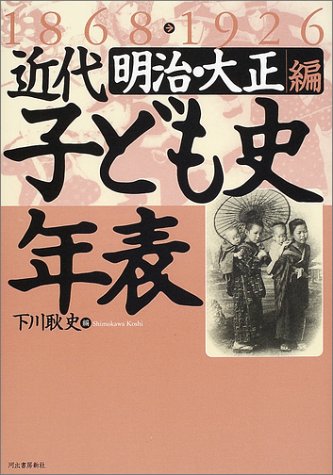1 0 0 0 OA 沐浴についての研究(第3報) : 藻風呂の歴史とその効用 : 11.保健に関する研究
1 0 0 0 超音波のうなりを利用した超音波実験装置の開発
- 著者
- 米田 隆恒
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.90-92, 2003
超音波の実験はさまざまな利点がある。しかし,超音波の発生方法は難しく,また,耳に聞こえないので観測が抽象的であるという難点がある。ところで,超音波のうなりの振動数が可聴音の領域にあると,うなりを耳で聞くことができる。このうなりを超音波の観測方法として利用し,ハウリングによる超音波発振機1)と組み合わせて,直感的にわかりやすい超音波実験装置を開発した。また,この装置を使って,干渉やドップラー効果などの生徒実験を行った。
1 0 0 0 IR 戦後の三井山野炭坑 (九州大学石炭研究資料センター10周年記念)
- 著者
- 八田 保政
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- エネルギー史研究 : 石炭を中心として (ISSN:02862050)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.228-249, 1991-12-25
1 0 0 0 家庭機能の外部化に関する社会分化史的アプローチ
家庭機能の外部化は、都市化と密接に関係する。都市への人口集中が、必然的に住宅価格を引き上げ、一家の居住面積を縮小した。結果的に家庭が果たしていたある部分が、外部化されていく。家庭機能の外部化が進行するということは、都市が拡大された家庭の役割を果たすことを意味する。家庭機能の外部化の進行は、経済発展と深く関わっている。戦後の急速な工業化社会の中で、第一次産業従事者が減り、代わりに第二次・第三次従事者が増大していった。まず食事機能の外部化を歴史的にみると古代から中世にかけては、花会の宴・歳賀の宴が盛んになっている。花会は梅・桃・桜・ハス・萩・菊の宴が主流であるが、遠出して野趣を味いながら一日を過ごすことも多くなった。その後、日本の宴会はいっぽうで確実に外部化が進み、多様化を示すとともに、また内在化も確実に定着しはじめている。現代の外食産業については、ファーストフードに代表されるが、その多様化も急速に進行中である。また宿泊機能の点ではなく、わが国におけるホテルの歴史は幕末の開港とともに始まった。神戸、横浜、長崎などの開港場には外国人の居留地が整備され、商用で訪れた外国人のための宿泊施設が、外国人の手によってつくられた。わが国のホテルは、外国人の旅行客をもてなす施設として誕生したため、一般には「洋風の宿泊施設」として理解されている。しかしその概念規程ははなはだ曖昧であり、このことは、ホテルの多様化をもたらしたと同時に、ホテルという用語の混乱を招く結果ともなった。さらに、ホスピタリティ機能の外部化について病院は、戦後、高度経済成長にともなう都市化の進行につれて、家庭で行えない療養の場として、急速に需要を延ばした。現代の日本人は、大多数が病院で生を受け、半数以上が病院で生を終える。病院は、日本人にとって実に身近な存在になっている。入院が驚くべき出来事ではなくなるにつれ、病院は家庭の延長としてとらえられるようにもなった。以上、本年度は食事・宿泊・ホスピタリティ(療養)の三つの家庭機能について、その外部化を考察した。
- 著者
- 吉村 貴之
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北 = Bulletin of the Wako Institute of Social and Cultural Sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.36-44, 2008-03-15
- 著者
- 吉村 貴之
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.36-44, 2008
1 0 0 0 OA 新豫算と増税問題
- 著者
- 汐見 三郎
- 出版者
- 京都帝國大學經濟學會
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.571-586, 1942-11
- 著者
- 宇佐美 賢祐
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- やどりが (ISSN:0513417X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.230, pp.22-23, 2011
1 0 0 0 IR フィギュアスケートにおける2回転と3回転フリップジャンプの動作分析
- 著者
- 山下 篤央 久米 雅 森井 秀樹 Atsuo YAMASHITA Masashi KUME Hideki MORII 京都文教短期大学 京都文教短期大学 京都文教短期大学 Kyoto Bunkyo Junior College Kyoto Bunkyo Junior College Kyoto Bunkyo Junior College
- 出版者
- 京都文教短期大学
- 雑誌
- 京都文教短期大学研究紀要 (ISSN:03895467)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.87-91, 2012
フィギュアスケート歴12年の女子ジュニア選手における2回転と3回転フリップジャンプの動作解析を行った。その結果、ジャンプの回転数の増加に伴い、Take-off時の膝関節伸展角度および回転運動の跳躍幅と時間の増加が認められた。これらの変化には、角運動量を増加するためのスキルが関連していると考えられる。また、Take-off時の左膝伸展角度が右膝伸展角度に比べ、高いことから左脚がジャンプ動作(跳躍高)に大きく貢献していることが示唆された。
1 0 0 0 OA 世界日曜学校大会記録
- 著者
- 日本日曜学校協会 編
- 出版者
- 日本日曜学校協会
- 巻号頁・発行日
- vol.第8回, 1921
1 0 0 0 IR 牛乳の殺菌温度によるアレルゲンの比較
- 著者
- 山田 満 山本 真弓 ヤマダ ミツル ヤマモト マユミ Mitsuru Yamada Mayumi Yamamoto
- 雑誌
- 和洋女子大学紀要. 家政系編
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.35-42, 2001-03-31
近年アレルギー疾患が増加する傾向にあり,アレルギー患者は国民の3分の1という高率になるという。そこで食物アレルゲンの一つである牛乳を対象として,牛乳の殺菌温度別アレルゲン性を測定し,アレルギー発症との関係について動物実験により比較検討を行った。抗原として低温殺菌牛乳(63℃30分),超高温殺菌牛乳(130℃2秒)および煮沸乳(100℃20分)を用い,マウス,ラットの腹腔内に注射し感作させた。アレルギー反応の確認はマウス血清IgE抗体値の測定と,ラット平滑筋のSchultz-Dale反応による抗原体反応によって確認した。その結果,低温殺菌乳に比べ超高温殺菌乳のマウス血清IgE抗体含有率の方が有意に高いことが分かった(P<0.05)。超高温殺菌乳と煮沸乳のIgE平均含有率の間には有意差は認められなかったが,高温で加熱時間の長いほどIgE値の高くなる傾向がみられた。一方,ラットによるSchultz-Dale反応でも低温殺菌乳では平滑筋の収縮は見られなかったが,超高温殺菌乳と煮沸乳では1分以内に著しい筋肉の収縮が認められた。これらのことより低温殺菌乳は,超高温殺菌乳に比較してアレルゲン性が弱く,加熱温度の高くなるほどアレルゲン量が増加し,アレルギー発症の原因になりやすいのではないかと考えられる。
1 0 0 0 OA 佐伯 胖
1 0 0 0 アメリカ映画とカラーライン(2)異人種間ロマンス
- 著者
- 金澤 智
- 出版者
- 高崎商科大学メディアセンター
- 雑誌
- 高崎商科大学紀要 (ISSN:1347703X)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.145-158, 2008
1 0 0 0 映画を利用した音読指導のあり方(選択授業)
最近のパソコンでは,DVDの映画を英語字幕を出しながら容易に視聴でき,また,映像に合わせてその字幕を読みながら音声を録音することができるようになった。この方法を用いると,英語の音読指導がより効果的にできるのではないかと考えた。本研究の目的は,実際に映画を用いて音読を生徒に試みさせ,初期の音読から終期の音読の変化を生徒の自己評価をもとに検証することであった。授業は,2年の選択授業で実施した。生徒数は,前期34名,後期30名であった。場所はコンピュータ教室。Windows XP搭載のパソコンを使用。使用したソフトは,Windows標準のサウンドレコーダとパソコン附属のDVD再生ソフト。授業回数は14回。映画は『ハリーポター(賢者の石)』を使用。最初の2回で,生徒は,読んでみたいセリフのある場面を8つ選んだ。3回目以降は,1回の授業につき自分で選んだ一つの場面をDVDを観ながら録音を何度も試みた。音声をファイルとしてポートフォリオ化し,いつでも聞き直せるようにした。毎回,表計算ソフトを用いて自己評価に取り組ませ,時系列で評価を見渡せるようにした。最終3回は全員に同じ場面に取組ませ,友人同士協力して行わせた。生徒の自己評価を通して言えることは,初期の音読では,何よりも教科書の学習では経験できない速さに難しさや戸惑いを感じている生徒がほとんどであるどいうことである。しかしながら,それでやる気をなくすことはなく,むしろ生徒意欲の高まりをひしひしと感じることができた。それは,映画の中にある本物の力,自分でやってみたい場面を選べた喜びに起因すると考える。回を重ねるに従って,スピードや英語らしい音に慣れてくると同時に,より上手になりたいという思いも強く感じることもできた。最終段階では,「どうやって本物に近いものになるか」「今は少しだけはっきりと,英語らしい発音で話せるような気がする」「他の場面でのセリフの成果もあった」など自己学習の成果がはっきりと見て取れた。
- 著者
- 工藤 瑞香 大塚 裕子 打浪(古賀) 文子
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. NLC, 言語理解とコミュニケーション (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.268, pp.41-46, 2012-10-20
本研究は,知的障がい者と健常者のコミュニケーションが成立するような環境づくりのために必要な情報支援の在り方に関する知見を得ることを目的とする.そこで,知的障がい者のコミュニケーションに関する2つの基礎的な分析を行なった.1つは,知的障がい者と健常者が実際に接触する場面のやりとりに関する談話分析で,もう1つは知的障がい者向けの新聞を対象とした「わかりやすい」文章構造や言語表現の分析と考察である.
1 0 0 0 量子効果を導入したナノワイヤー熱電変換素子の開発と評価
移動度の変化をホール係数測定により実験的に評価するために、集束イオンビーム加工を利用したホール測定用電極の作製を行った。サンプルの直径が非常に細い点とビスマスが大気中で酸化しやすいという点から、ナノワイヤー側面に局所的な電極を取り付ける事は非常に多くの困難を要する。そのため、ビスマスナノワイヤーにおけるホール測定の結果は、これまで報告されていなかった。そこで、本研究では研磨と集束イオンビーム加工を利用して、石英ガラス製の鋳型中に配置されたビスマスナノワイヤーに対してナノスケールのホール測定用の局所電極を作製した。このように作製した直径700nmのビスマスナノワイヤーを利用してホール係数の測定に成功し、キャリア移動度の評価を行った。ナノワイヤーにおけるホール係数の測定は世界で4例目、ビスマスナノワイヤーに関しては初めての結果となった。また、直径160nmのビスマスナノワイヤーのゼーベック係数の温度依存性を測定したところ、これまでの直径200nm以上のサンプルでは現れなかったゼーベック係数の上昇が観察された。これまでの研究では、ワイヤー直径を小さくすることによりキャリアの平均自由行程が制限され、キャリア移動度が減少するために、ゼーベック係数は徐々に低下する傾向があった。しかし、直径160nmのビスマスナノワイヤーの測定結果は、予想される温度依存性よりも上昇し、50K程度で極値を持つような温度依存性が得られた。理論計算によると直径200nm以下ではバンド構造が変化することにより、ゼーベック係数が変化すると予想されている。このようにビスマスナノワイヤーにおけるゼーベック係数の上昇を世界で初めて観測した。
1 0 0 0 日本と中国におけるりんご産業の棲み分け戦略に関する基礎的調査研究
この研究は日本と中国におけるりんご産業の棲み分け戦略に関する基礎的調査(2年間)プロジェクトであるが、初年度は主に中国のりんご産地を調査したのに対して、次年度は大連と青島の両都市でりんごの消費状況について視察した。それとは別に青森産りんごの中国での販売状況を把握するために2007年1-2月に青島でアンケート調査を実施した。これは地元の業者・片山りんご園の協力をえて百貨店マイカル青島で同社のりんごを購入した顧客を対象に行ったものである。また中国のりんご生産と消費事情に関する情報交換を目的に初年度に中国のりんご産業に詳しい地元関係者を呼んでシンポジュウム、次年度に中国陜西省果業管理局、中国西北農林科学技術大学との共催で日中りんご技術フォーラムを開催した。日本と中国のりんご産業の現状と課題を品種開発、栽培、貯蔵、加工、流通、政策など様々な視点から比較し、交流を図った。また青森県のりんご関係者(生産者、商人、行政担当者)を呼んで計3回りんごトークを実施し、青森りんご産業が直面している課題を討議した。研究チームは以上の活動を通してそれぞれの専門領域から与えられた研究課題について分析し、その成果を研究報告書にまとめられているが、研究代表者はそれを踏まえて青森りんご産業が輸出産業として位置付ける必要性を提言し、そして輸出産業として成功するために知的財産権を活用したブランド化戦略の追求が急務であることを指摘した。
1 0 0 0 現代日本における葬送儀礼の実践にみる死への態度-自然葬を中心に-
本年度は、主な調査対象であるNPO法人「葬送の自由をすすめる会」において、初めての会長交替による変化が著しく現れた年であった。その変化を捉えるために、既存のメンバーと新しく加わったメンバーとを分けて、インタビュー調査、各種集まりでの参与観察を行った。新しい会長は、今年61才で、70~80代が中心メンバーになっていた会の中では若い世代に属する。また、いわゆるポスト団塊世代であり、これまでの戦争体験者、団塊世代の会員たちとは異なる方向性を持っているようである。既存の会の方向性が、画一的な葬法や家制度、葬式仏教への反発と脱却だったとしたら、新会長が掲げる方針は、より合理主義に基づいている。このような方針に対して既存のメンバーたちが見せる反応や対応を調べると同時に、新しい方針に賛同して集まってくるメンバーたちに対してインタビューおよび、ライフヒストリー調査を行った。既存の世代の特徴が、①遺骨を「撒く」ことにこだわること、②国家・家・仏教といった既存の葬送を大きく形づける社会関係の拒否、③「個」の追求にあるとしたら、現段階で考えられる新しい世代の特徴は、①遺骨を「撒く」ことにこだわらないこと、②当たり前となった「個」である。彼らは、国家、家制度、仏教などが目に見える形で社会全般を支配していた頃とは違い、「個」という考え方が前提となっている時代に生まれ育った。従って既存の世代のように、ある意味、過激な形でそれまでの社会関係を否定する必要はなく、遺骨を「撒く」ことにこだわらないのではないか、という暫定的な結論が導出された。