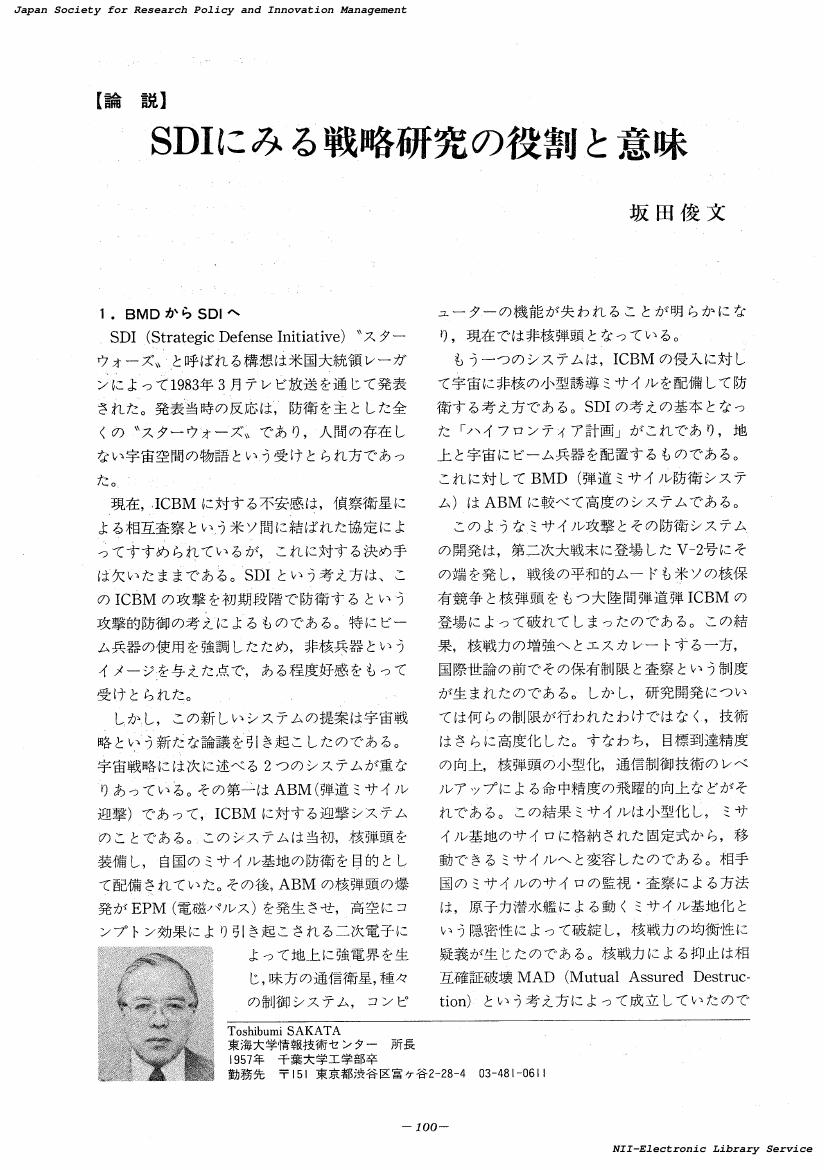2 0 0 0 OA Counter-texts, Commentaries, and Adaptations
- 著者
- Eckart FRAHM
- 出版者
- The Society for Near Eastern Studies in Japan
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.3-33, 2010-03-31 (Released:2013-05-09)
- 参考文献数
- 93
- 被引用文献数
- 2 5
Enūma eliš, the Babylonian epic of creation, was the most influential Mesopotamian religious text of the first millennium BCE. This article discusses how the epic was read, re-interpreted, and revised during the period from 900 BCE to AD 500, both within and outside Mesopotamia. The Assyrian version of the epic, and various Assyrian commentaries on the text, receive particular attention. The article argues that the Erra epic and parts of the Primeval History of the Bible represent counter-texts written in response to the ideological challenges posed by Enūma eliš, and that war and peace were factors that determined to a significant extent how the Babylonians and other people of the ancient world approached the epic.
2 0 0 0 OA 安全対策の費用対効果 一企業の安全対策費の現状とその効果の分析一
- 著者
- 中央労働災害防止協会調査研究部
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.155-158, 2003-06-15 (Released:2017-01-31)
企業の経営環境の激変により,経営のスリム化が指向されており,より効果の高い対策を重点的に実施していこうとする傾向が顕著となりつつある。そのため安全対策費についても,その投入効果を把握するための評価の方法について関心が持たれている.そこで,事業場に対してアンケート調査を行い,その結果をもとに,事業場レベルの安全に係る費用対効果にっいて,推計を試みることとした.
- 著者
- 髙石 吉將 荒井 篤 岡田 真幸 藤原 大悟 鵜山 淳 近藤 威
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.179-183, 2019 (Released:2019-09-10)
- 参考文献数
- 16
Various complications are found in ventriculo-peritoneal shunts (V-P shunts) used in hydrocephalus. Overdrainage can be the source of some of these complications and is the primary cause of orthostatic headache, nausea, and vomiting. Here, we report a case of overshunting-associated myelopathy with progressive tetraparesis. A 56 year-old female had undergone placement of a V-P shunt four years prior to presentation in our clinic. She presented with progressive spastic tetraparesis and dysarthria but had no headache. In a brain magnetic resonance image (MRI), enlargement of the bilateral subdural space was noted. Gadolinium enhanced MRI showed dural enhancement. The presence of intracranial hypotension was suspected. Engorgement of the epidural vein at the C2 level in the cervical epidural space was also observed in the gadolinium enhanced cervical MRI. Since overdrainage of the V-P shunt was obviously present, a programmable valve was placed, and the flow of cerebrospinal fluid was controlled. The symptoms improved, and the epidural enhanced lesion diminished in subsequent MRIs. Here, we report a case of overshunting-associated myelopathy after placement of a V-P shunt and a review of the currently available literature.
2 0 0 0 OA 造山帯の分類とその意義:古造構場復元の束縛条件 ―「丸山ほか:太平洋型造山帯 ―新しい概念の提唱と地球史における時空分布―」論文(地学雑誌, 120巻, 115-223)の追記―
- 著者
- 丸山 茂徳
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.6, pp.1090-1106, 2012-12-25 (Released:2013-01-07)
- 参考文献数
- 52
The geotectonic division of the Japanese islands has been proposed by Isozaki and Maruyama (1991) such that the eastern extension of the Dabie-Sulu 240-220 Ma collisional UHP-HP belt (DSB) passes through the Korean peninsula to Japan. The corresponding belt in Japan is the Higo-Unazuki-Hitachi-Takanuki belt (HUHTB), because the protoliths are a unique A-type (platform sediments) and the metamorphic facies series belongs to the intermediate-pressure type, in addition to 240-220 Ma of metamorphic ages. Ishiwatari and Tsujimori (2012) claim that Maruyama et al. (2011) did not evaluate a new proposal by Ishiwatri and Tsujimori (2003), who proposed that the DSB extends not to the HUHTB but to the Sangun belt in a complex manner because of the promontory nature of the continental margin. This is a Q-A report requested by Ishiwatari and Tsujimori (2012). In this paper the author first introduces a classification of orogenic belts based on protoliths and its great significance for understanding the history of complex orogenic belts, following the original article by Maruyama et al. (1996), in addition to current topics on the role of tectonic erosion. Preceding the final formation of the collisional orogen, the Pacific-type orogen must have been present structurally above the collisional orogen against the hanging wall of the continent or arc. If not, it suggests the presence of tectonic erosion. Moreover, the size of any of regional metamorphic belt, arc, and TTG belt could be an excellent indicator of the scale of tectonic erosion. The Triassic DSB continues not to Sangun belt, but to the HUHTB, for four reasons: first, the protolith of those belts, second; the nature of regional metamorphism along intermediate-pressure type; third, structural units above and below the HUHTB; and finally, paleogeographic reconstruction of the Triassic North and South China cratons. The tectonic juxtapositions of the four so-called Sangun BS belts —450 Ma, 340 Ma, 250-210 Ma, and 170-180 Ma— against the HUHTB in a narrow zone as klippes can best be interpreted by extensive tectonic erosion.
2 0 0 0 OA 光の三原色: RGBを基準にした実用的なカラー変換式
- 著者
- 飯塚 昌之 中嶋 芳雄
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.6, pp.372-379, 2000-06-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 26
2 0 0 0 OA 急性低音障害型感音難聴難治例に対する漢方薬の効果
- 著者
- 真鍋 恭弘 徳永 貴広
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳科学会
- 雑誌
- Otology Japan (ISSN:09172025)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.139-143, 2018 (Released:2019-03-07)
- 参考文献数
- 17
急性低音障害型感音難聴(以下、ALHL)は、比較的予後良好な疾患ではあるが、各種薬物治療に反応しない難治例が1割から2割程度存在すると考えられる。難治例の治療は、薬剤の選択や治療継続の判断が難しく、医師が治療を途中で断念したり、患者が高次医療機関への紹介を希望する場合も多い。したがって、ALHLの臨床上の課題の一つは難治例に対する治療であると考えられる。今回、我々はALHLの難治例に対し、人参養栄湯と五苓散をそれぞれ単独で投与し、その効果を検討した。その結果、人参養栄湯は五苓散よりも、ALHL難治例に対し、有意に効果を発揮した。そのことから、ALHLの発症に漢方医学で言われるところの「虚」の存在が示唆され、人参養栄湯が効果を発揮した可能性が考えられた。また、人参養栄湯の循環改善作用が蝸牛血管条に作用し、効果を発現した可能性についても考察した。
2 0 0 0 OA 地域特性と移住支援施策からみた地方移住の要因に関する研究 愛媛県の全20市町を対象に
- 著者
- 高村 友美 宋 俊煥 岡松 道雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.806-813, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
本研究は、愛媛県の全20市町を対象とし地域特性と移住支援施策を整理するとともに、近年の20市町の移住率との関係を明らかにすることで、地方移住への要因と課題を提示することを目的としている。まず、20市町における地域特性と移住率との相関関係(重回帰分析等)を分析した結果、少子高齢化の進行した地域かつ、医療・福祉の支援が受けやすい地域、第一次産業や公務といった第三次産業以外の産業が盛んな地域ほど移住率が高いことが明らかとなった。次に20市町の移住支援施策を指標化し、数量化Ⅲ類分析より4つの特性軸(I.第一次産業就業者の獲得性、II.定住促進性、III.情報の発信性、IV.地場産業促進性)を明らかにした。また、類型化を行い、各市町の地域特性と合わせた4グループの特性(GA:情報発信積極型【都市型】/GB:地場産業促進・第一次産業関連移住者獲得型【準農村型】/GC:若年層等移住者獲得中心型【農村型】/GD:大都市部移住者等定住促進型【準都市型】)を明らかにした。最後に各グループの高移住率の4事例を取り上げ、共通点として①農村的特性がみられる地域であることや②地域固有の特性を活かした施策が多く実施されていることを指摘している。
2 0 0 0 OA COVID-19と凝固検査
- 著者
- 朝倉 英策
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.604-618, 2020 (Released:2020-12-14)
- 参考文献数
- 87
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 麻黄附子細辛湯の腹腔滲出マクロファージ細胞内Caイオンに及ぼす影響
- 著者
- 溝口 靖紘 市川 裕三
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.133-136, 1991-01-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 総武鉄道高架延長線計画の沿革に関する研究
- 著者
- 小野田 滋
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.17-24, 2001-09-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 49
本論文は、わが国最初の高架鉄道として1904 (明治37) 年に開業した総武鉄道 (現・JR総武線) 両国-錦糸町間を対象とし、その計画から実現に至る経緯を鉄道会議議事録や市区改正委員会議事録、許認可関係文書など、主として当時の公文書に基づいて明らかにした。その結果、総武鉄道には資金難のために地平線へ変更する代替案があり、地域住民は交通渋滞の原因になるとしてこれに反対していたことなどが明らかになった。また、この事業に対して鉄道会議や東京市区改正委員会がどのように関与していたかが把握され、高架鉄道の実現が一鉄道企業の論理ではなく、地方行政や地域住民の合意を経ながら計画的に実施されていた経緯を示すことができた。
- 著者
- 内山 秀彦 鈴鹿 輝昭 永澤 巧
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.47-53, 2019-06-25 (Released:2020-06-25)
- 参考文献数
- 21
人と猫とのより良い関係を探るため,人の性格特性や動物に対する心的な態度が,人と猫双方の行動と生理学的反応に及ぼす影響について検討した。人と猫がふれ合う状況を設定し,このとき人および猫の行動分析とともに心拍変動解析による自律神経活動の測定,また同時に近赤外線分光法(NIRS)によって対象者の前頭前野活動を同時に測定した。その結果,人の性格(神経症傾向・開放性・調和性)や愛着度は猫に対する態度や行動に影響を及ぼし,人の気質的特徴における猫との相性の存在が示された。さらに,人は猫とふれ合うことで交感神経活性による適度に覚醒,前頭前野の賦活化による認知機能向上の可能性が示され,このことは猫とのふれ合いから得られる人の心身の健康効果の機序の一端を説明するものと考えられる。
2 0 0 0 外用コルチコステロイドの経皮吸収による全身的影響について
- 著者
- 山田 和宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.11, pp.1079, 1972 (Released:2014-08-26)
著者は,4種の外用コルチコステロイド剤(0.25%17-α-desoxymethasone,0.2%~0.025% fluocinolone acetonide,0.12% betamethasone 17-valerate,0.02% flumethasone pivalate)を用いて,正常皮膚2例と病的皮膚(尋常性乾癬)10例における全身的影響の有無を下垂体副腎皮質機能と電解質(尿中または血中)の面より検索した.その結果(i)大量の外用コルチコステロイド剤を病的皮膚に,全身の単純塗布で用いた場合とODT療法で用いた場合の両方に,明らかな下垂体副腎皮質系の抑制(循環好酸球数並びに血中コルチコステロイド値の減少,尿中17-OHCS値の低下)がみられ,全身的影響が惹起されることを認めた.その抑制は,処置を中止すると,2~3日で元の値に復帰する事から,一時的である事も判明した.(ii)さらに正常皮膚における検索でも,大量のコルチコステロイド剤をODT療法で用いると,病的皮膚におけると同様に,下垂体副腎皮質系への抑制傾向がみられ,全身的影響出現の可能性を認めた.
2 0 0 0 OA 通勤距離の変動からみた京阪神大都市圏における構造変容
- 著者
- 石川 雄一
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.355-369, 1990-08-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 4
2 0 0 0 OA 地方都市の郊外住宅団地における空き家の発生 —呉市昭和地区の事例—
- 著者
- 由井 義通 杉谷 真理子 久保 倫子
- 出版者
- 日本都市地理学会
- 雑誌
- 都市地理学 (ISSN:18809499)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.69-77, 2013 (Released:2020-09-09)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,郊外住宅団地における空き家の実態と空き家発生に伴う地域的課題を把握し,空き家の有効利用などによる地域活性化策を立案する基礎的資料を得ることである.大都市圏郊外地域では短期間に大量の住宅が供給され,入居者の年齢階層に著しい偏りがみられた.しかし,開発から30 ~40 年を経過した住宅団地では,世帯主夫婦は高齢化し,彼らの子どもたちが独立したことにより高齢者夫婦のみと高齢の単独世帯が卓越した地域へと変容している.そのため,郊外住宅団地ではスーパーマーケットの閉鎖や学校の閉校などがみられるようになり,衰退地域となっているところもみられる.地方都市の郊外住宅団地のなかでも公共交通機関や生活利便施設が十分ではない地域では,中古住宅として売りに出されたとしても購入者がなかなか見つからないため,長期間にわたって空き家となることが多い.空き家では,庭木の管理が不十分なために隣接世帯への迷惑となったり,不法侵入者による放火などの危険性もある.また,空き家住宅が増加するとコミュニティ維持の担い手が失われ,地域の衰退に直結するため,自治体では空き家住宅への入居促進に取り組まざるを得なくなっている.
2 0 0 0 OA 柳宗悦の足跡と産地の地図化
- 著者
- 小畠 邦江
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.230-247, 2001-06-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 122
By paying attention to the hitherto neglected "Map of Japanese Folk Crafts (Folding Screens)" ("Nihon Mingei Chizu Byobu"), the purpose of this paper is to consider the process of YANAGI Muneyoshi's discovery of the local handicrafts that resulted in making the Map on folding screens and writing the book "Handicrafts in Japan."The huge Folding Screen Map, which contains detailed information about 541 places of folk craft products, was completed and first exhibited in 1941. After being shown at the World Exhibition in Osaka in 1970, the Map has been on permanent exhibition at the Japan Folk Crafts Museum in Osaka. It was specially exhibited at the Japan Folk Crafts Museum in Tokyo in the jubilee years of 1989 (the first year of Heisei) and 2000. The Map is seen as the symbol of the Japanese Folk Craft Movement.For forty years, from his early twenties until five years before his death, YANAGI (1889-1961) traveled constantly throughout Japan, conducting research and collecting artistic items. "A Note on Folk Crafts in Prefectures in Japan" ("Nihon Shokoku Mingei Kenbetsu Oboegaki") has recently been found among the Yanagi materials at the Japan Folk Crafts Museum. It is argued that this comprises the basic data that were used in making the large Map. This Note is a valuable source that bridges YANAGI's original research and the resulting map and book. The Map also includes additional information supplied by YANAGI's friend JUGAKU Bunsho (1900-92), and SERIZAWA Keisuke (1895-1984), who painted the screens. A notable feature of SERIZAWA's map is that it is designed diagrammatically (like a railway map) so as to show the relative distance and position of the various places.With the development of mass production and extensive transportation networks, folk crafts were fast losing their idiosyncratic qualities. In response, the Folk Craft Movement searched for utility articles peculiar to individual localities that still survived. These local products were collected and exhibited in urban areas. The Folk Craft Movement made it a principle to avoid wordy explanations about the objects on display. Instead, maps were used as an effective way of supplying information. In folk craft exhibitions, the artisan's name is rarely supplied, and only the product place names are given. We can see here an emphasis on the importance of place with regard to Japanese folk crafts.Throughout the world during the first half of the last century, there was a tendency to extrapolate national characteristics from local arts, and YANAGI in Japan was no exception. In his "Map of Japanese Folk Crafts (Folding Screens)" and in "Handicrafts of Japan, " we can regard his gaze on various regions all over Japan as based on the geographical imagination.
2 0 0 0 OA 食品とジアセチル
- 著者
- 井上 喬
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.5, pp.315-323, 2004-05-15 (Released:2011-09-20)
- 被引用文献数
- 2
古くからジアセチルは発酵飲食品の品質を左右する重要な香気成分である。筆者は長年発酵飲食品中で最も弁別閾値の低いビール中でのジアセチル生成メカニズムとその制御について研究されてきた。ここでは全般的なジアセチル問題と新しい技術を駆使した制御問題を取り上げて貰った。
2 0 0 0 OA 韓国における海藻養殖の現状
- 著者
- 高 楠表
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.565-571, 1997-12-20 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA SDIにみる戦略研究の役割と意味
- 著者
- 坂田 俊文
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.100-107, 1986 (Released:2017-07-07)
2 0 0 0 OA MRI動画撮像により観測した日本語音節連鎖における調音結合(<特集>音声生理研究の方法)
- 著者
- 朱 春躍 波多野 博顕
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.45-56, 2010-08-30 (Released:2017-08-31)
This study employs MRI motion imaging to investigate vowel-consonant coarticulation during utterances with /t//c//d//z//k/, and /g/ in the Japanese syllabary. Image analyses were conducted for the variation in horizontal and vertical tongue position. Results show the followings. 1) Variation in tongue position and shape was larger for consonants than for vowels. 2) Articulatory positions for consonants varied depending on concentration of consonants at specific regions. 3) So-called velar consonants /k/ and /g/ in Japanese were realized as post-palatal consonants. 4) Tongue positions for vowels were higher after velar consonants, while they were lower after alveolar consonants. 5) Japanese five vowels were observed in two groups, anterior-mid (/i//e//u/) and posterior-low (/a//o/), with /u/ as a non-back vowel and /a/ as a back vowel.
2 0 0 0 OA 進化する科学館 ~日本科学未来館の挑戦~
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.1, 2021 (Released:2022-02-07)
Science Windowは、科学技術の魅力を紹介する電子雑誌です。大人も子どもも楽しんでいただけます。より良い未来社会の実現を目指して、科学技術と社会の関係について語り合えるきっかけを提供していきます。 今回の特集は[進化する科学館~日本科学未来館の挑戦~」です。 特集 科学博物館の歴史 科学博物館とは何か?その歴史と未来《科学史研究者・有賀暢迪さんインタビュー》 対話から共創へ、ともにつくる未来社会への案内人「科学コミュニケーター」 研究者・来館者が共創する展示:「ビジョナリーラボ」が目指すもの 未来館にある「研究室」:世界でも先駆的な取り組み 少し先の未来、みんなで考える《日本科学未来館 浅川智恵子館長インタビュー》