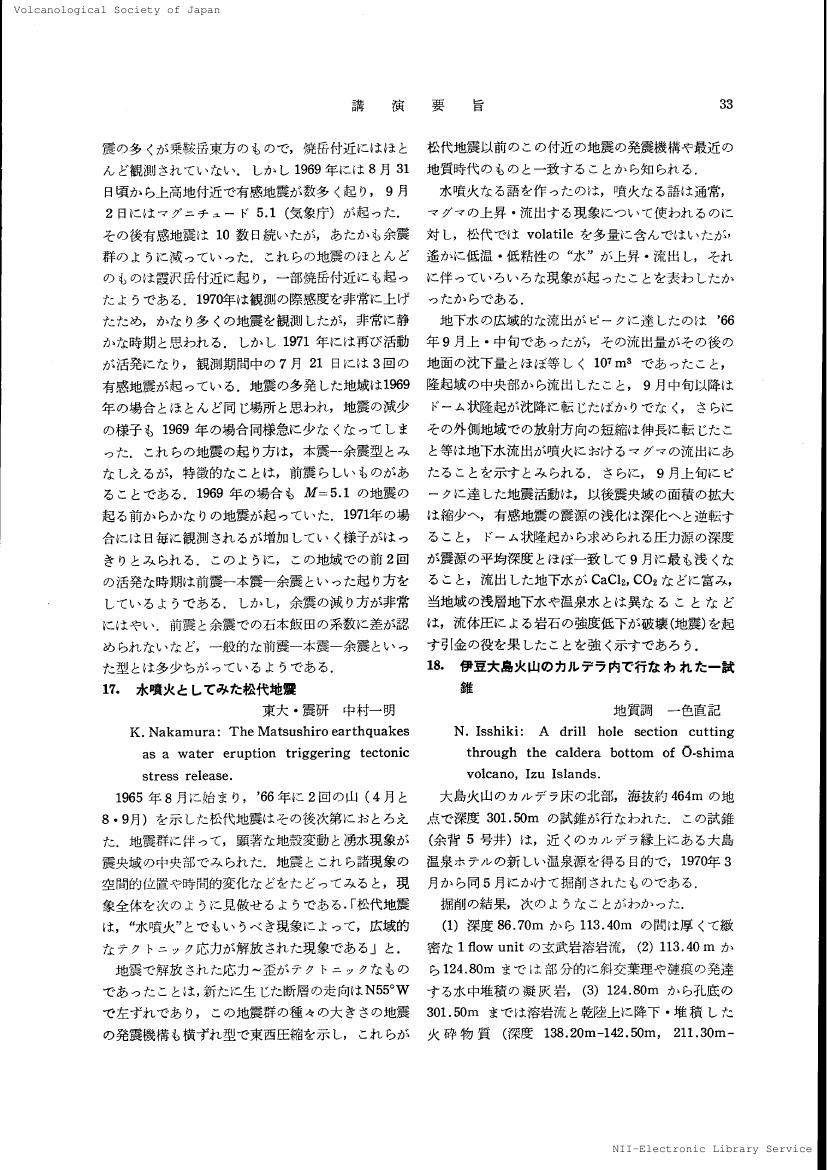2 0 0 0 OA 17. 水噴火としてみた松代地震(日本火山学会 1971 年度秋季大会講演要旨)
- 著者
- 中村 一明
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山.第2集 (ISSN:24330590)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.33, 1972-06-01 (Released:2018-01-15)
2 0 0 0 OA 絵画鑑賞における認知的制約とその緩和
- 著者
- 田中 吉史 松本 彩季
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.130-151, 2013-03-01 (Released:2014-11-20)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
It is known that naïve viewers have “reality constraints” in art appreciation, namely strong tendency to insist on identifying depicted object and its realistic expression in the artwork. Relaxing the reality constraints might help the naïve viewer to appreciate artworks in more creative way. In this paper we investigated whether reading com-mentary on artwork helps appreciation and what kind of commentary is more effective. Fifty college students without particular art education participated in an experiment. The participants were assigned to one of four conditions. The experiment consisted of two phases: preliminary appreciation phase and main appreciation phase. In the pre-liminary appreciation phase, three groups of participants were presented paintings by Renoir, Matisse and Klee, and made free descriptions on their thoughts on each paint-ing. Along with each of painting, a commentary on objects depicted in the painting was provided to participants in object commentary condition, a commentary on formal and technical aspects of the painting was provided to formal commentary condition, and no commentary was provided no commentary condition. No preliminary appreciation condition skipped the preliminary appreciation phase. After the preliminary apprecia-tion phase, all the participants were presented two paintings by Gogh and Kandinsky without any commentary and made free description. Analysis of free description in main appreciation phase showed that (1) reading commentary activated verbalization during the appreciation, (2) the participants generally focused on what was depicted in the painting, (3) reading commentary on technical aspects was more effective for relaxing reality constraints and deepening the experience of paintings.
2 0 0 0 OA 公務員制度改革と成績主義
- 著者
- 野見山 宏
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.38, pp.179-197, 2003-05-15 (Released:2012-09-24)
- 著者
- 小埜 栄一郎 村田 純 堀川 学
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.715-720, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 25
ゴマ(シソ目ゴマ科ゴマ属 Sesamum spp.)は種子にフェニルプロパノイドの二量体のリグナンと呼ばれる植物特化代謝物を蓄積している。セサミンに代表されるリグナンは多様な生物活性を有しているものの、同じフェニルプロパノイドから生合成されるフラボノイド類に比べると医薬や食品分野では認知度は低い。それらの多岐に渡る薬理活性については優れた先行文献に譲り、本稿ではリグナン代謝物の多様性がどのようにして生じているか、つまり特化代謝の進化をゴマの栽培種と野生種の酵素活性の比較を通じて論じたい。
2 0 0 0 ムラサキ科植物におけるシコニン生合成研究の新潮流
- 著者
- 矢﨑 一史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.705-709, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 19
脂溶性のナフトキノン系赤色色素であるシコニンは、ムラサキ科の6属内の限られた種だけが生産する化合物である。その化学構造は比較的単純であるが、特殊な化学特性を持つため、供給はもっぱら天然資源に依存している。その代表が絶滅危惧植物に指定されている薬用草本のムラサキで、新たな薬理活性が次々と報告される一方、供給には潜在リスクがある。今、世界的に新たな潮流を生み出しているこのシコニンをめぐる研究を紹介する。
2 0 0 0 OA 心房細動の薬物によるレートコントロール療法
- 著者
- 池田 隆徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.221-227, 2018-11-02 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 17
- 著者
- 大渕 憲一
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.166, 2008-11-30 (Released:2017-02-10)
2 0 0 0 OA アイシュタイン・ポドルスキー・ローゼンの相関と相対性理論 量子論における分離不可能性
- 著者
- 田中 裕
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.177-183, 1990-03-25 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 14
1982年のアスペによるベルの定理の実験的検証は, 遅延モードを採用する事によって量子力学的相関が光速度以下の因果作用によって引き起こされたものでない事を示す点で画期的なものであったが(1), この検証実験に対するベル自身のコメント (1986) は「何かがベールの陰で光速度以上の速さで伝達されている」こと, 即ち遠隔作用の実在性と「相対性理論をアインシュタイン以前の問題状況に戻す必要性」即ち「ローレンツ不変性を持つ現象の背後にローレンツ不変性を持たない深層レベルがあり, このレベルでは絶対的な同時性と絶対的な因果の順序があると想定する」ことによって量子論的遠距離相関 (EPR相関) を説明する可能性に言及している(2)。またエーベルハード (1989) のEPR問題の歴史的回顧と様々な解釈の包括的要約も, 冒頭に「光速度を越える遠隔作用は (アインシュタインにとって受入れがたい観念であったが) 今日では様々な実験結果と理論的な分析によって実在的な効果である可能性が強い」という視点を提示し, この遠隔作用が, いかなる意味で「実在的」であるかをめぐる様々な解釈の違いを分析している。量子力学を「観測者に言及せずに」実在論的に解釈するポパー (1982) は, 「遠隔作用があるならば何か絶対空間のようなものがある」ことを理由に「量子論に絶対的同時性を導入すべき理論的理由があるとするならば, 我々はローレンツの解釈に戻らなければないだろう」と言っている。
2 0 0 0 OA 造影CTでの遅延造影像が診断の契機となった心臓限局性サルコイドーシスの一例
- 著者
- 石丸 伸司 山口 隆義 川崎 まり子 柿木 梨沙 管家 鉄平 五十嵐 正 岡林 宏明 古谷 純吾 華岡 慶一
- 出版者
- 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会
- 雑誌
- 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会雑誌 (ISSN:18831273)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1_2, pp.41-44, 2018-10-25 (Released:2019-04-02)
- 参考文献数
- 15
2016年に公開された心臓サルコイドーシスの診断指針では,造影MRIによる心筋の遅延造影所見(Late Gadolinium Enhancement:LGE)が主徴候の一つとして挙げられているが,CT画像での異常所見については触れられていない.今回,我々はCTでの心筋遅延造影(Late Iodine Enhancement:LIE)が診断の契機となった心臓限局性サルコイドーシスの一例を経験した.本症例では,心臓CTでのLIEは心臓MRIでのLGEの部位と一致しており,また18F-FDG-PETでも同部に強い集積を認めた.サルコイドーシスの心病変診断において,CTはMRIと同等の診断能を持つ可能性があると考え報告する.
2 0 0 0 OA 植物増生病を引き起こすタフリナ属菌のインドール酢酸生合成
- 著者
- 山田 哲治 塚本 浩史 白石 友紀 野村 哲也 奥 八郎
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.532-540, 1990-10-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 17 22
サクラてんぐ巣病菌(Taphrina wiesneri),モモ縮葉病菌(Taphrina deformans),スモモふくろみ病菌(Taphrina pruni)など,植物に増生病を引き起こすタフリナ属病原糸状菌はインドールピルビン酸(IPyA),インドールアセトアルデヒド(IAAld)を中間代謝物としてトリプトファン(Trp)からインドール酢酸(IAA)を合成する。これらの糸状菌はまた,インドールアセトニトリル(IAN)をIAAに転換する能力をもつ。IANをIAAに転換する酵素,IANニトリレースは基質誘導を受ける適応酵素であるが,TrpをIPyAに転換する酵素,Trpアミノトランスフェラーゼは基質によって誘導を受けない。
2 0 0 0 OA 音楽のフラクタル次元 絵から音楽への変換
- 著者
- 中津山 幹男
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第23回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.431, 2007 (Released:2009-01-14)
絵画から音楽に変換する準客観的な手法として、絵画を適当な区画に別けて平均的なRGBの成分を抽出して、音符を割り当てる。これにより作成された音楽のフラクタル次元が存在し、また和洋の音楽のフラクタル次元と、ほぼ似た値がでることが判明した。
2 0 0 0 OA 細胞の酸化ストレス制御の構造生物学
- 著者
- 和田 啓
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.105-112, 2021-05-31 (Released:2021-06-05)
- 参考文献数
- 31
Oxygen is needed to produce energy for aerobic organism. Oxygen molecule exhibits high reactivity, thereby constantly leading to super-reactive molecules called reaction oxygen species. My research has focused on the system involved in the cellular redox control including the O2-sensing, H2O2-scavenging and protecting the cells, and have revealed their molecular mechanisms by means of the structural, biochemical and spectroscopic analyses.
2 0 0 0 OA 黒斑からみた縄文土器の野焼き方法
- 著者
- 久世 建二 小島 俊彰 北野 博司 小林 正史
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.8, pp.19-49, 1999-10-09 (Released:2009-02-16)
縄文土器の野焼き方法を復元するためには,黒斑などの焼成痕跡が最も重要な材料となる。縄文土器の黒斑は弥生土器に比べ明瞭なパターンを見い出しにくいので,野焼き実験により黒斑の形成過程を明らかにし,実験結果と縄文土器の黒斑を突き合わせる作業を積み重ねることが重要である。本稿では,一連の開放型野焼き実験に基づいて,形成過程の違いにより黒斑を「大きな炎を出す薪からのスス付着による薪接触黒斑(逆U字形と2個1対が典型)」「棒状の薪接触黒斑」「オキ接触黒斑」「残存黒斑」などに類型化した。東日本の縄文時代前・中期の5資料の黒斑を観察した結果,かなり多くの土器においてこれらの類型が適用できたため,黒斑の形成過程から野焼き方法をある程度推定できた。その結果,以下の点が明らかになった。1.大きな炎からのススを起源とする薪接触黒斑が本稿の分析資料の多くでみられたことから,覆い型ではなく開放型で野焼きされたことが再確認された。薪接触黒斑は土器の地面側の内面,地面側の外面,上向き側の外面などに付くことから,横倒しになった土器の下側や側面に多くの薪が置かれていたことが明らかになった。一方,覆い型野焼きでは内部が窯に近い状態になり,大きな炎から出たススによる黒斑は少ない。2.5資料の大半の土器において内面に薪・オキ接触痕がみられることから,内面に薪を入れたことが明らかである。弥生土器では内面に薪を入れないのに対し,縄文土器では内面に入れるのは,開放型の野焼き実験で示されたように,外面の薪だけでは内面まで十分に燃焼ガスが回りにくいためと考えられる。3.本稿では東日本の縄文前・中期の5資料の黒斑を観察したが,上述の共通性と共に,以下の違いもみられた。三内丸山遺跡Vb層の円筒下層b式土器(特に大型)は,薪の上に横倒しに設置し,側面・上面に薪と草燃料をかぶせている点で,野焼き途中で横倒しした可能性が高い他の4資料と異なる。このような方法をとる理由として,(1)土管のような形の円筒下層b式土器は,直立して設置すると口縁部まで十分な炎が当たりにくい,(2)土器の大量生産に伴う薪燃料の節約のため草燃料を併用した,などが考えられる。4.「器面の色調が橙色か白色か」についての資料間の違いは,内外面の黒斑の特徴や内外底面の黒斑の有無と相関を示すことから,焼成雰囲気と共に,加熱の強度の違いを反映する可能性がある。三内丸山遺跡Vb層では,5リットル未満の小型は大半が橙色なのに対し,大型は白色の方がやや多かったが,これは,薪・草燃料を土器に立てかける大型深鉢の野焼き方法の結果かもしれない。【引用文献 】阿部芳郎 1995「弥生前期土器の器体構造について」『津島岡大遺跡5』pp.89-1001995「土器焼きの火・煮炊きの火」『考古学研究』42(3):75-91青森県教育委員会 1979『板留(2)遺跡』1997『三内丸山遺跡VIII』後藤和民 1980『縄文土器を作る』中公新書。北上市教育委員会 1983『滝ノ沢遺跡』小林正史 1993「民族考古学からみた土器の用途推定」『新視点・日本の歴史1』 132-139頁。1993「カリンガ土器の制作技術」『北陸古代土器研究』3号74-103頁。1994「稲作農耕民とトウモロコシ農耕民の煮沸用土器―民族考古学による通文化比較」『北陸古代土器研究』4号 85-110頁。1995「縄文から弥生への煮沸用土器の大きさの変化」『北陸古代土器研究』5号 110-130頁。1998「野焼き方法の変化を生み出した要因―民族誌の野焼き方法の分析―」『民族考古学序説』民族考古学研究会編、pp.139-159、同成社久保田正寿 1989『土器の焼成I』クオリ久世建二・北野博司・金昌郁・藤井一範・姜興錫・南部次郎・小林正史 1994「縄文土器から弥生土器への野焼き技術の変化」『日本考古学協会第60回総会研究発表要旨』26-29頁。久世建二・北野博司・小島俊彰・小林正史 1996「縄文土器の野焼き方法」『日本考古学協会第62回総会研究発表要旨』94-97頁。宮川村教育委員会 1996『堂の前遺跡発掘調査報告書』小笠原雅行 1996「三内丸山遺跡出土土器の数量的研究」『シンポジウム考古学とコンピュータ―三内丸山をコンピュータする―』pp.29-44岡安雅彦 1994「黒斑にみる弥生土器焼成方法の可能性」『三河考古』7号 45-65頁。1996「縄文土器焼成方法復元への実験的試み」『古代学研究』133号 21-31頁。1999「野焼きから覆い焼きへ その技術と東日本への波及」『弥生の技術革新 野焼きから覆い焼きへ』pp.48-63 安城市歴史博物館
- 著者
- Shinsuke Yamashita Shungo Imai Kenji Momo Hitoshi Kashiwagi Yuki Sato Mitsuru Sugawara Yoh Takekuma
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.1151-1155, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
Olanzapine is effective for schizophrenia management; however, it is contraindicated in diabetes patients. In addition, olanzapine is useful for treating nausea and vomiting, such as in the case of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV). Therefore, we hypothesized that the contraindicated prescription of olanzapine likely occurs among cancer patients with diabetes, especially by non-psychiatric physicians. Hence, we conducted a nationwide survey to elucidate the situation of such contraindicated prescriptions and the associated risk factors. We extracted the data of patients who were newly prescribed olanzapine between April 2015 and March 2017 from the health insurance claims database developed by JMDC, Inc., Tokyo. The patients who were prescribed contraindicated olanzapine were defined as those who were prescribed olanzapine after a diagnosis of diabetes and diabetes drug prescription. In all, the data of 7181 patients were analyzed. We evaluated the proportion of diabetes patients who were prescribed contraindicated olanzapine from among those who were prescribed olanzapine. Furthermore, we investigated the background of patients who were prescribed olanzapine for information such as olanzapine prescribers and history of cancer chemotherapy. In all, 100 diabetes patients (1.39%) were prescribed olanzapine. In these patients, the frequency of olanzapine prescription was higher by non-psychiatry/neurology physicians than by psychiatry/neurology physicians (3.25 and 0.85%, respectively). Additionally, all olanzapine prescriptions in cancer chemotherapy-treated diabetes patients were issued by non-psychiatry/neurology physicians. Thus, our study revealed there were diabetes patients who were prescribed olanzapine. Additionally, olanzapine for CINV management was more likely to be a contraindicated prescription.
2 0 0 0 OA 「老人と子供」について
- 著者
- 宮田 登
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.426-429, 1982-03-31 (Released:2018-03-27)
2 0 0 0 OA マルクス主義法理論の批判的再構成
- 著者
- 山口 廸彦
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1972, pp.204-218, 1973-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 53
2 0 0 0 OA CONSTRUCTION OF A HIGH-ACCURACY POINT CLOUD MAP FOR THE AUTOMATIC DRIVING OF AN ELECTRIC WHEELCHAIR
- 著者
- Yuichi Abe Toshiya Hirose
- 出版者
- Shibaura Institute of Technology
- 雑誌
- SEATUC journal of science and engineering (ISSN:24352993)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1-6, 2020 (Released:2020-02-18)
- 参考文献数
- 4
The proportion of elderly people in traffic accidents is increasing in Japan. It is therefore necessary to make transportation for the elderly safer by automating the electric wheelchair. Technologies that estimate the vehicle position and orientation are required to realize automated driving. One technology is simultaneous localization and mapping. This technology computes the current self-position by comparing a map and data from a sensor. The present study used the normal distributions transform algorithm for self-position estimation. The main aim of the study was to construct a three dimensional map required for self-position estimation on a sidewalk. For the evaluation of this map, self-position estimation was performed using the map and estimated distances were compared with actual distances measured, by a laser range finder. Results show a difference between the actual position and estimated position of approximately 0.05 m in the area of a sidewalk. The self position estimation on the sidewalk using the normal distributions transform was thus accurate. Future work will focus on a next-generation map that contains point data for the upper part of a building.
2 0 0 0 OA 7. 地震と地鳴りの解析(日本火山学会 1967 年度春季大会講演要旨)
- 著者
- 関谷 慱
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山.第2集 (ISSN:24330590)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.90, 1967-08-01 (Released:2018-01-15)
- 著者
- Kazumasa Oura Keita Taguchi Mao Yamaguchi Oura Ryo Itabashi Tetsuya Maeda
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.7735-21, (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3
Takayasu's arteritis is an inflammatory disease of unknown etiology that causes stenosis, occlusion, or dilatation of the aorta and its major branches, the pulmonary arteries, and the coronary arteries. The incidence of extracranial carotid artery aneurysm in patients with Takayasu's arteritis is reportedly 1.8%-3.9%. We herein report a patient with Takayasu's arteritis who presented with transient left hemiplegia immediately after neck massage. Carotid ultrasonography revealed a thrombus within the fusiform aneurysm on the right common carotid artery. We speculated that fragmentation from the intra-aneurysmal thrombus was caused by neck massage.
2 0 0 0 OA トンネル覆工コンクリートに生じるひび割れの発生メカニズムに関する実験的研究
- 著者
- 高山 博文 増田 康男 仲山 貴司 植村 義幸 Narentorn YINGYONGRATTANAKUL 朝倉 俊弘
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F (ISSN:18806074)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.132-145, 2010 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 16
NATMで施工された覆工コンクリートでは,トンネル天端付近において軸方向に伸びるひび割れがしばしば確認されている.このひび割れは地圧によるものと類似するため,維持管理段階における健全度評価を困難なものとしている.本研究では,このひび割れの発生メカニズムを明らかにするため,実際の坑内環境と施工条件を模擬した模型試験とそのシミュレーション解析を実施した.この結果,吹付けコンクリート面の凹凸などによる外部拘束がない現在の覆工コンクリートにおいて,ひび割れの発生に寄与すると考えられるコンクリート自身が発生させる内空側と地山側との収縮量の差(内部拘束)を数値解析で適切に表現するためには,「湿気-応力連成解析」を行う必要があることを示した.