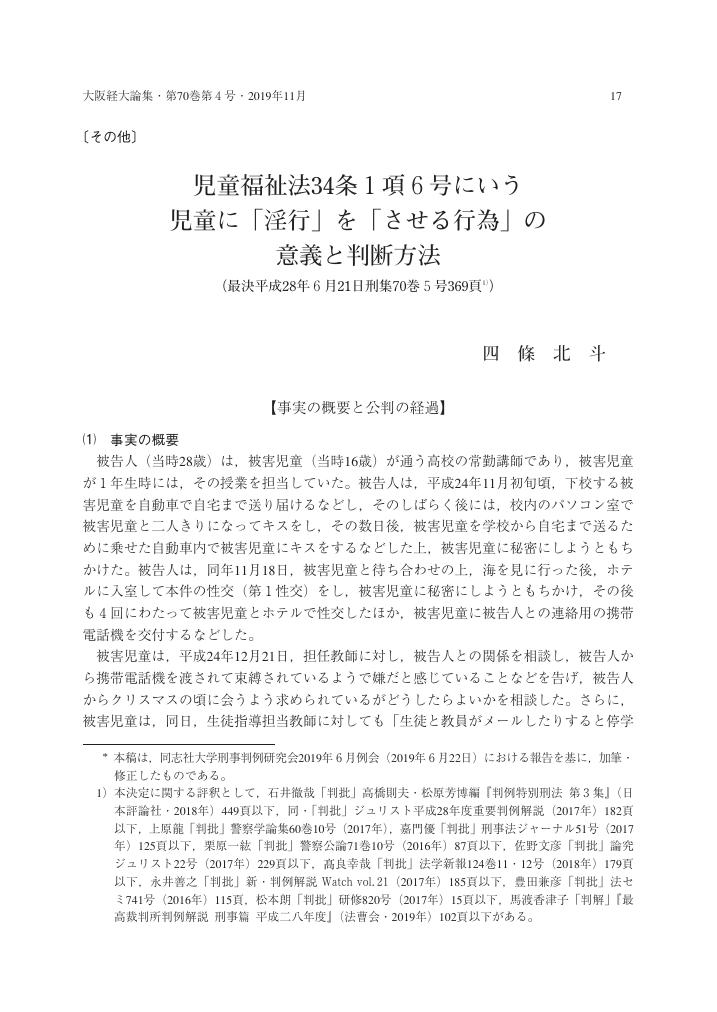2 0 0 0 OA 生物医学画像の自動分類を可能にした能動学習型ソフトウェアCARTA
- 著者
- 松永 幸大 朽名 夏麿 桧垣 匠 馳澤 盛一郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.217-221, 2013-07-01 (Released:2013-07-01)
- 参考文献数
- 2
生物医学画像データを自動分類できる能動学習型ソフトウェアClustering-Aided Rapid Training Agent(CARTA)を開発した。CARTAは,自己組織化マップによる画像のクラスタリングを介して,専門家の意見を繰り返し学習することで,研究や検査目的にあった的確な分類基準を自動的に検討して選択する。判別が難しい2種類のがんについて核磁気共鳴画像法で画像を取得し,CARTAを用いて分類したところ,2種類のがんを由来別に,高精度で分類することができた。CARTAは生物学,医学,数学と情報科学が融合した学際的な次世代ソフトウェアであり,今後,生物医学画像の自動分類や定量解析の有力な支援ツールとなる。
2 0 0 0 OA 先天性難聴児への対応 —本邦での課題克服へ向けて—
2 0 0 0 OA 乳幼児期の聴覚活用と言語習得
- 著者
- 中村 公枝
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.254-262, 2007-07-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 7 3
乳幼児期の聴覚活用と言語習得について以下の観点から考察を加えた. (1) 聴覚・コミュニケーション・言語習得, (2) 聴覚活用と言語習得の関係, (3) 聴覚障害乳幼児の音声言語習得上の課題と対応.聴覚障害児の聴覚活用とは, コミュニケーション場面での意味ある聴覚的経験を通して「能動的な聴くシステム」を形成することである.そのための必要事項として, (1) 前言語的コミュニケーション, (2) 語彙習得, (3) 文法習得, (4) リテラシーと談話理解の4つを取り上げ, そこでの課題と対応を明らかにした.なかでも音声言語習得に必要な情報処理として統語構造処理の重要性について述べた.また最大限の聴覚活用をするために視覚を活用することの意義と重要性についても言及した.
2 0 0 0 OA プラスチックの水平リサイクルとカスケードリサイクルの評価
- 著者
- 藤井 実 中谷 隼 大迫 政浩 森口 祐一
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第20回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.76, 2009 (Released:2009-09-25)
- 被引用文献数
- 1
プラスチックのリサイクル方法はマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、エネルギー回収と多様である。リサイクルによって代替される新規資源を設定して評価する従来のLCAによる評価でも、マテリアルリサイクルとエネルギー回収の差であれば、プラスチックの製造エネルギーを含めて代替されるか否かの差異として評価された。しかし、同じマテリアルリサイクルで、水平リサイクルとカスケードリサイクルを比較する際には、これらの差が結果に反映されない場合が多い。近年、使用済みPETボトルなどの廃プラスチックが海外に輸出され、リサイクルされている。国内のリサイクルは、海外でのリサイクルに比べて質の高いリサイクルを行っている場合があるが、これらの差異は従来のLCAでは十分に評価されていない場合が多い。本研究では、カスケードリサイクルとの相対的な水平リサイクルの効果を過不足なく評価する方法を検討する。
2 0 0 0 OA 日本人の音楽感覚
- 著者
- 小島 美子
- 出版者
- 日本喉頭科学会
- 雑誌
- 喉頭 (ISSN:09156127)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.91-95, 1997-12-01 (Released:2012-09-24)
When we speak of traditional Japanese music, we are refering to a variety of music ···from artistic music to folkloric music. Despite the variety, there are certain characteristics running through them in terms of the Japanese sensibility toward music. It is this musical sense of the Japanese that will provide an important base for the new Japanese music to develop in the future.A sense of rhythm is determined over a long period of certain group's history by the way how they have used their physical body. A majority of the Japanese, for instance, have a “static” sense of rhythm characteristic of the rice paddy farmers. People in the mountains, on the other hand, use their limbs in a flexible way, resulting in a “supple” sense of rhythm. People who live on the islands of Okinawa and Amami, as well as people who live on coastal areas, have a “swinging” sense of rhythm in correspondence to the undulation of ocean waves.A sense of timber is determined over a long period of time by the kind of life style and natural environment people live in. People in Japan have lived mainly by farming and fishing in a climate where the four seasons are distinct. Consequently they developed sharp sensitivity toward changes in weather, making them alert to natural sounds such as a rain and a wind. It is for this reason that the Japanese favor songs and instruments that sound close to natural sounds.Japanese melodies and based on six pentatonic scales. Each consists of two sets of the perfect fourth called the tetrachord. These scales have much in common with the music of Asia and Africa.The Japanese subconsciously feel, though vaguely, the presence of a god or spirit in every object. Such a tendency, or a habit of the mind, is also revealed in music and songs. This attitude, which may correspond to the idea of symbiotism, is demonstrated in the Japanese way of thinking that songs too possess spiritual power.
2 0 0 0 OA 未来の当たり前を作る「スタートアップ」とは
- 著者
- 山下 哲也
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.12, pp.1171-1176, 2017 (Released:2017-12-01)
・僅かなメンバーで起業し、加速するIT進化を駆使して未知の製品やサービスを生み出し、猛烈な速度で成長して世界を変えてゆく企業をスタートアップと呼ぶ。一見あり得ないと思えるアイデアを実現し、未来の当たり前を生み出すイノベーターである彼らについて、そのあらましを紹介する
2 0 0 0 OA 維持血液透析患者の食事・水分管理に関する信念尺度の開発
- 著者
- 南 里佳子 玉浦 有紀 赤松 利恵 藤原 恵子 酒井 雅司 西村 一弘 角田 伸代 酒井 徹
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.5, pp.198-209, 2020-10-01 (Released:2020-11-09)
- 参考文献数
- 25
【目的】維持血液透析患者の食事・水分管理アドヒアランス改善に向けて,関連する信念を評価する尺度を作成し,その信頼性と基準関連妥当性を検討する。【方法】3都市4施設で外来維持血液透析を受療中の患者378人を対象に,質問紙調査を実施し,食事・水分管理の信念に関する40項目と,主観的指標による食事・水分管理アドヒアランス状況をたずねた。同時にカルテから,属性とドライウエイト,透析間体重増加率,生化学検査データを収集した。探索的・確証的因子分析により,信念尺度の因子構造を検討した後,抽出された下位尺度の信頼性(クロンバックα)と基準関連妥当性(客観的/主観的指標によるアドヒアランス状況との関連)を確認した。【結果】尺度作成の結果,食事・水分管理の実施に関する信念として「食事管理の障害」「食事に対する懸念」「環境からの影響」「楽観性」の4下位尺度17項目,動機に関する信念として「重要性」の1下位尺度8項目が得られた。クロンバックαは0.531~0.830と概ね良好な値だった。また,各下位尺度の得点は,客観的または主観的指標によるアドヒアランス状況(良好群・不良群)と妥当な結果がみられ,基準関連妥当性が確認された。【結論】維持血液透析患者の食事・水分管理に関する信念尺度として,実施と動機に関する信念の2つの尺度の信頼性と基準関連妥当性を確認した。
2 0 0 0 OA レイモン・ブードン著 『イデオロギー--受容された諸観念の起源』
- 著者
- 山下 雅之
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.73-78, 1989-09-30 (Released:2017-02-15)
- 著者
- Kosuke Kiyohara Junya Sado Tetsuhisa Kitamura Mamoru Ayusawa Masahiko Nitta Taku Iwami Ken Nakata Yasuto Sato Noriko Kojimahara Naohito Yamaguchi Tomotaka Sobue Yuri Kitamura for the SPIRITS Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-17-1237, (Released:2018-02-15)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 1 19
Background:A better understanding of the epidemiology of pediatric out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) occurring in school settings is important to establish an evidence-based strategy for prevention and better prognosis.Methods and Results:The Stop and Prevent cardIac aRrest, Injury, and Trauma in Schools (SPIRITS) is a nationwide prospective observational study linking databases from 2 nationally representative registries, the Injury and the Accident Mutual Aid Benefit System of The Japan Sport Council and the All-Japan Utstein Registry of the Fire and Disaster Management Agency. Using these databases, we described the detailed characteristics and outcomes of pediatric OHCAs that occurred in school settings in Japan between 2009 and 2014. During the 6-year study period, 295 OHCA cases were confirmed. Overall incidence rate was 0.4 per 100,000 students per year. The majority of OHCA cases had a cardiac origin (71%), occurred during exercise (65%), were witnessed by bystanders (70%), and received bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation (73%). In approximately one-third of cases the student was defibrillated by public-access automated external defibrillator (38%). The proportion of patients with 1-month survival and a favorable neurological outcome was 34% among all OHCAs and 43% among OHCAs of cardiac origin.Conclusions:In Japan, approximately 50 pediatric cases of OHCA consistently occur yearly in school settings. The majority of students received basic life support from bystanders, and patients with OHCA of cardiac origin had a relatively good prognosis.
2 0 0 0 OA 植物のバイオミネラリゼーション-動けない生物の防御戦略
- 著者
- 尾﨑 紀昭 Fabio Nudelman
- 出版者
- 日本結晶成長学会
- 雑誌
- 日本結晶成長学会誌 (ISSN:03856275)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.46-3-04, 2019 (Released:2019-11-13)
- 参考文献数
- 51
With some exceptions, most land plants are static. Being static always involves the risk of being preyed. To counter that, plants have evolved various defence mechanisms against herbivores. These defence mechanisms can be divided into two main strategies. The first is called chemical defence, which involves synthesizing and storing organic compounds such as alkaloids, terpenes, polyphenols, and proteolytic enzymes. These organic compounds act as chemical weapons that are toxic to herbivores, or causes digestion and nutrient blockages. The second mechanism is physical defence, where the cellulose in the cell walls is often reinforced with deposits of inorganic minerals, forming an organic-inorganic hybrid armour. In this paper, we review several reports on plant biomineralization, which is an example of physical defence in plants, and discuss the molecular mechanism and significance of the mineral formation process from a biological point of view.
2 0 0 0 OA 農用運搬車の開発と作業改善
- 著者
- 野沢 正雄
- 出版者
- Japanese Society of Farm Work Research
- 雑誌
- 農作業研究 (ISSN:03891763)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.230-245, 1994 (Released:2010-02-09)
- 著者
- 四條 北斗
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.17-30, 2019 (Released:2019-12-25)
2 0 0 0 OA 「独生独死」観の受容と「翻訳」論的問題―中世の孤独と無常をめぐって― 荒木 浩
- 出版者
- 物語研究会
- 雑誌
- 物語研究 (ISSN:13481622)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.219-228, 2018 (Released:2021-07-01)
2 0 0 0 OA バレーボールのオーバーハンドパスにおける飛距離の違いが上肢および下肢動作に及ぼす影響
- 著者
- 縄田 亮太 石井 泰光 前田 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.111-122, 2013 (Released:2013-06-08)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
The purpose of this study was to identify the effects of different ball distances on the upper and lower limbs for the overhand pass in volleyball. Eleven male college volleyball players participated. The subjects performed the overhand pass toward objects located at three different ball distances (3, 6, and 9 m) on two force platforms, and motion analysis was performed via a motion capture system comprising 12 high-speed video cameras.The following results were obtained: (1) As the ball distance increased, the maximum dorsal flexion angular velocity of the wrist decreased, whereas the length of the pull phase, the vertical peak force on the rear leg, the maximum extension angular velocity of the hip and knee, and the maximum plantar flexion angular velocity of the ankle all increased. Therefore, adjustment of the ball distance for the overhand pass was facilitated by changing the impulse of the ball caused by increasing the intensity of both the rear leg step and the wrist stiffness. (2) In the previous instructional manual, the buffer action for the falling ball during overhand passing was facilitated by flexion of the whole body. However, in this study, the buffer action was facilitated conducted only with the upper limb irrespective of the ball distance. From the viewpoint of the series of movements during overhand passing, the whole body was used in the period from flexion to extension, but the flexion action of the whole body was incorporated into the preparatory phase, and the buffer did not involve the lower limbs after ball contact.This difference between the previous instructional manual and the present findings are attributed to the imprecise definition of movement phases in the manual.
2 0 0 0 OA 樹木根系の斜面崩壊防止機能
- 著者
- 阿部 和時
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 森林科学 (ISSN:09171908)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.23-29, 1998-02-01 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 香坂 玲 内山 愉太
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.2, pp.134-144, 2021-04-01 (Released:2021-06-26)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 5
2019年度に導入された森林環境譲与税(以下,環境譲与税)について,市町村は森林管理に関わり,税の使途も公表しなければならない。一方で市町村では受け皿の人材が不足しており,都道府県の支援が重要となる。本研究では,都道府県レベルにおいて①環境譲与税と府県単位の独自の超過課税(以下,県環境税)の使途の整理状況,②2020年度前後に設置された市町村支援の組織・会議体,③人事交流,④独自のガイドラインに着目して分析を行った。そもそも県環境税は各県に使途や背景に差異があり,全体比較には自ずと限界があるものの,二制度のすみ分けは主に間伐等の物理的な森林整備において府県間で対応が異なること等が特定された。支援では6県が独自にセンターを設置し,10府県が人事交流を実施し,県の普及員と市町村の職員を併任する制度を独自に導入した特徴的な事例(愛媛県)も存在した。17府県が森林経営管理制度または環境譲与税の独自のガイドラインを作成していた。41府県を対象とした定量分析では情報交換の会の設置状況は市町村数や私有林人工林面積率と相関があり,人事交流及びガイドラインの策定状況は譲与額との相関があった。
2 0 0 0 OA 事業用太陽電池発電設備の自然災害での事故事例
- 著者
- 大神 広記
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.408-412, 2019-11-30 (Released:2020-11-30)
- 被引用文献数
- 1
太陽電池発電設備は,耐用年数まで使用され,リユースやリサイクルが行われるものだけでない。近年,自然災害による太陽電池発電設備の損壊事故も多数発生している。自然災害により太陽電池発電設備にどのような事故が起きているのか,電気事業法における事故報告から,紹介する。 2018 年度に起こった,平成 30 年 7 月豪雨,台風 21 号,北海道胆振東部地震,台風 24 号による太陽電池発電所の事故報告は,計 48 件である。平成 30 年 7 月豪雨では,設備の立地地域における浸水や土砂崩れ等によるパネルやパワーコンディショナーの損傷といった被害が多い。台風では強風や高潮によるパネルの飛散や水没が多数発生。北海道胆振東部地震では,地震による地面の隆起,地割れ,液状化等に伴う架台,パネルの損傷や,パワーコンディショナーの短絡,地絡による運転機能喪失が発生した。
2 0 0 0 OA 就職活動時の自己分析・企業分析とキャリアに対する態度が就職先への満足度に与える影響の調査
- 著者
- 高橋B. 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.2, pp.59-63, 2021-07-03 (Released:2021-07-05)
大学でのキャリア教育において自己分析と業界・企業分析を深めさせることは新卒の離職率を抑える上で重要である.一方で,キャリアに対する前向きな態度も離職率を抑える上で寄与すると考えられる.本稿ではそれらが就職後の就職先への満足度にどの程度相関があるかの調査を行った.調査の結果,自己分析や業界・企業分析やキャリアに対する前向きな態度と就職先への満足度に相関が認められた.一方で,キャリアに対する前向きな態度があっても,自己分析や業界・企業分析ほど満足度には結び付かないことも分かった.また,そもそもキャリアに対して前向きな態度を持つものほど自己分析と業界・企業分析をしていることが明らかになった.
2 0 0 0 OA 2014年度 検索技術者検定 2級試験問題 公開用解答
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.11, pp.483-488, 2015-11-01 (Released:2017-04-13)
2 0 0 0 OA 数種の薬物の活性炭への吸着
- 著者
- 有森 和彦 宮崎 万理 若山 香都美 弟子丸 恵実 中野 眞汎
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療薬学会
- 雑誌
- 病院薬学 (ISSN:03899098)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.6, pp.380-384, 1990-12-20 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 13