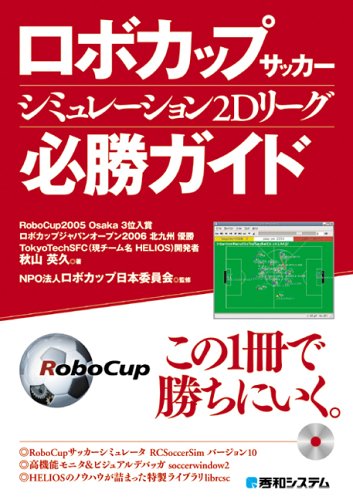- 著者
- 川手 圭一
- 出版者
- 東京学芸大学
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. II (ISSN:18804322)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.73-83, 2009-01
- 著者
- 林 成忠 木村 喜保 呉 啓変 米良 豊常 西原 達次 野口 俊英 木下 四郎 加藤 一男
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF PERIODONTOLOGY
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.919-935, 1983
- 被引用文献数
- 7 1
アパタイト (Hydroxyapatite Ceramic) を歯周治療に応用する可能性を調べるために, 外科的に形成したサルの3壁性歯槽骨欠損に, 粒子 (1) 600μ以上 (2) 100-400μ (3) 10μ3種類の大きさのアパタイトをそれぞれ移植し, 臨床的ならびに組織学的に観察した。その結果, (1) 臨床的には, 異常な炎症は認められなかった。また, 規格X線写真によると, アパタイトは殆ど骨欠損にとどまっており, 排出される徴候が認められなかった。(2) 組織学的には, 粒子600μ以上および粒子100-400μのアパタイトを移植した部位では, 一部アパタイトは直接に新生骨に接している像が観察された。これはアパタイトの骨親和性が高い事を証明している。以上より, アパタイトは歯槽骨欠損部の人工移植材として, 使用しうる材料であると思われる。
- 著者
- 山西 博之 廣森 友人
- 出版者
- 全国英語教育学会
- 雑誌
- ARELE : annual review of English language education in Japan (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.263-272, 2008-03
This paper reports the current attempt to develop English language proficiency benchmarks (Can-Do lists) suitable for students at Ehime University. A survey was conducted in order to create the educational and achievement goals for the university's General English Education courses and the standards for assessing the level of achievement of those goals. This paper focuses especially on the benchmark of the writing course and describes the concrete procedure by which it was established. If we set appropriate achievement goals and assessment standards we can decide on assessment standards and methods that conform to them. Once such standards and methods have been decided, we can use them as the basis for developing more effective teaching methods. Thus, this paper will be a beneficial source of information for both language educators and curriculum designers who intend to create more appropriate educational and achievement goals for their students and improve methods of teaching and evaluation suitable for them.
1 0 0 0 福島原発--「平和利用」の恐るべき陥穽(調査レポ-ト)
- 著者
- 吉原 公一郎
- 出版者
- 現代評論社
- 雑誌
- 現代の眼 (ISSN:0435219X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.6, pp.p184-193, 1975-06
1 0 0 0 緊急インタビュー/草野孝楢葉町長の"本音"に迫る
- 著者
- 岸谷 孝一 椎葉 大和
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. 構造系
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.57-58, 1975-08-25
1 0 0 0 OA 「奥行き」における「同時性」 : メルロ=ポンティの時間論の展開
- 著者
- 川瀬 智之
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美學 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.43-56, 2007-06-30
Merleau-Ponty, dans la Phenomenologie de la perception (1945), dit que, dans 1'experience de la profondeur, deux vues incompatibles de la meme chose, par exem-ple la vue frontale et la vue laterale, coexistent simultanement. Et il identifie la dis-tance entre le percevant et la chose percue avec la profondeur. Et dans ≪L'Oeil et 1'e-sprit≫(1961), il dit que, dans la peinture par Rembrandt, par la coexistence simultanee des vues incompossibles, le spectateur reconnait la profondeur de l'espace. Mais, en meme temps, il dit que la distance est, ainsi que la hauteur et la largeur, l'abstraction sur la profondeur. Que signifie cette difference des deux propositions sur le rapportde la distance et de la profondeur? Dans Le visible et l'invisible, ecrit de 1959 a 1961,il s'agit de la profondeur de la chair a laquelle appartient communement et le voyant etle visible. Ici, la profondeur n'est pas la distance entre le voyant et la chose percue, mais elle inclut le voyant meme. Cette transformation de la notion de la profondeurdesigne le detachement de la pensee de Merleau-Ponty de la philosophic de la conscience sur laquelle celle-ci s'etait fondee dans sa premiere periode.
1 0 0 0 高性能非球面偏光ルーペの自作実験
- 著者
- 小林 寛 福澤 輝雄
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.44-47, 1996-11-15
1 0 0 0 OA タッチスクリーンを用いた指タッチ操作による視覚障害者向け 文書情報読み上け.システム
1 0 0 0 OA 継時的比較の個人差──継時的比較志向性尺度の作成と検討──
- 著者
- 並川 努
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.6, pp.593-601, 2011 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 3
This study developed the Temporal Comparison Orientation Scale and investigated its reliability and validity. Study 1 (N=481) examined the factor structure and correlations with other related scales (self-consciousness scale; revaluation tendency scale; self-esteem scale; depression scale; social comparison orientation scale). The results suggested that the Temporal Comparison Orientation Scale had good reliability and validity. Study 2 examined the relationship between temporal comparison orientation and affect generated by temporal comparisons. The results showed that individuals high in temporal comparison orientation experienced more negative affect after upward and downward comparisons than individuals low in temporal comparison orientation. The possible uses and limitations of the scale were discussed.
1 0 0 0 OA 詩文法帖 : 墨妙真蹟
1 0 0 0 1P1-A06 月面レゴリス層掘削ロボットの推進手法
- 著者
- 渡邊 恵佑 下田 真吾 久保田 孝 中谷 一郎
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, pp.38-39, 2002
- 被引用文献数
- 1
今後の月探査ミッションでは, サンプル採取や観測機器の設置のために, 月面のレゴリス層を数mの深さにわたって掘削することが要求されている。これには, 全身が埋没してレゴリス中を掘削しながら推進し, かつ探査ローバに搭載可能なサイズの, モグラ型ロボットが適していると考える。このようなロボットを実現するためには, 「レゴリス中に空間を確保する」と「その空間の中を前進する」の, 2つのプロセスが必要となる。ここでは, 両者を一体として推進する手法を提案し, これを用いた簡易実験の結果を報告する。
- 著者
- Hideo TAKEUCHI
- 出版者
- (社)日本分析化学会
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.11, pp.1077-1077, 2011-11-10 (Released:2011-11-10)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 14 55
UV Raman spectroscopy is a powerful tool for investigating the structures and interactions of the aromatic side chains of Phe, Tyr, Trp, and His in proteins. This is because Raman bands of aromatic ring vibrations are selectively enhanced with UV excitation, and intensities and wavenumbers of Raman bands sensitively reflect structures and interactions. Interpretation of protein Raman spectra is greatly assisted by using empirical correlations between spectra and structure. Many Raman bands of aromatic side chains have been proposed to be useful as markers of structures and interactions on the basis of empirical correlations. This article reviews the usefulness and limitations of the Raman markers for protonation/deprotonation, conformation, metal coordination, environmental polarity, hydrogen bonding, hydrophobic interaction, and cation-π interaction of the aromatic side chains. The utility of Raman markers is demonstrated through an application to the structural analysis of a membrane-bound proton channel protein.
- 著者
- 豊國 伸哉
- 出版者
- 日本環境変異原学会
- 雑誌
- 日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集
- 巻号頁・発行日
- no.38, 2009-11-06
1 0 0 0 時間のつる草
- 著者
- 上岡玲子 廣瀬通孝 梅田晶子 田中尚文
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告エンタテインメントコンピューティング(EC) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.39, pp.19-22, 2006-05-03
- 被引用文献数
- 6
「時間のつる草」は、日々収集される様々なライフログ(生活や仕事の中のあらゆる情報)を有効に活用するための新しい可視化インタフェースである。このインタフェースでは、時間概念を従来の軸としてとらえるのではなく、「らせん」として捉えなおすことで、大量のライフログから事柄の周期性を発見し、過去の自らの行動の再認識とともに、新たな発見を即すエンターテイメント性のあるインタフェースの実現を目的とした。本論では、時間のつる草のコンセプト、試作システムおよび展示デモについての報告と今後の展望について議論する。The Vines of Time is a new interface developed for visualizing life log, which is a various kind of information collected under the daily life. The feature of this interface is that we don't treat a concept of time as a linear structure but treat it as a spiral one. Therefore the periodicity of the event out of a large amount of life log becomes possible. This makes possible to reconfirm self behavior as well as induce a new discovery by manipulating the interactive interface. This paper discusses the concept of the vines of time interface, the system outline of a prototype system and reports the demonstration and closes future work.
1 0 0 0 ロボカップサッカーシミュレーション2Dリーグ必勝ガイド
- 著者
- 秋山英久著 : ロボカップ日本委員会監修
- 出版者
- 秀和システム
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 OA 標準と正義
- 著者
- 中山 竜一
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.101-118, 1995-03
- 著者
- 佐々井 啓
- 出版者
- 社団法人日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, 2007-09-15
- 著者
- 横山 修一郎
- 出版者
- 国立音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:02885492)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.97-107, 2006
ダンテ・アリギエーリ作『神曲』の「天国」第3歌結末部において、ベアトリーチェは登場人物ダンテに対して強い輝きを放つ。すると登場人物ダンテは沈黙する。つづく第4歌冒頭部においては、2つの疑問の狭間でどちらを先に話すべきかわからずに沈黙する登場人物ダンテが描かれる。理由の異なる2つの沈黙がつづけて描かれることに違和感を覚えたことが本稿の執筆動機である。本稿では、まずベアトリーチェの強い輝きの意味を探る。第3歌結末部のベアトリーチェの強い輝きは、ベアトリーチェが見るための照明のような役割を果たしている。このことを踏まえて2つの沈黙の関係を整理する。その上で、「天国」第4歌においてベアトリーチェが述べることを確認し、「天国」第3歌結末部から第4歌冒頭部への話の展開が、作者ダンテのどのような意図により構成されているかを明らかにする。