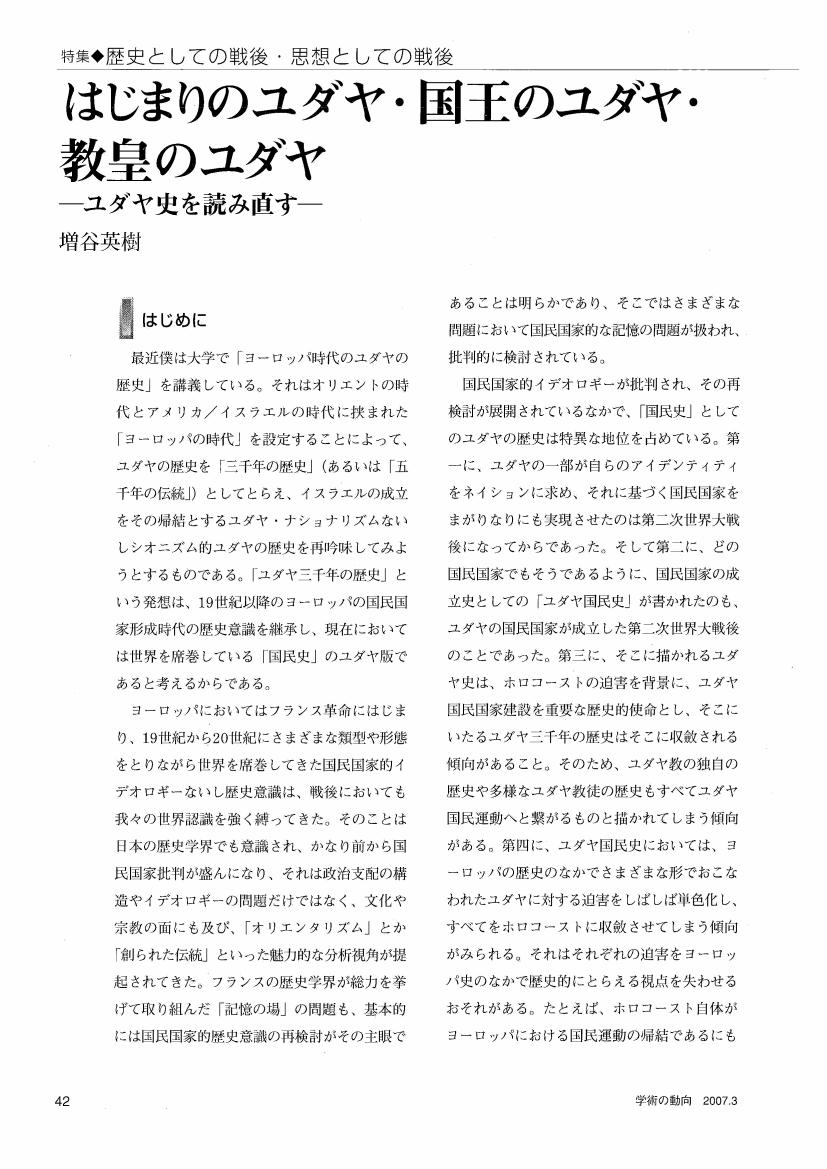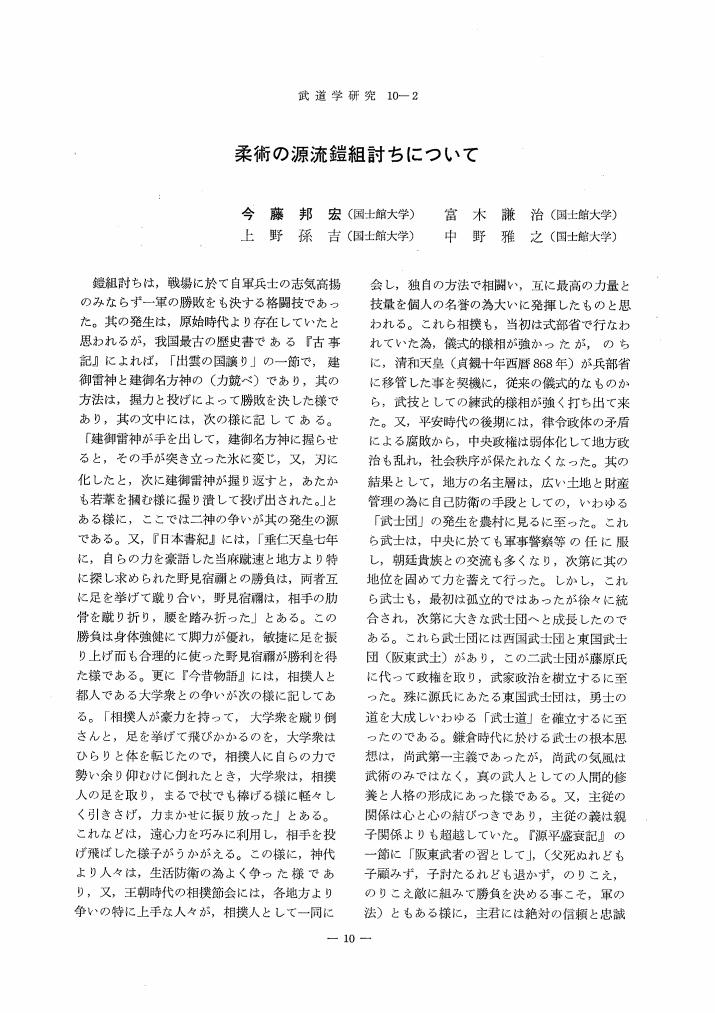2 0 0 0 OA 機能的電気刺激を用いた脳可塑性を生かすニューロリハビリテーション
- 著者
- 原 行弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.452-458, 2016-06-18 (Released:2016-07-21)
- 参考文献数
- 10
導出した筋活動電位に比例して電気刺激が行われる随意運動介助型機能的電気刺激(integrated volitional control electrical stimulator,以下IVES)は,容易な装着・操作に加えて筋肉スイッチといえる自律型制御を採用している.筋活動電位測定と電気刺激を同一筋肉で行える特徴があり,従来不可能であった可動域にまで関節機能を拡大できる.近赤外光脳機能測定装置を用いた検討では,IVES使用によって対側大脳感覚運動野の脳血流増加を認め,体性感覚入力増加と麻痺手の随意的運動促通の両方が相乗効果をもって,脳神経機構の再構築に寄与すると思われる.IVESのパワーアシストモード,外部入力モードは,脳卒中などで崩れた大脳半球間バランスを是正する作用があり,有用なニューロリハビリテーションの手段といえる.
2 0 0 0 OA はじまりのユダヤ・国王のユダヤ・教皇のユダヤ ユダヤ史を読み直す
- 著者
- 増谷 英樹
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.42-52, 2007-03-01 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 本條 晴一郎
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングレビュー (ISSN:24350443)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.31-39, 2020-03-04 (Released:2020-03-04)
- 参考文献数
- 24
先進的なニーズを認識し,ニーズの解決による便益を期待するリードユーザーは,製品の開発や普及,顧客開発など,様々な観点から注目を集めている。一方でリードユーザーについての定量的な研究は,特定の製品領域で行われてきた。本研究では,サーベイの枠組みで定量的な実証研究を行うことで,リードユーザーの一般的な特徴を見出すことを目指した。その結果,リードユーザーネスが製品領域に限定されずに消費者イノベーションの発生に帰結すること,幅広い他者に対して情報を探索するネットワーキング行動が先進性に正の,高便益期待に負の影響を与える先行要因となっていることが示された。製品領域に限定されない結果を得たこと,および,先行要因を行動レベルで捉えたことにより,リードユーザーに対する理解が,注目に見合うものに近づいたといえる。
2 0 0 0 OA ギリシャのブドウとワインについて
- 著者
- 濃辺 正平
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.12, pp.861-869, 1987-12-15 (Released:2011-11-04)
ギリシャにおけるワイン釀造は, ブドウとワインの神“ディオニソス (バッカス)”に守られて, 有史以前から現代にかけて営々と続いている。しかしながら, その現状については今までほとんど日本に紹介されていないだけに, 本稿はきわめて貴重な資料といえよう。
2 0 0 0 OA ショウガの成分がラットのエネルギー代謝に及ぼす効果
- 著者
- 石見 百江 寺田 澄玲 砂原 緑 下岡 里英 嶋津 孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.159-165, 2003-06-10 (Released:2009-12-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 7 9
高糖質食ならびに高脂肪食 (ラード食) にショウガ粉末あるいはショウガの有効成分であるジンゲロンおよびジンゲロール (ジンゲロンの還元型) を添加し, エネルギー消費に及ぼす影響を酸素消費量と呼吸商の面から検討した。添加前と比べた12時間の累積酸素消費量はショウガの2%添加によって高糖質食群で7%と有意に増加し, ラード食群でも増加傾向 (6%) を示した。その際, 呼吸商 (RQ) はショウガの添加によって高糖質食ならびにラード食群でともに有意に低下した。比較のために唐辛子を2%添加して調べたところ, ショウガ添加とほぼ同程度の酸素消費量の増加とRQの低下を認めた。ショウガの辛味成分であるジンゲロンの効果を調べると, 0.4%の添加によって, 高糖質食群では微増にすぎなかったが, ラード食群で著しく増加した。RQはジンゲロンの添加によって両食餌群ともに低下した。一方, 辛味のないジンゲロールを0.4%添加した場合には, 酸素消費量ならびにRQ値に有意な変化がみられなかった。しかし, ジンゲロンとジンゲロールを同時に添加すると, 酸素消費量は高糖質食群で34%, ラード食群で28%と有意に増加し, 両成分の相乗効果が観察された。RQも有意な低下をみた。以上の実験結果から, ショウガあるいはその辛味成分であるジンゲロンは酸素消費量を増加させ, かつ体内の脂肪の燃焼を盛んにすることによってエネルギーの消費を促進する作用を持つことが明らかになった。
- 著者
- Kenichi Kurosaki Masataka Kitano Heima Sakaguchi Isao Shiraishi Naoko Iwanaga Jun Yoshimatsu Takaya Hoashi Hajime Ichikawa Satoshi Yasuda
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.12, pp.2275-2285, 2020-11-25 (Released:2020-11-25)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3
Background:Congenital heart disease (CHD) is often diagnosed prenatally using fetal echocardiography, but few studies have evaluated the accuracy of these fetal cardiac diagnoses in detail. We investigated the discrepancy between pre- and postnatal diagnoses of CHD and the impact of discrepant diagnoses.Methods and Results:This retrospective study at a tertiary institution included data from the medical records of 207 neonates with prenatally diagnosed CHD admitted to the cardiac neonatal intensive care unit between January 2011 and December 2016. Pre- and postnatal diagnoses of CHD differed in 12% of neonates. Coarctation of the aorta and ventricular septal defects were the most frequent causes of discrepant diagnosis. Unexpected treatments were added to 38% of discrepant diagnostic cases. However, discrepant diagnoses did not adversely affect the clinical course. The 9% of the 207 neonates who required invasive intervention within 24 h of delivery were accurately diagnosed prenatally.Conclusions:Pre- and postnatal diagnoses differed in only a few neonates, with differences not adversely affecting the clinical course. Neonates who required invasive intervention immediately after delivery were accurately diagnosed prenatally. Prenatal diagnosis thus seems to contribute to improved prognosis in neonates with CHD.
- 著者
- 齊藤 有里加 下田 彰子 梶並 純一郎 小川 義和
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.493-496, 2020 (Released:2020-11-27)
- 参考文献数
- 3
理系学芸員課程の授業教材として,モバイル端末アプリケーションiNaturalistを使った体験を実施した.演習は国立科学博物館付属自然教育園で行われ,動植物の管理,保存,活用についてレクチャーと,植生管理のための生物モニタリングの試みとしてiNaturalistのシステムを紹介し,「バイオブリッツ」を体験し,ディスカッションとアンケートを行った.本発表では,大学生がiNaturalistを操作し,博物館資料として野外生物情報を習得し,公開するまでの過程を紹介し,野外博物館の資料特性理解の効果について考察する。
2 0 0 0 OA 統計的リテラシーにおける批判的思考態度の構造とスキルの関係
- 著者
- 古賀 竣也
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- pp.43086, (Released:2020-06-01)
- 参考文献数
- 30
研究の目的は,統計的リテラシーにおける批判的思考態度の構造を明らかにすること,および統計的リテラシーのスキルに関係する批判的思考スキルは何かを明らかにすることである.まず,質問紙調査を実施し,「数値やデータへの関心」,「懐疑的・複眼的な見方」,「他者との関わり」の3因子から構成される態度に関する尺度を開発した.次に,統計的リテラシーのスキルを測定するテストと,複数の批判的思考スキルを測定するテスト,作成した尺度を含めた質問紙調査を実施し,これらの相関を検討した.その結果,統計的リテラシーの得点と全ての批判的思考スキルの得点に正の相関がみられた.また,統計的リテラシーの得点と尺度の得点には有意な相関がみられなかったことから,統計的リテラシーにおける批判的思考態度を有していても,統計情報を適切に解釈できるとは限らないことが考察された.
2 0 0 0 OA 柔術の源流鎧組討ちについて
2 0 0 0 OA 日本におけるハタ科魚類キテンハタEpinephelus bleekeriの記録と分布状況
- 著者
- 藤原 恭司 高山 真由美 桜井 雄 本村 浩之
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.40-46, 2015-08-31 (Released:2018-03-30)
- 被引用文献数
- 2
The Duskytail Grouper, Epinephelus bleekeri (Perciformes: Serranidae), is recorded from Tanega-shima and Amami-oshima islands and the Yaeyama Islands in the Ryukyu Islands, southern Japan on the basis of six specimens (232.6-581.2 mm standard length). In addition, several records of E. bleekeri by photographs and/or observations from Kanagawa, Kochi, Ehime, Miyazaki, and Kagoshima prefectures are confirmed. Because E. bleekeri has previously been recorded from Taiwan and southward, the present specimens represent the first reliable records of the species from Japanese waters on the basis of collected specimens. Distributional implications of E. bleekeri in Japanese waters are discussed.
2 0 0 0 OA 第一類医薬品を購入した顧客の薬剤師サービスに対する意識調査
- 著者
- 長田 孝司 鈴木 弘誉 山田 重行 山村 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.400-407, 2010 (Released:2015-05-30)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
【目的】平成21 (2009) 年6月1日より改正薬事法が施行され, 薬剤師は第1類医薬品を購入する顧客に対して安全かつ適正な使用ができるよう情報提供を行うことが義務付けられた. 第1類医薬品に関する適切な情報を提供するために顧客の健康ニーズをアンケート調査した. 【方法】愛知県, 岐阜県, 三重県のドラッグスギヤマにおいて第1類医薬品を購入した顧客を対象とし, 薬剤師が購入した第1類医薬品に関する情報提供を行った後, アンケート用紙を配布した. 記入したアンケート用紙は, 郵便にて直接, 当研究室で回収した. 【結果】第1類医薬品の顧客のうち66.4%が購入を繰り返し, 77.6%が「満足」と回答した. また, 90%以上の顧客は, 購入時の薬剤師の説明について「分かりやすい」と感じているが, 64.2%の顧客が薬剤師の説明がないと買えないのは不便と思っていることも明らかとなった. そして, 今回アンケートに回答した顧客の6.0%に一般用医薬品使用後に調子が悪くなった経験があった. 【結論】添付文書を読まない顧客に対する薬剤師の説明や相談を丁寧でわかりやすいものにすることで, 第1類医薬品購入時の利便性意識を向上し, 安全で有効なセルフメディケーションの推進を加速すると考えられた.
2 0 0 0 OA コンテナ配置の最適化による荷役方式の比較
- 著者
- 西村 悦子 今井 昭夫
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.I_659-I_667, 2013 (Released:2014-12-15)
- 参考文献数
- 14
本研究では,国内外の大規模コンテナターミナルで使用される荷役方式に着目し,そこで主として使用される荷役機器とターミナルレイアウトの特徴がコンテナの配置計画にどのような違いをもたらすかを検証する.具体的には荷役機器の違いは,コンテナヤードの保管エリアにあるコンテナブロック間に設けられた通路のどこを搬送車両が走行するかで移動に要する時間が異なること,さらに荷役機器の大きさや機動性に伴ってターミナル全体の保管容量が異なることがある.そこで評価指標には,総サービス時間とスペース占有率を用いた.計算結果より,港の混み具合や係留パターンに関わらず,タイヤ型門型クレーンで評価が高かったが,そのうち半数のケースでレール式門型クレーンと同等の評価を得ることが分かった.
2 0 0 0 OA 脳脊髄液減少症の診断と治療
- 著者
- 橋本 洋一郎
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.51-55, 2020 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 10
脳脊髄液減少症の診断の第一歩は,病歴の詳細な聴取である.特に片頭痛,緊張型頭痛,薬物乱用頭痛をベースに脳脊髄液減少症を発症してきた場合には,複数の頭痛について根気強く病歴を聞いて,解きほぐして,ベースにある頭痛とともに新たに発症した脳脊髄液減少症(通常,鎮痛薬が効かない慢性連日性頭痛,起立性頭痛)を病歴で疑う必要がある.起立性頭痛を呈する体位性頻脈症候群の鑑別でも病歴は重要である.脳脊髄液減少症の発症初期は安静だが,体位性頻脈症候群では可能な限り安静を避けるようにするといった対応が必要であり,2つの疾患の鑑別は重要である.脳脊髄液減少症の経過中に体位性頻脈症候群に変わってくる症例への対応も重要である.
2 0 0 0 OA ミカンコミバエ種群の再侵入と今後の侵入害虫対策の方向性
- 著者
- 藤崎 憲治
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.8, pp.8_40-8_47, 2016-08-01 (Released:2016-12-02)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 心不全治療の新たな展開
- 著者
- 筒井 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.6, pp.1115-1122, 2018-06-10 (Released:2019-06-10)
- 参考文献数
- 11
心不全に対する薬物治療は,利尿薬や強心薬による治療から神経体液性因子を抑制する治療へと,そのパラダイムが大きくシフトした.現在,アンジオテンシン変換酵素(angiotensin-converting enzyme:ACE)阻害薬,アンジオテンシンII受容体拮抗薬(angiotensin II receptor blocker:ARB),ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(mineralocorticoid receptor antagonist:MRA)等レニン・アンジオテンシン・アルドステロン(renin-angiotensin-aldosterone:RAA)系抑制薬及びβ遮断薬が心不全の標準治療薬として位置付けられている.欧米を含め,世界各国では,既にアンジオテンシン受容体―ネプリライシン阻害薬(angiotensin receptor neprilysin inhibitor:ARNI)サクビトリル/バルサルタン(LCZ696)とIfチャネル阻害薬イバブラジンも使用されている.また,糖尿病治療薬であるナトリウム・グルコース共輸送体(sodium glucose cotransporter:SGLT)2阻害薬のエンパグリフロジンとカナグリフロジンが心血管イベント,特に心血管死や心不全による入院を減少させることが明らかとなり,心不全を対象とした大規模臨床試験が我が国も含め進行中である.
2 0 0 0 OA Forensic Examination of Soil Evidence
- 著者
- Yoshiteru Marumo
- 出版者
- Japanese Association of Forensic Science and Technology
- 雑誌
- 日本鑑識科学技術学会誌 (ISSN:13428713)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.95-111, 2003 (Released:2009-04-11)
- 参考文献数
- 115
- 被引用文献数
- 6 11
Soil can provide important information to criminal investigations as transfer evidence because many criminal cases take place under circumstances such that soil transfers to a criminal or victim. The variation in soils from place to place makes soil valuable evidence to prove linkage between a suspect and a crime scene. Soil is a complex mixture with a variety of mineralogical, chemical, biological, and physical properties. Considering such complexity, a variety of methods have been developed for forensic science purposes. Because minerals are an important component of soils, mineralogical examination is essential in forensic soil identification. Additionally, many other methods can be applied to raise the discriminating power, but not all kind of methods need to be used. What is important is that examiners select an appropriate combination of methods by considering the context of the soil samples. This report summarizes a wide range of reports on the analysis of soil components and of closely related materials such as plant fragments, pollen and spores, and diatoms, with emphasis on the importance of screening tests consisting of several simple techniques. The soil formation process involves parent materials, temperature, water condition, vegetation, time, and the chemical processes of solution, oxidation, reduction, and even human activities. The history of a soil's development as the results of such complex soil formation process is strongly reflected in soil color. The systematic observation of multiple soil colors is especially useful for screening.
2 0 0 0 はやぶさ2の化学推進系の開発と往路運用
- 著者
- 森 治 櫛木 賢一 成尾 芳博 澤井 秀次郎 志田 真樹 丸 祐介 道上 啓亮 中塚 潤一 高見 剛史 浦町 光
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 航空宇宙技術 (ISSN:18840477)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.29-35, 2019 (Released:2019-02-01)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
The chemical propulsion system of Hayabusa-2 consists of 12 bipropellant thrusters whose thrust is 20N. The communication with Hayabusa was lost due to the fuel leakage just after touchdown in 2005. Akatsuki failed to enter orbit around Venus in 2010. The chemical propulsion system of Hayabusa-2 took measure to prevent these accidents. It satisfied the requirements of continuous injection for SCI (Small Carry-on Impactor) operation. The short injection impulse was estimated using flight data. It was changed by the thruster temperature and the frequency of use. The approximation of the long injection impulse was improved using TCM (Trajectory Correction Maneuver) data and VIC (Velocity Increment Cut) test data. This paper presents development and outward operation of the chemical propulsion system of Hayabusa-2.
2 0 0 0 OA 酸化ストレスに対して神経細胞保護作用を有する化合物の作用機序の解明
- 著者
- 原 宏和
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.8, pp.1199-1205, 2007-08-01 (Released:2007-08-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4 4
NF-E2-related factor-2 (Nrf2), a basic leucine zipper transcription factor, is involved in the expression of numerous detoxifying and antioxidant genes via the antioxidant response element (ARE). Keap1, a cytoplasmic protein, sequesters Nrf2 in the cytoplasm under normal conditions. Various stimuli, including electrophiles and oxidative stress, liberate Nrf2 from Keap1, allowing Nrf2 to translocate into the nucleus and to bind to the ARE. Recently, there is increasing evidence that compounds that stimulate the activation of the Nrf2-ARE pathway may become useful therapeutic drugs for neurodegenerative diseases associated with oxidative stress. Apomorphine (Apo), a dopamine D1/D2 receptor agonist, is used for clinical therapy of Parkinson's disease. On the other hand, Apo is a potent radical scavenger and has protective effects on oxidative stress-induced cell death. We previously reported that pretreatment of human neuroblastoma SH-SY5Y cells with Apo enhanced the protective effects. In addition, we have recently demonstrated that Apo stimulates the translocation of Nrf2 into the nucleus and the transactivation of the ARE. Our findings suggest that not only the function as a radical scavenger, but also the function as an Nrf2-ARE pathway activator may be involved in the neuroprotective effects of Apo on oxidative stress-induced neuronal cell death. In this review, our recent studies on the mechanism underlying Apo-induced neuroprotection are summarized.
2 0 0 0 OA 「フリーター」のタイプと出身階層
- 著者
- 小林 大祐
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.287-302, 2011 (Released:2012-09-01)
- 参考文献数
- 28
フリーターと社会階層との関連を指摘する研究は数多いが,量的な研究においてはその関連性についての知見は必ずしも一致していない.この理由のひとつとして,フリーターには幾つかのタイプがあり,そのタイプごとに出身階層に幅があるという可能性を考えることができる.もしそうであれば,なんらかの基準でフリーターを分類することで,フリーターのサブ・カテゴリーと出身階層の関連がより明確になるかもしれない.そこで,フリーターをしている「理由」に着目し、3分類したフリーターに対して出身階層が効果を持っているのかを検討した。その結果,本人の教育達成をコントロールしても「やむを得ず型フリーター」へのなりやすさには「15歳時財産得点」がマイナスの効果を持っていることが示された.この結果は,意に反してフリーターをせざるを得ない層において,経済的困難が学力の低下や学校への不適応につながったり,就職先未決定のままでの大学卒業につながったりすることで,職業への移行において不利になることを示唆するものである.また,フリーターとして一括りにされてきた若年パート・アルバイト層が,階層的出自について幅を持つものであり,従来の量的研究ではそれを一括りに論じていたため,出身階層の効果が見えにくくなっていた可能性を示すものである.
- 著者
- 綱田 錬 竹本 真紹 小笠原 悟司 折川 幸司 齋藤 達哉 上野 友之
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.12, pp.939-948, 2020-12-01 (Released:2020-12-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5
In recent years, more than half of the electric power generated in the country is being consumed by motors. Therefore, high performance motors are desired especially for industrial applications. In addition, it is desirable to reduce motor size. Recently, motors called axial gap type have been proposed and researched to achieve both high torque and small size. Axial gap motors are generally suitable for applications requiring flat shape such as a disk. Conventional axial gap motors frequently employ Nd sintered permanent magnets (PMs) to achieve high torque. However, axial gap motors with Nd sintered PMs are not very efficient at high rotational speed due to the eddy current loss arising in the PM. Axial gap motors that use ferrite PMs have also been proposed, but torque density is low. In this paper, an axial gap motor using Nd bonded PMs is proposed to achieve high efficiency in the high-speed and high-torque region. The proposed axial gap motor using Nd bonded PM is compared with other axial gap motors employing Nd sintered PM and ferrite PM through 3D-FEA and experiments. Consequently, it was found that the Nd bonded PM is more effective in enhancing the efficiency of an axial gap motor in the high-speed and high-torque region, compared with Nd sintered PM and ferrite PM.