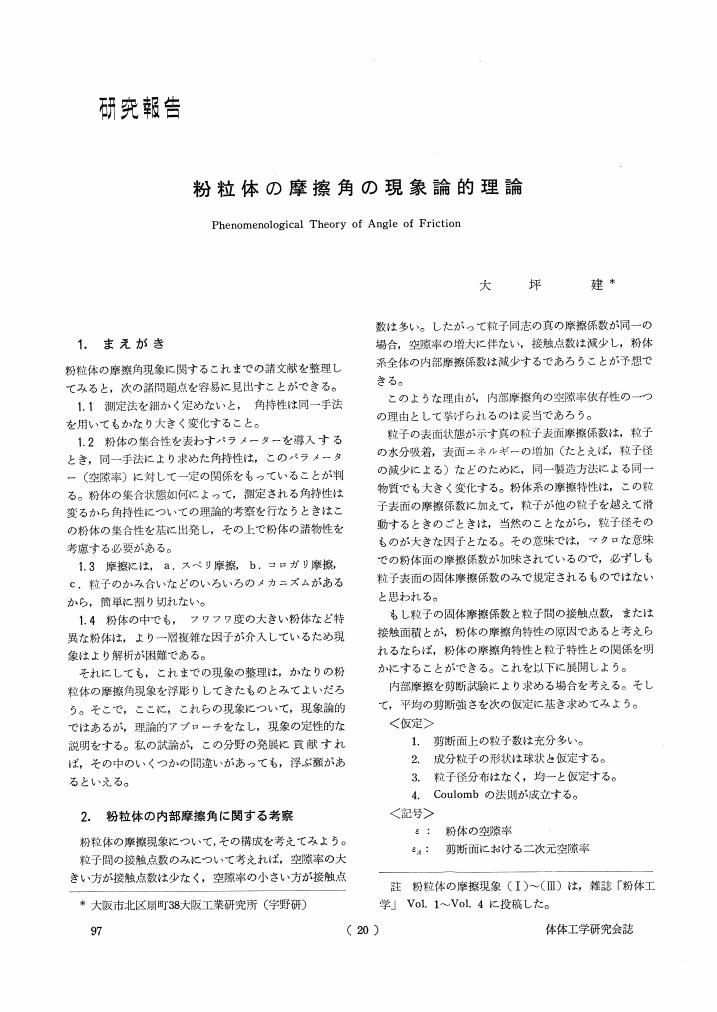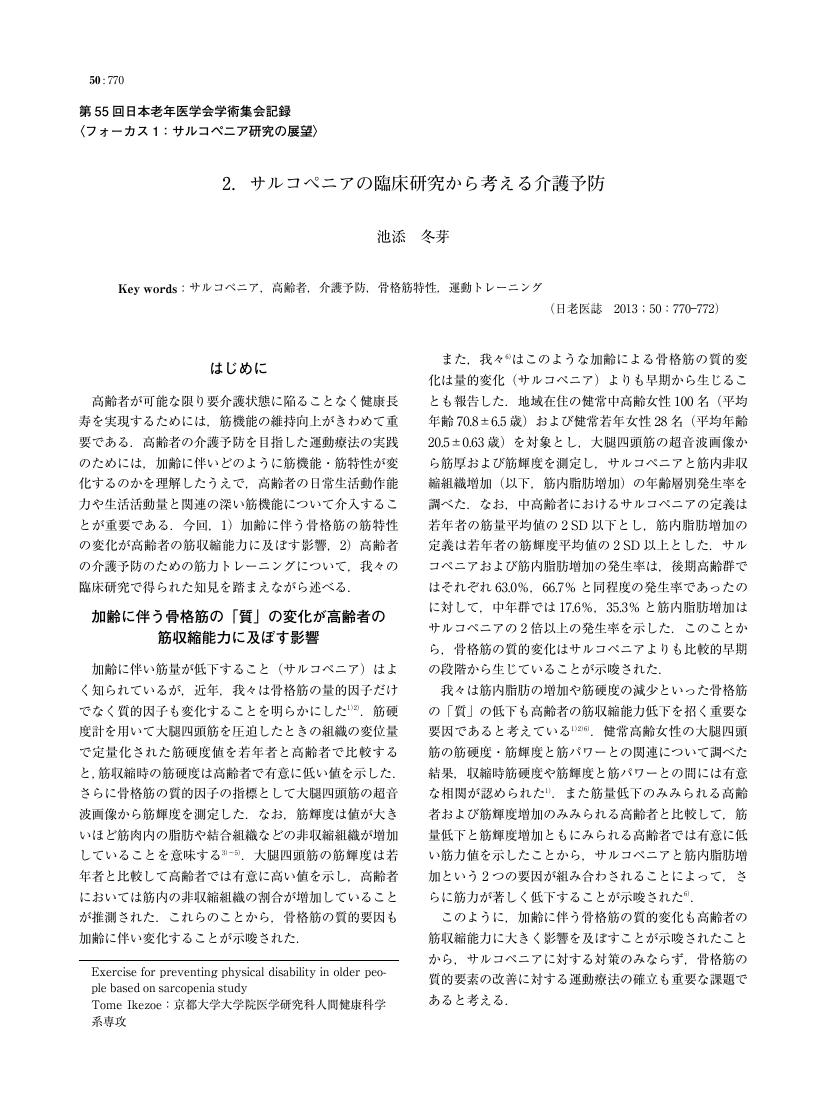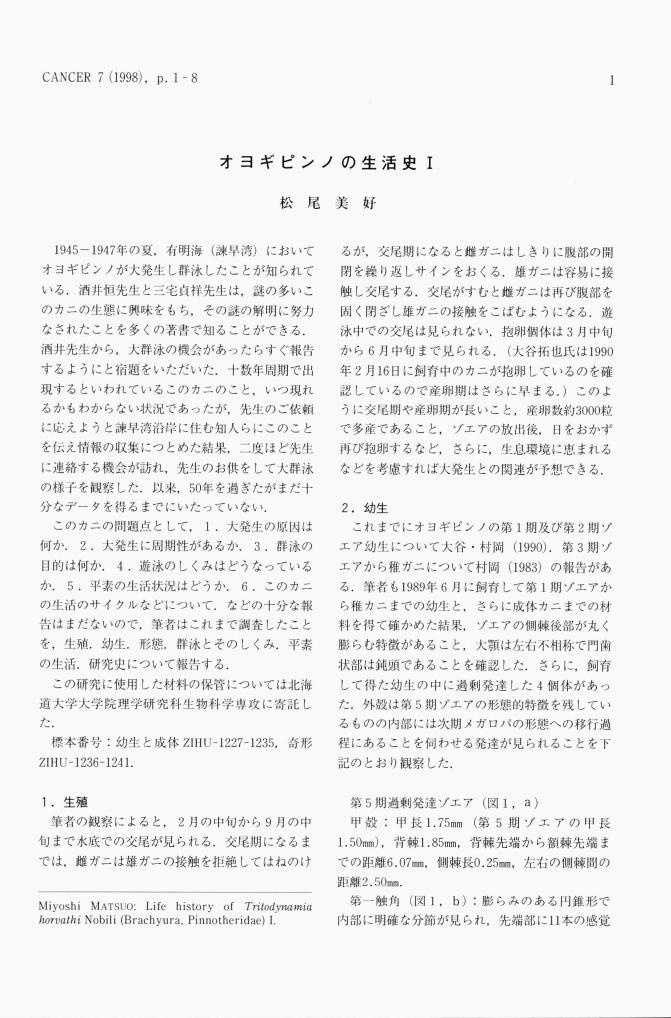2 0 0 0 OA たたら製鉄の炉内反応機構と操業技術
- 著者
- 永田 和宏 鈴木 卓夫
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.64-71, 2000-01-01 (Released:2009-06-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 7 6
"Tatara" was a traditional box-type furnace in Japan and had produced steel and pig iron directly until 1923. After then, because of the low productivity, Tatara was not commercially operated but only for producing the materials of Japanese sword in little. In 1977 with the blank ages after the World War II, Japan Institute of Art Japanese Sword reconstructed the Tatara furnace, called "Nittoho Tatara". Then, Mr. Yoshizo Abe as a leader "Murage" realized his own technique for the Tatara operation because of the technique transfer only by oral instruction to the Murage's family. The 3rd Tatara operation in 1999 winter has been studied on the effect of fire flame (so called "Hose") and sound from furnace, the color and viscosity of slag (so called "Noro") flowed out from furnace and the condition of tuyers to the productivity of "Kera" including steel (so called "Tamahagane") and pig iron (so called "Zuku"), etc. This operation met the trouble of air blowing to the furnace in the final stage. Though many efforts had been made to recover the stable operation, the activity of furnace was stopped in shorter operation time than the other two operations. From the experiences of the recover, the fundamental treatments to make the operation stable have been cleared and also the reaction mechanisms to produce.
2 0 0 0 OA 臍石について
- 著者
- 浜田 稔夫 鈴木 伸典 馬場 堯
- 出版者
- Meeting of Osaka Dermatological Association
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.112-118, 1975 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 13
臍石(Omphalith)の3例を報告し, 中2例は剥離摘出して組織学的検討を加えた。いずれも70 歳以上の女性で, 1~数年前に臍窩に黒褐色の疣状小結節のあるのに気付き, 放置していたところ, 漸次増大, 突出するようになった。皮膚面に固く附着するも, 剥離摘出したあとの臍窩皮膚はほぼ正常で, 剥離標本の露出部は黒褐色を呈し, 石のように硬いが, 非露出部では比較的柔らかく, 粥状で, 白色に近い。組織所見はH.E.染色でエオジンに瀰漫性に淡く染まるが, 核成分はみられない。臍窩の比較的深い者に清浄不良が重なって生じたもので, 皮脂, 角質などの蓄積によるものと考えられる。併せて鑑別診断などについても考察を加えた。
- 著者
- Naomasa Kobayashi Chisato Kataoka Shosaku Kashiwada
- 出版者
- The Japanese Society of Environmental Toxicology
- 雑誌
- 環境毒性学会誌 (ISSN:13440667)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.38-46, 2020-07-22 (Released:2020-07-21)
- 参考文献数
- 12
We compared stage-dependent sensitivities of the sea urchin Anthocidaris crassispina to silver nitrate (AgNO3) and silver nanocolloids (SNCs). Our experimental design included three different exposure experiments: (1) pre-fertilization exposures (to assess effects on first cleavage and embryogenesis); (2) exposures of fertilized eggs (to assess effects on cleavage and embryogenesis); and (3) exposures of gastrulae (to assess effects on the gastrula stage and embryogenesis). In the case of the pre-fertilization exposures, exposure of sperm to SNCs induced higher rates of abnormal development than did exposure to AgNO3, and SNCs had higher teratogenicity on pluteus formation than did AgNO3. In the case of the fertilized egg exposures, exposed embryos experienced high rates of cytolysis. These rates exceeded those observed in pre-fertilization exposures of eggs and sperm and were similar to those observed in exposures of sperm alone. In the case of the gastrula exposures, rates of cytolysis were higher than those observed in pre-fertilization exposures of eggs and sperm and lower than those observed in exposures of fertilized eggs and of sperm alone. Sperm exposures showed the highest chemical sensitivity, followed by exposures of gastrulae and of unfertilized eggs and sperm.
- 著者
- Yuki Takai Takumi Takamura Shintaro Enoki Moeko Sato Yoko Kato-Unoki Xuchun Qiu Yohei Shimasaki Yuji Oshima
- 出版者
- The Japanese Society of Environmental Toxicology
- 雑誌
- 環境毒性学会誌 (ISSN:13440667)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.10-21, 2020-07-21 (Released:2020-07-21)
- 参考文献数
- 48
Tributyltin (TBT) is an organotin compound that disrupts the endocrine system of aquatic organisms, and its obesogenic toxicity to various species is well known. However, the mechanism by which TBT disrupts the endocrine system has not been clarified. Therefore, to investigate the effects of TBT in fish, we exposed juvenile medaka (Oryzias latipes) to TBT and analyzed the gene expression changes using mRNA-Seq. As a result of this analysis, it was clear that toxicity-related genes, such as cytochrome P450 superfamily genes connected to hormonal metabolism, and peroxisomeproliferator-activated receptor signaling pathway genes related to obesity, were significantly affected by TBT. Thus, our mRNA-Seq results identified candidate genes for involvement in the mechanisms of TBT toxicity in TBT-exposed medaka. mRNA-Seq could be a strong tool to investigate and further understand the toxic effects caused by pollutants.
- 著者
- Takashi Yanagawa
- 出版者
- The Biometric Society of Japan
- 雑誌
- 計量生物学 (ISSN:09184430)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.69-79, 2020-06-01 (Released:2020-07-21)
- 参考文献数
- 15
Reproducibility is the essence of a scientific research. Focusing on two-sample problems we discuss in this paper the reproducibility of statistical test results based on p-values. First, demonstrating large variability of p-values it is shown that p-values lack the reproducibility, in particular, if sample sizes are not enough. Second, a sample size formula is developed to assure the reproducibility probability of p-value at given level by assuming normal distributions with known variance. Finally, the sample size formula for the reproducibility in general framework is shown equivalent to the sample size formula that has been developed in the Neyman-Pearson type testing statistical hypothesis by employing the level of significance and size of power.
2 0 0 0 OA 粉粒体の摩擦角の現象論的理論
- 著者
- 大坪 建
- 出版者
- The Society of Powder Technology, Japan
- 雑誌
- 粉体工学研究会誌 (ISSN:18838766)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.97-102, 1964-11-01 (Released:2010-08-10)
- 被引用文献数
- 1 2
2 0 0 0 OA 環境汚染化学物質ビスフェノール類の代謝から見えてきた薬物抱合の役割
- 著者
- 岩野 英知 大谷 尚子 井上 博紀 横田 博
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第43回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.S16-6, 2016 (Released:2016-08-08)
我々の身の回りには多くの化学物質があふれており、日常的に多くの化学物質に接触している。生体は、それら多くの化学物質を無毒化し、排除する効率的なシステムを備えている。たとえば、内分泌攪乱化学物質であるビスフェノールA(BPA)は、そのエストロジェン作用で大きく騒がれたが、現在では成熟した健康な大人であれば、大きな影響はないということが明らかとなった。それは、BPAが薬物代謝の第II相酵素UDP-glucuronosyltransferase (UGT)により効率的に代謝され、排泄されるからである。一方で、妊娠期にBPAを暴露すると、たとえ低容量であっても次世代に悪影響を及ぼすとの報告がある。この低容量BPAによる胎仔影響には、以下の3つのファクターが関与している、と我々は考えている。①妊娠期の母-仔間の体内動態 ②胎仔における代謝システム(グルクロン酸抱合と脱抱合) ③胎仔でのエストロジェニックな作用以外の攪乱以上の仮説をもとに、これまでに我々は以下の点を明らかにしてきた。①BPAの代謝物が胎盤を通過する可能性があること ②胎児側に移行したBPA代謝物がBPAに再変換されうること ③薬物抱合のタイプによっては、胎盤通過が異なる可能性があること ④ビスフェノール類(BPA、BPF)の妊娠期の暴露は、生まれた仔の成熟後に対して不安行動を増強すること。本発表では、これらの研究を踏まえながら、薬物抱合の役割、特に胎盤通過についての結果を中心に報告する。これまで薬物抱合反応は、薬物を排泄されるためのシステムであり、抱合体そのものの生体内での役割、影響については見いだせていなかった。生体内物質の抱合体には、排泄だけでなく運搬体としての意義があり、生体外からの化学物質も同様の過程をとる場合もあると考えている。今後、抱合体そのもの役割を詳細に検討するべきと考えている。
2 0 0 0 OA 2.サルコペニアの臨床研究から考える介護予防
- 著者
- 池添 冬芽
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.770-772, 2013 (Released:2014-03-13)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3 2
2 0 0 0 OA 住宅・土地統計調査を用いた住宅残存率曲線の決定手法および既存住宅築年推定法の検討
- 著者
- 小浦 孝次
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.741, pp.2907-2913, 2017 (Released:2017-11-30)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
In the building administration, it is necessary to improve existing buildings as earthquake resistant, fire prevention and energy conservation countermeasures. Grasp of the number of residual houses by building year is important. In this paper, the building year estimation method for existing buildings using "Housing and Land Statistics Survey" in the Ministry of Internal Affairs and Communications(MIC) Bureau of Statistics. At first, the number of houses built in each year was estimated. The residual rate curve of the housing can be calculated using three parameters and three statistics (estimated housing starts before 1944, the number of new housing starts by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport since 1945, housing and land statistics survey). The building year distribution of housing in 2013 was estimated from the 2008 survival curve. The estimation result was similar to the statistics of 2013. This method was confirmed that this estimation method is effective for short-term future prediction. This estimation method is effective for grasping the number of residual houses for each building year which was previously difficult. For example, in the total number of homes, the total number of houses with residence, vacancy, in a lost house. Furthermore, changes in the number of residual houses by construction year were obtained by comparing estimation results of "housing and land statistics surveys" every 5 years.
2 0 0 0 OA 好酸球性副鼻腔炎病態におけるカンジダアルビカンス遅延型皮内反応関与について
- 著者
- 若山 望 松根 彰志 大久保 公裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.10, pp.1316-1317, 2018-10-20 (Released:2018-11-21)
- 著者
- 櫻木 敬子
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.63-64, 2019-06-20 (Released:2019-07-12)
2 0 0 0 OA 日本と韓国における地震災害後の応急仮設住宅の供給に関する比較研究
- 著者
- 金 池潤 金 栽滸 加藤 孝明
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.829-835, 2019-07-01 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 18
本研究は,韓国史上最大の被害規模を記録した浦項地震における応急仮設住宅の供給について振り返り,日本と韓国での事例を比較して,今後の改善の方向性を模索することを目的としている.浦項地震における応急仮設住宅の特徴は,被災者の所有地で設置する自己敷地仮設住宅・仮設店舗併用住宅・一戸当たり屋外空間の一定規模が確保できる団地型仮設住宅・団地内管理事務所の設置などがある.日本と韓国における応急仮設住宅の事例を供給思想・供給類型・提供までの期間,建設コストなどの観点から比較分析を行った.
2 0 0 0 OA MPS法における勾配計算の高精度化とその応用
- 著者
- 入部 綱清 仲座 栄三
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.46-50, 2010 (Released:2010-11-09)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 7 7
A highly precise numerical calculation method of the gradient as a differential operator in a computational method with the MPS has been proposed in this study. The method is not dependent on the particle arrangement. Gradient calculations of a linear and nonlinear function have been introduced in the proposed method to verify the numerical accuracy. The results show high accuracy on the boundary in regular grid arrangement case but on both the boundary and inside in random arrangement case. High accuracy and computational stability are also obtained when applied to the calculations of the hydrostatic pressure and free surface of water.
2 0 0 0 OA アルコールの脱水反応(有機反応 : どうしてそうなるの 1)
- 著者
- 上方 宣政
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.7, pp.488-491, 1999-07-20 (Released:2017-07-11)
- 被引用文献数
- 1
有機化合物の反応では, 用いる触媒や反応温度が変わると異なった化合物が生成することがしばしばある。では, 触媒や反応温度など反応条件が変わると, どうして異なった化合物が得られるのか?これらの実験事実を説明するためには触媒の役割をふまえた反応機構を理解することが必要不可欠である。本稿では, エタノールを硫酸の存在下に加熱すると, 反応温度の違いによって, どうしてジエチルエーテルとエチレンがそれぞれ生成するのか, その機構について解説する。
2 0 0 0 OA 内外の特許資料の利用について
- 著者
- 水田 悦夫
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.11, pp.17-26, 1958-11-20 (Released:2016-03-17)
2 0 0 0 OA 皮膚の水分量 ・ 油分量 ・ pHならびに清浄度からみた清拭の効果
- 著者
- 橋本 みづほ 佐伯 由香
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.61-68, 2003-09-10 (Released:2016-10-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
清拭の皮膚の水分量 ・ 油分量 ・ pHならびに清浄度 (ATP) に及ぼす影響を調べるため, 清拭前から120分後までの経時的な変化を測定し, 一般的な清潔形態である入浴と比較検討した. 対象は20代から40代の健康な女性7名とした. その結果, ①入浴群の水分量は直後に一旦増加した後60分後には有意に減少し, 実験前値より低値を示した, ②入浴群の油分量は120分後まで有意に減少し, 減少程度は清拭群よりも有意に大きかった, ③ pHは両群ともに直後に有意に増加したが清拭群では30分後に戻った, ④ ATPは両群ともに直後に有意に減少したが120分後には戻り, 減少程度は入浴群の方が大きい傾向があった. 以上の結果, 入浴に比較して清拭の方が水分量 ・ 油分量 ・ pH ・ ATPの変化量が少なく, 皮膚が本来持っている機能に与える影響が少ないこと, その一方で清拭の方が除菌効果および皮脂の除去に関する効果が低いことが示唆された.
2 0 0 0 OA 人間らしさって何だろう?
- 著者
- サイエンスウィンドウ編集部
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.6, pp.1-36, 2010-12-01 (Released:2019-04-11)
サイエンスウィンドウ2010冬号の冊子体一式(PDF版)およびHTML版は下記のURLで閲覧できます。 https://sciencewindow.jst.go.jp/backnumbers/detail/10 目次 【特集】 人間らしさって何だろう? p.06 長谷川寿一氏に聞く「他者の気持ちが理解できる動物、人間」について p.08 人類の進化と分布を表す概念図 p.10 生物としてヒトはどう進化したのか p.12 「ヒトらしい脳」に人間らしさは詰まってる? p.14 人間らしさはどこまで科学で語れるか? 形態人類学×分子人類学 p.16 石黒浩研究室を訪ねて「ロボットに込める人間らしさ」 p.20 学校訪問 動物に学ぶ子どもたち 横浜市立川井小学校(神奈川県) 【連載】 p.02 似姿違質:ヨーロッパアナウサギ VS ニホンノウサギ p.18 人と大地:ダナキル砂漠(エチオピア) p.25 かがくを伝える舞台裏:「岩波科学教育映画を使った授業」に参加して p.26 いにしえの心:冬の雷 p.27 タイムワープ夢飛翔:進化論/ダーウィンをせかせた男 p.28 イチから伝授実験法:コイルを巻いて電磁石を作ろう p.30 ふるさと食の楽校:ハタハタずし 秋田県男鹿市 p.31 サイエンスのお仕事図鑑:科学的に「聞きやすい声」を追求する アナウンサー p.32 発見! 暮らしのなかの科学:太陽、水、そして植物が砂糖の甘みを生み出した p.34 せんせいクラブ p.36 人と大地:解説
2 0 0 0 OA オヨギピンノの生活史I
- 著者
- 松尾 美好
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-8, 1998-05-01 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 調製時における塩および油添加タイミングの違いによる塩味の感じ方
- 著者
- 佐川 敦子 笹原 由雅 鎌形 潤一 青木 仁史 大橋 きょう子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 2019年度大会(一社)日本調理科学
- 巻号頁・発行日
- pp.96, 2019 (Released:2019-08-26)
【目的】減塩につながる調味方法としては,食品内部に塩味を拡散させず,食べる直前に食品表面に塩味をつける方法がある。これまでに,うま味や酸味を添加することで塩味強度が強まるという報告はあるが,油を添加した場合の塩味の感じ方についての報告は見当たらない。そこで,油添加に着目し,調製時における塩および油添加タイミングの違いによる塩味の感じ方について検討した。【方法】塩および油添加タイミングを変えた飯表面に塩味をつけた試料(塩味表面試料)と,塩水で炊飯した試料(塩味均一試料)の塩むすびモデル系試料を調製した。塩添加量は米重量の1.15 w/w%(飯の0.5w/w%),油添加量は米重量の2.0 w/w%とした。試料の形状測定(マイクロスコープVHX-6000),物性測定(レオナーRE2-33005C)を行った。また,官能評価により,同一塩分濃度下における塩味の感じ方について,呈味強度(塩味,甘味,うま味)および味の好ましさを5段階評点法により評価した。【結果および考察】1. 形状測定:米飯対角幅,周囲長,面積において,塩味表面試料は,塩味均一試料よりも高値を示した。2. 物性測定:硬さにおいて,塩味表面試料は,塩味均一試料よりも有意に低値を示した。3. 官能評価:塩味表面試料は,塩味均一試料に比べ塩味強度は有意に高かった。また,炊飯前油添加試料は,炊飯後油添加試料よりも塩味強度は有意に高かった。炊飯前に油を添加し炊飯後に飯表面に塩味を付与すると,塩味の感じ方は強くなることが示唆された。官能評価の塩味強度と物性測定の凝集性および付着性で負の相関が認められた。結果,米飯の凝集性,付着性が小さいほど,塩味強度は高くなることが示唆された。
2 0 0 0 OA 日本版自由意志・決定論信念尺度の作成
- 著者
- 後藤 崇志 石橋 優也 梶村 昇吾 岡 隆之介 楠見 孝
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.86.13233, (Released:2015-01-15)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4 7
We developed a free will and determinism scale in Japanese (FAD-J) to assess lay beliefs in free will, scientific determinism, fatalistic determinism, and unpredictability. In Study 1, we translated a free will and determinism scale (FAD-Plus) into Japanese and verified its reliability and validity. In Study 2, we examined the relationship between the FAD-J and eight other scales. Results suggested that lay beliefs in free will and determinism were related to self-regulation, critical thinking, other-oriented empathy, self-esteem, and regret and maximization in decision makings. We discuss the usefulness of the FAD-J for studying the psychological functions of lay beliefs in free will and determinism.