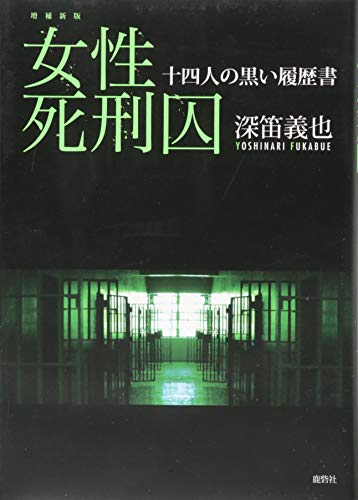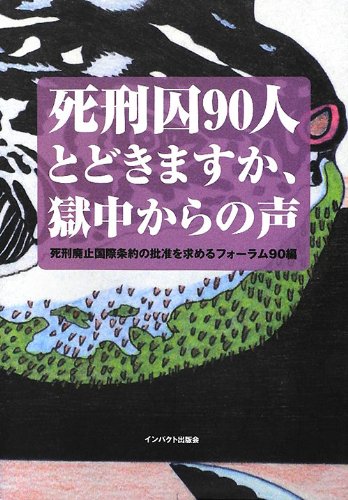- 著者
- 小島 渉
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.147, 2022 (Released:2022-10-22)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
コガネムシ上科には、オスが角や発達した大顎などの武器形質を頭部に持つ種が多く存在する。それらの中には長い前脚を持つ種が多く含まれる。このことから、頭部の武器と前脚は機能的に関連していることが推測されるが、二つの形質の機能に同時に着目した研究は少ない。本稿では、オスが1対の角と長い前脚という二つの誇張化形質を持つワリックツノハナムグリにおいて、オス間闘争におけるこれらの形質の機能について解説する。本種はタケの仲間の新芽に集まり、吸汁、配偶を行う。オスは交尾後にメスにマウントし、配偶者防衛を行うが、餌場での性比がオスに偏っており、防衛オスと単独オスとの間で頻繁に闘争が起こる。闘争行動を分析した結果、前脚は闘争の初期における儀式的行動で、角は闘争がエスカレートしたときの直接的な闘争でおもに使われることがわかった。また、大きな武器(あるいは大きな体)を持つオスほど、配偶者防衛、あるいは配偶者の乗っ取りに成功しやすかった。形態のアロメトリーの解析結果からも、角と前脚が性淘汰の産物であるという仮説が支持された。さらに、長い前脚が枝の上を歩く際に歩行速度を低下させるかを調べたが、体に対する前脚の長さと歩行速度の間に関係は見られなかった。相対的な前脚の長さは、相対的な中脚や後脚の長さと正の相関を示したことから、長い前脚を持つ個体は同時に長い中脚や後脚を持つことで、歩行の安定性を維持している可能性がある。
4 0 0 0 OA シトルリンの代謝と薬効
- 著者
- 林 登志雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.7, pp.460-464, 2008-07-01 (Released:2011-04-14)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
シトルリンはアミノ酸の一種で,尿素回路を構成する化合物の一つである.1930年に日本の研究者によって,スイカの果汁から発見された.化学式は C6H13N3O3,化合物名は2-アミノ-5-(カルバモイルアミノ)ペンタン酸,分子量は175.2である.「シトルリン(citrulline)」という名前は,スイカの学名である Citrullus vulgaris に由来する.動物,特に哺乳類に広く存在し,1950年ごろには,ヒトの体内で重要な役割を果たしていることが明らかになり,1980年代に入ると,一酸化窒素(NO)との関係が見いだされ,今日この分野での研究が活発に行なわれている.
4 0 0 0 OA 序論――安全保障の課題としての越境・難民問題
- 著者
- 墓田 桂
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.1-16, 2019-03-31 (Released:2022-03-14)
4 0 0 0 女性死刑囚 : 十四人の黒い履歴書
4 0 0 0 死刑囚90人とどきますか、獄中からの声
- 著者
- 死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90編
- 出版者
- インパクト出版会
- 巻号頁・発行日
- 2012
4 0 0 0 OA ぺた語義:千葉県公立高等学校情報科教員の現状 -千葉県校長会によるアンケート調査から-
4 0 0 0 OA 福島県いわき市の河川で採集された暖水性の水生動物5種
- 著者
- 山川 宇宙 内田 大貴 外山 太一郎 津田 吉晃
- 出版者
- アクオス研究所
- 雑誌
- 水生動物 (ISSN:24348643)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, pp.AA2023-14, 2023-08-02 (Released:2023-08-02)
Two warm-water fish species, Eleotris fusca (Bloch and Schneider, 1801) and Sicyopterus japonicus (Tanaka, 1909), and three warm-water decapod crustacean species, Macrobrachium formosense Bate, 1868, M. japonicum (De Haan, 1849), and Varuna sp., were collected from a river in Iwaki, Fukushima Prefecture, Japan. The occurrence of E. fusca represents a new record from the prefecture and the northernmost record for the species. It is likely that M. japonicum overwintered, but the other four species probably dispersed from the south via ocean currents. In recent years, the range of many species has been extending northward due to global warming and thermal discharge. To understand changes in the distribution and habitat of these aquatic animal species, it is necessary to continue monitoring the occurrence of warm-water aquatic animals in coastal areas and rivers in the prefecture.
4 0 0 0 OA 高温超電導フィーバーを憶う
- 著者
- 上之薗 博
- 出版者
- 公益社団法人 低温工学・超電導学会 (旧 社団法人 低温工学協会)
- 雑誌
- 低温工学 (ISSN:03892441)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.9, pp.375, 2004 (Released:2008-03-10)
4 0 0 0 OA ヤギによる耕作放棄地の植生管理
- 著者
- 真野 宏子 Hiroko Mano
- 雑誌
- 共立女子大学文芸学部紀要 = The Kyoritsu journal of arts and letters
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.47-75, 2016-01
4 0 0 0 OA 許宏著『大都無城―中国古都的動態解読』
- 著者
- 黄川田 修
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho (ISSN:03869067)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.4, pp.29-37, 2018-03
4 0 0 0 OA マッチングゲームの実証分析
- 著者
- 中嶋 亮
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱経済研究所 経済研究書 (ISSN:27587711)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.107, pp.1-97, 2015-02-10 (Released:2023-08-01)
- 著者
- Akihito Yokoyama Hiroshi Okazaki Naoyuki Makita Ayako Fukui Yi Piao Yoshifumi Arita Yohji Itoh Naoki Tashiro
- 出版者
- Japanese Society of Allergology
- 雑誌
- Allergology International (ISSN:13238930)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.47-54, 2022 (Released:2022-01-27)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 7
Background: In Japan, regional differences in asthma mortality have been reported; however, regional differences in asthma exacerbations have not been studied extensively. Therefore, using a health insurance claims database, we investigated the regional differences in the incidence of asthma exacerbations in Japan.Methods: This study used data from Medi-Scope (Japan Medical Information Research Institute Inc., Japan)-a nationwide health insurance claims database. Patients with asthma at the index date (the latest date of an asthma-related prescription with an asthma diagnosis before October 1, 2018) were included in the analysis. The pre-index period was defined as 1 year before the index date, and the follow-up period as 1 year after the index date. The incidence of asthma exacerbation events was analyzed for each region.Results: The primary analysis population comprised 24,883 patients who were continuously prescribed ICS or ICS/LABA at least four times during the pre-index period. The incidence rate of asthma exacerbations with hospitalization was the highest in Chugoku (2.95/100 person-years [95% CI, 1.97-4.43]) and the lowest in Kanto (1.52/100 person-years [95% CI, 1.26-1.83]). The incidence rate of asthma exacerbations for the composite outcome of hospitalization, injectable corticosteroid prescription, and oral corticosteroid burst was the highest in Fukui (105.00/100 person-years [95% CI, 64.53-170.85]) and the lowest in Nagasaki (15.69/100 person-years [95% CI, 10.84-22.72]).Conclusions: Regional differences in the incidence of asthma exacerbations as well as their treatments were observed in Japan.
4 0 0 0 OA 超電導電力貯蔵装置(SMES)の現状
- 著者
- 渡部 智則 長屋 重夫 平野 直樹
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.12, pp.873-876, 2012-12-10 (Released:2014-09-02)
4 0 0 0 OA エスノメソドロジーとテクストデータ
- 著者
- 岡沢 亮
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.540-556, 2022 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 31
本稿の目的は,テクストデータを用いるエスノメソドロジーの方針と取り組むべき課題をめぐる方法論的議論を進展させることである.まずテクストのエスノメソドロジーの基本方針が,テクストを社会現象の表象として扱うのではなく,テクストにおいていかなる活動がいかなる概念連関に依拠して行われているのかを分析することだと述べる.次に,テクストを分析する際の資源としての受け手の反応(の不在)をめぐり会話分析から寄せられた批判に応答し,テクストの分析可能性を擁護する.その上で,Goffman の参与枠組のアイデアとそれに対する会話分析の批判的検討を参照し,書き手と読み手がテクストをめぐる参与枠組を形成する方法を解明することが興味深い課題になると論じる.またその課題に取り組むにあたり,テクストを書く/読む実践の制約かつ資源となるインターフェイスへの着目の重要性を主張する.以上を踏まえ,ウェブ上の映画作品レビューとそれに付されたコメントの具体的分析を行うことにより,テクストの参与枠組を形成する方法の分析が当のテクストの活動としての理解可能性の解明に資すること,そしてその分析においてテクストを書く/読む際のインターフェイスへの着目が有効であることを例証する.最後に,本稿の議論がエスノメソドロジーと会話分析の関係の再考や,テクストデータを用いる社会学一般をめぐる方法論的議論に寄与することを示唆する.
- 著者
- 粕谷 誠
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱史料館論集 (ISSN:13453076)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.24, pp.1-14, 2023-03-20 (Released:2023-08-01)
4 0 0 0 OA ワットパクナム日本別院の形成とそのタイ系居住者との関わり
- 著者
- 佐藤 百香 阿部 拓也 山田 協太
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.810, pp.2348-2359, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 26
This paper clarifies the spatial composition and formation history of a Theravada Buddhist temple, Wat Paknam Japan Branch, which is a focal point of daily lives of Thai originated dwellers, and the relationship between the temple and them through on-site surveys. By considering land and facilities, Thai-Japanese mixed characteristics of the temple are clarified. Buddhist concept of merit was the key of temple expansion. Then, by considering movement route and activities within facilities it is clarified that temple is used by eight types of peoples with different purposes and degrees of overlap between their dwelled enviroment and temple differ.
4 0 0 0 OA マウスにおける視覚研究:ゲシュタルト知覚をめぐる展開
- 著者
- 後藤 和宏
- 出版者
- 日本視覚学会
- 雑誌
- VISION (ISSN:09171142)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.98-104, 2022-10-20 (Released:2022-10-26)
- 参考文献数
- 29
4 0 0 0 OA 平尾光司教授退職記念研究会記録
- 著者
- 平尾 光司
- 出版者
- 専修大学社会科学研究所
- 雑誌
- 専修大学社会科学研究所月報 (ISSN:0286312X)
- 巻号頁・発行日
- vol.558, pp.2-70, 2009-12-20
平尾光司教授退職記念研究会;[2009年]3月14日(土)都市センターホテル708会議室
4 0 0 0 OA 「健康支援型」道の駅の利用と主観的健康感:3時点パネルデータを用いた縦断研究
- 著者
- 熊澤 大輔 田村 元樹 井手 一茂 中込 敦士 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.22-128, (Released:2023-06-28)
- 参考文献数
- 33
目的 千葉県睦沢町では,2019年に「健康支援型」道の駅を拡張移転した。仮説として,道の駅を利用した高齢者では,利用しなかった高齢者に比べ,主観的健康感不良者が減少したと考えられる。そこで,道の駅利用が主観的健康感不良の減少と関連するのか検証することを目的とした。方法 2019年9月の道の駅拡張移転前後の3時点パネルデータを用いて道の駅開設後の利用群と非利用群を比較評価した縦断研究である。道の駅拡張移転前の2018年7月(2018年度調査)と2019年の拡張移転後の2020年11月(2020年度調査)と2022年1月(2021年度調査)の3回,自記式調査票の郵送調査を行い,個票レベルで結合した3時点パネルデータを作成した。目的変数は2021年度調査の主観的健康感不良,説明変数は2020年度調査時点の道の駅利用とした。調整変数は2018年度調査の基本属性と2018,2020年度の外出,社会参加,社会的ネットワークとした。多変量解析は多重代入法で欠損値を補完し,道の駅利用のみを投入したCrudeモデルと,2018年度調査の基本属性(モデル1),2018年度調査の外出,社会参加,社会的ネットワーク(モデル2),2020年度調査の外出,社会参加,社会的ネットワーク(モデル3)を投入した各モデルについて分析を行い,修正ポアソン回帰分析を用い,累積発生率比(Cumulative Incidence Rate Ratio, CIRR),95%信頼区間,P値を算出した。結果 対象者576人のうち,道の駅利用者は344人(59.8%)であった。基本属性を調整した多変量解析の結果,道の駅非利用群に対して利用群では,主観的健康感不良者のCIRR : 0.67(95%信頼区間 : 0.45-0.99,P=0.043)であり,有意に少なかったが,道の駅開設後の2020年度調査の外出,社会参加,社会的ネットワークを調整したモデルではCIRR : 0.71(95%信頼区間 : 0.48-1.06,P=0.096)と点推定値が1に近づいた。結論 本研究では,3時点パネルデータにより,道の駅拡張移転前の交絡因子を調整した上で,利用群で主観的健康感不良者が減少,つまり不良から改善していた。外出のきっかけとなり,人と出会う機会となる道の駅などの商業施設が「自然に健康になれる環境」になりうることが明らかとなった。