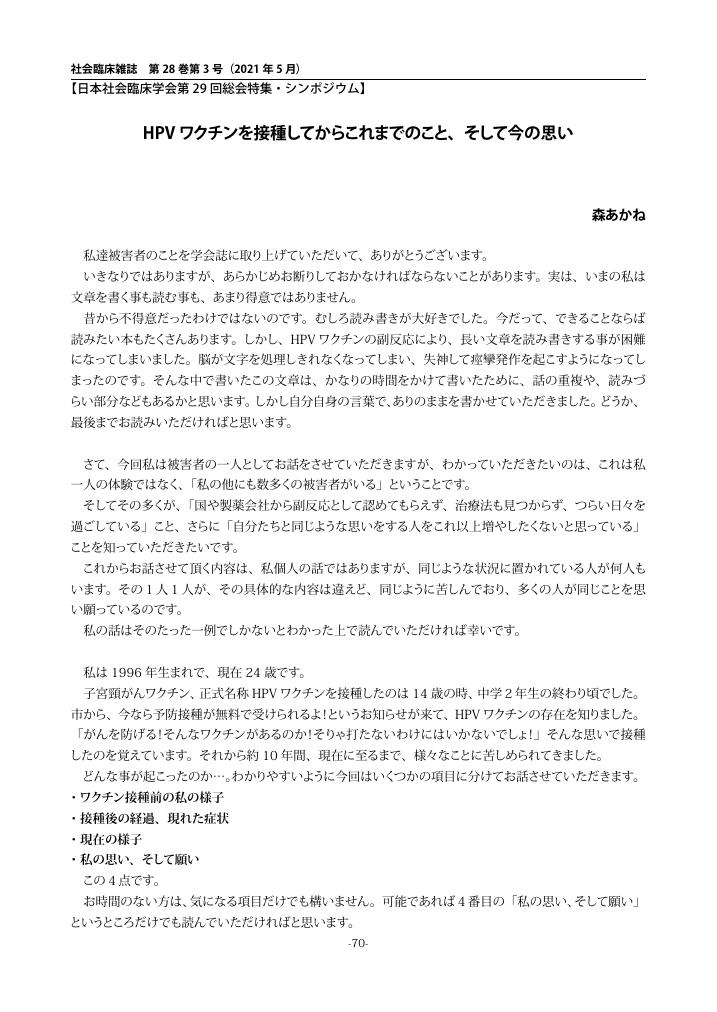4 0 0 0 OA 〔大日本沿海輿地全図 〕
- 著者
- 〔伊能忠敬//測量・製作〕
- 出版者
- 写
- 巻号頁・発行日
- vol.第90図 武蔵・下総・相模(武蔵・利根川口・東京・小仏・下総・相模・鶴間村), 1873
4 0 0 0 エボシガイの血球
4 0 0 0 OA 胆石の種類と成因
- 著者
- 正田 純一
- 出版者
- 日本胆道学会
- 雑誌
- 胆道 (ISSN:09140077)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.672-679, 2013-10-31 (Released:2013-12-05)
- 参考文献数
- 27
胆石は胆嚢あるいは胆管の胆道内に生じた固形物である.胆石はその存在部位と構成成分により,背景病態や生成の機序が異なる.胆石はその主要成分により,コレステロール胆石,色素胆石(ビリルビンカルシウム石と黒色石),稀な胆石に分類される(日本消化器病学会胆石症検討委員会1986年).日本人の胆石症の頻度・種類は欧米並となり,胆嚢結石ではコレステロール胆石が約70%程度を占めるようになり,また,黒色石が増加している.胆石の成因は胆石の種類により異なるが,それらの形成機序は,胆石主要構成成分の胆汁における過剰排泄,それに伴う結晶化による析出,さらに,胆道系における結晶の迅速な成長からなる.成因の理解のためには胆汁の生成,分泌,濃縮の生理学の知識も必要となる.本稿では,胆石症診療ガイドライン(2009年)における「胆石症の病態と疫学」の内容に触れながら解説をおこないたい.
4 0 0 0 OA 母子の食物新奇性恐怖と食生活コミュニケーションが野菜摂取におよぼす影響
- 著者
- 淀川 尚子 徳永 淳也 丸谷 美紀 波多野 浩道
- 出版者
- 日本民族衛生学会
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.5, pp.183-202, 2016-09-30 (Released:2016-10-31)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 1
This study aimed to characterize the effects on vegetable consumption caused by mother-child food neophobia and their dietary communication, both of which have a great influence on the child’s eating behavior. A self-administered questionnaire was conducted in elementary and junior high school students who had regular dental visits and their mothers, and 193 subjects were analyzed. Items included in the questionnaire were largely basic attributes and food neophobia of the mother and child, likes and dislikes, triggers of the child’s food aversion, eating habits, mother-child communication about eating habits, frequency of vegetable intake, and preference. Multiple regression analysis determined that food neophobia of the child, experience of forced feeding by the parents, and experience of forced feeding by teachers had a significant positive influence on the likes and dislikes of children, while joint eating behavior with the mother and conversation at table with friends, child age had a significant negative influence. As the factors influencing the number of vegetables the child cannot eat, likes and dislikes of the child, mother’s preference for new food, and the number of vegetables the mother cannot eat had a significant positive influence. In contrast, food neophobia of the child had a significant negative influence. Mother-child food neophobia can affect eating behavior, specifically holding the key to vegetable consumption or non-consumption. The study results suggest that when eating habit guidance is provided emphasis should be placed on joint eating behavior of the mother and child such as food-related conversation, shopping, cooking, and vegetable cultivation, which are considered to be effective in decreasing the likes and dislikes of children, and interventions to enhance dietary communication, for example conversation at table with friends.
4 0 0 0 OA 「戦後」沖縄における「標準語」指導
- 著者
- 長谷川 精一
- 出版者
- 相愛大学総合研究センター
- 雑誌
- 相愛大学研究論集 = The annual report of researches of Soai University (ISSN:09103538)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.21-29, 2014-03
4 0 0 0 OA 会津藩士人名辞典 : 役名禄高住所明細
- 著者
- 古今堂書店古典部 編
- 出版者
- 古今堂書店
- 巻号頁・発行日
- vol.安政5年調, 1933
4 0 0 0 OA 東浅井郡志
- 著者
- 黒田惟信 編
- 出版者
- 滋賀県東浅井郡教育会
- 巻号頁・発行日
- vol.巻2, 1927
4 0 0 0 衛生壽護禄
4 0 0 0 OA がんばれ!日本の客船 : 豪華なだけが客船じゃない(サロン)
- 著者
- 渋谷 晶子
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)
- 巻号頁・発行日
- vol.870, pp.118-123, 2002-11-10 (Released:2018-03-28)
- 参考文献数
- 3
4 0 0 0 OA 冷戦期アメリカの批評における「不可知なもの」―「ダヴォス討論」とルネ・ウェレック
- 著者
- 鈴木 英明
- 雑誌
- 紀要. 人文・社会・自然 = Bulletin of Showa Pharmaceutical University (ISSN:03714845)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.33-42, 2015-02-25
4 0 0 0 OA II.HTLV-1感染・複製機構と発がん
- 著者
- 松岡 雅雄 安永 純一朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.7, pp.1376-1382, 2017-07-10 (Released:2018-07-10)
- 参考文献数
- 13
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(human T-cell leukemia virus type 1:HTLV-1)は,ヒトで初めて同定された病原性レトロウイルスであり,生きた感染細胞を介してのみ感染するという特徴を有している.生体内では,主にCD4陽性Tリンパ球に感染しており,その感染細胞の形質を変化・増殖させ,次の個体へと感染を拡大している.HTLV-1のマイナス鎖にコードされるHTLV-1 bZIP factor(HBZ)はHTLV-1の病原性発現に極めて重要な役割を担っている.この感染細胞を持続的に増殖させるというウイルスの戦略が病原性と結び付いており,感染細胞の抑制が発症予防にも重要である.
4 0 0 0 OA 公共政策に関する大手新聞社説の論調についての定量的物語分析
- 著者
- 田中 皓介 中野 剛志 藤井 聡
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.I_353-I_361, 2013 (Released:2014-12-15)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 4
人文社会科学において,“物語”は,人間,あるいは人間の織り成す社会の動態を理解するにあたって重要な役割を役割を担うものと見なされてきている.それ故,人間や社会を対象として,公共的な観点からより望ましい方向に向けた影響を及ぼさんと志す“公共政策”においても,物語は重大な役割を担い得る.また公共政策の方針や実施においては,マスメディアが少なからぬ影響を及ぼしていることが十二分に考えられる.ついては本研究では,現在の日本において,政策が決定,採用されてきた背景を把握するにあたり,新聞の社説を対象とし,新聞各社に共有されている物語を定量的に分析することとする.
4 0 0 0 OA XF-2の空力設計
- 著者
- 森 重樹 才上 隆 堀川 誠 浜田 充 柳 武 清島 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.555, pp.228-233, 2000-04-05 (Released:2019-04-11)
4 0 0 0 OA HPV ワクチンを接種してからこれまでのこと、そして今の思い
- 著者
- 森 あかね
- 出版者
- 日本社会臨床学会
- 雑誌
- 社会臨床雑誌 (ISSN:21850739)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.70-79, 2020 (Released:2021-11-10)
4 0 0 0 OA わさびの辛味成分と調理
- 著者
- 中野 典子 丸山 良子
- 雑誌
- 椙山女学園大学研究論集 自然科学篇 (ISSN:13404067)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.111-121, 1999
4 0 0 0 OA 経営学とファミリービジネス研究
- 著者
- 加護野 忠男
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.68-70, 2008-01-01 (Released:2012-02-15)
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 新修本草
- 著者
- (唐) 李勣 等奉敕撰
- 出版者
- 傅雲龍
- 巻号頁・発行日
- vol.[2], 1889
4 0 0 0 OA 東京都区部におけるシェアハウスの立地特性とシングル女性の住宅ニーズからみたその背景
- 著者
- 石川 慶一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.4, pp.203-223, 2019 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 6
本稿は,東京都区部のシェアハウスの立地特性および台東区を事例としたシングル女性のシェアハウス居住の実態を明らかにした.分析結果から,シェアハウスの多くは,都心周辺部の鉄道駅付近に立地し,単身者向け賃貸住宅と比較して居住性が高いことが示された.それらは,ファミリー世帯の需要が低い商業地区に立地する住宅が転用されたものである.台東区の女性シェアハウス居住者は,低所得層の者が多い.彼女たちにとってのシェアハウスの優位性は,家賃が低いにもかかわらず,交通利便性の高い場所に住むことができ,台所や浴室といった住宅設備を快適に利用できることだった.一方,シェアハウス運営事業者はその管理物件にシングル女性のニーズを反映させていた.近年のシェアハウスの増加の背景には,都心周辺部での余剰住宅ストックの増加と,職住近接や生活の質の向上を指向するシングル女性のライフスタイルの存在があると考えられる.
4 0 0 0 OA 診断名の提示が自閉症スペクトラム障害に対するスティグマに及ぼす影響:知識との関連から
- 著者
- 谷口 あや 山根 隆宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.130-140, 2020 (Released:2022-09-20)
- 参考文献数
- 38
本研究の目的は,自閉症スペクトラム障害(以下,ASD),アスペルガー障害(以下,AS)の診断名の提示が大学生のASDに対するスティグマにどのような影響を及ぼすのか,またASDへの知識との関連がみられるのかを検討することであった。大学生286名を対象に質問紙調査を実施した。ASDの特性(関心の制限,社会的相互作用の困難)を示す登場人物を描写した2つの場面のビネット(グループ課題場面,クラブ活動場面)を提示し,1)ASD条件,2)AS条件,3)診断なし条件の3条件をランダムに配布し,ビネット内の登場人物に対する社会的距離を評定させ,スティグマを測定した。その結果,どちらの場面においても,ASD条件,AS条件,診断なし条件のすべての条件間において,社会的距離に差は見られなかった。次に,どちらかの診断名を提示している,診断あり条件と,診断名を提示しない,診断なし条件間で知識の影響を確認するために,社会的距離を従属変数とした階層的重回帰分析を行った。その結果,診断名の有無と知識の交互作用が確認された。どちらの場面においても診断あり条件において知識の単純傾斜が有意であり,知識が高い場合には社会的距離が近かった。以上のことから,大学生のASDに対するスティグマには提示する診断名そのものの効果はみられず,診断名提示の有無と知識の高低の関連を踏まえた上で検討していく必要性があることが示唆された。