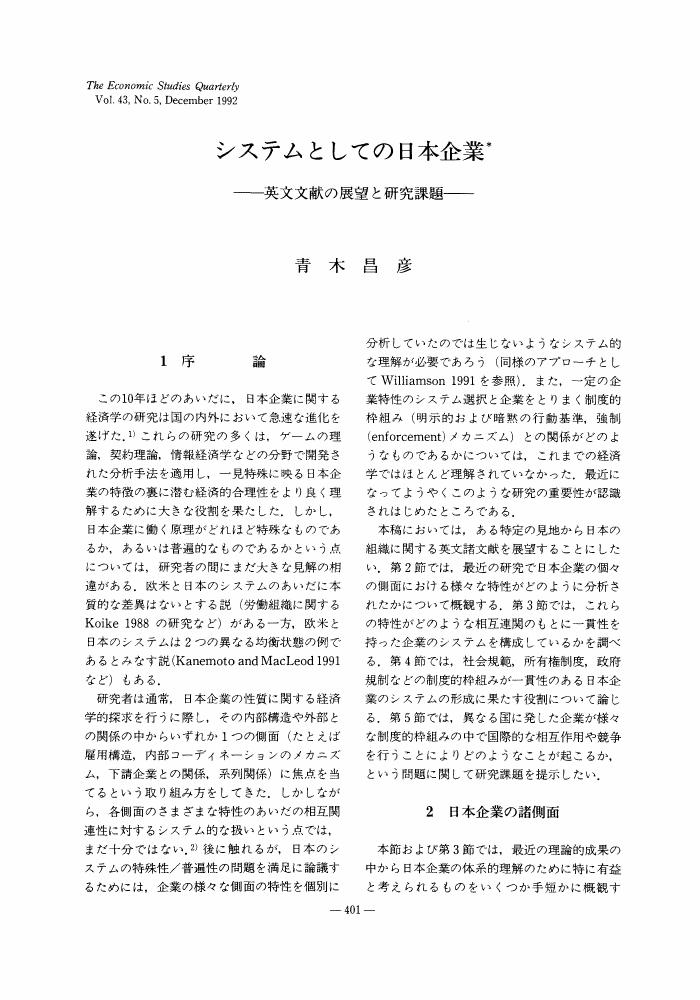- 著者
- 中山 敬太
- 出版者
- 協創&競争サステナビリティ学会
- 雑誌
- 場の科学 (ISSN:24343766)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.42-62, 2022 (Released:2022-07-01)
萌芽的科学技術の科学的不確実性を伴うリスク対する予防的措置に関して、本稿ではナノテクノロジーを事例として、その規制対象を「テクノロジー」と「マテリアル」の要素に区分し、科学技術の「機能」や「性質」にも考慮した上で、規制対象を区分せずに予防的措置を講じた場合と比べ、社会的許容性と妥当性を相対的に担保し、社会的不都合性が生じることをより軽減するアプローチに繋がる可能性があることを明らかにした。また、既にナノテクノロジーに関して規制措置を定めるEU等の諸外国に対して、日本では具体的な予防的措置は講じられていない状況下で、今後のナノテクノロジー規制の展望に関して政策的示唆を含め新たな視座を示した。
4 0 0 0 心拡大,高度浮腫を伴つた急性多発性神経炎
- 著者
- 高橋 和郎 田中 和子 西川 清方 米本 哲人
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.10, pp.1140-1152, 1975
- 被引用文献数
- 1
8例の特異な急性多発性神経炎について臨床的ならびに末梢神経の電顕的検討を行なつた.これらの症例は下肢の著しい浮腫,疼痛をもつて始まり,上行性の運動麻痺,駆幹あるいは四肢末端の知覚障害,深部反射の低下をみる.麻痺は顔面神経に及ぶことがあり,一般に四肢末端に強い。知覚障害は比較的軽い.発症は急性あるいは亜急性で時に寛解,増悪を示し,しばしば,発熱,白血球減少,血沈促進, CRP陽性, A/G比低下など感染,アレルギーを思わせる所見を有する.同時に著しい心拡大,心雑音,時に心電図異常を認める.心臓症状は多発性神経炎の回復に先立つて軽快する.神経症状はGuil1ain-Barré症候群に類似するが,脳脊髄液は細胞数増加を示すことが多いが蛋白量は正常である。末梢神経は軸索,髄鞘共に著しい障害を示し,軸索再生,髄鞘再生の像がみられ,障害は有髄線維に著しい.再生した細い無髄線維の著しい増加がみられる.筋は軽度の血管周囲性リンパ球浸潤を示すものがあるが,筋炎という程の所見ではなく,一般に神経原性萎縮を示す.いずれも男性で1973年から1974年にかけて発症し,近年多発する傾向がある.脚気にも類似するが,要因と思われるものが見出し難く,かつしばしば感染,アレルギーを思わせる所見を有する.
4 0 0 0 OA アンソニー・ギデンズの「再帰性」概念について
- 著者
- 萩原 優騎 Yuki Hagiwara
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル = The Journal of Social Science
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.51-69, 2008-09-30
4 0 0 0 OA インターネットを通じ購入したGHB服用による深昏睡の1例
- 著者
- 池田 弘人 金子 一郎 多河 慶泰 遠藤 幸男 小林 国男 鈴木 宏昌 中谷 壽男
- 出版者
- Japanese Association for Acute Medicine
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.190-194, 2001-04-15 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 21
A middle-aged man was found unconscious at apartment after ingesting gamma hydroxybutyric acid (GHB) purchased via the internet sales and was admitted to our critical care center. He underwent gastric irrigation and respiratory assistance with intubation at the emergency room due to a probable drug overdose and respiratory acidosis. After fully recovering, he admitted he had taken large doses of GHB with alcohol. The US Federal Drug Administration (FDA) banned GHB sale as an OTC drug in 1991 but has not succeeded in controlling increased GHB addiction. Unconsciousness, coma, hypothermia, bradycardia, hypotention, muscle weakness, myoclonus, convulsion, respiratory distress, and vomiting are common symptoms after GHB ingestion. Treatment such as gastric irrigation, atropine for bradycardia, and respiratory assistance in hypoxia are recommended. Little attention is paid to GHB in Japan because of its rarity and its sale is not illegal, unlike the strict restrictions in the US and European countries. With GHB available over the Internet, its abuse is expected to increase.
4 0 0 0 OA システムとしての日本企業 英文文献の展望と研究課題
- 著者
- 青木 昌彦
- 出版者
- 日本経済学会
- 雑誌
- The Economic Studies Quarterly (ISSN:0557109X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.401-418, 1992-12-25 (Released:2008-02-28)
- 参考文献数
- 66
- 著者
- 中野 毅 Tsuyoshi NAKANO
- 出版者
- 創価大学社会学会
- 雑誌
- SOCIOLOGICA (ISSN:03859754)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1/2, pp.25-41, 2001-12-01
- 著者
- 樫本 喜一
- 出版者
- 大阪府立大学21世紀科学研究機構現代生命哲学研究所
- 雑誌
- 現代生命哲学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.31-49, 2014-03
- 著者
- 藤井 久
- 出版者
- ジャパンミリタリー・レビュー
- 雑誌
- 軍事研究 (ISSN:05336716)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.6, pp.82-92, 2004-06
- 著者
- 野田 潤
- 出版者
- 東洋英和女学院大学
- 雑誌
- 人文・社会科学論集 (ISSN:09157794)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.27-46, 2022-03
In the process of modernization of family in Japan, home cooking has been given a special value, and homemade meals became as a symbol of family love. As a result, even today, homemade meals by married women function strongly as a symbol of love. This may be one of the reasons why the excessive burden of housework put on women and the division of gender roles have not changed much when compared to other countries.This paper examines the origin of the norm in Japan that a wife should prepare extremely time-consuming homemade meals for her family in relation to modern family norms of affection, using text analysis.First, an analysis of articles from Yomiuri Shimbun (1874-2020) that included koshi-ben, aisai bento, and aijo bento in their headlines revealed that a strong connotation of between a homemade bento and affection was established in the mid-1960s to 1970 in Japan and has continued to the present day.Second, an analysis of articles on daily family food menus and recipes that appeared in Yomiuri Shimbun (1915-2020) shows that social standards for daily homemade meals in Japan rose sharply in the 1970s, and the menu consisting of one soup and three dishes became commonplace between the end of 1980s and the early 1990s. But it was also found that from the mid-1990s onward, there was a growing awareness of the need to shorten time and save labor when preparing meals.The above analyses reveal that the rapid rise of social standards for wives' homemade cooking went hand in hand with the emergence of the idea that a married woman's homemade cooking is a sign of her love for her family. This suggests that the deep-rooted tendency in Japan to view a wife's home-cooked meal as a proof of love is one of the reasons why wives have been slow to reduce their burden of housework, even today.
4 0 0 0 OA 小さき花 : 聖女小さきテレジア之自叙伝
4 0 0 0 OA 寝具の違いが睡眠の質に影響を及ぼすか?
- 著者
- 金江 亮
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.229-250, 2022-02-17
4 0 0 0 OA 食物網の複雑性と柔軟性、個体群の安定性について(宮地賞受賞者総説)
- 著者
- 近藤 倫生
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.249-261, 2005-08-31 (Released:2017-05-27)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 1
食物綱とは生物群集内の捕食・被食関係を描いたグラフである。個体群動態は直接・間接の種間相互作用の影響を受けるが、捕食・被食関係を通じた相互作用の生じ方は食物網の構造に依存する。したがって、食物綱構造は個体群動態を理解するうえでの鍵となる。これまで、食物網の複雑性(種数、結合度)と安定性の間の関係について多くの研究がなされてきたが、数理モデルを用いた理論研究ではしばしば食物網の複雑性が高くなると安定性が低下するとの予測がなされてきた。その後、現実の食物網の特徴や現実的な仮定を組み込むことによって、複雑な食物綱が安定に存続しうることが理論的に示されてきた。しかし、これらの研究の多くは「食物綱の構造は固定的で変化しない」という生物の根本的な特徴を無視した仮定にとらわれてきた。生物の最も重要な特徴のひとつは、表現型可塑性や進化のためにその行動や形態が適応的に変化するということだ。捕食行動や対捕食者防御行動が適応的に変化する場合、食物網を構成する捕食・被食関係のリンクもやはり時とともに変化しうる柔軟なものとして捉えなくてはならない。このような適応のひとつである適応的餌選択とそれに由来する食物網の柔軟性を考慮すると、食物網・生物多様性の維持に関してこれまでとはまったく異なる理論予測が導かれる。第一に、複雑性-安定性関係が正になりうる。第二に、食物網の結合度と安定性の間の関係が時間スケールと結合度の差を生み出すメカニズムに依存するようになる。第三に、生物の適応が生物間の相互作用の歴史の結果にできたものであることから、歴史こそが群集を安定化する鍵になっていると考えることができる。食物網の柔軟性が個体群動態におおきな影響を与えうることが多くの研究によって示唆されてはいるが、それを確かめるのは容易ではない。なぜなら食物綱の時とともに変動する詳細な構造を調べ上げることは簡単ではないからだ。工夫を凝らした実証研究によってこれらの理論予測をテストしていくことが今後の課題であろう。
4 0 0 0 OA <論文>やなせたかしの童話における『フランケンシュタイン』の受容
- 著者
- 道合 裕基
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科思想文化論講座文芸表象論分野
- 雑誌
- 文芸表象論集 = Literary Arts and Representation (ISSN:21880239)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.15-28, 2016-12-31
This study argues on the influence of Mary Shelley's Frankenstein in Yanase Takashi's fairy tales. Specifically, I take up Anpanman and Kyurakyura no Chi for discussion. The motifs of ugliness and the oppressed person are shown in these two fairy tales as well as in Frankenstein. Through comparison of both writers works, it can be considered that Yanase found important source of ideas for his works in Frankenstein.
- 著者
- 森田 のり子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.198-218, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
本論はアジア・太平洋戦争期の日本において、それまで左翼思想を背景とした記録映画の表現方法に取り組んできた作り手らが、戦時国策プロパガンダの要請に対して自らの議論と製作実践をどのように変容させていったのかという問題を、「主観」的表現という論点に着目して考察するものである。具体的な対象として、当時国内最大のドキュメンタリー映像分野の国策映画製作会社であった、日本映画社の撮影技師・坂斎小一郎と演出家・桑野茂の両活動に照準する。まず、1940年代初頭までに記録映画の表現における「主観」「客観」の関係性をめぐる議論と実践が充実していたことを確認した上で、アジア・太平洋戦争期になると国民としての「主観」を持つ「戦記映画」が求められていったことを論じる。こうした状況のなかで、『陸軍航空戦記 ビルマ篇』(1943)の撮影を担った坂斎は戦地の現実に向き合うこと自体に積極的意義を見いだしたものの、完成作品はその認識とギャップを呈していた。一方、『基地の建設』(1943)の演出を担った桑野は、戦争当事者の立場で想定したような現実に対面できなかったことで、結果的に自らの認識を生かした作品を手がけることとなった。それぞれの条件の下で異なる展開をたどりながら、両者とも表現する主体としての「作家」であろうとする問題意識に基づき、自らの左翼思想によって培った「主観」と戦時国家に要請される「主観」とを接続しようと試みたことを明らかにする。
4 0 0 0 OA インフルエンザA/H1N1 pdm感染を契機に急性肝炎重症型を発症した1例
- 著者
- 舛石 俊樹 酒井 義法 細谷 明徳 鈴木 健一 伊藤 剛 鎌田 和明 水谷 佐和子 村野 竜朗 相馬 友子 永山 和宜 草野 史彦 田沢 潤一 鈴木 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.7, pp.461-467, 2011 (Released:2011-08-18)
- 参考文献数
- 20
症例は23歳女性.38℃台の発熱・倦怠感・嘔気・関節痛が出現したため,当院救急外来を受診した.インフルエンザ迅速診断キットでインフルエンザA型陽性のためインフルエンザウイルス感染症と診断された.また,血液検査ではトランスアミナーゼの著明な上昇とPTの低下を認め,急性肝炎重症型の診断で当科に緊急入院した.与芝らの劇症化予知式により劇症化の可能性があると判断し,劇症肝炎に準じて血漿交換療法・ステロイドパルス療法を施行した.第2病日よりトランスアミナーゼ・PTの改善を認め,第12病日退院した.肝障害の成因として薬物性肝障害の可能性は否定できなかったが,臨床経過からは新型インフルエンザ(以下A/H1N1 pdm,PCR法で診断)感染が成因である可能性も否定できなかった.A/H1N1 pdm感染による高サイトカイン血症を契機に急性肝炎重症型を発症したと考えられる1例を報告する.