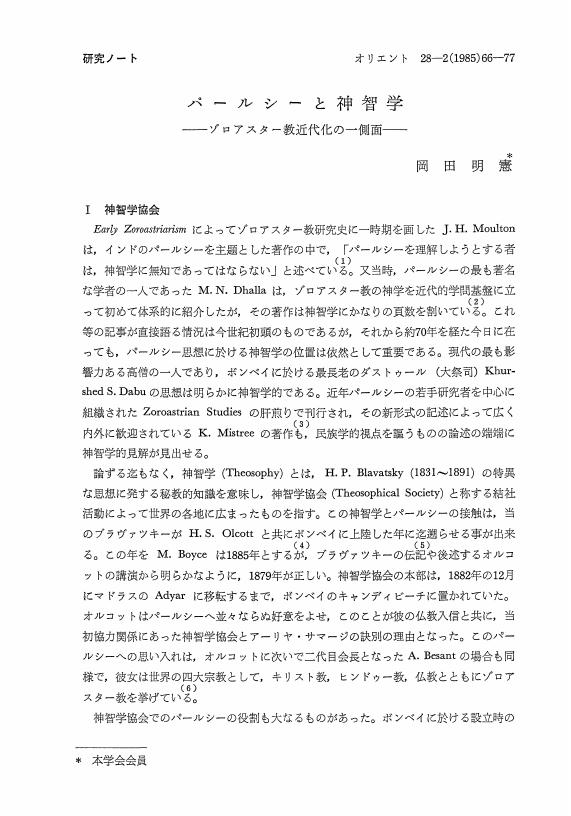4 0 0 0 OA 模式的教材を中心としたる各科教授の研究
- 著者
- 京都府女子師範学校附属小学校教授法研究会 編
- 出版者
- 明治出版協会
- 巻号頁・発行日
- vol.第1巻(尋常小学 第1・2年), 1917
4 0 0 0 OA ウル第三王朝の王シュルギと英雄ギルガメシュ
- 著者
- 前田 徹
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第4分冊, 日本史学 東洋史学 西洋史学 考古学 文化人類学 日本語日本文化 アジア地域文化学 (ISSN:13417541)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.5-19, 2015-02-26
4 0 0 0 IR 医療ソーシャルワーク業務の変遷 : 個別の生活問題を社会の問題としてきたか
- 著者
- 小畑 美穂 Miho Obata
- 出版者
- 同志社大学社会学会
- 雑誌
- 評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)
- 巻号頁・発行日
- no.136, pp.45-85, 2021-03-31
本論文は,医療ソーシャルワーク業務が,時代や政策といった社会の影響から受け身的傾向が強まり,社会へ働きかける視点が希薄化される経緯を整理し,要因との関係性を明らかにした。貧困や傷病で困窮する患者の受診・入院支援を中心に家族も含め地域社会を視野に業務を担っていた萌芽期を経て,戦後GHQ 撤退後の保健所医療社会事業後退によって地域社会への視点が希薄化した。同時に援助論の偏重傾向が強まった。創設された職能団体は,質向上と業務明確化を求めるも当初の目的から逸れ資格化運動に傾倒した。政策は少子高齢社会による財源支出抑制に対応するため基礎構造改革,早期退院,地域移行を推進した。医療ソーシャルワーク業務は,政策,組織に後進することで内向きとなり,個別に現れている生活問題を社会の問題とする視点は薄められた。論文(Article)
4 0 0 0 OA 二人のシュナイダー
- 著者
- 梅原 秀元 ウメハラ ヒデハル Hideharu Umehara
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.1-12, 2022-03
4 0 0 0 OA 長時間飛行の疲労評価と対策
- 著者
- 金澤 富美子 菊川 あずさ 金丸 善樹 髙澤 千智 大類 伸浩 丸山 聡 柳田 保雄 小林 朝夫 柏崎 利昌 藤田 真敬
- 出版者
- 航空医学実験隊
- 雑誌
- 航空医学実験隊報告 (ISSN:00232858)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.1-13, 2017 (Released:2017-05-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
Pilot fatigue, which causes 21% incidents in US Civil Aviation, 25% lethal accidents in US Air Force's night tactical flight, and 12% lethal accident in US Navy, has been recognized as an insidious threat through out aviation. Despite our recognition of fatigue, no guideline was published until 2011, due to its difficulty in objective assessment. Recently, objective assessment for fatigue has been partly established and contributed to open guidelines. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) published guidebook as "Plain language about shiftwork" in 1997. Aerospace Medical Association published position paper as "Fatigue countermeasures in aviation" in 2009. International Air Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organization (ICAO), and International Federation of Air Line Pilots’Association (IFALPA) published "Fatigue Risk Management System (FRMS) Implementation guide for operators" in 2011. Those guidelines says that aviation-related fatigue is caused by disorder of sleep and circadian rhythm. Psychomotor Vigilance Task (PVT) or Motion logger watch (Actigraphy) are recommended for objective assessment of fatigue. Best counter measures for shift work and aviation related fatigue are adequate sleep. We review those guidelines and discuss applicability for safe flight in Japan Air Self-Defense Force.
4 0 0 0 OA 粘菌ネットワークの賢さ
- 著者
- 伊藤 賢太郎 中垣 俊之
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.178-181, 2011 (Released:2011-07-25)
- 参考文献数
- 10
The origin of information processing is a fundamental problem in evolutionary biology. True slime mold, Physarum, has become a model organism for study of problem solving by single-celled organisms. Here we report its ability to find a smart network by describing its aptitude in maze solving, multi purpose optimization for transportation network and risk management in a spatio-temporally varying field. We discuss these results in the context of a risk management strategy.
4 0 0 0 OA 日本産Adela属(鱗翅目,ヒゲナガガ科)の分類学的再検討
- 著者
- 広渡 俊哉
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.271-290, 1997-11-30
- 参考文献数
- 16
これまで,Adela属の種として日本からミドリヒゲナガA.reaumurella(Linnaeus)とケブカヒゲナガの2種のみが知られていた.今回,日本産Adela属の分類学的再検討を行った結果,A.nobilis Christophとされていたケブカヒゲナガは,独立種であることが明らかになり,A.praepilosa sp.nov.として記載した.さらに,2新種A.luteocilis sp.nov.(アトキケブカヒゲナガ:新称),A.luminaris sp.nov.(ムモンケブカヒゲナガ:新称)を見いだし,計4種が日本に分布することがわかった.なお,A.nobilis Christoph,1882は,基産地であるウラジオストク周辺のロシア沿海州などに分布し,おそらく日本には分布しない.Adela属は,♂の触角第8-9鞭節に特異な突起(hook-peg)を持つことによって特徴づけられる.日本産Adela属は,ミドリヒゲナガとそれ以外の3種にグルーピングできる.ミドリヒゲナガでは,transtilla側背面の突起がヘラ状で,ケブカヒゲナガを含む他の3種では,刺状.また,ケブカヒゲナガを含む3種では雌交尾器のvestibulumに顕著な板状の骨片(vestibular lamella)が存在するが,ミドリヒゲナガではこれを欠く.日本産の種はいずれも平地では4月下旬-5月上旬,山地などでは5月-6月に見られる.成虫はカエデ類の花などに集まる.Adela属では,♀に比べて♂の触角が長く複眼が大きいという性差が見られる,今回扱った種では,♂の複眼の大きさや触角の長さに種間差が認められた.複眼の大きさ,触角の長さは,それぞれhd/md(複眼の水平直径/複眼間の最短距離),al/fl(触角長/前翅長)で表した.Nielsen(1980)は,Adela属とNemophora属の種で,♂の複眼が大きいものはスウォーム(群飛)するものが多いとしている.実際,ケブカヒゲナガ.A.praepilosa sp.nov.の♂の複眼は大きく,スウォームすることが知られている.一方,アトキケブカヒゲナガA.luteocilis sp.nov.とムモンケブカヒゲナガA.luminaris sp.nov.では,♂の複眼は小さく,触角が長いが,これらの種がスウォームするかどうかは観察されていない.日本産のAdela属とNemophora属でスウォームしないとされているのは,現在のところクロハネシロヒゲナガNemophora albiantennella Issiki 1種のみである(Hirowatari&Yamanaka,1996).クロハネシロヒゲナガでは♂の触角が長く(al/fl:3.36±0.02),複眼の大きさに性差は認められない(hd/md:♂0.44±0.03,♀0.42±0.2).ヒゲナガガ科では,他個体の認識はすべて視覚によってなされていると考えられている.しかし,複眼が小さく,スウォームしないクロハネシロヒゲナガの♂は,単独で飛翔して♀を探索するが,この時視覚以外の感覚(嗅覚など)を用いていることも充分考えられる.今回,雄交尾器,特にvalva形態から,複眼が小さく触角の長いムモンケブカヒゲナガと,複眼が大きく触角の短いケブカヒゲナガがもっとも近縁であると推定された.従って,♂の複眼の大きさや触角の長さは,各種でおそらく配偶行動と密接に関係しながら独立に進化したと考えられる.さらに,これらの種では複眼が大きいと触角が短く,複眼が小さいと触角が長かった.ただし,ムモンケブカヒゲナガとアトキケブカヒガナガでは,複眼が小さいといっても♀よりは相対的に大きく,視覚で他個体を認識している可能性が高いが,その際,長い触角で嗅覚等,視覚以外の感覚を相補的に用いているのかもしれない.ヒゲナガガ科の配偶行動とそれに関わる形態の進化については,さらに多くの種で詳しく調べる必要がある.以下に日本産各種の形態的特徴と分布などを示す.A.reaumurella(Linnaeus,1758)ミドリヒゲナガ分布:北海道,本州,九州;ヨーロッパ.前後翅とも一様に暗緑色の金属光沢を有しており,日本では他種と混同されることはない.雄交尾器のtegumen後端の形態がヨーロッパ産のものに比べて異なっており(森内,1982),♂の複眼の大きさもヨーロッパ産のものよりやや小さいと思われるが,複眼の大きさは地理的変異があるという報告例もあるので(Kozlov&Robinson,1996),ここでは従来の扱いのままで保留した.A.luteocilis sp.nov.(新種)アトキケブカヒゲナガ(新称)分布:本州(長野県,岐阜県,滋賀県,和歌山県,奈良県[伯母子岳,大台ヶ原]).♂の複眼は小さく(hd/md:0.86±0.03),触角は長い(al/fl:3.33±0.14).♂の頭頂毛,触角間毛は黄色.♀の触角の基部約3分の1が黒色鱗で覆われる.雌雄とも後翅の中室端から前縁部にかけて淡色の斑紋がある.後翅の縁毛が黄色であることで,他種と区別できる.A.luminaris sp.nov.(新種)ムモンケブカヒゲナガ(新称)分布:本州(大山),九州(福岡県[英彦山,犬鳴山]).♂の複眼は小さく(hd/md:0.83±0.05),触角は長い(al/fl:3.63±0.21).♂の頭頂毛,触角間毛は黄色.♀の触角の基半部が黒色鱗で覆われる.雌雄ともに,後翅の中室端から前縁部にかけて淡色のパッチがなく,一様に茶褐色-黒紫色であることで,他種と区別できる.A.praepilosa sp.nov.(新種)ケブカヒゲナガ分布:本州,四国,九州.これまで,A.nobilisと混同されてきた.♂の下唇鬚は密に長毛で覆われる.♂の頭頂毛,触角間毛は黒色.♂の複眼は大きく(hd/md:1.87±0.17),触角は比較的短い(al/fl:2.27±0.16).♀の触角の基半部が黒色鱗で覆われる.雌雄とも後翅の中室端から前縁部にかけて淡色の斑紋がある.後翅の縁毛は茶褐色.雄交尾器,特にvalvaの形状から,ムモンケブカヒゲナガに近縁であると思われる.これまで混同されていたA.nobilisとは,valvaの形状の違いで区別できる.♂成虫はカエデ,コバノミツバツツジ,ユキヤナギの花の上でスウォームする.
4 0 0 0 OA 有機溶剤乱用による動因喪失症候群とその治療
- 著者
- 尾崎 茂 和田 清
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.1, pp.42-48, 2001 (Released:2002-09-27)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 4 5
動因喪失症候群(amotivational syndrome)は, 有機溶剤や大麻等の精神作用物質使用によりもたらされる慢性的な精神症状群で, 能動性低下, 内向性, 無関心, 感情の平板化, 集中持続の因難, 意欲の低下, 無為, 記憶障害などを主な症状とする人格·情動·認知における遷延性の障害と考えられている.1960年代に, 動因喪失症候群は長期にわたる大麻使用者における慢性的な精神症状として報告された.その後, 精神分裂病の陰性症状, うつ病, 精神作用物質の離脱症候などとの鑑別が問題とされ, 定義の曖昧さを指摘する意見もあるが, 現時点では臨床概念として概ね受ケ入れられつつある.その後, 有機溶剤使用者においても同様の病態が指摘されるとともに, 覚せい剤, 市販鎮咳薬などの使用によっても同様の状態が引き起こされるとの臨床報告が続き, 特定の物質に限定されない共通の病態と考える立場がみられつつある.また, 精神作用物質使用の長期使用後のみならず, かなら早期に一部の症状が出現することを示唆する報告もある.1980年代より, X線CTなどを用いた有機溶剤慢性使用者における脳の器質的障害の検討によって, 大脳皮質の萎縮などが指摘されてきた.最近は, 神経心理学的手法, MRI, SPECTといった形態学的あるいは機能的画像解析などを用いて, 動因喪失症候群の病態をより詳細に解明しようとの試みがなされつつある.それによれば, 動因喪失症候群にみられる認知機能障害の一部には, 大脳白質の障害が関連し, 能動性·自発性低下には前頭葉機能の低下(hypofrontality)が関連している可能性が示唆されている.これについては, 動因喪失症候群の概念規定をあらためて厳密に検討するとともに多くの症例で臨床知見を重ねる必要がある.治療については今のところ決め手となるものはなく, 対症的な薬物療法が治療の中心である.賦活系の抗精神病薬や抗うつ薬を中心に投与しつつ, 精神療法や作用療法を適宜導入して, 長期的な見通しのもとに治療にあたることが求められる.
- 著者
- 宇都宮 啓吾
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.453-472, 2016
稿者は、前稿(1)において、智積院新文庫蔵『醍醐祖師聞書』(53函8号)について、次の二つの記事を手掛かりとしながら、<br><br>○頼賢の法華山寺での活動<br>(略)遁世ノ間囗ノ/峯堂(法華山寺)ニヲヂ御前ノ三井寺真言師ニ勝月(慶政)上人ノ下ニ居住セリ/サテ峯堂ヲ付屬セムト仰アリケル時峯堂ヲハ出給ヘリ其後律僧ニ成テ高野山一心院ニ居其後安養院ノ/長老ニ請シ入レマイラセテ真言ノ師ニ給ヘリ (6裏~7表)<br><br>○頼賢の入宋遍知院御入滅ノ時此ノ意教上人ニ付テ仰テ云ク我ニ四ノ思アリ遂ニ不成一死ヌヘシ 一ニハ一切經ヲ渡テ下●酉酉ニ置キタシ二ニハ遁世ノ公上ニ隨フ間不叶●死スヘシ 三ニハ法花經ヲ千部自身ヨミタカリシ不叶 四ニハ青龍寺拝見セムト思事不叶頼賢申テ云ク御入滅ノ後一々ニ四ノ御願シトケ申サル其後軈遁世セリ軈入唐シテ五千巻ノ一切經ヲ渡シテ下酉酉ニ經藏ヲ立テ、納也此時意教上人ハ青龍寺拝見歟不見也御入滅後三年ノ内千部經ヨミテ結願アリ四ノ事悉ク皆御入滅後叶給ヘリ(6表~6裏)<br>主として、以下の如き四点について指摘した。<br><br>①智積院新文庫蔵『醍醐祖師聞書』は、従来、奥書の類による確認でしか叶わない、意教情人頼賢の高野山登山前の法華山寺での活動や頼賢入宋の記事を含む新発見の「頼賢伝」資料として位置づけられる。<br>②法華山寺慶政を頼賢の「ヲヂ御前」とする記事から頼賢と慶政との関係の深さが確認できると共に、別の箇所では「意教ノ俗姓ハ日野(ヒノ、)具足也」(5裏)とする記述の存することから、頼賢の出自についても新たな資料が得られる。<br>③②を踏まえるならば、本書が慶政の出自に関わる新資料の提示ともなっていることから、慶政を「九条家」出身とする従来説との関連を考える必要が存し、その意味で、慶政の出自に関する再検討が俟たれる。<br>④本書の「頼賢伝」(頼賢の入宋と法華山寺慶政との関係)は、意教流、特に、東寺地蔵院流覚雄方相承の中において伝えられていたものと考えられる。また、本書が、家原寺聖教の一つであることから、家原寺を拠点とした律家側の資料として文章化されたものと考えられる。<br><br> 前稿においては、新たな「頼賢伝」資料の提示を中心とした、本書の紹介に主眼が存したため、本書の成立の背景や本書の記事を手懸かりとした分析には至っておらず、この点に関する検討の必要性を感じる。<br> そこで、本稿においては、本書分析の一つとして、本書の成立の〝場〟について考えると共に、本書の記事を手懸かりとした東山と根来寺とを巡る問題についても検討したい。
4 0 0 0 OA パールシーと神智学 -ゾロアスター教近代化の一側面-
- 著者
- 岡田 明憲
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.66-77, 1985 (Released:2010-03-12)
4 0 0 0 IR 大地の用益権は生きている人々に属する--財産権と世代間正義についてのジェファーソンの見解
- 著者
- 森村 進
- 出版者
- 一橋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 一橋法学 (ISSN:13470388)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.715-762, 2006-11
4 0 0 0 IR ヤングケアラーになる移民の子どもたち:大阪・ミナミのケーススタディ
- 著者
- 原 めぐみ Megumi Hara
- 雑誌
- 多民族社会における宗教と文化 : 共同研究
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.43-52, 2021-03-31
- 著者
- SCREECH Timon
- 出版者
- International Research Center for Japanese Studies
- 雑誌
- Japan review : Journal of the International Research Center for Japanese Studies (ISSN:09150986)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.5-32, 2022-02
Hokusai's print known as the Great Wave, from the series Thirty-Six Views of Mt. Fuji, is among the most recognized works of art worldwide. Prior scholarship has addressed its production, circulation, and extensive afterlife. This paper, by contrast, enquires into what the subject actually means. Why did Hokusai make a representation of vessels in heavy seas, with a sacred mountain behind them? I question what Hokusai might have wanted to impart, and where his visual conceptualization could have come from. In this iconographic investigation, the argument will be made for the Great Wave being best understood in terms of Dutch maritime disaster painting. Such works were theological, offering the terror of death averted by some external divine intervention. Several examples were brought to Japan during the Edo period. It would not have seemed odd to Japanese viewers that ships were capable of supporting symbolic meanings. At the same time, there is no previous example of an independent Japanese depiction of ships in distress. Furthermore, Mt. Fuji offered precisely the promise of safety, its name punning on "no death."
- 著者
- 梶谷 懐 カジタニ カイ Kai Kajitani
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.2, pp.64-78, 2022-03
4 0 0 0 OA ロシア 殉職軍人遺族等への金銭報酬の支払に関する法改正
- 著者
- 大河原健太郎
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 284-2), 2020-08
4 0 0 0 IR 谷崎潤一郎『鶴唳』における漢籍要素
- 著者
- 李 春草 リ シュンソウ Ri Syunsou
- 出版者
- 同志社大学国文学会
- 雑誌
- 同志社国文学 (ISSN:03898717)
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.67-79, 2013-12
4 0 0 0 OA 接ぎ木の親和・不親和性
- 著者
- 仁藤 伸昌
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.87-92, 1989-02-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 9
4 0 0 0 OA 嗅神経細胞の再生
- 著者
- 土井 清司
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.68-69, 2008 (Released:2009-06-05)