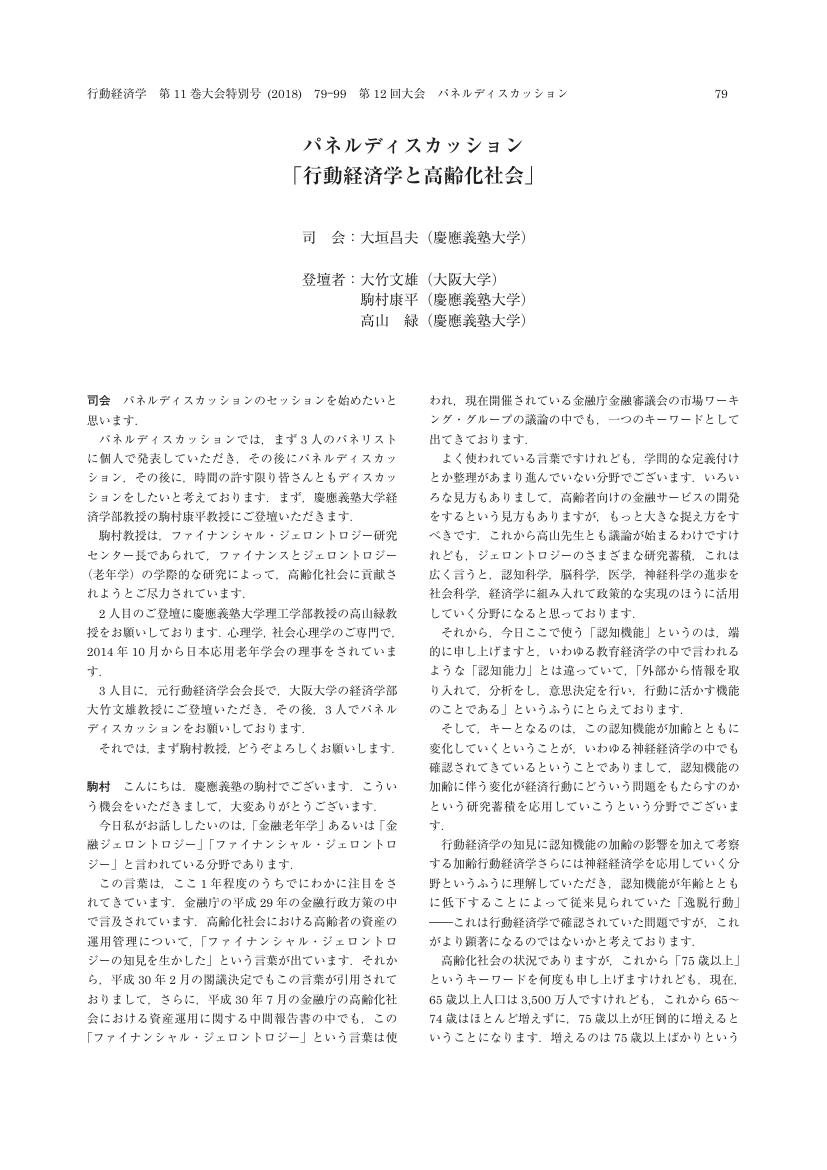4 0 0 0 OA 渋江抽斎没後の渋江家と帝国図書館
- 著者
- 藤元直樹
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.60, 2004-03-30
4 0 0 0 IR 幕末期肥後藩の中央政治参加への試み : 「独自」と「提携」の相克
- 著者
- 呉 永台
- 出版者
- 『年報 地域文化研究』編集委員会
- 雑誌
- 年報地域文化研究 (ISSN:13439103)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.47-71, 2014
4 0 0 0 OA ヒノキ科花粉症と咽喉頭症状
- 著者
- 荻原 仁美 湯田 厚司 宮本 由起子 北野 雅子 竹尾 哲 竹内 万彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.2, pp.78-83, 2011 (Released:2011-07-12)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3 3
背景と目的: スギ花粉症にヒノキ科花粉症の合併が多く, その原因として両花粉抗原の高い相同性が挙げられる. しかし実際の臨床の場において, ヒノキ科花粉飛散期にスギ花粉飛散期にはみられない強い咽喉頭症状のある例に遭遇する. そこで, ヒノキ科花粉症の咽喉頭症状について検討した.方法: スギ・ヒノキ科花粉症患者で2008年のスギ・ヒノキ花粉飛散期の咽喉頭症状を1週間単位のvisual analog scale (VAS) で検討した. また, 2008年と2009年に日本アレルギー性鼻炎標準QOL調査票No2で鼻眼以外の症状を調査し, 花粉飛散数による相違を検討した.結果: VASによる鼻症状は花粉飛散数に伴って悪化し, スギ花粉飛散期でヒノキ科花粉飛散期より強かった. 一方, のどの違和感と咳は, ヒノキ科花粉が少量飛散であったにもかかわらず, ヒノキ科花粉飛散期で悪化した. また日本アレルギー性鼻炎標準QOL調査票No2の鼻眼以外の症状において, スギ花粉症では飛散総数が多いと全般に症状が悪化したが, ヒノキ科花粉症は少量飛散でも強い咽喉頭症状を示し, 大量飛散年に類似した.結論: ヒノキ科花粉症はスギ花粉症と同一のように考えられているが,スギ花粉症とは異なる鼻眼以外の症状を呈する. 特にヒノキ科花粉症において咽喉頭症状が強く, 少量の飛散でも強い症状がある.
4 0 0 0 OA めっこ飯の生成条件およびそのメカニズム
- 著者
- 河東 ちひろ 香西 みどり 畑江 敬子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 59回大会(2007年)
- 巻号頁・発行日
- pp.305, 2007 (Released:2008-02-26)
[目的]炊飯途中の加熱中断や保温キーによる炊飯などにより「めっこ飯」といわれる炊き損じ飯が生じ、再炊飯しても通常の飯にならず食味が低下することが知られている。本研究ではめっこ飯の生成条件を明らかにし、そのメカニズムを解明することを目的とした。[方法]試料米は日本晴とした。90%とうせい米に加水比1.4で加水し、20℃で1h浸漬後、恒温水槽で浸漬処理(1~12h、20~90℃)した浸漬米とこれを炊飯した浸漬炊飯米について水分含量、外観観察(写真)、テクスチャーアナライザーによる米粒表層および全体の物性測定を行った。エタノール・アセトンで調製した脱水粉末試料を用いて糊化度(BAP法)、糊化特性(DSC)、FT-IR,1HNMR測定およびX線回折による結晶構造の比較を行った。浸漬米についてMRIにより吸水状態およびヨウ化カリウム染色後のでんぷんを観察した。浸漬炊飯米を50%エタノールで抽出した飯抽出液の全糖(フェノール硫酸法)、還元糖(ソモギネルソン法)を測定した。[結果]20℃1h浸漬のみの通常の飯に比べて65℃浸漬米は硬くなり、65,75,90℃の粘りは有意に低下し、いわゆるめっこ飯は65℃4hで明瞭にみられた。65、75、90℃で各4h浸漬した米の糊化度は25,83,93%であり、DSC測定では65℃浸漬米にのみ20℃浸漬より数℃高温側に糊化ピークがみられた。DSC,X線回折、NMR,MRI等の観察より、65浸漬米が硬いのは糊化不十分が関与し、65,75,90℃浸漬炊飯米の粘り低下には糊化度以外の原因が示唆された。飯抽出液分析から65℃浸漬処理ではデンプンの低分子化、75,90℃では浸漬液が米粒に吸収され、糖の溶出が起こらないことがそれぞれの浸漬炊飯米の粘り低下の原因と考えられた。
4 0 0 0 OA 臨床心理学における研究の動向と今後の課題 —実証的な研究をめざして—
- 著者
- 石川 健介
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.84-101, 2015 (Released:2015-08-25)
- 参考文献数
- 117
- 被引用文献数
- 1 1
本稿では,2013年7月から2014年6月までの1年間に,わが国で発表された「臨床心理学」に関する研究の動向を展望した。はじめに日本教育心理学会第56回総会の「臨床」部門に発表された論文を概観し,年齢区分ごとに特徴的なキーワードを挙げた。次に,6つの学術雑誌に掲載された「臨床心理学」に関する研究を概観した。この結果,心理的不適応/精神症状では,「抑うつ」に関連する研究が最も多く,「反すう」や「ストレス」,「バーンアウト」を扱った研究も同様に多かった。尺度開発を扱った研究は少なかった。介入プログラムや心理療法では,認知行動療法・行動分析・アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)が多く取り上げられていた。
4 0 0 0 OA メディア効果論の再検討
- 著者
- 有田 亘
- 雑誌
- 国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 = OIU journal of international studies (ISSN:09153586)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.57-67, 2021-03-31
This article re-examines the strong effects theory, a popular theory in mass media studies. First of all, there is the theory of bullet effect, typified by Cantril's research on Orson Welles' The Invasion from Mars. However, this has been questioned and controversy continues to this day. But in the first place, Cantril did not advocate bullet theory, nor was the Martian Riot intended by the radio station to panic people. Furthermore, the Martian invasion Riot itself was fake news. Some kinds of hoaxes and also demythologization spread readily according to the media effects theory. In this paper, an overview of this is given and it is suggested that it would be better to reposition the media effects theory, which has been conducted as part of Media Studies, into the category of rumor studies. In that sense, it is argued that it may be possible to reconsider it as message theory rather than media theory.
4 0 0 0 OA パネルディスカッション「行動経済学と高齢化社会」
4 0 0 0 OA 入門コーナー「フィンスタビライザー」・「可変ピッチプロペラ」
- 著者
- 木田 隆之
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.293, 2012-03-01 (Released:2013-10-30)
4 0 0 0 IR オリンピック東京大会沖縄聖火リレー-1960年代前半の沖縄における復帰志向をめぐって
- 著者
- 豊見山 和美 TOMIYAMA Kazumi 沖縄県文化振興会
- 出版者
- 沖縄県公文書館
- 雑誌
- 沖縄県公文書館研究紀要 = OKINAWA PREFECTURAL ARCHIVES BULLETIN OF STUDY (ISSN:13442155)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.27-36, 2007-03-28
4 0 0 0 OA チャバネゴキブリにおけるグルコース忌避の味覚受容メカニズム
- 著者
- 勝又 綾子 Jules Silverman Coby Schal
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.220-230, 2014-12-25 (Released:2015-01-19)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 4
チャバネゴキブリの駆除には糖で甘味づけした毒餌が用いられる。しかし毒餌によって急激な淘汰圧を受けた地域では, 毒餌を食べない個体群が出現する。私たちは, これらのゴキブリが摂食促進物質として毒餌に使われるグルコースを忌避することを示し, また, 強い淘汰圧下で出現した「グルコース忌避」という適応的食物選択行動が, 味受容細胞の感受性の変異によることを, 電気生理学的手法で明らかにした。グルコースを好む野生系統(WT型)は, 他の生物種と同様に, 口器にある甘味物質感受性の味受容細胞でグルコースを受容する。しかしグルコース忌避系統(GA型)では苦味物質を感受する味受容細胞がグルコース感受性を示す。つまりGA型のゴキブリは, グルコースを甘味ではなく苦味として判断していると考えられる。また, グルコースと誘導体を用いた構造活性相関試験によって, GA型の苦味受容細胞に発現している味覚受容体の構造が, グルコースと結合するように変異している可能性があることがわかった。急激な環境変化に伴い生物個体群が適応的食物選択行動を新しく出現させる時, 味受容細胞の感受性の遺伝多型が重要な役割を果たしていると考えられる。
4 0 0 0 OA 江崎貴裕(著)『データ分析のための数理モデル入門:本質を捉えた分析のために』(2020年,ソシム) 『分析者のためのデータ解釈学入門:データの本質を捉える技術』(2020年,ソシム)
- 著者
- 清水 裕士
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.119-120, 2022-03-31 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 1
4 0 0 0 OA 送配電網の費用負担と託送料金の仕組み : 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた制度改革
- 著者
- 山口聡
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.839, 2020-12
4 0 0 0 OA 「脱炭素」をめぐる動向と課題
- 著者
- 石渡裕子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 脱炭素社会の技術と諸課題 : 科学技術に関する調査プロジェクト報告書
- 巻号頁・発行日
- 2022-03
4 0 0 0 OA Sorafenib inhibits tumor cell growth and angiogenesis in canine transitional cell carcinoma
- 著者
- Shohei YOKOTA Tomohiro YONEZAWA Yasuyuki MOMOI Shingo MAEDA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-0478, (Released:2022-04-05)
- 被引用文献数
- 9
Canine transitional cell carcinoma (cTCC) is the most common naturally occurring bladder cancer and accounts for 1–2% of canine tumors. The prognosis is poor due to the high rate of invasiveness and metastasis at diagnosis. Sorafenib is a multi-kinase inhibitor that targets rapidly accelerated fibrosarcoma (RAF), vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR)-1, VEGFR-2, VEGFR-3, platelet-derived growth factor receptor-β (PDGFR-β), and KIT. In previous studies, a somatic mutation of B-rapidly accelerated fibrosarcoma (BRAF) and expressions of VEGFR-2 and PDGFR-β were observed in over 80% of patients with cTCC. Therefore, in this study, we investigated the anti-tumor effects of sorafenib on cTCC. Five cTCC cell lines were used in the in vitro experiments. All five cTCC cell lines expressed VEGFR-2 and PDGFR-β and sorafenib showed growth inhibitory effect on cTCC cell lines. Cell cycle arrest at the G0/G1 phase and subsequent apoptosis were observed following sorafenib treatment. In the in vivo experiments, cTCC (Sora) cells were subcutaneously injected into nude mice. Mice were orally administered with sorafenib (30 mg/kg daily) for 14 days. Sorafenib inhibited tumor growth compared to vehicle control. The necrotic area in the tumor tissues was increased in the sorafenib-treated group. Sorafenib also inhibited angiogenesis in the tumor microenvironment. Thus, sorafenib may be potential therapeutic agent for cTCC via its direct anti-tumor effect and inhibition of angiogenesis.
- 著者
- G. Michael Mallow Alexander Hornung Juan Nicolas Barajas Samuel S. Rudisill Howard S. An Dino Samartzis
- 出版者
- The Japanese Society for Spine Surgery and Related Research
- 雑誌
- Spine Surgery and Related Research (ISSN:2432261X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.93-98, 2022-03-27 (Released:2022-03-27)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 10
With the emergence of big data and more personalized approaches to spine care and predictive modeling, data science and deep analytics are taking center-stage. Although current techniques in machine learning and artificial intelligence have gained attention, their applications remain limited by their reliance on traditional analytic platforms. Quantum computing has the ability to circumvent such constraints by attending to the various complexities of big data while minimizing space and time dimensions within computational algorithms. In doing so, quantum computing may one day address research and clinical objectives that currently cannot be tackled. Understanding quantum computing and its potential to improve patient management and outcomes is therefore imperative to drive further advancements in the spine field for the next several decades.
4 0 0 0 OA 統合失調症患者の精神症状と自尊感情の関連性
- 著者
- 國方 弘子 豊田 志保 矢嶋 裕樹 沼本 健二 中嶋 和夫
- 出版者
- 日本保健科学学会
- 雑誌
- 日本保健科学学会誌 (ISSN:18800211)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.30-37, 2006-06-25 (Released:2017-10-27)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 5
本研究は,地域で生活する統合失調症患者を対象とし,精神症状が自尊感情を規定するのか,それとも自尊感情が精神症状を規定するのか,それら因果関係モデルのデータへの適合性を明らかにすることを目的とした。分析対象は,横断的研究には109名,縦断的研究には61名のデータを用いた。精神症状の測定には,信頼性と妥当性が支持された9項目版BPRSを用いた。横断的研究の結果,反応が低下した症状である「鈍麻・減退因子」が,自尊感情と有意な負の関連があった。縦断的研究の結果,1年後の追跡調査時点において9項目版で測定した精神症状は自尊感情に有意な負の効果を示し,時間的先行性を検証できたことから,精神症状が自尊感情に影響を及ぼすといった因果関係が示された。以上より,統合失調症患者の鈍麻・減退に伴う感情をサポートすることは,彼らの自尊感情を回復させることに繋がると示唆された。
4 0 0 0 IR コミュ二ティ放送とソーシャルワークとの相似点 : 社会的包摂の番組から見る機能と役割
4 0 0 0 OA がん患者の終末期医療に携わる医師の実存的苦痛(スピリチュアルペイン)とその構造
- 著者
- 的場 康徳 村田 久行 浅川 達人 森田 達也
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.321-329, 2020 (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
【目的】がん患者の終末期医療に携わる医師のスピリチュアルペイン(SPP)を明らかにする.【方法】医師の臨床体験レポートを記述現象学と3次元存在論で分析した.【結果】すべてのレポートで医師のSPPが抽出され,時間性,関係性,自律性に分類された.とくに医師の意識の志向性が,がん治療や症状緩和の限界や患者の訴えるSPPに対応できないことに向けられ,それが医師としての無力・無能として現れる自律性のSPPが大多数を占めた.自律性のSPPの体験の意味と本質は,[治療(キュア)の限界に直面している自己が無力として現れる][患者のSPPに対応できない自己が無力として現れる][自分を取り巻く外的な環境の問題(過重労働や教育の不備など)が原因で自己の無力が生じる]という三つの構造で示された.またキュアの限界で医師が患者に会いづらくなる,避けるという体験は医師の自律性のSPPへの対処(コーピング)の可能性が示唆された.
4 0 0 0 宝治二年院百首とその研究
4 0 0 0 OA 圧力鍋調理後のビタミン残存量と煮汁中へのアミノ酸溶出量
- 著者
- 尾立 純子 藤田 忠雄 神戸 保 大柴 恵一
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.267-273, 1980-09-25 (Released:2010-10-29)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 1
圧力鍋と常圧鍋を用いで炊く, 煮る, 蒸す調理をそれぞれ質玄米, 大豆, さつまいもで行い, 調理後のビタミン類の残存量とアミノ酸の煮汁中への溶出量を比較した。1. 玄米を炊いた場合のB1残存量は, 圧力鍋で56~64%常圧鍋で72%となり, 圧力鍋での損失量が約10%大きかった。2. 大豆を煮た場合のB1残存量は, 圧力鍋で65~70% (豆中57~60%, 煮汁中8~9%), 常圧鍋で51% (豆中50%, 煮汁中1%) となり, 圧力鍋での損失量が約15~20%少なかった。3. さつまいもを蒸した場合のB1とCの残存量は, でんぷんα化度約90%で比較すると, 圧力鍋でB1 73%, C54%, 常圧鍋で, B1, Cともに85%となり, 圧力鍋での損失量がB1で約10%, Cで約30%大きかった。4. 大豆調理時の煮汁中への窒素とアミノ酸の溶出量は圧力鍋で常圧鍋の約1.5倍大きかった。また溶出されやすいアミノ酸はトリプトファン, アルギニン, アラニン, グルタミン酸, セリンの順で, アミノ酸の溶出パターンは, 両鍋で差異はなかった。