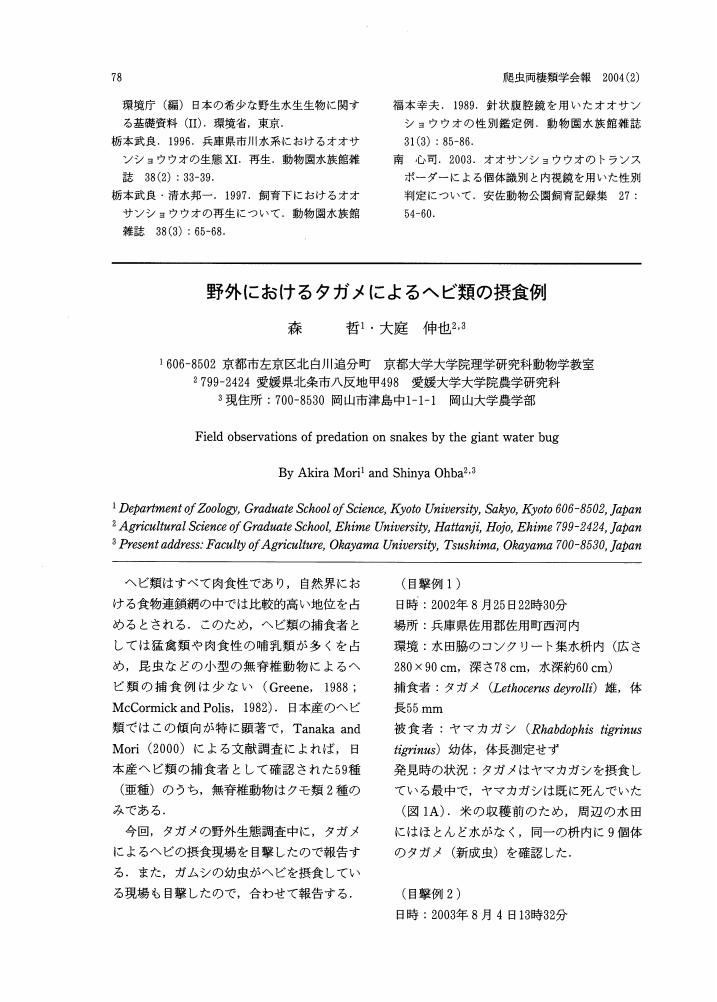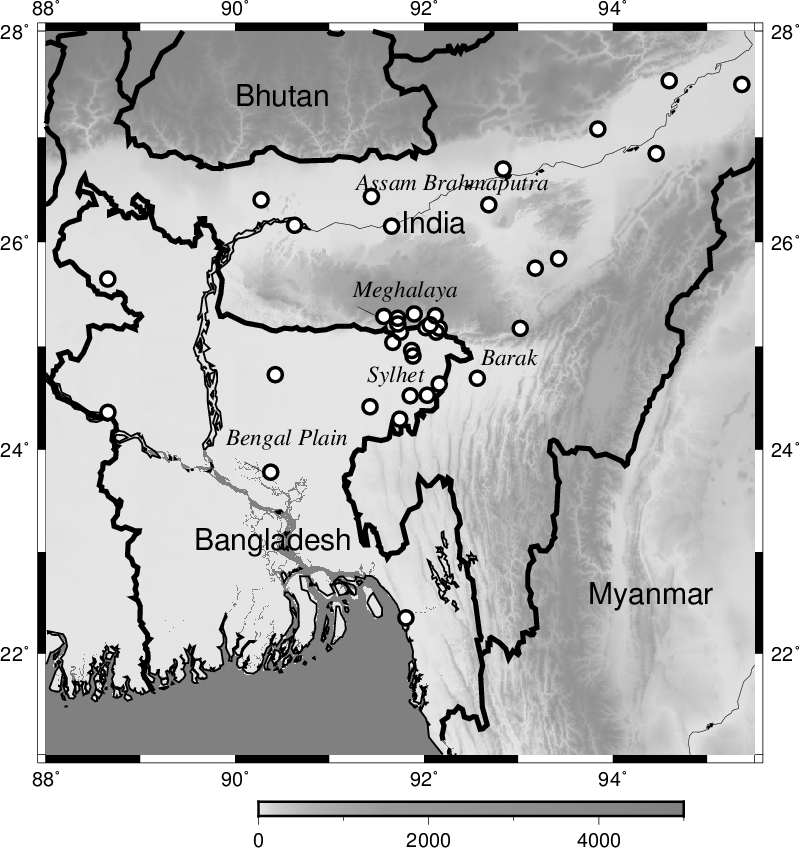- 著者
- 安部 達雄
- 出版者
- 成城大学共通教育研究センター
- 雑誌
- 成城大学共通教育論集 = The Seijo Kyoiku Ronshu (ISSN:18837085)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.127-181, 2017-03
3 0 0 0 OA 野外におけるタガメによるヘビ類の摂食例
- 著者
- 細谷 亨
- 出版者
- 立命館大学経済学会
- 雑誌
- 立命館経済学 = The Ritsumeikan economic review : the bi-monthky journal of Ritsumeikan University (ISSN:02880180)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.1054-1073, 2016-03
3 0 0 0 早坂一郎先生を悼む
- 著者
- 北村 信
- 出版者
- 日本地質学会
- 雑誌
- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.12, pp.829-830, 1977-12-15
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 英国法律全書
- 著者
- 貌刺屈斯的 (ウヰルリァム・ブラックストヲン) 著
- 出版者
- 袋屋亀次郎等
- 巻号頁・発行日
- vol.第1編 巻之1, 1878
- 著者
- 深水 圭 酒井 和子 甲斐田 裕介 大塚 紹 和田 芳文 杉 健三 奥田 誠也
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.367-374, 2014 (Released:2014-06-28)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
血液透析 (HD) 患者におけるカルニチン欠乏は, 貧血や低栄養を惹起しQOLを低下させる. 最近わが国において透析患者に対するL-カルニチン経口・静注治療が可能となり, その効果が期待されている. 今回, HD患者に対する6か月間のL-カルニチン900mg経口投与が貧血や栄養状態にいかに影響するかについて, さらに500mg, 1,000mg静注への切り替えによりカルニチン濃度がどのように推移するかについて観察した. 総カルニチン50μmol/L未満の102人のHD患者を単純無作為化によりコントロール群, L-カルニチン群に分け, 6か月後の時点で観察し得た患者を比較検討した. カルニチン投与群 (n=23) では, コントロール群 (n=24) と比較しすべてのカルニチン濃度は有意に上昇し (p<0.001), アシルカルニチン/遊離カルニチン (A/F) 比は低下した (p=0.006). コントロール群と比較しL-カルニチン群ではHt (p=0.02), 総コレステロール (p=0.002), 中性脂肪 (p=0.022) が上昇し, AST (p=0.008), ALT (p=0.013) は低下した. 経口900mgから静注1,000mg (n=8) への切り替えはHD前後, 静注10分後においてすべてのカルニチン濃度を上昇させたが, 500mg (n=6) への切り替えは経口投与と同等であった. 500mgと比較すると1,000mgへの切り替えはHD前後ともに遊離カルニチンを上昇させたが有意差は認めなかった. カルニチン欠乏HD患者に対するL-カルニチン900mg経口投与は貧血や栄養状態, 肝機能を改善しうる可能性を見出した. カルニチン濃度, 患者アドヒアランス, 医療経済効果, トリメチルアミン-Nオキシド産生等を考慮すると静注が推奨されるが, 今後はどちらの投与方法が透析患者に有用であるかを検証するための比較試験が必要である.
- 著者
- モリス J. F.
- 出版者
- 青木書店
- 雑誌
- 歴史学研究 (ISSN:03869237)
- 巻号頁・発行日
- no.948, pp.26-30, 2016-09
- 著者
- 末木 新
- 出版者
- 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.289-295, 2017-06
- 著者
- ヌーニェス=ガイタン アンヘラ 湯上 良
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要. アーカイブズ研究篇 = The bulletin of the National Institute of Japanese Literature. 人間文化研究機構国文学研究資料館 編 (ISSN:18802249)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.171-180, 2016-03
マレガ・プロジェクトは、多分野間の共同作業の模範的事例であり、閲覧のために長期保存を行うことを主な目的としている。まず、無酸素処理による殺菌を行い、次に各要素の構造を反映した整理番号を付し、調査票を記入する。日本の作業グループとの共同作業は、すべての基礎となるものである。修復作業は、文書全体のデジタル化の準備段階にあたり、取り扱い時の安全性と高画素撮影を保証する。日本の文書素材は、西洋のものとは異なるため、金山正子氏や青木睦氏によって、バチカン図書館の修復士向けの特別研修が行われた。これにより、新しい技術を学び、日本のアーカイブズ素材に対応できるようになった。このプロジェクトは、「歴史というものを自覚し、研究活動に配慮する教会は、真理を求めるすべての探究者たちとともに、過去の足跡と、時代を越えた保護活動によって受け継がれてきた宝物をともに分かち合う」という教皇レオ13世の考えを具現化しているのだ。Marega Project is an example and a model of interdisciplinary and joint venture between the Far East and the West without which it would have been difficult to tackle the conservation and study of the collection, such were the thought at the basis of the project.The first action was the disinfestation through anoxic treatment; for the next phase, compiling the inventory of the material, the weeks of collaborative work with the group of Japanese colleagues were fundamental.The conservation treatments are preliminary to the digitization phase of the entire collection, ensuring safe handling of the documents and high quality image capturing. Japanese material is rather different from western material, so it was necessary for the Vatican conservators to undergo specific training led competently by Masako Kanayama and Mutsumi Aoki. This training allowed us to get accustomed to materials and conservation techniques unusual and novel to us and we learned to recognize specifically significant elements of Japanese archive material.The Marega Project makes real and concrete the idea by Pope Leo XIII of "a Church aware of History, attentive towards research, ready to share with those who seek the Truth the vestiges of its past, and the treasures gathered through century-long attentions".
- 著者
- 大橋 幸泰
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要. アーカイブズ研究篇 = The bulletin of the National Institute of Japanese Literature. 人間文化研究機構国文学研究資料館 編 (ISSN:18802249)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.123-134, 2016-03
本稿では、日本へキリシタンが伝来した16世紀中期から、キリスト教の再布教が行われた19世紀中期までを対象に、日本におけるキリシタンの受容・禁制・潜伏の過程を概観する。そのうえで、どのようにしたら異文化の共生は可能か、という問いについて考えるためのヒントを得たい。キリシタンをめぐる当時の日本の動向は、異文化交流の一つと見ることができるから、異文化共生の条件について考える恰好の材料となるであろう。 16世紀中期に日本に伝来したキリシタンは、当時の日本人に幅広く受容されたが、既存秩序を維持しようとする勢力から反発も受けた。キリシタンは、戦国時代を統一した豊臣秀吉・徳川家康が目指す国家秩序とは相容れないものとみなされ、徹底的に排除された。そして、17世紀中後期までにキリシタン禁制を維持するための諸制度が整備されるとともに、江戸時代の宗教秩序が形成されていった。こうして成立した宗教秩序はもちろん、江戸時代の人びとの宗教活動を制約するものであったが、そうした秩序に制約されながらも、潜伏キリシタンは19世紀中期まで存続することができた。その制約された状況のなかでキリシタンを含む諸宗教は共生していたといえる。ただし、それには条件が必要であった。その条件とは、表向き諸宗教の境界の曖昧性が保たれていたことと、人びとの共通の属性が優先されたことである。This paper is an overview of the process of the acceptance, prohibition, and concealment of Christianity in Japan from the time it was first introduced in the mid-16th century until its re-introduction in the mid-19th century. In doing so, it is my hope that we can find some lessons for making the co-existence of different cultures possible. Happenings relating to Christianity in Japan at the time can be seen as a form of cultural exchange, and therefore will surely provide suitable material for considering the conditions for cultural coexistence.While the Christianity transmitted in the mid-16th century was widely accepted by Japanese at the time, it also was resisted by the forces that sought to maintain the existing order. Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu, who brought about unification after the Sengoku period, considered Christianity to be incompatible with the national order they sought, and they attempted to thoroughly eliminate it. Then, as various systems were developed to maintain the prohibition of Christianity through the latter 17th century, the religious order of the Edo period was formed. While this religious order was, of course, intended to restrict the religious activities of the people of the Edo period, hidden Christians were able to continue to exist up to the mid-19th century, even under its constraints. It could be said that various religions, including Christianity, coexisted under these constrained circumstances. However, there were necessary conditions for this, namely, the ambiguity of the boundaries between religions being preserved on the surface, and the attributes people share in common being prioritized.
3 0 0 0 OA 高度IT人材育成の軌跡:5.OJL :産学連携による新しい人材育成の試み
- 著者
- 馬部 隆弘
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 = Journal of Japanese history (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- no.642, pp.51-80, 2016-02
3 0 0 0 OA 佐河田昌俊の前半生について
- 著者
- 渡辺 憲司
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.1-10, 1979 (Released:2017-04-28)
3 0 0 0 OA 語(句)の商用化について―雑誌記事タイトルにみられる「話題」の場合を例に―
- 著者
- 大谷 鉄平
- 出版者
- 長崎外国語大学
- 雑誌
- 長崎外大論叢 = The Journal of Nagasaki University of Foreign Studies (ISSN:13464981)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.57-72, 2016-12-30
AbstractSome commonly used Japanese expressions exhibit what the author calls advertisement-like nuances. These expressions often leave an impression of exaggeration because they are used in such a way that they are expected to convey something more than their lexical meanings. These expressions have undergone a commercialization-process which gives them the functions of advertisement, exaggeration, and situation shift in the author’s terms. In this paper, the author attempts to describe the characteristics of these advertisement-like expressions through the analysis of the expression wadai, or “topic,” as they appear in the titles of magazine articles. For this purpose the magazine article database Web-OYA and the analysis tool KH Corder were used. The results of the analysis suggest that meanings resulting from commercialization are present in the use of the wadai- expression in the titles of magazine articles, although those new meanings are not necessarily expected to be added to the lexical meanings of the expression in the future.
3 0 0 0 OA アメリカにおける歴史的環境保全
- 著者
- 小幡 宣和
- 出版者
- Hokkaido University(北海道大学)
- 巻号頁・発行日
- 2013-12-25
103p.
3 0 0 0 IR 『出雲国風土記』とヤマタノヲロチ
- 著者
- 伊藤 剣
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- no.520, pp.1-27, 2016-09
3 0 0 0 OA 英領インド気象局日降水量データを活用したインド亜大陸北東部における降水特性変動の解析
- 著者
- 寺尾 徹 村田 文絵 山根 悠介 木口 雅司 福島 あずさ 田上 雅浩 林 泰一 松本 淳
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100300, 2017 (Released:2017-05-03)
1. はじめにインド亜大陸北東部は,陸上における世界的な豪雨域である。とりわけメガラヤ山脈南斜面には年降水量10000mmを大きく超える地域が広がり,世界の年間雨量極値(Cherrapunjee, 26,461mm, 1860年8月~1861年7月)を持つ(木口と沖, 2010)。この領域の降水は、アジアモンスーン循環を駆動する熱源であり、当該地域に住む人々の生活に本質的な影響を与えている。われわれの研究グループは、現地の観測網の充実による降水過程の解明、過去のデータを取得、活用することによる経験的な知見の集積を進めてきた。災害や農業、公衆衛生をはじめとしたさまざまな人間活動との関係を研究してきた。 2. 観測ネットワークわれわれの研究グループは、2004年以降,当該地域に雨量計ネットワークの展開を開始しており、2007年頃までに雨量計は40台に達し、現在まで維持管理している(図1)。自動気象観測装置も活用してきた。現地気象局等との協力関係を発展させ、過去の各気象局の持つデータの収集を進めてきた。 3. データレスキューインド亜大陸北東部のうち、英領インド東ベンガルおよびアッサムの一部は、1947年にパキスタン領となり、その後バングラデシュとして独立した。そのため、現インド気象局では降水量データのデジタル化がなされていない。バングラデシュ気象局もパキスタン独立以前のデータの管理をしていない。そのため、デジタルデータは1940年代以前が空白となっている。 英領インド気象局の観測は充実しており、バングラデシュでもっとも雨の多いSylhet域の降水観測点は、現バングラデシュ気象局の観測点の数倍ある。バングラデシュ最多雨地点とされるLalakhalには現気象局の観測地点がなく、旧いデータも保管されていない。 われわれの、データレスキューで得られた1891-1942年のSylhetとLalakhalの雨量データから、この二地点の当時の降水量の差を解析した結果、Lalakhalの方が30%近く月降水量が多いことが確かめられている。 当日は、われわれの研究成果を概観し、データレスキューの現状と、われわれの雨量計の観測データやリモートセンシングデータなどを活用した、初期的な解析結果をお示しする。 図1インド亜大陸北東部に設置した雨量計観測網。雨量計は○印で表されている。参考文献木口雅司・沖大幹 2010. 世界・日本における雨量極地記録. 水文・水資源学会誌 23: 231-247.
- 著者
- 平山 るみ 田中 優子 河崎 美保 楠見 孝
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.441-448, 2010
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
本研究では,批判的思考を支える能力を測定するための尺度としてコーネル批判的思考テスト・レベルZ(ENNIS et al.1985)を用いて,日本語版批判的思考能力尺度を構成した.まず,コーネル批判的思考テスト(ENNIS et al.1985)を日本語に翻訳し,その内的整合性および難易度を検討した.さらに,批判的思考態度尺度,および認知能力としての知能を測定する京大SXとの関係性を検討した.大学生43名に対し,批判的思考能力尺度,批判的思考態度尺度,認知能力尺度を実施した.そして,批判的思考能力尺度について検討した結果,尺度の内的整合性が得られ,課題の難易度は適切であることが確認された.また,批判的思考能力尺度得点と言語性の認知能力尺度得点との間には正の相関がみられ,この尺度には言語能力が関わることが示された.そして,批判的思考能力尺度と情意的側面を測定する批判的思考態度尺度とは,関係性がみられず,それぞれ独立した尺度であることが示された.
3 0 0 0 IR ゲーム音楽と音楽ゲーム : 聴覚ゲームの音楽性事例
- 著者
- 北岡 一道
- 出版者
- 仁愛女子短期大学
- 雑誌
- 仁愛女子短期大学研究紀要 (ISSN:09138587)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.79-85, 2012-03
3 0 0 0 OA 調練足並略圖
- 巻号頁・発行日
- 1800