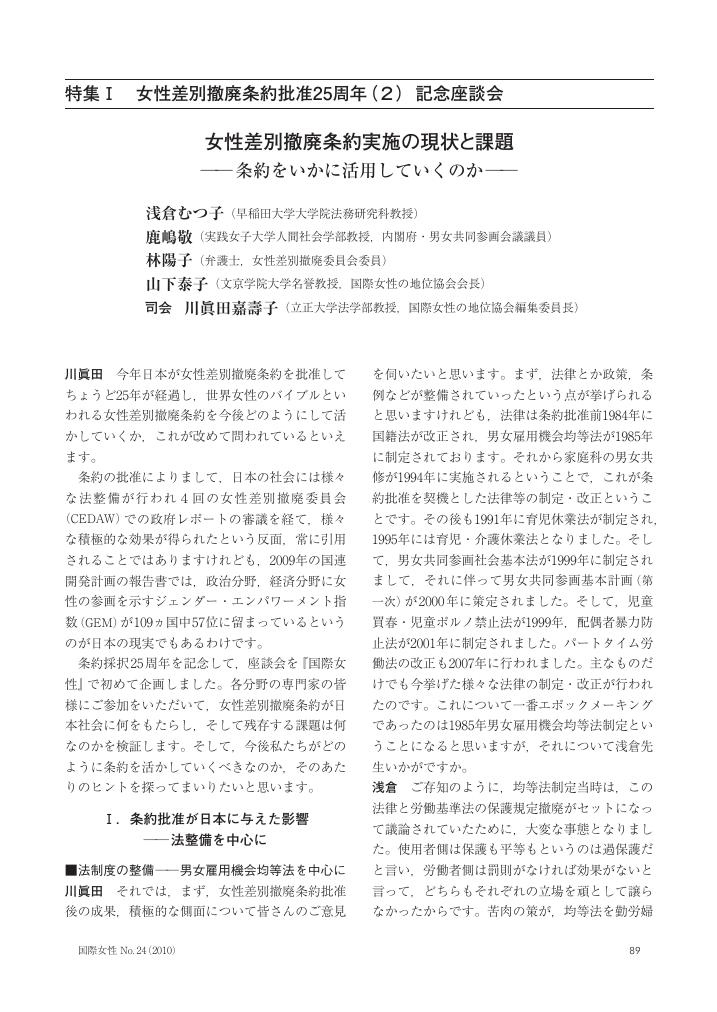2 0 0 0 心肺蘇生に対する水素ガス吸入の効果
水素ガスが細胞毒性の高い活性酸素種であるヒロドキシルラジカルを選択的に消去し、虚血再灌流障害を抑制することが確認され、ラットの中大脳動脈閉塞による局所脳虚血再灌流モデルにおいては、2%の水素ガス吸入が脳梗塞の範囲を縮小し、神経学的予後を改善させることが報告されている。水素ガス吸入が心肺停止からの救命率の向上、および蘇生後脳症の発症の予防に有効かどうかを確認するために、ミニブタを用いた心肺停止モデルを作成し、水素ガス吸入が救命率向上および神経学的予後改善に寄与するかどうか検討を行った。気管挿管による全身麻酔下に心室細動による3分間の心肺停止を行い、1) 水素吸入群は除細動による蘇生開始後より100%酸素ガスに2%水素ガスを混合したガスを1時間吸入、2) 対照群は除細動による蘇生開始後より100%酸素ガスを1時間吸入した。水素吸入群と対照群において3分間の心室細動後の自己心拍回復率および蘇生後の血行動態に差を認めなかった。また、蘇生後の神経学的予後改善に水素吸入が影響を与えるかどうかは検討できなかった。幾つかの論文では水素ガス吸入による虚血再灌流後の臓器保護効果を認めているが、我々のミニブタを用いた心肺停止モデルにおいては、水素ガス吸入による救命率の向上は確認できなかった。また、水素ガス吸入による蘇生後の脳神経保護効果は検討できなかった。今後、心肺停止時間の異なるミニブタモデルを作成し、水素吸入が心肺停止からの救命率向上に貢献するか、また、蘇生後脳症を軽減させるかどうかさらに検討を重ねていきたい。
- 著者
- Fuminari Asada Takuo Nomura Kenichiro Takano Masashi Kubota Motoki Iwasaki Takayuki Oka Ko Matsudaira
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- Environmental Health and Preventive Medicine (ISSN:1342078X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.36, 2023 (Released:2023-06-15)
- 参考文献数
- 43
Background: We designed a quick simple exercise program that can be performed in a short period of time in real-world occupational health settings and investigated the effects of three months of program implementation on non-specific low back pain (NSLBP).Methods: Participants were 136 individuals working in the manufacturing industry. The quick simple exercise program was designed to be doable in three minutes and consisted of two exercises: a hamstring stretch and a lumbar spine rotation with forward, backward, and lateral flexion. This was a randomized controlled trial incorporating an intervention group to whom the exercises were recommended within a leaflet, and a control group to whom the exercises were not recommended. NSLBP was evaluated at baseline and after three months using numerical rating scale (NRS) scores, ranging from 0 points (no pain at all) to 10 points (worst pain imaginable). The percentages of cases that improved by a minimal clinically important difference (two points or above) were compared.Results: Overall, 76.1% of the intervention group participants performed the quick simple exercises at least once every one or two days. Three months after baseline, a significantly higher percentage of participants in the intervention group (17 participants: 25%) had NSLBP improvement of two or more points on the NRS compared to that in the control group (8 participants, 12%) (P = 0.047). The average NRS score decreased significantly from 1.87 ± 1.86 to 1.33 ± 1.60 in the intervention group but showed no significant change in the control group, transitioning from 1.46 ± 1.73 to 1.52 ± 1.83. A significant interaction was also observed between the intervention and control groups (F = 6.550, P = 0.012).Conclusions: Three months of a quick simple exercise program among workers in the manufacturing industry increased the percentage of workers with improvement in the NRS scores. This suggests that the program is effective in managing NSLBP in workers in the manufacturing industry.Trial registration: UMIN-CTR UMIN000024117.
2 0 0 0 OA 人年法の計算と利用方法
- 著者
- 青木 伸雄
- 出版者
- 社団法人 日本循環器管理研究協議会
- 雑誌
- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.64-66, 1991-04-30 (Released:2009-10-15)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 宇野木 洋
- 出版者
- 日本現代中国学会
- 雑誌
- 現代中国 (ISSN:04352114)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.96, pp.64-66, 2022 (Released:2023-06-21)
- 著者
- Tohru MATSUURA Yoshiaki HISHIMOTO Shozo SHIMAZAKI Masakazu OCHIAI Toshiaki KIRIYAMA Naoto ENDO Takashi HACHIYA Susumu ICHINOSE Toshitami SAWAYAMA Tsuguo SHIKATA Isao NIKI Susumu MARUMOTO
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- Japanese Heart Journal (ISSN:00214868)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.247-257, 1968 (Released:2008-12-09)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
The thyroid murmur was analyzed in respect to the various characteristics of the murmur per se, the changing aspects in the diseased state as well as the process of the therapy, and finally the pathogenesis by angiography and cast preparations of the thyroid.1. The thyroid murmur was recorded in 37 out of 39 cases of hyperthyroidism and it was often continuous murmur with systolic accentuation. The murmur was best recorded at the isthmus of the gland, and the murmur over the right lobe was significantly louder in many cases. The reason of this localization was discussed, based on the anatomy of the vessels.2. The intensity and duration of the murmur were well correlated with the severity of the signs and symptoms in the individual case. Thus it is concluded that the routine phonography of the thyroid gland has an important diagnostic value in the assessment of the diseased state as well as the objective judgement of the treatment.3. Investigated by the angiography and cast preparations, the most probable origin of the thyroid murmur was mainly in the region of the arterio-venous and arterio-arterial anastomoses. The accessory importance of the other conditions, such as hyperkinetic state and the compression of the artery by the congestion of the gland, was also discussed.
2 0 0 0 OA 文章構成指導の固定化とその形成過程―「はじめ・なか・おわり」の出現と要因―
- 著者
- 都筑 航
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 143 (ISSN:24321753)
- 巻号頁・発行日
- pp.115-118, 2022-10-15 (Released:2022-12-29)
2 0 0 0 OA 軍隊に随伴する文民の武力紛争法上の地位
- 著者
- 岩田 健司
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.115-136, 2006-03-31 (Released:2022-04-24)
2 0 0 0 IR 近世初期の北野社と南光坊天海-松梅院と宮仕の座配争論を中心に-
- 著者
- 中川 仁喜
- 出版者
- 大正大学
- 雑誌
- 大正大学大学院研究論集 = Journal of the Graduate School, Taisho University (ISSN:03857816)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.113-123, 2009
- 著者
- JUNICHI AZUMA AKIHIKO SAWAMURA NOBUHISA AWATA
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- JAPANESE CIRCULATION JOURNAL (ISSN:00471828)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.95-99, 1992-01-20 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 95 116
We compared the effect of oral administration of taurine (3g/day) and coenzyme Q10 (CoQ<>) (30 mg/day) in 17 patients with congestive heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy, whose ejection fraction assessed by echocardiography was less than 50%. The changes in echo-cardiographic parameters produced by 6 weeks of treatment were evaluated in a double-blind fashion. In the taurine-treated group significant treatment effect was observed on systolic left ventricular function after 6 weeks. Such an effect was not observed in the CoQ10-treated group.
2 0 0 0 OA 女性差別撤廃条約実施の現状と課題 ── 条約をいかに活用していくのか──
- 著者
- 司会 川眞田嘉壽子
- 出版者
- 国際女性の地位協会
- 雑誌
- 国際女性 (ISSN:0916393X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.89-111, 2010 (Released:2013-03-01)
- 著者
- 熊倉 和歌子
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.214-218, 2018-03-31 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 小松 香織
- 出版者
- 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター
- 雑誌
- イスラーム世界研究 (ISSN:18818323)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.252-254, 2019-03-25
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1918年02月13日, 1918-02-13
2 0 0 0 OA 財宝に触発される記憶と希望 フィリピンにおける「山下財宝伝説」の語りから
- 著者
- 師田 史子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第57回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.F01, 2023 (Released:2023-06-19)
本発表は、フィリピンにおける財宝伝説「山下財宝」の語りや宝探しの実践を通じて、不確実な存在が確実な存在として立ち現れていく様相を明らかにする。財宝譚を語ることで人びとは、戦時中の略奪された記憶を基層としながら、自らの生活世界に隠れる富のイメージを精緻化している。今は掴めずともいつか掴みうる潜在的な財として財宝の存在が据え置かれることに、財宝伝説が社会に残存し続ける現代的な意味が見出せる。
2 0 0 0 OA 応用哲学は学ぶものか?: 「応用哲学を学ぶ人のために」 - 「これが応用哲学だ!」
- 著者
- 村上 祐子
- 出版者
- The Philosophy of Science Society, Japan
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.69-76, 2012 (Released:2016-01-13)
2 0 0 0 OA 深呼吸方式の違いによる換気量の変化 ―シルベスター法と深呼吸の比較―
- 著者
- 湯口 聡 森沢 知之 福田 真人 指方 梢 増田 幸泰 鈴木 あかね 合田 尚弘 佐々木 秀明 金子 純一朗 丸山 仁司 樋渡 正夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.D0672, 2005 (Released:2005-04-27)
【目的】 開胸・開腹術後患者に対して呼吸合併症予防・早期離床を目的に、呼吸理学療法・運動療法が行われている。その中で、ベッド上で簡易に実施可能なシルベスター法を当院では用いている。シルベスター法は両手を組み、肩関節屈伸運動と深呼吸を行う方法で、上肢挙上で吸気、下降で呼気をすることで大きな換気量が得られるとされている。しかし、シルベスター法の換気量を定量的に報告したものはない。よって、本研究はシルベスター法の換気量を測定し、安静呼吸、深呼吸と比較・検討することである。【方法】 対象は呼吸器疾患の既往のない成人男性21名で、平均身長、体重、年齢はそれぞれ171.0±5.2cm、65.3±5.6kg、24.9±4.0歳である。被験者は、安静呼吸・シルベスター法・安静呼吸・深呼吸・安静呼吸または、安静呼吸・深呼吸・安静呼吸・シルベスター法・安静呼吸のどちらか一方をランダムに選択した(各呼吸時間3分、計15分)。測定姿位は全てベッド上背臥位とし、呼気ガス分析装置(COSMED社製K4b2)を用いて、安静呼吸・シルベスター法・深呼吸中の呼吸数、1回換気量を測定した。測定条件は、シルベスター法では両上肢挙上は被験者が限界を感じるところまでとし、どの呼吸においても呼吸数・呼吸様式(口・鼻呼吸)は被験者に任せた。統計的分析法は一元配置分散分析および多重比較検定(Tukey法)を用い、安静呼吸、シルベスター法、深呼吸の3分間の呼吸数、1回換気量の平均値を比較した。【結果】 呼吸数の平均は、安静呼吸13.02±3.08回、シルベスター法5.26±1.37回、深呼吸6.18±1.62回であった。1回換気量の平均は安静呼吸0.66±0.21L、シルベスター法3.07±0.83L、深呼吸2.28±0.8Lであった。呼吸数は、分散分析で主効果を認め(p<0.01)、多重比較検定にて安静呼吸・シルベスター法と安静呼吸・深呼吸との間に有意差(p<0.01)を認めたが、シルベスター法・深呼吸との間に有意差は認めなかった。1回換気量は、分散分析で主効果を認め(p<0.01)、多重比較検定にて安静呼吸・シルベスター法・深呼吸のいずれにも有意差を認めた(p<0.01)。【考察】 シルベスター法は深呼吸に比べ1回換気量が高値を示した。これは、上肢挙上に伴う体幹伸展・胸郭拡張がシルベスター法の方が深呼吸より大きくなり、1回換気量が増加したものと考えられる。開胸・開腹術後患者は、術創部の疼痛により呼吸に伴う胸郭拡張が制限されやすい。それにより、呼吸補助筋を利用して呼吸数を増加させ、非効率的な呼吸に陥りやすい。今回、健常者を対象に測定した結果、シルベスター法は胸郭拡張性を促し、1回換気量の増加が図れたことから、開胸・開腹術後患者に対して有効である可能性が示唆された。
- 著者
- 陳 徴 砂長谷 由香
- 出版者
- 服飾文化学会
- 雑誌
- 服飾学研究 (ISSN:24344443)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.23-31, 2023-02-28 (Released:2023-06-20)
2 0 0 0 OA 完新世後期海面変動と湾口砂嘴・波食棚・古環境との関係 ―千葉県坂川低地の例―
- 著者
- 下総台地研究グループ
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.359-373, 1999-09-25 (Released:2017-07-14)
東京低地の北東部に位置する坂川低地では,縄文海進によって古奥東京湾の溺れ谷の1つである古流山湾が成立し,その周辺部に典型的な砂嘴・波食棚が発達する.古流山湾において,湾口部の砂嘴構成層や湾内の沖積層中に,標高+2.5mの侵食面が確認された.^<14>C年代および珪藻化石・貝化石の解析から,完新世後半の海面変動には,この侵食面の形成期(縄文中期の海退期)をはさんで2つの高海面期が見い出され,それぞれ古い方から第1高海面期(約5,800y.B.P.),第2高海面期(約4,000y.B.P.)とした.ボーリング資料の解析から,下総台地の縁辺には下総層群の団結泥岩からなる標高0〜+3mの埋没平坦面が広く分布することが示された.この埋没平坦面は,第1高海面期から形成が始まった波食棚で,湾内に分布するものは縄文中期まで,湾外のものは第2高海面期までその形成が続いた.一方,湾口部の砂嘴は,その内部構造や貝化石の解析から,第2高海面期に南東へ向かう沿岸流によって成長を始め,約600年で湾口を封鎖したことがわかった.
2 0 0 0 OA 運動イメージの臨床応用 F波を用いた検討からわかること
- 著者
- 福本 悠樹 東藤 真理奈 松原 広幸
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.56-62, 2019 (Released:2019-12-26)
- 参考文献数
- 22
This study examined the motor imagery effect using F-waves in order to verify a report that performance and body function were improved by motor imagery. To improve motor accuracy, motor practice for 30 seconds or 1 minutes before motor imagery was important. For the assumed scenarios in activities of daily living, motor imagery of compound movements must include the shoulder, elbow, wrist, and finger. Under these circumstances, it is desirable to set the task difficulty according to individual motor imagery ability. In the future, thorough investigation of F-wave forms will be necessary for the interpretation of the excitability of the spinal neural function during motor imagery.
2 0 0 0 OA 貝類雜記 (5)
- 著者
- 瀧 巖
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- ヴヰナス (ISSN:24329975)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.6, pp.346-358, 1933-02-28 (Released:2018-01-31)