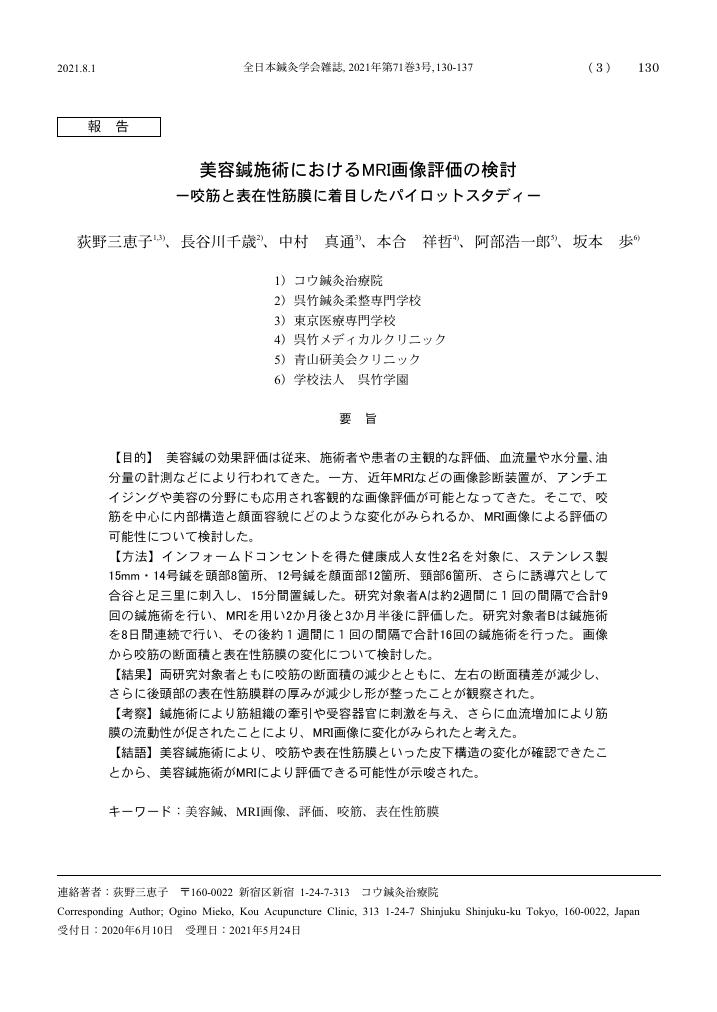2 0 0 0 OA 左向きの物体画像は右向きの物体画像よりも好まれる
- 著者
- 水原 啓太 柴田 春香 入戸野 宏
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第18回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.87, 2021-03-15 (Released:2021-03-15)
左右対称な物体において,正面から見た画像よりも,斜めを向いた画像のほうが好まれる (Nonose et al., 2016)。斜め向きの画像は,物体についての多くの情報を表すため,見た目が良く感じられると考えられている。本研究は,左右対称な物体の画像において,物体の左右の向きが物体の選好に与える影響について検討することを目的とした。オンライン実験で,左右の向きのみが異なる日常物体100個の画像を対提示し,見た目が良いほうの画像を強制選択してもらった。画像は物体が正面を向いた状態から,鉛直軸に関して左右のどちらかに30°回転した画像と,それを左右反転した画像であった。その結果,左向きの物体を選好する割合は平均61.2%であり,有意に偏っていた。物体ごとに検討しても左向きよりも右向きのほうが有意に好まれた物体はなかった。この結果について,物体の操作可能性や左方光源優位性の観点から考察した。
2 0 0 0 OA 日本人大学生における異文化理解の現状
- 著者
- 沼田 潤
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.55-63, 2012 (Released:2013-01-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
The purpose of the present research was to examine the present state of Japanese university students' intercultural understanding in order to obtain some implications for intercultural education in university. The results revealed the present state of Japanese university students' intercultural understanding was not monolithic. On the one hand, some attached importance to intercultural understanding, on the other hand, others slighted or resisted intercultural understanding. Moreover, it was clarified that there were differences on understanding toward social minorities and stereotypic understanding between female and male university students. Based on these results, future direction and tasks on intercultural education in university were investigated.
2 0 0 0 OA 幼児による嘘と真実の概念理解と嘘をつく行為
- 著者
- 上宮 愛 仲 真紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.393-405, 2009-12-10 (Released:2017-07-27)
子どもの証言能力の査定では,嘘と真実の理解や,意図的に嘘をつけるかどうかが重要な問題となる。従来,幼児による嘘と真実の理解は,嘘と真実を概念的に弁別させる,定義させる,同定させる,実際に嘘をつかせるなど,様々な課題を用いて研究されてきた。しかしこれらの課題間の関係は必ずしも明らかではなく,嘘と真実に関するどのような理解が実際に嘘をつく行為と関わっているのかは明確でない。本研究では,様々な課題を用いて嘘と真実の理解を調べるとともに,これらの課題と嘘の産出との関係を調べた。年少,年中,年長児(3-6歳)73名が,人形が嘘をついているか,真実を話しているかの判断する同定課題(1),嘘と真実の違いについて説明する弁別課題(2),嘘と真実の定義をする定義・善悪判断課題(3),話者の信念と嘘との関係を調べる嘘の基準を明確化する課題(4),適切な嘘をつけるかどうかを検討する行動課題(5)を行った。その結果,年少児に比べ,年中,年長児は嘘と真実の善悪判断や同定を正しく行うことができた。また,年長児では嘘か否かの判断には信念が関わっていることの理解が可能になり始めることが示された。行動課題では,年少児は意図的に相手を騙すことができるような嘘をつくことは難しいが,年中,年長ではそれが可能になる。また,嘘をつく能力は,"信念の理解"によって一部予測できる可能性が示唆された。
2 0 0 0 OA 自民党の組織構造と首相の権力
- 著者
- 高安 健将
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.35-48, 2014 (Released:2018-02-02)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
首相の権力は議院内閣制下において何によって規定されるのであろうか。戦後日本の首相については,首相のもつ公的権力資源,官僚制の強さ,国会議員を選出する選挙制度,政権党の執行部がもつ権力資源などさまざまな要因が指摘されてきた。これに対し,本稿は,首相に対する政権党の拘束力に注目する。本稿は,プリンシパル・エージェント・モデルを援用し,特にプリンシパルとしての政権党という視座に焦点を当てる。プリンシパルとしての政権党は複数のメンバーから構成されており,意見集約の困難さを意味する「複数のプリンシパル問題」を抱えている。この問題の本質は集合行為問題である。集合行為問題を克服できる政権党は首相を強く拘束でき,克服できない政権党は首相を拘束することができない。政権党が集合行為問題を克服できるか否かはその政党の組織構造次第である。本稿は,自民党政権下の首相の権力の変化を,集合行為問題に着目しつつ,結党から今日に至るまでの自民党組織の変遷を通して考察する。
- 著者
- Yuri Murayama Ken Inoue Chiho Yamazaki Satomi Kameo Minato Nakazawa Hiroshi Koyama
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.249, no.2, pp.101-111, 2019 (Released:2019-10-22)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 6
For the prevention of suicides, the early detection of depression symptoms and the implementation of suicide prevention measures based on the local community’s conditions are critical. In rural or remote communities with poor access to urban areas, the medical care is often insufficient. We conducted the present study to investigate the relationship between depressive state and social-environmental factors in a depopulated inland rural area in central Japan, where the suicide rate is high and specialized psychiatric care is not available. Using a correspondence analysis, logistic regression analysis, and structural equation modeling (SEM), we examined the questionnaire responses of 912 residents (average 60.5 years old). Total Health Index-Depression (THI-D) scale scores were used to measure depressive state. The lifestyle-related factor with the strongest link to depressive state was ‘concerns about interpersonal relationships’ (OR = 2.7, 95% CI: 2.06-3.53, p < 0.0001), whereas financial concerns, number of friends, exercise habits, and perceived amount of sleep were also useful for predicting depressive state. The SEM showed that one’s job and private life, particularly concerns about interpersonal relationships, are correlated with higher THI-D scores. Thus, social and lifestyle factors (e.g., concerns about interpersonal relationships and financial situation) can be used to predict depressive state in a depopulated rural area, and the newly revealed order in which depressive symptoms manifest is important. Our findings can be used to advance assessments of depressive symptoms and will be useful for mental health and suicide prevention.
2 0 0 0 OA ベニテングタケの保存及び加工処理過程におけるイボテン酸とムシモールの消長
- 著者
- 角田 光淳 井上 典子 青柳 康夫 菅原 龍幸
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.153-160_1, 1993-04-05 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4 4
ベニテングタケによる食中毒防止の観点から, 言い伝えられている保存法や調理加工法に準じてイボテン酸 (IBO) 及びムシモール (MUS) の消長を調べた. IBOは容易に脱炭酸されてMUSになり, それが幻覚を引き起こすことが知られている. 本研究の結果, 1) 乾燥するとIBOは減少するがMUSが増加し, MUSによる生理作用は強まるものと思われる. 2) 乾燥保存中のIBO及びMUSは安定で, また短期塩漬保存では両者の変動はわずかで, その生理活性を失うことはないと思われる. 3) 10分程度の加熱調理では, 両者の変動はわずかで, 無毒化を期待することはできない. 4) 湯がきや水さらしにより, 両者の含量は大きく減少したが, 実際には個体差, 喫食量及び他成分の影響等を考えるとこれらの処理は推奨される調理方法とはいえない.
- 著者
- 長谷川 敦大 門脇 耕三
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.804, pp.446-456, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 24
The situation related to building production in Japan is becoming increasingly complex from both social and urban perspectives. House-builders are finding it difficult to cope with these circumstances due to the system’s closed nature. Therefore, We made the purpose of this study to identify the problems that building systems deal with irregular customize. As a case study, we focused on a project with irregular customization. We conducted a textual analysis of design meeting transcripts to examine user participation in decision-making during the design process. The results showed the possibility of reconstructing the relationship between decision-making entities in the OPENBUILDIN theory.
- 著者
- Shunta Sato Wataru Sasaki Tomoyuki Sekino Tatsuhiko Yoshino Masahiro Kojima Shigeki Matsunaga
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.79-82, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 37
Metallaphotoredox-catalyzed allylation represents an emerging synthetic methodology that enables allylic substitution using nucleophilic radical species. The C–H allylation of N-aryl tetrahydroisoquinolines is an innovative example in this area and allows access to synthetically useful precursors for the further derivatization of tetrahydroisoquinolines. However, previous methods have required the use of noble metals, which has hampered their application due to concerns over their sustainability. Here we report the C–H allylation of N-aryl tetrahydroisoquinolines using a cobalt/organophotoredox dual catalyst system. Based on precedent, control experiments and controlled irradiation experiments, a mechanism for the cobalt/photoredox-catalyzed allylation that involves a π-allyl cobalt complex is proposed.
2 0 0 0 OA 『寶劍記』と『水滸傳』 : 林冲物語の成立について
- 著者
- 小松 謙 Ken KOMATSU
- 雑誌
- 京都府立大学学術報告. 人文 = The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Humanities (ISSN:18841732)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.1-16, 2010-12-01
2 0 0 0 OA 尖閣諸島に関する中国史料の研究(四) 古地図リサーチを中心に
- 著者
- 班 偉
- 出版者
- 学校法人山陽学園 山陽学園大学・山陽学園短期大学
- 雑誌
- 山陽論叢 (ISSN:13410350)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.67-82, 2021 (Released:2021-09-11)
2 0 0 0 OA 対話としてのケア : ハイデガーにおけるケア論の可能性とその展望
- 著者
- 黒岡 佳柾
- 出版者
- 立命館大学人文科学研究所
- 雑誌
- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, pp.125-150, 2021-11
2 0 0 0 OA 石けんおよびペーパータオルの設置と排泄後の手洗い行動に関する調査研究
- 著者
- 佐竹 幸子 小林 冴葉 西川 直子 猫平 千夏
- 出版者
- Japanese Society of Environmental Infections
- 雑誌
- 環境感染 (ISSN:09183337)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.124-128, 2005-06-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 8
トイレの手洗い設備に石けんとペーパータオルが設置されていない環境と設置されている環境で, 看護学生の排泄後の手洗い行動に関する観察調査を実施した. その結果, 石けんとペーパータオルの設置により平均手洗い時間が2.7秒 (n=38) から8.1秒 (n=35) と長くなり (p<0.001), 手拭き率も13% (5名/38名) から71% (25名/35名) に上昇した (p<0.001). これらの結果から, 石けんとペーパータオルの設置は手洗いの質向上に効果があったと考える. 排泄後の手洗いに関する看護学生の意識を知るためにアンケート調査を行った結果, 83% (63名/76名) が石けん使用の必要性を認めており, 41% (31名/76名) が実際に石けんを使用すると回答した. しかし, 観察調査で実際に石けんを使用したのは31% (11名/35名) であった. また, 手洗い後に髪に触れる動作が多く観察され (34%) (12名/35名), アンケート調査で50% (38名/76名) が手洗い後に髪に触ると回答した. 手洗い行動について看護学生の注意を喚起するために, この観察結果とアンケート調査結果を看護学生に報告した.
2 0 0 0 OA AIと代謝工学を組み合わせ生産株開発を加速
- 著者
- 国立研究開発法人科学技術振興機構
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- JSTnews (ISSN:13496085)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.2023.1, pp.10-11, 2023-01-04 (Released:2023-01-31)
藻類による物質生産では、光の自己遮蔽効果による細胞密度の頭打ちと、光エネルギーを物質生産に集中できないことが実用化の妨げとなっていた。神戸大学先端バイオ工学研究センターの蓮沼誠久教授はこの課題解決に際し、二酸化炭素(CO2)吸収と代謝を維持したまま細胞分裂を停止させる細胞増殖制御因子を発見した。さらに、AIと代謝工学を組み合わせることで物質生産株の開発を加速するとともに、実験操作のオートメーション化にも取り組んでいる。
2 0 0 0 OA 鍼灸治療によるヒップアップの効果
- 著者
- 中村 真理 坂口 俊二
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.2-9, 2018 (Released:2019-05-13)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 美容鍼施術におけるMRI画像評価の検討 ー咬筋と表在性筋膜に着目したパイロットスタディー
- 著者
- 荻野 三恵子 長谷川 千歳 中村 真通 本合 祥哲 阿部 浩一郎 坂本 歩
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.130-137, 2021 (Released:2021-12-01)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA 婚姻の破綻と婚姻費用分担義務――最高裁平成17年6月9日決定を契機として――
- 著者
- 黒田 樹里
- 出版者
- 国士舘大学法学会
- 雑誌
- 国士舘大学大学院法学研究科国士舘法研論集
- 巻号頁・発行日
- vol.9, 2008
2 0 0 0 OA 分子シャペロンHSP90をターゲットとする抗癌薬の開発と作用機序
- 著者
- 宮田 愛彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.1, pp.33-42, 2003 (Released:2003-01-28)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 7 9
HSP90は主要な細胞内分子シャペロンの一つであり,細胞ストレス状況下で発現量が増大するが,通常でも細胞質にもっとも多く存在するタンパク質の一つである.HSP90は様々な細胞内タンパク質と相互作用してその正確なフォルディングと機能を保証する役割を持つ.HSP90と相互作用するクライアントタンパク質にはプロテインキナーゼやステロイドホルモン受容体等の細胞増殖や分化に重要な役割を果たすシグナル伝達分子が多く含まれる.HSP90はCdc37やFKBP52といった他の分子シャペロンと協調しながら,クライアントタンパク質が正しくシグナルに応答して機能する為に必須の因子としてATP依存的に働いている.ゲルダナマイシンはHSP90のATP-bindingポケットに結合してそのシャペロン機能を抑制する特異的な阻害薬であり,HSP90依存性のクライアントタンパク質の不活性化·不安定化と分解を引き起こす.HSP90のクライアントタンパク質には細胞周期·細胞死や細胞の生存·癌化に関わる機能タンパク質が多く含まれ,ゲルダナマイシン処理でHSP90を阻害すると培養癌細胞の増殖が抑制され,また実験動物での腫瘍縮小効果が観察される.ゲルダナマイシンはHSP90という単一のタンパク質に対する特異的な阻害薬でありながら,細胞周期·細胞分裂·細胞生存シグナル·アポトーシス·ステロイドホルモン作用·ストレス耐性などに関わる多面的なクライアント分子を同時に阻害できるという点で,これまでに無く広範でかつ効果的な抗癌作用を持つ薬剤となり得る.ゲルダナマイシンと同様のHSP90阻害効果を持ちながら腎·肝毒性を軽減した誘導体である17-allylaminogeldanamycin(17-AAG)は既にヒトに対するPhaseIの治験を経て,まもなく癌患者に対するPhaseIIの臨床試験が始められようとしている.
- 著者
- 上野 雄己 小塩 真司 陶山 智
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.287-290, 2018-03-01 (Released:2018-03-06)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
This study investigated the influence of the combination of an athlete's big five personality traits and athletic event (individual/group event) regarding competitive level. A questionnaire survey was conducted with university athletes (N=857, 303 men and 554 women, mean age=19.7 years, SD=1.0). The results showed that competitive level was significantly lower when individual events were combined with high agreeableness and higher when group events were combined with high conscientiousness. These results suggest that the function of the big five personality traits differs depending on their combination with the type of athletic event.
2 0 0 0 室町幕府下の出羽国・「奥州」
- 著者
- 鈴木 満
- 出版者
- 秋田大学史学会
- 雑誌
- 秋大史学 (ISSN:0386894X)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.31-46, 2015-03
2 0 0 0 OA 日本における〈指紋小説〉の展開( 2 )
- 著者
- 井上 貴翔
- 雑誌
- 北海道医療大学看護福祉学部紀要 = JOURNAL OF NURSING AND SOCIAL SERVICES (ISSN:13404709)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.1-7, 2022-12-20