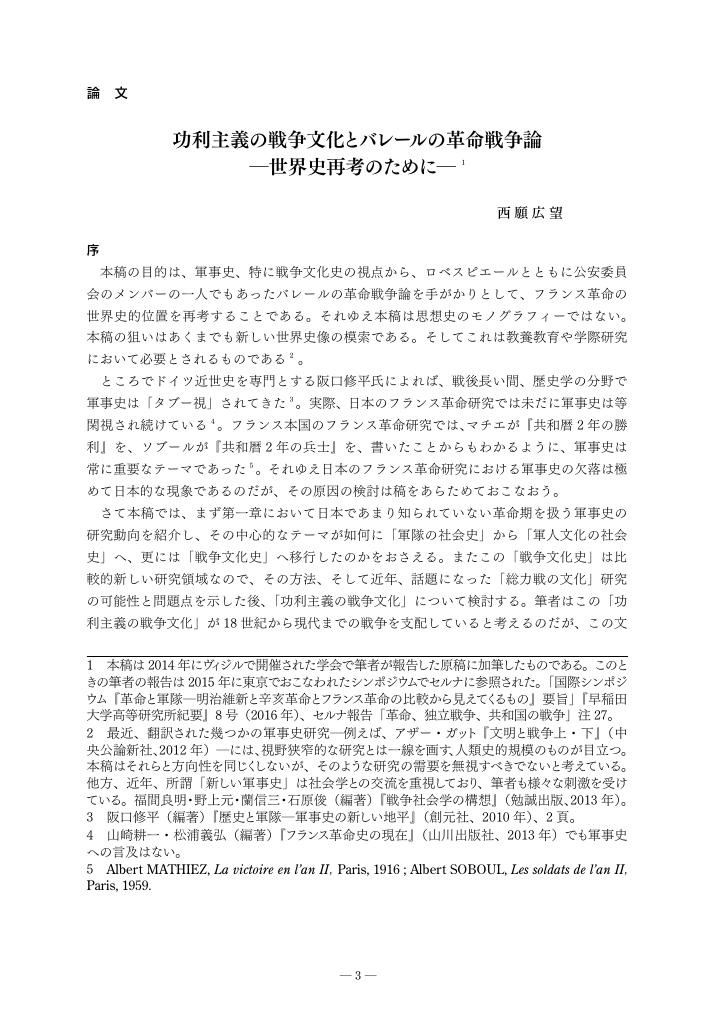2 0 0 0 OA 心臓サルコイドーシスに対する18F-FDG PET検査の手引き 2018年改訂
2 0 0 0 OA 『詩經』篇名攷
- 著者
- 野村 和広
- 雑誌
- 二松 : 大学院紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.C1-233, 2003-03-31
2 0 0 0 ウメ花粉症の研究
- 著者
- 打越 進 野村 公寿 木村 廣行 宇佐 神篤
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.374-378, 1981
- 被引用文献数
- 1
Six patients with nasal allergy due to Japanese Apricot pollen which are called "Ume" pollen were clinically examined. All cases had hyperrhinorrhea and nasal obstruction with ocular symptoms, and one of them also had itching in the pharynx. They have lived for 8 to 47 years near by a large grove of Japanese apricot and 4 of them were fruit-growers. Among these four cases, three have suffured from nasal and ocular symtoms while they were working in the grove. These cases had positive skin reaction to clude "Ume" pollen extract, and five patients also reacted to nasal and ocular provocative tests.<br>Serum IgE value by RIST was distributed from 98 to 2300IU/ml (mean value 887IU/ml). Specific anti-"Ume" pollen IgE in the serum was measured by BrCN activated RAST method, and serum value of five patients was 1.6 timed to 3.5 times higher than that of non-allergic subjects.<br>Air-borne "Ume" pollen collected in a grove were observed from the beginning of February to the middle of March, and maximum grain count was 43 per cm<sup>2</sup> in 24 hours.
- 著者
- 猪又 直子 池澤 善郎 守田 亜希子 桐野 実緒 山崎 晴名 山口 絢子 山根 裕美子 立脇 聡子 広門 未知子 近藤 恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.10, pp.1276-1284, 2007
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 5
【背景・目的】本邦では多数の植物由来食物による口腔アレルギー症候群(oral allergy syndrome : OAS)を検討した報告は稀である.そこで,本研究では本疾患の臨床的特徴と花粉感作との関連性を明らかにするため,OAS診断例63例について検討した.【方法】6年間に植物由来食物摂取後の口腔症状を自覚した例に被疑食物と花粉のプリックテスト(SPT)や特異IgE測定(CAP-FEIA : CAP)を施行した.【結果】被疑食物のSPTが陽性となったOAS診断例63例(男 : 女=1 : 2,平均年齢 : 28.7歳)の原因食品はリンゴ13例,モモ12例,キウイ12例,メロン11例であった.モモは口腔以外の症状を高率に誘発し,モモとウメの各1例でアナフィラキシーショックに至った.上位4食物のSPT陽性率は55.0〜63.2%であった.リンゴではCAPとSPTと間に相関をみとめたが(r=0.39,p<0.05),メロン,モモ,キウイではみとめられなかった.花粉症の合併は66.1%と高率で,花粉のCAP陽性率はリンゴではハンノキで,メロンではカモガヤ,ヨモギ,ブタクサで高い傾向があった.【考察】SPTとCAPの陽性率は食物の種類によって大きく異なる傾向があり,また,全体として患者の訴えより低い.現時点では,植物由来食物によるOASを診断する際に皮膚テストを用いるほうがよいと考えた.
2 0 0 0 IR ボルヘスと私、と野谷先生 (特集 ラテンアメリカ文学 : 野谷文昭教授記念号)
- 著者
- 高山 宏
- 出版者
- 現代文芸論研究室
- 雑誌
- れにくさ = Реникса : 現代文芸論研究室論集 (ISSN:21870535)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.25-28, 2013
特集 ラテン文学エッセイ
2 0 0 0 IR 計画経済期における中国の社会主義的福祉政策の考察
- 著者
- 黄 璋
- 出版者
- 愛知大学国際中国学研究センター
- 雑誌
- ICCS現代中国学ジャーナル = ICCS Journal of Modern Chinese Studies (ISSN:18826571)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.56-75, 2021-12-23
- 著者
- 中村 恵美 浅見 泰司
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.801, pp.2203-2210, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)
- 参考文献数
- 13
We analyzed the mechanism of urban food desert expansion based on data at the block level. According to the food demand curve, the elasticity was high and the nutritional value diet decreased as the store prices increased. The store prices within 500m from the redevelopment would tend to increase because luxury supermarkets would dominate, while over 500m they would often tend to decrease because new non-luxury supermarkets would compete for opening. There are only two types of blocks with high risk of food desert: a block surrounded by multiple redevelopments or a block whose store price has gone up considerably.
- 著者
- Noraini M. NOOR Shukran Abdul RAHMAN Jamil FAROOQUI Ahmad Muhammad NASR Hazizan Md NOON
- 出版者
- Psychologia Editorial Office
- 雑誌
- PSYCHOLOGIA (ISSN:00332852)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.235-245, 2003 (Released:2004-04-06)
- 参考文献数
- 21
This study examined the psychological profile of effeminates (n = 45) in comparison with matched-groups of normal males (n = 45) and females (n = 45). Respondents were Malaysian students aged between 19-24 years. Results of the one-way analyses of variance showed that effeminate students were similar to females in terms of their perceptions of their body image, thinking, and gender characteristics. However, they were more androgynous than normal female students. Although effeminates reported the lowest level of self-esteem, contrary to prediction, they showed low psychological distress. The results are discussed with respect to their current situation as well as the general literature in this area.
2 0 0 0 OA 映像論的観点からみる岩井俊二映画の構築論:『リリイ・シュシュのすべて』を中心に
- 著者
- 佐藤 唯香 Yuika Satoh
- 雑誌
- 日本文学ノート (ISSN:03867528)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.23-43, 2017-07-30
2 0 0 0 OA シスデムとしての銀行と信用創造
- 著者
- 田中 英明
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.45-57, 2006-01-20 (Released:2017-04-25)
The main function of the capitalist credit system is to create additional purchasing power in advance of future reflux of money, that is, credit creation. Commercial credit is the most fundamental form of credit creation, but it has the restrictions by individual situations, such as the sum of money due, the terms of payment and the acceptability of a bill. Banking credit is the capitalist social mechanism that overcomes the limitations of commercial credit, and realizes constant and overall credit creation. An individual bank, however, will be exposed to liquidity risk as well as credit risk, by responding to various requests based on many individual situations. This paper shows that the liquidity risk of banking credit is not actualized under the following conditions. 1) The banking system which has the mechanism of bill clearing and settlement, and of inter-bank lending or rediscount, is systematized. 2) The banking system is carrying out inclusion of the whole social reproductive process. 3) The social reproductive process is smooth and favorable. Under the conditions, bank liabilities, banknotes and deposits, which banks create in the course of bill discounting, circulate as means of purchase and payment, achieving the function as reserve that idle money has accomplished.
本研究では、主に妊娠前の働く女性に焦点を当て、健康行動の実態やニーズを把握し、ウィズ/ポストコロナ時代に利用できる携帯のアプリケーションソフト(以下アプリ)を利用した栄養と運動を中心とした健康に対する介入プログラムを開発、検証する。主な目的は以下の通りである。1)妊娠前の働く女性を対象とした、モバイルアプリとFitbitなどを使ったInternet of Things(以下IoT)の科学的根拠に基づく健康支援プログラムを開発する2)ランダム化比較試験によって、健康支援プログラムの有効性を検証する
2 0 0 0 OA 高齢者の運転評価と運転免許返納意識に関する研究
- 著者
- 元田 良孝 宇佐美 誠史 堀 沙恵
- 出版者
- 一般社団法人 交通工学研究会
- 雑誌
- 交通工学論文集 (ISSN:21872929)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.B_1-B_5, 2017-02-01 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
ここでは運転免許更新時の高齢者の意識を調査し、主として自己の運転評価と運転免許返納意識について分析を行った。盛岡運転免許センターに更新の手続きに来た70 歳以上の 155 名にアンケート調査を行った結果、運転頻度が低い人、運転の自己評価の低い人、苦手な運転行為がある人は運転免許返納の意識が比較的高いことが明らかになった。高齢運転者が運転免許更新時の実技で指導員による指摘と自分の意識する苦手な運転に違いがあり、自己評価とのギャップが存在する。返納を促進するためには公共交通等の整備とともに運転免許更新時等で自分の客観的な運転技量を認識させる必要がある。
2 0 0 0 OA 周術期の感染症─麻酔科術前診察で注意する感染症─
- 著者
- 稲垣 喜三
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.674-680, 2017-09-15 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 5
麻酔科術前診察では,感染症のスクリーニングとして,梅毒やB型肝炎ウイルス,C型肝炎ウイルスの血中抗原や抗体価を検査している.施設によっては,ヒト免疫不全ウイルス(HIV)のスクリーニングも実施し,術中・術後の患者および医療従事者の感染予防に役立てている.成人では,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やクロストリジウムディフィシル腸炎(CDI)の感染の発見と予防が,その後の創部感染や院内感染の防止に繋がる.小児では,年齢によって発症しやすい感染症が存在する.術前診察では,発疹や上気道症状,消化器症状の既往を注意深く問診し,診察による理学的所見を的確に取ることが求められる.不活化ワクチン接種から手術までの期間は2日間で,生ワクチンの接種から手術までの期間は21日間である.手術後の予防接種は,少なくとも術後7日間以上の間隔を空けて実施する.
2 0 0 0 OA 論文 功利主義の戦争文化とバレールの革命戦争論 ―世界史再考のために―
- 著者
- 西願 広望
- 出版者
- 日仏歴史学会
- 雑誌
- 日仏歴史学会会報 (ISSN:24344184)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.3-18, 2016 (Released:2020-03-31)
2 0 0 0 OA ウクライナ侵攻初期にテレビは何を伝えたか ~ソーシャルメディア時代の戦争報道~
- 著者
- 上杉 慎一
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.7, pp.38-50, 2022-07-01 (Released:2022-08-20)
2022年2月24日、ロシアが隣国ウクライナに軍事侵攻した。圧倒的な軍事力を背景に、空からのミサイル攻撃と並行し地上軍も進軍させた。当初は首都キーウの陥落も時間の問題とみられた。力による一方的な現状変更にアメリカはじめG7各国は強く反発し、経済制裁を強化した。世界各地で反戦デモが行われ、ロシア国内でも反対の声が上がった。 21世紀に起きた侵略戦争を日本のテレビはどう伝えたのだろうか。それをつかむため、報道量の調査を行った。調査対象期間は侵攻初日から最初の停戦交渉が行われた2月28日までの5日間。調査対象はNHKと民放の夜のニュース番組5番組とした。またこの間の、スタジオ解説や中継・リポート、オンライン取材、SNSで発信された映像についても調査・分析を進めた。調査の結果、期間中の報道では戦況や被害、ロシアの思惑、経済制裁に関する報道量が多かったことが分かった。さらにSNS映像が多用され、一連の報道を「ソーシャルメディア時代の戦争報道」と位置付けられることも判明した。 本稿校了時点で戦闘がやむ兆候は見られず、事態は長期化している。今回の調査は侵攻初期に焦点を当てたものだが、戦争報道の全体像をつかむためにはさらに長期間を対象にした調査や過去の戦争報道との比較も重要となる。
2 0 0 0 OA ぶつくさ君:自身の外界認識と内部状態を言語化するロボット
- 著者
- 湯口 彰重 河野 誠也 石井 カルロス寿憲 吉野 幸一郎 川西 康友 中村 泰 港 隆史 斉藤 康己 美濃 導彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.10, pp.932-935, 2022 (Released:2022-12-24)
- 参考文献数
- 8
We propose an autonomous mobile robot Butsukusa, which describes its observations and internal states during the looking-around task. The proposed robot observes the surrounding environment and moves autonomously during the looking-around task. This paper examined several language generation systems based on different observation and interaction patterns to investigate better communication protocol with users.
2 0 0 0 OA 女学生の手紙の世界
- 著者
- 稲垣 恭子
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.111-118, 2004-10-31 (Released:2016-05-25)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 東京都における臨床心理士オフィスの立地パターン
- 著者
- 渡部 正浩
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.193-204, 2006-09-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 2
本稿では,非医療分野の精神衛生施設の経営や立地展開の事例として,東京都における臨床心理士オフィスの経営実態と立地パターン,および立地要因を明らかにした.わが国では,臨床心理士に関して国家的な制度がなく,身分や収入が不安定になりがちである.とりわけ,収入の安定化は臨床心理士オフィスの経営にとって大きな課題となるが,多くのオフィスはカウンセリングに向けて高く動機付けられ,長期継続が見込めそうなクライエントを獲得するために,医師や同業者からの紹介に頼る傾向がある.立地パターンについては,次のことが明らかになった.まず,神経症・心理的問題を臨床領域とするオフィスは,ターミナル駅付近と港区西部および渋谷区東部に立地が集中していた.前者は交通利便性を,後者はクライエントの多くは高所得者であると想定し,彼らが選好しそうな街を意識したためである.また,児童の問題を専門とするオフィスは,医療・福祉機関との近接性を意識して開業地を選定していた.児童の精神問題は,しばしば器質性を帯び,そして,児童のための福祉機関が利用者の需要に追いつけないという事情から,三者の連携が不可欠なのである.以上のように,経営面において主に医療機関への依存度が高い臨床心理士オフィスであるが,医師への従属度がより高いとされる「医療心理師」の新設を見据え,それらとの競合を避けるための新たな経営・立地戦略の模索も必要となろう.
2 0 0 0 OA がん疼痛マネジメントの看護実践尺度の開発と信頼性・妥当性の検討
- 著者
- 髙橋 紀子 青山 真帆 佐藤 一樹 清水 陽一 五十嵐 尚子 宮下 光令
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.19-29, 2023 (Released:2023-02-03)
- 参考文献数
- 29
エビデンスに基づくがん疼痛マネジメントの看護実践を評価する尺度を開発し信頼性・妥当性および関連要因の検討を目的とした.がん疼痛の薬物療法に関するガイドラインに基づき仮尺度を作成し,地域がん診療連携拠点病院1施設の看護師189名に再テストを含む2回の調査を行った.探索的因子分析の結果,一因子50項目のがん疼痛マネジメントの看護実践尺度とその短縮版を開発した.尺度全体のCronbachのα係数は0.98(短縮版0.88)で内的一貫性を,再テストの級内相関係数は0.52(短縮版0.77)で信頼性を,緩和ケアの実践,知識,困難感,自信尺度とのそれぞれの相関で併存妥当性を確認した.がん疼痛マネジメントの看護実践の関連要因は,がん看護の経験年数,卒後教育の回数,卒後教育を十分に受けたと思うかだった.本尺度は,日々の臨床実践の評価やがん疼痛看護研修など教育的な取り組み後の実践評価などに活用できる.
2 0 0 0 OA 子ども連れ世帯の保育送迎時に着目した移動負担要因に関する研究
- 著者
- 明渡 隆浩 長野 博一 庄子 美優紀 伊東 英幸 藤井 敬宏
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.5, pp.I_1029-I_1036, 2016 (Released:2016-12-23)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
わが国では,子育てと仕事の両立支援や女性が出産・育児のしやすい環境づくりに向けた検討が順次進められているが,子ども連れ世帯は就業状況・世帯状況・子どもの発育状況により,外出活動そのものが多様化しており,移動負担要因についても明らかにされていない部分が多い.そのため,これらを支援する内容もより複雑化することが今後予測される.本研究は,保育園および幼稚園通園世帯におけるご両親にそれぞれアンケート調査を実施し,移動時の負担と行動意識,世帯状況等の子育て環境,立地状況の整理を行ったうえで,共分散構造分析を用いて移動負担要因との関係性を定量的に示した.また,移動支援策の利用要因を数量化II類を実施し,共分散構造分析から得られた結果と同等の要因が影響していることが明らかになった.