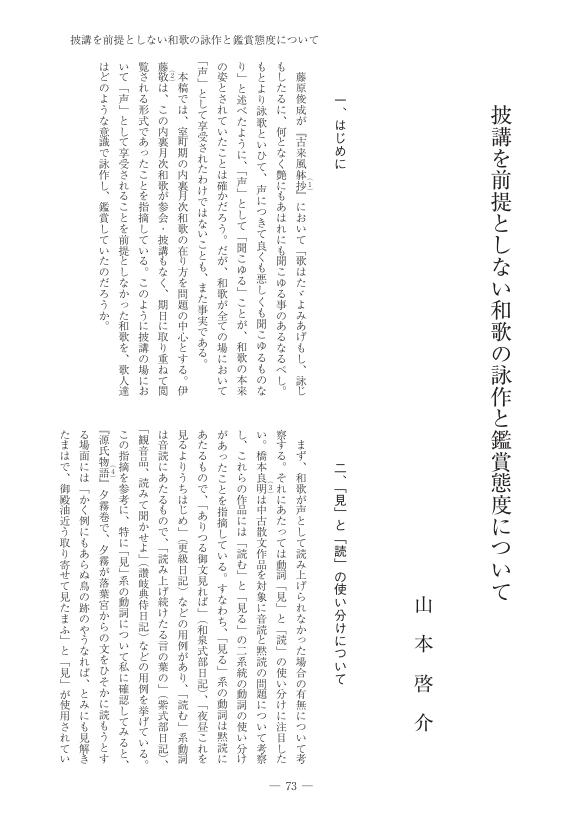- 著者
- 温 秋穎
- 出版者
- 日本メディア学会
- 雑誌
- メディア研究 (ISSN:27581047)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.119-136, 2022-08-10 (Released:2022-11-22)
This paper is a media study that attempts to elucidate how the language of "others" was imagined in "Shinago Kōza," a radio program for Chinese language study broadcast by the Japan Broadcasting Corporation (NHK) from 1931 to 1941. In Japan, the creation of a "national language" had already entered the stage of standardization in the 1930s, while the expanding military invasion of China was accompanied by efforts to popularize the Japanese language. At this stage, why had "Shinago Kōza" been broadcast for 10 years toward a wide range of nationals to learn Chinese, a language that was not their own? Focusing on the multilayered nature of the language as presented in the audio radio and print texts, this paper will examine how the image of China, which was in effect a hostile country, was imagined through the study of the Chinese language on the radio. Based on this examination, it will also consider the role played by this popular Chinese learning broadcast, which failed to transform the Chinese language to a hostile language in wartime. This article takes a historical approach, drawing on the published "radio textbook," radio program lists published in newspapers, "Radio Yearbook," "Gyōmu Tōkei Yōran," and other sources, and elucidates them in relation to the language policy of the Japanese empire.In conclusion, in the Japan Broadcasting Corporation’s "Shinago Kōza," while the language form of Chinese was always different from that of Japanese, the otherness of China, which was regarded as a negotiating partner, showed complicated features due to the transition of the situation in wartime. Thus, "Shinago," which was recognized as a language of a friendly and affiliated partner country, was placed in an ideological gray zone between an enemy language and "our" language, while maintaining the form of the language of the other.
2 0 0 0 OA 苦痛を伴う検査時の看護師の関わり ──話しかける介入と話しかけながらタッチする介入の対比
- 著者
- 加悦 美恵 井上 範江
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.3_3-3_11, 2007-09-15 (Released:2011-09-09)
- 被引用文献数
- 10 2
目的:検査を受ける患者の心身の苦痛を軽減する方法として,検査中に話しかける介入または話しかけながらタッチする介入で,患者の感じ方や気持ちに違いがあるかを明らかにすることである.方法:胃内視鏡検査を受ける入院患者43名を話しかけ群21名と話しかけタッチ群22名に振り分け介入し,気分調査票を用いて検査前と検査中の気持ちを調査し,かつ自由な感想を得た.結果:話しかけ群では検査前と検査中の気持ちに差はみられなかったが,話しかけタッチ群では,緊張や気がかりで落ち着かない気持ち(緊張と興奮),沈みがちな気持ち(抑うつ感)がやわらぎ,リラックスする気持ち(爽快感)が高まっていた(いずれもp<.05).また,両群とも看護者の介入に対し【苦痛に耐えるための心強い励まし】【身体的緊張の緩和】【精神的緊張のやわらぎと安心感】【自分に向けられた思いやり】を感じていたが,話しかけタッチ群では【親や家族がそばにいるようなぬくもりとやすらぎ】【好意に対するうれしさ】という感想が聞かれた.結論:苦痛を伴う検査を受ける患者は,看護者により話しかけられながらタッチされるほうが,より検査を楽に受けられると考えられた.
2 0 0 0 OA 堀米四郎兵衛家における紅花出荷の動向 : 『萬指引帳』の基礎的考察
はじめに 本稿は、近世後期に出羽国村山郡松橋村(上組)沢畑の豪農堀米四郎兵衛家がおこなった紅花出荷の動向について、とくに荷数や出荷の形態などに関する基礎的な考察をおこなうことを課題とするものである。堀米四郎兵衛家に関しては、幕末期の農兵頭としての活動についての研究があり、「村山地方屈指の大地主」の一人として注目されてきた。また、今田信一氏による一連の最上紅花史の研究において、堀米家の紅花生産や取引関係の史料の一部が紹介されており、かつ、同家の家屋敷地が河北町(山形県西村山郡)に寄贈されて河北町立紅花資料館として公開されたことからも、同家が紅花荷主として活躍したことはひろく知られてきているといえる。しかし、堀米四郎兵衛家の紅花荷主としての活動をはじめ、その経営に関する実証的な研究はほとんどなされておらず、羽州村山地方における豪農の一典型として著名なわりには、その実態は未解明なままであるのが研究の現状といえよう。近世後期における堀米四郎兵衛家の経営構造は多角的な性格を有しており、その全体像を解明するためには同家の様々な社会的経済的活動に関する分析を蓄積していくことが必要である。本稿は、そうした作業の一環として位置づけられる。また、紅花荷主帳簿の史料的性格については研究者間で議論が展開しておらず、分析方法についても共通認識が形成されていないのが現状である。本稿は、以下で取り上げる「萬指引帳」の分析過程をやや子細に示すことにより、ささやかながら荷主帳簿論の前進を果たそうとするものでもある。近年、堀米四郎兵衛家文書は、河北町誌編纂委員会・河北町立中央図書館をはじめ、地域の先学の尽力により、保存・閲覧の体制が整えられるとともに史料翻刻の作業が進められた。本稿は、こうした研究条件の進展を基盤としている。また、山形大学人文学部日本経済史(岩田)ゼミナールでは堀米四郎兵衛家文書の研究を進めている。本稿は、ゼミナリステンとの議論の産物でもあることを明記しておきたい。
2 0 0 0 OA ペアデータによる2者関係の相互依存性へのアプローチ
- 著者
- 浅野 良輔
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.139-141, 2017 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 相違決定の極小モデル
- 著者
- 上田 昇
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.1136-1144, 2008
ディグナーガの因の三相による論理学には相違決定(viruddhavyabhicarin)の現象が見られる.この現象について学者(古代,現代)は様々に説明するが,本稿は,これが特定の思想的立場に基づく論証に生ずる現象ではなく,因の三相による論証自体に内在する問題であることを明確にする.そのため,本稿は,因の三相の論理学を純粋に形式的な観点から見て,相違決定となるための必要条件を求めた上で,相違決定の極小例を提示し,相違決定の「発生現場」を捉える.相違決定の必要条件はまず喩体(遍充関係)に基づいて求められる.続いて,因の第二,三相の各々が喩体を論理的に含意することを証明する.第三相が喩体を含意することは基本的にJ.F.Staalのかつての証明に譲るが,第二相が喩体を含意すること-Staalが証明を試みたが,成功していない-の証明は新たに行う.また本稿は,因明で謂うところの「因同品」「宗同品」の概念を用いて第二相を定式化することによっても喩体が導出できることを示す.相違決定は喩体とは直接のかかわりはない.しかし,因の第二相・第三相が喩体を(論理的に)含意していることが上のようにして示されるから,喩体を基礎として得られた相違決定の必要条件は因の三相を推論の基礎としたときの相違決定の必要条件と考えてよい.従って,第二相・第三相,喩体のいずれを推論の基礎とするかに拘らず,本稿で得られた相違決定の必要条件は成り立つ.
2 0 0 0 軍事と技術
- 著者
- 陸軍兵器行政本部 編
- 出版者
- 軍事工業新聞出版局
- 巻号頁・発行日
- vol.(11月號), no.167, 1940-11
2 0 0 0 OA 転倒リスク因子としての足底触覚閾値の有用性
- 著者
- 佐藤 満 山下 和彦 仲保 徹 加茂野 有徳
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.465-473, 2020 (Released:2020-10-20)
- 参考文献数
- 49
【目的】体性感覚の低下は高齢者の転倒にも深く関与する。本研究は高齢者の足底触覚閾値を測定し,転倒事象との関連を明らかにする。【方法】通所介護施設の利用者110 名を対象に,高い刺激強度再現性を有する足底感覚計で足底触覚閾値を測定した。併せて下肢筋力など9 項目の心身機能を測定し,転倒群と非転倒群の間で比較した。さらに転倒を目的変数としたロジスティック回帰分析にて各変数のオッズ比を算出し,過去1 年間の転倒歴に対する足底触覚閾値の関連を検討した。【結果】転倒群と非転倒群との比較で足底触覚閾値,足関節背屈角度に有意差が認められた。性別比と疾患の有無で調整したオッズ比は足底触覚閾値と足関節背屈角度が有意であった。【結論】足底触覚閾値は高齢者の転倒を説明する変数として強い関連が認められた。要介護認定者の集団では転倒リスクの評価に従来の指標に加えて足底触覚閾値の測定が有効である可能性が示唆された。
- 著者
- 川﨑 祐介
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.e20-e29, 2022-08-01 (Released:2022-08-24)
- 参考文献数
- 13
2 0 0 0 IR 現代日本漢語の漢字音
- 著者
- 岩尾 俊兵
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.70-86, 2018-12-20 (Released:2019-02-12)
- 参考文献数
- 55
改善活動は,分権的組織によって創出される多数のインクリメンタル・イノベーションの集合として,半ば規範的に捉えられることもある.これに対し本稿は,インクリメンタル・イノベーションとしての改善活動の実態が必ずしも上記規範に一方的に規定されるとは限らないと指摘し,そこには「どのような規模のものに集中し,どのような組織で取り組むか」という全社的な戦略的意思決定の余地が残されていることを明らかにした.
2 0 0 0 OA 酒の話 (一)
- 著者
- 谷口 豐二
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.10, pp.1073-1075, 1935 (Released:2011-11-04)
2 0 0 0 OA ポルトガルの薬物政策調査報告・2014-2015年 〔欧州薬物調査シリーズ (2)〕
- 著者
- 丸山 泰弘
- 出版者
- 立正大学法学会
- 雑誌
- 立正法学論集 (ISSN:02864800)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.234-196, 2016-03-20
2 0 0 0 OA 心拍数の変化に応じてノーツの落下速度が変化するリズムゲームの開発
- 著者
- 稲垣 誠 川合 康央
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, pp.81-83, 2021-08-23
本研究では,ユーザーの心拍数をリアルタイムに計測し,一定時間内の心拍数をノーツの落下速度に割り当てることで毎回異なる変化をするリズムゲームを開発しました.このシステムでは,同じ曲をプレイすることで生まれる「飽き」を軽減させるため,ユーザーの心拍数の変化に応じてリアルタイムで状況を変化させ続けるリズムゲームをプレイすることが出来ます.また,曲中での心拍数の変化をグラフにし,可視化させることで練習箇所を特定し,次回プレイ時の上達を助力します.
2 0 0 0 OA ASCONE実施報告
2 0 0 0 OA 披講を前提としない和歌の詠作と鑑賞態度について
- 著者
- 山本 啓介
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.73-82, 2015 (Released:2018-02-09)
2 0 0 0 OA 人体筋骨格系不具合に対する運動療法の構造モデリング
- 著者
- 嘉陽 宗弘 狼 嘉彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集C編 (ISSN:18848354)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.803, pp.2273-2285, 2013 (Released:2013-07-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
The objective of this paper is to establish a concise structural model of the human musculoskeletal (HMS) system to be used for an exercise therapy of a malfunction or a distortion called Somatic Balance Restoring Treatment (SRBT). This model must be comprehensive for therapists while maintaining a theoretical thoroughness in mechanics. For this objective, a system approach called Interpretive Structural Modeling (ISM) has been applied to bridge multi-body dynamics and clinical observations. From a mechanical viewpoint, the HMS system can be treated as a collection of joint connected 15 rigid bodies in a topological tree. From a clinical viewpoint, joints are of major concern since most malfunctions take place at the joints. Based on clinical observation data accumulated for 36 years, we have discovered that all HMS motions can be constructed by a combination of 80 fundamental motion elements and that all motions are interacted with each other. By applying the ISM for the HMS system, we have obtained that an active motion element with intention induces associated motion element(s). In addition, the ISM yields a tiered structure of the fundamental motion elements according to the degree of activeness; and most importantly, an overall investigation of the matrix characteristics has revealed a fundamental structure of the SBRT.
2 0 0 0 OA 公営競技撤退における首長判断をめぐって
- 著者
- 福井 弘教
- 出版者
- 法政大学公共政策研究科『公共政策志林』編集委員会
- 雑誌
- 公共政策志林 = Koukyo Seisaku Shirin : Public Policy and Social Governance (ISSN:21875790)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.321-336, 2021-03-24
自治体の収益事業には競馬,競艇,競輪,オートレースなど公営競技も該当する。公営競技事業は,自治体財政に大きく寄与する時期もあったが,それが難しい状況となっている。そうしたなか公営競技の撤退を決定する自治体が増加している。財政貢献が主たる事業目的であることからすると,当然の帰結といえるが多くの場合,撤退は唐突に発表され,結果のみが提示されて過程が不透明であることが課題である。本稿では公営競技撤退における首長判断に着目し,撤退と継続の両面から自治体の比較分析を行い,関連する政策終了論の検討も加えて,撤退判断の背景・要因を解明することを目的としている。考察の結果,それらは直接的利益や維持管理コストといった一側面を基準に撤退の決定がなされることが指摘できる。同時に議決不要などの制度や政治的事象に左右されることも散見された。すなわち,撤退判断にあたって明確な指標や基準は存在しないことが示唆された。
- 著者
- Yutaka HIROI Akinori ITO Eiji NAKANO
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- KANSEI Engineering International (ISSN:13451928)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.59-66, 2009 (Released:2018-05-31)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 8
Familiarity is one of the most important requirements for human symbiosis robots, such as care service robots. To improve familiarity of a human symbiosis robot, we proposed a novel concept called “robot avatar.” A robot avatar is a small robot mounted on a main robot, and it performs gestures instead of the main robot. Although our previous study revealed that a robot avatar was effective for increasing users’ familiarity with a robot, the effect of users’ age on the improvement of familiarity by a robot avatar was not investigated well because the most of the subjects in the previous study were young. When considering the application of a robot avatar to care service robots, it is important to investigate the effect of a robot avatar on elderly people. In this paper, we focus on elderly subjects, and carried out an experiment to test if a robot avatar is effective for elderly people to improve familiarity. The result was positive, and the effect of a robot avatar on elderly people was stronger than that on younger people. From a comparison of the results from elderly subjects with those from younger subjects, we found that the elderly paid less attention to dialogue between a human and a robot.
2 0 0 0 OA ILO「労働は商品ではない」原則の意味するもの -労働法との関連をめぐって-
- 著者
- 石田 眞
- 出版者
- 早稲田商学同攻会
- 雑誌
- 早稲田商學 (ISSN:03873404)
- 巻号頁・発行日
- vol.428, pp.125-134, 2011-03-15
2 0 0 0 墓建築
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 巻号頁・発行日
- 1969