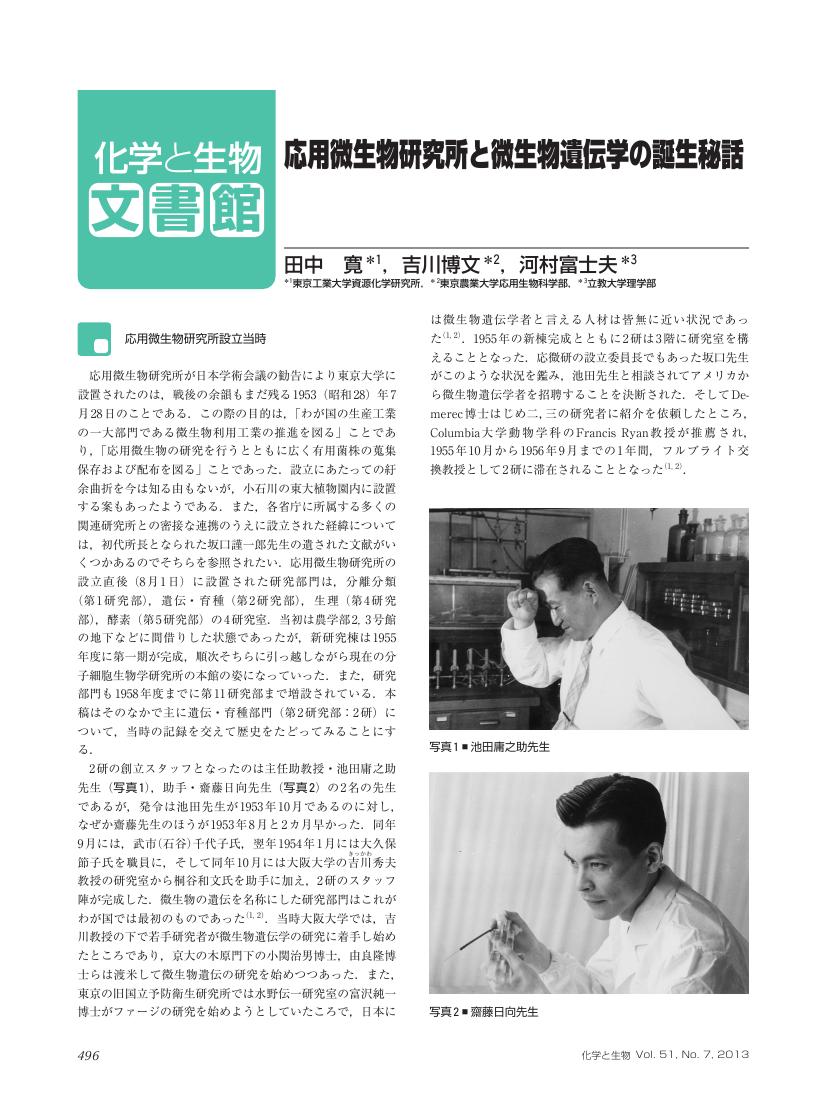2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1915年08月24日, 1915-08-24
2 0 0 0 OA 朝永著作集を高校に贈る運動について
- 著者
- 玉木 英彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.12, pp.983-985, 1982-12-05 (Released:2020-06-01)
2 0 0 0 OA 応用微生物研究所と微生物遺伝学の誕生秘話
- 著者
- 田中 寛 吉川 博文 河村 富士夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.7, pp.496-499, 2013-07-01 (Released:2014-07-01)
- 参考文献数
- 11
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1922年09月21日, 1922-09-21
- 著者
- Kyosuke Hirayama Hiroyuki Toda Takafumi Suzuki Masayuki Uesugi Akihisa Takeuchi Wolfgang Ludwig
- 出版者
- The Japan Institute of Metals and Materials
- 雑誌
- MATERIALS TRANSACTIONS (ISSN:13459678)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.586-591, 2022-04-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
Crystallographic assessment of the hydrogen embrittlement behavior of Al–Zn–Mg alloy was performed by means of a technique combining fracture trajectory analysis and synchrotron X-ray diffraction contrast tomography. The 3D microstructure reconstructed using diffraction contrast tomography contained 119 grains. Fracture surfaces revealing intergranular fracture, ductile fracture, and quasi-cleavage fracture were observed in the alloy. While the intergranular crack initiated at a grain boundary with high grain boundary energy and a high angle between the grain boundary plane and loading direction, the crack propagation itself was not observed to be sensitive to these two parameters. The quasi-cleavage fracture surfaces were not characterized by any specific crystal orientation because of variation in the free surface segregation energy of hydrogen uniforms without depending on surface orientation.
2 0 0 0 OA 学校教育につきつけられる諸課題から, これからの学校教育の姿を考える
- 著者
- 清水 睦美
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.11, pp.11_47-11_52, 2021-11-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 16
新型コロナウイルスの感染拡大と、その対応に伴う政治・経済・社会状況の変化の中で、学校教育を問い直す動きが活発化している。特に、政治主導のもとでの一斉休校は、そのあまりの唐突さによって、「子どもの生活を守る」という学校の機能に光をあてることになった。さらに、学校再開時に行われた「分散登校」は、日本では長く据え置かれてきた多人数学級の仕組みを少人数学級へと導く原動力となった。こうした動きの背景について、コロナ禍直前の学校の姿を、子どもたちの実態と社会構造の観点から捉えることを通して、学校教育の何が問い直されているのかを明らかにしていく。それらを通して、これからの学校教育の姿を検討する。
2 0 0 0 OA 平坦な物語をつむぐ ―日常系漫画における退屈さの可能性―
- 著者
- 古戸 杏実 東方 悠平
- 出版者
- 八戸工業大学
- 雑誌
- 八戸工業大学紀要 = The Bulletin of Hachinohe Institute of Technology (ISSN:24346659)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.34-45, 2021-03-26
2 0 0 0 OA 糖尿病者にスタチンは禁忌―緊急提言
- 著者
- 奥山 治美 浜崎 智仁 大櫛 陽一 浜 六郎 内野 元 渡邊 浩幸 橋本 道男
- 出版者
- 日本脂質栄養学会
- 雑誌
- 脂質栄養学 (ISSN:13434594)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.173-186, 2013 (Released:2013-10-01)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 1 1
Statins have been recognized clinically to raise blood glucose and glycated protein (HbA1c) levels enhancing the development of insulin resistance. However, most clinicians appear to adopt the interpretation that the benefit (prevention of CHD) outweighs the risk (new-onset of diabetes mellitus). Consistently, "Japan Atherosclerosis Society Guidelines for the Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases 2012" recommends diabetics to maintain LDL-C levels below 120 mg/dL; 40 mg/dL lower than the value for those without risky complications. This recommendation necessitates many diabetics to use statins. However, we pointed out that statins exhibited no significant benefit for the prevention of CHD in the trials performed by scientists independent of industries after 2004, when a new regulation on clinical trials took effect in EU (Cholesterol Guidelines for Longevity, 2010). Here, we reviewed clinical evidence that statins could induce diabetes mellitus, and biochemical evidence that statins are toxic to mitochondria; they suppress electron transport and ATP generation through decreased prenyl-intermediate levels. They also inhibit seleno-protein synthesis and dolichol-mediated glycation of insulin receptor leading to insulin resistance and cardiac failure, similarly to the case of Se-deficiency. These mechanisms of statin actions are consistent with clinically observed decreases in blood ketone body, mitochondrial dysfunctions and enhanced glucose intolerance. Based on these lines of evidence, we urgently propose that statins are contraindicant to diabetics and their prescription should be restricted to special cases* for which medical doctors rationally decide to be necessary.
2 0 0 0 OA 第9回 心臓性急死研究会 児童・生徒の心臓性急死
- 著者
- 大国 真彦
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.Supplement5, pp.61-68, 1992-12-10 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 森 明子 上村 洋充 髻谷 満 曽田 幸一朗 眞渕 敏 川上 寿一 道免 和久
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, 2007-04-20
【はじめに】デグロービング損傷は機械を扱う労働者が機械に巻き込まれ上肢を受傷するケースが多いが、下肢の受傷ケースは少ない。歩行獲得に向けて理学療法士の役割は大きいにも関わらず症例報告はほとんどない。そこで今回、早期より下腿デグロービング損傷と足関節伸筋腱断裂を伴った症例を経験したため報告する。<BR>【症例】19歳女性。平成17年4月25日列車脱線事故により、右下腿デグロービング・足関節脱臼、左足関節内果骨折、左前腕骨折受傷。その他重篤な外傷なし。右足関節伸筋腱すべて断裂していたため同日、縫合術施行。血液検査データはCK1855U/l、白血球15500/μl、第3病日ではCK3448U/l、CRP12.1mg/dlと高値であった。表皮の欠損が広範囲のため第31病日より右下腿創部にハイドロサイト、第36病日よりフィブラストスプレーを使用開始した。第75病日、全荷重許可後より右下腿皮膚形成の急速な進行がみられた。<BR>【理学療法経過】第15病日より理学療法(以下PT)開始。右長下肢、左短下肢ギプスシーネ固定中。右膝屈曲は禁忌。左下肢は踵部での全荷重可能。寝返り、起き上がりは痛みの範囲内で自立。立ち上がりは左踵骨のみの荷重で介助下にて可能。左下肢筋力は4レベル。第24病日、右下肢は短下肢ギプスシーネに、左下肢は軟性装具へ変更。右膝ROM、右大腿四頭筋、ハムストリングスの筋力強化を等尺性運動にて開始。また左足関節装具装着にて左下肢全荷重開始。第30病日、右下腿ギプスシーネ除去し右足関節・足指自動運動開始。第36病日、PT室にて右下肢1/3荷重開始。第39病日、右足関節・足指他動運動開始。第65病日、右下肢1/2荷重で歩行練習開始。第75病日、右下肢全荷重、両松葉杖歩行、自転車エルゴメーター開始。第88病日、軟性装具装着下にて歩行自立。第99病日、装具なしにて病棟内歩行自立し、第120病日には病院内歩行許可となり、第151病日、自宅退院となる。退院時の右足関節可動域は背屈10°、底屈30°。左右片脚立位は30秒以上可能。階段昇降は自立。ジャンプ、ランニングは困難であった。<BR>【考察】デグロービング損傷の場合、皮膚の再生や創部への負荷を考え、早期からの荷重や歩行は困難とされることを臨床上経験することが多い。しかし、本症例では感染に注意しハイドロサイトやフィブラストスプレーを併用し、創部の浮腫や腱への負担を注意しながら早期から荷重・歩行練習行うことで順調な経過を得ることができた。荷重・歩行は筋ポンプ作用による筋血流量増加や、皮膚への血流量の増加につながり、皮膚組織の再生にも寄与したのではないかと考えられる。損傷部位の組織修復過程を考慮した治療が肝要である。<BR><BR>
- 著者
- 能口 盾彦
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 言語文化 (ISSN:13441418)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.43-71, 2007-08
英国版『親指トム』とグリム童話の内容は大差無いが、グリム童話の『蛙の王様』や日本の『一寸ぼうし』の様に、蛙を叩きつけたり打出の小槌を振るとかで魔法が解ける展開にはつながらない。親指トムはハッピー・ーエンドに終わるが、フィールディングの原作や改訂版は悲劇或いは悲劇中の悲劇と題されている。英国版親指トムが狼の胃袋に収まる前段階、即ち雌牛に干し草もろとも飲み込まれる逸話を捉え、フィールディングは『悲劇中の悲劇』で巨人達を撃破した凱旋将軍トムを、赤雌牛に飲み込ませて彼の末路とする。『親指トム一代記』でも英雄トムの不慮の死として同様の場面が挿入されているが、『悲劇中の悲劇』同様に乳搾り女や狼が介在することもなく、ゴーストとなった親指トムが再登場し、トムのゴーストが刺殺されることを契機に、登場人物の死の連鎖が繰り広げられる。一方、『悲劇中の悲劇』第三幕第一場に預言者マーリン(Merlin)に姿を変えたゴーストが現れ、親指トムは婚儀を終えた幸せの絶頂期に、ゴーストの予言通りに赤牛に飲み込まれて頓死する。親指トムの死を契機に前作同様、登場人物は次々と凶刃に倒れる。旧来の親指トムでは夢想し得ぬ結末に、フィールディング劇の真骨頂がある。何故フィールディングはハピー・エンドに終わる童話の体を借りて悲劇化を目論んだのか。この課題は劇作家フィールディングの野望と18世紀英国演劇界の状況を把握せずして理解は覚束ないだろう。「きき台詞」の多さや多様さは、芝居通や文芸批評家の衒学さへのフィールディング流諷刺の一端で、専門家気取りの演劇関係者への痛烈な皮肉として、周到に練られた策ではなかったか。前世紀のコングリーブ(William Congreve)等による『風俗喜劇』(Comedy of Manners)が急速に廃れた現実を前に、ホメロス、ウェルギリウス、ルキアノス等の古典に慣れ親しんだフィールディングは、演劇界で糧を得ようとして道化劇や英雄悲劇の形式を踏襲するのも、その紋切り型の手法を揶揄する折衷案、即ち英雄悲劇を茶化す笑劇に活路を見出した。
2 0 0 0 系統連系インバータにおける能動的停電検出法
- 著者
- 原 邦治 雨海 秀行
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. PE, 電子通信用電源技術
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.150, pp.25-29, 1994-07-19
最近、クリーンなエネルギーを利用した発電システムとして、大陽光発電が注目を浴びている。この発電装置がインバータを介して商用電源と連系して運転する場合には、いくつか問題がある。特に、商用系統が停電したとき、太陽光発電装置のインバータの単独運転は、連系システムの保安上、危険であるため、商用の停電を検出して運転を停止する必要がある。しかし従来の停電検出法には不感帯が存在し、確実な停電検出が困難である。本論文ではインバータの出力電圧に高調波を重畳させ、単独運転時に顕著に現れる高調波電圧を検出し、インバータの単独運転を防止する方式を開発したのでこれを報告する.
- 著者
- 韓 瑞元 リ ジュンファン 中嶋 正之
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.28, pp.49-54, 1997-05-19
- 被引用文献数
- 4
Virtual Studio currently uses cromakey method in which a image is captured, and blue portion of that image is replaced by Computer Graphics image or real image. The replaced image must be changed according to the camera motion. This paper proposes a method to extract camera parameters (camera position, rotation and focus) using recognition of pentagonal patterns. At first, we find matching points of two projective images using invariable features of pentagon. Then, we calculate the projective transformation of two projective images and camera parameters using matching points. Simulation results indicate that camera parameters are calculated easily compared with conventional methods.
2 0 0 0 宮城県の旧石器及び「前期旧石器」時代研究批判
- 著者
- 小田 静夫 Keally Charles T.
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.3, pp.325-361, 1986
- 被引用文献数
- 4
日本の旧石器時代の研究において,一つの関心事は日本列島に最初に渡来した人類の問題であろう.現在多数の研究者は1万-3万年前頃の旧石器時代人類の存在は認めているが,3万年以前に遡るとされる所謂「前期旧石器時代」になると,その存在に賛否両論があり現在未解決の問題として残されている.日本の前期旧石器時代については,1969年頃から芹沢長介により本格的に研究され始め,全国に遺跡,遺物の発見があった.しかし,ここ数年,岡村道雄•鎌田俊昭らが宮城県内で推進している「新たな前期旧石器時代」の提唱は,芹沢により研究されてきた本来の「前期旧石器問題」を解決させることなく,これこそ真の石器であり,遺跡も完壁なものであると力説する.現在宮城県内で33ヵ所の前期旧石器時代遺跡が発見されており,その中でも座散乱木,馬場壇A,志引,中峯C,北前,山田上ノ台遺跡等が有名である.
2 0 0 0 OA 当事者研究におけるファシリテーター・当事者の実践——共成員性とカテゴリー対を中心に——
- 著者
- 中村 和生 浦野 茂 水川 喜文
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.65-75, 2018-01-31 (Released:2019-02-26)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
本稿は、当事者研究、すなわち日常生活を送っていくにあたり何らかの苦労や困難を持つ人々による自分たち自身を対象とした共同研究(我々のデータでは、精神障害を持つ人々のグループセッション)という実践を主題とする。そして、このグループセッションという相互行為において、ある者が当事者をする中でファシリテーターを担っていることに注目し、このことの意義ならびに、そのような担い手によるいくつかのやり方を解明することを目的とする。ときに、この担い手はファシリテーターから離れた参加者としてもふるまうが、これがいかにして可能であり、また、その可能性の下でどのように首尾よく成し遂げられているのかを検討し、プレセッションにおいてすべての参加者が行う、自己病名の語りを通した自己紹介によって当事者としての共成員性が確立することを見いだす。また、このファシリテーターはどのように発言の順番をデザインしているのかを分析し、ファシリテーターはほぼすべての順番を自己選択で取り、またしばしば次話者選択をする一方で、次話者選択しない場合にも、状況に応じた適切な指し手を繰り出していることを見いだす。
2 0 0 0 OA 茱萸の酒 : 随筆集
2 0 0 0 IR 前田本色葉字類抄の徳声について
- 著者
- 二戸 麻砂彦 二戸 麻砂彦 NITO Masahiko ニト マサヒコ Nito Masahiko
- 出版者
- 山梨県立大学
- 雑誌
- 山梨国際研究 : 山梨県立大学国際政策学部紀要 (ISSN:21874336)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.61-74, 2019-03-05
Dictionaries in Ancient Japanese have been inflected by Chinese Dictionaries. These are divided into three classes, Bushu(部首:parts of Kanji), Igi(意義:meanings of Kanji)and Jion(字音:readings of Kanji)from the point of view about there search systems. These systems were not fit for Japanese Language. And so, Dictionaries by the use of Iroha(イロハ)search system were composed in late Heian period. "Iroha-jiruisyō" is one of them. This study analyzes the tone 'Toku-syō'(徳声)in "Iroha-jiruisyō".
2 0 0 0 OA 中世都市鎌倉以前 : 東の海上ルートの実相
- 著者
- 平川 南
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, pp.253-281, 2004-02-27
中世の幕府は、なぜ鎌倉の地に設置されたのか。おそらくは、鎌倉の地を経由する海上ルートは、中世以前に長い時間をかけて確立されてきたものと想定されるであろう。小稿の目的は、この歴史的ルートを検証することにある。最近発見された、三浦半島の付け根に位置する長柄・桜山古墳は、三浦半島から房総半島に至る四〜五世紀の前期古墳の分布ルートを鮮やかに証明したといえる。また、八〜九世紀には、道教的色彩の強い墨書人面土器が、伊豆半島の付け根の箱根田遺跡そして相模湾を経て房総半島の〝香取の海〟一帯の遺跡群で最も広範に分布し、さらに北上して陸奥国磐城地方から陸奥国府・多賀城の地に至っている。また古代末期の史料によれば、国司交替に際しても、相模―上総に至る海上ルートが公的に認められていたことがわかる。このルートは『日本書紀』『古事記』にみえるヤマトタケルの〝東征〟伝承コースと符合する。これは古東海道ルートといわれるものである。上記の事例の検討によって、ヤマトから東国への政治・軍事・経済そして文化などの伝来は、古墳時代以来伊豆半島・三浦半島・房総半島の付け根と海上を通る最短距離ルートを活用していたことが明らかになったといえる。この西から東への交流・物流の海上ルートの中継拠点が鎌倉の地である。中世の鎌倉幕府は、そうした海上ルートの中継拠点に設置され、西へ東へ存分に活動したと考えられる。
- 著者
- 坪根 由香里 田中 真理
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.111-127, 2015-09-30 (Released:2017-05-03)
本稿の目的は,第二言語としての日本語小論文の「内容」「構成」の評価が,評価者によって異なるのか,もしそうならどのように異なるのかを検討し,その上で「いい内容」「いい構成」がどのようなものかを探ることである.調査では,「比較・対照」と「論証」が主要モードの,上級レベルの書き手による6編の小論文を日本語教師10名に評価してもらった.その結果を統計的手法を用いて分析したところ,「内容」「構成」ともに,異なる評価傾向を持つ評価者グループのあることが分かった.そこで,上位4編の評価時のプロトコルから「内容」「構成」に関する部分を抜き出し,それを実際の小論文と照合しながら,各評価者グループの評価観の共通点・相違点について分析した.その結果から,「いい内容」の要因は,1)主張の明確さ,2)説得力のある根拠を分かりやすく示すこと,3)全体理解の助けになる書き出し,4)一般論への反論であることが分かった.視点の面白さと例示に関しては評価が分かれた.「いい構成」は,1)メタ言語の使用,2)適切な段落分けをし,段落内の内容が完結していること,3)反対の立場のメリットを挙げた上で反論するという展開,4)支持する立場,支持しない立場に関する記述量のバランスが要因として認められた.本研究で得られた知見は,第二言語としての日本語に限らず,第一言語としての日本語小論文の評価にも共有できるであろう.