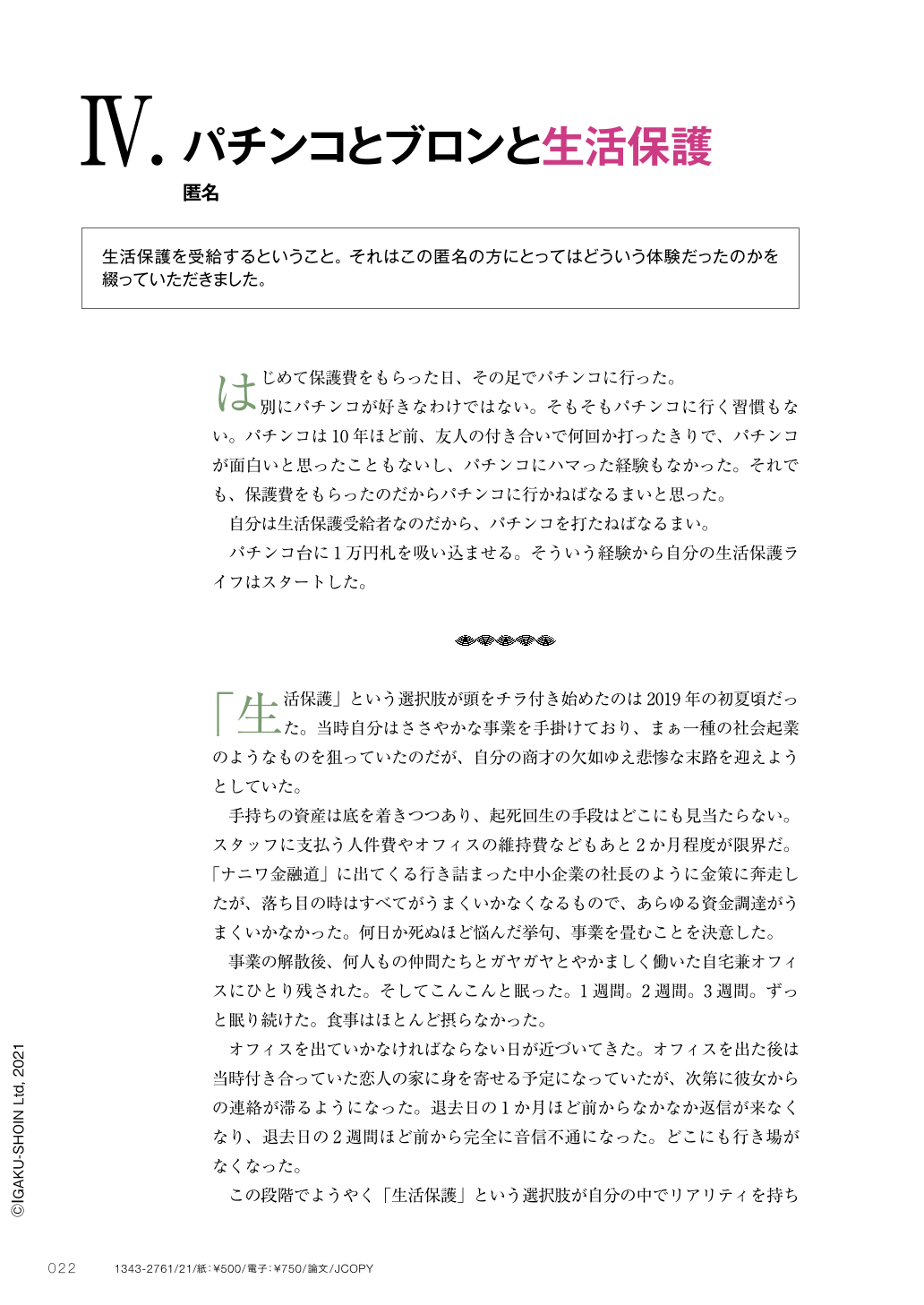2 0 0 0 IR 日系コーヒー企業の台湾市場参入の現状と課題 : UCC社の進出を中心に
- 著者
- 口野 直隆 浜口 夏帆 大島 一二
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.3-34, 2022-02-17
The environment surrounding the restaurant industry in Japan isbecoming increasingly severe every year. Aside from the immediateproblem of the rapid contraction of demand for food service due to thespread of the new coronavirus, the biggest long-term problem is theongoing contraction of the domestic market due to Japan's declining andaging population. In contrast, overseas markets are steadily expanding dueto population growth and rising incomes, showing a favorable contrast tothe Japanese market.For this reason, in recent years, an increasing number of restaurantcompanies have actually turned their attention to overseas markets,especially Asian markets, and many of them are planning andimplementing overseas expansion.In previous research, this research team examined the performance ofJapanese food service companies expanding overseas and the status ofstore development by company, with a particular focus on their expansioninto the Taiwanese market. In this section, we examine the current statusof what groups of food service companies are actually expanding overseasby comparing 2017 and 2021. As a result, it became clear that the overallsituation of overseas expansion is becoming more polarized, with the socalledleading large corporate groups expanding further and the smallerand medium-sized corporate groups decreasing and withdrawing. However, this paper left some unanswered questions as to whether thesemacroeconomic conditions are universally applicable to all types andsectors of food service companies or not.Therefore, in this paper, we will focus on a sector of the food serviceindustry where there is not much prior research on overseas market entry,unlike the fast food chains and Japanese restaurants such as Japanese-stylepubs, which have been the main focus of research so far. In this paper, wefocus on the case of UCC's expansion into Taiwan. As will be discussedlater in this paper, UCC's expansion into Taiwan is characterized by thefact that it is not only an overseas expansion as a food service companywith coffee shop business as its core business, but also a strategy toexpand sales of coffee bean-related products in the Taiwanese market as afood (processing) industry.
2 0 0 0 IR 中国市場における日系食品企業の製品戦略に関する分析 : 日系H社の事例を中心に
- 著者
- 刘 博晗 大島 一二
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.105-123, 2022-02-17
In this paper, I have described the development of Company H's productstrategy in the Chinese market, which was established in roughly threestages. In the first stage, the company confirmed that there was a certainlevel of product demand in the Chinese market through antenna stores andthorough tasting and development. Next, in the second stage, by promotingthe localization strategy in product development, we have improved thesatisfaction level of local consumers and achieved sales expansion bypromoting further adjustments. By juxtaposing this localization strategywith the promotion strategy, the company has promoted the recognition ofJapanese style curry among Chinese consumers. Finally, we believe thatthe current third staircase aims to further expand sales in the market bydiversifying the product through various adjustments.With the progress of these efforts, Company H has achieved somesuccess.
2 0 0 0 IR 日系外食産業のアジア市場進出の現状と課題 : 台湾市場への進出を中心に
- 著者
- 口野 直隆 浜口 夏帆 大島 一二
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.37-63, 2022-01-20
The market size of the Japanese restaurant industry peaked at 29 trillionyen in 1997 and has been sluggish since then. Even more problematic isthat it is likely to decrease further in the future. According to the Japanesegovernment's announcement, due to the declining birthrate, Japan'spopulation is expected to reach 86.74 million by 2060, a significant decreasefrom the present. In other words, unlike the situation so far, it is predictedthat Japan will experience a serious population decline in the medium tolong term, which will inevitably reduce the market size of the Japanesefood service industry.Under these circumstances, the Japanese food service industry hasreached a time when it should seek new growth opportunities. The growthopportunity is, inevitably, to enter overseas markets where the populationis growing rapidly and income is rising significantly. In particular, the foodservice market in developing and emerging markets in Asia is likely todevelop significantly in the future.In this paper, based on this situation, we analyzed the actual situation ofthe overseas expansion of the Japanese restaurant industry, especiallyfocusing on the expansion into the Taiwanese market.
2 0 0 0 国会と内閣の関係
- 著者
- 矢部明宏[著]
- 出版者
- 国立国会図書館調査及び立法考査局
- 巻号頁・発行日
- 2004
2 0 0 0 IR 芸能にみるパラオのアイデンティティの多層性 : 2007年東京・静岡公演の事例から
- 著者
- 小西 潤子
- 出版者
- 静岡大学
- 雑誌
- 静岡大学教育学部研究報告. 人文・社会科学篇 (ISSN:02867303)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.59-72, 2007
2 0 0 0 Ⅳ.パチンコとブロンと生活保護
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.22-25, 2021-01-15
生活保護を受給するということ。それはこの匿名の方にとってはどういう体験だったのかを綴っていただきました。
- 著者
- 中村 恵理
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2015
【目的】先天性両側性傍シルビウス裂症候群は,シルビウス裂周囲の構造異常により,上肢優位の痙性麻痺や嚥下困難,てんかん発作,高次脳機能障害を併発する。先行報告では,運動発達遅滞は少なく,仮性球麻痺や言語発達遅滞が報告されている。確定診断例が全国で約500例と非常に稀であり,リハビリテーションの介入報告は皆無に等しい。今回,同症例が疑われる児をNICU入室時から外来フォローまで担当し,他職種間の連携を心がけた結果,哺乳・摂食機能,運動機能面に発達が認められたのでここに報告する。【症例提示】在胎40週3日,出生体重3685gにて出生した女児であり全身の低筋緊張を認め,特に頭頚部が著明であった。出生3週間後よりNICUにてリハビリを開始し出生2ヶ月で自宅退院,その後,当院で1回/月の外来リハを開始し,現在は療育センターでのフォローも行っている。【経過と考察】NICU介入時,頭頸部の低緊張の為,十分な体重増加の為の哺乳量を経口摂取で確保することが難しく経鼻栄養管理であった。哺乳時の姿勢検討や,舌への感覚刺激入力,抗重力活動の促しを図り,哺乳頻度の調節を行った。また,スタッフ間でのポジショニングの周知や,哺乳時間にNICUへ出向きDr.,Ns,STと共に児の自発的経口摂取獲得に向けて何度もディスカッションを行なった。退院時は経口摂取が可能となったが,その後経口摂取量が伸びず現在経鼻栄養である。外来フォロー時は,哺乳時の姿勢や抱っこの仕方を母親に指導した。1歳10ヶ月で寝返りを獲得し,2歳現在は未定頸,腹臥位ではon elbowsで頭頸部挙上し保持可能,座位では頭頚部正中位保持が困難である。離乳食は嫌がり吐き出してしまうが,少量の重湯であれば自ら開口し飲水でき,徐々に経口摂取が可能になってきている。NICUから広がったチームの輪は,児の成長とともに形を変え外来でのSTとの強固な連携,そして療育施設のスタッフとも結びつきながら現在に至っている。
2 0 0 0 OA 風力発電の発電特性と系統連系
- 著者
- 牛山 泉
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.8-9, pp.514-517, 2000-08-01 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA メニエール病1,008名の集計と有酸素運動による治療成績
- 著者
- 高橋 正紘
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳科学会
- 雑誌
- Otology Japan (ISSN:09172025)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.828-835, 2015 (Released:2019-02-13)
- 参考文献数
- 19
8年5ヶ月間のメニエール病1,008名の集計結果、罹病期間と聴力の関係、有酸素運動とストレス対策の治療成績を報告した。発症年齢は30〜50代が64.8%を占め、発症誘因上位は、男性は職場の多忙・ストレス、女性は家庭内不和・トラブル、多忙、職場ストレス、介護、子供(親)と同居、家族の病気・死であった。難聴は罹病期間の対数にほぼ正比例して進行し、罹病4〜8年で全音域障害が55.4%に達し、罹病>8年で両側障害が増加した。患側左が右の1.4倍と有意(p<0.005)に多かった。有酸素運動とストレス対策によりめまい発作は早期に消失した。初診時、低音障害は3ヶ月以上、高音・全音域障害は6ヶ月以上観察した319名(平均観察期間1年5ヶ月)で、治療後、罹病6ヶ月〜8年の集計と全集計で聴力正常の割合が有意(p<0.00001)に増加した。今回の結果から、メニエール病はストレスによる内耳恒常性の低下が原因であり、早期のストレス対策と有酸素運動で治癒可能な疾患と確認された。
2 0 0 0 OA 新形三十六怪撰 平惟茂戸隠山に悪鬼を退治す図
- 著者
- 片山 徹 手嶋 晃 池田 良穂
- 出版者
- 社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 関西造船協会論文集 (ISSN:13467727)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.236, pp.181-190, 2001
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
An experimental investigation on the transverse porpoising instability of a planning craft in drifting motion at high advance speeds in calm water is carried out. Some types of transverse porpoising are observed in measuring motions in oblique towing tests under heave, pitch and roll free condition. In order to clarify the influence of hydrodynamic forces on the transverse porpoising, captive model tests in oblique towing condition are carried out. The experiments are carried out by systematically changing trim angle, drift angle, towing speed and draft. From the measured hydrodynamic forces, the restoring forces and moments of heave, roll and pitch are calculated. The results show that the coupling restoring coefficients between heave and pitch have the different sign each other(∂F_z/∂θ>0, ∂M_y/∂z<0)and the coupling restoring coefficients between heave and roll also have the different sign each other (∂F_z/∂ψ>0, ∂M_x/∂z<0)at large drift angle. The results suggest that the transverse porpoising considering in the present paper may be a self-excited phenomena in a coupling motion among roll, pitch and heave.
- 著者
- 古谷 好絵 前田 忠直 水上 優 朽木 順鋼
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.343-344, 2003-07-30
- 著者
- 中川 純
- 出版者
- [日本障害法学会]
- 雑誌
- 障害法 = Disability law (ISSN:2435967X)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.3-18, 2021-11
2 0 0 0 OA 通信品質を向上させるネットワークアプライアンスに関する研究
- 著者
- 磯部 隆史
- 出版者
- 筑波大学 (University of Tsukuba)
- 巻号頁・発行日
- 2015
2014
2 0 0 0 大学生が次世代に伝えたい料理
- 著者
- 石澤 恵美子 坂本 恵
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.167, 2006
【目的】女性の社会進出と核家族化により食の外部化が進み、家庭の味や食文化の伝承が難しくなっている。現代の食環境で成長してきた若者たちが、どのような料理を受け継ぎ、次世代へ伝えたいと考えているのかを目的として、大学生を対象に調査を行ったので報告する。<br>【方法】調査対象者は本学管理栄養士課程の1年生118名とし、平成18年4月から5月に実施した。内容は次世代に伝えたい料理2品を選び料理を作成し、材料・調理方法・出来上がりの盛り付け図(写真可)を提出してもらい、併せて作成時の様子や料理する時に大切なことなどについて自由に記入してもらった。<br>【結果】作成した料理では、肉じゃが8.5%、ハンバーグ3.8%、餃子3.0%、オムライス3.0%、ロールキャベツ2.1%の順であった。また、特徴としてエスカロップ、くるみ餅、ほうろく焼きなどの地域性に富んだ料理も作られていた。調理するときに指導を受けながら作ったの回答は72.0%であった。指導は母親から受けたが64.4%と圧倒的に多く、次いで祖母5.1%、父3.4%の順であった。指導を受けながら一緒に調理をしたのは35.6%、しなかったの回答は33.1%であった。一緒に調理をしなかった者は、TVで見たのを自分流にアレンジした、電話で指導を受けた、料理本を参考にした等の回答が多かった。今回作成した時に一番大変だったことについては、味の再現(味付け)、材料・調味料の計量、じゃがいもの皮剥き等が多かった。調理する時に大切なことは、食べる側のことを考えて作る、衛生面に気をつける、心を込め丁寧に作るの回答が多かった。料理を作成した感想は、母が簡単に作っている味と同じにするのは難しいと思った。母と一緒に料理ができて楽しかった。大変ではあったが、少しでも母の味を覚えられてよかったなどであった。
2 0 0 0 OA 社会的敗北ストレスが腸内エコシステムに与える影響
- 著者
- 鈴木 チセ
- 出版者
- 公益財団法人 腸内細菌学会
- 雑誌
- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.187-195, 2017 (Released:2017-11-03)
- 参考文献数
- 39
精神的ストレスは精神疾患のみならず様々な疾病の危険因子でもある.健康の阻害要因であるストレスを腸管の側から,すなわち食品によってストレスを軽減することを目的に,マウスのうつ病モデルである慢性社会的敗北ストレスモデルを用いて,精神的ストレスが腸管に及ぼす影響を網羅的に解析した.本稿では,慢性社会的敗北ストレスモデルの実験方法やストレス負荷マウスの特徴について解説するとともに,筆者らの行った盲腸のメタボローム解析,盲腸・糞便の菌叢解析および回腸末端の遺伝子発現のマイクロアレイ解析の結果について,宿主の腸管の遺伝子発現と腸内細菌の構成,宿主および腸内細菌の代謝物という腸内エコシステムの観点から考察する.また社会的敗北ストレスを負荷したマウスの行動変化や身体的な変調を軽減する食品成分の探索について最近の研究例からその可能性について紹介する.
2 0 0 0 OA 2003年イラン・バム地震の余震観測と初期震源決定
- 著者
- 鈴木 貞臣 サイエド モハムド ファテミ アグダ 中村 武史 松島 健 伊藤 喜宏 ホセイン サデギ メヒデ マレキ アラシュ ジャファー ガンドミ サイエド セイバン ホセイニ
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 東京大學地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.37-45, 2005-03-23
2 0 0 0 OA 神経計算学 並列学習情報処理を目指して
- 著者
- 甘利 俊一
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.255-263, 1988-03-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 30
2 0 0 0 IR <わたしの提言>筑波大学のスポーツ風土を考える : スポーツを通じた地域貢献
- 著者
- 長谷川 悦示
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 筑波フォーラム (ISSN:03851850)
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.79-83, 2003-03
今年度における筑波大学のスポーツクラブの活躍は近年のなかでも目に見張るものがある。バレーボール男子が大学選手権6連覇を達成し、バレーボール女子も15年ぶりに選手権制覇でアベック優勝を果たした。同様に剣道の男女が団体で …