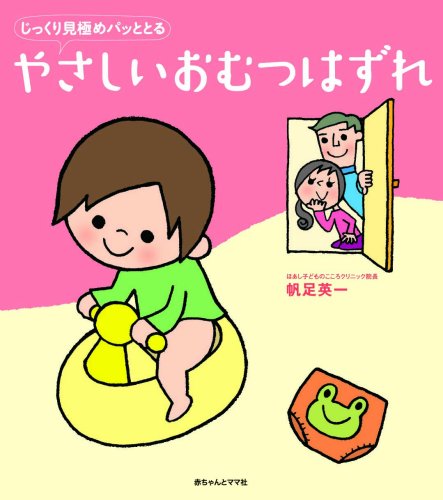2 0 0 0 OA 日本木材界人物伝
- 著者
- 菊池武徳 著
- 出版者
- 日本木材界人物伝編纂部
- 巻号頁・発行日
- vol.第1巻 (名古屋版), 1927
2 0 0 0 OA 地震電磁気現象の計測技術と研究動向
- 著者
- 早川 正士
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J89-B, no.7, pp.1036-1045, 2006-07-01
近年地震に伴って各種の電磁気現象が発生することが報告されている.すなわち,地圏から直接放射する電磁気現象や地震に伴う大気圏や電離圏のじょう乱などである.本論文では,地震の短期予知の観点から極めて注目されている二つの観測項目;(1) ULF電磁放射(地圏から直接放射される極低周波電磁放射);(2)電離層じょう乱(VLF/LF送信局電波の伝搬異常として検出)を取り上げ,その計測手法や最新の成果までをレビューする.
2 0 0 0 OA 農民文学とその社会構想 農民文学者・犬田卯の農本思想
- 著者
- 舩戸 修一
- 出版者
- 日本村落研究学会
- 雑誌
- 村落社会研究 (ISSN:13408240)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.31-42, 2004 (Released:2013-09-18)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
Shigeru Inuta (1891-1957), a well-known writer of peasant literature, constructed Nohonshiso (Japanese Agrarianism), exhibiting his theories of its literature. However, his Nohonshiso has been disregarded for a long time. Therefore, we certainly must remember that his thought is highly suggestive. In this paper, I would like to clarify several important aspects of his Nohonshiso. Inuta started to write peasant literature from 1918. If one examines his articles, one can see he considered this literature as a self-expression of farmers. He asserted that this literature had been written from their viewpoint. He also considered this literature as an effective means to reorganize rural communities. In addition, he criticized the peasant literature written by writers of proletarian literature, because they regarded such literature as a strong tool to overthrow the government and the Tenno (Japanese Emperor) system. Inuta, that is to say, criticized that the literature they formulated did not thoroughly expressed the sense and feeling of farmers, and that it lacked the reality of agriculture and rural life. In 1938, an association of peasant literary writers and theorists, Nomin-bungaku-konwakai, was organized by the government authorities. Most of them took part in this national association of for peasant literature. Unfortunately, it played the role of a governmental agency and, in World War II, it supported Japanese Fascism. Inuta, however, did not take part in this association, because he thought that its literature should express the sense and feeling of peasants, and the reality of agriculture and rural life. He definitely did not think that it should be adjusted to national policy.
2 0 0 0 OA 大学教育研究委員会第三部会(入試と選抜)発表 : 大学入試制度の教育学的考察
- 著者
- 中内 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.31, 1972-09-02
2 0 0 0 OA 総合食品会社の広報誌 : -味の素(株)『奥様手帖』と『マイファミリー』を事例に-
- 著者
- 三島 万里
- 出版者
- 文化学園大学
- 雑誌
- 文化女子大学紀要. 人文・社会科学研究 (ISSN:09197796)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.31-43, 2010-01
効果測定の不明確性,企業業績の悪化の改善を理由に,企業コミュニケーション中の自社媒体の見直しが相次いでいる。なかでも広報誌の休廃刊を行う企業は多く,09年4月には30年の歴史を持つ『サントリー・クオータリー』が休刊した。理由は「事業の多角化とグローバル化を進めるなか,その役割を見直す」ためという(同社HPより)。同社は2010年12月を持って大阪・サントリーミュージアム「天保山」も閉館するという。量的には決して多くはないものの根強い愛好者をはぐくんできた自社媒体を相次いで廃止することで,当該企業の企業コミュニケーションはどのように変わっていくのだろうか。本稿では「多角化とグローバル化」を旗印に躍進を続けている味の素株式会社(以下味の素(株))の二つの企業広報誌と,その休刊後の企業コミュニケーションの変化を分析,企業コミュニケーション上の広報誌の位置を検証する。
2 0 0 0 IR 与論島における観光化と地域振興
- 著者
- "桑原 季雄"
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 南太平洋海域調査研究報告=Occasional papers (ISSN:13450441)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.90-96,
与論島では昭和54年をピークに観光客が減少していくなかで、様々なイベントを企画することによって、シーズンオフ期の冬場の観光客の開拓と誘致を積極的にはかってきた。従来の若者中心のビーチ観光やマスツーリズムから、ブーム後は様々なイベントの企画によって幅広い年齢層、多様な観光客の誘致を目指して大きく方向転換した。また、ブーム期は兼業農家が激増したが、ブーム後は兼業農家が減少し専業農家が増え、脱観光産業化と農業重視の方向性が顕著である。特に、切り花や輸送野菜への多角化と畜産の比重が増大した。観光も、受動的観光から能動的観光へ、量から質の観光へ、自然依存型から自然利用型観光へ、娯楽型から健康・癒しの観光へ、農業と観光の分離から連携へ、個人から島民全体の観光へ、夏型から通年型観光へとシフトし、「健康・癒し」を軸にセルフイメージの構築と差別化の過程にある。"Tourism in Yoron had its peak in 1979 and after that the number of tourists decreased markedly. After the boom, Yoron islanders have ever been trying to bring tourists back again by creating various kinds of events and attractions not only in summer but also in off-seasons. During the boom, farmers were more depending on tourist industries. A fter the boom, they are more depending on agriculture and stock breeding. Tourism in Yoron also sifted from passive to active, from quantitative to qualitative, from amusement to health oriented, and from summer to all year round type tourism. Yoron island seems to be still in the process of constructing self-image to differentiate her from other touristic sites by focusing on 'health and healing'."
2 0 0 0 OA サリン事件と私
- 著者
- 森 謙治
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.917-918, 1995 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 能登畠山氏の権力編成と遊佐氏
- 著者
- 川名 俊
- 出版者
- 大阪市立大学日本史学会
- 雑誌
- 市大日本史 (ISSN:13484508)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.25-44, 2021-05
2 0 0 0 帰耆建中湯加附子による褥瘡の治療経験
- 著者
- 長坂 和彦 土佐 寛順 巽 武司 嶋田 豊 伊藤 隆
- 出版者
- 社団法人日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.273-280, 1998-09-20
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 7 4
西洋医学的治療に抵抗した難治性の褥瘡に帰耆建中湯加附子が奏功した4症例を経験した。症例1は82歳, 女性。繰り返す褥瘡に帰耆建中湯加附子が有効であった。帰耆建中湯加附子の内服を継続することにより、新たな褥瘡の再発はない。症例2は59歳, 女性。直径2cmの褥瘡周囲の皮下に直径10cmにわたるポケット形成があり、同部の皮膚は紫色を呈していた。帰耆建中湯加附子内服後、皮膚の色は正常になり褥瘡は治癒した。症例3は85歳, 男性。過去2回、瘻孔を伴う褥瘡の手術を受けたが治癒しなかった。帰耆建中湯加附子内服後、体交時, おむつ交換時に看護婦を大声で怒る元気がでてきた。また、創部消毒時に強い痛みを訴えるようになった。痛みの自覚は血流が改善してきたことによると考え、同方を継続。褥瘡の治癒とともに全身状態も改善した。症例4は64歳, 女性。心筋梗塞後に心停止し、脳死状態になり、仙骨部に褥瘡を形成するに至った。褥瘡は大学付属病院,総合病院で治療を受けたが改善しなかった。帰耆建中湯加附子 (黄耆30.0g, 白河附子6.0g) で治癒した。帰耆建中湯加附子は、難治性の褥瘡には一度は試みてよい方剤と考えられた。
2 0 0 0 OA 鎌倉幕府と天人相関説 : 中世国家論の観点から
- 著者
- 下村 周太郎 Shutaro SHIMOMURA
- 雑誌
- 史觀 = Shikan : the historical review (ISSN:03869350)
- 巻号頁・発行日
- no.164, pp.28-46, 2011-03-25
2 0 0 0 OA 中世前期京都朝廷と天人相関説 : 日本中世<国家>試論
- 著者
- 下村 周太郎
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.6, pp.1084-1110, 2012-06-20 (Released:2017-12-01)
Within the recent research done on the Japanese medieval state, a debate has arisen over how to evaluate the Kamakura Bakufu in contrast to the imperial court in Kyoto. If we try to relocate the problem somewhat differently, we end up fundamentally focusing on the question of what is the meaning of "state" in medieval Japan. The present article focuses on contemporary ideology and extraordinary events from the analytical perspective of the relativization of the modern nation-state, in order to trace indicators and characteristic features of the "state" within the Japanese medieval world, within the context of the time-space continuum of premodern East Asia. In concrete terms, the author takes up the political ideology of correlating divine will with human action (tenjin 天人) in connection with extraordinary events, a set of beliefs which originated in China then spread throughout the regions on its periphery, as the ideology developed in Kyoto aristocratic society during the early medieval period, which is a given factor when trying to place the Kamakura Bakufu within context of the state at that time. This tenjin ideology involved understanding the origins of extraordinary events, both favorable and disastrous, as stemming from divine judgement towards corresponding good or bad political governance. What the author terms the "tenjin correlation" can therefore be identified as the fundamental necessary condition for aristocratic organizations responsible for political action and therefore for those political entities of the premodern East Asian world which we conceptualize as "states". Although the research to date has tended to undervalue and de-emphasize the importance of the "tenjin correlation" in the workings of the imperial court in early medieval Kyoto, the author is able to verify the continuing existence of an ideology of causality based on the "tenjin correlation," in particular with respect to extraordinary natural phenomena. That is to say, the idea of such phenomena as crucial events being a characteristic feature of the medieval world is the key to evaluating the early medieval Kyoto imperial court as a "state" within the time-space continuum of premodern East Asia. On the basis of such ideology, the various political responses that were selected and implemented on the occasion of extraordinary natural events can be understood structurally as composed of invocation (exorcism) and public acts of benevolence. The author concludes that the medieval Japanese "state" model can be understood in terms of extraordinary natural events, etc. being ultimately judged as divine punishment for immoral, mistaken political governance on the part of the ruler, and also as a political entity composed of rulers and their counselors responding to the will of heaven with two kinds of human action, acts of expiation and public displays of benevolence. It is within this context that the situation of the Kamakura Bakufu and medieval social structure should be placed.
2 0 0 0 OA 犬コアワクチン接種後の経過年数による抗体保有状況の推移
ワクチン接種後の経過年数と犬ジステンパーウイルス(CDV),犬パルボウイルス2型(CPV-2),犬アデノウイルス1型(CAdV-1)及び犬アデノウイルス2型(CAdV-2)の免疫状態を24カ月齢以上の犬178頭の血清を用いて抗体検査により検討した。その結果,ワクチン効果の保有率及び抗体価は4ウイルスともに経過年数に伴い減少する傾向が観察された。さらに抗体価の変動係数を検討したところ,ワクチン接種後2年以降,CDV,CAdV-1及びCAdV-2において顕著な上昇が観察された。以上の成績から,特にワクチン接種後長期間経過している例では抗体価が減弱している例が多く,そのために免疫状態の個体差が大きくなるものと思われる。このため,特に免疫介在性疾患等の理由でワクチン接種を避けるべき例に対して定期的な抗体検査により免疫状態をモニタリングする必要性があると思われる。
- 著者
- 村上 潤 真山 茂樹
- 出版者
- 東京学芸大学
- 雑誌
- 環境教育学研究 : 東京学芸大学環境教育実践施設研究報告 (ISSN:13446444)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.39-52, 2016-03-18
2 0 0 0 OA 小学生のいじめ加害行動を低減する要因の検討 ―個人要因と学級要因に着目して―
- 著者
- 外山 美樹 湯 立
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.295-310, 2020-09-30 (Released:2021-02-18)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 4
本研究の目的は,小学4―6年生646名を対象に1カ月間の短期縦断研究を行い,いじめ加害行動の抑制に関連する個人要因としていじめ観ならびに罪悪感の予期を,学級要因として学級の質を取りあげて検討することであった。本研究の結果より,いじめを根本的に否定する考え方を有している小学生は,いじめ加害行動の抑制につながりやすいことが示された。一方で,罪悪感の予期は,いじめ加害行動の抑制につながらなかった。さらに,友達関係雰囲気,学級雰囲気,承認雰囲気,いじめ否定雰囲気といった子どもが所属している学級集団の質の要因が,いじめ加害行動の抑制につながることが示された。最後に,Time 1の加害行動とTime 2の加害行動の関連の強さが学級集団の質によって調整されることが明らかとなり,学級集団の雰囲気が良い学級においていじめ加害行動が多くみられる児童は,その傾向が長期化しやすいことが示された。いじめの問題を取りあげる際には,教室環境の要因を加味し,個人要因と教室環境の要因のダイナミクスを検討する必要性が示唆された。
2 0 0 0 IR 外国人児童のためのリライト教材・音読譜による国語科の指導
- 著者
- 光元 聰江 岡本 淑明 湯川 順子
- 出版者
- 岡山大学教育学部
- 雑誌
- 岡山大学教育学部研究集録 (ISSN:04714008)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.1, pp.113-122, 2006
本研究は、外国人児童生徒の学習言語能力の伸長は目指した教科学習という視点から、国語科の学習を容易にするための「リライト教材・音読譜」という教材作成法を考案し、公立小学校の日本語学級において実践したものである。外国人児童(以下、子ども)の日本語力に対応させた国語教科書(以下、原文)のリライト教材・音読譜を作成した。そして段階的にリライト教材のレベルをあげ、最終的には、原文をリライトしないで学習できるように指導した。このリライト教材・音読譜を作成するにあたり、学年相当の国語の学習目標と日本語の学習目標の2本柱を立て、現時点での子どもの日本語能力に配慮しつつ「表現はやさしく、内容は相当学年レベルで」を目指した。本実践では、編集時、日本語を全く解さなかったK児と日本語入門程度のS児(2名とも中国語母語者)が、約1年間の上記実践によって、教師の口頭による説明のみで原文がそのまま学習可能となった。
2 0 0 0 じっくり見極めパッととるやさしいおむつはずれ
2 0 0 0 夜尿症児の精神生理学的研究:第I編睡眠リズムと夜尿について
- 著者
- 帆足 英一
- 出版者
- The Japanese Society of Child Neurology
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:18847668)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.303-310, 1977
夜尿症の病態生理を明らかにする目的で, idiopathic enuresis 21例について終夜睡眠ポリグラフを第1夜に記録し, 分析をおこなった.<BR>1) 正常児と比較して, 睡眠段階の割り合いはSV, S1, S3の増加, SREM, S4の減少傾向がみられた.<BR>2) 夜尿時の睡眠段階は, 22回の夜尿のうちS2で12例 (54.5%) と多く, S3, SREMは各1例と少ない.<BR>3) 夜尿前後の睡眠段階の変化から, 覚醒機構の未熟性あるいは障害が推定された.<BR>4) REM睡眠とNREM睡眠の周期的変動の乱れがつよく, 入眠期の障害とREM睡眠の睡眠内周期の障害が推定された
2 0 0 0 OA 瀋陽状啓
- 著者
- 京城帝国大学法文学部 校訂
- 出版者
- 京城帝国大学法文学部
- 巻号頁・発行日
- 1935